|
�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^ �Q�O�l�������

���グ��s�A�j�X�g�F�o�b�N�n�E�X�^ �P���v�^�O���_�^�O�[���h�^���[�r���V���^�C���^�z�����B�b�c�^�|���[�j�^�A���E �^�A�V���P�i�[�W�^�[���L���^�M�����X�^���q�e���^�y �� �C�A�^�I�R�[�i�[�^�u�����f���^�s���X�^���C�X�^�o�����{�C�� �^�V�t�^�O�����[ �@�x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^�́A�n���X�E�t�H���E�r���[ ���[�Ɂu�s�A�m���y�̐V���v�ƌĂ�i���j�A �N���V�b�N���D�Ƃ̊Ԃł͂悭�R�ɚg�����܂��B�x�[�g�[���F�����g�̍� �i�Ƃ��Ă������ȁE���y�l�d�t�Ȃƕ��傫�ȎR�ł����A�s�A�m�\�i�^�̃W�������Ƃ��Ă��A���̍�ȉƂ̊Ԃ� ���т�������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���q�����g�E�V���g���E�X�͎R�Ǝ]�����郏�[�O�i�[��]���āu�ڂ��� �o�炸�[������Ă����v�ƌ����������� �����A�����o�R�͋��Ȃ̂œr���̌����炵��ō�����������A���[�v�E�F�C�ň�C�ɏ���ē��ɂɂȂ����肵�Ă���킯�ŁA�ƂĂ��\�i�^�̑�c���Ȃ�Ė����ł��B�D���Ȑl�͌Í��̖����t���J��Ԃ������Ă���ł��傤����A����Ȑl���S���R��_����ׂ��ł��B���������Ă����ł́A�����������f�B�[�Ŏn�܂���̂��t�҂ɂ���Ēe��������ψقȂ�u�����v�i�P�S�ԁj�ƁA�Ȍ��Ȓ��Ɍ������ƐÂ����̗��ʂ����Ȃ�������̌���A�R�O���̃\�i�^ ����ȑ�ނɂƂ��āA������Ƃ�����r���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�ŏ��͂��̍�ȉƂ̓��B�_�Ƃ������ׂ��R�Q�Ԃ̑��y�͂Ŕ�r���ׂ����Ƃ��v���A����Ă݂͂��̂ł����A�]���̍����l�����̒��ɋ^��Ɏv������̂�����������A�̂��̋Ȃ����܂�ǂ��v���Ȃ������̂͂��ꂵ���m��Ȃ������������ƋC�Â����̂ł�߂܂����B ���A���g�D�[���E�j�L�V���ƂȂ��Ŏw���҂Ƃ������̂̒n�ʂ��m�����Ă������̑�w�� �҂ł���A�u�h�C�c�R��B�i�o�b�n�^�x�[�g�[���F���^�u���[���X�j�v�Ȃ錾�t���ނ������o���܂����B�u�V���v �Ƃ����̂́A�o�b�n�̕��ϗ��N�����B�A�ȏW�������ɂȂ��炦�����Ƃɑ��Ă����Ă�܂��B  Wilhelm Backhaus �E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X �@�܂��A��ɊO���Ȃ��I�[�\���e�B������܂��B�x�[�g�[���F���̃\�i�^�̏ꍇ�A�o�b�N�n�E �X�̉��t������ɓ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�P�W�W�S�N�h�C�c�̓��C�v�c�B�q���܂�ŃP���v�����\�߂��N��A�o���g�[�N�Ɠ�������̐l�� �P�X�U�X�N�ɂW�T �ŖS���Ȃ��Ă��܂��B���C�v�c�B�q�̓h�C�c��`���̂��鉹�y�� �s�ł���A�ނ͂��̃s�A�j�Y���̌p���҂��Ƃ����Ӗ��ŁA�悭�u���Ղ̎��q���iLion of the keyboard�j�v�ƌĂ�܂��B���C�v�c�B�q�s�̖�͂����C�I��������ł��B�܂��A���{�ł͕]�_�Ƃ̋g�c�G �a���������]���������ƂŐl�C���蒅�����悤�ł��B �u���҂̉��y�v�Ƃ����^�C�g���ŁA�g�c���͋����[�����Ƃ��� ���Ă��܂��B���܂��܃t�B�V���[�E�f�B�[�X�J�E�Ɠ����^�N�V�[�ɏ�荇�킹���A�Ɗi�D�ǂ��n�܂�ł����A���̂� �����̐��E�I�̎肪�o�b�N�n�E�X ���w���Č��҂��ƌ������Ƃ����̂ł��B���̈Ӗ�����Ƃ����ނ́A���Ղȃe���|�E���o�[�g������邱�Ƃ��痈��i���̍������Ɖ��߂��邱�ƂŎ��g�̘_���^ ��ł��܂��B�e���|�E���o�[�g�Ƃ����̂́A�ꑱ���� �t���[�Y�̒��ł��鉹�𑁂߂���x�������肵�Ă��炵�A����̗h���\��������@�ł��B���ʂ͂���t���[�Y���������������߂ɂ��̓���x�߂����ʁA����ȍ~�̕���������Ƃ� �Ď����I�ɑ��܂�܂��B�V���p���Ȃǂł͑��p�����킯�ł����A �u���[���X�̃R���`�F���g�ł́A�u��������ƃg�����B�A���i���}�j �ɂȂ�v�ƃo�b�N�n�E�X���g���������̂������ł��B�i�������\����ڎw���Ă����Ƃ������Ƃł��傤���B�����Ă��������Ă��܂��ΒP�������߂���������܂� �A�g�c���ɂ��ƃo�b�N�n�E�X�̉��t�̋Z�p�I���ʂ́A���������F��a���o���Ƃ����_�������A�u�A�S�[ �M�N�i�e���|�̐L�яk�݁j�ɂ����� �A�b�`�F�������h�i����ɑ����Ȃ�j�͂������ŁA���o�[�g�͂����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B �@�ł́A���ۂɕ����Ƃǂ��ł��傤�B�g�c�G�a���S���Ȃ��Ă��܂��A���̃h�C�c��܂���̂̂����肵������� �� ���Ȃ��Ď₵���ł����A���C�ȍ��͘V�����z �����B�b�c���u�Ђт̓����������i�v�ƕ\�����Ęb��ɂȂ�܂����B�ނ��L���ł͂����Ă��R�}�[�V�����Y���ɗ��������A�����̎��ŕ����Ɨ@�����l�Ȃ̂ŁA���������Ȃ�ɕ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B �@�o�b�N�n�E�X�̉��t�ł����A�����ɂ͂ǂ����ނ̌����悤�ɂ͕������Ȃ��Ƃ��낪����܂��B�u�����v����s���܂��ƁA�o�����̗L���ȑ����̕����ł� �e���|���ĊO�x���A�ǂ�������ƃV�t���u��������v�Ɲ������Ă����悤�ȓ`���I�\���ɂ��������܂��B���̊ɏ� �y�͂ł͑S�̂ɑ����l�̂悤�Ɋ�����̂ɁA�S�����d���\���ɐU��镝������悤�ł��B �@�����Ă���������O�������āA�����Ĕے�I�\�����������Ɍ����Ȃ�A�i���ɂ́j�S�̂ɗ��������̂Ȃ��X���� �������܂��B���Y�����s����łȂ����ɕ�������Ƃ��낪����̂ł��B����͂R�O�Ԃ���̍Ō�̃\�i�^�Q�ł� ���l�ł����A�m���Ƀt�����X�l�̒e���V���p���̂悤�ȑ�_�ȃ��o�[�g�ł͂Ȃ���������܂���B�������ׂ荇���� �����̂܂Ƃ܂���ϓ��ɒe���Ă���̂Ƃ͈Ⴂ�܂��B�h��Ă���̂ł��B�������t���[�Y�̓������ɒx�炷�h��͈ĊO�ڗ������A������ɑ����Ȃ�������ɂ��� ���B�A�b�`�F�������h�Ƃ����ƁA�t�H���e�̕�����I���Ɍ������ċ������đ����Ȃ��Ԃ��C���[�W���܂����A���� �������[�b�Ƃ��ݏグ�Ă���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�o�b�N�n�E�X�̏ꍇ�͂��Z���P�ʂŁA���߂̓��̔������܂�� ������ނł��B�u�ԓI������Ƃ������A�v����ɑ������ւƂ��炷���o�[�g�Ȃ̂ł��B�Ƃ��������ނ���A�������܂��������̌�낪���т�Ƃ����⏞�I�ȋK�����͂Ȃ��A�ǂ�ǂ߂���֒Z���l�� �čs���ƌ��������������ł��傤���B����Ƃ��A���ꂪ�g�c�G �a�̌������������u�A�b�`�F�������h�v�Ȃ̂ł��傤���B���̌X���͂T�O�N��̓��ɓ��ꂽ�O��̘^���̕��������ł����A�Ō�̑S�W�ł������͂���� ����c���Ă��܂��B �@��������h�ꕝ���͔̂����ł���A�����ɑO���ŊԂ�����Ď��ɋ����@����ʓI�ȃ��o�[�g������܂����A���ʂƂ��đS�̂ɊÂ��̂Ȃ��A��ɗ�����Ȃ����ɕ������܂��B����Ɍ����A�I���̉������\���ɉ� ���Ȃ����ʁA�]�C�𖡂���ĂȂ��悤�Ȉ�ۂ�����܂��B�R�P�Ԃ̃t�[�K�ȂǁA�|���[�j�Ƃ͂܂��Ⴂ�܂����A��ڂȂ��ɑ����čs�����Ɏ��͂���� �ƋC��ꂵ�܂��B���̒^�M���Ȃ��l�q�͖���Ȃ����q�̂悤�ł� ���A����͔ނƂقړ�����̃��@�C�I���j�X�g�A�V�Q�e�B�����}���h�̑���������ƌ�����悤�Ȃ��ƂƊW�� ����̂ł��傤���B �@�����ʼn������v���o���܂��B�����A�o�b�N�n�E�X�̃��Y�����Êy�퉉�t�̃t���[�W���O�ɂ�����Ǝ��Ă���̂ł��B �Êy�Ȃ烋�o�[�g�ł͂Ȃ��āA�Q������ �L�яk�݂�����m�[�g�E�C�l�K���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�������܂��A��̘b��ɂȂ� ���u�O�̂߂�t�@�v�ɖ��킢�����Ă��܂��B�������Êy�t�@�����ɏo�Ă����̂͂U�O�N��ŁA���̐����������r�ꂽ�̂͂V�O�N��ɓ����Ă���Ȃ̂ŁA���� �o�b�N�n�E�X�̂U�P�N�̘^���ƌÊy��̗��s�Ƃ͉��̂�����������܂��B �@���Ђł������ɐh���̂��Ƃ��菑���܂������A���ՂɃ����h���}�e�B�b�N�ɂȂ�Ȃ��̂͊m���Ƀo�b�N�n�E �X�̔��_���Ǝv���܂��B�x�[�g�[���F���̃\�i�^���ŏ��ɑS�Ș^�������V���i�[�x���A������̑ΏƓI�ȕ\���̃P�� �v�ƕ���ŎO�喼���ƌ�����̂��킩��܂��B�P���v�Ƃ͍D�������������ƌ����܂����A�o�b�N�n�E�X�� ���F����ς��ꂢ�Ȃ��Ƃ͋g�c�G�a���̎w�E����ʂ�ł��B�o�b�N�n�E�X�̓x�[�[���h���t�@�[���g���Ă���̂ł� �ˁB�������x�[�[���h���t�@�[�e���̃O���_�����͂Œ@���X���͏��Ȃ��A�^���N��őz�������肸���Ɣ������� ���y���߂܂��B���͎����P���v�h�̉҂�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���H  Wilhelm Kempff ♥ �E�B���w�����E�P���v ♥ �@�P�W�X�T�N���܂�łP�X�X�P�N�ɂX�T�ŖS���Ȃ����h�C�c�̃s�A�j�X�g�A�E�B���w�����E�P���v�́A�x�[�g�[ ���F���̉��t�ƂƂ��Ă̓o�b�N�n�E�X�ƕ��ԑ�ƂƂ���Ă��܂��B�܂��A��l���������قɂ��Ă���̂ōD�݂��ǂ� �炩�ɕ������Ƃ������܂��B�o�b�N�n�E�X�͓Ɠ��̋삯�o���悤�ȕ����Ƌ��̉��� �����Ȃ��������u����ʎ��q�v�̊o���𖡂�킹�A�g�c�G�a���u���ҁv�ƌĂ��Ƃ͏�L�o�b�N�n�E�X�̕����ŏq�ׂ܂����B����ɑ��ăP���v�Ƃ� ���l�͂��̐U��q�̔��Ƃ��Ĉ����邩�炩�A���}����`�̓k���ƌ����܂��B�������o�b�N�n�E�X�����҂Ȃ�A �P���v�������̑����𗣂ꂽ���t�ł��傤�B�}�g�̂���̂͂������܂����A�������Ԃ߂Ă���̂ł͂Ȃ��Ǝv���� ���B���̐l�͐M�����������̂ł��傤���B�����̐g�� �N�����Ă��邱�Ƃ����ł��ꂶ���ƌ��Ă���M���̂悤�Ȃ��̂������܂��B�͂����肪���������Ď����̊���ɐ����A�����ɒB����ǂ�Ȃ����J�Ɖ�z���������Ă��܂��B �@ �@�P���v�̃x�[�g�[���F���S�W�͂R�Z�b�g�قǏo�Ă���悤�ł��B���m��������̂��̂Ɠ��{�ł̃��C�u�A�����Ă� ���U�S�`�U�T�N�̃O�����t�H���̃X�^�W�I�^���ł��B�P���v�̓��C�u�ő�ϖ��킢�[�������o�����Ƃ�����A�܂��ӔN�̘^���ɂ͓Ɠ��� ���E���W�J���܂����A���̑S�W�͂��̂ǂ���ł��Ȃ��Ȃ���A�P���v�炵�����킢�ł͋��ʂ��Ă��܂��B�e�����̓� �����o�b�n�̃S�[���h�x���N�̂Ƃ���i�S�[���h�x���N�ϑt�� CD ��������j �ŏ������̂ŏd�����܂����A�����������Ă݂܂��傤�B �@�����̏o�����ł͂�⑬�߂̃e���|�ł�����Ǝn�߂Ă���A���ꂾ���ł��ނ̉��y���v�����ꂽ���Ղ�Ƃ������� �ł��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�� �����A�e�̔Z���͈�ۓI�ł��B�����ȍ��������ɂ���悤�ŁA���̋����̃X�e�b�v�������̂ł��B�����ĐÂ����̒���Y�������ɁA�E�肪���炩��������͂� ����Ƃ������ւƐ���オ���Ă���悤�ȂƂ���Ɉ��������܂��B�o�b�n�ł͂Ȃ��̂Ń|���t�H�j�[�ɂ������K�v�� �Ȃ��킯�ŁA����̔��t�ɑ� �ĉE�肪����t�ł�Ƃ��A�P���v�͏�ɂ�������ƉE��Ɍ�点�܂��B �@���t�̎O�����̉����͎O�ڂ�������x �炷�悤�ɕ\��t���A���o�[�g�����݂ł����A�M���C�z�͂���܂���B���ꂪ�����s�i���Ƃ��āA�S������h��Ă���̂ɁA������ �Êς��Ă���悤�ȂƂ��낪����܂��B �@���y�͂͑��̉��t�ł͑O�̊y�͂ƃR���g���X�g��t����̂ł����A�P���v���Ӑ}�I�ȕω������悤�Ƃ͂��܂���B�y�₩�Ȃ�������Ƃ����قǂł͂Ȃ��A��͂�ǂ����Â��ł��B�ނ̒��ł̈�ۂɏ]���Ă���̂ł��傤�B�W�J���̓���ł͋���������A�����ł̓R ���g���X�g�����܂��B �@��O�y�͂͑����_�C�i�~�b�N�ł��B���������𖡂킢�� �v���Ă���ނ̖ڂ������܂��B���́A������_�����Ă���悤�Ɍ��J���ꂽ�ڂł��B�����ăt���[�Y�̓r������}�ɗ͂������Đ���オ�鎩�݂����P�� �v�炵���Ƃ���ł��B �@�R�O�Ԃ̏o���������ɂ�����Ƃ��Ă��܂��B�ǂ����y�������Ƃ��猾����قǁA����̍�i�Ƃ����\���͂���� ����B�e�����Ǝ��̂���тȂ̂ł��傤���B�ł����̋Ȃ͖{�����������ȂȂ̂�������܂���B�E��̋���������ς�������Ƃ��Ă��� ���B �@���y�͂̓X�^�b�J�[�g�C���Ƀ��Y�~�J���ł��B�����ł��������悤�ȂƂ���͂���܂���B �@��O�y�͂�������Ƃ��Ȃ��疡�킢�̂���▭�ȃo�����X�ŁA���}���h�̂���͍~��Ă��܂���B�������o�b�N�n �E�X�̖���ʏ�Ƃ͈Ⴄ�o���ł��B�e����P���v�̊���������t���ė��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA���}���e�B�b�N�ł͂� ���̂ł��B�ЂƂ������E�ɂ�čs���ꂽ�悤�ŁA���������e����͑��ɂ��Ȃ��� ���傤�B�Ō�͂������ƌ������āA�Â��ɏI���܂��B�@  Friedrich Gulda �t���[�h���q�E�O���_ �@�O���_�̑S�W�͏܂��Ƃ�A���O�̑啨�]�_�Ƃ���^����x�[�g�[���F���̃X�^���_�[�h�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��� ���B���{�ł̓o�b�N�n�E�X�A�P���v�A�O���_�A�Ƃ������ňٌ������ɐ��E���Ă��炦�Ă�悤�ł��B�E�B�[�����܂� �ł���Ȃ���E�B�[�����`���ɔw�������A�i�D���s�����q�b�s�[�� �悤�ł���A�W���Y�����ł���čs���ƌ����Ď��� �����������肵�����̊�s�̐��X�́A�O�[���h��X�R�b�g�E���X�A�A�b�v���̃X�e�B�[���E�W���u�Y�̂悤�ȃJ���X �}�I�l�C�ɂȂ����Ă��܂����A�x�[�g�[���F���̂��̂P�X�U�V�N�̉��t�͑�ϐ����I�Ƃ����̂��A�����Ăӂ����� �����Ȃ���Ώ���C���Ȃ��A�W���Y�̑����߂����V�тɖ����Ă���Ƃ����킯�ł��Ȃ����^�ʖڂȂ��̂ł��B������ ��ϗ͋����B�����ƁA�^�ʖڂȐl�����炱���̊�s�������̂ł��傤�B �@���[�c�@���g�̃s�A�m���t�ȂQ�O�ԂƂQ�P�Ԃ̔Ղ͘^�����������L�c���Ƃ��낪������̂́A�S�n�ǂ��������̗V �т�����A�Q�P�ԂȂǖ��邳������Ȃ���Ђ��ނ��ŁA�����ɂ� �������̂��Ȃ��Ǝv�킹��f���炵�����̂ł��B�W���Y���e���s�A�j�X�g�����炱���̍D���ƌ���ꂽ �킯�ł����A����Ńx�[�g�[���F���̕��͂��������z�����͂�菭�Ȃ��悤�Ɋ����܂��B���t���Ă��āA�O���_�̓x�[�g�[���F�������������h���Ă����̂��ȁA�Ǝv���܂����B�� �`��ǂ킯�ł͂Ȃ��̂ł͂����肵�����Ƃ͒m��Ȃ��̂ł����A���[�c�@���g�̋��t�Ȃł��x�[�g�[���F�� �̃J�f���c�@���g���Ă������i�o������������ł��傤���j�A�������y���Ɗ��o�I���ʂɑi����p�������Ȃ��A�e ���|���������̂Ƃ���͑�ς�������ƒe���Ă��܂��B����̍�i�ł͂Ȃ��Ȃ��猎���ȂǓ��ɁA�ǂ̏u�Ԃ��^�������� ���B �@�^�b�`�������Ƃ���̓��[�c�@���g�̂Ƃ��������ł������A�����ł͂���ɋ��������܂��B�x�[�g�[���F���Ƃ��� ��ȉƂɑ����ʂ̃C���[�W�𗠐�Ȃ����̂��Ǝv���܂��B�E�B�[���̓`���ɂ͔w���������������ɂ���A�ނ� �E�B�[���̖���ł���x�[�[���h���t�@�[�E�s�A�m�͈��p���Ă��܂����B�����������ł̉��͂��̖��邭�ĉs���ɂ� ��Ȃ������A�悭�e��ŋ������ቹ�Ƃ�����ۂƂ͑啪�قȂ��ĕ������܂��B�ő���ɖ炵�鋭���̂����ł��� �����B �@�P�X�R�O�N���܂�łQ�O�O�O�N�ɖS���Ȃ��Ă����ό��I�ȃs�A�j�X�g�A�O���_�B�v���o������A�D���ȉ��t�� �̈�l�ł��B�ʔ����g���R�X�̂悤�Ȃ̂���A�R���T�[�g�̋ȖڏЉ�ł͉p��̂������A������Ƃ��ǂ����悤�� ����ŃV�j�J���Ƃ��Ƃ�鋗�����������������Ă���Ă��܂����B�Ȃ������l������ł��傤�B�����A���̑� �\��ł���x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^�́A���͂������đS�����_���Ȃ��Ȃ���A �l�I�ɂ͂����ƗV�т̕��������҂��Ă����ƌ����Ă����܂��傤���B�x�[�g�[���F���̃\�i�^�Q�ɑ��Đ��q����قǂ̈�������Ȃ������ł��傤���B�ł���l���炢����Ȃ��Ƃ������Ă��A���̖����̓r�N�Ƃ����Ȃ��͂��ł��B  Glenn Gould �O�����E�O�[���h �@�^���N�オ�O�サ�܂����A�O�[���h�͂��̃L�����A�̏��߂̍��ł���P�X�T�U�N�A��̃S�[ ���h�x���N�ϑt�Ȃ̒���Ƀx�[�g�[���F���̌���O���\�i�^�W���o���Ă��� ���B��������ɏo���Ă���p���̓|���[�j�Ƃ����ʂ��܂����A�ނ̏ꍇ�͉���\���Ă���ł��傤���B�����Ƃ��� �ł��x���Ƃ���ł��ɒ[�ȉ��t�����A�F���������锭����A�����ċC���Ђ��Ă������I�̌ǓƂȓV�ˁA�x�[�g�[���F ���ł��J���X�}�I�l�C������̂ŊO���܂���B �@�����͂U�V�N�̘^���ł����A�ǂ�ȋ���Ȃ��̂��o�ė��邩�Ǝv���A�ӊO�Ȃ��Ƃɑ����e���|�Ŕ��ɂ������ ���Ă��܂��B���o�[�g�͂����炸�A�}�g�͂����Ƃ��Ă��܂��B���̃|�[�J�[�t�F�C�X�Ԃ肪�O�[���h�炵���̂� ������܂��A�܂��Ƃ��ł��B �@���y�͂͋����̗}����ꂽ�������^�тł��B�y���Ō��Ђ͈�ؐU�肩�����Ȃ��� �Ƃ����Ƃ��낪�ʔ����ł����A��������炩���ߍ\���Ă���ƕ��ʂɕ������܂��B��O�y�͂̑����̓O�[���h�ł��B�y���A�Ԃ���炸�ɂǂ�ǂ�� �|�ꂩ����悤�ɖ҃X�s�[�h�ōs���܂��B �@�R�O�Ԃ̕��͂Ȃ��A�t�����\���̉��t�𑁉ŕ����Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂł��B�Ƃ����̂��A�o�b�n�⌎�� �Ȃǂł͂��܂芴���Ȃ��������o�[�g�����Ȃ�傫���A�������ɂȂ������Ǝv���ƑO�ւȂ��ꂩ����悤�ɑ����� ��A�ƂĂ���_�Ȃ̂ł��B�t���[�Y�̕ς��ڂŊԂ��J�����A���̎�肪�O�̏I���ɂ��Ԃ�悤�ɑ�����ꂽ��A ���� �Ƃ���ł͂����ɂ��O�[���h�̒������o���肵�܂��B���y�͂ł͕��Ԃ��C�܂܂ȕ��ɖ|�M����A����Ă͎~ �܂�� ���ł���A�V�ߖ��D�Ƃ������͖T�ᖳ�l�ƌ������玶����ł��� �����B���������̖��@�n�т��삯������h���t�g�E�X�|�[�c�J�[�̂悤�ȉ^�т��A����Ă���Ə��Ă��邩��s�v�c�ł��B����ő�O�y�͂̂������̂Ƃ��� �ł͂����Ԃ�Ǝ��Ԃ��Ƃ��Ă����Ղ�̂킹�Ă���A���� �ɕ�������_�ɓ����Ă��܂��B�O�[���h�̓J�i�_�l�ł����A�܂�Ő��I���t�����X�̃f�J�_���Ƃł������̂��A�W���E�g�D�E���̂悤���V�����\����e���Ȃ����Ă���f��̎���ɂł�����悤�ȍ��o���o���邩��s�v�c�ł��B 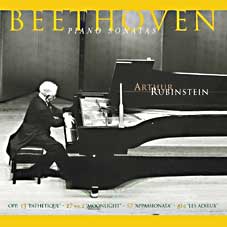 Arthur Rubinstein �A���g�D�[���E���[�r���V���^�C�� �@�V���p���e���Ŗ��������[�r���V���^�C���͂P�W�W�V�N�ɃV���p���Ɠ����|�[�����h�ɐ��܂ꂽ���_���n�̐l�ŁA ��펞�ɃA�����J�Ɉڂ��Ċ��A�P�X�W�Q�N�ɂX�T�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B���o�I�L���͂��ُ�ɍ��������� �Ƃ͗L���ŁA�x�[�g�[���F���͈Õ����ă��p�[�g���[�Ƃ��Ă͎����Ă����悤�ł����A�^���͂��܂�o���Ă��܂� ��B�����A���̏��Ȃ����̂̕]���������悤�ł��̂ŁA�����ł͂U�Q�N�^���̌����݂̂Ŕ�r�����܂��B���������_ ���n�ŃA�����J�Ŋ��A�V���p���ӂƂ��Ă����z�����B�b�c�Ɣ�ׂ��邱�Ƃ������悤�ł��B �@�����̎n�܂�͂�����肵���e���|�ŁA���Y���ɓƓ��̏d���Ǝ��肪�����āA��ϑ��d�Ȉ�ۂł��B����̓V���p ���ł������悤�Ɋ����܂������A�Ƃ���ǂ���ʼn��������Ēx�炷�����̂悤�ł��B �@���y�͂ł����̌X���͓����ł��B�����͂悭�A�������ꂽ�悤�ɑO�Ƃ̃R���g���X�g�����邱�Ƃ������̂ł� ���A�S��X�^�b�J�[�g���d�������������܂��B������肵���e���|�̒��A�m���߂�悤�ɐi�݂܂��B �@��O�y�͂̓e���|���������ł����A��������Ƃ��銴���ł͂Ȃ��A���̋����Ƃ��Ĕ����Ă��܂��B �@���[�r���V���^�C���̉��t�́A�ЂƂ��ƂŌ����Ώd�݂�����A�i���������̂��ƌ�����ł��傤�B�͂�ė͂����� ���z�����B�b�c�Ƃ͑ΏƓI�ő�ϖʔ����Ǝv���܂����B  Vladimir Horowitz �����f�B�~�[���E�z�����B�b�c �@�ǂ�ȓ�Ȃ���������邩�̂��Ƃ��T���T���ƒe���Ă��܂�����Z�I�Ƃ������Ƃōŏ��ɗL���� �Ȃ����l�ł���A���̉��F���Ɠ��������Ƃ��Đ_������I �Ȗ��������z�����B�b�c�ł����A���X�g��V���p���ȂǂӂƂ��郌�p�[�g���[�̂������A�l�I�ɂ� ���܂蕷���Ă��܂���ł����B�x�[�g�[���F�����܂� �܂��Ę^�����c���Ă���킯�ł͂���܂��A�����͍����]������l�����܂��̂ŁA�ԊO�ғI�ɂ��ꂾ�����グ�܂��B �@�֑��ł����A�����f�B�~�[���Ƃ����͉̂p�ꔭ���A�E���f�B�[�~���Ƃ����̂̓��V�A�ꔭ���̂悤�ŁA�\ �L�͈�肵�܂���B �@���y�͂̏o�����͂�����Ƃ����͂ꂽ����ł�������_���p�[�E�y�_�����g���A�������������ꂢ�� ���B�V�t�̂悤�ɏ�ɎO���̈ꓥ�݂������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ���� ����Ŗ߂��ĉߏ�ȉ����z�������Ă��܂����A�܂�œ��݂������̂悤�ɕ�������̂̓x�[�g�[���F���̈Ӑ}���킩���Ă���Ă���̂ł��傤���B �S�̂Ƃ��Ă͗͂��Ƃ��낪��ۓI�ŁA�������ȗ}�g�������悤�ɑ��Â��Ă���A���ꂪ�������Ƃ��� �Ȃ�A�̐l�ւ̎v���͂����Q�����߂��Ă���悤�ł��B��z�̒��̑����ł��傤���B�������ݏグ�Ă��� ���̂����܂ɂ������Ƃ��Ă��A���̎��̉��ł͒��߂�����̂��A���炩�������� ���B�������s�A�j�X�g�̔g���ɖ������ߋ����ォ�璭 �߂��Ƃɂ����킳��Ă���悤�ȁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ�����������܂��B����قǒW�X�Ƃ��Ė��킢�[�� �����̃A�_�[�W���͖ő��ɂȂ��Ǝv���܂��B�m���ɔ��[�Ȑl�ɂ͒e���Ȃ����n��������܂���B �@���y�̗͂͂̔�����͂ǂ��ł��傤���B�킴�Ƃ��ǂ��ǂ����e���Ă��邩�̂悤�ȕs�v�c �Ȗ�������܂��B�ア���͏������邩�̂悤�ł��B �@��O�y�͂��o�������瑬���ɂ�������炸�A�͂������Ă��܂��B�ŏ��Ƀw���L������g���L���ɂ܂� �����ĉE�肪�o���o���o���o���P�U�������ŋ삯�� �����čs���A�Q���ߖڂ̏I���ŃW�����W�����A�ƃX�^�b�J�[�g�t��������������������ł��炳���Ƃ���ŁA�z�����B�b�c�͔��q��������ア���Œe ���Ă��܂��B�����͋����A�N�Z���g�Œe���Ƃ����X�t�H���c�@���h�L���isf�j�����Ă���͂��Ȃ̂ł� ���A���ł��B �@�P�X�O�R�N�E�N���C�i���܂�ŃA�����J�Ŋ��� �z�����B�b�c�ł����A�����̘^���͂P�X�V�Q�N�ł��B��ʂɂ͒���Z�I�Ƃ������Ƃł����A��ۂ͈قȂ�� �����B������Ȃ������ȃe�N�j�V�����Ȃł͐���蓾�܂���B�ނ��됳���ŁA��ϖL���ȏ ���������킹���l�ł��B�����A���łɂǂ����˂������Ă���悤�ł��B  Maurizio Pollini �}�E���c�B�I�E�|���[�j �@�P�X�S�Q�N�~���m���܂�łP�X�U�O�N�ɃV���p���R���N�[���ɗD�������|���[�j�́A�N���^���̂ł��Ȃ����̊��� �ȃe�N�j�b�N�Œm���Ă��܂��B�y���̊��S�ȍČ��Ȃ̂ŁA��������ނ̉��t���ׂ����Ƃ����l�����܂��B�R�O �Ԃ̃\�i�^�i�V�T�N�^���j�ōŏ��̔������o�������Ă݂�ƁA�����������Â��ȂƂ���ł́A���}���C���Ȃ� ��m���Ɋ����ȗ}�g�����Ă��܂��B��ɗ����ꂸ�A�������Ȃ����Ȃ炸�ɏ\���ɉ̂��Ă��āA���^���_���h������ ���A���Y���ɉ��̋����̔����ȉA�e������܂��B���������ꂪ�ЂƂ��т������ȂƂ��납�瑖��o���悤�ȃp�b �Z�[�W�ɗ���ƁA�r�[�ɖʔ������Ƃ��N����܂��B�C�����ǂ����炢�ɉ��������̂ł��B�����҂��\���Ă��Ĉ�C�� �e���Ă���Ƃ��������ł��B�����p�[�g�Ɋ�т��o���Ă���̂ł��傤���B�|���[�j��]���āu�@�B�I�v�Ƃ����l�� ���܂����A����͂����������Ƃ������̂ł��傤�B�t�H���e�̑����Ƌώ����A����͕����̂��Ƃł͂Ȃ��A�ǂ��܂ł������Ă��܂��B������ �t�H���e�ł�������炩�������Ƃ������G�ł͂Ȃ��A��ϋ��x�ȁA���������̘A���ɂȂ�܂��B���̋Ȃ̒��قǂ� �͑�ό���I�ȃt�H���e����������������܂����A�l�ɂ���Ă͂��������Ƃ��낱�������̉� �t�Ƃ炵�����C���ǂ����Ɗ����邾�낤���̂́A������̂ł����A�l�I�ɂ͂���푛���̂悤�Ɋ����ĂƂĂ��� ���čs���Ȃ��Ƃ�������܂��B�ł����݂̂悤���Ƃ܂ł͌���Ȃ����̂́A�����߂���̂ł��B�����A���̉��͑��� �����������Ƃ�����܂��B������������ɂ͂��БO�u�������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@���_�����̕��ނ͕��ނ̂��߂ɂ�������̂��Ƃ������ƁA�܂�Ȃ�Ƃ��V���h���[���Ƃ��f�B�X�I�[�_�[�� ���������b�e����\���ĕa�C�𗝉�����͈̂�҂ɂ͕֗���������܂��A�f�f��Ō��������������_�����̑����ɂ͂Ȃ�琶���w�I�ȍ����͂Ȃ��Ƃ����� ��������܂��B�ނ�����̗����𒒌^�ɕ����߁A���ʂ�x�z�ȂǁA �Љ�I�ɐV���ȍ���ݏo�����ɂ���Ȃ�Ƃ����̂ł��B�{����̌��������̂��A�������Ƃɂ������̃O���[�v�ɏ���ɑ��˂����̂��a�C������ ��܂���B���˕���ς���Ό��̕a�C�͏��ł��܂��B �@�����ł���Șb�������o���͖̂ʓ|�Ȃ��Ƃ�������܂��� ���A����͈��Ղɐ��_�����̖��O���o���č� �\����l�ނ��邱�Ƃ͏\���ɗp�S���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B �@���̏�ł����ă|���[�j�̌|�p�ɂ��ĕ]����Ȃ�A���̋ώ��ŋ��x�ȃt�H���e�̕����͎��ǃX�y�N�g���� (ASD) �Ɛf�f���ꂽ�L�\�ȃs�A�j�X�g���x�݂Ȃ��e�����Ɏ��Ă��銴��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B�m���Ă���͈̂ꕔ�̗�ł����A�������ϓI�Ȕ�g�\���ɉ߂��� ���B �@ASD �Ƃ����͎̂��NJ֘A�̏Ǐ�ނ���Ƃ��ɍŋߎg����悤�ɂȂ����������ŁA�y�x�ō��@�\�̃A�X�y���K�[�nj�Q�����W�����I�ɂ����Ɋ܂܂�܂��B�Ƃ� �ɑ��l�̊���� �����邱�Ƃɍ�����o���邱�Ƃ̂���l�����ł����A�O�����E�O�[���h���A�X�y���K�[���Ƃ悭������ɂ������� �炸�A���͔ނ������ɕ��ނ����悤�ȃ^�C�v�ł͂Ȃ��Ǝv���ƃO�[���h�̂Ƃ���ŏ����܂����B�O�[���h�͐l�̊� ��ɉߕq�Ȑl���Ǝv���܂��B�ނ��낻�������Ӗ��ł̓|���[�j�̕����A���̏�ł́A����E�Ə���������u���� �Ƃ̂ł���l�̃e�C�X�g�������Ă���悤�ȋC�����܂��B�ތl���A�X�y���K�[���ƌ��������킯�ł͂���܂� ��B�q�ϓI�Ȍ|�p�\���Ƃ����Ǝ��̕�����J��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�ǂ�Ȃ��̂ł���l���ƌ|�p�ɂ͈Ӗ�������܂��B�����ȉ��t�ɂ͂��ꎩ�� �ō��� ���l������܂��B�������ŋ߂ɂȂ��ă|���[�j�̎w �͐����Ă������A���̕������킢�[���Ȃ��Ă���Ƃ����l������ ���̂ŁA�ǂ̘^�������ꂩ�킩��܂��A�@��������畷���Ă݂����Ǝv���܂��B  Claudio Arrau �N���E�f�B�I�E�A���E �@�`���o�g�Ńh�C�c�Ŋw�A���E�́A�h�C�c�������\����x�[�g�[���F���e���̈�l�ł��B�P�X�O�R�N���܂�� �X�P�N�ɂW�W�ŖS���Ȃ��Ă���Q�O���I�̋����ŁA�S�W�͓��o���Ă���A�U�Q�`�U�U�N�ɘ^�����ꂽ�f�b�J�A�W�O�N�`�X�P�N�̃t�B���b�v�X�̂��̂�����܂��B�����I�ɂ��������Ă��Ȃ��̂ł������肵 �����Ƃ͌����܂��A�V���Ƃ��ɕ\���̕������͑傫���ς���Ă͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�V��Ƃ��Ȃ�� �w���������͎̂d���Ȃ��ł����A���̏d�Ȃ�Ƃ��낪�������₪�₵�����������̂ł��B �@�A���E�̃x�[�g�[���F���́A���S�ł����ނ̑傫�Ȋ���\���ɍʂ��Ă��܂��B�ςȗႦ�ł����A�Z���搶�ɋ� �����Ă���悤�ȁA�Ƃł������܂��傤���B�ӂ������炫���Ǝ����܂��B�A�S�[�M�N�A�f�B�i�[�~�N�i�h��Ƌ� ��j�A�Ƃ��ɑ�ϑ傫���ł��B �������ӊO���A�V�т�y���Ƃ������Ƃ͑S���Ȃ��A�܂��Ƃ��ȕ\���ʼn����̋���������܂��B����I�Ƃ͂������� ���Ƃ��Ƌ����Ă����悤�ɁB�^�ʖڂȉ��t�Ƃ��������O���_���M�����X�����̑����̉��t�Ƃ��܂܂�Ă��܂��� �ł��������������ɂȂ����킯�ł����A�ł͋�̓I�ɂ͂ǂ��e���Ă��邩�ƌ����A�͂Œ@�����͂Ȃ����̂́A������m�F����悤�Ɍ��R�ƒx���Ȃ�܂��B���������̂悤������肪�������ɂȂ� �Ƃ���ł͑�_�ɒx���������A�͂�������܂��B��ЂƂ��J�Ɋm�F���čs���悤�ș{���ʂ��ł��B���������ĂR�O�Ԃ̑�O�y�͂ȂǁA���ɂ����Ղ�Ɖ̂��Ă��܂��B���̓y�_���̈��� �̂������A�����n���ğӑR��̂ƂȂ��Ă��܂��B  Vladimir Ashkenazy �E���f�B�[�~���E�A�V���P�i�[�W �@�P�X�R�V�N���V�A�i�\�A�j���܂�ŕ��������_���n�A��ɐ����ɖS�������s�A�j�X�g�ł��B�����Ƃ����f�Ȃǂ� �������t�ł悭�]����A�[���Ō��_���Ȃ����������t�͖��l�ɍD�܂��ƌ����܂��B�f�r���[�����͉ؗ�ȋZ�I�ɂ��Č���A���̈���Ńx�[�g�[���F���̎����y�ł͂ނ���p�̂��郊�Y���ŏd�X�����Ќ��̂悤�Ȃ��̂������������ʂ�����悤�ŁA���̐l�炵������錾�t�͑��݂ɖ������肵�܂��B�R���N�[���ŗǂ����т��c���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ꑰ�̎g����тсA��ϋ�J�����l���Ƃ����b�������܂��B�����A�悹�ė~�����Ƃ���ƕʂ̕����Ɋ�����悤�Ɋ��������A���J�߂���悤�Ɏv��������A�������͂悭������Ȃ��s�A�j�X�g�̈�l�Ȃ̂ŁA�����ŏڂ����������Ƃ͂�߂Ă��������������̂�������܂���B �@�P�X�V�P�N����W�O�N�ɂ����Ę^�����ꂽ�x�[�g�[���F���̑S�W�̓X�^���_�[�h�Ƃ��đ�ϕ]�����������̂ł��B���̕]���ʂ�A���Y���͈��ɋ߂��A�傫���e���|�����悤�ȂƂ���͂���܂��A�������̂Ƃ��� �ł̕������ɂ͓���������A�Ƃ��ǂ��x�߂ĔS��̂͂��̐l�̌��̂悤�ł��B��̎����̂̓��V�A�I����Ƃł�������悤�ȏd�����^�ʖڂȂ��̂�����������u�Ԃ�����܂����A���ꂪ�\�ʂɏo�߂�����͂��܂���B����ɑ��ăs�A�m�̉��̓t�H���e�Ōy�����邢�̂��ΏƓI�ł��B����̓f�b�J�̘^���̂�����������܂��A�������ɏ�ɋ����I�Ȕ{�������h��ȂƂ��낪����܂��B�����p�b�Z�[�W�͐��m�ł��B
�@�l�I�ɂ̓��t�}�j�m�t�̃��v�\�f�B�[�i�p�K�j�[�j�̎��ɂ�鋶���Ȃ̈�Ȃʼnf�� �u������ǂ����Łv�̃e�[�}�j�ȂǁA�������܂�Ȃ����Ȃ��o���Ă���Ă���̂ň������Ă��܂��B���������t�}�j�m�t�̋��t�ȑ�Q�Ԃ̍ŏ��̘^���Ɋւ��Ă����́A�d���͂��邯�ǐ�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B  Rudolf Serkin ���h���t�E�[���L�� �@�́u�c��v�����Ƃ��ɂ͋����ȊO���܂��ۂɂȂ������̂ł����A�[���L���Ƃ����l�A�������R�O�Ԃ��A�Ȃ� �Ə�̂��鉉�t�Ȃ̂ł��傤���B�S�̂ɂǂ��������Ēx���Ȃ��^�т̒��̂��̕\��̖L�����A�����������Ɋׂ�� ���ْ����B�ǂ��e���Ă���̂ł��傤�B �@�����̑��y�͂ł͂�����Ɨ���Ă���悤�Ŕ�����u�x�ꂽ�肵�ĐÎ���������܂��B�U�ꕝ�̏��Ȃ����ɂ� �������Ƌ�������G�ɑ��Â��Ă��܂��B�Ƃ��Ɍۓ��������ɑ����Ȃ�Ƃ���ȂǁA�v���o�����Ƃ��߂����l���ꂵ�� ��̂��A����������������̂��A�u�ԓI�ȋ������h���S�̓������f���o���܂��B���̑@�ׂ��̓[���L���Ȃ�ł͂� ���傤�B�����đ�O�y�͂̋����悤�ȑ������܂��Ƀp�b�V�����ł��B �@�W�V�N�^���̂R�O�Ԃ��o�����̕��������G���K���g�ł��B�g�̂悤�ȑ傫�Ȍċz������Ȃ����Ƃ͑S���� �Ȃ�f���P�[�g�Ȗ��킢������܂��B�t�H���e�̃^�b�`�͑�ϋ����ł����͂ʼn�����݂��͂���܂���B�ꉹ�� ������������Ƒ��炸�A����o�����ƂȂ��[���ŁA�N���o���Ă�����̂ɑf���ɏ]���Ă���悤�ł��B�� ��y�͖͂����ł��B��O�y�͂�����̃A�N�Z���g���͂�����Ƃ��āA�c�X�Ƌ�����͋����t�H���e������܂��B�����ĉ��ɓƎ��̔S�肪����̂ɏd�������M�� �܂���B���ꂪ���ݏグ�Ă���Ƃ��� �����Ȃ�Ȃ��Ƃ���ɂ͖{���Ɋ������܂��B���F�͓Ɠ��ŁA�����^�b�`�ł͔{���ɂ�����ƃn�[�V���ȉs�������� �����A���̂Ƃ��ɂ͂��łɐS����������Ƃ��܂�Ă���A�����ꂽ���Ƃ͂܂���������͂Ɋ����܂��B���̋Ȃ̏I �����͓��˂ł����A���̌�Ɏ��ԍ��ł���ė��鋻���Ɉ��|����܂����B�f��������܂��̂Ő��Ăق����Ǝv ���� ���B �@���h���t�E�[���L���A�`�F�R���܂�̃��V�A�n���_���l�ŃE�B�[���炿�B�P�X�X�P�N�ɂW�W�ŖS���Ȃ��Ă��� ���B�s�A�m�̓X�^�C���E�F�C�ł��B�S�Ȃ͑����܂��A������̂����ł��x�[�g�[���F���̃\�i�^�Ƃ����ΊO���� ���������Ǝv���܂��B  Emil Gilels �G�~�[���E�M�����X �@�P�X�P�U�N���܂�̃��_���n���V�A�l�̃s�A�j�X�g�A�M�����X���x�[�g�[���F���e���Ƃ��Ă͖������l�ł��B�P�X�W�T�N�A�S�W����������O�ɖS�� �Ȃ��Ă��܂����̂őS�Ȃ͑����܂��A�R�O�Ԃ͍Ō�̔N�ɘ^�����ꂽ���̂ł��B�����ŗY�ӂȉ��t�Ƃ悭�]���� �܂������A������肵���p�[�g�ł͂ǂ��ɂ�����Ƃ��낪�Ȃ��A��┏��x�����炷���Ƃ�����A�d���ƂƂ��ɓƓ� �̐[���Â���������܂��B�ꉹ����ɒe���čs���悤�ȉ��͂����Ƃ�Ƃ������������A���̃s�A�j�X�g�̔ӔN�� ���n�������܂��B�t�H���e�͋}�����ƂȂ��A�͋������R�Ƃ��Ă��܂��B�u�|�S�v�Ƃ����\���������邩�ǂ����͂킩 ��܂��A�ǂ����Ƃ��Ă���ϐ����Ȑl�ł���悤�Ȉ�ۂ�^���܂��B��ϑf���炵���ł��B�����̕����d���A�� �}���e�B�b�N�Ȏ�͂���܂����A������Ɩ��̒��ɂ���悤�ȁA�Ɠ��̕������܂��B �@�R�O�Ԃ̘^���͐V��������������A�ނ̏���Ȃ����t�ɑ����� �������Ɖ��̂��邫�ꂢ�ȉ��ł��B���q�e���̉��ɂ����Ę^��Ă��܂����A�X�^�W�I�Ƃ������_������̂��A������ �̕��������₳����������ł��傤���B �@�M�����X�̌|�p���w���āA����قǐ[�����_�����������鉉 �t�͂Ȃ��̂��ƌ����l�����܂��B���_���Ƃ������t������\�����͂Ƃ������A�����Ƃ��邱�Ƃ͂悭�����ł��܂� ���B���x���\�A�����猾���킯�ł��Ȃ��ł����A�������̐l�����̉��Ɍ���Ă���悤�ɐ����Ȑl��������A�R�� �N�[���̂��ƂȂǐF�X�����܂����A�����炵�����낤�Ƃ��ċ�J�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�x�[�g�[���F���� �����l�ɗ͋����Ƃ܂����������C���[�W����l�ɂƂ��āA�M�����X�������̐l�A�ō��̉��t�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B �S�Ȃ�����Ȃ��A�Ƃ��ɂR�Q�Ԃ��Ȃ��͎̂c�O��������܂��A�����I�ł��B �@  Sviatoslav Richiter �X�����g�X���t�E���q�e�� �@���V�A�̃s�A�j�X�g�ŃM�����X�Ƃ悭��r�����̂̓��q�e���ł��傤�B�N����ΈႢ�̂P�X�P�T�N���܂�A��� ���V�A�l�Ȃ��畃�̓h�C�c�l�ł��B�̐��䂦�ɂ��̕������ǂ����^���ƉƑ����ŁA�����₷���N���ɔނ��ߍ��� ���X�𑗂������Ƃ͂悭�����Ƃ���ł����A�@�ׂł������Ō��i�Œ���I�ƌ�����ނ̐��������������̌� ����o�����̂ł��邱�Ƃ͑z���ɓ����܂���B����A���Ђ╶���ł��̌|�p�������\���̗c�t�ł����A�c�O�Ȃ� ���X�͎������Ă��Ȃ�����W�c���ꉻ���鐶�����ł����A�ƏW�c�Ƃɂ͕s�v�c�����s�I�W������܂��B���������č������Ƃ������̂��A�c�����Ɏ��͂̉��l���z�����ނ��ƂŁA����� �x���̐F���������Ă��Ă��܂�����������̂ł��傤�B�Ɗw�̕����������������q�e���͕ʂ��� ���Ă��A�s�A�m�̌�@�Ƃ����ǂ���O�ł͂Ȃ��A���t���������̂悤�ɒe���̂��ƑS���Ŏ����Ă���A���ꂪ�o�� �_�ɂȂ�̂�������܂���B�T�O �N��̃��_���E�W���Y���V�O�N��ɂȂ��ĕώ����Ă�����A���̃r�E�o�b�v���c���Ă���͖̂k�� ���A�������ƌ���ꂽ�悤�ɁA�T�A�U�O�N��܂łłP�X���I�I�ȃ��}����`�̌p���҂͑�ւ�肵�A���̐F���c���Ă���̂̓��V�A�n�̐l�������ƌ���ꂽ���� ������܂����B�ł�����͂����郍�}����`�Ƃ͕ʕ��ł����āA���V�A�Ǝ��̉����Ȃ̂�������܂���B���������炷��ƁA���q�e���ȊO�ł��ˑR���U�[���E�x���}����~�b�V���}�C�X�L�[�̂悤�� ���l���o�ė���͕̂s�v�c�Ȃ킯�ł��B�@�@ �@���q�e���ƃM�����X�A���̓�l�ɋ��ʂ��Ă���̂͂��܂�ׂ��ȍH�������A����肪�傫���A�d�����������A���v������������^ ����Ƃ���ł��傤�B�^�b�`�̋��������Ă��܂��B�ǂ�����t�H ���e����ϗ͋����̂ł��B���q�e���̕��͍D�݂ł� ���Ȃ͎��グ�Ȃ������Ō������������A�R�O�Ԃł̔�r�ƂȂ�܂������A�^�����h�C�c�E�O�����t�H���ƃt�B���b�v�X�̃��C�u�Ƃ����Ⴂ�͂����Ă��A���F�̌X���� ������Ǝ��Ă��܂��B �@�Ⴂ�̕��́A�傫�ȃ��o�[�g�ł͂Ȃ��ł������q�e���̕������ׂ����h���X��������A�����I�ɂ͑��肩�����ʂ������܂��B �S�̂Ɍ���I�Ȉ�ۂł��B�o�b�n�̕��ϗ��ȂǂŎv������̋����㉹�����郊�q�e�� �ł����A��������̓�������̂�����̊炾�Ƃ����C�����܂��B���q�e���͂X�P�N�̘^���� ���̂U�N�O�A�M�����X���l�ӔN�̌͂ꂽ���n�ƌ�����Ȃ���A���̒����ǂ����݂�^���_���h�ł̓��q�e���A�����Ƃ�������q�e���̕����M��I�ł��B���W�X�� �����Â���������̂̓M�����X�ł��傤���B �@ 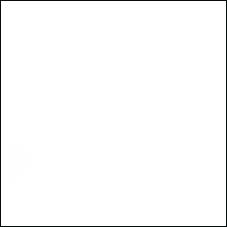 �@ Murray Perahia �}���C�E�y �A�C�A �@�o�b�n�ł͗����悤�Ɏ��݂ȗ}�g�̂����A���������o���Ă����y���C�A�A�x�[�g�[���F���ł͂ǂ��ł��傤 ���B�S�W�͏o���Ă��炸�A�������R�O�Ԃ� CD �͂Ȃ��̂ł����ł͔ԊO�҂ɂȂ�܂����A�R���T�[�g�̖͗l�� �E�F�u��ŕ� ���܂��B�o�b�n�̂Ƃ��̐Â����Ƃ͂܂������Ⴂ�A�R�O�Ԃł͂��d���A�^���̂���x�߂̃e���|���Ƃ��Ă��܂��B�͂܂Ȃ��Ƃ���͑��ς�炸�ł��B��O�y�� �ȂǁA���^�M�C�����Ǝv����قǂ̒�����������͍̂�ȉƂɑ���ނ̊������Ȃ̂ł��傤���B�������̎v���� ���ނ悤�ȌX���͌�����l���Ǝv���܂��̂ŁA�ÓT�h�Ȃ��烍�}���e�B�b�N�ȂƂ���̂���x�[�g�[���F���Ƃ͑� �����ǂ��悤�ł��B�u�����f���̊����₷���Ɗ����Ɏ��Ă��� �悤�ɂ��v���܂����A�����߂����ł���������������������ł��傤���B �@�S�[���h�x���N�ϑt�Ȃł̓A���h���[�V���E�V�t�Ɣ�ׂ܂� �����A�����ł������I�ȌX���͂���A�y���C�A�̕����V�t�����Z���t���[�Y���ł̗h��͏��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B �ꏬ�߂̒��ł��镔��������������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���������傫�ȃt���[�Y���Ƃɗ}�g��t���܂��B�傫�Ȃ� �����Ă��A���E�̂悤�ɉ����Ă��銴���ɂ͂Ȃ炸�A�S�̂ɂ�Ƃ肪����܂��B�o�b�n�̂Ƃ��Ɠ����悤�ȐÂ����� �����Ă���Ƃ������܂��B�Ƃ����Ă������t�H���e���_�C�i�~�b�N�łȂ��Ƃ����̂ł͂���܂���B�ނ������\���̑傫�ȉ��t���ƌ���˂Ȃ� �܂���B�ς�������悤�Ȋ����ł͂Ȃ��A�R�Ă��܂��B �@�P�X�S�V�N���܂�̃A�����J�̃s�A�j�X�g�A�������Ɍ���I�ő���͌������A��������Ă��܂��B�������^���� �^�������ȁA�����\����x�[�g�[���F���̈�ł��傤�B  John O'Conor ♥♥ �W�����E�I�R�[�i�[ ♥♥ �@���̐l�ɂ��Ắu�����v�Ɋւ��ĕʂ̏͂ł��łɂƂ肠���܂����i�u�Â��ȃ^�b�`�^�x�[�g�[���F�������\�i�^�v �j�B�P�X�S�V�N�A�C�������h�̃_�u�������� ��ŃE�B�[���Ŋw�l�ł��B���̃x�[�g�[���F���ɂ͒�]������A�P���v���C�^���A�ŋ����Ă����u���������p ���A�A�����J�ł͒m���x�������悤�ł��B �@���t�͕Ȃ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ȃ����ϓƓ��ŁA����قǂ��炩���\�����������l�͂� �Ȃ��ƌ����܂��B�����đ��炸�����炸�A�x�[�g�[���F��������Ƃ����Ăނ�݂Ȍ���ɋ���邱�Ƃ͂���܂���B�t�H���e�͖����Ȃ��͋����ł����A�ߓx �Ɨ]�T�������Ē@������悤�ɂ͒e���܂���B��ɉ��₩�Ȓ� �ɑ@�ׂȕ\�����A�㉹�̕\���ϖ������܂��B �@�R�O�Ԃ������������\�t�g���n�܂肩���O�y�͂̐� �����܂������ŁA�Â��Ȃ炸�ɐ[�݂�����A�ӔN�̐��� ���n��]���Ƃ���Ȃ��`���Ă��܂��B�F�X�ȉ��t�������Ă݂���Ŏv���̂ł����A���̑�l�̖��͂ɂ͍R���邱�Ƃ� �ł��܂���B �@�s�A�m�̓n���u���N�E�X�^�C���E�F�C�Ə�����Ă��܂����A�X�O�N�^�������̉��͉��t�Ɏ������� �h�肳���Ȃ��A���������F�ł��B���[�x���̓e���[�N�ł����A�X�`���[�_�[�̃R���\�[���ɃX ���b�V�����h�̃A���v�A�ȂǂƋ@�ނ��ׂ��������Ă���A�P�W�r�b�g�^���������悤�ł��B�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�Ƃ��ẮA�l�I�ɂ̓V�t�ƃ��C�X �ɕ���ōł��D���Ȃ��̂̈�ł��B 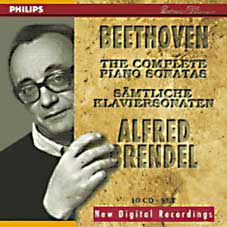 Alfred Brendel �A���t���[�g�E�u�����f�� �@�P�X�R�P�N�`�F�R���܂�̃I�[�X�g���A�̃s�A�j�X�g�A�u�����f�����x�[�g�[���F���ӂƂ���l�ŁA���̑S�W���x�X�g�Ƃ���t�@���������Ǝv���܂��B�u �����f���̃s�A�m�������ȂƂ����h��ȂƂ���͂Ȃ��Ȃ� ��A��ɉA�e�ɕx�݁A���ȓI�ȍ����Ƃ��Ƃ��Ɠ��̏�������o ���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�����̃h���}���ƌ����Ă��ǂ���������܂���B�����Ԑ̂Ƀt�B���b�v�X����o�� �o�b�n�̍�i�W�ȂǁA��_�Ƃ��Ƃ��قǃ��}���I���o�b�n�Ƃ͎v���Ȃ��Ƃ��낪����܂������A�x�[�g�[���F���ɂ��ẮA���̑��ȉƂ��Ƃ� �ǂ�������Â���������܂��\�����Ă��ꂻ���ȋC�����āA��ϊ��҂��܂����B �@�����͂����Ղ肵�߂���������Ƃ��߂��������A�\��L���Ɏn�܂�A��σI�[�\�h�b�N�X�Ȉ�ۂł��B�_���p�[�� ����ɕ�������قǂ����Ղ�Ƌ������v ���ʼn������āi�y�_��������āj����A�����ł��B����ŁA�\�z�������͎v�����ꂽ���Ղ�Ƃ����킯�ł͂���܂���ł����B��� �y�͂̃R���g���X�g���f���炵���A�y���� ���A�^�ʖڂȉ^�тł��B��O�y�͂͑����Ȃ��獎���ŗ͂��������Ă��܂��B �@�R�O�Ԃ͈ӊO�Ȃقǂ�����Ǝn�܂�A�삯���ɂȂ�Ƃ���ł͌y���ł��B�u�����f���͂���������ɑ����̑t�� ����������߂����ȂƂ���Ō���������H�킹�ăe���|�ǂ��s���ꍇ������܂����A����ȏꍇ�ł����̉��ɂ͂ǂ� �����̎v���̂悤�ȏ�����܂��B���y�͂͗͂ʼn��������͂Ȃ��Ȃ��玕��ǂ��A�ɂ߂�Ƃ���ł� ���炩�����ݍ��݂܂��B��O�y�͓͂Ɣ��I�u�����f���̓ƒd��ł��傤���B�e���|�����ő�ɒx���킯�ł͂���܂��A��ЂƂ̉��ɍő���̎v������ �߂��Ă���悤�ł��B����C������A��₤�ނ��Ă��āA�߂����ȖڂŐZ���Ă���ނ̎p�������Ԃ悤�ł��B�� ���Ƃ܂ł͌����܂��A���̂��ꂢ���� �ޓƓ��̐��E�ł��B�`�F�R�l�̃����^���e�B�ƊW������̂ł��傤���B���̎v����₵���Ȋ����͂Ƃ��Ƀy ���C�A�ɂ�������܂����A�u�����f���̂͂����炩���A�����ł����₭�������Ȃ��̂Ɋ����܂��B �@���M���ׂ��̓s�A�m�̉��̂��ꂢ���ł��B���炩���Đc������܂��B���t�B���b�v�X���u�����f�����^���͂ǂ�������ł� ���A�ۂ����ƍd���ȋP���̃o�����X���ǂ��A���[�c�@���g�̋��t�ȂȂǁA�ɏ��y�͂Ȃǂ����Ղ���߂����Ǝv���� ����������̉��̂��ꂢ���Ɏ䂩��Ă����Ă������Ƃ��v���o���܂��B �@�R�x�ڂ̑S�W�͂P�X�X�Q�N����X�U�N�̘^���ł����A�x�[�g�[���F���̃\�i�^���͂Â��łȂ��������Ȃ��Ɗ��� ��l�A�ׂ₩�ȃj���A���X���~�����āA�Ȃ������̃u�����f���Ɠ��̊���E���D�݂ɍ����l�ɂƂ��ẮA����� �ō��Ɋ����x�̍����Z�b�g���Ǝv���܂��B���������Ƃ��낪�ǂ��ɂ���������܂���B  Maria Joao Pires �}���A�E�W���A���E�s���X �@�P�X�S�S�N���X�{�����܂�̃s���X�i�s���V���j���P���v�̋����������Ƃ̂���s�A�j�X�g�ŁA��̌̏�ŋx�ވȑO�͗��̑��������F�Œ[�� �ȉ��t�A���A�ȍ~�����炩�ȕ\��Ȃ��炶������Ɖ� ���l�Ƃ����C���[�W������܂��B�ꎞ�����@�C�I�����̃f�����C�ƃp�[�g�i�[�ł����̂ŁA���̂Ƃ��Ɉꏏ�ɗ����R ���T�[�g�Œe�����R�O�Ԃ̃\�i�^�̔������͈�ۂɎc���Ă��܂��B�s�A�m�����}�n�������̂Ŏ㉹�̂��炩���͗� ���������̂́A���̂Ƃ��̃Z�b�e�B���O�ł͋������̗֊s�͂��܂肭�����肵�Ȃ������o������ ��܂��B���{������̃`���C�X�Ȃ̂��A�z�[���ɂ̓X�^�C���E�F�C���x�[�[���h���t�@�[������̂ɂȂƎv���Ă��� ��A���̌����ƂR�O�Ԃ̓����� CD �ł� CF-�V���g���Ă���̂ŁA�{�l���C�ɓ����ă��}�n��e���Ă���悤�ł��B�����ł̘^���ł͂��̔��_���o�Ă���ƌ�����ł��傤�B �@�W���P�b�g�͎����� CD �𗯂߂�Ƃ��낪�R���N�ɂȂ��Ă���A�傫�Ȍ����`���ꂽ�������Ȃ��̂ł��B�����Ƃ��̊֘A�Ȃł���P�R�ԁi���j�A����Ɍ�� �̒��ł����z�Ƃ������͌��ł���悤�ȂR�O�Ԃ̑g�ݍ��킹�ɂ́A�����ł���s���X�̐��r���I�z�������߂��� ����̂�������܂���B�h�C�c�E�O�����t�H���Q�O�O�O�N�̘^���ł��B ����O�y�͂̏o�������s �A�m�E�R���`�F���g�̎O�Ԃ̑��y�͂��v�킹�܂����AOp.27 �Ƃ��Č����Ƒg�ŏ�����Ă��܂��B�l�y�͍\���Ō��z�ȕ��\�i�^�Ƃ���A�P�Q�Ԃ́u�����v�Ƃ̗ގ����w�E����邱�Ƃ�����Ȃ���A�����Ƃ��ǂ��A�{���� ���Ƃ͊W������܂���B �@�����̏o�����ł� �������Ƒ@�ׂȕ\����Ă��܂��B���肵������̔��t�̏�ʼnE��̉��F���ω�����l�� �L���ȉ̂ł����A�e ��������������̂ł͂���܂���B�Ƃ����� ��ۓI�Ɍ����E��̋������̓X�^�C���E�F�C�Ƃ͈���������ŁA�ߓx�ɉ����t�����A�Ō��� ����œr������d�߂̔{�������т� �悤�ȓƓ��̂��̂ł��B�S�̂ɂ��炩���������ǂ��Ƃ���ł���Ȃ���A�\���b�h�ȕ\����`������̂ł��B �@���y�͂���ۓI�ȃ��K�[�g������A�悭�̂��܂��B�ڈȍ~�� ���C�Ȃ����������ς莝�������郊�Y�����G���K���g�ł��B��O�y�͂͑����ł����A�y�₩�Ő[���ɂ͂Ȃ�܂���B �@�R�O�Ԃ͏o������������������悤�ȁA��ЂƂ� ���������ނ悤�ȃe���|�Ői�݂܂��B�r�������Ƃ���ł�╽�R�ȂȂ� �Ɋ����镔��������܂����A�S�̂ɂ͒x���A����ł��Ēj���̃s�A�j �X�g�ɂƂ��ǂ�����悤�Ȋ����I��ɂׂ͊�܂���B������悤�ł͂����Ă��y�V�~�X�e�B�b�N�ł͂Ȃ��A���J�� ������̂悤�Ɋ������܂��B����͑�O�y�͂̃X�^�b�J�[�g�������Ƃ���ł��A�����y�₩�Ƃ����̂Ƃ͂������ �Ⴄ�[���ȕ\��ƂȂ��Č���Ă���悤�ł��B���̐l�A����̌����Ă��镔���ɂ͂��܂�͓_���Ȃ��̂ł��傤���A�Ō�̊y�͂̑����p�b �Z�[�W�ł������悤�ɂ��Ȃ��čs���܂��B �@���S�ł�����������t�ł����B���J���@�ׂȂ̂ɁA���炸�A�� ��킳�������Ƃ��낪����s�v�c�Ȗ��͂ł��B�x�[�g�[���F���ӔN�̂ӂ����ꂽ���邳�Ƃ����Ӗ��ł́A������ ���邩������܂���B �@�@�@  Paul Lewis ♥♥ �|�[���E���C�X ♥♥ �@����C�M���X���\�����L�ȍ˔\�ŁA�{���ł͘b����s�A�j�X�g�B�����`�p�J���҂ʼn� ���ɉ��y�W�҂��N�����Ȃ����ň炿�A�u�����f������q�Ɏw�������Ƃ������̎��̃s�A�j�X�g�ɁA���ǂ������� �S��D���Ă��܂��܂����B�P�Q�ɂȂ��Ă���{�l���D���Ńs�A�m���n�߂��Ƃ����o���́A���܂��O���珀���� �ꂽ���łR�ɂ��Đ_���Ԃ���A�Ƃ����̂łȂ���f�r���[�ł��Ȃ��悤�ȃR���T�[�g�E�s�A�j�X�g�̐��E �ɂ����āA��̐V�����_�b�Ȃ̂�������܂���B�C���^�r���[�ł�����Ȃ��l���ŁA�R���T�[�g�ł͒d��ŋ����� ��I�[�P�X�g���̏����t�҂��V�������l������悤�Ȋ፷���𓊂��܂��B�ł��O�������ł͂Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B �x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^�Ƃ����ƁA�������������Ǝv���ĉ����ɂȂ�Ƃ������A�咣�̋������t�ł͓��ɂ����ł����A�������̋C�ɂȂ�Ȃ��Əd�������� ����Ȃ����Ƃ�����܂��B���������̐l�̉��t�͓����ŁA���ȑ����Ă����Ă������ȂƎv�킹�鎊���̎��ݏo�� �܂��B�ȏW�ɑ����ۂ��ς���Ă��܂��Ƃ����Ӗ��ł͊v���I�ȑ̌��ŁA���̓_�Œ��_�̃x�[�g�[���F���������� �܂���B�ǂ����ǂ��e���Ă���ƂƂ肽�Ăĉ������悤 �ȂƂ���͂Ȃ��̂ɁA�f���P�[�g�ł���߂đN��ł��B �@���������t�Ȃł́A�ŏ�������Ɣ����Ă悭�킩��Ȃ������Ɣ��Ă����܂��B�u�c��v�ȂǐF�X�ƕϑJ���Ă� �܂����B�P���v�̑��y�͂��ō��Ȃ���^�����Â��ăI�[�P�X�g���̉�����Ȃ��Ǝv���Ă݂���A���x���o���u�� ���f���̌Q�̒��Ŗ����ČÂ����̃n�C�e�B���N�Ƃ̘^����T������A�y���C�A�Ɋ��������肵�Ă������̂́A�Ȃ��� ����Ƃ������ߎ�Ɍ����܂����B�����ă��C�X�̂���ɓ��ꂽ�Ƃ��A�Ȃ�ƂȂ��A���������Ȃ��ȁA�Ǝv�����B���� ���ǂ���獡�ƂȂ��ẮA���t�ȂƂȂ�Ƃ��̐l���肩���Ă��܂��B �@�l���B���E�}���i�[�̂Ƃ���ł��������Ƃ������܂������A�p���̉��t�ƂƂ����ƁA�����Ɨ}������ϕi�̂悢 �W�F���g���}���i�E�[�}���j�ł����āA�h�C�c�l�̂悤�Ɍ��i �ł����}���e�B�b�N�ł��Ȃ��A�t�����X�l�̂悤�ɕ����������ł��Ȃ��A�����������ǂ��� ����������̂��킩��Ȃ��Ƃ����� �Ԃ��N�����܂��B�C���������悤�ɕ����������t���F���i�������ƖJ�߂�̂��Ɓi�}���i�[�̂��Ƃł͂��� �܂���j�A���Ă͌��ЂƂȂ�Βm��Ȃ����̂��m�����ӂ������A��̃C�M���X���X�m�r�Y������Ȃ��̂��Ɗ��J�肽���Ȃ�܂��B�������Ȃ̂͂����ꕔ�ł���A�f���炵�����t�Ƃ͂�������킯�ł����B �@�ł̓��C�X�͂ǂ��Ȃ̂��A���̉��t���m���ɃC�M���X�l�ƌ��� �C�M���X�l�ł� ��A�A�S�[�M�N������������ďo�߂����Ƃ��낪����܂���B������Ƃ��Ă��ĉߏ�ȃ��}���e�B�V�Y���Ƃ͈�����悵�܂��B�ǂ��\�����܂��傤���A�I�R�[�i�[�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�I�R�[�i�[�͋C�ɂ����ĕʍ��i�u�Â��ȃ^�b�`�^�x�[�g�[���F�������\�i�^�v �j�ň����܂����B�����đ傫�Ȑ����o�����A���炩�Ȏ㉹�̒��ɖ������~�������Ă���̂��������ł��B �@���Ƃ����āA�t�ł���`�F�R���܂�̃u�����f���Ƃ������͈Ⴂ�܂��B���C�X�Ɏt�̂悤�� ���ނ��������Ǝv�����݂̗͂͊����܂���B�Ƃ茾���������߂閶������܂���B �@������肵�������ł̓f���P�[�g�ɑ�ς悭�̂��A���₩�ŗD�����A���y�̓����ɕ��������� ����悤�ł��B���C�u�f���Ȃǂł͂Ƃ��ɂ������߂���قnj������ĉ��Ɏv�������߂Ă���Ƃ��������܂����A ����ł����������Ɖ������͊������܂���B �@���������������g�債�Č��Ă݂�ƁA���ɔ��ׂȂ̂ł����A�v��ʂƂ���ŏ���������߂���A����������A �Ԃ��Ƃ�����Ƃ������͂̔��������Ɋ��S���܂��B�M���Ȃ�߂����A�X�g���[�g�ɒʂ�߂����ɏ��������҂��Ă��� �悤�ŁA�������ɃZ���X�̗ǂ���������̂ł��B�Ƃ����Ă��قƂ�NjC�Â��Ȃ��قǍT���ڂŁA�ɂ₩�Ɍċz���鑧 �����ɂ���������킹��ƁA�L���Ȋ����������Ă���Ƃ�����ނł��B�I�R�[�i�[��肳��ɍT���߂�������܂� ��B �@�����Ĕނ͌����ڂ̑@�ׂ��Ƃ͈���đ̊i���ǂ��A����傫���̂ł��傤���B��σp���t���Ȑl�����ƂȂ������� �Ƃ��������ŁA�ǂ�Ȃɑ����p�[�g���y�X�ƒe���Ă��܂��܂��B�I�N�^�[�u�ȏ�ɘA�Ȃ�Ƃ���ł͑S�Ẳ������C���ǂ��������Ă���A�X�^�C���E�F�C�Ɠ��̂�����Ƃ����{�����܂܂������Ă��܂��B���̐ꖡ�͂������̂ł͂���܂���B�����̒������炩���ߌ������Ŕ`�� �Đ����Ă������悤�ȗ}�g������ł��܂��B�Z�p�ɂ����Ċ����Ƃ����_�ł̓|���[�j�ɗ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤 ���B�S�����ώ��ɑ����ċ��x�ȃ|���[�j�͑��̂��Ȃ��Ƃ��������܂������A���C�X�͌y�₩�ł��B �q�����C�ɓ������V�т��J��Ԃ��₩�܂�����A���ł̘A���ɖ��@���ȔM�ӂ������邱�Ƃ͂���܂���B���������ăt�H���e�͑҂��������A���������܂��B�����Ăӂ��ƖK���㉹�̑����̂ޔ������B �@�Ȃ��Ƃɏ����̂�Y��Ă܂������A�����ɂ��Ă��R�O�Ԃɂ��Ă��A���ɂǂꂩ�̋Ȃ��Ⴄ�e �����Ƃ����킯�ł͂���܂���B����Ȓ��œ����I�Ȃ��� ��������Ƃ���A�����g�V���^�C���͋����قǕω��ɕx��ł����ł��傤���B�܂��A�]�v�ȍH�������^�������e����邹��������A�R�Q�Ԃ̑��y�͂��f���炵�����̂ł����B �I�R�[�i�[�̂悤�Ȃ��炩�ȉ̗w���Ƃ͈Ⴂ�A�}���Ĕ��ɂ������e����邽�߂����������_�鐫����������ʂ� ����܂��B�r���t�H���e�ɂȂ��O�ϑt�̕����ł͗͋����������A�܂��������Ƃ����ϐ����ɖ߂�܂��B�V�t�ق� �G�l���M�[�̒���߂��h��͂Ȃ��ł����A�����炩�畷���ɍs���� ���̋Ȃ̌Ǎ��̔��������Ă���܂��B �@�Q�O�O�T�`�Q�O�O�V�N�i�S�W�^�����͂O�U�N�A�R�O�Ԃ͂O�V�N�j�̃n�����j�A�E�����f�B�̘^�����ǂ��A�ނ� �P�O�O�O�l�ڂɑI�ꂽ�X�^�C���E�F�C�E�s�A�j�X�g�������ł����A���̉�����ϔ������̂����̑S�W�̖��͂� ���B�o�����X�I�ɒ��ቹ�̓r�[���Ƌ����Ă��炩���A�������ߓx �ɂ���т₩�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ���G�b�W�������Ă���A�Ⴂ�������Ԃ��ē����������Ȃ��邱�Ƃ͂���܂���B�� ���炢�̂��炩���^�b�`�Ɖs���^�b�`�Ƃ̉��F�̍����傫���A�����̍������ł��B���������^���ł͔ނ̖��͂͑䖳���ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B �@�|�[���E���C�X�B�����������Ȃ����B���t�҂��Ƃ��������A��i�Ɍ�点�鉉�t�ł��B���̂悤�ɂ��ĕ����яオ���Ă���� �ȉƂ̌����ނ̈Ӑ}����Ƃ���ł���A���܂łɂȂ��V�����ł��B�������肵�Ă���ƋC�Â����ɒʂ�߂��Ă��܂��悤�ɍT���ڂł����A�������ꂽ��}�ƌ����܂��傤���B������V��������̃x�[�g�[���F���Ȃ̂��A���C�X�炵���Ȃ����ƂŃ��C�X�炵���x�[�g�[���F���� �̂��B�I�R�[�i�[�ɂ��V�t�ɂ��ʂ̖��͂�����܂����A�ډ��̂Ƃ���x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^�S�W�Ƃ��Ă͊ԈႢ�Ȃ���Ԃ̈�ł��B���� �x�[�g�[���F���������l�A�����Ă��n�t��������ς����������ɂł���l���ŏ��ɔ����ׂ����́A���ꂪ����� ���B�����Ă��ꂾ������Ώ\���ł��傤�B�P�X�V�Q�N���܂�B���� ���l���o�Ă��܂����B  Daniel Barenboim �_�j�G���E�o�����{�C�� �@�S�W���O�قǏo�Ă���悤�ł��B��背�[�x����n������悤�� EMI�A�h�C�c�E�O�����t�H���Ɨ��āA�ŐV�̂͂Q�O�O�U�N�̃��C�u�����^�����f�b�J�Ղł��B���̃o�����{�C���Ƃ����l�͎w���҂Ƃ��Ă���ʂ̘^�����o���� ���܂��B�P�X�S�Q�N�A���[���`�����܂�̃��V�A-���_���n�s�A�j�X�g�ł����A�悭�����ł��ĂȂ��̂ł��܂��鎑�i���Ȃ���������܂���B���y�ɂ͉��̊W������܂��A�W���N���[�k�E�f���v����M�h���E�N���[�����Ƃ̕��G�ȊW�����ԓI�ɂ͘b��ɂȂ�悤�ŁA�f�悷��蒆�ɂ���˔\����l�̂悤�ł��B���̉��y�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�����ɂ���Ă͋����_�̂�����������ɂƂ��Ă͕��������[�c�@���g����������A���ɂ���ȏ�͂Ȃ��Ǝv����傫�ȕ\�������������ʂ̍�ȉƂ̋Ȃ��������肷��Ƃ�����ۂł��B�x�[�g�[���F���̐V�����S�W�̘^���́A������₷���}�g�Ƃ����Ӗ��ł͌�҂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�ǂ���̏ꍇ���������猻��ė��鉽���ɂ����炪�`���[�j���O�ł��ĂȂ��悤�ł��B���̐l������Ƃ������Ƃ͂�����D�ސl������킯�ł�����A�ڂ����]�̓t�@���̕��ɔC���܂��B  Andras Schiff ♥♥ �A���h���[�V���E�V�t ♥♥ �@���g�̃}�X�^�[�N ���X�ŁA�V�t�͌����\�i�^�Ɋւ��āu�܂������v���I�ȃ\�i�^�ł��B�ӏ܂���Ƃ����������ƒe�����ׂ��ȂŁA ���͂���͑�Ϗd�v�ȋȂ��Ǝv���܂��v�ƌ������A���ۂɏo�����̐����߂��_���p�[�E�y�_���܂ܒe���� �݂��Ă���ȉ�������Ă��܂��i�r������ ��j�F �@��ϊ���Ǝv����������܂���ˁB�����Ă���݂͂Ȃ��� �m���Ă銴������Ȃ����A�݂Ȃ��e������ ����Ȃ����A�݂Ȃ���̂�������e���悤 �Ȏd���ł��Ȃ�... �N������ȕ��ɒe���Ȃ��킯�ł��B�ŁA������Ɛ��������Ăق�����ł��B���߂̖���_���Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ȃ�D�܂����Ȃ��ł��傤���A���̃P�[�X�͑�� �d�v�ŁA�Ƃ����̂����̋Ȃ͂ƂĂ��L���Ȃ킯�ł��B�����Ď��͂��ꂪ�Ԉ�����d���Œm���Ă��܂��Ă���� �m�M ���Ă����ł��B���̋Ȃقnj�����`���̌��� �w�ɕ���ꂽ�Ȃ𑼂ɒm��܂���B�܂��ŏ��ɁA�����Ƃ������O�A����̓i���Z���X�ł��B�x�[�g�[���F���ɂ���� ����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B���l�Ŕ�]�Ƃ� ���������[�g���B�q�E�����V���^�[�v�ɂ���Ă����Ăꂽ��ł��B�������l�ł݂Ȃ�����V���[�x���g�̔����̉� �̉̎��Œm���Ă���Ǝv���܂��i�e���ĉ� ���j�B���ꂪ�����ł����A���̔ނ�������������ł�...�@�� �c�F�����ɕ����ԃ{�[�g�ɍ����Ă��Ƃ��A����͔����� �[�ׂŖ������������ǂ��A���̌i�F�������� ���� C���}�C�i�[�̃\�i�^�̑��y�͂��v���o�������A�ƁB����ł��̃\�i�^�̃j�b�N�l�[�������[�����C�g�E�\�i �^�ɂȂ����B�x�[�g�[���F���Ƃ͉��̊W���Ȃ� �킯�ł��B�ł����̖��O�͂��̃\�i�^�ɌЂ݂����ɂւ���Ă��܂����B �@���̋Ȃ͔��ɓ��ʂȁA�x���y�͂Ƃ��Ďn�܂�܂��B����͑�ϒx���đ��̒����A�_�[�W���E�\�X�e�k�[�g�� �� ���A�������A�܂����Ă��������͂��̃\�i�^���i�x�[�g�[���F���́j�� �e���������Ă�킯�ł��B���̎菑���̕��ɔނ́A�A���E�u���[���F�Ə������A�ŁA�����œq�ŋ���čs���� �Ƃ����Ă݂����Ǝv���܂��B�N�����X���[�E �A�_�[�W�����ƌ������ɂ��Ă��A�ꏬ�߂ɂQ��������B�����A�c�[�A�����A�c�[�i���t����j... ����ł��\���ɒx���킯�ł����A�ł��ʏ퉉�t�����悤�ȃe���|�ł��Ȃ����e���Ƃ���Ƃ���Ȋ����i�x���e���Ă݂��� �@�̂��̂��j���[���[���A���[���[��... ���̊Ԃɒ��H���H�ׂ��܂���B�����Ă������т��A�ӂ��т��B����ł����킢�����ȃs�A�j�X�g�͂܂����y�͂� �e���Ă�B�ŁA�����ЂƂ��ƌ��킹�Ăق������ �����A�x�[�g�[���F���͂��̊y�͂̎n�܂�ɂ��ăC�^���A��̕��������Ă�i�C�^���A��ňÏ����Ă݂���j�B����� �|��ƁA���̋Ȃ̂� �ׂĂ��σf���J�V�[�������Ēe���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����ă\���f�B�[�m�͂Ȃ��ŁA�Ƃ����̂ł��B�ł������ŗp ��̖�肪�o�Ă���B�Ȃ����Ƃ����ƁA�\���f�B�[�m�̓\�t �g�E�y�_�����Ӗ����Ȃ���ł��B�x�[�g�[���F���̓E�i�E�R���_�Ə������B����Ŕނ̓\�t�g�E�y�_�����Ӑ}���Ă��킯 �ł��B���̃\���f�B�[�m�Ȃ��ŁA�̓_���p�[ �Ȃ��łƂ������ƂɂȂ�B������_���p�[�͏グ���܂܁A�܂肻�ꂪ�Ӗ�����̂́A���̊y�͑S�̂Ńy�_����p�� �ĉ��t���Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����Ƃɂ� ���ł��B�����Ȃ�Ƃ������A���̓��������̑����́u����A���̂��Ƃ͂悭�m���Ă��A�ł�����̃s�A�m�ł� ����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ���v�ƌ����̂ł��B�ŁA���� �ǂ����Ăł��Ȃ��́H�@�����Ă݂��́H�@�ƕ�����ł��B����Ɣނ�͓�����A�u������A�������Ⴂ�Ȃ��B�ł����� �͂ł��Ȃ����ĂB�v����͘_�c���ĂԂ� ����ł���B����Ȃ�\������Ȃ��B�x�[�g�[���F���́A�����v���ɂ͏\���Ɉ̑�Ȉ̑�ȍ�ȉƂŁA�ނ̂��� �͂����Ƃ܂��߂Ɉ���Ȃ����Ⴂ���Ȃ��� �炢�̑�ł��B����������ނ�����ɂ��ĉ������ʂɏ������Ƃ����Ȃ�A�ނɃ`�����X��^���Ă���������B���� �ɂ͗��R���������͂��Ȃ�ł��B�ނ͔��� ���ʂȉ���]��ł���ł��B����̓n�[���j�[���ꏏ�Ɋ���悤�ɓ������ƁA�ЂƂ̔g�i����j�̒��łˁB������ �����ł͔{�������݂��ɋ��������B�Ȃ��� �炱���ł́A�ቹ������i�ቹ��e���j�A�����ĎO�A���̃I�X�e�B�i�[�g�i�������O�A����e���j�A���ꂩ�炻��炪�ꏏ�ɂȂ��āi�e���j... �����ăA�[�e�B�L�����C�g�i�����j�ɂ��Ĕ��ɒ��Ӑ[������Ȃ�A�������s�A�m�ł͎��̓y�_�����܂ł͓��܂Ȃ��킯�ŁA�O���̈�őS���\�� �Ȃ̂ł��B���ꂩ��A���́u�_�v�ŕ`���ꂽ���Y��������i���̎���e���j�B����͂܂��A�����s�i�̃��Y�� �Ȃ�ł��B�G�h�E�B���E�t�B�b�V���[�̃x�[�g�[���F�� �̃\�i�^�Ɋւ���f���炵���{�ŁA�t�B�b�V���[�͈̑�Ȕ����������̂ł����A���������Ă��܂�...�@���͌����\�i�^ �Ɋւ���L�q�ɂ��Ă͂����Ɗ���������܂���ł����B�Ȃ��Ȃ炿���Ƃ��[���ł��Ȃ�����ł��B�ŁA����� ���E�B�[ ���E���W�[�N�t�F���C���}���ق̕ۑ��L�^��������ł��B�i���̓x�[�g�[���F���̎菑���̃X�P�b�`���o���Ă��܂����B���ꖇ�ł������A����̓x�[�g�[���F�� �����[�c�@���g�̃h���E�W�����@���j���珑���� �������̂ł���...�@�ƁA�����ނ͏����Ă���̂ł��B���̃V�[���̓h���E�W�����@���j���R�}���_ �g�[���i�R�m�c�Nj撷�j���E����ʂŁA���̉��y���i�e���j... ����Ȋ����B����� C���}�C�i�[�ɓ]������Ƃ����Ȃ�i�e���F�����̏o�����Ɏ��Ă���j�B����͎��ɂ͔��ɖ����Ȃ��Ƃł����A���̉��y���\���̂́A�m�[�A�m�[�A���̌����� �Ȃ��āA�����̃e�[�}�ł���B����̓��[�c�@���g�̃h���E�W�����@���j�̂��Ƃ��l�����e�[�}�Ȃ�ł��B �@�����Ȃ�܂������A�V�t�̌����̉��t�͂�����ƕς���Ă���̂ŁA�y�_���̈����Ƃ��̋Ȃ̉��t�\���Ɋւ��� ������Ōf�ڂ��܂����B�ł́A���ۂ̉��t�͂ǂ��ł��傤���B �@���y�͂̎n�܂�̓e���|�������A�\��������̂悤�ȍ� ���ȃ��o�[�g���Ȃ��Ă������ɂƂ���قǒW�X�Ƃ��Ă��܂����A�_���p�[�E�y�_���܂܂Ȃ̂ʼn����� ���������đS���s�v�c�Ȍ��ʂ������炵�܂��B���ꂪ�x�[�g�[���F�����Ӑ}�����ʂ肾�Ƃ������ƂȂ�v�V�I�ł��B ���܂ł̉��t�ň�ԈӊO�ł��B�܂�ŗ��l�I�Ȗ��̒��̑����s�i�̂悤�ŁA�V�t�͂����������Ƃ����s����l�Ȃ̂� ���ˁB���X�g���班���O�ɉE�肪�˔@�C�̒����炭������Ɨ��N����悤�ɋ����Ȃ�Ƃ���ȂLj�ۓI�ŁA�h�r���b �V�[�̒��߂鎛�̂悤�ł��B���y�͂̓R���g���X�g������Ƃ��낾�ƌ����Ă��܂��������̒ʂ�ŁA�A�N�Z���g���傫���A�X�^�b�J�[�g�����ǂ��Ă���悤�ł��B��O�y�͂̓_�C�i�~�b�N�ő����ł����A����̉��̘A �Ȃ�����o�����悤�ɋ��������V�t�Ɠ����h�ꂪ�A�������̗ǂ��������肵�����ŕ\������Ă��܂��B �@����łR�O�Ԃ͐Â��ɓ���܂����A�����ꂽ���F���N�₩�ł��B �o�b�n�̂Ƃ����������^�b�`�̕����ł��͂������e���Ă���ł��傤���B�\�����_�ŁA���߂����������v�� ���Ă��܂��B�E���������ꉹ���������肵�A�܂�Ŏw���� ����@���Ă��邩�̂悤�ł����A�p���[������̂� ���傤�B�����ł̓y�_�����g�������̂́A�B���Ȃ���̒��ɒ��܂Ȃ��̂���ɃV�t�̓����̂悤�Ɏv���܂��B�@ �@���y�͂̋��������ł̓P���v��藎���������g�[���ŁA�� ���ł��N���A�ő���܂���B��O�y�͂̓x�[�g�[���F���ōł����������y�Ɏd�オ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�r���X�^�b�J�[�g�C���ɋ���Ĉ�u�Ԃ𑽂� �������A�����~�܂�悤�ɕ���o�߂���A��x�Ɠ������Ƃ����܂���B�����Ƃ͈���ă_���p�[�œK�ɋ������z�����Ă���̂ňꉹ�ꉹ���͂����肵�܂��B �����ď�ɗ�����Ȃ��̂ɏ�ɂ��ӂ�Ă��܂��B��̈�ۓI�Ȍ㔼�̃X�^�b�J�[�g�����͂������ŁA�͂�����J ����̂悤�Ȕ����������܂�܂���B �@�����ƂR�O�ԂŔ�r����ƌ��� ���̂ł����A�V�t�̂R�Q�ԁA�x�[�g�[���F���Ō�̃\�i�^�ɂ��Ă��G��Ȃ��킯�ɂ͍s���܂���B���̋� �͂���Ȃɕω��ɕx��ł����ł��傤���B����ۂސÂ����̒��ł̋����قǑ��l�ȕ\��A����ɂ��̒��� ���B�x�[�g�[���F���͌ÓT�h�Ƃ����g�ł͂� �Ă��Ƃ炦���Ȃ����낵���V�˂� ���B������}���h����˂������Ă���ł��傤�B���y�͂̓s�A�m���y�َ̖��^�ł��B�V�t�̉��t�ł́A�� �̃s�A�j�X�g�ɂ���Ă͂܂�Ȃ�������ꂽ�Ƃ���ɂ��ׂĈӖ��������܂��B���قǁA�R�Q���̂P�Q���q �ɕς������R�ϑt�Ńt�H���e�̎R���}������A�I���l���̈ꂠ����A��T�ϑt�ɓ����Ă���Ō�̃g�� ���ɓ���O�̕����œ�x�ڂ̔g�����܂����A���̑傫�ȑ��ŃN���b�V�F���h���čs���l�ɂ͐g�k�����܂� ���B�Ō�̃t�H���e�̎��X�Ȃ܂ł̘A�łɂ���قǐS�����ꂽ���Ƃ�����܂���B���t�ɂ���Ă͂Ƃ� �ǂ��₩�܂����Ǝv���Ă����炢�ł�����B�����č���̃g�����̏�ʼn�z������߂������Ǝv�����炠�� �Ƃ����ԂɐÂ܂��ďI���A��R�Ƃ��āA���̋Ȃ̉��l�����܂ł悭�킩���Ă��Ȃ������ȁA�Ǝv���܂� ���B �@�P�X�T�R�N�A�n���K���[���܂���V�t�i�o�b�n�̉��t�ɂ��Ă��u�V�t�Ƃ������v�̏͂ň����Ă��܂��j�� �s�A�m�́A�s���X�̒[�����Ƃ͂܂�������Ӗ��Ŋ���ɐ�����Ƃ���̂Ȃ��m�I�ȉ��������Ă��܂��B���̔z�u�� �������Č�����킯�ł����A���ꂪ�L�@�I�ŁA�v�l�I�ɂ͂Ȃ炸�Ɋ��o�I�ł��B�����_�}�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���i�߂Ă���̂ł��傤���A�s�A�m�̊y�Ȃ������ɔ������� �邩�ɍő���̒��ӂ��Ă��邩�̂悤�ł��B����o�����藧���~�܂�����A�N�ɂ��^���̂ł��Ȃ��ԍ����ƃA�N�Z���g�����݂ł��B�������x�[�g�[���F���炵���̂��ǂ����͌����� ���ł��傤���A�V�t�Ɠ��̔��̐��E�ł��B�܂��A�n���K���[�l�͂悭�ߊϓI���ƌ����܂����A�V�t�Ɋւ��Ă͂� ���������[�h�͊�����ꂸ�A�Z���`�����^�����Ƃ͂ނ��딽�ȋC�����܂��B�o�b�n�ł͖��x�̒��ɂ���A�x�[�g�[ ���F���͉��̂Ȃ����̂悤�ȔR�Ăł��B �@�s�A�m�̉��̂��ꂢ���ł��x�X�g�ł��B�y��̓X�^�C���E�F �C���C�^���A�̒����t���ꕔ���������A���W�F���E�t�@�u���[�j���Ƃ������Ƃł��B�����̕��͂Q�O�O�T�N�A�R�O�Ԃ͂Q�O�O�V�N�A�`���[���q�E�g�[ ���n���̃��C�u���^�ŁA���[�x���̓W���Y�� ECM �ł��B�l�I�ɂ̓x�[�g�[���F���̃\�i�^�Ƃ��Ă��ꂪ�x�X�g�̉��t�ł��B   Helene Grimaud �G���[�k�E�O�� ���[ �@�P�X�U�X�N���܂�̃t�����X�l�ŃW���b�N�E�����B�G�Ɏt�������s�A�j�X�g�ł��B �h�C�c���y�ɂ��ϋɓI�ŁA�u���[���X�̊ԑt�Ȃ��f���炵���������Ƃ͂��łɏ����܂��� �i�u���}���X�Ɠ���Ɓ^�u���[���X�̎����y�v�j�B�x�[�g�[���F���̃\�i�^�͂܂Ƃ߂Ă͏o�Ă� ���A���t �ȂƂ̃J�b�v�����O�Ō������R�O�Ԃ������܂��B �@���̋��t�Ȃ̕��ł́A���Ƃ��u�c��v�Ȃǂł͕������ɐ����������� ��A���y�͂̂�����肵���������킴 �Ƒ����ɂ���Ƃ��낪���܂̂��Ⴍ�̃t�����X�l��������Ƃ��������������肵�܂����A ���������ɂ����ė͋������U�@�ŁA�\�i�^�ł͂Ƃ��ɂ����� ���܂��B �@ �����ɂ��ẮA�E���t�E���[�����C�g�ȂǂƂ��āA�T�̉f���Ɩ������I�[�o�[�_�u�������̂� YouTube �ɏo�Ă��܂��B�ĊO����������肵�܂����A�ǂ����Ă����������ƂɂȂ邩�Ƃ����ƁA�G���[�k�͖쐶�̘T�̌����ɔM���グ�Ă��邩��Ȃ� �ł��B�j���[���[�N�B�ɕی�Z���^�[���ݗ����܂����B���t�̕��͂ǂ��炩�Ƃ����Ƃ�����肵�� �e���|�ŕ\�����A���}���e�B�b�N�ł��B�����Ȃ�Ƃ���� �X�P�[���̑傫�������������܂��B���̐l�A���ꂢ�ȏ����ł����A�͋����ł����z�I�ȂƂ� ��ł��j���ۂ�����������Ƃ�������܂��B���D�ɂȂ�l�ɒj ���z��������������悤�Ȃ��̂ł��傤���B �@�R�O�Ԃ��Â��ȂƂ���͐[��������������������ŁA�_�C�i�~�b�N�ȕ����͎��ꂪ�ǂ��� ���B��O�y�͂͂������ŕ\����L���ł���A�������߂�Ƃ� ��Ɨ͂��Ƃ��낪��_�ł����A�ĊO�ߓx�̏�����Ԃ��Ă���悤�ɂ͕������Ȃ��̂��s�v�c �ȂƂ���ł��B���Z���`�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂͂�͂菗��������ł��傤���B������ɂ���A�W�F�� �_�[���ʂȂnj|�p�ɂ����Ă͉��̈Ӗ����Ȃ����Ƃ������Ă���܂��B�X�^�b�J�[�g�̕����� �������ڂȂ��痬���悤�ŁA�Ȃ��Ȃ����͓I�ł��B �@�_�C�i�~�b�N�ʼn�������A�����Ș^�����G��ł��B���t�Ȃ̂S�ԂƃJ�b�v�����O���ꂽ�R�O�Ԃ� �R�P�Ԃ̕����P�X�X�X�N�A���������������ǂ����Ǝv���܂����A���{�Ղ̂������J�b�v�����O�� �ꂽ�u�c��v�̕����Q�O�O�U�N�`�O�V�N���^�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������������������������������������������������������� �@�x�[�g�[���F���̃s�A�m �\�i�^���t�ɂ��đ�Ϗ���Ȃ��� �������Ă��܂������A���ɗ��j�I�����ɐ�������Ƃ���ł́A�g�c�G�a�� ���J�߂��P�X�O�Q�N���܂�̃C�M���X�̃s�A�j�X�g�A�J�b�g�i�[�E�\�������������Ă݂܂����B�R�O�ԂȂǑ�O�y�͂̎㉹���ƂĂ����ꂢ�ŁA���� �������ƁA�����Ђ��߂�Ƃ���̔��������ۂ����Ă��܂����B�������x���Ƃ���͒W�X�ƒx���ł����A�����Ƃ���͗͂܂� �Ɍy������悤�ɗ����Ă���A�S�̂ɂ₳�����Â��Ȉ�ۂ̃s�A�j�X�g�ł��B �G�h�E�B���E�t�B�b�V���[�� �P�W�W�U�N���܂�̃X�C�X�̃s�A�j�X�g�ŁA�R���g�[��M�[�[�L���O��Ɠ������Ɋ��A�w���҂̃t���g ���F���O���[�Ƃ��e�����������悤�ł��B�V�t���u�`�Ō��y���Ă��܂������A�o�b�n��x�[�g�[���F���̉� �y�ɑ�ϑ��w���[�������ƌ����܂��B�����Ȃǂł͎��݂Ƀe���|�𑬂߂���x�߂���L�яk�݂��A�� �M���߂�����ɂ��Ȃ�Ȃ��l�q�����̘^�����畷�����Ƃ��ł��܂��B�R�O�Ԃ̌㔼�ł��[���}�g�̂���� ���������A�������߂ĐÂ��Ɍ�镔���ł̖��킢�ɂ͉������������܂��B�������S���Ȃ����̂� �P�X�U�O �N�Ȃ���^���͐V�����Ă��T�O�N��O�����炢�܂ł����Ȃ��A���̉����ł��ׂĂ����Ƃ����̂�������� ���т����Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�ނ������x�[�g�[���F���̍ō��̉��t���ƌ����l������悤�ł����B �@���߂ăx�[�g�[���F���̃\�i�^�S�W�������������A���g�D�[���E�V���i�[�x���͂P�W�W�R�N�I�[�X�g���[���܂�̃��_���n�s�A�j�X�g�ŁA��̐���ɑ�ϑ傫�ȉe����^�����l�ł��B���̐l�� ���^������ ���̂ŋ����^�b�`�̊p�̕������悭�������Ȃ����Ƃ�����A���m�ȕ]���͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�� ���܂��B�����͂�����Ƃ��đ�ϐÂ��ɕ������A�R�O�Ԃ̑�O�y�͂Ȃǒx���Ȃ�Ƃ���ł͎~�܂肻�� �Ȃقǂœ����͊�������̂ł����B�e�N�j�b�N�ɓ����ƌ����l�����܂����A�m���Ƀ~�X�^�b�`�͂��� �� �� �̓����̘^�����������ł��傤�B������ɂ��Ă����̉��t�͎��オ�������Â��l���Ƃ��ĕЕt���邱�Ƃ̂ł��Ȃ������͂�����Ǝv���܂��B �@���N�̃��m�[�����^���́A�������莨���X����ƐF�X�Ȃ��Ƃ������Ă���܂����A���̖��͂�͂肠��킯�ŁA�D��ŕ������ł͂Ȃ��̂ł��ꂮ�炢�ɂ��Ă����܂��B INDEX |