|
割り切れない和音の魅力
/ ルイ・クープランの宇宙 
ルイ・クープランの作品の美しさは、知る人ぞ知るといったところかもしれません。1626年生まれのフランスの音楽家です。甥にあたる1668年生まれのフランソワ・クープランばかりが有名なのは、ルイがモーツァルトと同じく三十五歳という若さで病死してしまって作品が少ないからだとも、フランソワが自分の作品を楽譜にして出版したからだとも言われます。しかし近年、このルイの地位が見直されつつあるようです。本当に才能があったのはむしろ伯父のルイの方ではないか、と。実力などというもの、物差しで計るわけには行きませんが、 ルイ・クープランのクラヴサン音楽を聞いて心奪われる人はたくさんいるようです。個人的にも初めて聞いたときにその不思議な響きに魅せられてしまいました。クラヴサン曲はバッハやフランソワのものなど聞いてはいたけれども、それらとはまたちょっと違った種類なのです。興味を引かれて他にどんな作品があるのか探したところ、室内楽とオルガン曲があるものの実際多くはなく、イギリスの個人蒐集家が抱え込んだまま楽譜の写本を出版しないという残念な事情もあるようです。 シャンボニエールへの義理立て
ルイが世に出るきっかけとなったのは、当時の作曲家でクラヴサン奏者だった(ジャック・シャンピニオン・ド・)シャンボニエールに認められたことだとされます。シャンボニエールが別荘で宴会を行っていたところへ若きクープランが弟たちを連れてやってきて、自分の作った曲を兄弟皆で演奏したところ、当時宮廷にも出入りしていたシャンボニエールはその才能に驚いて、ぜひパリへ来るようにと推薦してくれました。その後ルイはパリで才能を開花させ、サン・ジェルヴェ教会のオルガニストの地位を得るまでに至ります。その地位は以後クープラン一族が占めることになるわけです。しかし恩人であったシャンボニエールは後年、宮廷音楽家の地位を失ってしまいます。当時は太陽王ルイ14世の時代で、イタリアから出てきたリュリが王の友人とさえ言われるほどに出世していました。リュリは地位を得るために様々な策を弄し、強引なやり方で敵を作ったとされます。指揮棒で間違って自分の足を突いて化膿させ(今の指揮棒とは違って重く、床をドンドンと打ち鳴らしてリズムを取っていました)、それがもとで死んだ作曲家ですが、どうやらシャンボニエールはそのリュリの下で伴奏することを断ったために王の不興を買い、追い出されてしまったようです。そのときまでに才能を認められていたルイ・クープランは後に宮廷クラヴサン奏者としてシャンボニエールのその地位を引き継ぐように求められますが、自分の才能を買って世に出してくれた恩人の職に就くわけにも行かず、義理堅く辞退したといいます。しかし彼の能力は傑出していたために、特別にトレブル・ヴィオール奏者という地位が創出され、結局彼は宮廷で仕えることとなりました。トレブル・ヴィオールというのは高音域のヴィオラ・ダ・ガンバで、チェロのように立てて弓で弾く弦楽器ですが、小型でヴァイオリンぐらいの大きさだったようです。膝の上に乗せて弾きました。 連続する不思議なコード
さて、彼のクラヴサン曲ですが、その魅力を表現するのは難しいです。順を追って考えてみますが、まず和音の組み合わせが複雑です。一つ前の記事で、フランソワ・クープランの「パッサカリア」の最後の方の和音がジャズのテンション・コードのように複雑だと述べました。煩雑なのでここではあのときのように実際の音の構成を楽譜から追ったりはしませんが、それと同じことが曲全体に渡って言えるように思います。 クラヴサンという楽器はプレクトラムという爪で弦を弾いて音を出します。その子孫のピアノがフェルトのハンマーで叩いて音を出すのとは大分異なります。そして当時のフランスではリュートが愛されており、それがギター同様に弦を掻き鳴らす楽器であるために、クラヴサンの方も「鍵盤付きのリュート」と考えられていました。したがって演奏の際もリュートを模倣した分散和音で弾かれます。つまり、順番に指で弦を弾くようにバラバラバラーン、と時間差で和音を鳴らすのです。ルイ・クープランの曲ではそれが連続するので大変よく分かります。両手で一つのコードを鳴らすと、二オクターブにまたがって分厚い低音の上に和音が展開するようなことになるため、響きが強烈です。 ジャズの音に似ていると言いましたが、ドミソのような基本の三和音(トライアッド)に対して、ジャズでは最高音の上にもう一個加えた四和音(セブンス・コード)以上の複雑なものを使います。ナインス(五和音)、イレブンス(六和音)など、音数も多くなることがあるし、同じセブンスでもただのセブンス、メジャー・セブンス、マイナー・セブンス、マイナー・メジャー・セブンスなどのようにどれかの構成音が半音ずれた組み合わせによって種類も色々あります。例えばメジャー・セブンス(CM7)ならドミソシ、ですが、このドとシは半音隣り合った音で、すぐ隣を弾けば濁った不協和音となって汚く響きます。でもドから見てオクターブ近く上のシなら濁るといっても干渉し合う率が減って複雑ながら案外きれいに聞こえます。古典派の時代には使われなかった和音だけど、その音は明るいんだけど儚げなところがあり、憧れるような寂しいような、ちょっと諦観の混じった感じにも聞こえます。クープランでも特に後でご紹介するアラン・カーティスの演奏するヘ長調(F Major/en fa majeur)の組曲などでは一部そんな風に聞こえるところがあります。そしてこういう複雑な音を多用することでジャズはあの独特の洒脱な感じを出しているのです。シはドミソから見て波長が同調しない音なのでテンションと呼ばれ、クラシックの理論ではそういう音が混じった和音を使ったら次の音はきれいな協和音に戻さなくてはいけない(解決)という理屈がありますが、ジャズでは数が増えて複雑になったテンション・コードでももう少し自由に使います。そしてルイ・クープランの曲には数の多い和音がただ展開して行くだけのように聞こえる瞬間があり、前の音の名残りが記憶に重なりもし、より複雑な音が次々と繰り出されるように聞こえます。それで何だか現代的なもののようにも感じるわけなのです。 さらに、また教科書のような話ながら、バロック以前の合唱曲では二つのメロディーがどちらが主でもなく重なり合うポリフォニー音楽でした。モーツァルト以降の楽曲はホモフォニーで、メロディーが主になって伴奏が付きます。ルイ・クープランの音楽はそのどちらでもないような複雑な動きに聞こえるときがあります。伴奏の分散和音なのか、相互にもつれ込んだ旋律部分なのか分からなります。そんなところも実験的なジャズの曲と重なるるような感覚でちょっと前衛的に聞こえます。まるで色とりどりの花火が次々と打ち上げられて行くようです。共感覚を持っている人なら様々な色が見えることでしょう。 予想できない着地
転調の問題もあります。転調の自然さはモーツァルトの十八番だけど、ルイ・クープランの曲は短い周期でくるくると転調を繰り返しているように聞こえ、もはや基本が何調なのか思いつかなくなってしまいます。また、メロディ・ラインがありながら予想したところで終わらない節回しの長さはテレマンの特許だとして、テレマンの場合ではそれが時として付け足されたみたいに感じる一方、ルイ・クープランはメロディがどこで終わるか初めから予測がつかず、そのままどこまでも引っ張って行かれます。そして迷い続けながら森の散歩を楽しむことになるのです。  調弦による割り切れない音
ルイ・クープランの不思議な音についてはもうひとつ、調弦の問題もあります。これについてはバロック時代は今のように平均律で調律してはいなかったわけで、調弦に関してこの作曲家だけが特別どうということはなく、必ずしもその特徴としては挙げらないのですが、フランソワ・クープランやバッハの録音ではほとんどそういうことがないのに、彼らより数十年先輩にあたるルイの作品を聞くと、より音程が外れたように聞こえる瞬間があります。録音にもよるけれど、これは当時の調弦の仕方がより純正律に近い古典調律法によっていたからでしょう。具体的に音律の名前を言えるといいのですが、ブックレットに書かれていないので具体的にはよく分かりません。 話が飛んだので最初から言いますと、現代のピアノは平均律(イコール・テンパード)で調律します。バッハの曲に「平均律クラヴィア曲集」 というのがありますが、あれはウェル・テンパード、つまり程よく調律されたという意味の言葉を「平均律」と訳しているので当てはまりません。実際は何律だったのかは色々と研究があるようながら、総称して古典調律と言われ、種類は色々あります。平均律は1オクターブの音を十二に割って一音ずつ割り当てるやり方で、ドとレ、レとミの間がみな均等です。しかしもともとハーモニーは二つの音の振動数が整数倍のときによく響くのであって、一音ごとの間隔が等しい平均律ではそうなりません。そのため、昔は耳で聞いて響きの良い調弦が追求されていたわけです。ピアノでも平均率が徹底されたのはベートーヴェンより後、ロマン派の時代になってからです。しかし古典調律だと調律に調性が出てしまいます。ハ長調で調弦した楽器で別の調の和音を弾くと音が狂って微妙に不協和音になります。実際の音楽はたとえハ長調の曲でも転調しますから、曲の途中で音が狂うわけです。それをどの程度平均に防ぐかによって、古典調律にはいくつものバリエンーションが存在します。もちろん波長の倍数の観点で一番共鳴し合う純正律(純正調とも言う)もそこに含まれます。転調したときの狂い具合も色々というわけです。
さて、その古典調律ですが、古くはピタゴラス音律と呼ばれるものがありました。和音のないメロディだけの音楽だと最もきれいに聞こえる調律法だそうです。先日FMで合唱音楽を聞いていたら、それが合唱団によってピタゴラス音律で歌われているのだという解説をやっていました。あるいは、合唱は純正律で歌うんだという話も最近はよく聞きます。本当に歌えるのでしょうか。和音がきれいにハモるようにお互いに音を少し時間をかけて部分的に調整し合う、ぐらいじゃないんでしょうか。出来るならすごいことだと思います。絶対音感で数セントという狂いが分かる人もいるのかもしれません。自分なら無伴奏で一曲歌った最初のドと最後のドが同じピッチですらないでしょう。ヴァイオリンなどのフレットのない弦楽器を習った人は分かると思いますが、指で押さえる位置が少しずれただけで、糸巻がわずかに緩んだだけでピッチはずれます。それを注意されると大抵の生徒は困惑するのです。 脱線しましたが、そのピタゴラスは弦の共鳴(管の共鳴はまたちょっと違います)で実験した上で、12音を決めるにあたっては耳で共鳴が分かりやすい5度を重ねて行って出しました。ド→ソ→レ→ラ→ミ→シ、のようにです。ラヴェルの「ダフニスとクロエ」の出だしのようだけど、それがピタゴラス音律です。しかし調性感を決定づける上で重要な3度(ド→ミ)の音が濁るという理由からルネサンス期には純正律、そしてアーロンの中全音律 (ミーントーン)というものに変わりました(ルネサンス以降に調性というものがはっきりして来たことにも関係あるのでしょう)。詳しく言うのは難しいですが、中全の「全」とは全音(2度)のことで、純正律では間隔の広い・狭いの二種類の全音が出来てしまったのに対して、中間(ミーン)をとって一つにしたということのようです。またバロック期にはその中全音律ですら狼の遠吠えのような唸り(ウルフ・トーン)を立てることから、改良型中全音律というものに変わったりして、古典調律も色々と変遷して来ました。ルイ・クープランの頃は色々な調律法が試されていた時期のようです。そして彼の作品は転調も転調だし、たとえばハ長調の曲であってもそこから離れた調性の和音を途中で次々と花咲かせます。したがって当時の調律法で合わせた楽器で演奏されるとしょっちゅう音程の外れた音が聞こえるのです。それがまた狼が来たというのか、なんとも異国的に響きます。 切れ目なしに変化し続ける線香花火のようなルイ・クープランの音楽。調性が残ったままで道に迷う心地良さを味わえます。無調音楽やフリー・ジャズは感性に基づかないせいで心地良さを突き抜けてしまうところがあるけど、そんな音を経験した現代の我々の耳にすら、フランス・バロックの作曲家がこれほどぎりぎりのスリルを味わわせてくれることに驚きを禁じ得ません。 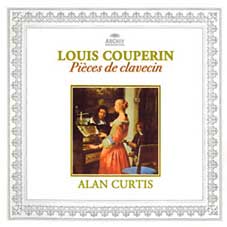 Louis Couperin Pieces de clavecin Alan Curtis (hc) ♥♥
ルイ・クープラン / クラヴサン曲集 アラン・カーティス(クラヴサン) ♥♥
CDの演奏ですが、LP時代にはアルヒーフからアラン・カーティスの一枚ものが出ていました。CDになって 再販されたのかどうか、今この時点では検索してもヒットしません。サブスクライブのサイトにはありました。カーティスはグスタフ・レオンハルトに学んだアメリカのハープシコード奏者で、バロック・オペラの指揮者でもあります。人気のあるクリストフ・ルセのように崩しの大きな表現ではないものの、大胆な音の選択があって味わい深い演奏です。 先日ジャズを弾く知人と雑談していたとき、メジャー・セブンは教育を受けた者しか発想しない音なので黒人ジャズやブルースでは出ないんじゃないか、という話を聞きました。面白い話だけど、このCDでのコード選択も案外カーティスのセンスによるところがあるのかもしれません。すべての音が楽譜に書き込まれているわけではないようだからです。 またこの盤にはもうひとつ特徴があります。それは前述の調律です。基準の調性を外れたときの不協和音が他の演奏家よりもいっそう目立つので、平均律から見てより遠い調弦法を採用しているのではないかと想像します。何の調律法でしょう、ミーントーンなのか改良型ウルフ・インターバルなのか、全然分かりません。しかしこの狂った音は慣れると癖になります。  Louis Couperin Harpsichord Suites Laurence Cummings ♥♥
ルイ・クープラン / クラヴサン曲集 ローレンス・カミングス(クラヴサン)♥♥
ローレンス・カミングスの演奏するナクソスの盤も素晴らしいものです。こちらは現行のCDで、しかもナクソスは廉価版です。またカーティスとは一曲だけ選曲が違います(ト短調の代わりにハ長調)。一枚もので買いやすくもあります。この人はイギリス人で、かの国にありがちな羽目を外さない良識を持ちながらも、案外大胆なところもあります。カーティスとは即興部分も大分違うけど、ハ長調のパッサカリアなど、太い低音を響かせながら分厚い分散和音の上にトリルが散らばる音はちょっとしたショックです。全体に遅めのテンポで混濁させないようにゆったり音を響かせ、表情が豊かです。 録音がまた優れています。チェンバロは音量が小さいためか、マイクを楽器に近いところに置いて収録することがよくあり、やけに迫力があったりガシャガシャ と機械ノイズが乗ったりします。生の音はやさしくピーンと響いて心地良いのですが、そういうCDは案外見つけるのが難しいものです。しかしこのカミングス盤は大変自然な音に録音されています。  Louis Couperin Pieces de clavecin Blandine Verlet (hc) ♥
ルイ・クープラン / クラヴサン曲集 ブランディーヌ・ヴェルレ(クラヴサン) ♥
全集ではフランスの女性クラヴサン奏者、ブランディーヌ・ヴェルレの盤がゆったりとよく響かせながら粋なルバートの表情もあってお勧めです。録音がまたローレンス・カミングスの盤と並んで大変優れています。 他にはハルモニア・ムンディから英国人のリチャード・エガーのものが出ており、速めのテンポで崩しの少ない演奏をしています。 スキップ・センペは アメリカ人の鍵盤奏者で、ちょっと走るところが印象的ですが、残響がかなり長いものです。  Louis Couperin L'OEuvre d' orgue Jan Willem Jansen (org / fnac music WM 334 592291) ♥
ルイ・クープラン / オルガン曲集 ジャン・ウィレム・ジャンセン(オルガン)♥
クラヴサンではありません。でもこのジャン・ウィレム・ジャンセンのオルガン演奏も貴重で、独特の世界を見せてくれます。クラヴサンのようにリュートを模した弾き方をしないため、分散和音が連続する不思議さはないけれども、荘重でどこか超越した感じのする、やはりルイ・クープランらしい幻想的な響きがあります。どこへ着地するか分からずに続いて行く流れにオルガンという楽器の神秘性が加わって、人間くさい喜怒哀楽から少し外れた、まるで別の星系から来たメッセージのようでもあります。  La Harpe Royale Andrew Lawrence-King (Baroque-hp) ♥
王のハープ〜ルイ14世宮廷の音楽 アンドルー・ローレンス・キング (バロック・ハープ)♥
これもクラヴサンの演奏ではなく、ハープによるものです。曲はルイ・クープランだけではないけど、他の作曲家を挟みながらも全体にルイの曲を散りばめているあたり、この作曲家のトーンに惹かれるものがあるのでしょ う。「王のハープ」というアルバム・タイトルで、ルイ14世宮廷の音楽ポートレート、ダンス&ラメント、となっています。キングの演奏はそよ風が吹くよう にやさしく繊細で、ハープという楽器の性質もありますが、常時部屋に流しておきたいような安らぎに満ちています。ルイ・クープランの曲も非常にゆっくりと軽いタッチで弾いており、鮮烈さとはまた別の味わいがあります。 INDEX |