シューマン / 交響曲第4番 取り上げる CD 23枚:マリナー/オラモ/ティルソン・トーマス/ヘレヴェッヘ/ガーディナー/ラトル/アーノンクール/ヘンゲルブロック /チェリビダッケ/ヴィト/ハイティンク/スウィトナー/サバリッシュ/クーベリック/フォンク/セル/パレー/フルトヴェングラー/ヴァント /ジンマン/カラヤン('57/'71/'87) 「シューマンはお好き?」というタイトルは、恋愛小説としてはどんなもんでしょう。ご当人に登場願ってクララとブラームスとのトライアングルなら割り切れ ない大人のあきらめと惰性も描けそうな気がしますが、シューマンこそが好きだというファンの人は果たしてどのぐらいの割合でしょうか。これは音楽を学ぶ人 の間ではよく話題にされ、かなり論議を巻き起こすことがあるようです。詩人の恋の「美しい五月に」があまりにもきれいで、ホルツマイヤーの歌がまた格別 だったのでここではすでに記事にしましたが、私はそれ以外となるとせいぜい4番のシンフォニーを楽しむぐらいでしょうか。いくらブラームスよりストレート だと言われても残りの三曲は、元気一杯の演奏ならもちろんのこと、何度トライしてもはかばかしくありません。人間の性質だからいいも悪いもないのですが、 躁状態の人に付き合わされてるようで手に負えない感じなのです。病のことを挙げる人もあります。それはともかく、気に入ったフレーズを繰り返し、断片的モ チーフがどこで終わるか見通せない。多分反復と壮大さに対する自分の耐性が低いのでしょう。ボレロやクープランのパッサカリアのようにクライマックスへの心理的効果を出すものは圧巻です。ビートが主体の音楽もまた別の話で すが、反復が躁でなくうつの作曲家も含めて、いずれにせ よ繰り返しへの愛着は強迫的な気がします。形 は違うながらメンデルスゾーンにもシューベルトのグレートにもちょっと近いものを感じる瞬間があります。もし音楽が理解するものならば、これはオーケスト ラ曲愛好者検定の三級ぐらいに毎年落ち続けている状況でしょう。努力してでも好きになるまで頑張るというのもまた強迫的なので、この先も見込みはなさそう です。したがってこんな作曲家への物言いも「評価」ではありません。すべての存在には等しく価値があり、あるがままです。 さて、そんな自分にも4番は大変魅力的に聞こえます。四つあるうちの唯 一の短調の曲で、4番となっているものの作曲は比較的早くて二番目、1841年で す。妻クララの誕生日祝いとして贈られ、十年後には改訂されています。この作曲家のオーケストレーションの巧拙を論じる力はないですが、執拗さはないし、 VU メーターが右に振れっ放しになるほどリミッターは効きません。情念という言葉はともかく、こみ上げてくるほの暗い力と美しいメロディーとのバランスが素晴 らしいと思います。そこで以下に CD の演奏を少しだけ比較してみます。シューマンの交響曲が好きな人は自分とは違う演奏を好まれることがありそうですから、あるいはここで褒めないものがベス トかもしれません。この作曲家は取り上げるのが難しいです。 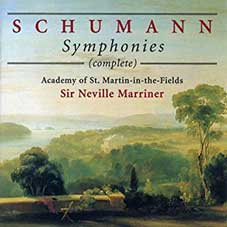 Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Neville Marriner Academy of St. Martin-in-the-Fields ♥♥ ネヴィル・マリナー / アカデミー室内管弦楽団 ♥♥ 実は最初にこれ一つで記事をやめておこうかと思ったのがマリナー盤です。決定盤という言葉は使いたくないですが、自分の中ではそんな感じです。シューマ ンの第4交響曲を初めて聞いたのは、昔のことではっきりしないものの、オーストリア放送協会かどこか提供のテープを放送で流したライヴ演奏で、晩年とは 言えない頃のチェリビダッケだった気もします。遅いテンポではなく、ドイツ・ロマン派流の重厚さとは違う演奏でした。しかし素 直に素晴らしい曲だと思ってそれ以来、同じように満足できる演奏はこのマリナー盤まで長らく出会えませんでした。マリナーについては一つ前のグリーグをは じめたくさん取り上げてきましたが、この人の盤でなければ、という曲はそんなに多くはありません。洗練されていて、少しだけ速めのテンポで常に颯爽として 滑らかに歌う敏感さが身上で、毒のない人だと思われていることでしょう。ここでもそう言えますが、この曲は見事です。大仰さに一切傾かないことで、 シューマンの真摯な心の歌が伝わってきます。よく垢が洗い流された、などと言いますが、そんな初々しい感じの演奏です。例えば本来は区切ってアクセントを 施したくなるようなフレーズでも連続的につなぎ、感情の一続きの自然な動きを妨げません。何気ないようでよく考えられていると思います。スムーズですが、 それがかえって情熱的だとも言えるでしょう。 スコアは通常使われる改訂版(1851年版)です。オーケストレーションの問題でこれを使わず、初稿(1841年版)の方が良いと考えるアーノンクール やラトルらの考えも分かります。指揮者も特徴を出さなくてはいけないし、ひとつには、音の重なりから来る不透明さを嫌うということもあるのでしょう。自分 なりに手を加えて演奏する人もいるぐらいですが、私は通常版を使って響かせ方に注意を払い、力を入れ過ぎずにすっきりとやったものの方が流れがあって好き です。これは好みの問題です。 演奏の特徴はもうすでに書いてしまいましたが、テヌートで切れ目なく行くところに良さが出たりすることがある第一楽章は、滑らかでありながら上滑りにな らない味わい深いものです。肩に力を入れ、眉をひそめたパフォーマンスでないと感情の大きさが感じられないなら他の演奏にしか目が向かないかもしれませ ん。緩徐楽章も軽快な運びで快活さが出ます。第三楽章も穏やかで落ち着きがあり、最後まで気負わない演奏です。 マリナーはこの前の1985、86年の録音でシュトゥットガルト放響とも全集を出していました。ディジタル期になって一度自分の楽団を出て、そしてまた 古巣のアカデミー室内と組んだのがここで取り上げる盤なのです。解釈としてはどちらも同じ人の表現だと言え、シュトゥットガルトも良いと思います。そちら の第一楽章の始まりの部分はソフトフォーカス・レンズで捉えた風景のようなやわらかな出だしです。オーケストラは室内管弦楽団ではないので人数がより多い でしょうか、響きが重厚です。落ち着いた真面目な演奏という印象で、軽快に進めるのはアカデミー室内との方です。第二楽章もこのアカデミー室内との方がよ り速めのテンポ設定に聞こえ、その方が快活さが出ていると思います。 録音がまた見事なのがこの盤の良いところです。1998年ヘンリー・ウッド・ホール収録で、ヘンスラー版権でディスカウントのブリリアントから出ていま す。艶やかにして固まらず、自然で生っぽい素晴らしい音です。ホール・トーンも良いバランスです。これに比べるとシュトゥットガルト放響との盤は残響がや や少なめで、高域がもう少し前に出るでしょうか。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Sakari Oramo Royal Stockholm Philharmonic Orchestra ♥♥ サカリ・オラモ / ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ マリナーで満足していたところ、それに勝るとも劣らない魅力的なものが出てきました。1965年生まれのフィンランドの指揮者、サカリ・オラモです。サ イモン・ラトルが育てたバーミンガム市交響楽団で、その後を任された人です。その後2008年からはアンドリス・ネルソンスがその地位に着きましたから、 この楽団はまるで才能ある指揮者が登場するときの登竜門になってるようです。ネルソンスがストレートで真摯、団員本位で熱くなると大変感動的な演奏となる 直球型の指揮者であり、変わったことをしないので楽団が乗らないと平坦に聞こえる場合もあるのに対して、オラモの方は才気豊かな工夫の人という感じです。 といってもショウマンで作為的な演奏とは違います。ラトルも若いときにそうでしたが、巧者でありながらより巧者に聞こえないと言えるでしょうか。爽やか に、知的でありながら音楽の中の心の動きを出して行く自然さ、信頼して任せて行ける気持ちの良さがあります。大変理解力のある人のようです。グリーグのピ アノ協奏曲の伴奏でもいい味を出していました。 マリナーとは違い、スタッカートで短く切る音も使い、やわらかさと交互にメリハリを付けて行きます。といっても誇大な方向性ではありません。 気持ちのよいアクセントとしてです。そしてそれによって動きを作り出し、シューマンらしさを損なうことなく心地良く乗れる状態へと持ち込みます。スムーズ にさらっと歌わせるマリナーに対して、起伏を付けることで濃密な霧のような視界の悪さを払拭して行くのです。思い切って速くするところもあり、テンポ感の ある軽快さが味わえます。緩徐楽章ではよく歌わせ、やはり意欲的な工夫によって表情が豊かであり、ところどころで切って弾ませたりします。ベタっとしがち なシューマンに対しての良い表現で感服しました。途中からのヴァイオリン・ソロもくっきりと浮き出して美しい音で、まるで室内楽のようで印象的です。その 後も生き生きと弾む運びで暗くなりませんが、それがこの曲でのシューマンだと思います。 2009年録音のソニー・クラシカルで、これまた録音が大変きれいです。古楽の室内オーケストラのような機動性があるとも言える演奏を、透明度の高い音 が支えます。くっきりとしていながら瑞々しいのです。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony ♥♥ マイケル・ティルソン・トーマス / サンフランシスコ交響楽団 ♥♥ ヨーロッパの南の方にも大陸西岸の陽の光溢れた風景がありますが、アメリカの西海岸も晴れた日差しのからっとした気候で、サンフランなどは映画でも しょっちゅう出て来るだけあってやっぱりきれいです。ツインピークスの山の上からの眺めなんか、霧でなければきらきらしてていいです。LA 生まれのユダヤ系の指揮者、ティルソン・トーマスの演奏は透明な音の見晴らしが素晴らしく、そんな土地の空気を感じさせるものと言っていいでしょう。肩の 力が抜けていて、シューマンのもやの晴らし方としてこういうのもありです。鮮やかなフレームの眼鏡や身だしなみの整った写真があり、この指揮者はゲイなの だそうですが、そういうところも光溢れる先進国、サンフランシスコという感じです。 ゆったりよく歌わせています。潤いのある芳醇な音で、録音としてもこの曲のベストの一つだと思います。出だしはかなりゆっくりですが、ドイツ的な鬱屈は 感じさせず、過剰なロマンティシズムに陥りません。この指揮者ももう若くはないので、以前の意欲的な乗りのガーシュウィンのようなフレッシュなリズム志向 ではなくじっくりと聞かせる方向に変わってきているのかもしれません。形が崩れることは一切なく、余分な思い入れがなく、ヴァントのような神話性は感じさ せない分、曲の構成がよく分かります。形がくっきりとしていて完成度が高いと思います。ただ、テンポの伸び縮みのある演奏ではないので、終楽章の後半など で人によっては平坦に感じるかもしれません。緩徐楽章でもゆったりと分解的に進め、やさしいけれども変わったことはしません。アイディアとパッケージで勝 負しようとしないで中身の歌で来る種類で、ひょっとしたらストレートの男性には気づかれ難いのかもしれませんが、わめくことなく、とにかく繊細できれいな 演奏です。それとも、アメリカは伝統がないからだめでしょうか? 自主レーベル SFS メディアで、2016年録音です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées ♥ フィリップ・ヘレヴェッへ / シャッンゼリゼ管弦楽団 ♥ ピリオド楽器を使ってもピリオド奏法的な癖を見せないでよく歌わせるという一つの流れを生 み出した指揮者です。ぱっと聞いただけでは古楽器楽団の演奏とは思わせません。その意味で未だユニークであり、個人的に好みの方向です。語る言葉を聞いて も大変頭のいい人だなと思います。アーノンクール同様人のやらない分野を開拓しようという意欲があるようですが、ここでは古楽派の間で最近流行の1841 年版を用いず、スコアは通常の改訂版です。この人の美学に適うのでしょう。元々は古楽の合唱曲、宗教曲が専 門だとみなされていたものの、後年モーツァルトや第九、そしてロマン派の作品にまでレパートリーを広げてきました。 滑らかな曲線でつなげて歌わせる演奏ですが、少し遅い出だしは重厚です。やわらかさのある響きが気持ちが良いです。この人らしく完璧に計算された音の彫 琢で、忘我熱演という方向には決してならないタイプの指揮者だと思いますが、情感のこもった力強い展開もあります。したがってテンポは揺らさなくても熱い 演奏と感じる人もいるでしょう。第一楽章はそのややゆったりめなテンポを維持し、くっきりと一音ずつ鳴らすブラスをはじめ楽節を丁寧に音にして行きます。 第二楽章も遅過ぎはしませんが、ピリオド楽器の楽団によくあるさらっと速いテンポはとりません。この人の特徴です。やわらかな抑揚を乗せて気持ち良く、 弱くし過ぎもせず溺れもせずに歌います。第三楽章も力強いパートはきれいさを保ちつつ十分力強く、静かなパートは緩徐楽章同様のやわらかさを発揮し、響き が美しいです。そして健全な迫力で大きく盛り上がった後、終楽章は中庸のテンポで適宜速度の緩めを加えたりしながらエッジを尖らせることなく進めます。重 さもあり、迫力もあってよくコントロールされており、最後の最後で走る演奏もある中で安定した運びで締め括ります。 ハルモニア・ムンディ・フランス1996年の録音です。古楽器ですが線が細くなり過ぎず、どっしりとして滑らかさもあります。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 John Eliot Gardiner Orchestre Révolutionnaire et Romantique ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク ガーディナーもピリオド楽器による数少ないシューマンの一つということになると思います。ノリントン旧盤もそうですが、ガーディナーの場合はヘレヴェッ ヘ同様、楽器が当時のもの、演奏の抑揚はあまりピリオド奏法然としない素直なものという組み合わせを期待できそうなケースです。ちょうどモダン・オーケス トラをピリオド奏法でやるのが一つの流行になっているのと反対に、ということです。しかしノリントン共々ユーモラスだったり過激だったりではないものの、 シューマンにおいてはガーディナーもほどほどピリオド奏法らしいシャープなアクセントのようです。初稿版と改訂版の両方を録音していますが、すっきりした 改訂版を期待してまずそちらを取り上げます。 一音ごとに音符を盛り上げる古楽奏法のアクセントがあり、スラーで音を延ばさない覚醒した印象で、弦は独特のきれいな音です。繊細なモーツァルトよりは 力がありますが、同時に丁寧に音にしている印象もあります。テンポ自体も出だしではマリナーとも大して変わらないものの、第一楽章は冒頭から加速するとこ ろも聞かれます。その後は速めの展開になり、弾むようなティンパニのリズムで切れよく進めます。編成の小さい見通しの良い音です。終わりに向けても軽快に 走ります。 第二楽章は古典派で聞かれるピリオド奏法の慣例のように速く流すものではありません。これはノリントンも同じです。中庸のテンポで主題を歌うところと、 さらっとしていて清々しいところとがあります。 第三楽章は快活でやや速めながら、ほぼオーソドックスなテンポです。深刻さに縁のない軽快な運びで、中間部も舞うような動きで軽さがあります。最後では ぐっと緩めます。 第四楽章も弾むリズムでやや速めに進めて行き、後半は走ります。全体にピリオド奏法の表情はあるものの、それなのにというか、そのせいでというか、あっ さりした演奏であり、拍ははっきりしながら端正に感じます。バッハのカンタータのときのような深い情感が聞かれるという種類ではないようで、全楽章アタッ カで(続けて)奏されたとしても、幻想的ではありません。 1841年初稿版による演奏も同じ波長で、より軽々としているようです。パンパンと弾んで元気に楽しく進めます。 1997年録音のアルヒーフです。残響の大きいものではなく、くっきりしています。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Simon Rattle Berliner Philharmoniker  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Nikolaus Harnoncourt Chamber Orchestra of Europe  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Thomas Hengelbrock NDR Sinfonie Orchester サイモン・ラトル / ベルリン・フィル ニコラウス・アーノンクール / ヨーロッパ室内管弦楽団 トーマス・ヘンゲルブロック / 北ドイツ放送交響楽団 シューマンの厚ぼったい管弦楽法へのソリューション・ナンバー1とも目されているものに、軽快さを感じさせる1841年初稿版の採用とピ リオド奏法の組み合わせがあるようです。こ れには同じような演奏を繰り返しても仕方がないという意識も加わっているのかもしれません。曲に新しい角度で光を投げかけようとする意欲的な指揮者たちに よって取り上げられています。アーノンクール、ヘンゲルブロック、ラトルなどで、頭の良い人たちはそちらへ向うようです。しかし二つの版のうちどちらをと るかは常に意見の分かれるところです。これは古くはブラームスから論議されている問題です。シューマン本人と妻クララは1851年の改訂版を気に入ってい たということですが、前述した通り私も改訂版をさらっとやったものの方が好きですので、ここではまとめて概観するにとどめます。というのも、ピリオド奏法 の語法も一つの定まったセオリーがあるわけで、どっちがどういいかと いう違いを見極める基準がよく分からないところもあるからです。また、これらの演奏はモダン楽器をピリオド奏法でやる趣向のものであ り、反対に古楽器を素直な表現でやってくれるといいなという思いも加わっています。今のところそういう方向はヘレヴェッヘぐらいでしょうか。 ラトル盤 ピリオド奏法の語法と申し上げたのは実は色々ありますが、ノン・ビブラートということを除けば大雑把にここで は短く区切る リズム傾向のことです。そういう歯切れ良く軽快に進んで行くものではない、オーソドックスな部分を一番多く感じさせるのは、この三人のうちでは新しく出し てきたラトルかもしれません。十分にピリオド奏法ですが、この人なりに工夫・解釈したものなのでしょう、ベルリン・フィルということもあって低音もよく出 ていて、当然ながら小さいオーケストラ然とはしません。最も落ち着いている部類で、途中でぐっと遅くしたりの表現も聞かれますし、テンポだけでなく強弱で も緩めるところが多い気がします。ラトルはこの版が好きとのことで、知性を感じさせながら聞いていて気持ちの良い演奏でした。 アーノンクール盤 ピリオド奏法ではその師匠級にあたるアーノンクールも、この曲はウィーンの古楽の手兵によるものではないせい もあり、室内 オーケストラながら厚みのある低音を響かせます。このやり方に先鞭をつけたものということになります。ほぼ同時期に前後して改訂版も録音しており、そちら はベルリン・フィルとのものですが、この人らしいという意味でここでは初稿版の方と比較しました。 ノン・ビブラートによる響きの純粋さが他の演奏より良く味わえます。こ の奏法の責任者の一人ということでラトルよりも表情はよりそれらしいですが、重みは結構感じられます。金管とティンパニをともなったくっきりしたリズムの 合間に歌うようなやわらかさもあり、さすがにその歴史も長い考案者だけあって様式としてこなれています。大変オリジナリティーがありながら、何度も聞いて いるとこれがスタンダードに思えてくる不思議なところがあります。 ヘンゲルブロック盤 その点、ヘンゲルブロックの方が若干リズムが弾んで明るいでしょうか。この人は1958年生まれのドイツの指 揮者で、フラ イブルク・バロック・オーケストラで活躍し、ロ短調ミサなどの清新な演奏に驚かれた方もいらっしゃると思います。シューマンは彼が北ドイツ放送交響楽団の 主席になった記念としての第一弾 CD ということです。 古楽のメリハリをつけたピリオド奏法らしい演奏です。流すところはテヌートでつなげ、時々切るところはスタッカートという変化をつけたもので、表情の豊 かさという点ではラトルとも似ています。聞いた感じはビブラートがないからということもあるものの、それだけではなく直線的でストレートであり、はきはき しています。 緩徐楽章も真っ直ぐで清々しく、遅くはないですが特に快速で流すわけでもなく、よく歌っています。しかしロマン派の影はありません。あくまでも明るく すっきりとして、伝統的な解釈とは別の音楽になっています。 第三楽章の始まりのトランペットはユニークで、以降のリズムは大変切れます。前へとドライブが効いていて面白いという印象です。 第四楽章は舞踊のような運びで、パンパンと軽く弾むティンパニがガーディナーと同様にちょっと盆踊りみたいに聞こえなくもありません。 ラトルは2013年の録音で、新しく一般の販路で扱うベルリン・フィル・レコーディングスというレーベルとしての第一弾です。アーノンクールはテルデッ クの1994年、ヘンゲルブロックはソニー・クラシカル2010〜11年の録音です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Sergiu Celibidache Münchner Philharmoniker ♥ セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィル ♥ 反対に遅い方にほぐす演奏ではだめかというとそうでもないのです。単にテンポではなく、音をどう捉えるかということでもありましょう。晩年のチェリビ ダッケはテンポが遅くなったことで有名です。そのシューマンはというと、堂々としていてやかましくなく、さすがに味わいがあります。出だしからやわらかく 遅く出ますが、独特の雰囲気です。悠然としてきばらず、別世界です。これはこれで大変説得力があります。第二楽章の出だしは室内楽のような内省的な響き で、ヴァイオリン・ソロ以降も静かなまま、物語の音楽のようです。それは瞬間的にペールギュントかと思わせるほどです。第三楽章になってもやはり遅いです が、深刻な雰囲気はなく、響きが美しいです。最後まで決して走ることがありません。音の純粋さを追求して行った演奏という印象で、奇才ゆえに単にドイツ的 というような言葉では言い表せません。 1988年の録音はこのシリーズの共通点である生っぽい厚みとやわらかさのある音で、深々と音に浸れるものです。レーベルは EMI で、廉価なボックス・シリーズが出ました。  Antoni Wit Polish National Radio Symphony Orchestra アントニ・ヴィト / ポーランド国立放送交響楽団 晩年のチェリビダッケを思わせるような遅いところのある演奏をもう一つ。といってもテンポは伸び縮みします。1944年生まれのポーランドの指揮者、 ヴィトはナクソスからのリリースで、ゆったりとした自然な演奏です。 かなりゆったり入ります。重さのある荘重な演奏という感じの始まりです。しかし第一楽章の最初のテーマの提示の後で速くはなり、オーソドックスなテンポ の箇所もあります。第二楽章も大変ゆっくりで、チェリビダッケを褒めるならこれも褒めなくてはいけないかもしれません。ところが第三楽章は特にゆっくりと いうわけではなく、通常のテンポで始めて展開部も同様です。そして最後になって、少し音を切りつつ間を空けながらスローダウンします。第四楽章では静かな ところから高まって行く最初の部分が悠揚迫らざる運びで感動的です。途中大きなテンポの揺れ(緩め)があります。そこをちょっと作為的に感じる人もいるか もしれませんが、意欲的な表情とも言えるでしょう。ラストでは走り、そして緩めて終わります。 1993年ナクソスの録音は弦が分解されていて自然です。残響があってやわらかく、コンサートで聞いているようです。 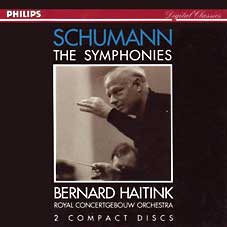 Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra ♥ ハイティンク/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ♥ 次に伝統的な楽団によるオーソドックスな演奏を三つほど続けてご紹介します。後ろ二つは旧東ドイツの楽団です。 まずオランダの名門、コンセルトヘボウです。ハイティンクのシューマンはあまり話題にされないところがあるかもしれませんが、彼の演奏の中でも出来の良 いものだと思います。もっと注目されてしかるべきではないでしょうか。派手な演出をしない指揮者と捉えられることが多いですが、出だしから案外うねりのあ る弦の運びが聞かれます。表情があって湧き上がるように盛り上がり、少し速めるような動きも意欲的です。テンポはゆっくりと始 まった後は中庸やや速めです。重くなることはなく、その後はしばらく素直に運びます。 第二楽章はゆったりとよく歌います。しっとりとしていていいと思います。そして後半は大変ゆっくりになりますが、ここでも音がきれいです。 第三楽章は重さを出し、過度に興奮することなく堂々と進めます。終楽章へ向けて一旦静かになるところではスピード・ダウンしてぐっと抑えますが、健全な 冷静さを保っています。そこから徐々に夜明けのように進める箇所は美しく、ベートーヴェンの第5の終楽章へと入るところのような緊張感が漂います。 第四楽章の入りは力があり、興奮に我を忘れることなくスケールが非常に大きい表現となっています。そして最後では意外にも速まり、熱を帯びて終わりま す。ノー・モア・ノー・レスの種類で曲の純粋形を示すものでありながら、その伝統的な解釈の中に熱さの感じられる大変魅力的な演奏だと思います。マンフ レッド序曲も同じ波長です。 フィリップスの潤いある音の録音は大変魅力的です。1984年の録音です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Otmar Suitner Staatskapelle Berlin オトマール・スウィトナー / シュターツカペレ・ベルリン 伝統的なオーケストラのオーソドックスな解釈の好演をもう一つ。スウィトナーとシュターツカペレ・ベルリンです。全体には真面目な人柄を感じさせる演奏 ですが、初めの音から熱がこもっています。ハイティンクのフィリップスと並んで、こちらのイエス・キリスト教会の録音も美しいものです。テンポは中庸やや ゆったりで始め、ハイティンク同様最初の動機の提示の後速めます。残響が豊かなので埋もれがちですが、よく聞くと細かな表情があって弾むリズムも感じら れ、ハイティンクよりもねばるような歌も聞かれます。その後の第一楽章の運びでも若干力が入っているかもしれません。重さもあります。後半はまた少し速ま ります。 第二楽章はゆったりではありますが、あまり遅くし過ぎず、さらっと進めつつ味わいある抑揚があります。 第三楽章以降も力のある展開で、適宜テンポを動かしながらラストまで運びます。途中ブラスのクレッシェンドで大変大きな表情を付け、終わりの直前で少し 速めるもののハイティンクと異なって走るわけではなく、力強い歩みで締めます。 1987年録音の DENON PCM シリーズですが硬過ぎず、この団体と会場の良さを出していると言えるでしょう。ただ少し残響過多かもしれません。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Wolfgang Sawallisch Staatskapelle Dresden ウォルフガング・サバリッシュ / シュターツカペレ・ドレスデン そして三つめ、これも伝統的なオーケストラで真っ向勝負であり、大変迫力があるという演奏です。軽さを出してシューマンをすっきりやろうという意図とは 正反対です。というか、そういうことは考えていないでしょう。したがってスケールの大きな演奏を求める真摯なオーケストラ・ファンの方にはまずこれかもし れません。バーンスタインの演奏を好む人々にも支持されているようで、時々並べて言及されます。演奏はバーンスタインの思い入れのあるよく造作された大き な演奏よりは真っ直ぐですが、力強さを感じさせるという点では双璧で、どちらも満足行くものでしょう。特に日本では大変人気がある盤のようです。演奏スタ イルと同時に N響との親密な関係なども人気の理由かもしれません。 大変重い音の一撃で始まります。出だしから雄大さが感じられ、遅いところは力を込めて粘ります。スケールの大きな音楽が始まるな、という予感がします。 そして力を込めたままぐっと速くなり、それも大変勢いが良いです。振り子が両側へ振れ、予感は的中します。昔のロマン派のようなテンポの揺れではありませ んが、自在な伸び縮みの呼吸があります。 第二楽章も遅いテンポでしっかりと歌います。けれん味のない運びです。繊細というよりもグラマラスな方向で、音に包まれる感じがします。それもやわらか い音で心地が良いです。 第三楽章はかなり速めのテンポを取り、そしてガツンと来る力強い運びです。展開部もあまり遅くはせず、案外軽さも出します。そこからのクレッシェンドは すごく抑えたところから地を這って、という感じにはなりませんが、息が長く、最後で盛り上げます。第四楽章の入りは走らず、テンポは中庸です。この楽章も 小細工はなく、威風堂々と終わります。 1972年 EMI です。ドレスデン・ルカ教会での録音はイエス・キリスト教会のスウィトナー同様残響過多なところがあります。浴室のように大変よく鳴っているという印象で す。演奏のスケールを大きく感じさせるという意味では大事なポイントだと思います。ピラミッド型の安定した太い音に艶が乗ります。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Rafael Kubelik Bayerishen Rundfunks ♥ ラファエル・クーベリック / バイエルン放送交響楽団 ♥ ワルターが好きだったという指揮者、クーベリックはやわらかい歌と落ち 着いた力に魅力があります。これもシューマンの4番として大変人気があり、オーソ ドックスな演奏と言えますが、楽団の方は第一級水準ながら戦後結成ですので、伝統的とまでは言えないかもしれません。クーベリックは1963〜64年にド イツ・グラモフォンからベルリン・フィルとも出しており、そちらを評価される方も多いようです。基本的な解釈は同じだと思いますが、比べればベルリン・ フィル盤の方がフレッシュさがあるとも言えるでしょう。要所で力強く区切りを見せるダイナミックなところがあり、第三楽章のラストはより遅く感じられま す。そしてここでバイエルン放響の方を取り上げたのは主に録音です。ドイツ・グラモフォンも良い音ですが、この時期のこのレーベルらしく高域弦と金管の倍 音がやや薄い傾向にあります。リマスター盤はほとんど気にならない範囲ですが、もう少し抑えるとベストでしょう。 第一楽章ですが、ベルリン・フィル盤より重さのある出だしで音も分厚い録音です。やはり滑らかなスラーでやや荘重に運びます。フレーズの最初の音を弱く 入ってふわっと持ち上げるような滑らかさはこの人の一つの特徴で、他の演奏と比べても魅力的な点です。最後の音も長く延ばします。無駄に熱くならず、穏や かな大人の落ち着きがあっていい演奏だと思います。テンポもややゆったりの方に入ります。といっても最近のさらっとしたものが主流になる前はこのぐらいが 標準でした。アンサンブルの切れでベルリン・フィルの方が好きな人もいるかもしれませんが、このアタックの角が揃い過ぎない自然な鳴り方の方がリラックスできま す。どこか明るさも感じます。 第二楽章はかなり遅いと思います。他にもっと遅いものもありますからすごく遅いとは言えませんが、所々で緩めつつたゆたう心地よさがあります。新世界の 後半でもそうでしたが、クーベリックらしさの出たきれいな緩徐楽章だと思います。 第三楽章はオーソドックスなテンポ設定でしっかりとした力もあります。丁寧に鳴らして行く感じがします。最後は遅くなります。 第四楽章も中庸なテンポで始まりますが、途中からすっと速くなって穏やかな揺れがあります。後半の、ものによっては繰り返しが退屈になる部分にも表情が あって飽きさせないし、フレーズ最後の音を延ばしながらの優雅な運びと突進しないエンディングは十分な強さもあります。 1978〜79年ソニー・クラシカルの録音はふくよかで滑らかな音です。良い録音です。残響はかなりある方です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Hans Vonk Cologne Radio Symphony ハンス・フォンク / ケルン放送交響楽団 伝統ある有名オーケストラという範疇ではないかもしれませんが、これもオーソドックスな解釈の演奏です。1942年生まれで二度病に倒れ、2004年に 亡くなったオランダの指揮者ハンス・フォンクも大変知られた人というわけではないですが、このシューマンを高く評価する人もいます。 リズムに重さがあり、スケールの大きいところの感じられる正攻法の演奏だと思います。それでいて騒々しくならず、粘る歌があると同時に運びにゆとりも感 じられます。チェリビダッケのように遅くはないですが、テンポはややゆっくりです。そして決して走りません。第一楽章の最初のモチーフから変わって少し速 くするところでは、曲の造り上確かに若干速くなりますが、それでも基本は落ち着いています。この楽章はずっとそんな調子です。第二楽章でのテンポもやや ゆっくりからゆっくりの間という感じで、終始しっとりと歌います。その後の楽章も同じで、第三楽章から第四楽章へ移る部分での静かに抑えるところでは大変 遅く、最終楽章はややテンポを上げて、他の演奏者でも聞かれるオーソドックスな流れとなります。華やかさのある演奏ではなく、最も真面目なものの一つで しょう。 レーベルは EMI で1992年の録音は潤いのある響きです。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 George Szell The Cleveland Orchestra ジョージ・セル / クリーヴランド管弦楽団 次は歯切れの良いもの。これは昔から定評のある演奏です。スコアに独自の改訂を加えて臨んでいるということですから、私には解説できませんので聞いてみ てください。よくコントロールされた直線的で滑らかな弦の流れに対してリズムはくっきりと歯切れが良く、曖昧なところがありません。曇り空のようなシュー マンではなく、強い風で雲を吹き飛ばしたような見通しの良さが身上です。力強く引き締めることと楽譜の改訂とによって響きの不透明さを克服するという戦略 でしょう。 第一楽章ではテンポもきびきびしており、速めです。元気に弾み、ブラスも短く鋭く切れます。走り出すと速度を上げた蒸気機関車が爆走する映画のシーンの ようになります。第二楽章では無駄のないしなやかな歌も聞かれます。シューマンってこんなに決然としてる人だろうかと思わないこともないですが、説得力は あります。第三楽章もくっきりとしたリズムですが、ここは速くはありません。一つひとつかっちりと区切って行くような拍動を感じて進むところに評判通りの セルの人柄が表れています。そして楽章は変わり、最後は圧倒的にまくって終わります。悪い意味ではなく鍛錬されたサーカスのようであり、曖昧なものが嫌い な人はこれが一番かもしれません。そして最も硬派な演奏ながらやかましいものではなく、隅々まで制御され、どこか清々しいところもある演奏だと思います。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Paul Paray Detroit Symphony Orchestra ポール・パレー / デトロイト交響楽団 歯切れの良いセルに続いて、その先輩格にして古くから定評のあるパレーの元気のある演奏です。1886年生まれのフランス人ですが、デトロイト交響楽団 を鍛え上げた人です。シューマンの交響曲というとこれを挙げる人もいます。適度な伸び縮みがあり、曇りのない明確な運びで力もありながら騒々しくなく、リ ズムがくっきりと歯切れの良いところはちょっとセルを思わせてエネルギッシュです。静かなパートではテンポを落とし、滑らかさも出します。ステレオになっ てからも活躍した人ですが、シューマンの4番は1953年録音のモノラルで、音が古いのは仕方のないことです。フランス管のような華やかな響きが聞こえた 気がしたので、さすがフランスの人だなと思ったらデトロイト・シンフォニーでした。鼻にかかった音に聞こえる古い録音の加減でしょうか。弦にはポルタメン トが聞かれます。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Wilhelm Furtwängler Berliner Philharmoniker ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィル さて、古い時代のパレーを出してきたところでもう一つ忘れてはいけないものにドイツ・ロマン派を代表する揺れる演奏があります。それはシューマンの4番 の金字塔とも言われてきたもの、フルトヴェングラー盤です。ワルターが40年代のモノラルなのに対してこちらはパレーと同じ年、1953年のセッション録 音です。この指揮者の中では収録のコンディションも良く、これを取り上げる人にとっては無二の存在であり、したがってここでは取り上げなくてもいいかもし れませんが外すのもためらわれます。まずいことも書きたくありません。ホット・ポテトです。 重く深刻なまでの情感をたたえた入りであり、まさに深い森に霧が立ちこめているようです。バーンスタインとはまた違ってネイティヴにスケールの大きな物 語性があります。音の運びが神秘的です。といっても主題の提示が終わって速くなるところも猛然と走って行くほどの演奏ではないので、新しい録音が良い人は ヴァントに行くのかもしれません。 第二楽章は遅く、ヴァイオリン・ソロが自覚してたどたどしいまでに表現する泣きの表情が古き良き時代を感じさせます。 ゆっくりの第三楽章は決してもったいぶっているわけではなく、重々しくて偉大です。 第四楽章のデモニッシュな入城はまるでワーグナーを聞いているようで、この楽章ではライヴほど激しくはないですがお約束のテンポの揺れが聞こえます。緩 めたり速くなったりで、最後もバイロイトの第九ほどではないもののやはり走って行って終わります。聞き終えると、感動とともに6輪のメルセデスで凱旋する政治家のフィルム映像が浮かぶような気もし ました。ビートルを見て同じものを思い出すイギリス人の偏見のようです が、その政治家はフルトヴェングラーの大ファンでした。難しい立場でそ の意向に反対してきたこの偉大な精神に対しては言い難いことながら、戦後と言えどもそんな激動の時代の音であることに変わりはありません。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Günter Wand Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ギュンター・ヴァント / ベルリン・ドイツ交響楽団 1912年生まれのドイツの指揮者です。前出ケルン放送交響楽団と縁が深く、後に北ドイツ放送交響楽団の主席として活躍しました。シューマンの4番は 1979年の N響、1991年の北ドイツ放響との RCA 盤もありますが、ここではベルリン・ドイツ交響楽団のものを挙げます。 これも正統派の演奏と言えますが、前へ出る種類の熱演です。遅くはない適度なテンポで進めますが、ドイツロマン主義の生き残りのように言ってフルトヴェ ングラーと比較する人もあります。そこまでの揺れはないものの、フリッチャイ同様なんとなく昔のドイツのスタイルと言われればその通りかもしれません。独 特の呼吸があり、遅いところからぐっと速くなったりするのです。 緩徐楽章は相当遅いテンポで、そこは北ドイツ放響盤とも同じ解釈です。拍がちょっともたっと聞こえるところがあるのもなんとなく戦前のドイツの雰囲気か もしれません。好きな人にはこたえられないでしょう。かといって最終楽章は強烈な盛り上がりで終わるわけではありません。 1995年 RBB 放送連盟収録ですが、弦に少しだけディストーションが乗る気もします。しかしスパイスのようなもので、この演奏が好きな方にとっては却って迫力が増して喜ばれるかもしれません。少なくとも雰囲気を作っている一つのファクターだとは言えます。そしてこの盤はそれが ない北ドイツ放送交響楽団とのものよりも熱い演奏だと思います。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 David Zinman Tonhalle Orchestra Zurich デイヴィッド・ジンマン / チューリヒ・トーンハレ管弦楽団 アメリカの指揮者です。モントゥーに習ったということですが、性質は大分異なるようです。95年からはチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の音楽監督で す。これも熱い演奏です。 決して遅いテンポはとらず、やや速めでしょうか。面白いのはスタッカートとは言えない範囲ながら、一つのフレーズのおしまいの音を延ばさずにすっと切る ことです。もたもたとする感覚を好まない人かもしれません。テンポは常に一定というわけではなく、途中からスピード・アップすることもあります。典型的な 巨匠風の演奏というのとは少し違う気もするけど、乗っているのだと思います。1936年生まれの人ですから、十分に巨匠でしょうか。間を詰め、雄大にはな らないで興奮の度を高めて行きます。しかしそのようにエキサイトして走るところは昔気質のロマンティックなスタイルに近いのかもしれません。フルトヴェン グラーの演奏が好きな人にはヴァントやフリッチャイといった指揮者と並んでこの人も好まれるのかもしれないなと思いました。 第二楽章もテンポはやや速めで間を空けずに進めますが、力を抜いて軽快という印象はなく、真剣さから外へと踏み出すことがありません。落ち着いた感じで もなく、激しい感情の間のつなぎとしてさっと流すという印象です。 すぐに第三楽章になり、また走りますが、かと思うと途中で大胆にゆっくりにすることもあります。そこは緩徐楽章よりも遅いです。これは最後の盛り上がり に対してのメリハリがつけたいのかもしれません。そして終楽章がまた前へ前へと熱っぽく走ります。古楽奏法や楽譜にも知識と関心が高く、使用楽器に対する こだわりがすごい指揮者という話ですが、聞いていると計算するタイプではなくてハイ・テンションの人であり、楽団員も皆が真剣です。熱演です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker 1957 ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィル(1957) 古い時代のドイツ・ロマン派の様式と決別する流れをメインストリームにおいて作ったカラヤンは、この曲だけ三回録音しています。好きだったのでしょう。 となると彼の演奏スタイルの変遷という例の問題にぶつかるわけです。カラヤンのマナーを時期によっていくつに分けるかは捉え方によると思いますが、60年 代のスピーディで颯爽としていながらダイナミックさを兼ね備えた時期をフェーズ1、そこから技術の上でも楽団の一つの黄金期を迎え、以前とテンポはあまり 変えないながらグラマラスになって、いわゆるカラヤン・レガートと言われる流麗さがはっきりしてきた70年代をフェーズ2、さらに曲によっては大変大きな 表情をつけ、人によっては人工的だと言う場合もありますが、ストップウォッチでタイムを管理したり楽団員と不仲になって空疎な音を聞かせるケースもあった ディジタル の80年代をフェーズ3、そして表現の上では同じフェーズとも言えますが、ラスト・コンサートなどで驚くほど熱い演奏を聞かせてくれた最晩年のものを フェーズ4にするというのが今までの頭の中の整理区分でした。 ところが驚いたことに、もう一つ、それらの前の位相があったのです。あるいは時期ではなく、曲による思い入れの違いなのでしょうか。モノラル時代、 1957年のシューマンの4番の演奏を聞くと、60年代の颯爽として余分な表情を削ぎ落としたフェーズ1のものではありません。まだ自分らしさを模索して いる最中だったのか、それ以前のフルトヴェングラーのベルリン・フィルですと言われても分からないような表現です。テンポは揺れ、深刻さすら感じさせる大 きな感情表現のように感じます。フェーズ0としましょうか。少しだけ見て行きましょう。 この最初の録音は時期のわりに案外スローな出だしです。力がこもって重々しいです。ベルリン・フィルの音色がフルトヴェングラー時代のものだと言う人も いるようですが、表現だけでなく、モノラルの音は確かにそうも聞こえます。録音の癖を除いてまでそう言えるかは私にはよく分かりません。そして急激にス ピードアップして行く様もまるでフルトヴェングラーのようで、この人のおなじみの顔ではありません。こういう一面もあったのかと驚きました。その後もテン ポは揺れるし、うねるような呼吸もあります。走ったり短くリタルダンドしたり、フレーズの最後の音だけ延ばしたり、およそカラヤンとは思えません。静かに なるとスローダウンし、そこにまた時代の空気を感じます。そしてこの第一楽章のラストは走る走るで仰天です。 第二楽章は一転してゆっくりで、自己の感情に没入するかのようです。その憂いの影はドラマ性を感じさせ、それも後のドラマチックさとは違うサスペンスも ののような種類です。この状態からどうやってあのカラヤンらしい様式を築いて行ったのでしょう。我々がカラヤンと認識している固定的なモードは、 実は試行錯誤して組み立てられたものであり、本人の中ではいつでも変化させられる状態として維持していた幻影のようなものかもしれません。だから外からは 多様な顔を持つ複雑な人に見えるのです。ヴァイオリンのソロ以降は大変スローに、やはり揺れを伴って歌われます。 第三楽章は速くはないですが力強く、後半では止まりそうなほど緩めます。 第四楽章へのクレッシェンドにも重たい神秘のもやが覆い被さります。確かに晩年にもこういう大きい表現はまた出て来ましたが、そうした迫力は残しながら スピードアップし、揺れを除いて構築して行ったのが次の60年代のスタイルなのでしょうか。そして揺り戻しでまた遅くなり、速くなりを何度も繰り返し、最 後は走って締め 括ります。 こうして聞くと、この巨匠にもまだ自分のスタイルを確立していない時期があったわけです。カラヤンという人、整ってはいるけれどもどこにその人らしさが あるのか分からない演奏家もいるなかで、大変個性のある人です。そして好きであろうとなかろうと、いっぱい言いたくなる人です。  Schumann Symphony No.4 in D minor, op.120 Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker 1971 /1987 ♥♥ ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィル(1971) これは前述の区分で言えばフェーズ2になりますが、感覚としては2.5 のような感じでしょうか。颯爽として流麗というよりも、滑らかにしてダイナミックです。 57年盤と比べると最初の一撃から低音が響いて豊かです。同時に磨かれ、洗練された音に感じられます。テンポは同じようにゆっくりから速くしますが、た だスコアに従っているというよりも、この曲はカラヤンにとってはさらっと流すことができないものであって、元々大きな表現に向かう傾向があるのかもしれま せん。それはシューマンの演奏が一貫しているとも言えます。ここではフェーズ3の80年代にあった大きな表情が聞かれるわけですが、シューマンにはフェー ズ1と2の演奏がないことになります。といってもアンサンブルは流麗と言われた通りで、隈取りはしっかりなものの弧を描くような滑らかさも加わります。こ れを意図したレガー トだと言うのもどうかとは思いますが、引きずるようなつながりは確かに出て来ているのです。恐らくこうした弾き方は当時のスタンダードで、楽団の血と肉に なっていたのでしょう。 第二楽章は遅めのテンポで、57年盤の影を感じさせる神秘性というよりはもっとスムーズになっています。太く甘いヴァイオリン・ソロは流れるようで、過 度と言えるほどに歌わせる静かな部分が妖艶です。オーボエとのユニゾンには光沢があります。 第三楽章は以前よりも重く、力を込めています。フル・オーケストラのスケールの大きさを感じます。 そして第四楽章ですが、ここの高まって行くところは前の演奏の方が迫真というか、心理的な切迫感がありました。一方でここでは雄大です。その後の展開も テンポは遅めで、以前のように速くなったり遅くなったりの揺れはありません。分厚い、という感覚です。終わりに向って緩める歌はまた流麗で、最後の最後に 速くする以外はずっとゆっくりのテンポです。 ヘルベルト・フォン・カラヤン / ウィーン・フィル(1987)♥♥ こちらは87年五月ということで、日本でのラスト・コンサートのちょうど一年前、カラヤンの最後のコンサートは89年四月で七月には亡くなっていますか ら、晩年と言っていい時期のウィーン・フィルとのライヴ録音です。ベルリン・フィルとのいさかいの後、それと相反するように彼の音楽表現はより自然なもの へと変わりつつあったのかもしれません。ここでのカラヤンは東京公演での素直に感動できるあの波長をすでに持っているようです。スケールの大きな演奏なの でシューマンの個人的な好みの方向ではないにもかかわらず、本来はこうかなとも思わされ、いい演奏だと言う以外にありません。 第一楽章ですが、遅いテンポで、表現としてはよりスラーでつながっています。滑らかだけど重い運びです。何よりウィーン・フィルのやわらかさが魅力的で す。表現の大きさは71年のときと変わりません。波のようにうねる呼吸があり、57年の揺れとは違いますが、遅いところからかなり速めに移る動きが聞かれ ます。しかしこの動きはどこか真摯です。こういう感覚というもの、オーケストラですから指揮者一人の心境が表れるているとは言い難いですし、その場の信頼 関係から醸成されるものかもしれませんが、それならばこそ指揮者の存在が大きいとも言えるでしょう。70年代の演奏と形の上では同じ種類なのに、ゴージャ スな感覚や流麗さが前に出るというよりも、より真剣で、信頼の置ける人という印象です。 第二楽章は静かにゆっくり運び、やわらかな歌が美しいです。ピリオド奏法とは違いますが、フレーズを自然に中程に向って膨らませるウィーン・フィルのボ ウイングがふくよかです。ヴァイオリン・ソロもゆったり素直に歌っていて、気がつけば心を合わせています。そして途中では大変遅くなりますが、以前のショ ウマンぶりや人工美は全く感じません。便宜的区分のフェーズ4としていいでしょうか。 力強く重さのある第三楽章も響きが美しく、真っ直ぐに一歩一歩区切るような拍で進めます。中間部は素直な歌で、やはり作為は感じさせません。最後は大変 ゆっくり静かに抑えるので表現の幅が大きいですが、それでも自然です。 第四楽章のクレッシェンドは荘重で、息が長く滑らかです。ウィーン・フィルの木管と弦の合わさった音が芳醇で、自在に緩めながら進めて行きます。中間部 では大きな間にこの頃のカラヤンらしさを感じますが、57年のときのように前へと走る興奮性の揺れは作らず、専ら緩める方に動かします。終盤では走らせる 前までは落ち着いた確固とした足取りで、ラストもその感覚で締めます。 ライヴですが録音はバランスが良く、70年代のセッション録音よりやわらかさと自然な艶があります。カラヤンのベスト録音だと思います。 INDEX |