|
ベートーヴェン / 序曲集
エグモント & コリオラン

取り上げる CD 18枚: クリュイタンス/スウィトナー/ハイティンク(’74/’85)/ヤンソンス/フリッチャイ/セル/カラヤン/ベーム/マズア
/デイヴィス/アバド/ジュリーニ/ノイマン/アーノンクール/ハーディング/ヤルヴィ/ドゥダメル
ベートーヴェンの序曲は交響曲の CD の余白に入っていたりしますが、序曲集としてまとめられることもあり、この作曲家の名曲のうちに数えられるでしょう。特に悲劇を扱うコリオラン序曲とエグモント序曲には力強さがあり、髪を振り乱すあのベートーヴェン像を思わせるような運びにおいて「運命」交響曲などとも似た波長を持っています。何とも格好いいというか、迫力のオーケストラ・サウンドを満喫できるという意味ではちょっと男性愛好家向きかもしれないけれども、クラシックの入門曲に数えてもよいぐらいだと思います。特に「エグモント」序曲など、深刻さとロマンティックな感覚が混じり合ったいかにもベートーヴェンという劇的な曲です。短調で進んで行って最後に歓喜の長調で終わるところはこの作曲家の好きな展開で、そうした作りは入門曲の代表のようなムソルグスキーの「禿山の一夜」やシベリウスの「フィンランディア」あたりとも共通しています。歓喜の爆発ではなく、同じ長調でも耳に残る歌のようなきれいなメロディーであったなら、入門曲としての認定は決定的になっていたと思います。そのままでも「モルダウ」や「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」などと組み合わせてビギナーへのクラシック曲の紹介のようになってる CD も存在します。
この二曲以外によく演奏されるベートーヴェンの序曲には他に、オペラの「フィデリオ」用である「レオノーレ」第3番の序曲、そのベートーヴェン唯一のオペラ名をそのまま冠した「フィデリオ」序曲(「レオノーレ」は「フィデリオ」に本来付けられるべきタイトルであり、本人はその名を望んでいました。その上演に関して色々とやり直し行程があり、レオノーレの名では1番と2番の序曲も存在します)、バレエ音楽用の「プロメテウスの創造物」序曲、全体としてはほぼ忘れられている戯曲のための「アテネの廃墟」序曲などがあり、録音でもよくカップリングになっています。
序曲集というものが成立するのはなにもベートーヴェンだけというわけではありませんが、他の作曲家を挙げるなら、どれもオペラ本体が有名なモーツァルト、ロッシーニ、ワーグナーぐらいでしょうか。ワーグナーは序曲だけでなく前奏曲なども含まれます。オペラを書かなかったブラームスはベートーヴェンと似た状況で、演奏会用序曲がいくつかあるものの、録音においてはそれこそ交響曲の余白扱いが多いようです。そういう意味で、単独で名曲扱いになるベートーヴェンの序曲は注目に値するのです。ということで、ここでは「エグモント」序曲を中心にして色々な演奏の聞き比べをしようと思います。
 Lamoral, Count of Egmont
エグモント序曲について
この曲はゲーテの戯曲に付けられた一連の劇音楽(全10曲)の最初に来る序曲です。劇はオペラではなく、語り演じられるものながら、その中の曲のいくつかではソプラノが歌ったりします。ただ、最も有名でそれだけが演奏される機会が多い序曲は最初の上演には間に合わず、少し遅れて完成されたとのことです。「エグモント」という劇は1788年に出版されたもので、「ファウスト」で有名な文豪ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)はベートーヴェンより二十歳ほど上という同時代人です。ベートーヴェンはゲーテを崇敬しており、ウィーンで上演される予定の作品を依頼され、喜んで引き受けました。1809年から作り始め、翌10年には本人の指揮で演奏されました。ベートーヴェン三十九歳の年でした。交響曲で言えば6番と7番の間ですが、6番は5番ともほぼ同じ頃なので、「運命」にも近い時期とも言えます。この前後には他にピアノ協奏曲の「皇帝」、三重奏曲「大公」などもあり、耳の具合は悪くなって来るけれども(「ハリゲンシュタットの遺書」を書いたのは11年前)、作曲家中期の実り多い時期でした。そして作品は初演当時から評価が高く、ゲーテ本人からも賛辞を得ました。
エグモントと劇のあらすじ
エグモントというのは人名です。オランダの独立運動初期の英雄で、エフモント伯ラモラール(ラモラール・ファン・エフモント 1522-1568)という人物(エグモントはドイツ語読み)です。当時オランダを支配していたスペインによって斬首刑に処せられました。劇ではこのエグモントの事件がオランダ独立戦争(八十年戦争)につながって行ったかのように見せますが、そうした大きなうねりの中で起きた一つの事件でした。歌劇「フィデリオ」にしろ、ナポレオンを理想視して作った交響曲「エロイカ(英雄/第3番)」にしろ、ベートーヴェンは戦って自由をもたらす英雄には心を動かされるようです。
舞台は当時オランダ(ハプスブルク領ネーデルランド)の首都であった16世紀のブリュッセルで、オランダを支配していたのは国王フェリペ2世のスペイン帝国でした。このスペイン帝国はオーストリアのハプスブルク家が実効支配する神聖ローマ帝国と同じ系統であり、フェリペ2世もハプスブルク家の人間です。宗派の勢力で言うならオーストリアに加えてスペインを含むヨーロッパ南部はカトリックの国であり、フェリペ2世も熱心なカトリック信者。対してヨーロッパ北部はプロテスタント側の国が多く、その頃のオランダ(フランドル=フランダース地方)はプロテスタントの一派であるカルヴァン派が勢力を伸ばしつつあり、フェリペ2世はそれを快く思っていませんでした。
主人公のエグモント伯(伯爵)はオランダで富と力を持つ家系の生まれで、フェリペ2世の父のカール5世の軍に従軍した軍人であり、フェリペ2世の治世においては指揮官として戦って戦果を挙げました。そしてそれによってフランドルとフランス北部の知事となっていました。したがって最初は王から信頼を得ていたのです。しかしネーデルランドの総督はマルガリータ(マルグリット・ドートリッシュ 1480-1530)であり、彼女は劇中では穏健派として扱われますが、その宰相(さいしょう/君主の命を受けた首相)であったグランヴェル枢機卿(アントワーヌ・ド・グランヴェル 1517-1586)はプロテスタントを弾圧し、エグモントはこれに抵抗していました。物語はそのマルガリータ総督が、フェリペ2世から次代の総督となるアルバレス公爵(1567年から総督/フェルナンド・アルバレス・デ・トレド 1507-1582)の派遣を受けるという手紙を受け取ったところから始まります。マルガリータは総督の座を降りることを決意します。
そしてエグモントのミストレス、つまり愛人クレールヒェンが登場します。ベートーヴェンの曲の中で歌われるソプラノはこのクレールヒェンです。愛人というのは怪しい響きだけども、エグモントがすでに結婚して子供もいる四十代半ばの男だったからです。この若きクレールヒェンには彼女を思うブラッケンブルクという年齢相応の青年がいるのですが、クレールヒェンはエグモントに夢中で相手にしていません。ただし、既婚者というのはさすがに英雄としてまずいだろうということで、ゲーテの戯曲の中でのエグモントは若い独身者のように扱われています。
新たに着任したアルバレス総督は一段と弾圧を強めます。これもカルヴァン派へというよりも、オランダ全体への弾圧という扱いでしょうか。エグモントはアルバレス総督に対して「ネーデルランド人の権利を剥奪してもスペイン国王への忠誠を守ることにはならない」と説得をしますが、失敗します。そしてこの後エグモントは逮捕され、投獄されることになります。
クレールヒェンは獄中の恋人を救い出そうと手を尽くしますが、国王を恐れて市民たちは何もしません。孤立したエグモントは不安のうちに時を過ごします。そして結局大逆罪によってエグモントの死刑が決まるのですが、それを聞いたクレールヒェンはブラッケンブルクが止めるのも聞かず、服毒自殺を図ります。
獄中で斬首刑の判決を伝えられたエグモントを前に、以前から彼を尊敬していたアルバレス総督の婚外子であるフェルディナンドが嘆き悲しみますが、エグモントはそのフェルディナンドに「自分の仲間や愛するクレールヒェンのことを頼む」と言い残します。斬首刑を言い渡したのはアルバレス総督に他ならないわけだけど、エグモントはその家族にも愛されていたことになります。そして夢の中でエグモントに女神が現れます。顔の見た目はクレールヒェンです。その女神は彼の死がオランダに自由をもたらすことになるだろうと予言します。処刑の年から始まったオランダ独立戦争により、オランダ北部7州がネーデルランド連邦共和国として独立することになることを言っているのでしょう。物語はエグモントが刑場に向かうところで終わります。序曲(と劇音楽全体)の最後が明るいのは、彼の死が独立の英雄としての勝利を意味するからです。
 Gnaeus Maricius Coriolanus
コリオラン序曲について
演奏会用序曲「コリオラン」の方はエグモントの三年前、1807年に作られました。ベートーヴェン三十六歳のときで、同じ頃に作曲されたのは交響曲の第4番です。5番の「運命」と6番の「田園」も翌年完成ということで近く、エグモント序曲と同様に「運命」と似た雰囲気を持っているのも納得します。前年にはピアノ協奏曲の4番とヴァイオリン協奏曲を作っていたという、実り多き中期の作品です。出来上がったこの序曲は音楽好きのチェコの貴族の邸宅で最初に演奏されました。そのときには上記の交響曲とピアノ協奏曲の4番も同時に取り上げられました。
作曲の経緯としては、ウィーンの劇作家で友人であるハインリヒ・ヨーゼフ・フォン・コリン(1771-1811)が作った戯曲「コリオラン」(1804)を見て感動したからということのようです。実在する人や物事に理想を見出し、実際はそうでもない対象に憧れを投影して挫折するようなことを繰り返す人間くさい一面がベートーヴェンにはあったようです。ナポレオンについては当時は英雄視する人が多かっただろうし、マルクスですら社会主義の独裁を見抜けなかったのだからそうした理想論はある程度やむを得ないことでしょう。ただ、ベートーヴェンにはもう少し逸脱する傾向も見られました。部屋が片付けられず、ごみ屋敷になると引っ越してたことや、些細な理由で怒りを爆発させていたことなどから、モーツァルト同様に今でいう ADHD(発達障害)傾向があったともされるけど、行き過ぎた愛情から甥を自殺未遂に追いやったり、相手を理想化した熱烈なラブレターを書いたりもしていました。近くにいる人には火の粉が降りかかって大変だったでしょう。裏を返せばそれだけ純粋な人だったのだと思います。
コリオランと劇のあらすじ
エグモントは16世紀オランダの人でしたが、こちらのコリオラン序曲の主人公コリオラヌスは古代ローマの将軍です。それも帝政になる前、初期の共和制の時代であり、紀元前5世紀頃のお話です。「自由を求めて」という点では少し違うかもしれないものの、戦う英雄伝で悲劇というところは「エグモント」と同じであり、ベートーヴェンの好んでいたテーマにぴったりと当てはまります。
元となった話はローマ帝国時代の歴史家プルタルコス、リウィウス、ギリシャの歴史家ディオニシオスらが言及したもので、戯曲としてはシェークスピアも取り上げています。ベートーヴェンが感動したコリンの方の脚本は実はあまり有名ではありません。そしてこれら歴史家の見解や台本の内容はそれぞれに少しずつ食い違いがあります。
コリオラヌス(グナエウス/ガイウス・マルキウス・コリオラヌス 519BC?-?)は貴族出身で、立場的にも貴族側ではありますが、二十歳ぐらいから数々の戦いで名を揚げ、前493年にはローマ近郊の(ローマとナポリの間あたりまでに住んでいた)異民族であるウォルスキ族の最大の町、コリオリを陥落させました。一旦は背後からも敵に挟まれて苦戦したのですが、町に火を放つなど大胆かつ勇猛果敢な働きで形勢を逆転させたのです。この戦功によってグナエウス・マルキウスは「コリオリの勇者」を意味する、そのコリオラヌスという三つ目の姓を与えられました。ニックネームのようなものです。因みにその都市名であるコリオリですが、台風を反時計回りに渦巻かせることで有名な「コリオリの力」を想起させるかもしれません。でもそちらはフランスの物理学者の名前から来ており、語源的にはつながりがあるとしても直接は関係ありません。
その後ローマでは食料不足が起きてシシリアから穀物を輸入することになりましたが、その分配をめぐって貴族と平民とでどう分けるかという問題が生じます。貴族側に立っていたコリオラヌスはその三年前に平民が勝ち取った護民官(平民の立場を代表する官職)制度を反故にすることと引き換えに平民に食料を与えるべきだと主張します。その護民官制度を勝ち取る際の戦いで、平民たちが穀物生産を怠ったために食料不足が起きたからだというのです。これに対して護民官は怒り、コリオラヌスを告訴します。コリオラヌスは法廷に出廷せず、そのために国外追放になってしまいます。でも実はこれ以外にも追放になった理由があると述べる歴史家もいます。その説によると、食料危機が起きたとき、コリオラヌスは上記のウォルスキ族の別の町であるアンティウムから足りない分を略奪して見せたけれども、そのときの戦利品を国庫に納めなかったために追放されたというのです。いずれにせよ、ローマの英雄は国を追われることになります。
ローマの仕打ちに腹を立てたコリオラヌスは復讐を誓います。そしてそれまでの敵だったウォルスキ族と手を組むのです。コリオリを陥落させたとき、コリオラヌスはローマからの褒美をもらう代わりにウォルスキ人の友人の命を助けたこともあり、ウォルスキのリーダーは彼に協力しました。そしてウォルスキ族の人々と共に、コリオラヌスは元の自分の国であるローマに向けて進軍を開始することになるのです。
その軍勢がローマの目前まで来た頃のことでした、そこで別の動きが起こります。ローマ共和制樹立の立役者(プヴリコラ)の妹が大勢の女性たちを引き連れ、コリオラヌスの母の家へ行ってその母を説得したのです。母は進軍中のコリオラヌスの元へ向かいます。そして彼の妻も加えて女性たち全員でコリオラヌスを説得します。結局彼は母の嘆願に負け、ローマを攻めるのをやめて兵を引き払うことにします。前488年のことです。
しかし率いていたかつての敵の軍勢であるウォルスキ族をローマの門の前で引き返させられなかったため、コリオラヌスは責任を取って自らの命を絶ちます。これがベートーヴェンが序曲を作ったコリンの戯曲の結末です。シェークスピアの台本では自殺ではなく、この英雄が殺されるように描かれています。これには色々な歴史家の説があり、どれが正しいのかは分かっていません。コリオラヌスは兵を引いた後アンティウムで引退したけれども、ウォルスキ族のその町で査問にかけられ、その間に過激派によって殺されたという記述もあります。
序曲ではコリオランがローマに攻め入ろうとしている部分が勇ましい短調で表現され、その母が思いとどまるように嘆願する様子が長調で描かれています。武勇と愛の物語です。
フィデリオとレオノーレについて
ベートーヴェンの序曲として、ここでサブタイトルをエグモントとコリオランとしたのはその二曲が名曲だと思ったからですが、他にもレオノーレ序曲第3番やフィデリオ序曲も有名です。それだけ聞こうと思ったことは正直あまりないかもだけど、序曲集には必ず入っていて必然的に馴染みのあるものになります。しかもその二曲、同じ歌劇「フィデリオ」からのものなので、簡単にその内容についても触れてみます。オペラ好きの方には外せないでしょう。
フィデリオのあらすじ
歌劇「フィデリオ」はベートーヴェンが作った唯一のオペラです。作曲時期は中期の1805年から14年頃までにわたり、大きく分けて二回書き換えが行われるなど、成功するまでに時間がかかりました。交響曲で言えば第3番の「英雄」から第8番までの長い間ということになります。「レオノーレ」というのはこのオペラの主人公の女性の名前です。ベートーヴェンは最初その名での公演を望んだのですが、すでに別の作曲家による作品が存在していたので受け入れられず、「フィデリオ」というタイトルになりました。フィデリオというのはレオノーレが男装したときの名前です。男装の女性を扱うというのは同時代の他のオペラから最近の少女漫画や韓国ドラマに至るまで普遍的なことで、両性具有や性役割のテーマ追求というに限らず、そもそもそえ自体が魅惑的なものなのでしょう。原作はジャン・ニコライ・ブイイというフランス人で、フランスで実際に起きた事件をもとにしています。オペラの脚本はまた別の人です。
舞台は16世紀末のスペイン、セビリアの刑務所です。その刑務所の所長ピツァロは悪いやつで、貴族で政敵である政治家のフロレスタンに自分の悪事をあばかれそうになったので、フロレスタンを無実の罪で捕らえ、自分の刑務所の地下牢に閉じ込めています。どういう悪事でどうあばかれそうになり、どうやって捕まえたのかは語られていませんが、その幽閉されているフロレスタンには妻がおり、それがレオノーレです。レオノーレは刑務所の夫を救い出そうとして男装し、フィデリオと名乗って刑務所に看守(刑務官)の助手として雇われる形ですでに二年ほど潜り込んでいます。話の骨子としては、その妻であるレオノーレ扮するフィデリオが囚われの身の夫フロレスタンを見事に救出するというだけなのですが、他にも五人ほど脇役がいて少し分かりづらいところがあります。
まずその刑務所の看守ロッコは、潜入しているフィデリオ(レオノーレ)を助手として使っているけれどもその働きぶりに感心しており、まさか女だとは思わずに自分の娘マルツェリーネといずれ結婚させようと思っています。マルツェリーネもフィデリオを男だと信じて恋していたからです。しかしフィデリオと同じようにロッコの助手をしていた同僚のヤキーノはそのマルツェリーネにぞっこんであり、求婚しては断られるということを繰り返しています。
ある日のこと、刑務所に大臣のドン・フェルナンドが視察に来るという情報(手紙)が入ります。刑務所長ピツァロが無実の人間を捕らえているという悪いうわさをフェルナンドが聞いたからでした。大臣に来られたのでは悪事がばれてしまいます。そのため、ピツァロはその前に地下牢のフロレスタンを殺して埋めてしまおうと考えます。まず部下の看守ロッコに殺させようとするものの、さすがにそれはいやだと言うので、本人がやることにして、ロッコには墓穴を掘らせます。フィデリオは何とか夫フロレスタンに近づこうと(それまで刑務所内で一度も会えていません)、ロッコを手伝って墓穴掘りを一緒にすることにし、やっと地下に入ることが出来ます。そこには衰弱して倒れてしまっている夫がいました。しかしフロレスタンは最初それが自分の妻だとは気づきません。フィデリオは途中夫にパンを与えたりしながら時間を稼ぎますが、そのうち墓は掘り終えられてしまいます。
そこへ刑務所長のピツァロがフロレスタンを殺しに降りて来ます。フィデリオは立ち塞がり、先に殺せと言って自分がフロレスタンの妻だということを明かします。ピツァロは一まとめにして二人を殺そうと剣を振りかざしますが、フィデリオは隠し持っていた拳銃を抜き、そこへタイミング良く大臣が到着してピツァロは逮捕されます。大臣ドン・フェルナンドと捕まっていたフロレスタンは以前からの仲間であり、二人は再会を喜び合います。フィデリオ(妻のレオノーレ)は夫の手錠を外します。
この話も自由を求める英雄の勝利という、ベートーヴェンの好きなテーマに沿った物語です。しかも「エグモント」とは幽閉からの解放という意味で共通しており、「コリオラン」とは解放を求めるのが女性という点で一致しています。
アテネの廃墟とプロメテウスの創造物
序曲集にいつも一緒に入っているカップリング曲として「プロメテウスの創造物」序曲と「アテネの廃墟」序曲というのもあります。それらについても触れておきます。
プロメテウスの創造物
「プロメテウスの創造物」は1800年から翌年の間に作曲されたバレエ音楽です。ベートーヴェンは三十歳頃ということで、初期の作品になります。交響曲で言えば第1番の頃です。時のオーストリア皇帝フランツ2世の皇后であったマリア・テレジアの進言によって作曲がベートーヴェンになったという説もある一方、作られた経緯は正確には分からず、バレエの台本も失われていて詳しいことは不明という状態です。脚本を書いたのは当時バレエ団を率い、妻マリア・メディナとともに欧州各地で巡業していたイタリア人ダンサー、サルヴァトーレ・ヴィガーノという人です。ベートーヴェンがこのバレエに付けた音楽については全曲録音もありますが、現在はほぼ序曲のみが演奏されているという状況です。初演はウィーンで同バレエ団が行い、評判は良いものでした。
内容ですが、ギリシャ神話で天界から火を盗み出して人間に与えたとされるプロメテウスの話から取られています。ただしそのままのストーリーではなく、それを題材にして独自の話に展開させています。以下の通りです:
プロメテウスは泥を捏ねて人形(人間を意味する)を作りました。そしてゼウスの雷鳴が轟く中で天上の火を盗み出し、その人形に吹き込んで生命を与えました。しかし人形たちには理性も感情もなく、その動きはぎこちないものでした。仕方がないのでプロメテウスはその人形たちを教育することにします。そしてその方法として、芸術の女神ミューズ(ムーサ)たちの住むパルナッソス山に連れて行き、芸術の神アポロンに頼むことにしました。パルナッソス山に着くとミューズたち(複数います)が現れ、泥の人形たちは踊ります。バレエでは団長のヴィガーノとその奥さんとのカップルによる踊りを中心に据えていました。人形たちの教育過程としてはまず、楽器の神であるエウテルペーと舞踊の神であるテルプシコラー(両柱ともミューズの一人)が、音楽に合わせて踊ることで感情の基礎を与えます。次に悲劇の神であるメルポメネー(これもミューズの一人)が悲しみというものを教えるために、彼らの親であるプロメテウスを殺してしまいます。泥人形たちは驚き、嘆き悲しみます。するとそこへ喜劇の神タレイア(ターリア/タリーア/ミューズの一人)が現れ、プロメテウスの死は遊びだったんだよと告げます。そして牧神パンの笛によってプロメテウスが蘇り、酒の神バッカス(ディオニソス)が賑やかな饗宴を開いて喜びというものを教えます。そうやって泥人形たちは人間らしくなって行きました。
このバレエの中に、当時の啓蒙思想を見るという解釈があります。人間は生まれただけでは完成しておらず、理性(と感情)をしっかりと身につけることではじめて人間となる、というわけです。上でも触れて来た通り、自由をもたらす英雄に夢中になったベートーヴェンは、フランス革命にもつながったとされるこの進歩的な考えを好んでいたことは明らかです。その意味で他の序曲たち(エグモント、コリオラン、フィデリオ)と共通する動機があります。自由を求める、英雄的行為という以外でも、女神が役を果たすという意味ではフィデリオとも共通しています。
アテネの廃墟
「アテネの廃墟」は1811年から12年頃、四十一歳前後の中期の作で、シンフォニーで言えば7番の前あたりの時代ということになります。ハプスプルクのオーストリア皇帝(フランツ2世)がハンガリーの現ブダペストに建てた劇場のこけら落とし用に上演される目的で作られた同名の戯曲があって、それに付けた音楽ということになります。劇の方を書いたのはアウグスト・フォン・コツェブーという人ですが、内容はギリシャ神話を題材として時の皇帝を褒め称えるという、バッハなんかにも見られるいかにもなものです。作曲は依頼されたからであり、上述の作品たちのように劇を見てそのテーマにベートーヴェンが感激したからではありません。ベートーヴェンは当時健康状態が悪くて湯治のために現チェコ(当時のハプスブルク領内)の温泉地に出掛けており、そこで書き上げました。
あらすじですが、物語はギリシャの知恵の女神アテナ(ミネルヴァ)の視点から描かれます。アテナは哲学者のソクラテスが裁判にかけられたとき(有罪で死刑になりました)、庇わずに見殺しにしたことでゼウスの怒りを買い、二千年間眠らされてしまいます。そして目覚めて自分の街アテネを見てみると、そこはトルコに奪われて廃墟となっていました。実際パルテノン神殿はトルコ軍に占領され、その火薬が爆発して今の瓦礫状態になったという歴史があり、そういうことを踏まえているのでしょう。劇の中ではトルコ軍が歩き回る様子も描写され、それがこの劇付随音楽「アテネの廃墟」の中でも序曲と並んで有名な「トルコ行進曲」の情景となっています。そしてアテナが途方に暮れていると、旅人の守護神であるヘルメス(メルクリウス/マーキュリー)が現れ、芸術の女神ムーサ(ミューズ)たちはすでにハンガリーへ行ったと告げ、そこへ連れて行ってくれます。するとそこの街(現ブダペストのドナウ川東岸側で、上記の劇場が出来たところ)は繁栄しており、それを見たアテナはその地のハプスブルクの皇帝の像に月桂冠を授けて賛美します。
CD ですが、今回は最初に個人的に気に入った演奏の盤をいくつか取り上げ、その後に任意に選んだものを録音年代順に並べて行こうと思います。
Beethoven Overtures
André Cluytens Berlin Philharmonic ♥♥
ベートーヴェン / 序曲集(交響曲全集)
アンドレ・クリュイタンス / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥
演奏の良し悪しについての絶対評価などあり得ないのであくまでも好みの問題ですが、エグモント序曲については特にこのクリュイタンスの演奏に以前より大変満足して来ており、今聞いてもやはり変わらなかったので最初に取り上げます。コリオランも同じ水準で良いです。
クリュイタンスは1905年生まれで67年に亡くなったベルギー出身のフランスの指揮者で、ドイツ語も堪能でした。フランスもののフォーレのレクイエムなどで評価される人だけど、ベートーヴェンも素晴らしいです。ここではカラヤンが常任に着いたばかりのベルリン・フィルを指揮しており、帝王色になる前のこの楽団の雰囲気を味わえます。ベートーヴェンの交響曲全集としてはカラヤンではなく、彼のものがベルリン・フィルで最初でした。
エグモントで見て行きます。テンポは少しゆったりめです(トータルのタイムで9分10秒ぐらいです)。落ち着きがあって堂々としており、力強さと切れの良さを十分に具えながら活きいきとした流麗な歌わせ方が見事です。オーソドックスと言えば言えるのですが、一歩ずつ拍を進める伝統の生真面目さではなく、滑らかなつなぎで呼吸のある抑揚が聞けます。しかもその歌は必要十分で作為はありません。とにかく見事です。この人のベートーヴェンは交響曲の方も素晴らしく、田園なども名演だと思います。8番は好みの演奏がなくて保留にしていたなどとそのページでは書きましたが、クリュイタンスのは軽いリズムの古楽器演奏というわけではないけれども、逆におっとりと行くことで無用にやかましくなったりしません。もちろん奇数番での構築力のある運びも良いです。硬柔バランスの取れた理想的なベートーヴェンだと思います。
そしてそのクリュイタンスの交響曲全集は現在廉価(CD一枚分ほど)で販売されており、序曲も含まれていてありがたいです。上の写真右側がその全集です。左側は今回のお題である序曲集で、タワーレコードよりリマスターされて出たものです。残念ながら今は廃盤でしょうか。このリマスターのシリーズは、例えばヘブラーのモーツァルトの旧ピアノ・ソナタ全集(Philips 原盤)などのように、オリジナルより高域をはっきりさせる編集がされていて細かなニュアンスが飛んでしまっているものと、そうなってないものとがあるようです。今回は聞けてないのでこの序曲集がどちらの組に入るのかは分かりません。
1957年の EMI の録音です。ベルリンのグリューネヴァルト教会での収録で、ステレオです。ちょっと古いながら音はしっかりしており、上記全集に関しては今現在通用する良好な音響です。50年代はカンテッリのも良かったし、案外 EMI の黄金期なのかもしれません。その昔は序曲集として一枚にまとまった LP が廉価版シリーズのセラフィムから出ており、それに関しては潤いが感じられる大変良い音でした。CD になってデジタル化されたわけですが、多少薄っぺらく痩せたというのか、ややハイが硬めに前に出た印象の音になり、個人的にはアナログのときの高域バランスの方が良かった気がして4〜7KHz あたりが出過ぎないように調整したりもしました。カートリッジと CD プレイヤーという機器の違いがあるので単純比較はできませんが、特に最初のブラスなどハーシュに感じました。これは RIAA の問題かもしれず、マスターテープ本来は CD のようなバランスに近いのかもしれません。リマスターは1995年のフランス盤(黒枠赤地の印刷でベートーヴェンのデスマスクがあしらわれているもの)が最初でしょうか。2017年の新たなリマスター盤(上記右のもの)では低音の張り出しが多少抑えられ、わずかにヒスノイズが目立たなくなって滑らかさが増したかなというところです。楽しむにあたっては最近の録音と比べてもほとんど遜色はないだろうと思います。その新しい全集についてはサブスクライブのサイトでも聞けます。その場合、イコライザーを活用できるところもあるでしょう。
  Beethoven Overtures
Otmar Suitner Staatskapelle Berlin ♥♥
ベートーヴェン / 序曲集(交響曲全集)
オトマール・スウィトナー / シュターツカペレ・ベルリン ♥♥(序曲集:左、交響曲全集:右)
こちらは1985年に CD としても出たものの廃盤になってしまい(どうしても手に入れようとすると中古のオークション狙いです)、やはり現在は全集(CD二枚分ぐらいの価格)か交響曲の第3番(コリオラン/エグモント)と第6番(レオノーレ第3番/フィデリオ)買いになってしまう序曲集ですが、文句のつけようがない演奏であり、クリュイタンス盤と甲乙付け難いベストの一つと思います。因みに6番の「田園」はクリュイタンス同様名演の誉れが高く、出た当時国内で賞も取りました。そしてこれもクリュイタンスと同様、日本では偶数番交響曲に相応しいとされる、柔な方の演奏と見られているかもしれません。確かに7番などでは柔軟に弧を描く歌わせぶりも聞かせています。これらスウィトナーのベートーヴェン、録音もデジタルになって間もなくでありながら、瑞々しくて大変良いのです。後で触れますが、あるオーディオ評論家の方が録音・演奏ともにベストと語ったことで廃盤から復活したことがあるデイヴィス盤と比べても、個人的には録音バランスとしてこちらの方が好ましく感じるぐらいで、ベートーヴェンの序曲としてこれこそ演奏・録音のベストとしたいところです。
オトマール・スウィトナーは1922年生まれ(2010年没)のドイツ/イタリア系オーストリア人の指揮者で、主に旧東側の二つの楽団、シュターツカペレ・ドレスデンとシュターツカペレ・ベルリンで活躍しました。モーツァルトも定評があります。同じくシュターツカペレ・ドレスデンの顔だったことのあるスウェーデンのブロムシュテットと比べられることもあるけれども、演奏スタイルも東側に相応しいと言われたりするオーソドックスなものでした。
エグモントですが、出だしではクリュイタンスより多少速めのテンポかなというところながら、ジェントルでゆったりとした運びです。間も十分空けて行き、力づくではないけれども正統派のスケールの大きな演奏となっています。クリュイタンス以上に解釈としては変わったことをしませんが、気合の入り方みたいな感じでテンポを部分的に少し上げたりするような表情はあり、終始厳密なインテンポというわけではありません。コリオラン序曲などではそう言う面がより出ているようです。そしてこのエグモント、ラストは転調するところから少し速くなります。そのエクサイト具合も最高です。旧東側の落ち着いたオーケストラの音を堪能できる名演だと思います。
1984年の録音で、レーベルは DENON です。デジタル初期ながら残響成分が良いことで知られているベルリン・イエス・キリスト教会で録音しており、低域が豊かで心地良い響きの優秀録音となっています。PCM のシリーズではあってもシャルプラッテンから技術者が加わっているようで、ディレクターがエバーハルト・ガイガー、エンジニアがエバーハルト・リヒターと記されています。クリュイタンスの演奏も好きだけれども、正直音ではこれにかないません。
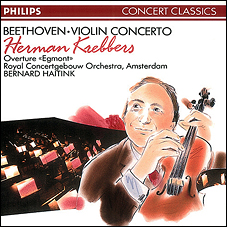 Beethoven Egmont overture
Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra ♥♥
ベートーヴェン / エグモント序曲
ベルナルト・ハイティンク / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥
 Beethoven Egmont overture
Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra ♥♥
ベートーヴェン / エグモント序曲
ベルナルト・ハイティンク / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ♥♥
今度はハイティンクです。この人も恣意的な表現に走らないオーソドックスな演奏で定評がありました。1929年生まれで2021年に亡くなってしまったオランダの指揮者です。コンセルトヘボウ管の顔で、ロンドン・フィルでも活躍しました。ベートーヴェンはやはり序曲集という形では出ていません。エグモント序曲はヴァイオリン協奏曲とカップリングになったロンドン・フィルとの1974年の録音(写真上)と、交響曲全集に含まれているコンセルトヘボウとの85年のもの(写真下)があります。
これも上記のスウィトナー盤と甲乙付け難い出来です。というか、正直なところ表現の上でどこがどう違うのかを説明するのにこちらが役不足というか、録音のコンディションと音色の違いぐらいしか分からない感じで困るところもあるのです。言い訳をさせていただけるとするなら、オーケストラの場合、ピアノやヴァイオリンといった個々の楽器の演奏と違って指揮者がそのまま弾くわけではないので、意外で瞬間的なテンポの揺れや即興的な強弱の表情などは出しようがないと言いたいところです。でも耳の良い方ならオーケストラ固有の音色の違いや団員たちの気分など、もっと感じられることでしょう。スウィトナーの方が少しだけ、部分的に速めるような表情や、フレーズの取り回しでの瞬間的なやわらかさが出る箇所などがあるでしょうか。でもとりあえず、ハイティンクの新盤は旧盤より2秒だけ短く、それよりもさらに2秒だけ短いとスウィトナーのタイムになります。テンポ設定もどれも大枠では同じで、最後に長調になって歩を速めるに至る切り替わりのタイムなど皆ぴったりと同じです。最初は少しゆったり目の運びで、ラストで少しテンションを上げて速めるわけで、特に引っ掛かるような拍節のリズムでもなければレガート過ぎることもありません。ハイティンクの旧盤は映像でも確認出来るので、その指揮ぶりを見ていると覇気のある鋭い動きをしてる分、演奏も力強い気はしますが、よく聞くと必ずしも新盤がゆるいわけではありません。どちらを選んでも間違いのない優れた演奏だと思います。
両録音ともレーベルはフィリップスで、このレーベルらしい自然な音です。旧の74年の方はライヴでアナログ収録。新盤はスタジオでのデジタル録音です。フィリップスはデジタル初期にはアナログより少し不自然に聞こえるものもあった気はしますが、これについてはそういうことはありません。どちらも良い音で、木管などは新しい方が少しまろやかかもしれず、高音の弦も旧盤の方が多少前に出るバランスのようだというぐらいです。全体には新しい方が滑らかできれいに聞こえるでしょうか。スウィトナー盤共々、オーケストラの違いを聞き比べるのに最適な気がします。より重心が低くて温かみを感じさせるという意味では個人的にはコンセルトヘボウ盤の音の方が好みかなというところです。でも違うオケでここまで同じ表現を再現させる揺るぎのなさ、逆の意味でハイティンクは自分らしさをしっかりと発揮しているのではないでしょうか。
 Beethoven Overtures
Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra ♥♥
ベートーヴェン / エグモント序曲
マリス・ヤンソンス / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ♥♥
こちらは正統派ではあっても個性的な方の演奏になるでしょう。ヤンソンスはいつも楽団から活きいきとして楽しそうな雰囲気を引き出し、わざとらしさはどこにもないのにしっかりとしたメリハリと歌を聞かせる才能溢れるリーダーでした。1943年ラトヴィア生まれで2019年に亡くなってしまいました。21年に逝ったハイティンクとともに大変残念です。
エグモントですが、ベストの一つだと思います。最初の一音のロングトーンの後で低音が区切るように動くところ、心地良く弾ませています。続くオーボエから始まる木管は艶のある音で、たわみのある歌が思い切っており、これはバイエルン放響とではないですが、やはりプレイヤーに意欲をもって自由に吹かせている感じがします。次の2分あたりから始まる速くなるモチーフのところではしっかり区切りをつけて速め、強弱も明確にしています。でも力んだ感じにはなりません。そしてそこから大きくクレッシェンドして行ってさらに一層力がこもり、生気が感じられる展開は理想的です。滑らかでやわらかく弧を描いて歌わせる指揮者というのとは違いますが、言うべきことを言う、どの瞬間も生きた音楽という感じがします。やはりニュアンスに溢れているヤンソンスは一味違うようです。
2006年のライヴ収録です。レーベルはオーケストラ自前の RCO です。自然で厚みもあり、大変良好な音響です。ただ、序曲集としてまとまったものは出ておらず、交響曲全集で聞けてしまうというのとも違います。レオノーレ第3番をバイエルン放響とやったのは出ていますが、コリオランは配信はあるものの、CD としては出たことがあるのでしょうか。このエグモントに関しても2015年発売のコンセルトヘボウ管とのライヴ集(Mariss Jansons Live, The Radio Recordings 1990-2014)があるぐらいです。サブスクライブでは聞けます。
正統派と言うことばかりが続いてしまいましたが、恣意的な表現が苦手なせいで好きなものから並べるとどうしてもこういう選び方になってしまいます。さて、ここからはほぼ録音年代順に行きます(同一指揮者で複数録音がある場合は任意のもので代表させます)。その前に歴史的名演に触れると、まずフルトヴェングラーの重々しさがあってゆったりとした1947年の録音は外せないでしょう。ファンの方は必聴だと思いますが、モノラルなのでコンディションはそれなりです。クレンペラー盤も一部で根強い支持があるでしょうか。フィルハーモニア管との57年録音で、そちらはステレオであり、歴史的とまでは行かないかもしれません。演奏については悠然としたこの人らしい運びかと思うと、エグモントのテンポは遅いものではありません。でも音を切らず、途中じっくりくっきりと一歩ずつ進めるようなところはあります。
個人的に期待した人としてはワルターもいますが、ステレオ時代のコロンビア響との録音ではエグモントがなく、レオノーレとコリオランのみでしょうか。1954年のニューヨーク・フィルとのものは存在します。チェリビダッケはどうもないようです。ブロムシュテットは廉価の交響曲全集はあるものの、序曲は入ってないようです。
 Beethoven Egmont overture
Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic ♥
ベートーヴェン / エグモント序曲
フェレンツ・フリッチャイ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥
あのフルトヴェングラーがステレオで録音した、なんて言ったら両方のファンから叱られるだろう、みたいなことを他でも言いました。それは主にフルトヴェングラー側のファンからかもしれませんが、でもそんな風に言いたくなるような、「ドイツ・ロマン主義の影を色濃く残したデモーニッシュな演奏」というのがこのフリッチャイの特徴です。病気の前と後とで演奏スタイルが変わったという人もいるようだけれども、そのあたりのことは追いかけてないので真偽は分かりません。1958年の秋に白血病の症状が現れましたから、この録音はちょうどその年の9月なので発症直前ということになるのでしょう。カップリングの第九はもう少し前だけど似たスタイルではあり、58年秋以降の録音でも同じような傾向は感じられるし、反対に最後の方のモーツァルトの大ミサなどで古典派らしい端正なところを見せている例もあることから、一概に言えないのではと思ったりもします。このフリッチャイ、その白血病で四十八歳にして亡くなってしまったハンガリー出身の指揮者で、1914年生まれで63年没です。ベルリンで地歩を固め、そこを中心に活躍しました。フルトヴェングラーよりは二十八歳年下ということになります。
エグモント序曲ですが、タイムは8分53秒なのでノイマンの新盤とほぼ同じ、クリュイタンスよりは速いもののハイティンクやスウィトナーよりは遅いです。でもテンポが揺れるのでその指標は全く意味を持ちません。影のあるエグモントです。出だしは堂々としており、最初の一音が少し長めながら速度も一般的なものです。そしてその提示が終わる最後の二音で思い切って弱音に抜くような処理が聞かれます。そして次の展開へ向かうところでうんと遅くして重い足取りになり、霧の中を歩くようです。切り替えで今度は速くなり、アッチェレランドしてさらに速くなります。ラストは猛然と、とまでは言わないとしても勢い良く走って行きます。大変聞き応えがあります。時代を感じさせると言ったら否定的に響くと思うけれども、暗さが感じられるところはベートーヴェンに似つかわしいと感じる人が多いでしょう。ぴたぴたに合わせることには重きを置かないようで、振ってから時間差で揃いながら燃えて行くような粘性を感じさせ、重厚感があります。そのため歯切れが良い方だとも言えないものの、燃焼型の演奏を好まれる方にはこれほど満足できるものもそう多くないのではと思います。
ドイツ・グラモフォン1958年のスタジオ録音で、音は大変良いです。同じ頃のクリュイタンスの EMI 盤を褒めましたが、あれより多少良いぐらいかもしれません。フリッチャイの DG 盤には良好なものが多い気がします。組み合わせはフィッシャー=ディースカウがバリトンを歌う唯一の第九です。序曲集ではありませんし、交響曲全集の中で序曲が全て揃うというのでもありません。他の盤になりますが、レオノーレの第3番とフィデリオ序曲の録音はあります。でも序曲としてはそれぐらいでしょうか。この盤以外にもエグモントとレオノーレ3とが一緒に入った「英雄」(交響曲第3番)の国内盤や、エグモントがモルダウやアイネ・クライネ・ナハトムジークなどと一緒に入ったクラシックの入門盤的な輸入盤なども存在します。
  Beethoven Overtures
George Szell Cleveland Orchestra
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
ジョージ・セル / クリーヴランド管弦楽団
セルはフリッチャイ同様ハンガリー出身のユダヤ系アメリカ人指揮者で、1897年生まれで1970年に亡くなりました。1946年に常任指揮者に就任して以来クリーヴランド管で活躍しましたが、大変厳しい練習で知られた人で、筋肉質で飾りのない端正な演奏スタイルに特徴がありました。
こちらはベートーヴェンの序曲集として出ています。その中でも定番とまでは言わないにしろ、名盤として評価されることがあります。これもエグモントで聞き比べます。
辛口淡麗な演奏です。同じハンガリー出身の上記フリッチャイとはオーケストラの鳴らし方がまるで違います。それは音の揃わせ方も全体的な表現もです。テンポは少し速めな方で、タイムはハイティンクやスウィトナーより10秒以上短い8分32秒。最初から音の区切りを短く切り、きびきびと歯切れが良くて曖昧さがありません。変わったことを一切しないかといえば、最初の楽想の区切りがつく1分44秒あたりの下降のフレーズでぐっと遅くし、次の速めとのコントラストを鮮やかに見せたりはします。ポーカーフェイスではなく柔軟性もあるのです。クレッシェンドには力がこもり、一分の隙もありません。リズムは終始小気味よく区切れて狂いがなく、フォルテは決然としています。ラストに向けてはアッチェレランドはせず、確固として走りません。きっかりとインテンポで明晰に最後まで行きます。しなやかに歌うところも見せるコンセルトヘボウ管との第五シンフォニー(運命)が見事だと思ったので、それと波長が似た曲であるこのエグモントなども個人的には期待するところですが、やはりむしろクリーヴランド管との第五の方に近い感覚かなとも思いました。欠点を見出す余地のない演奏で、評判通りの名演でしょう。
コロンビア原盤ソニー・クラシカルで1967年の録音です。音はこの時期にしては多少ソリッドな印象はあるけれども良好です。この序曲集以外にも、エグモントの劇音楽全曲の録音も存在します。
 Beethoven Overtures
Herbert von Karajan Berlin Philharmonic
 Beethoven Egmont Overture
Herbert von Karajan Berlin Philharmonic '1985
ベートーヴェン序曲集
ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
有名なカラヤンの序曲集(写真左)です。交響曲の余白ではないし、欠落曲もないしでありがたいです。カラヤンは映像やライヴを除けばベートーヴェンの交響曲全集をベルリン・フィルと三回録音しています。スピーディで端正な60年代、流麗な70年代、デジタルで入れ直した80年代ということで、それぞれに特徴があります。しかし序曲集としてまとめて録音したのは1969年だけのようです。ベルリン・フィル以外ではその前にフィルハーモニア管とも交響曲を入れており、そのときの序曲はあります(1953 モノラル)。また、70年代のにはなかったけれども、80年代の方の全集録音時にも序曲は収録しました(写真右)。それら以外にもライヴ映像があり、75年や85年のものが出ているようです。個人的には晩年のウィーン・フィルとの活動の中で素直で滋味溢れる交響曲・序曲集などを再録音してくれてればなあと思ったりもします。
エグモントです。モノラルのを除いたベルリン・フィルとのスタジオ録音の二つについては、表現の形は似ているようです。出だしは最初のロングトー ンで山を描きつつ尾を引いて減衰させる滑らかな処理を聞かせた後、そこの提示部分の区切りまではゆったりとしたテンポで厳めしく、でも荒くならないように磨きをかけてじっくりと運びます。しかしその後の展開部分からはくっきり切り替えてアップテンポで畳み掛けるように飛ばすという劇的効果を見せます。新盤の方については最速の部類でしょう。序曲なのでドラマティックにしているところもあるのでしょうか。テンポは最後までそのまま速い状態で進みます。表現上の特徴としては和音構成上の基音の低音部ではなく、上の金管の音を強調したり、飾りの音が浮き出して聞こえるなどがあるものの、新奇なことというほどで もありません。そして最後の二音でメトロノームを少し落として終わります。以上は新盤の方であり、タイムは8分ちょうどぐらいです。それを見ても快速なのが分かります。
序曲集となっている旧盤の方では管の飾りの音が目立って聞こえたりすることはなく、最後の二音でも減速はしません。でも基本的なスタイルは新盤とよく似ています。タイムは8分18 秒ぐらいで、数字だけ見ればやや速い部類ということになるにせよ、後半のスピーディな印象は変わりません。この当時、新しい時代の息吹を感じさせたエグモントだと言えるでしょう。
レーベルはドイツ・グラモフォンで、旧盤の方は1969年の録音です。写真(左側)はガレリア・シリーズの輸入盤で、序曲関係が二枚にまとまって全部入っているものです。他にも一枚ものなど、輸入・国内盤を含めて色々な意匠で出ています。また、劇音楽「エグモント」として、序曲以外の戯曲全体の音楽が聞けるものもあり、そちらも同じときの録音です。それらは60年代の交響曲全集と同じような音響で、少し硬質ながらもコンディションは良いです。新盤の方は1985年です。現代のような分解能こそないにしても、残響の豊かさによって独 特の雰囲気が出ており、旧盤よりも聞きやすいかと思います。 写真(右側)は交響曲第3番とエグモント序曲の組み合わせになっているものです。残りの序曲も聞きたければ全集ということになります。
 Beethoven Overtures
Karl Böhm Vienna Philharmonic
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
カール・ベーム / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
カラヤンと来たらベームでしょうか。ベルリンのカラヤン、ウィーンのベームで一時代を築きました。オーストリア人で1894年生まれ。年齢的にはカラヤンより十四歳ほど上にな り、1981年に亡くなっています。そのベームのベートーヴェンの序曲集、ウィーン・フィルのふくよかでやわらかい響きを味わえる一枚となっています。こう言うとウィーン・フィルはやわらかくなんかないんだ、と反論する業界の人もいたりして、オーケストラの音色について安易な表現をするのはタブーかもしれません。あくまでも録音を比較しての話です。それと、最近 はどこもインターナショナルに寄って来ているのでしょうか。でもこの頃のオーケストラ、特にベームの後年の録音ではウィーン・フィルの音色が楽しめる、と言いたくなります。
全く外連味がないというか、 自然体の演奏です。したがって気が抜けていると捉える人もいるかもしれません。ベームはチェリビダッケと同様、晩年になるとテンポが極端に落ちて来ました。ウィーン・フィルとの DG の録音はどれもゆったりとしています。このエグモントでも9分23秒ほどと、クリュイタンスよりも遅く、最もリラックスした部類でしょう。むしろ落ち着きがあって正攻法と言うべきでしょうか。
リズムについてもちょっと特徴があります。ベームの演奏は、モーツァルトの協奏曲の伴奏やウィンナ・ワルツなんかでは柔軟な拍でうっとりするのですが、伴奏部分に同じリズムが続くような曲の場合、ときにドイツ語発音的な角ばった生真面目さが出るときもあります。ミキシングの問題もあるでしょうが、それが実直な感じにつながるとも言えるので、美点ともとれるけれども好き嫌いはあるかもしれません。ここでも遅い運びである上にカラヤンのようなレガートではない結果、尖ってはいないけどどうしても途中少し四角なところ、一歩ずつ感のようなものがウィーン・フィルの典雅な響きと共存するところが聞かれます。気にならない人が多いだろうし、それが好きな方もいらっしゃるでしょう。一方でラストに向かっては少しアッチェレランドをかけて速くなります。弦の音がきれいです。
ドイツ・グラモフォン1971年の録音です。上述の通り、音は大変良いです。弦、管ともにうっとりとします。他のどの録音よりもずっと聞いていたくなるかもしれません。
 Beethoven Overtures
Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
クルト・マズア / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
1970年から96年までゲヴァントハウス管の顔だったマズアも有名な指揮者ながら、以前は東ドイツ側だったということもあってか音盤上はあまり注目を浴びて来なかったような気もします。旧東側の演奏家に共通する特徴として派手な演出をしない癖のなさも関係があるでしょうか。1927年生まれで2015年に亡くなっています。ベートーヴェンの序曲集としてはここで取り上げる70年代の録音がある他、エグモントに関しては終始安定した運びの92年のニューヨーク・フィルとのもの(8’37”/「運命」と劇音楽「エグモント」/Teldec・Apex)、同じくインテンポでティンパニが轟き、残響の抑えられた2012年のイスラエル・フィルとのライヴ(8’42”/交響曲第7番/Helicon)がある他、YouTube にはさらに別の音源がいくつも出ているようです。この曲を好んで演奏していたのでしょうか。
後発のものを差し置いて最初の頃の録音を取り上げるのも気が引けますが、マズアのエグモントに関しては70年代のフィリップスの録音が意欲的でまとまりも良く、何度も意匠を変えて音源として出続けただけのことはあるかと思います。序曲としてまとめてあるということもあるでしょう。
変わったことはしませんが、オーケストラの熱を感じられるスケールの大きな演奏です。全体は8分45秒でハイティンク盤と同じタイムであり、ややゆっくりめの中庸ということになるでしょうか。力に満ちた出だしはかなり遅めで、重々しく運びます。前奏部分の後では速くなりますが、その後はほぼ安定した速度を保ちます。途中熱が入ってさらに少し速くなったかという印象のところも出ますが、形は崩さずに熱気をぶつけて来ます。同じゲヴァントハウス管でもノイマンの旧盤よりダイナミックな感じがします。勝利に満ち溢れているかのような最後の長調部分も少し速めの同じ速度のまま進み、燃焼して結末を迎えます。これぞ力強いベートーヴェンという印象で、そういう種類の演奏で正攻法のものを求めておられる方にはこのマズア盤が最も良いのではないでしょうか。
1972年のフィリップスの録音で、多少ヴァイオリン群の強いところで倍音が薄く固まる傾向はあるものの、音響の良いドレスデン・ルカ教会での収録ということも重なって良い音です。上記写真の他にも別のデザインの CD も出たことがあり、ペンタトーンからは SACD ハイブリッド盤も出ています(未試聴)。
 Beethoven Overtures
Colin Davis Bavarian Radio Symphony Orchestra
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
コリン・デイヴィス / バイエルン放送交響楽団
コリン・デイヴィスは1927年生まれで2013年に亡くなったイギリスの指揮者で、色々なオーケストラを指揮して来ました。ここまでスウィトナーやハイティンク、ノイマン、ベーム、マズアといった、正統派でオーソドックスなスタイルの指揮者たちを見て来ました。このデイヴィスもまた、今度はイギリス紳士らしいというべきかどうかはともかく、あっさりとした歌い回しを聞かせる一面を持っている印象です。同じイギリスのマリナーとも共通するところがあると言えるでしょうか。そのマリナー/シュトゥットガルト放響の93年の序曲集は端正で落ち着きがあり、後ろの方でティンパニも燃焼するけれども、ブラスの存在を感じさせないやわらかい響きはまさにジェントルな演奏です(8’38”/カプリッチョ)。そしてこのデイヴィスの方の序曲集ですが、日本の有名なオーディオ評論家の方が褒め、録音・演奏ともに最高で、機器調整時のリファレンスなのに廃盤で残念だと発言したことで復刻されたという経緯もあります(現在はまた廃盤でしょうか)。その際、オーディオ機器を出している高級国内ブランド名で CD 化されたりもしました(上記の写真)。
走るところはなく、一つひとつのフレーズを確実に処理して行く演奏です。最後までインテンポで、ラストに向けて燃えて行くかどうかという点ではマリナーよりさらにジェントルな運びとも言えます。オーソドックスで、どの部分も完璧丁寧に扱う文句のつけようのないパフォーマンスです。トータルの演奏時間は9分04秒で、クリュイタンスよりは6秒速く、ハイティンクよりは20秒近く遅いタイムです。ゆったりした方だと言えるでしょう。
1985年の CBS 原盤ソニー・クラシカルです。上に掲げた盤は元のものとジャケットの顔写真は同じですが、露出と枠の色が異なるエソテリック名義のものです。前述の評論家の方の意見でその当時買ってみました。ミュンヘンのヘラクレス・ザールで収録されたもので、明晰ながら自然な艶と潤いもあります。フィリップス系のワンポイント的なやわらかい音場型のものではなく、デッカなどでも聞かれたような、分解能があって各楽器がくっきりとする方向でしょうか。レコーディング・プロデューサーは EMI で仕事をして来たデイヴィッド・モトリー、オルフェオの録音があるウォルフラム・グラウル、エンジニアは同じく EMI のマルティン・ヴェアとなっています。確かに良い録音だと思いますが、他に類を見ないほどかどうかは専門家ではないのでよく分かりませんでした。その評論家の方が褒めるオーディオ機器は自分の好みではなかったし、結局こういうことは好き嫌いの問題なのだろうと思います。
 Beethoven Overtures
Claudio Abbado Vienna Philharmonic
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
クラウディオ・アバド / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ベームに続いてのウィーン・フィルですが、今度はアバドです。ご存知イタリアの名指揮者で、1933年生まれで2014年没。イタリアなので歌のアバドなどとも言われますが、そんなに単純ではなく、時期や曲によって色々な顔を持ってた人という印象があります。その通りのカンタービレもあれば無機質なほどのゆっくりもあり、反対に速いこともあったしピリオド奏法に目覚めたりもしました。
エグモントですが、出だしのみゆったりで、途中から速くなり、そのままずっと快速を保つ運びとなっています。不思議な表情はありませんが、そうしたテンポ設定が意欲的であり、他の伝統オーケストラの正統派演奏とは違って指揮者の意図を感じさせます。カラヤンもちょっとそんな構造ではあったけど、ああいう滑らかな当たりの処理に特化した印象ではなく、滑らかに弱音へと落として声をひそめるところでは歌の要素があるとも言えるけれども、構えた感じにはならないし、ことさら外連味があるというほどでもありません。速く走って行くところはしっかり燃焼しているという風情で、トータル・タイムは7分57秒と、最速かと思ったカラヤン新盤より3秒短いです。そしてラストに向けてもひたすら走って行きます。最後の最後で、フルート・パート(ピッコロ)の飾りの部分が鳴り響くホイッスルのように浮き出して聞こえますが、録音バランスだけの問題ではないかもしれませ ん。何か強調の指示があったとしたら唯一工夫がある部分ということになるでしょうか。ベームのようにゆったりとしたものではなく、気合いの入った状態でウィーン・フィルの音が楽しめる贅沢な一枚となっています。
ドイツ・グラモフォンの1987年録音です。コンディションは良好です。アバドは劇音楽「エグモント」として、序曲以外の残りの曲全部が入ったアルバムも出しています。ソプラノが歌ったりするのでオペラみたいでもあるけど、全体がどういうものだったかが分かります。最後の曲として序曲の終わりの部分が使われたりしています。
 Beethoven Egmont and Coriolan overture
Carlo Maria Giulini La Scala Philharmonic Orchestra
ベートーヴェン / エグモント序曲 / コリオラン序曲
カルロ・マリア・ジュリーニ / スカラ座フィルハーモニー管弦楽団
アバドと同じくイタリアの指揮者であるジュリーニですが、ドイツ語圏のイタリアで過ごしたことがある人で、ドイツとイタリアの特徴が聞かれるなどと言われます。かっちりしたところと歌の要素との両方が存在するということでしょう。1914年生まれで2005年に亡くなりました。しっかりと構築された感のある大変遅い演奏でも知られました。ここではイタリアの歌の殿堂であるスカラ座のオーケストラを振っています。序曲集ではなく、田園にエグモントとコリオラン序曲がカップリングされています(上の写真)。全集にも序曲は入っています。
全体で9分35秒かかるという、最大遅いかと思ったベーム盤よりも12秒遅い演奏のエグモント序曲です。最初のロングトーンの後は歯切れが良く、序の部分の前半では必ずしも遅い演奏だとは感じさせません。でもその後は終始ゆったりとしており、この人らしい展開となります。滑らかなレガート処理ではなく、くっきりと拍節を区切る運びで、一つひとつの音に力がこもります。極めて丁寧な進行であり、「分解的」と言われる手法でしょうか。ミラノ・スカラ座だから歌うようにというのとは違います。そして最後の最後までその遅いテンポで通します。大変個性的です。一歩ずつ進んで行く雄大な音楽です。熱いファンも存在します。
1992年録音のソニー・クラシカルのセッション録音です。エグモントは他にも70年代のニュー・フィフハーモニア管との EMI 盤や、フィレンツェ五月祭管弦楽団による1984年のライヴ盤などがあります。
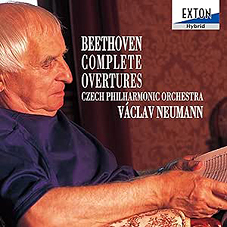 Beethoven Overtures
Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra ♥
ベートーヴェン序曲集(交響曲全集)
ヴァーツラフ・ノイマン / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 ♥
チェコ・フィルのノイマンです。チェコ人の泣き節があるかというとそんなこともなく、弱音に落とすときによく延ばして歌う傾向はあるけれども正統派の演奏です。ノイマンは1920年生まれで95年に亡くなっていますので、ここでの演奏はその一年前ということになります。最晩年の境地と言えるでしょう。チェコ・フィルの指揮者の中では歌うクーベリックのようには亡命せず、前任のアンチェルのように抑制された中に独特の寒色の美を描き出すというのとも違い、柔軟によく歌うながらも羽目を外さず、安心してこの楽団の音に身を任せられる人、という感じがします。演奏解釈の点では♡♡です。
エグモントは中庸やや遅めのテンポです。遅い方のハイティンクより5秒遅く、クリュイタンスより18秒速いと言ったら果たして了解可能でしょうか。特に走ったり立ち止まったりはありませんので、形の上ではそれらと同じようだとも言えますが、間をちゃんと取るところに落ち着きが感じられます。フォルテで立ち上がる音が頭から揃ってどんと来ず、弧を描くせいで丸みが出るようなところもありますし、後半三分の一あたりで弾む金管に独特の音程感が出ておやっと思う瞬間もあります。取り直し編集などしない方が自然かもしれません。柔軟自在な運びであり、指揮者が晩年であるせいか、やわらかく慈しむような歌の味わいも出ている気がして大変魅力的です。
1994年の録音で、レーベルは日本のオクタヴィアです。全体にはやや引き気味の音場ながら華やかな倍音成分とリヴァーブのかかったようなリッチな残響が聞かれます。その艶と反響の乗り、楽器の距離感においてわずかに個性的ながら豊かな音響です。これよりも前にノイマンはチェコ・フィルではなく、ゲヴァントハウス管♡とも序曲集を録音していました。そちらは1968年収録の東独エテルナ原盤で、テルデックになって Apex の廉価版も出ました。表現は変わらないけどもう少し引き締まり、これぞより正統という感じでテンポは新盤より30秒ほど速いです。したがって中庸ではあってもゆったりの方ではありません。若さが感じられ、むしろ颯爽とした演奏と言えるでしょうか。適度に残響があり、新盤のような艶の成分はなく、この時代に共通した高音弦の固まり傾向はあるものの破綻のない良好なバランスです。音場としては新盤よりナチュラルかもしれません。ただしコリオラン序曲だけはノイマンではなくカイルベルトの指揮となっています。最初のテーマ提示では歯切れ良く切る一方で、全体にずしっと重みのある演奏です。残響はあるものの少し抑えられ気味にも聞こえて音響的にシックなところがあり、それ以外の曲とは異なっています。
 Beethoven Overtures
Nikolaus Harnoncourt Chamber Orchestra of Europe ♥
ベートーヴェン序曲集
ニコラウス・アーノンクール / ヨーロッパ室内管弦楽団 ♥
古楽運動の旗手、アーノンクールがモダン・オーケストラながらピリオド奏法で演奏したものです。この人も2016年に亡くなってしまいました。1929年の生まれはドイツながら、オーストリアの貴族であり、オーストリアの指揮者です。バロックや古典派の音楽においては、角のあるリズムに加えてブラスとティンパニで畳み掛けるアグレッシブな古楽解釈に定評がありました。でもベートーヴェン以降の曲では柔軟な姿勢を見せ、ロマン派作品などでは大変よく歌うところもありました。あのラトルもピリオド奏法の極意を教えてほしいと頼んだという話があります。このロンドンの若者のオーケストラ、ヨーロッパ室内管とのベートーヴェンについては、交響曲では5番も6番も意外なほどの柔軟な歌を聞かせ、その節回しも独特でありながら洗練されていました。匠という感じです。ここでの序曲は軽快で歯切れの良いホグウッド盤よりは後ながら、ピリオド奏法によるパフォーマンスに先鞭をつけた形でしょうか。
エグモントのタイムは8分05秒なのでカラヤンの次ぐらいに速い方になります。でもこれはピリオド奏法的な解釈という点では驚きではないでしょう。最初のロングトーンの後の低音弦二音は力まず、強面ではないぞという始まり方です。その後の拍はよく区切られていてリズミカルに弾みます。ノン・ビブラートの透明な音はやはり特徴的で、アンサンブルが揃っていることと残響の少なさが合わさって人数があまり多くないような印象を与えます。でもそれは室内管だから実際に少ないのでしょう。フレーズの尾部をあまり延ばさない処理もピリオド奏法的ながら、尖った感じには聞こえません。かといって、小人数のピリオド奏法だからベートーヴェンらしい迫力に欠けるというわけではありません。結構激しいところもあるし、最後はかなりまくります。そしてそんな激しさはあるけど、どこか優雅な丸みも感じさせるところがこの人のベートーヴェンらしい面白さなのです。歌わせ方が繊細なのでしょう。そのやわらかな物腰の歌と歯切れの良いリズムの組み合わせが巧者な印象を与えます。他の人には真似出来ない演奏だと思います。
テルデックの1994年の録音です。序曲集として出ているのは国内盤だけでしょうか。もちろん全集には収録されています。残響はさほどないと言いましたが、潤いはあります。弦もバロック・ヴァイオリンではないけど、揺れのない透明さは独特の音として魅力があります。モダン・オーケストラの分厚い音を聞き慣れていると不思議な印象かもしれませんが、大変良い音です。
 Beethoven Overtures
Daniel Harding Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
ベートーヴェン序曲集
ダニエル・ハーディング / ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン
ダニエル・ハーディングは1975年オックスフォード生まれの指揮者で、ラトルのアシスタントとしてバーミンガム・シティ・オーケストラでデビューしました。パリ管やスウェーデン放響の芸術監督などに就いたりしましたが、エールフランスの商業路線のパイロットとしての顔も持ち、エアバス機の副操縦席に座っている写真なども見ることができます。パイロットとしての経験は指揮者として人間に指示を与えるよりも対応に迫られることが多く、学ぶことも多いのだとか。分野の異なる操縦のプロとして面白い経歴です。ドイツ・カンマーフィルではパーヴォ・ヤルヴィの前任者として1999年から2003年まで音楽監督でした。このハーディングによる序曲集は上述のアーノンクール盤と並んでモダン楽器のオーケストラによるピリオド奏法の演奏ということになります。
切れの良い演奏です。二十三歳のときの収録ということで、カラヤンやアバドより速いテンポで7分35秒という快速急行のエグモントとなります。古楽系としては比較的新しめだけど、スタイルは典型的なピリオド奏法ということになるでしょうか。「カンマーフィルハーモニー」は室内管弦楽団であり、ノン・ビブラートと相まって透明な響きを聞かせます。アーノンクール同様に最初のロングトーンの後の二音は短く、弾んで切れのある拍節、強拍と弱拍を交互に組み合わせるような浮き沈みのあるリズムには軽さが感じられます。一方で合間にしなりのある柔軟な歌を聞かせるアーノンクールの個性とは異なっており、終始きびきびとしていて颯爽とした運びです。大型のエアバスというよりはビジネス・ジェットのようでしょうか。古楽系らしい鋭角直線的かつ瞬間燃焼的なフォルテが聞かれます。ラストも軽快な走りで締め括り、力強いながら大変爽やかです。
ヴァージン・クラシックス1999年の録音は残響がやや少なめの直接音寄りで、端正な演奏を引き立てます。 編成が大きくなくてピリっとしたこのパフォーマンスに相応しく、明るく輝きのあるモダンな好録音です。
 Beethoven Overtures
Paavo Järvi Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ♥♥
ベートーヴェン序曲集
パーヴォ・ヤルヴィ / ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン ♥♥
1962年生まれのエストニア出身の指揮者パーヴォ・ヤルヴィは、同じく指揮者であるネーメ・ヤルヴィを父に持ちます。ラトヴィアのアルヴィド・ヤンソンスに対するマリス・ヤンソンスみたいな二世指揮者ながら、どちらもお父さん何だっけと思うぐらいに子供の方が有名ではないかと思います。パーヴォはアメリカで学び、多くの米人指揮者の指導を受けました。ドイツ・カンマーフィルでは前述のハーディングの後を受け、2004年から芸術監督の地位にあります。日本の多くのオーケストラも振り、そういう運びになるとは思わなかったので驚きました。この人も前任者と同様、モダン楽器ながらピリオド奏法であり、部分的には古楽器仕様のものもあります。ベートーヴェンに関しては新しい印象の「運命」に圧倒されました。大変歯切れが良くて趣向が凝らされているように聞こえ、でもベーレンライターの新版に忠実ということなのでどうなっているのだろうと思ったものです。人気のクライバーよりも個人的には衝撃が大きく、その「運命」と似た波長を持っているエグモントなどは大変期待しました。この盤は序曲集ですが、交響曲集の録音より後に出ました。
「運命」のときと同じように、やはり大変魅力的な演奏でした。ただし♡♡にしたことについては多少の躊躇はありました。好みの度合いに過ぎないことなので迷う必要もないはずだけど、それはエグモントもコリオランも基本は悲劇の要素を感じさせるところのある曲であって、出だしなど厳めしいと理解していたのに、聞いているとなんだか楽しくなってしまうからです。楽しいというと語弊があるでしょうか。歯切れ良く、乗りがいいのです。「運命」の記事でも同じことを書いたと思いますが、スポーツのような爽快感があり、こういう曲だっけか? となります。スポーツといっても競技での勝つか負けるかぎりぎりの真剣勝負ではなく、趣味の領域であり、格闘系でもなく乗りこなし系というか、例えば乗馬のギャロップで全速力になったとき、スキーで膝を屈伸しながらこぶを飛び越えているとき、上手く乗れて来た瞬間に思わずふっと笑みがこぼれてしまう、そんな感じです。オーケストラですから指揮者一人が楽しいわけではないでしょう。それなら団員たちが喜んでるのか。きびきびしてるといってもジョージ・セルのピリピリ感とは違うようです。この人は日本の有名オーケストラをいくつも指導してるので、そこらへんに関しては誰かが現場の雰囲気について書いてるかもしれないけど、知らないのでジャケットで真顔のヤルヴィを眺めます。どことなく目もとが肖像画のナポレオン皇帝のようでもあり、謎に微笑んでるモナリザのようでもあります。怖い顔なのか笑顔が似合う人なのか分かりません。聞いての楽しさはこちらの感情移入でしょうか。亡くなったマリス・ヤンソンスの演奏も団員が自発的で楽しんでいる雰囲気がありました。現代は昔の権威主義指揮者の時代ではなく、そういう傾向かもしれないけど、とにかくヤンソンスよりもスポーツしてるのです。エグモントについてはある程度予想してたのでさほど驚かなかったけれども、他の序曲たち、コリオランもフィデリオも、最初のプロメテウスもみな楽しく乗れてしまい、意外性に満ちています。
具体的にはどうでしょうか。エグモントですが、7分54秒なので、同じピリオド奏法である前任者のハーディングよりは20秒ほど遅く、アーノンクールよりは10秒ほど速いタイムです。最初の長い音の後で低音弦が二度区切るところから、やはり短く歯切れます。ハーディングも語尾を短く切るのは同じながら、こんなに毎回ゴムボールのようには跳ねないし、もう少しポーカーフェースです(リズムに強弱をつけて弾ませる箇所はあります)。真っ直ぐな金管、ノン・ビブラートの弦、透明感などはピリオド奏法に共通しています。でも切れが良いのに切羽詰まった感じはしません。心地良く弾んで進み、そのリズムをつなぐ歌には柔軟性があります。かといってアーノンクールのように滑らかに弧を描く歌とも少し違います。特徴的なところとしては、古楽器の類であるらしいティンパニの乾いた切れのある音が目立ち(バチが硬いものだそうです)、連打が雷鳴のようです。それと、ほとんど終わりの部分(322小節目/7分17秒前後)で、ピッコロが金管にかき消されずに浮き出すところには耳が行きます。こういう趣向は「運命」でも聞かれたし、他の演奏者でもここまでじゃないけどアバドなどは似ています。そして「運命」のときよりも少しリラックスしているでしょうか。あるいは同じぐらいかもしれないながら、全体を通して聞いていて気分が良くなるのでそんな気がしました。
RCA 2010年の録音です。音は大変良いです。透明だけど艶消しといったら言葉の矛盾になりますが、弦が艶々とし過ぎないのはモダン・ヴァイオリンをノン・ビブラートでやっているからでしょう。そういうものでもバランスによってはバロック・ヴァイオリンに近く聞こえる場合があるものの、この録音はそこまで硬質ではありません。低域は引き締まっていて弾力があります。被らないけど真っ直ぐに消えて行く適度な残響が心地良いです。カップリングとしてはいつもの曲たちに加えて「献堂式」序曲 op.124 も入っています。
ただし、販売サイトによっては扱ってないところもあるようです。輸入盤は廃盤なのか、安い価格に落ち難いみたいだし、海外でも格安中古は非英米の一部の販売者にしか見当たりませんでした(「英雄」にコリオランとエグモントが入った日本独自企画盤というものは存在しており、それだと安価な中古も存在するようです)。また、サブスクライブのサイトに関しても老舗のスウェーデンとフランス発の配信元にはなく、YouTube にもない状況であり、大手 MP3のダウンロードが見つかるぐらいです。ソニー・クラシカルと同じ資本提携ではあっても著作権保護に対する日本市場独自の考え方に関係しているのでしょうか。'Under license to Sony Music Japan International' となっており、Sony Music Entertainment とは扱いが違うようです。購入前に確かめられるとありがたいし、それが出来なくてこの人たちが聞かれないことになったら気の毒な気もします。
 Beethoven Overtures
Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
ベートーヴェン序曲集
グスターボ・ドゥダメル / ベネズエラ・シモン・ボリバル交響楽団
ハーディングよりも若い世代、1981年生まれのベネズエラの指揮者、ドゥダメルです。そして本拠地ベネズエラのシモン・ボリバル交響楽団の演奏です。この楽団は1999年創立で、ストリート・チルドレン更正のために組織された少年オーケストラの青年部ということになります。ドゥダメルは創立当初の十七歳から音楽監督として指揮をしており、バンベルクのマーラー指揮者コンクールに優勝して有名になりました。起伏の大きな大変意欲的な演奏をする人です。このアルバムは序曲集ということではなく、交響曲第3番「英雄」とプロメテウスの創造物序曲、そしてこのエグモント序曲の組み合わせです。
最初の一音のロングトーンが長く、力強くゆっくりと入ります。序の部分は遅く設定し、展開から少し速め、思い切ってクレッシェンドしていてスケールが大きいです。展開部分では軽やかに跳ねるようなリズムも織り交ぜ、表情があるし、柔軟さも見せます。フォルテの切れという意味では古楽系のような軽さはなく、ずしっとした重量感を感じさせます。後ろの長調に転じるところからエクサイトする感じもしっかりとあるけれども、走って行くという扱いではありません。9分丁度というタイムで、ベームやクリュイタンスよりは短いけれどもハイティンクやスウィトナーよりは15秒ほど長い、デイヴィス盤と同じぐらいのゆっくりな方になります。この指揮者は熱血な雰囲気を醸し出し、ときに派手に表情を設定して外連味を感じさせる曲もあったりする印象ながら、このベートーヴェンの序曲では良い意味でしっかりとした熱気のみがあり、やり過ぎ感の強い爆演かもと思うのは取り越し苦労でした。老練な伝統のオーケストラが圧倒的な技量で畳み掛けて来るという種類ではないとしても、堂々とした見事なエグモントとなっています。熱い演奏を探しておられるなら、形は違うけれどもフリッチャイやアバド盤と並んで是非これを選んでいただきたいと思います。「英雄」の方はエネルギーを感じる若さのある運びです。緩急強弱の表情が濃くてしっかりしており、第二楽章の葬送は情緒たっぷりで遅く粘り歌う雄渾なものです。セッションでもライヴのような燃焼を見せており、好きな方にはこれ以上のものはないでしょう。
|

