バッハ / イギリス組曲 イギリス組曲について 組曲集の体裁をとるバッハのクラヴィーア(ピアノ)作品はイギリス組曲、フランス組曲、パルティータ(それに加えて単体の組曲としてはフランス風序曲)で、イギリス組曲はその後世の人のネーミングからフランス組曲と対になるかのように思われています。ただ、フランス組曲が比較的構成が完結で弾きやすく、感性的なメロディーに溢れているのに対して、イギリス組曲の方は組み立てが堅固でより厳しい雰囲気があるとされたりもします。でも聞いてみれば分かる通り、決して馴染み難い曲ではなく、むしろ美しい調べに、何かをしていたとしても思わず手をとめて感じ入るところが無数にあります。堅いというのは曲調のことではないのでしょう。名作です。 構成としてはプレリュード(前奏曲)が付いて五つの舞曲が並ぶ形の六曲による組曲となっています。 名前の由来 「イギリス組曲」という愛称ですが、伝記作家と息子のクリスチャン・バッハによって伝えられた「イギリス人のために作曲」という文言によってそう呼ばれています。それが誰かなど、詳しいことは何も分かっていません。ただ、筆写譜の記号の書き方がイギリス式であるようです。 作曲時期 フランス組曲と対のように思われるという話ですが、近年の研究によると作られたのはフランス組曲より前で、第1番はワイマール時代(1708-1717)の1712年頃、そして残りは恐らく13年から14年ぐらいに書かれ、1710年代の後半には最初の形は出来上がっていたとされます。推敲されたのはその後で、世俗作品の傑作が目白押しであるケーテン時代(1717-1723)であり、それはフランス組曲と同じ頃です。したがって主には二十八歳から二十九歳頃の作ということになるでしょうか。バッハの鍵盤作品としては早い時期にあたり、これより前で有名なものには十代だったと思われるカプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」があるぐらいです。でもバッハは早熟だったので早い時期から作品は完成されています。カンタータなどを通しで聞いてみても分かりますが、ワイマール時代には美しい調べのものがいくつもあります。 演奏について / シフ、アンデルシェフスキとバッケッティ バッハのピアノ曲に関しては、今や権威ともなったグールドの登場以降、演奏者はある種何でも出来る自由を獲得したと言えるかもしれません。バッハの時代はピアノについてはその前身があったぐらいで、バッハ自身がその新楽器にどう対応していたかは議論を呼んでいるにせよ、一般的には音量差の出ないチェンバロで演奏するのが普通でした。したがってチェンバロで弾くなら、当時どう弾いていたかという音楽史的な奏法の解釈を無視できないでしょう。一方でモダン・ピアノでバッハを弾くなら、そこには最初から音の強い弱いに対する規範が存在しないとは言えます。楽譜に強弱の記号はありません。でも音量差が出せるクラヴィコードという楽器は当時からあって、バッハはそれでよく弾いていたということですから、彼の頭の中に鍵盤曲に関する音量差のイメージがなかったとは言えないかもしれません。つまり現代ピアノでどういう風に抑揚をつけようか、ということは大変スリリングな問題なのです。超速のゴールドベルク変奏曲などによって、グールドはそこに積極的に新しい可能性を見出したと考えてもいいのでしょう。そしてそれによって表現の幅を獲得した数多の現代の弾き手の中から気に入ったものを選ぼうとすると、それはそれで贅沢な試練となります。 ポスト・グールドということで外せないのは、やはり評判通り、ゴールドベルク変奏曲のところで触れたアンドラーシュ・シフでしょうか。あの覚醒した瞑想状態は魅力的です。愉悦を感じさせる自在さがあり、同時に恣意的なプレイというわけではなく、真摯なのは他にない個性です。 それ以外ではアンデルシェフスキーとバッケッティも魅力的でした。この二人は色々な縛りからかなり自由な感じがします。大変現代的かつ非凡で、シフよりは演奏者の側に引き付けるような要素があるかもしれないけれども、目立ちたがり屋なだけではありません。今回このページでは彼らの盤を中心にして、他のプレイヤーも少し交えてバッハの代表的なクラヴィーア曲であるイギリス組曲をまず最初にここで、続けてフランス組曲、パルティータ、イタリア協奏曲などをそれぞれに分けて比較してみようと思います。CD はリリース年代順にはしませんでした。 ピョートル・アン デル シェフスキは1969年生まれのポーランド/ハンガリー人。アンドレア・バッケッティは1977年生まれのイタリア人です。年齢は少し離れているけど活躍を始めた時期はほぼ同じ頃で、シフ同様どちらもコンクール歴が華々しいというわけではありません。モダン・ピアノでのバッハ弾きとして、今最も注目しています。 明らかに天才肌のバッケッティはときにトリックスターのようです。ゴールドベルク変奏曲など正にそれで、すでにそれについては書きました。もちろんゴールドベルク変奏曲自体が、指揮者にとってのヴィヴァルディの「四季」がアーノンクールからビオンディに至ってそうなったのと同様、グールド以降にあっては演奏家がその個性を発揮するための舞台になって来たという事情もあります。冒険をしてもいい曲なのです。したがってバッケッティ自身もそれ以外の曲ではもう少し節度があり、とくにフランス組曲ではゆったりしっとりと抑えて進むところも あります。でもどんな場合でも単調には陥らず、自分の中で音を転がして楽しんでいるようです。伝統的な感情表現とは違って悲しいとか憂いとかはスルーしてるところはあるかもしれないけど、情感はしっかりとあってしんみりと伝わってくる部分も感じられます。独特の拍の動きは考え抜かれて自然というか、そもそも考えてのことではない生来のリズム感覚なのでしょう。 一方でアンデルシェフスキはどうかというと、ディナーミク、アゴーギクの面ではどうかするとバッケッティより大胆かとも思えるところがあり、特に弱い音で弾くときの徹底した静けさはこの人の特徴で、ここまでするのかと思います。その結果抑揚のダイナミックレンジが大きくとれてるにもかかわらず、むしろバッケッティよりもしっとりとした情緒的な感じがしたりもします。そしてそれでいてロマン派的な思い入れとは違って聞こえるので、やはりバッケッティ同様重たい感情の押しつけには至らず、自由を感じさせます。  Bach English Suites Nos.1-6 BWV 806-811 Andrea Bacchetti (pf) ♥♥ イギリス組曲全曲 BWV 806-811 アンドレア・バッケッティ(ピアノ)♥♥ 見た目が個性的なピアニストだと言われる場合もあるようです。インタビューを見るとちょっとがやがやした高い声で答えています。落ち着かない様子でときどき鼻を触るのは、自慢は出来るけれども自慢げに響くのは恥ずかしいということでしょうか。大変繊細でアイディアに溢れ、自分の感覚を大事にしている人だということはその様子からも窺える気がします。弾いている姿は首を伸ばした猫背であり、ちょっとグールドを思い出させるところがあって、喋るとき同様に左右に揺れています。反抗的なゼスチャーには感じられず、心の中の音を楽しんでいるのでしょうか、自分の世界に浸っているみたいです。弾きながら楽しそうな表情を見せることもあります。挨拶のときに胸の前で手を組んでちょこんとお辞儀をする様も謙虚さと自信が表れていてチャーミングです。 では、その演奏はどう表現したらいいでしょうか。歯切れ良くリズムに乗せてくれ、同時に溺れることのない繊細な情緒を味わえるものです。 ゴールドベルク変奏曲では透明でくっきりしたエッジの音が次の音を押して、前後の音符が独特の関係を結んで伸び縮みしていました。リズム感の良さはジャズのようです。ここでも音の粒立ちがくっきりしているのは同じで、グールド以降の世代というのか、スタッカートを上手に使います。それは片方の手のみがスタッカートだったり、繰り返しに入ると部分的に弾ませたりという自在な使い方で、こなれています。しかしばりばりと前のめりに速くなったりするような豪鬼さを感じさせるところはなく、ニュアンスがあります。弱音への静まりは特に美しく、アンデルシェフスキーの自在な感情の揺れよりは安定しているけども、十分に情緒的であり、感受性の豊かさでは同等という感じがします。 たとえば3番サラバンドの中ほどあたりの静かなパートで感じるのは、イタリアの音楽家にはよくあることだけど、晴れた日の夕暮れの影が濃いとでもいった風情です。ゆっくり大きく歌うのにどこか直線的で湿り気がなく、フランス流儀のようなしなを作るやわらかい抑揚でもなければ、ケンプのような枯れた達観とも違います。でもそれがまた大変美しいです。 面白いのはこの人には引き出しがたくさんあるようだということです。前述の通りゴールドベルク変奏曲では大変趣向を凝らした演奏を聞かせてくれたのですが、あれが毎度のことかと思いきや、この組曲では全体にもっと落ち着きがあります。といって録音ゆえのスタジオの冷静さということでもなさそうです。この曲集もフランス組曲もだけど、しっとりとした情感をたたえる部分では落ち着いた美しさを味わえます。でもコンサート映像を見ると、これらの組曲集でもゴールドベルクのときと同じようにはじける演奏をしてる様子も見受けられます。そっちを高く評価する意見もあるようだけど、2007年ライブのフランス組曲ではスタッカートが強調され、トリルもエッジが際立っており、抑揚も大胆です。それならばより若い時はそんな具合で、後になると静かになる方向なのかというと案外そうでもなく、イギリス組曲は古いですが、フランス組曲はゴールドベルク変奏曲より後です。 ピアノの違いもあるのでしょうか。コンサートではスタインウェイだけど、CD ではイタリアの新進ピアノメーカーであるファツィオリを弾いています。歴史が浅くても世界一高価であり、ジュリアードにも納入されたというものです。このバッケッティに関してはレーベルの異なるイギリス組曲とフランス組曲の録音で同じ傾向が感じられることから、共通した音の特徴はあるようにも思えます。ニューヨーク・スタインウェイのように強打で金属的になったり華やかな倍音が乗る感じではなく、透明感のあるすっとした音です。シフが好んで使うスタインウェイを改造したファブリーニも倍音の静けさでは似た感じがあるところから、こういう高域の響きを求める流れもあるのかもしれません。独特の艶はあるものの、ベヒシュタインの粒立ちと濡れた艶とも違うようだし、軽く明るさがありながら金属的な倍音は含まないベーゼンドルファーとも違うみたいです。この音を聞いていると純粋なトーンが鳴り止まって行くときの余韻を聞きたくなるけれども、ひょっとしてバッケッティもそんな減衰音を味わってゆっくり弾いてるのかな、とも想像しました。こうして抑制気味に弾かれると、却ってピアノの美しい響きに耳を傾けることができます。 考え過ぎでしょう。この人は次から次へと弾き方のアイディアが湧いて来るのでしょう。どんな弾き方も出来ることを見せ、バリエーションを楽しんでるような気がします。そしてこのイギリス組曲、曲自体がフランス組曲と比べてより構築的とされるものの、しっとりした旋律美の要素もたくさん聞かせてくれる曲でもあり、色々言いましたが、トータルではこの演奏、イギリス組曲の多くのパフォーマンスの中にあっては大変歌のある、ゆったりした面を聞かせる方に入ると思います。そういう意味でこの曲集を聞いていて心地良いものベストと言えます。 録音は2005年、レーベルはデッカです。しかし今現在、CD としては廃盤扱いなのでしょうか。ダウンロードは可能ですが、MP3 レベルだと最高でも 320Kbps と CD の情報量の23%ほどになります。最近は CD レベルのサブスクライブのサイトも出て来ました。Spotify にも Deezer にもあります。音のバランスは大変良いです。再販するか新録音を出してほしいです。 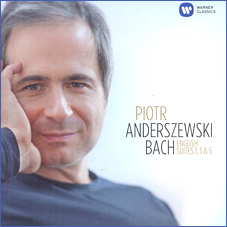 Bach English Suites Nos.1, 3, 5 Piotr Anderszewski (pf) ♥♥ イギリス組曲 第1番、第3番、第5番 ピョートル・アンデルシェフスキ(ピアノ)♥♥ バッケッティとはまた違った印象です。最初に耳に飛び込んで来るのは装飾音が大変繊細だということです。そして速いパートではさらっと速く、バッケッティのように一音ずつを際立たせる間を意識したような種類ではな く、師のペライアにも近いような、もっと連続的につながって変化する抑揚がつきます。それがまた大変敏感に変化して細かく波打ち、生きい きとしています。よくここまで緻密な表情が付けられるものです。さらにバッケッティと比較するなら、どちらも大変心地良く音楽に乗れるのだけど、バッケッティがリズムに乗る感覚なら、こちらは波に乗る感じです。小刻みにボルテージが変化するので、マイルドなジェットコースターに乗るような揺られ心地です。しかもジェットコースターが次に右へ曲がるのか左へ曲がるのか時々分からなくなるように、その表情の付け方には安易な予測を拒む面白さがあります。 静かなパートでは音がデリケートで、もしも演奏記号が付いているのなら、ピアノはもう一段低いピアニシモで弾いているような静けさがあります。この弱い音の徹底ぶりはバッハの時代の縛りから解放されており、そんなパートではテンポも大変ゆったりになったりします。ソフトで流動的な表情が付き、常套句的ではないものの情緒的です。その点については彼が演奏している姿を見れば一目瞭然です。音を聞きながら心を込めて弾いているようです。人差し指一本だけを残して他の指を握り、何かを指差すような格好で滑らせて手前に引いたりする面白い動きも見られたりするけど、鍵盤をやさしく撫でるような弾き方で、バッケッティ同様体を左右に振りふり、陶酔した表情を見せます。東欧系の人なので、チェコ人などにありがちな泣き系の歌謡性かとも考えましたが、それでいて感傷に浸る音にもならないのは現代のピアニストだな、と思わせます。元々たっぷりと情感に酔うような素質が年齢とともに洗練されて来たのでしょうか、独特の知的なセンスが合わさっています。 このピアニストは CD リリースを見る限り、今のところ系統立って全集を出して来ることがなさそうです。今後全曲録音となるのかもしれませんが、イギリス組曲は1 番、3番、5番が一枚で出ているのみです。ワーナー2014年の録音です。弾き振りでモーツァルトのピアノ協奏曲も少し出していて、そちらも魅力的なので、両者ともに未収録曲のリリースが待ち遠しいところです。 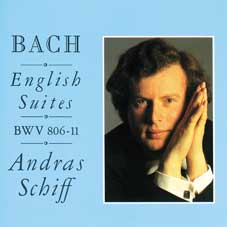 Bach English Suites Nos.1-6 BWV 806-811 András Schiff (pf) ♥♥ イギリス組曲全曲 BWV 806-811 アンドラーシュ・シフ(ピアノ)♥♥ 平均率でもゴールドベルク変奏曲でも大変魅力的な演奏を届けてくれたアンドラーシュ・シフですが、イギリス組曲はどうでしょうか。 やはり他と同様素晴らしい演奏でした。さらっとしているのに味わい深く、現代的な趣向が見えるのに作為的なところは感じさせません。この人独特のバッハはモダン・ピアノによるバッハの定番だと言っていいでしょう。ただ、2000年代に入ってからの ECM の新録音は出ておらず、デッカの1988年の録音のみです。 シフは時代によって演奏スタイルが大きく異なるということはありませんが、耽溺はしないものの若いときの方が多少ロマンティックに響くところがあるような気はします。後年の方が自由で弾むようなところがあり、即興的な感じがするわけです。このイギリス組曲ももし新しいのが出ればそうなるかもしれませんが、ここでの録音は必ずしもそういう感じではないかもしれません。冗漫なところがなく、引き締まってよく構築された感じがします。知的で爽快な面を持ち合わせ、活きいきとしていて大変良いです。3番の出だしなど、スタッカートも交え、弾みもありつつ、控えめに洗練されつつ情緒もあります。   Bach English Suites Nos.1-6 BWV 806-811 Murray Perahia (pf) ♥ イギリス組曲全曲 BWV 806-811 マレイ・ペライア(ピアノ)♥ ペライアは戦後生まれ(1947年)のユダヤ系アメリカ人で、国を追われたり厳しい環境の中でコンクールを勝ち抜いて来たりした世代ではなく、演奏も力や技巧で押すところがない洗練が持ち味であり、バッハ弾きとして高い評価を受けています。シフと人気を二分するぐらいではないでしょうか。 素晴らしいセンスを持ったピアニストで、個人的にもゴールドベルク変奏曲やこのイギリス組曲は愛聴して来ました。演奏をどう表現するかは難しいですが、まず突飛なことをしようという方向ではありません。バッハのピアノ演奏では、近頃は面白いところを打ち出そうと力む人も出ますが、ペライアは大胆なスタッカートや速いテンポ、コントラストの強い表情などにおいて工夫を凝らし過ぎることはなく(2番のジーグのスタッカートや5番のブーレでの装飾音など、意欲的なところはあります)、今の人の中では比較的素直に弾いてる方なので、シフや、この後で取り上げるヘブラーなどと比較しても面白いかもしれません。 シフの方は、特にフランス組曲などではかなり速く弾くパッセージもありましたが、ペライアにはそういうところはあまり感じません。どちらも見事に芸術的な抑揚が上品についており、その中でペアイアの持ち味はと言えば滑らかさだということになると思います。切れ目なく漸進的な抑揚があります。力みがなく、自由に、しかしあくまでも滑らかにつながった抑揚を聞かせます。女性奏者にありがちなという意味ではないながら、一般的な意味でちょっと女性的な印象もあります。シフはもう少し粒立ちがあって、くっきりとした輪郭を感じさせます。 自在な変化があるという点ではシフも同じですが、一番大きな違いはというと、シフが愉悦の方向ならば、ペラ イアはそこはかとないメランコリーを感じさせるところでしょうか。しっとりとした湿り気のあるテクスチュアがあります。最初聞いたときはよく分からなかったものの、しばらくすると、ちょっと重さのある(リズムは軽くても)、微かに胸塞がれる感覚に気づくのです。前にも他の曲でこの点については書いたけれども、それならばどこをどう弾いたからメランコリーになるのかと聞かれると大変困ります。同じ曲をただ聞いていて片方はどちらかと言えば愉悦を、片方はもの悲しさを感じることからこちらの投影ではないだろうと思うものの、技法的には説明し難くく、そう感じるとしか言えません。アンデルシェフスキの場合も弱音が極度に抑えられていて、そこにペライアと同じく滑らかで思い入れの強い抑揚が、むしろもっと付くぐらいなので、それなら彼もメランコリックかというとそれはまたちょっとニュアンスが違います。もちろんペライアの演奏を喜びと表現する人もいますから、こういうのは主観的な見方であることは間違いありません。少なくとも自分に言えるのは、このペライアというピアニストは力みが全くなく、あくまでも滑らかにつながって行く演奏をするということです。そして静けさが心に染み入るように響きます。大変美しいです。この後新しく出たフランス組曲などは、そういう情緒が望ましい人にとっては他に代え難いのではないでしょうか。 イギリス組曲はレーベルはソニーで、録音は1997〜98年です。  Bach English Suite No.3 / French Suite No.5 Capriccio in B Flat, BWV 992 "On the Departure of a Dear Brother" Toccata in D BWV912 Wilhelm Kempff (pf) ♥♥ イギリス組曲第3番 / フランス組曲第5番 カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに向けて」BWV 992 トッカータ 二長調 BWV 912 ウィルヘルム・ケンプ(ピアノ)♥♥ このCD はケンプの項目ですでに紹介しました(「晩年のケンプ」)。 1895年生まれのドイツのピアニスト、ケンプは晩年になって枯れた美しさを示しました。ちょっと他では聞けないため息の出るような演奏なので、イギリス組曲は3番だけという選集ですが、ぜひ聞いてほしい一枚です。 INDEX |