| ベートーヴェン/「大公」トリオ ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 op.97「大公」 Beethoven: Piano Trio in B-flat Major op. 97 "Archduke"  取り上げる CD26枚: カザルス・トリオ/カザルス・シュナイダー・イストミン/カザルス・ヴェーグ・ホルショフスキー /ハイフェツ・ルビンシュタイン・フォイアマン/オイストラフ・トリオ/ボザール・トリオ/スターン・イストミン・ローズ /デュ・プレ・ズッカーマン・バレンボイム/ケンプ・シェリング・フルニエ/スーク・トリオ( ’61 '75 '83)/アシュケナージ・パールマン・ハレル /ボロディン・トリオ/ハイドン・トリオ・ウィーン/カリクシュタイン - ラレード - ロビンソン・トリオ/トリオ・フォントネ /プレヴィン・ムローヴァ・シフ/フロレスタン・トリオ/トリオ・ワンダラー/トリオ・エレジアク/キャッスル・トリオ /トレンドリン・トリオ/インマゼール・ベス・ビルスマ(ラルキブデッリ)/ファウスト・メルニコフ・ケラス/ストリオーニ・トリオ 楽曲の性格と作曲時期 ピアノとヴァイオリン、チェロの組み合わせによるピアノ三重奏というジャンルは、古くはバロック時代にそういう編成の曲が作られていたようですが、それ以降しばらくはピアノに対してヴァイオリンとチェロが付け足しのような扱いであり、本格的に各楽器が主張し合うような曲はベートーヴェン以降だと言われます。つまりベートーヴェンがこの形式を完成させた、と言ってもいいでしょう。そして、そのベートーヴェンの三重奏作品の中でも最も知られており、完成度が高いのが第7番の「大公」なのではないかと思います。ピアノ三重奏としては最後の作品であり、時期的には1811年完成ということなので四十一歳、中期の終わり頃で、ピアノ協奏曲「皇帝」や弦楽四重奏「セリオーソ」を作った後、第7交響曲の前あたりになります。晩年の孤高とも言える作風ではないにせよ、脂の乗り切った頃の作品です。 四楽章構成で演奏時間は40分ほどです。第二楽章がスケルツォになっており、第三楽章がアンダンテ・カンタービレの緩徐楽章です。 他にもピアノ三重奏曲は他曲からの編曲や変奏曲、作品1以前のものなどを除いて六曲あります。1番から3番までは二十五歳頃の曲、4番「街の歌」がその三年後でいずれも若い時の作品であり、5番の「幽霊」と6番が「運命」や「田園」と同じ三十八歳頃、いわゆる「傑作の森」の時期ではあるけど、大変人気があるというほどでもないようです。恐らく「大公」の次に知名度の高いのは「幽霊」でしょう。第二楽章ではゴーストの名前の由来になったピアノの低音部の連続音が途中不気味にずっと響いており、モーツァルトの「不協和音」の新しさにも似た意欲的な取り組みが見られます。「街の歌」の第二楽章もきれいだし、6番の出だしもいいです。でも一般的にはピアノ三重奏といえば「大公」としておいてよいのではないでしょうか。 大公のこと さて、「大公」という愛称が曲に付いていますが、この大公というのはオーストリアの貴族、ルドルフ大公という人のことです。正式な名前はルドルフ・ヨハネス・ヨーゼフ・ライナー・フォン・エスターライヒと言います。ベートーヴェンがこの曲をそのルドルフ大公に献呈したのでそうした愛称で呼ばれるようになったわけだけど、年齢はベートーヴェンより十八歳年下で、曲が作られた頃は二十三歳でした。このルドルフはベートーヴェンの弟子にしてパトロンでした。こういうのは当たり前で、ブラームスの時代にやっと作曲家は自立して食べられるようになったのです。モーツァルトはそうしようとして一時は大成功したものの、後に貧乏で暖房の薪も買えなくなりました。昔は皆貴族のお抱えだったわけです。ベートーヴェンも例外ではなく、貴族からお金をもらっていました。しかしパトロンとはいっても、十五のときにピアノと作曲の弟子にしたルドルフ大公とはずいぶん気が合ったらしく、生涯友達のような間柄だったようです。献呈もこの曲だけでなく、他にも有名なものが多数あります。大公は自身も才能があったようで、作曲もしているし、彼のためにベートーヴェンがピアノのパートを書いた作品もいくつもあります。ベートーヴェンの死後三年経つとその虚弱だった弟子ルドルフも若死にしてしまいましたが、師には最後まで年金をあげていたそうです。 大公もベートーヴェンもウィーンに住んでいたけど、元々この大公の家はロレーヌ家といってフランスとドイツの国境のあたりが発祥です。ルドルフ大公のおじいさんで後に神聖ローマ皇帝となったフランツ1世がマリア・テレジアと恋愛結婚したために、あの有名なオーストリアのハプスブルク家と一体化しました。同じく神聖ローマ皇帝だった父のレオポルト2世とフランス革命でギロチンにかかったマリー・アントワネットは兄妹という関係で す。つまりマリー・アントワネットは大公の叔母さんです。叔母さんとはいっても、仲の良かったフランツとマリ ア・テレジアの子供は16人もいたし、大公本人の兄弟も16人でした。フランツには奥さん以外にも何人も愛人がいたとのことで、このあたりの貴族たちの生活は、色々な意味で人間関係の一大シンフォニーです。 因みに「大公」という位は貴族の中でも王のすぐ下に当たります。英語だとarchduke、その下には公爵 duke、王子/公子 prince、侯爵 marquis、辺境拍 margrave、伯爵 count、子爵 viscount、男爵 baron など、国によっても違いはあるでしょうが、実にたくさん位があります。 演奏スタイルと評について ベートーヴェンの作品に豪快さを求める人は多いでしょう。確かにモーツァルトと比べると断定的で意志の強そうなところは感じます。ユニゾンで強調したり、多重和音で宣言したりするフォルテがあったりするわけです。でもそうした部分で走ったり力まかせに叩いたりしたら、音が濁ってよく聞こえなくなってしまうこともあります。そうしたベートーヴェン解釈が現在は少しずつ、若手の演奏家の間では流行らなくなって来ているような気もします。もしこの曲の演奏スタイルを三つに分けるなら、一つはピリオド楽器とその奏法によるものでしょう。そしてモダン楽器による残り二つのうちの一つは往年の巨匠風の壮大なもの、そしてもう一つが昨今の、軽く爽やかで深刻さを感じさせないスタイルのものになる気がします。「往年」と「昨今」の境界線がどこかは曖昧だけど、個人的には最後のカテゴリーが好みです。ここで取り上げる盤は色々ですが、コメントにはそういう人間のバイアスがかかっていると思います。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Casals Trio Pablo Casals (vc) / Jacques Thibaud (vn) / Alfred Cortot (pf) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 カザルス・トリオ: パブロ・カザルス(チェロ)/ ジャック・ティボー(ヴァイオリン)/ アルフレッド・コルトー(ピアノ) カザルスの演奏した「大公」は主に三種類です。その中で最も古く、最も有名なのがティボーとコルトーと組んだカザルス三重奏団による1928年盤でしょう。パブロ・カザルス(1876-1973)はチェロの巨人ですから説明するまでもないかもしれませんが、バッハの無伴奏組曲を再発掘したり、新しい奏法を確立したりしてチェロの演奏に革命をもたらした人です。フランコ政権に反対して生涯母国に帰らなかったことも有名だし、あのヨーヨーマも神のように讃えています。粘り気があって力強く朗々と歌い、感情表出のあり方が当時としては非常に個性的だったと思います。個人的な話ながらこの演奏で初めて「大公トリオ」という曲を知りました。傷んだ盤に何度も針を通したこともあって自分の物差しになってるところもあるのであらため説明するのも難しいですが、三種類の中ではこれがいいと思っています。音質を除けば、今聞いても納得です。 アルフレッド・コルトーは1877年生まれでフランス人とスイス人を父母に持ち、フランスで活躍したピアニストで、祖先はカザルスと同じカタルーニャ出身だとされます。ジャック・ティボーもフランスのヴァイオリニストで1880年生まれ。カザルスが1876年生まれですからほぼ同世代の人たちです。ティボーは飛行機事故で死にたいと発言して実際にその通り亡くなった珍しい人です。この話は有名なので、弟子だった女性ヴァイオリニスト、ジネッタ・ヌヴーについて書いたブラームスのヴァイオリン協奏曲のページですでに触れています。 さてその演奏ですが、溌剌とした出だしからしてニュアンスに富んでおり、古さを感じさせません。引きずるわけでもなく大仰でもなく、むしろ明るく爽やかで、ドイツ系ともユダヤ系とも違う印象です。フランコ=ベルギー派の典型ということだけど、この当時のフランス流なのかどうかも分かりません。割合ゆったりしたテンポで、弱音で鳴らすピアノのトリルが静かです。1928年ながら40〜60年代の演奏より新鮮です。ヴァイオリンがポルタメントを使うのが時代を感じさせるぐらいでしょうか。あとはヴァイオリンとチェロがユニゾンで大きくビブラートをかけながら丸い抑揚を付けるところも独特の空気感だし、コルトーによくあったことらしいけど、時々ピアノは乱れます。ヴァイオリンのピツィカートが続くところでピアノと歩調が合わず、ヴァイオリンだけが速く走ってしまうのはさすがにどうかと思うけど、それもご愛嬌でしょう。また、ヴァイオリンとチェロが長い和音を奏でる場面で「はもり」が共振しているのはどちらかの音程がずれてるからだと思うけど、これについてはカザル スは表現手段としてピッチを微妙に変える技を使っており、上昇フレーズと下降とで音が違ったという話もあります。下げておいて最後に上げて合わせるというのは歌ではよく使われる手法です。気になる人は狂ってるように聞こえ、昔だからこの程度かと考えるかもしれません。 第一楽章のアレグロ・モデラートです。一般に想像されるような往年の名演スタイルとは違うと言ったけど、実際に興奮して走って行くようなところはないし、カザルスが主張し過ぎることもありません。歌があり、決して力で押し切ることなく、壮大な演奏でもありません。 次のアレグロのスケルツォはデリケートな抑揚をつけながら、過度に元気にならないところがいいです。 第三楽章も出だしは適度にゆったりなテンポで陰影に飛んでいます。弦に音の途中で盛り上げる強弱があり、ピリオド奏法が出て来る前からこういう表現があったのだなと思いました。フレーズの変わり目で間を十分に取るところはピリオド奏法とは異なります。途中からはかなり遅いテンポになるけれども感傷的ではなく、瞑想的な静けさです。テンポの緩め方も良いです。フランコ=ベルギー派とはいえ、ビブラートのないヴァイオリンが山なりに鳴らすところもあります。後半はゆったりと濃厚に歌い、チェロの深い抑揚が聞こえます。 アレグロ・モデラート/プレストの終楽章はややテンポ変動が大きく、走るフレーズも聞かれ、音がくっきりしないところも若干はあります。 写真は古い LP のジャケットだけど、最新のリマスター CD は驚くほど音がいいです。とても1928年とは思えない仕上がりで、演奏同様、40から50年代前半の録音と言われても分からないでしょう。ただし SP からの復刻なので針ノイズはあるし、箱鳴りのような響きで低音が少ないのは致し方ないことです。音が重なるフォルテで濁りもあります。レーベルは EMI で、残響は少ないです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Pablo Casals (vc) Alexander Schneider (vn) Eugene Istomin (pf) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 パブロ・カザルス(チェロ)/ アレクサンダー・シュナイダー(ヴァイオリン) ユージン・イストミン(ピアノ) カザルスの加わった「大公」の二つ目は1951年のフランスでの録音です。1925年生まれでユダヤ系アメリカ人のユージン・イストミンがピアノ、1908年生まれの同じくユダヤ系アメリカ人でブダペスト四重奏団のメンバー だったアレクサンダー・シュナイダーがヴァイオリン、というものです。二人はカザルスよりずっと若く、カザルスを尊敬している立場です。 演奏スタイルは上記カザルス三重奏団とは大変異なり、軽くて陰影に富んでいる種類ではありません。第一楽章のテンポは次に取り上げるヴェーグ盤ほどではないけどぐっと遅めです。弦はスラーの印象があり、フォルテは力強いけどエネルギッシュではありません。アゴーギク(テンポの揺れ)はティボー/コルトーとの盤とは種類が異なり、強調しようとするところで遅くする傾向が目立ちます。そしてヴェーグ盤と同様、遅い中で一つひとつ進めて行く感覚があります。ヴェーグ盤ほど訥々とした印象ではなくて滑らかさはあるものの、丁寧という点では同じです。 スケルツォも同様で、ヴェーグ盤よりよく波打って滑らかさがありますが、リズムパートは遅く区切られた印象 です。破綻のない運びです。 緩徐楽章である第三楽章は大きく波打ったり消え入るように弱まったりはせず、滔々と流れて行きます。それでいてクレッシェンドがダイナミックでもあります。テンポはヴェーグ盤ほどではないけれどもかなり遅い方です。フレージングも丸く感じ、途中ゆっくり歌わせるところでは止まりそうなほど遅くして揺らします。感情的に重いわけではないけどリズムは重いです。好きずきながら、こういう運びが良い人も多いと思います。 終楽章は結構力強いです。リズムが区切られていて意外な揺れはなく、真っ直ぐな解釈です。ここもヴェーグ盤ほど遅くはありません。 脇をアメリカの門弟たちが固めるこのカザルスの録音、手法こそ違うけど後のスターンたちを思い起こさせると ころもあるし、音を捉える形として、少し様相を変えながらバレンボイム盤、アシュケナージ盤などにつながる一面もある気がします。 録音はモノラルです。でも次のヴェーグ盤のステレオより音が悪いとは思いません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Pablo Casals (vc) Sándor Végh (vn) Mieczyslaw Horszowski (pf) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 パブロ・カザルス(チェロ)/ シャーンドル・ヴェーグ(ヴァイオリン) ミエチスラフ・ホルショフスキ(ピアノ) カザルスがチェロを弾く「大公」の第三弾は国内では「銘盤」シリーズとなっており、現在日本以外でも出てるのかどうかは分かりませんが、日本のウェブ辞典では一時期これだけが名盤として記載されていました。恐らくカザルスが SP からの復刻ではなく、ステレオで聞けるところがその理由なのだろうと思います。1958年、ボンのベートーヴェン・ハウスでのライヴ録音で、カザルスはこのとき八十二歳でした。 メンバーはヴァイオリンがハンガリー出身のフランス国籍でヴェーグ四重奏団を創設したシャーンドル・ヴェー グ(1912-1997)、ピアノはユダヤ系アメリカ人のミエチスラフ・ホルショフスキー(1892-1993)というものです。ホルショフスキーは高齢まで活躍し、その晩年の演奏活動を高く評価する声もありますので、それも名盤の根拠の一つかもしれません。 演奏ですが、カザルスの参加した三枚を比べると年代ごとにテンポが遅くなっているようです。後の二つの録音は他のメンバーがカザルスを慕っている関係ですから、このテンポ設定は老齢のカザルスに合わせてそういうテンポになってるのか、あるいは曲の構成上重要なパートであるピアノが決めるなどして若手に任せた結果かは分かりません。その辺の事情はファンなら知っているかもですが、とにかく遅いです。出だしからして大変ゆったりなテンポです。ヴァイオリンはやや引きずるように運ぶ傾向があります。ピアノは一音一音鳴らして行くという印象で、丁寧です。遅いピアノに合わせてヴァイオリンが抑揚を付けず、音を延ばさずに弾くところでは途切れ気味に聞こえたところもありました。個人的な感想だけど、こういう状況は遅いテンポ設定に奏者がついて行けないときに生じるような気がします。一方で表情があるのはカザルスのチェロで、この人らしくうねるように弾いています。 スケルツォも同様で、一つひとつ音を鳴らしている感じがします。くっきりしているけれどもちょっと催眠にかかりそうです。この楽章では大変個性的な運びと言えるでしょう。 第三楽章は元来遅いパートであり、他にも遅い演奏があるので違和感はさほどないけれども、やはり最初からス ローです。抑揚を抑えたモノトーンのピアノで入り、ヴァイオリンは力が抜けています。ここでもやはりチェロの音程が低く感じるときがあり、そのせいでヴァイオリンとのハーモニーに干渉のうねりが生じます。この楽章は全体に起伏の少ない運びで感情移入はなく、ただ静かにフラットであり続けます。そんな中、細いヴァイオリンの音が印象的です。後半はひたすら遅いと言っていいでしょう。この呼吸の感覚を共有できる人には唯一無二の名演になると思います。 第四楽章もフラットで大変ゆったりです。 録音はカザルスとしては新しくてステレオだけど、ライヴ収録で音的には古い感じもします。強調された広がりを除いて、音場そのものの印象はモノラルかな、とも感じます。でもカザルスがステレオで聞けるなら問題ないでしょう。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Yasha Heifetz (vn) Arthur Rubinstein (pf) Emanuel Feuermann (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)/ アルトゥール・ルビンシュタイン(ピアノ) エマーヌエル・フォイアマン(チェロ) ベートーヴェンの「大公」は密かなブームになったのだそうです。それはカズオ・イシグロの読者が沈黙する一方で、毎年ノーベル賞の受賞を期待する熱いファンを有する日本の作家の功績のようです(と書いたこの記事の後、そのファンには気の毒ながらイシグロの方が受賞しました)。どういうことかというと、その作家が自身の小説の中で音楽を取り上げることを毎回仕掛けにしており、その一つが「大公トリオ」だったのです。処女作だけ読んだぐらいでコメントできないけど、今や世界的存在であり、それでこの曲が売れて室内楽に親しむ人が増えたのは良いことだと思います。 小説の中での演奏はこのルビンシュタイン(1887-1982)/ハイフェッツ(1901-1987)/フォイアマン(1902-1942)たちのものだったようです。そして音楽祭の宣伝担当が考えたそうだけど、この三人は「百万ドルトリオ」と呼ばれることもあります。「ミリオンダラー(百万ドル)」というのは素晴らしいものに付ける形容詞です。三人共ユダヤ系の演奏家だけど、ユダヤ人はビバリーヒルズに住むお金持ち、ということではありません。でもユダヤ系アメリカ人が音楽界を牽引して来たことは事実だし、「大公」はかなりの割合で彼らの録音が占めています。そしてことこの曲に限っては、ある時代において、聞き比べているうちにユダヤ系の演奏家に共通する傾向かと思いたくなるような空気感があるような気もして来ました。具体的な演奏スタイルのことではありません。それは直感に従って揺れ動く自発性だとか、外し崩しの粋とかではないような種類であり、ストレートさ、押して来るような感動の型とでもいったものです。恐らくそれも一頃のドイツ系は角張ったリズムだったと言うのと同じような話であり、イストミンやホルショフスキ、バレンボイムやアシュケナージたちのアンサンブルに限ってたまたまそう感じただけかもしれません。差別は愚かだし、好きなユダヤ系の演奏家はたくさんいるわけで、一括りに典型化するマインドの方が問題なのでしょう。 前置きは何かと言うと、ここでの百万ドルトリオの演奏に接して、有名作家も取り上げる名演奏なのでついて行こうとしたのですが、第三楽章はかなりいいと思ったけど個人的には正直よく分からず、複雑な気分を味わったということです。もちろん、このページで何を言ってもその価値は減じないでしょう。巨匠たちによる「金字塔」と呼ばれる演奏です。1941年、真珠湾攻撃の三ヶ月前のハリウッドです。ルビンシュタインとハイフェッツは気が合わず、後年仲違いしたそうだけど、目指す方向性が違うのでスリリングだとも評されます。「火花散る」というのは喧嘩してるから早く終わらせたいというのとは違うだろうし、セッションが見切り発車だったわけでもないでしょう。でもハイフェッツはルビンシュタインの引きずるようなリズムに苦言を呈したということですから、ひょっとして速く行きたいハイフェッツがルビンシュタインを急き立ててる構図もあり得るのでしょうか。ときに随分急いでいるように感じます。テンポは合意の上のはずながらヴァイオリンが先走ります。そんなところでは前のめりに拍が早まります。スラーでつなげて一続きに盛り上がる大きなクレッシェンドがあるかと思えば、転げるように馳け出すフレーズもあります。 第一楽章からです。ルビンシュタインはショパンなどで独特のルバートというか、粘るような重いリズムを聞かせることがあり、それが一つの特徴でもあります。ハイフェッツもそう思ったわけだけど、どういうわけかこの「大公」では印象が違いました。ヴァイオリンに気遣ったのかどうか、同じように前のめりに駆けるところがあります。さらっとした流体のようで、新しい一面を見せられた感じです。 ハイフェッツは超絶技巧の持ち主と言われました。ここでのハイフェッツが本人らしいのかどうかは分かりません。でも一般に演奏家に評価される演奏家というものはあり、そういう玄人受けする演奏なのかもしれません。ここでは常に前へ前へという気持ちを感じました。 チェロのフォイアマンはヒンデミッドと組んで弦楽三重奏をやるなど、ヨーロッパで有名だったけれどもナチに追われました。このトリオでは仲人役、仲裁役と言われます。控え目で目立とうとせず、場に溶け込んで自然に歌います。 第二楽章も短く切り上げるフレーズが目立ち、踊りながら馳けるような調子で面白いです。 第三楽章のアンダンテは味があります。ただ、主題はゆったり歌うものの、展開部分ではやはり転げるように 速いところが出ます。小さな山を一つひとつ盛り上げながら進むようなうねりが聞かれるけど、ルバート様の時 間方向の揺れは少ないです。ヴァイオリンはフレーズの間をつながずに空白を設けます。遅いテンポに抵抗しているのでしょう。かといってピアノが終始遅いかというとそうでもなく、フォルテでは同じ音を隙間なく埋めるように叩く超速連打も繰り出します。猫が鳴くようなポルタメントはやはりこの時代の空気を感じさせます。その弦には常にビブラートがかかっています。繰り返し現れる主題のうねりが心地良いです。後半では揺れる波に任せていると夢見心地になって来ます。音も手伝ってか、大変懐かしい感じがします。 終楽章も同様で、前倒れに走るフレーズがあります。アゴーギクが大きくないと書いたけど、時々はルバートがかかり、一瞬もつれるように遅くなって間が出来たり、反対に駆け出したりということはあります。第二楽章とよく似た処理で、踊るように身をよじって馳けるフレーズが爽快です。 1941年の録音は年代相応でしょう。ピアノは鐘が響いてるみたいであり、そのせいで霞の中にいるようです。全体に音が常に鳴ってるように感じます。別の言い方をすれば針音の懐かしいセピア調の響きです。鼻にかかったようで音域が狭いけれども、それは琥珀色の輝きとも言え、味わいがあります。文学の装置としては新しい録音でない方がいいだろうし、件の作家は作品の世界の続きとしてこの音の余韻を読者に聞かせたかったのかもしれません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" David Oistrakh (vn) Lev Oborin (pf) Sviatoslav Knushevisky (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 オイストラフ・トリオ: ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)/ レフ・オボーリン(ピアノ) スヴャトスラフ・クヌシェヴィツキー(チェロ) やさしさの感じられるアンサンブルです。オイストラフ(1908-1974)と聞けばたっぷりと歌う、あのやわらかい音色を思い浮かべる人もいることでしょう。ここでもそれは裏切られません。往年の名演の範疇に入るだろうけど、力で押し出 すところはなく、滑らかな運びでロマンティシズムに溢れています。濃厚でメロウなヴァイオリンに軽妙なピアノが絡みます。白熱した演奏ではないけど、粋な揺れや崩しを指向しているわけでもありません。何でもお国柄にするのは良くないにせよそこはロシア流、ひたすら豊かに歌います。テンポは終始ゆったりです。因みにオイストラフもユダヤ系です。弾圧されたソビエト体制の中では、音楽でしか貧困を抜け出せなかったこともあって多くの演奏家が出ました。しかしオボーリン(1907-1974)のピアノはソビエトの養成メソッドから出て来たとは思えない繊細さで、超絶技巧の演奏家とは方向性が異なり、軽さと温かさがあります。アシュケナージの先生です。この演奏の良さはそのオボーリンの存在によるところも大きい気がします。チェロはモスクワ音楽院の教授だったスヴャトスラフ・クヌシェヴィツキー(1908-1963)です。 丁寧な第一楽章は悠々とした運びで、走ったりしません。ピアノが力まないのがいいです。ヴァイオリンはややねっとりした節回しです。チェロは爽やかです。三人が揃ってそよ風のように心地良く耳を撫でる静かなパートもあります。 やや遅めのスケルツォは真面目なフレージングで、パートによって区切れて軽さがないように感じるところと、ふわっと軽いタッチで行くところとが現れます。ピアノはやわらかくて陰影があり、そっと弾くタッチが心地良いです。一切走るところがありません。 第三楽章もやはりゆったりで切れ目がなく、ヴァイオリンはむせび泣きながらもひたすら抑え気味に進行します。感傷的に抑揚を付けるわけではありません。ここまでスローに一語ずつ発音して行くのか、という部分もあります。延々と続くかのように遅く、ホルショフスキーたちのスケルツォもそうだったけど、ここでも催眠にかかったようになります。でも全編そんな進行というわけでもなく、やわらかい抑揚でヴァイオリンが撫でて行くような箇所もあるので、他の演奏でときに感じるような乗れない感覚はなく、全体としては心地良く浸れます。最後の方でヴァイオリンとチェロが受け渡しをする場面でうっとりさせられることもありました。ピアノの音は丸いけどきれいです。 第四楽章は前楽章とコントラストの付いた短く強いフォルテで始まり、やはり速くはない展開ながら、軽さを感じるのはピアノのせいでしょうか。後半は落ち着いて崩れることなく進んで行き、お終いに近づくとやや速まり、最後は加速して終わります。 1958年の録音でレーベルは EMI です。ステレオです。今や昔の巨匠の名演だけど、音はかなり良いです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Beaux Arts Trio ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ボザール三重奏団 ボザール・トリオは近年味わい深いソロ活動で脚光を浴びているメナハム・プレスラー(1923-2023)がピアノ、ダニエル・ギレ(1899-1990)がヴァイオリン、一人だけヘブライ系ではなさそうなバーナード・グリーンハウス(1916-2011)がチェロというアメリカのピアノ三重奏団で、1955年にデビューして2008年までピアノ以外のメンバーを変えながら長らく活動して来ました。そのプレスラーについては別項で取り上げましたが(メナハム・プレスラーのモーツァルト)、枯れて洗練されており、内側に耳を傾ける瞑想的な味わいが独特でした。1964年、四十一歳のときのこの「大公」の演奏にそうした枯れた趣きはないものの、晩年の演奏に共通する部分もその奥に見ることはできるような気もします。同時にあのような熟成の味を出す前はこういう傾向だったということも分かります。イストミンやホルショフスキーとは違った叙情性の表現で、やり過ぎかと思えるほど揺れ動くテンポには若さと熱気を感じ、分かりやすい側面もあります。ロマンティックな人であり、ひたむきなところは晩年と変わらないとも言えます。団体名については、フランス語で Beaux は美しい、Arts は芸術で、リエゾンした「ボザール」一語で「美術」という意味になります。 第一楽章の運びは、この時代のスタンダードだった遅くて重い傾向ではないものの、途中で急に速まったり大胆に遅くなったりし、情緒に揺れる音楽となっています。それがロマンティックに聞こえるところです。それでも変わったことをしようという計画性を感じさせないところは後年のプレスラーのソロにも共通しています。ヴァイオリンはレガートでよくつながっています。全体にフレーズは区切るらず、軽く滑らかです。 スケルツォも軽やかに流れるようであり、やはり感情に従って湧き立つような揺れがあります。 第三楽章はゆったりだけど展開部で速まるところもあるし、やはり思い入れの強い抑揚が付きます。フレーズを小節後半で遅くする様が叙情的です。感情に飲み込まれるにせよ盛り上がるにせよ、小細工なく真っ直ぐだとも言えるでしょう。そういう種類の叙情性を好む聞き手にとっては、これか次のスターンたちの盤かというところかもしれません。ボザールの方はフルトヴェングラーみたいなテンポの揺れが売りです。 終楽章も傾向はそれまでと同じです。平均してテンポはやや速い方でしょう。最後は転げるように駆けて行って、断定的に遅くして締め括ります。 1964年の録音はフィリップスで、このレーベルらしく音が自然で良いところが魅力的です。艶やかかつ滑らかです。レーベルが良い演奏として推していたのでしょう、上のジャケットではないけれど、大変バランスが良かった96KHz24bit リマスター版も出たことがあります。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Isac Stern (vn) Eugene Istomin (pf) Leonard Rose (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 アイザック・スターン(ヴァイオリン)/ ユージン・イストミン(ピアノ)/ レナード・ローズ(チェロ) アメリカ文化を感じさせる、アメリカらしい演奏と言うと大雑把でしょうか。逆に大雑把なのがアメリカ流だと言ったら悪い意味になるけれども、大味なマッチョではなく、些細なことに気を取られずに要点を大づかみに捉えられ、大胆なのは良いことです。男性が男らしいことはアメリカでは重要です。もし洗練を必要とするなら努力していつかそこに到達しようという心構えがあり、それゆえ超一流も存在します。このユダヤ系アメリカ人の三人、ヴァイリニストのアイザック・スターン(1920-2001)とピアニストのユージン・イストミン(1925-2003)、チェロのレナード・ローズ(1918-1984)のトリオによる「大公」の演奏は、そんなアメリカらしい理想を実現した名演だという気がします。荒削りながら正確な形にカットした具象的な彫刻のような安心感があります。男っぽくて真っ直ぐな叙情性、ヒューマンで豪快なタッチ。全体に重さのあるフレーズながら、ゆったりしているのでうるさくなりません。ストライクゾーンの真ん中に来る堂々たる演奏は美しくもあります。もしシュティーラーの肖像画のような雄々しいベートーヴェンを望むなら、これを選んで間違いないでしょう。 第一楽章はゆったりとした始まりで、余裕があって堂々としており、よく抑揚が付いています。あるいはもったいぶってるように聞こえる人もいるかもしれません。フレーズの区切りはフォルテで力強く叩き、くっきりしています。ヴァイオリンはビブラートを大きくかけ、深い呼吸で歌います。歌い方は丁寧だけど、同じぐらいのテンポでもオイストラフのように甘くやわらかいのではなく、もっと骨太です。またスークのようにすっきりした中庸表現でもなく、より隈取りがはっきりしています。強調する際に緩めることはあっても走り出すことはありません。せかせかしたら器が小さく見えるでしょう。洗練ということで言えば、ピアノのイストミンはカザルスの51年盤でも弾いていたけど、傾向は同じでもこちらの方がより洗練されて聞こえます。 第二楽章もくっきりとしたフレーズでゆったり進められます。スケルツォとはいってもおどけてもいないし軽くもなく、真面目な雰囲気があります。途中チェロが遅くして間をとる方向に崩すところもあるものの、意外な表情は少ないです。 第三楽章も中庸ややゆったりめに入り、要所でくっきり強く叩きながら悠然と進みます。しっかり呼吸が入っているので気持ちがいいし、たっぷりとした情感があって浸れます。細かな動きや詩情を期待する人には向かないとも言えます。でも弦にやわらかいうねりが聞かれるので間延びには感じません。中間部は大きめのルバートで波打ちます。そしてラストに向かってテンポも劇的にゆっくりになり、濃厚な表情が付きます。 第四楽章はその前のアンダンテからコントラストを付けて速めますが、他の演奏と比べてすごく速いというわけでもなく、テンポとしては中庸と言えるでしょう。リズムはやはりくっきりとしています。力強さとともに明るさを感じます。そして最後まで走ることなく堂々としています。 1966年 CBS コロンビア原盤です。音はこもらず弦も滑らかで、ピアノはぴんとしてきれいです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Jacqueline du Pré (vc) Pinchas Zukerman (vn) Daniel Brenboim (pf) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ)/ ピンカス・ズッカーマン(ヴァイオリン) ダニエル・バレンボイム(ピアノ) 見た目の可愛らしい印象と反対に思えるスケール豊かな演奏で人気を博した夭折のチェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-1987)は映画にもなりました。この盤は彼女とその夫だったダニエル・バレンボイム(1942-)に、美音が有名なヴァイオリニストであるピンカス・ズッカーマン(1948-)が加わった二十代の若者たちによる演奏です。イギリスでありながらフランス文化を持つ英仏海峡の島に祖先を持つデュプレを、ピアノ・トリオではあるけど、ユダヤ系の演奏家たちが支えている形と言っていいでしょうか。それだとデュプレが主体だという見方なわけだけど、あるいはバレンボイムが主導しているのかもしれません。 若いときの録音といっても最近のさらっと軽快な演奏ではありません。デュ・プレということで気迫に満ちた運びだろうと思って聞くと、その通りだけれども粘り腰な歌もあるし、遅くして弱めるところも徹底しています。これ以上の振幅の幅はちょっと考えられないぐらいです。やわらかい音を聞かせるズッカーマンの弦もここでは軽くはなく、演奏によって印象の異なるバレンボイムのタッチは軽やかなところと最大限のフォルテが続くところとがあります。アンダンテ・カンタービレの第三楽章は大変遅く、重々しくて思い入れたっぷりな感じがします。感情的になることを恐れず大胆だという意味で個性的であり、時代の空気を感じます。同時にそれは、やはり演奏者の若さから来るのかもしれません。 具体的には、くっきりしたピアノでゆったり入る第一楽章は初めからチェロが雄大に歌います。反対に弱音では抑えて行くので振幅が大きいです。ヴァイオリンはレガートで滑らかにつないでいるけれども、同調して抑揚が大きいです。途中でテンポがゆっくりになり、間を十分に取った濃厚な表現だなと思っていると、さらに遅くなります。フレーズごとに十分に歌いつつ、一個ずつ解決して行く感じです。タ・アー、タ・アー、タ・アーという具合に音の中程で盛り上げて強調を入れます。洗練を求めない力演です。最後はややテンポが速くなります。 第二楽章は中庸な運びながら拍に強調があり、スケルツォとして軽く弾ませているのかもしれないけど力が入っ ているように聞こえます。途中の展開ではチェロが大変ゆっくり弾き出し、それに他の楽器が同じように続くところが出て来るけど、そう思っていると急に目覚めて加速したりしてドラマがあります。また、フォルテが一拍ずつ区切れて強かったり、引きずる手法で強調する弦があったりで、やはり全体に振りが大きいです。 緩徐楽章である第三楽章はストレートに遅く、重々しい始まりです。弦の振幅が大きく力が入っているし、ここでも引きずるようなボウイングが聞かれます。ピアノもときに驚くほど強く叩いています。そして遅いところは最大限遅い運びであり、途中で止まったかと思ったぐらいです。粘りがあり、チョコレートにピーナッツバターを加えたような濃厚な味わいというか、これ以上に思いを込めるのは難しいと思います。 第四楽章は第三楽章に比べれば霧が晴れたかのように溌剌としていますが、客観的に言えば特に軽快なテンポではありません。それでもちょっとしたルバートが軽く聞こえます。 ジェットコースターの絶叫マシンのようなスリルがある凄い演奏です。この強烈な G を楽しめる人には最近の軽い演奏は気が抜けてるように感じるでしょう。 1969年 EMI の録音です。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Wilhelm Kempff (pf) Henryk Szeryng (vn) Pierre Fournier (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ウィルヘルム・ケンプ(ピアノ)/ ヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)/ ピエール・ フルニエ(チェロ) ピアノの詩人ケンプ(1895-1991)に、いつも洗練された歌を奏でるチェロの名人フルニエ(1906-1986)、国内でもレコード賞に輝いた名匠シェリング(1918-1988)のヴァイオリンによる「大公」です。ケンプに注目すればドイツ流ということになるのかもしれませんが、メンバーがそれぞれ別の文化に属するので(フルニエはフランス人、シェリングはユダヤ系ポーランド人)どこの国風というわけでもありません。滑らかな運びで、ピアノにケンプらしい歌があり、独特の美を感じます。ヴァイオリンもチェロもやわらかい流れでつながれ、よく歌います。そしてピアノも弦も共に弱音の美しさが際立っています。その意味では第一楽章と第三楽章が特に印象的でした。 一方でスケルツォの第二楽章は全く走ることなく進むのでおどけた感じや軽妙さがなく、真面目で遅く感じます。これは最後の第四楽章も同じで、この楽章でここまでゆったりしたテンポは珍しいのではないかというぐらいです。場所によってはちょっと間が空いた感覚を覚え、区切り過ぎて乗れない感じもしました。単にテンポだけの問題ではないでしょう。でも第三楽章の出だしでは過度にロマンティックにならないようにすっきりと入り、遅過ぎず、溺れずにやわらかく歌う様が美しいです。そして徐々にゆったりと深まって遅くなって行きます。最近の軽さのあるもの以前の、いわゆる巨匠たちの演奏の中では個人的には最も魅力的に感じました。 カップリングは技巧派カール・ライスターがクラリネットを受け持つオリジナル版(ヴァイオリンでの演奏が多い)の「街の歌」(ピアノ三重奏曲第4番)です。これは国内限定の廉価版で(写真上)、他にチェロ・ソナタと一緒になっているのが出ており、そちらの方がドイツ・グラモフォンの正規盤です。全集は今は出てないようです。フルニエのチェロ・ソナタは同曲のベストの一つだと思うし、「街の歌」は本来のクラリネットの音が聞けます。 1969年のドイツ・グラモフォンの録音は状態が良いです。このぐらいの年度になるとアナログ・ステレオの録音技術も完成に近づき、特に編成の小さな室内楽では今の録音と比べても遜色ありません。ここでも各楽器がバ ランスよく瑞々しい音で聞けるし、このレーベルで時々あったきつい中高音の癖もありません。ただし残響は少なめでやや詰まった感じはあるので、滑らかで繊細という方向とは違うかもしれません。    Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Suk Trio '61 Suk Trio '75 Suk Trio '83 ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 スーク・トリオ 日本のクラシック愛好家の間では、昔は「大公」のレコードと言えばカザルスでした。そしてその後、世界的には色々あったものの、わが国で次に人気を博したのがスーク・トリオです。理由は日本の DENON が PCM 録音シリーズを立ち上げ、契約料の安かった東側の演奏家を中心に色々面白いものを出して来ており、その目玉としてドヴォルザークの曾孫であるスークの「大公」が出たからだと思います。雑誌では評論家が皆褒め、FMでこの曲がかかれば常にスーク・トリオという時期がありました。したがってその世代の間ではこれこそが原点と思っておられる方も多いと思います。日本のアマゾンでは上位に出て来ます。また、前にハイフェッツ=ルビンシュタイン盤のところで述べた作家も、この盤についても言及しているようです。 ヨゼフ・スーク(1929-2011)というチェコのヴァイオリニスト、飾り気がなくすっきりと真っ直ぐで、ビブラートは用法として用いるものの艶やか流麗という感じではなく、温かいと言われがちなこの国の演奏家の中ではちょっと寒色の、時に鋭くエッジの立った音で進める厳しい人という感じです。伝統的に旧東側の音楽家は真面目であり、楽譜から大きく外れることはないけど楽譜通りという言葉から来る生気のない演奏ではなく、楽譜に生命を与え、活きいきとした呼吸を音にして行く場合が多いように思います。ボッセやズスケといったヴァイオリニストもそうだろうし、オーケストラもそんな印象です。 ここでのスーク・トリオの演奏も同じことが言えます。三回ほど録音しているけどスタンスは変わらないのではないかと思います。お酒だと大吟醸の味わいとでも言えばいいでしょうか。味が強くなくて水のように喉に入り、後でふわっと温かくなる、そんな風合いです。火入れしていない無濾過原酒じゃないでしょう。「大公トリオ」とはこういう音楽だということを遊びに気を取られることなく味わえる名演です。 変わった表現があるわけではないので楽章ごとに描写するのはやめますが、三つの録音を一まとめにするのも乱暴なので少しだけ触れますと、一回目の録音はスプラフォン・レーベルで1961年。メンバーはヤン・パネンカ(1922-1999)のピアノにヨゼフ・フッフロ(1931-2009)のチェロです。テンポは他よりも若干速めで、 ピアノのリズムがよく弾んでいて若々しく、元気が良い印象です。録音バランス的にはヴァイオリンの音が前へ出てい るけど、スメタナ四重奏団でもそうだったように、ややつや消しのスプラフォンらしい音です。ときに細く泣く 昔の録音のような倍音に聞こえる場面もあります。 二回目の録音は DENON の PCM シリーズで1975年。メンバーは一回目と同じです。こちらはテンポが全体にややゆったりになり、よく歌っていて心地良いです。特に緩徐楽章のアンダンテはいいです。ピアノも振りが大きくなっており、テンポも静かな部分では遅めです。収録が教会だったので残響が豊かであり、艶やかな弦の音が大変良いのが印象的です。個人的にはこれが好みです。 三回目の録音も同じくレーベルは DENON の PCM シリーズで1983年。ピアノがヨセフ・ハーラ(1928-2019)に変わりました。しかしオリジナル・メンバーで人気のある二回目と比べて決して悪いわけではありません。テンポは三回目の方が速めで軽やかになります。ピアノ以外の表現も若干はさらっとしているでしょうか。残響は二回目より少なめです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Vladimir Ashkenazy (pf) tzhak Perlman (vn) Lynn Harrell (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ウラディーミル・アシュケナージ(ピアノ)/ イツァーク・パールマン(ヴァイオリン) リン・ハレル(チェロ) チェロのリン・ハレル(1944-2020)を除いてこれもユダヤ系の演奏者によるパフォーマンスということになります。アシュケナージ(1937-)のピアノ、パールマン(1945-)のヴァイオリンです。こうして見て来るとたくさんリリースされているのが分かります。ここで取り上げただけでも11枚ありま す。ピリオド奏法の盤を除けば全体の半分以上です。ユダヤ人は劣等だと言ったワーグナーは彼らの能力を恐れていたのかもしれません。ハイフェッツ盤のところでこのグループの人たちの演奏についてあまり良く言わなかったかもしれないけど、旧ソ連から出た演奏家の多くは、差別待遇から逃れようとする一族の期待を一身に背負い、やめたくてもやめられない状況の中で大変な努力をして来たようです。ヴィルティオーソを養成する独自のメソッドがあり、コンペティションで必ず勝利しなければならない重圧の下で舞台に立つのです。ですから実際に才能があり、巧いです。ソ連時代はアイス・スケートの選手たちもウルトラ C のジャンプで得点を量産しました。アイスダンスでは優雅でなくても、置かれた環境を考えれば致し方ありません。だからそのジェネレーションの音楽家たちがときに硬直した様子を見せ、華やかで自由な表現を苦手としていても責められません。新しい世代は波長が違って来ています。 このアシュケナージたちの演奏も力の抜けた滑らかなものなどではなく、やはり真面目で押しと硬さのある表現に思えます。それがむしろドイツ的と言ってもいいのかもしれません(アシュケナージという語がヘブライ語でドイツを意味するからドイツ的というわけではありません)。きれいな音色であるとか華麗だとか評されることもあったアシュケナージ、亡命直後のラフマニノフの協奏曲はシックで重みも感じさせるタッチによる落ち着いた運びで、底光りのする実に美しいものでした。その後色々と変化したわけだけど、この「大公」はそうした均整の取れた美しさが前面に出る種類ではなく、前出のイストミンと同様、ややごつごつとした感触です。ソナタのときとも協奏曲のときとも違うような気がするので、何か考えるところがあるのでしょうか。ロマン派には収まり切らない力強さを持つベートーヴェンということで、それを端正に、謹厳に解釈すればこういう行き方が正しいのかもしれません。教科書的で破綻がないなどと言えば貶してるようだけど、スターンと並んでど真ん中の、正統派の堂々とした演奏です。これこそが「大公」の名盤だと紹介する人もいます。 第一楽章ですが、テンポは中庸です。タッチは重々しくはないけど、テヌートが目立つところはあります。楽譜はスラーながら、それが強調されているという趣きではありません。ヴァイオリン、チェロともにビブラートが速くて大きいので意欲とテンションが高い感じがします。歌わせ方としては、山を作ってワンフレーズごとに覆い被せるように、ふわっ、ふわっと大きめの抑揚を付けて区切って行きます。ピアノも定型の波を作って同じように区切ります。この辺は好みの問題でしょう。リズムに破綻はなく、アクセントは強いです。弦が力強く押し切るようなところ、トリルが連続するパートで一単位ごとに区切るところ、ピアノのスタッカートと弦のピツィカーとが合わさるパートで音が途切れて聞こえるところが、個人的には強調構文のように感じます。でもそれは残響がないせいもあるでしょう。 第二楽章のスケルツォは、これも残響が少ないせいでしょうか、やや途切れがちに聞こえました。テンポは遅くなくても角張ったリズムだからかもしれません。端正だとも言えます。そして結構力強いです。 第三楽章に入ると、遅くも速くもない進行でよく抑揚がついていながらも、テンポは伸び縮みせず、やはりちょっと間で区切れた歌の持って行き方です。音節の頭で弦が二段構えにずれてアタックする形で力を込め、それが懐かしい手法に感じられます。ゆるやかに波のような抑揚を付けるのではなく、また滑らかさを狙っているわけでもないでしょう。引きずり気味の音の運びが見られる一方、フレーズごとに完結した歌が乗っています。スタッカート気味に進める所もあります。夢見心地とは反対の、分解的で辛口なベートーヴェンを目指したのかもしれません。真面目で飾らない緩徐楽章です。 第四楽章です。ここもテンポは常識的な範囲です。楽譜をクリアに見ているようで、フレーズごとに区切って力を入れます。盛り上げては終わりを切るような弦の運びに荒い呼吸を感じ、個人的にはちょっと息苦しくなりました。苦闘する偉大なベートーヴェンです。全ての運びが正確です。 1982年の EMI の録音です。前述の通り、残響が少ないです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Borodin Trio ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ボロディン・トリオ ボロディン・トリオはボロディン四重奏団の初代ヴァイオリニストだったロスティスラフ・ドゥビンスキー(1923-1997)が、ピアニストで奥さんのリューバ・エドリナ(1929-2018)、チェリストのユーリ・トゥロフスキー(1939-2013)と1976年に結成した三重奏団です。ドゥビンスキーは後にソ連からオランダを経てアメリカへ渡っています。四重奏団についてはボロディンの弦楽四重奏のページでその洗練されている様を褒めましたが、そのときの録音は同じカルテットでも時期が違い、ヴァイオリンはミハイル・コペルマンでした。 激しくはないものの、たっぷりと大きく歌う演奏です。その大胆に波打つ歌謡性が好きな人も多いと思いま す。苦しいベートーヴェンではないので聞いていて乗れます。悠然としたところはスターンたちの演奏にも通じる気がするけど、あちらが鍛えた筋肉のやわらかさを思わせたのに対し、このボロディン・トリオはそういった男っぽさはあまり感じさせず、もし男ならやさしい父親像という感じです。 第一楽章のテンポはゆったりの方です。ピアノは女性ではありますが、ピリオド楽器のキャッスル・トリオにもちょっと似た、フォルテで間を大きめに空けてから強く打つような強調が聞かれ(中村紘子も後年やってましたから、ロシアン・スクールの特徴でもあるかもしれません)、ためを効かせたフレーズでゆったり歌わせます。 弦は特に弱めてから遅くして力を抜くところが独特で、ちょっと大げさかもしれないけれども心地良く、やわらかい印象を与えます。全体に波打つような抑揚だけど、フランス流のやり過ぎない洗練を目指すというよりも、恐れることなく大胆に聞かせます。そして訥々と区切れる演奏とは反対で、切れ目のない大波に洗われる感触です。たっぷりとして気持ち良いです。 第二楽章もややゆったりしたテンポながら、今度はタッチが想像していたよりもやわらかく、静かに進む印象です。 録音の良さによってチェロに艶が感じられ、ピアノの滑らかに光りながらも煌びやかさを持った音が良いです。フォルテに向かうところでのアクションの大きさは第一楽章と共通しています。あくの強さがあると同時に独特の安心感も抱かせる運びです。 第三楽章はたっぷりと夢見心地に入ります。よく延ばして大きく歌う様はロシア的叙情とでも言うか、リヒテルの平均率の静かな歌わせ方を彷彿とさせるものがあります。テンポは遅くて細工がなく、グレート・マザー的というのか養育的な父親というのか、何ごとも差別なく受け入れてくれる感じです。英国流でもフランス流でも、粋な演奏が落ち着かない向きには好まれると思います。中間部のスローな展開は大河のように悠然としており、浸ってしまいます。スラーでつながって、どこまでも大らかです。そして第四楽章ですが、ここもゆったりしていて走りません。 1984年、イギリスでのシャンドスの録音はたっぷり響いていながら艶があり、ピアノのフォルテがぴんとして心地良いです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Haydn Trio Wien ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ハイドン・トリオ・ウィーン 知らない三重奏団でしたが、アペックスの廉価版シリーズにラインナップされていたので取り上げました。結成は1964年ということですから、最近のグループではないです。ピアノはハインツ・メジモレック(1940-)、ヴァイオリンはミヒャエル・シュニッツラー(1944-)、チェロはウォルサー・シュルツ(19世紀生まれのチェリスト Walter の方ではなく、Walther/1944-)です。 ためのあるピアノのタッチがくっきりと強く、弦も盛り上がりの力強さと、逆に思い切って力を抜く静かな表 現の間にコントラストがあります。ディナーミクは大きく、アゴーギクはさほどでもありません。滑らかに大き なスラーでつないでうねって行くような演奏では なく、ドイツ語的と言っていいかどうかは分かりませんが、正統派のベートーヴェンというか、短い音節ユニットで区切り気味に解決して次へ進むという感じです。典雅なウィーン風のやわらかい運びを期待すると意外に思うでしょう。 第一楽章は比較的ストレートに進むけれどもさらっと流すのではなく、くっきりとしていて力強さを感じます。フォルテで一つひとつ区切って強く打つからかでしょう。フレーズの終わりで間を空けて強く叩くピアノの手法は前出のボロディン・トリオやキャッスル・トリオとも共通したところだけど、この種類のアクセントはよく見られるものではあるのでこの程度ならばさほど重くは感じません。 第二楽章はややゆったりしたテンポで弾むように進めます。粒立ちのいいピアノの音が心地良いです。やはり滑らかに流すのではなく、音節を区切って行きます。軽やかでおどけたスケルツォではなく、真面目に取り組んでいます。 第三楽章ですが、あまり遅くないテンポで真っ直ぐに表現しています。緩徐楽章にもかかわらず、ピアノによる途中のフォルテがかなり強く叩かれます。数音単位の短い間にうねるような抑揚を付けて行くので、滑らかに進んで行く音を目を閉じて味わうという感じにはなりません。これもドイツ語のアクセントのようです。 第四楽章に入ると、出だしのところで音節の最後の音をスタッカート様に短くせず、鳴らしたまま次の音まで続けるため、区切れた感じがないのが意外でした。でもそこだけであり、全体の流れは他のところと同様、一つずつ断定するように音を積み重ねて行く律儀さが感じられます。終わりの方でチェロの音程と他とがカザルスみたいに微妙にずれて聞こえるような瞬間がありますが、そういう表現でしょうか。テンポは最後までゆっくりとしています。 レーベルはワーナー・アペックスで、録音は1983年です。滑らかできれいなピアノの音が聞け、弦も潤いがあります。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" The Kalichstein-Laredo-Robinson Trio ♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 カリクシュタイン - ラレード - ロビンソン・トリオ ♥ これも今まで知らない演奏者でしたが、褒める人もいるので手に入れてみました。アメリカの団体で、レーベルはカリフォルニアの MCA クラシックスとなっています。グループとしては1978年にニューヨークでデビューとあるけれども、ピアノのジョゼフ・カリクシュタイン(1946-2022)はテルアビブ出身のアメリカ移民だそうです。ヴァイオリンのジェイミー(ハイメ)・ラレード(1941-)はボリビアからアメリカに来て一時はピアニストのルース・ラレードの旦那さんだった人で、チェロのシャロン・ロビンソン(1949-)はいつも一緒に活動する彼の現在の奥さんであり、テキサス生まれということです。 独特の存在感があって良いと思います。普通なのにどこかに分類できない種類の演奏で、どう説明したらいいでしょうか。アメリカ発なのでスターンたちをやさしくした感じとも言えなくはないけれども、生気溢れる運びでありながらアットホームでゆったりしています。崩しが粋という方向ではないし、特に意外な表現も見当たらないけれども、全体にたっぷりとしたテンポで通し、静かに歌わせる部分ではそのスローな歌が大きく波打っています。間をよく取るところも良いです。フォルテの前ではそれが若干強調されて感じますが、かといって切れたリズムで角ばって聞こえるような癖はありません。単にフォルテが力強いと言った方がいいでしょうか。「大公」の演奏としてはスタンダードなものです。アンダンテの楽章も他よりゆったりしており、それでいて流れが途切れません。 第一楽章からですが、やわらかく入り、一音節一楽句を噛みしめるように丁寧に進めます。ゆったりめのテンポです。音符の間に風を呼び込むような落ち着いた間が心地良く響きます。フォルテで力がないわけではなく、緩めて抜くような今風の流し方ではなく、ピアノはくっきりと強く、弦もそれに合わせてしっかり奏でます。それでいて大声でがなるようなところのない演奏です。テンポが自在に揺れるという感じではありません。 第二楽章のスケルツォでも同じで、軽くやさしくはあるけど、一音ずつがくっきりとしています。テンポはややゆったりで、明るく爽やかです。仲の良い楽しげな感覚が伝わります。 第三楽章は大変ゆったりしています。それでいて俗っぽくはありません。やはり一音ごとに丁寧に鳴らして行くところがあってレガートという感じではなく、むしろ自分の呼吸を一つひとつゆっくり意識するような落ち着きがあります。この感覚は素晴らしいです。そういう意味では瞑想的とも言えるけど、ロマンティックとはまた違ったリラックス感です。弦のアタックなど、新しい世代とは違う大振りなところもあるけれども、ヴァイオリンもチェロもよく歌っており、この楽章は聞いていて大変くつろげます。 第四楽章はリズムに軽さがあり、弦に伸び縮みもあって気持ち良く進みます。ピアノの強打は結構しっかりです。その際間を取って遅くして強調する感覚があります。テンポは速くも遅くもないけど、どちらかと言えばややゆったりでしょうか。ただ、平均すればそうであり、非常に遅いところと、後半でかなり速まるところとがあります。この楽章ではピアノに粘ったルバートの動きも時々聞かれます。 1987年の録音は艶と明るさがあり、きれいです。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Trio Fontenay ♥♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 トリオ・フォントネ ♥♥ 80年代ぐらいまでに出て来ていた大御所たちとは一線を画す新しい世代の演奏です。トリオ・フォントネはドイツのハンブルクで1980年に結成された団体で、メンバーはミハエル・ムッケ(1953-)がヴァイオリン、 ヴォルフ・ハーデン(1962-)がピアノ、イェンス・ペーター・マインツ(1967-)がチェロです。「フォントネ」というのは音大の近くの通りの名前に因んでいるということです。古いフランス語では 'source' の意味があるそうで、泉の意味のファウンテンと語源学的には近いようです。 蒸留水のような、と形容したら味がしないという意味になるかもしれないので、名前の通りの泉の水のような演奏と言いましょうか。そうなると、スーク・トリオを大吟醸みたいと言ったのとどう違うのかという話にもなってしまいます。楽譜通りと言えば褒め言葉にならないけど、活きいきとした呼吸はあっても恣意的な解釈は加えず、端正に進める演奏というものはあります。スーク・トリオが伝統的なスタイルでそういう感じならば、ここでのトリオ・フォントネの演奏は、昔ながらのベートーヴェンの概念に縛られることなく、楽譜から音楽を直接受けとめて感覚的な喜びに従っている、そんな感じです。 新しい世代では後で取り上げるイギリスのフロレスタン・トリオとフランスのトリオ・エレジアクも素晴らしく、個人的には三つ巴で「大公トリオ」のベストだと感じています。より好みなのは後者二つの方ではあるけれども、このフォントネはダイナミックでありながらも余裕の感じられる演奏です。 フォルテで音数が多く、テンポが速いとが音がダマになり、個々の和音構成が分からなくなってがやがやしがちです。昔の演奏はそういうパッセージでも遠慮なく進めることが多かったけれども、昨今は音をずらしたり歩調を緩めたり、少し弱めたりして全体像を見せる手法が多くなって来ました。フロレスタン・トリオとトリオ・エレジアクにはそういう配慮が感じられます。しかしこのトリオ・フォントネの方は、同じように揺らしたり自在に弱くしたりがあるものの、どうやらそれは表現の一つであるようです。この団体は決してやわらかく繊細に行こうとしているわけではないと思います。速度を緩めることなくリズミカルに、強く進めて行くところも特徴的なのです。それはドヴォルザークのドゥムキーでも同じことを感じました。民族調の歌をゆったりと歌ってみせるというより、ストレートに楽譜の持つポテンシャルを発揮する快速な進行がありました。ここでも同じです。蒸留水のようだと最初に言ったのはそんなひたむきな姿勢のことです。そしてありがたいことには録音が素晴らしいので、そういう速くて強めにリズムを叩く場面でも音が濁りません。真っ直ぐ強いところとしなやかに弱めるところの間のレンジが広い名演です。 第一楽章は速くもなく遅くもないテンポで、奇を衒ったところがありません。しかしニュアンスに満ち、リラックスしたゆとりのあるタッチが聞かれます。この楽章は理想的だと思います。フレーズの最後でテンポを緩めたりアタックを弱めたりといった配慮があるけれども、かといってフォルテが混濁することを気にしてそうしているわけではないのは後の楽章を聞けば分かります。歯切れのいいアタックも出て来るからです。勢い込まず、生真面目にも深刻にもならない、肩肘張らないスタンダードな演奏です。大仰な振りが疲れる聞き手には理想的でしょう。 第二楽章も快適なテンポで軽さと明るさがありながら、ここは十分にダイナミックです。切れが良くて大変弾むので、舞踏の聖化と呼ばれた第7交響曲のリズムを思い出させるところがあります。これはカップリングのカカドゥ変奏曲でも同じで、第9の第二楽章に似たパートを歯切れ良く聞かせてくれるのはこのグループの特徴です。引きずるような重さがなく、もたつくところがありません。ロックやポップスに馴染んだ世代でも乗れるでしょう。 第三楽章のアンダンテ・カンタービレは軽快なテンポで案外あっさりしています。でもピリオド奏法の演奏家が緩徐楽章で素っ気なく飛ばして行くのとは違い、よく抑揚が付いていて適度に速いという感じです。健康的な明るい波長であり、ことさら夢想的だったりロマンティックだったりしないのです。個人的にはもう少し静けさがあってゆったりな方が好みではありますが。 中間部ではピアノのタッチがかなり強いところがあります。立体感が出るとも言える意欲的な表現です。後半は抑揚が深まります。 第四楽章も弾むように進行して力強いですが、重く引きずるところがありません。リズムが強調された演奏と言えるでしょう。でもただ走って行くようなものでもなく所々で間を空ける余裕があり、楽しんでいる感覚があります。 1992年のベルリン・テルデック・スタジオでの録音は大変優秀です。恐らくベストの一つでしょう。この人たちの録音は大体いつも水準が高いようで、前述したドゥムキーでもそこが魅力でした。プロデューサーは違っても録音エンジニアは同じ人です。ピアノ、弦の合奏共に強い音でも透明感を維持しており、低音が出ているのですが高い方に被りません。弦楽器は胴が良く鳴っており、艶があります。ピアノも艶っぽく、強いタッチではくっきりとしており、きらっとした音も出る一方で金属的になり過ぎません。廉価版も出たようだけど正規盤のリリースは止まってるでしょうか。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Andre Previn (pf) Viktoria Mullova (vn) Heinrich Schiff (vc) ♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 アンドレ・プレヴィン(ピアノ)/ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン)/ハインリヒ・シフ(チェロ)♥ ピアノのアンドレ・プレヴィン(1929-2019)は大変才能のある人で、ジャズを弾かせてもセンスがいいし、指揮者としても繊細で絶妙な息遣いをオーケストラに伝えることが出来るようです。パートナーの華やかさでもムローヴァと並び、それもこの人の魅力のうちでしょう。ベルリンでユダヤ系ロシア人の家庭に生まれたということで、これまでのところユダヤ系のミュージシャンに対して洗練が見られないとか、否定的なことを言って来たかもしれないけど、この人は天才の部類だと思います。しかも情緒が分からない式ではなく、音楽が生きています。 ヴァイオリンはヴィクトリア・ムローヴァ(1959-)です。ロシアから亡命し、名器による美しい音色を聞かせてくれました。最近はバロック・ヴァイオリンでの活躍も目覚ましく、バッハの無伴奏など、独特の語法で新しい境地を開きました。彼女もジャズに対する理解があるようです。 チェロのハインリヒ・シフ(1951-2016)はオーストリアのチェリストです。ロストロポーヴィッチの代役で有名になったそうで、ここでもよく歌っています。 他が出たから価値が減じるということもないわけだけど、個人的には長らくナンバーワンだと思って聞いていた「大公」です。繊細さがありながら力強いという希有な組み合わせの特徴を持つベートーヴェンで、完成度が高いと思います。♡二つにしなかったのは、第三楽章のゆったり安らいだ部分でもっとうねりつつ揺れてほしいと思ったからです。カップリングのブラームスの方はよりロマンティックに波打たせているので、古典派のベートーヴェンに対する解釈なのかもしれません。好みの問題だけど、個人的には懐かしく夢見るような楽想を感じるところなので、覚醒した美しさのあるこの演奏も素晴らしいけれども、もう少し酔わせてもらいたかったというところです。他の楽章でも、ゆったりかどうかには関わりなく、フォルテの部分以外で全体にボルテージが高いように感じる箇所がありました。p がやや mf 寄りになっているというのか、タッチがしっかりしていて鳴り響いて感じなのです。豪放なのがいい人にはこれでも足りないのかもしれないけど、わずかに単調な強さを覚える瞬間もあります。でも全体としてはニュアンス豊かだし、今でもこの曲のスタンダードな名演として一番の一つだと思います。 第一楽章のテンポは中庸です。チェロがよく歌っており、豊かな抑揚が付いています。勢いと力強さがありながらデリケートなニュアンスが感じられ、場所によってピアノがゆったり間を空けたり一音弱めたりといった繊細な配慮を聞かせます。音色も大変きれいです。 第二楽章はほんのわずかにゆったりめです。そしてリラックスしたスケルツォだと思っているとフォルテの力強さもあります。トリオ・フォントネのように飛ばして素早い連打でリズムを強調するのではなく、丁寧に抑揚を付けつつ曲の構造を表出させます。 第三楽章だけど、所々でわずかなルバートを用いながら十分に歌います。中庸ややゆったりめのテンポで滑らかながら、全体に一つのスラーでつながった大きな波のような抑揚ではなく、小節ごと、楽節ごとに丁寧に抑揚をつけながら進んで行く感じです。でも往年の名演奏にありがちな途切れとぎれの印象はなく、スムーズです。静かに抑えたパッセージも印象的です。後半はテンポが十分に落ちますが、それでも情緒に浸っているという感覚ではありません。しっかり目覚めていて安らいでいるような独特の運びです。 第四楽章は勢いがあり、テンポがかなり速くなります。ストレートで活きいきとしています。この人たちは強い音でダイナミックに運んでもうるさい感じになりません。過度に力を込めたり、強調の区切りを連発したりしないからでしょう。息苦しくなるような演奏とは一線を画します。十分に加速して元気よく終わります。 1993年のフィリップスの録音はいつもながら自然な楽器の艶があり、大変良いバランスです。 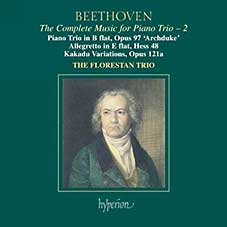 Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" The Florestan Trio ♥♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 フロレスタン・トリオ ♥♥ フロレスタン・トリオは1995年にロンドンで結成された三重奏団で、息の合った活動をして来ましたが、ハイペリオンに数多くの録音をし終えた後、2011年にはメンバーがそれぞれの道を選び、チェロはロンドン・ハイドン四重奏団へ、他のメンバーはソロ活動へと移ることになり、12年に最後のコンサートを開いて解散しています。ラテン語で繁栄を意味するフロレスタンはよく人の名前にも用いられるけれども、シューマンのペンネームでもあります。執筆活動もするスーザン・トムズ(1954-)がピアノ、アンソニー・マーウッド(1965-)がヴァイオリン、リチャード・レスター(1959-)がチェロです。 ベートーヴェンの「大公」の演奏で個人的に一番となると、フランスの新進トリオ・エレジアクとこれかなと考えたりします。このイギリスのグループ、本国以外での知名度がどのくらいかはよく知らないけど実力があり、現代の最も洗練されたピアノ・トリオなのではないかと思います。その持ち味はふわっとした羽のような軽さ、力の抜けたやさしさと温かさです。アットホームな感覚があるのは息が合っていることの証明だと思います。剛毅なベートーヴェンではなく、はっきりとリラックス指向の演奏だと言っていいでしょう。でもゆっくり弱々しくやるという意味ではありません。力強いフォルテはあってもさらっと何気なくて繊細されており、どのパートでも音を慈しみ、楽しんでいます。 比べるならフランスのトリオ・エレジアク(後出)にはゆるやかな起伏があり、滑らかに寄せては返す波に揺られるような心地良さがあります。一方でこちらのフロレスタン・トリオの方は、何でもお国柄でそう言うのもなんだけど、英国紳士の大人の上品さがあり、粘るのではなく、さらっとしています。あるいはピアノが実質的なリーダーなら、ここでの女性ピアニストの資質によって、控え目でありながらも知性と感性の調和が見られるのでしょう。フォルテだからといって無闇に強く叩かずに待つ呼吸はフロレスタン、エレジアク両者に共通するけど、洗練の現れ方は違いますす。究極的には文化や性別は超えられるものではあるにせよ、そういえばトリオ・ワンダラーもフランスで、テンポ強弱の独特の癖が感じられたし、ドイツのトリオ・フォントネには時折ストレートなフォルテがありました。 第一楽章からです。出だしからちょっとためが効いています。やわらかく、テンポは軽快なのに少しも急いだ感じがしません。次の歌に入る前に深呼吸し、一瞬待ってから入るような余裕もあります。フォルテの最初の部分も力んで入らず、弱めてから強くするようなこなし方です。かと思えば、他の演奏では皆が間を空けたりルバートをかけたりするところを均等なリズムで流す場面も目立ちます。それは外しというよりは控え目な音に響きます。イギリス流の洗練でしょうか。 ピアノは軽く鈴が鳴るようで美しく、フォルテの和音もあっさりしています。録音の加減で低音が出ることもありるけど、左手の内声部を右の旋律と同じぐらい強く弾いている箇所があり、全体の構成が分かって立体的です。 弦も軽やかで力が抜けていますが、スラーがかかって滑らかなつながりです。ピリオド奏法ではないのでビブ ラートは使うものの、割と線の細い音です。静かに囁きかけるようなフレーズが印象的です。ピツィカートとピアノのスタッカートの合わせ技は両者が合っていて軽快です。 全体に軽いタッチであり、急に弱めたり、大胆なほど潜行するフレーズがあったりしてフットワークの軽さがあります。感興に即応する敏感さと言いますか。窓を開けて爽やかな朝の空気を取り込んだような気分になります。 具体的にはどう揺らしているかというならば、四つ続きの音符の二番目でわずかに遅らせるようなリズムが心地良いです。例えば第一楽章の頭の部分で説明すると、ここは四分音符4つで一小節なので、ハ長調だとドミシド・ソーとなります(実際は♭シレラ♭シ・ファー)。それがド( )ミシド・ソーとなるような間の取り方なのです。他の箇所で他の演奏者が時折やるような、1フレーズの最後の長音(次の小節の付点二分音符)の前で間を取って最後を強く叩くような重たい強調はやりません。 第二楽章は速い方ではないながら、他の楽章と同様やわらかく音を転がして行きます。力が抜けていてフォルテの立ち上がりが良いので、強弱のレンジの広さを感じます。スケルツォとして弾むところはちゃんと弾むけど、おどけている感じではなく、リズム主体になりがちなこの楽章で落ち着いてパッセージの美しさを聞かせる進行です。最弱音で弦が二音ずつ行き来して揺れるところでは靄のかかったやわらかさがあり、次のフォルテが際立ちます。 第三楽章のアンダンテも最初の入りからさらっとしており、さすがに現代のアンサンブルらしく過剰なロマンティシズ ムには陥りません。でも静かに抑えながらも軽く、やわらかくレガートで延ばして美しく歌います。ピアノの低音が響いて懐かしい感情を呼び覚まします。そして右手がさざ波の音形を出しつつ低弦がメロディーを奏でるところは静かで美しいです。今度は朝もやの残った晴れた高原を散歩しているようです。 弦同士の受け渡しの呼吸は合っており、崩しのセンスが光ります。最後まで溺れることなく、デリケートな陰影を描いていてやすらいでいます。 終楽章も余裕があって楽しい波長が感じられます。力がこもるところでも弦の合いの手がさっと入って愉快だ し、お互いに顔を見合わせて微笑んでいるみたいです。実際に間合いを合わせるのは楽しいのでしょう。一方で静かになる箇所ではぐっと弱め、ひそひそ声になります。最後に向かって速くなるところも楽しくて仕方がない感じです。こうした喜びの感覚はこの曲に相応しいと思います。 ハイペリオンの2002年の録音は煌びやかではなくおとなしい音で、低音がよく響きます。ピアノも派手ではないけど、新しい録音だけに強い音でこもらず、ぴんと伸びた倍音を聞かせます。金属的にはなりません。残響はやや少なめです。ぱっと聞きには渋くて引っ込みがちに感じるかもしれないけど、細部がマスクされることはありません。噛めば味が出るというか、演奏と波長の合った質の高い録音です。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Trio Wanderer ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 トリオ・ワンダラー 1987年に結成されたフランスの三重奏団による演奏で、ハルモニア・ムンディ・フランスから出ているベートーヴェンのピアノ・トリオ全集です。トリオ・ワンダラー、メンバーはジャン=マルク・フィリップス=ヴァイジャベディアン(1965-)がヴァイオリン、ヴァンサン・コック(1963-)がピアノ、ラファエル・ピドゥー(1967-)がチェロです。 これも大変魅力的な演奏です。全体の傾向で言えばゆったり滑らかな方だと言えると思いますが、歯切れの良いフォルテが続くパッセージもあるので、同じフランスのトリオ・エレジアク(後出)よりはいわゆる正統派ベートーヴェン的に聞こえるところもあります。正統的といっても、ディナーミク(強弱)、アゴーギク(揺れ)が小さいわけではありません。むしろ反対の一面があります。ためを効かせ、間もくっきりしています。大胆に表情を付け、洗練均衡から外れることを厭わないのです。共通するのは思い切った表情があっても力んだりしない柔軟性でしょうか。現代的とも言えるかもしれないけど、演奏している自分を観察するもう一人の自分がいるような感覚があります。外連味はあれども往年の巨匠たちとはまた違います。 具体的にどんな表情があるかというと、一まとまりのフレーズの最後で力を抜いて遅くしたり、反対に最後で強いアクセントを付けて盛り上げたりが目立ちます。つまり語尾に個性的な表現が盛り込まれるのです。一方でフレーズ全体で力を抜いて囁やいたりする大胆な計画性もあります。そうした静けさへの傾斜はフランスの演奏者と聞くと納得するところもあります。昔のパイヤールの演奏にもそんな具合にブロックごとに極端に弱めるやり方がありました。 弦には時折テヌートが目立ちます。滑らかに弧を描くようにつなげるレガート/スラーではなく、抑揚を抑え気味にして同じ音の強さで切れないようにつなげて行く、いわゆるテヌートです。それがノン・ビブラートで静かに鳴らされるとまるでピリオド楽器のように聞こえます。ボウイングの圧も強くないでしょう。ヴァイオリンだとバロック・ヴァイオリンのように細く繊細な倍音に聞こえるときもあります。そしてその音でやわらかい抑揚で弾かれるとぞくっとします。楽器はグァルネリウスということです。エレジアクがたっぷりとしたビブラートをかけてピリオド奏法に興味がなさそうなのに対し、このトリオ・ワンダラーの魅力はこうしたビブラートを抑えた弦の音 にあるかもしれません。全体にピリオド奏法的だとは言えないにせよ、ヴァイオリンが一音の中で大きく強める表現も見られます。また、何音かにまたがるクレッシェンドでは短い間に盛り上げるダイナミックなところもあります。古楽の奏法を知ってる世代です。 アンダンテ・カンタービレの第三楽章ではこのグループのそんな美点が現れていると言えます。 弦にミュートがかかったような静けさがあり、前述のテヌートでつながる独特の旋律線も目立つし、何より表情がよく付いています。出だしからゆったりではないにしても美しく歌い、かといって往年のトリオによる力の入った叙情性とは違い、どこか覚めたところもあります。途中、ピリオド奏法的な盛り上がりの抑揚が加わる部分もあり、ピアノが軽く律動的に弾み、リズム主体の曲であるように進める箇所もあります。名前の通り彷徨い歩くワンダラーとでも言うか、トリオ・エレジアクよりマインドが勝った表現に聞こえます。 2010年の録音は残響は少なめだけど魅力的です。奏法のせいもあるでしょうが、弦は前述の通り艶よりも繊細な倍音を感じさせるものです。一方でピアノの音はシルクのようなやわらかさが印象的で、強い音で芯は出るけれどもきらきらする傾向はありません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Trio Élégiaque ♥♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 トリオ・エレジアク ♥♥ トリオ・エレジアクはチェロのヴァージニー・コンスタンが2001年に創設したフランスのピアノ三重奏団 で、ヴァイオリンはローラン・ル・フレシェ、ピアノはフランソワ・デュモンであり、この録音のときもその創設メンバーでした。2014年以降はヴァイオリンが交代してパリ管弦楽団のコンサート・マスター、フィリップ・アイシュになったとのことです。このトリオの名前に関してですが、ラフマニノフの初期のピアノ三重奏曲に「悲しみの三重奏曲」と訳される同名の二作品があります。エレジアクの言葉の意味は英語の elegiac 、エレジーと同じで、哀歌、挽歌(死を悼む歌)です。比較的新しいトリオで、CD もこのベートーヴェンの全集が評価を受けているという段階で他にたくさんあるというわけでもなく、将来を期待されるグループでしょう。今回の録音は様々なソースから廉価版を出しているブリリアント・レーベルから直接出ています。 ベートーヴェンの「大公」の CD の中で個人的に一番だと思った演奏です。と言うとフロレスタン・トリオのところで言ったことと同じになるけど、知名度はまだ高くないトリオにせよ、これほど自然で自発的なパフォーマンスも滅多にないでしょう。やわらかい生きた呼吸が感じられる名演だと思います。好みを除いて演奏に対しての客観評価などということはあり得ないわけだけど、その好みの点では♡を三つ付けたいぐらいです。同じフランスではハルモニア・ムンディから出ている先輩格のトリオ・ワンダラー(前掲)があって知名度から行けばそちらが上でしょうが、気を張った部分と計画性がない分、こちらのエレジアクの方が乗れました。男振りのベートーヴェンが好きな人には物足りないかもしれないけど、フランス郊外のゆるやかな丘陵の連なりを思わせるような、しなうように滑らかな歌わせ方が美しいです。力まず引きずらず、ピアノには適度な軽さもあります。アゴーギクの面では慌てず急がずで、間の取り方にも余裕があります。ディナーミクについては何と言うか、一番きれいに鳴る音の強さを意識しているかのようであり、感情の押し付けは無粋といわんばかりにエレガントです。フロレスタンのイギリス紳士的に控え目な洗練とは違ってそこはかとない官能もあります。 具体的に見ます。第一楽章のテンポは速くも遅くもないけど、余裕が感じられる分ゆったりに聞こえます。やわらかい抑揚が付きます。クレッシェンドで盛り上がるところで前のめりにならず、新鮮な空気を呼び込むように間を緩めます。その結果音が濁らず、きれいに和音が聞こえます。フォルテで一音を強調する場合も同様で、力まかせにせず一旦呼吸を置いて鳴らします。大きな間の後の強烈な音というやり方ではありません。大仰さがなくて自由な空気を感じます。一瞬で力を抜いて弱めるところもあり、音と戯れているようです。ピアノは艶があり、鈴が鳴るようなトリルも印象的です。ピリオド奏法ではないので弦にはしっかりとビブラートがかかっています。そして良く鳴って滑らかに歌うチェロもこの楽団の魅力です。 第二楽章のスケルツォも走らず、力で押さずで軽妙です。やかましくないので耳が聞きに行きたくなります。軽く弾むピツィカートが美しく、各パートが分解されて明快に聞こえます。低音でピアノが刻む持続音が浮き出したりするところもあります。 アンダンテ・カンタービレの第三楽章です。ここも自在でやわらかい表情が付き、リタルタンドもあって臆することなく情緒的だけど、過剰なロマンティシズムではありません。伸び縮みする歌に任せて静かで満ち足りた感覚を覚えます。初めは遅過ぎないテンポで、後半ではかなり遅くなってしっとりと聞かせてくれます。各フレーズと一音の配置にニュアンスがあります。速度を緩めるときも自在に揺れながら自然に遅くなり、ピアノの微かなルバートが絶妙です。途中でフォルテになるところは大変強いながら鮮やかで、弱音との対比が印象的です。 終楽章もゆったりながら間延びしない表情があります。やはりちょっとしたルバートがかかり、ゆとりが感じられる運びです。ピアノが粒の揃った音で明るくきらめくと同時に、速い楽章にもかかわらず静けさがあります。この楽章の美しさに初めて気づかせてくれた気がします。そしてラストに近づくにつれ、喜びが込み上げて来ました。なかなかない体験です。 アイルランドで収録された2012年のブリリアントの録音です。サウンド・エンジニアはフレデリク・ブリアンとなっています。ピアノはしっとりしていながらフォルテでは艶と共にきらっとした強さも出る好録音です。トリオ・フォントネ盤ほど前へは出ませんが、台風の後で霞みが飛んだようにクリアです。またフロレスタン・トリオ盤よりも響きが明るく、弦も潤いがあります。このレーベルは廉価なのでデュアル・ジュエルケースの五枚組ではあっても一枚ちょっとの値段で買えてしまいます。「大公」だけが欲しい人にも良いでしょう。ベートーヴェンのピアノ・トリオが網羅されていて作品1などの心地良い曲も聞け、珍しいところではあの緩徐楽章が美しい名曲、第2交響曲をピアノ三重奏にしたものも入っています。 ピリオド楽器による演奏 ピリオド楽器によってピアノ三重奏を演奏することのメリットは音色の美しさに限ります。バロック・ヴァイオリンは照り輝くような艶の面では劣るものの、その細身で繊細な倍音が魅力的です。チェロでも同じことが言えるでしょう。ただしフォルテピアノとなると微妙な場合もあります。モダン・ピアノは進化している分、フレーム強度が高くてよく響きます。でも古典派時代のフォルテピアノの録音は、典雅だけど木琴のような、あるいはアルミパイプ鉄琴の子供用ピアノみたいな音になる場合もあります。そこへピリオド奏法の独特のアクセントが乗って来るので落ち着けないこともあるでしょう。 そんなわけで、下記にモダン楽器による演奏と分けて取り上げることにしました。ピリオド奏法のアクセントについては学問的な部分には言及しないし、強いものは個人的に好みではないので、盤によっては個々の違いについて詳しくは触れません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" The Castle Trio ♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 キャッスル・トリオ ♥ キャッスル・トリオは1984年に結成されたアメリカ人の団体で、活動拠点としてワシントン DC のスミソニアン室内楽協会に席を置いています。ここでの楽器がすべて同博物館所蔵のものかどうかは分からないですが、楽曲に適切なピリオド楽器を用いて演奏することを主眼にしているようです。ピアノは1824年製のコンラッド・グラーフに倣って1984年に製作された R・J・レジエ、ヴァイオリンは1670年のアンドレーア・グァルネリ、チェロは1708年のカルロ・アントニオ・テストーレとあります。演奏しているのはランバート・オーキス/オルキス(1946-)がピアノ、マリリン・マクドナルドがヴァイオリン、ケネス・スロウィック(1954-)がチェロです。 ピリオド楽器による「大公」の中で何が良いか、個人的な好みを言わせてもらえばこのキャッスル・トリオか ラルキブデッリ盤かということになります。録音が少し気になることを除けばイザベル・ファウストたちの演奏も素晴らしいと思います。キャッスル・トリオがいいのは、ピリオド奏法にもかかわらず第三楽章のアンダンテ・カンタービレがゆったりと進められるところであり、アンナー・ビルスマとインマゼールのラルキプデッリがいいのは爽やかな高揚感があり、強いアクセントがなくて洗練されているところです。ピリオド奏法のアクセントがあるとその分だけそれ以外の抑揚を削るので、選ぶのが難しくなります。 このキャッスル・トリオ、気になる部分は何かと言うと、些細なことだけどピアノのアクセントで一カ所、ト長調に変わった後の第一楽章53小節目で、「シシシラ・ソソソ#ファ・ミミミード」の最後に来る「ド」の音の前で長い間を空け、そのドを思い切り強く叩いて強調するところです。これがどうも、何回聞いても馴染めませ ん。その後でも繰り返しで同じ音が出て来ます。波形編集でクロスフェード設定にしてコンマ何秒かカットすれば普通のアクセントに出来るけど、アイドル・タレントの CD デビューではありません。確かにスフォルツァンド・ピアノ(sfp)が付いてるのでそこだけ強くしてまた弱めるのは間違ってないし、チェロのパートにはスラーがあるのにピアノにはないので区切りを付けるのも分かるけど、ここまではどうかなと感じた次第です。他の箇所でもこのピアニストはフォルテで概ねそんな風に間を空けて強く叩く強調をする傾向があります。エレノア・ソコロフに師事したということだけど、それが恐らくこの人のピリオド奏法の語法でもあるのでしょう。気になるのはそこだけで後は素晴らしいと思うけれども、繰り返し強く表れて来るとそれだけ拍が固定的になって自由が奪われる気がしないでもありません。 でもありがたいこともあります。このアメリカの古楽グループはヨーロッパの人たちとは若干アクセントの解釈 が異なるのです。弱音のパートでゆっくりと弱く、リズムに誇張を入れずに進めるところがあって、それは一般的なピリオド奏法の解釈とは違って静かで良いですし、トータルで癖が少ないか、その方向が気になりません。 何よりも、この曲で最も好きな第三楽章のアンダンテ・カンタービレは、ピリオド楽器による演奏の中でこの 団体が良かったです。決して速くやろうという気はなく、十分に歌ってくれます。小節後半の拍を短く切り上げてロマン派と呼ばせない覚醒した雰囲気にする意図はなく、十分に延ばしてくれるのです。ときどきアタックが強いところもあるけど、たっぷりとしていて音に浸れます。つまり静かに歌う部分では癖が少ないわけです。古楽器の音を味わえる最善のアンダンテでしょう。表現の幅が大きい分だけ陰影も深いです。 一方でスケルツォは速く軽快で、第四楽章は比較的遅めながら柔軟性に飛んでいてもたれません。 ロンドンで収録された EMI/ヴァージン・クラシックスの1990年の録音については、ピアノの音はきらきらしません。フォルテピアノのひなびた軽い音の響きはあるけど案外モダン・ピアノに近い音にも聞こえます。弦は強いところで野太さが出たり、わずかにクリップ気味に濁るところもあった気がしますが、5キロヘルツ辺りの高域が強く輝く録音バランスのせいでそう聞こえるのでしょう。倍音は繊細です。トータルで懐かしい感じの良い音です。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Tröndlin Trio ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 トレンドリン・トリオ トレンドリン・トリオはベルギーの団体で、トレンドリンというのは19世紀前半のドイツ、ライプツィヒの フォルテピアノ制作者の名前です。ここで使われているのは1820年頃にウィーンで製作されたグラーフのレプリカということです。トレンドリンではないようですが、作り手のトレンドリンも南ドイツとウィーンで製作を学んだということで、ウィーンという点では共通性があるのでしょう。メンバーはピアノがベルギー人のジャン・ヴェルメレン/ヤン・フェルメレン(1954-)、ヴァイオリンがピーター・デスピギュラー/ペーター・デスピヘラーレ、チェロがカレル・ステイラーツ(1964-)です。 第一楽章では二拍目を強くするアクセントなど、ピリオド奏法の語法が見られます。演奏自体はやわらかく静かという方向ではなく、アタックの強いくっきりとしたものです。 第二楽章のスケルツォはスタッカート気味の強調されたリズムでよく弾みます。拍ごとに区切られた感じがあるけれども、静かな部分ではゆっくりとうごめくような表現も見られます。 第三楽章もアクセントが強く、二拍目が強いときもあります。速めのテンポで走るフレーズも見られます。 第四楽章のテンポは遅めですが、よく区切られたアクセントはここでも健在です。強い音でダイナミックな表現 です。 エトセトラ・レコーズ1999年の録音で、ベルギーの教会で収録されました。1982年設立のアムステルダ ムのレーベルです。フォルテピアノの軽い音が魅力的です。ぴんと響く、最もフォルテピアノらしい録音と言えるでしょう。一方でヴァイオリンはあまりバロック・ヴァイオリン的な細い倍音が目立ちません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Jos van Immerseel (pf) Vera Beths (vn) Anner Bylsma (vc) ♥ ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ラルキブデッリ: ヨス・ファン・インマゼール(ピアノ)/ ヴェラ・ベス(ヴァイオリン)/ アンナー・ビルスマ(チェロ)♥ ピリオド楽器を使用するものの中でいかにもピリオド奏法というアクセントが少ない方であり、高揚する盛り上がりが聞けて心地良い演奏です。ピアノのインマゼールの性質か、さらっとしていて敏感で、良い意味でのクールさを感じる瞬間もあります。語尾を延ばさないこともあるでしょう。インマゼールは古典派の作品ではこういう傾向が顕著で、ロマン派ではゆっくりになってもう少しまったり歌わせるように思います。そしてこうしたちょっとクールな運びはシューベルトの「ます」などでは大変ありがたいものです。ピアノ五重奏は楽器が多くて元々音が濁りがちだし、特に「ます」の場合、ピアノが重かったり合奏が力一杯だったりすると曲自体が嫌になるので、このグループの人たちの演奏が救世主でした。シューベルトの甘い歌謡性もすっきりまとまってベスト盤という感じです。そして同じような意味でここでのベートーヴェンもいいです。人によっては軽くさっぱりし過ぎだと言うかもしれないけど、この爽やかさが癖になります。ピリオド楽器による演奏で最も洗練されたものだと思います。 第一楽章はビルスマの伸びやかなチェロがよく響きます。ピリオド奏法の呼吸はきつくはないので気にならない けど、小節内の不均等な揺れは少しだけあります。弦にやや大きめな山なりの強弱が出ることもあります。ピツィカートとピアノが合わさるパートには工夫が感じられます。小気味よく走るところもあり、テンポは速めで颯爽としています。 第二楽章のスケルツォは力が抜けており、アクセントがはっきりしていて軽快です。 第三楽章は速過ぎはしませんが、どちらかというと速めのすっきりした運びであり、やはりさらっとしています。目覚めていて感傷的にならない爽やかなアンダンテです。前半ではもう少し浸りたい気持ちになるけど、後半で遅くなる部分では清涼感がありつつ味わい深いです。短くふわっと盛り上がってはすっと弛まる抑揚が高揚感をもたらします。同じピリオド楽器によるキャッスル・トリオとどちらを取るかは悩むところで、第三楽章に限って言えばゆったりのキャッスル・トリオがいいと思うときもあれば、こちらの高揚感を味わいたいときもあります。ピリオド奏法の強弱は若干あるけど、それが良い具合に現れていると思います。 第四楽章も明るく軽快で、弾むようなリズムが心地良いです。 1999年の録音です。弦はピリオド楽器らしい細い音で、ピアノの響きには軽さがあります。でもモーツァルトでよくあるようなアクションのノイズが聞こえるほど控え目な音ではなく、もう少し今のピアノに近づいています。これは他のピリオド楽器の演奏者でも同じで、ベートーヴェンの頃のものはそういう感じです。中域にきれいな残響が乗ります。カップリングの「幽霊」がまた録音が良く、演奏もこの人たちのには他では聞かれない魅力があってベスト・パフォーマンスに思えて来ます。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Isabelle Faust (vn) Alexander Melnikov (pf) Jean-Guihen Queyras (vc) ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 イザベル・ファウスト(ヴァイオリン)/ アレクサンドル・メルニコフ(ピアノ) ジャン=ギアン・ケラス(チェロ) まず最初に、演奏が素晴らしいです。でも初めに聞いたときにちょっと違和感を感じてボリュームを絞りました。どうやら音の問題のようです。ハルモニア・ムンディ・フランスの録音はいつも優秀だけど、今回は残響が少なめで中高域が張った音です。そのせいでピアノもチェロも強い音で前へ出て来ます。チェロは乾いた感触の音色であり、ファウストのヴァイオリンもいつもより鋭い印象です。 そしてこの音で聞くと普段気づかない部分に目が行きました。それは主に第二楽章と終楽章の一部でフォルテになるパートでの拍の処理なのだけど、間を空けて強調するのとは反対に、詰めて前のめりにするフレーズが出て来ます。ピリオド奏法ではよくあることながら、この人たちの演奏ではあまり感じなかっただけにどうしたのだろうと思いました。そしてその上で中高域が張った音だったのでボリュームを絞ったのだと思います。 そういうことが気になったのは期待が大きかったからでしょう。ファウストのヴァイオリン協奏曲やソナタの「春」、クロイツェルは気に入っています。線の細いビブラートを抑えた音で、クールに張りつめつつも穏やかさも感じさせる独特の空気感があります。あの魅惑的な音を欲していたのです。でもピアノ三重奏はピアノに重心があります。ベートーヴェンがこの曲を献呈した大公はピアノの名人だったし、初演ではベートーヴェン自身がピアノのパートを力一杯弾きました。したがってここでの主役はメルニコフです。そして今回の録音では現代のスタインウェイではなく、ベートーヴェンが亡くなった頃のフォルテピアノが使われています。メルニコフ自身の楽器のようで、気合いです。そしてそのせいもあってか、普段よりピリオド奏法的なのです。前述の通り拍を速めて前のめりにすると熱い演奏に感じるので、それが好きな人も多いでしょう。個人的にも音の問題がなければ悪くないと思います。 第一楽章ですが、メルニコフに節度のあるピリオド奏法の呼吸が見られます。スタッカートも軽く扱っていていいと思います。分散和音で鳴らす試みも見られます。弦を伴っての漸進的なクレッシェンドが心地良いです。独り駆け上がるところ、トリルで下がるところで当時のピアノの音が典雅に響きます。全体的に軽さがあり、間もゆったりと取れています。 第二楽章のスケルツォは速過ぎないテンポで軽く弾みます。弱めて強めるピアノの呼吸がリズミカルです。使っている楽器の違いでこうして弾き分けられるメルニコフの臨機応変さに感心します。 第三楽章のアンダンテ・カンタービレのテンポは、出だしではやや軽快です。タッチも優しく軽く、ゆったり間が取れているところがいいです。途中から大変ゆっくりになって来るけれども、それでも爽やかな運びであって夢心地ではありません。それがまた大変いい味を出しています。さざ波の中を進んで行く、ピリオド奏法のスパイスがかかった個性的なアンダンテです。キャッスル・トリオやインマゼールとどっちが良いだろうと、ちょっと悩むところです。 第四楽章も軽く弾むところがスケルツォと同じです。テンポは速くはありません。軽さがあって力みもありません。ラストは駆け上がって行きます。パソコンの小さなスピーカーで聞くと全然気にならずに楽しめるので、もったいないから録音バランスをイコライザーで調整したくなります。 録音は2011年です。音についてはすでに書た通りです。トータルでは決して悪いものではないでしょう。フォルテピアノの音色は想像とはちょっと違いました。弦の張力の低いこの楽器はモーツァルトなどで聞かれるものと基本的に構造は違わないのかもしれないけど、ここではもう少し現代的な音に聞こえます。強弱もはっきりしています。フォルテピアノとモダン・ピアノの中間ぐらいで、強い打鍵でも金属的にはならないものの、艶があって輪郭もくっきりしています。そしてバランス的にはこれも中域のしっかりした音であり、ジャズ・ピアニストが好んで出す艶っぽい音に似てなくもありません。  Beethoven Piano Trio in B-flat major op. 97 "Archduke" Storioni Trio ベートーヴェン / ピアノ三重奏曲変ロ長調 op. 97「太公」 ストリオーニ・トリオ 1995年にアムステルダムで結成されたピリオド楽器によるトリオです。新しい世代ですが、はっきりとしたピリオド奏法の呼吸が見られます。ピアノはバート・ヴァン・デ・ロエ(1972-)、ヴァイオリンはウーター・ヴォッセン、チェロはマーク・ヴォッセンです。 第一楽章はオランダの人たちのピリオド奏法と聞いて思い描く通り、特定の拍の強調があり、揺れも割合大きめです。所々で駆け出すパッセージもあります。フォルテでは歯切れ良く力強いです。 第二楽章は活気と力強さがあり、ピツィカートもよく響き、ピアノの音が歯切れ良くきらきらしてきれいです。 第三楽章ですが、緩徐楽章で快速で飛ばすピリオド楽器の団体が存在する中で、ゆっくりの部分はなかなかゆっくりです。やはり不均等な間と揺れがあり、癖は結構感じます。弦は若干引きずりながらテヌートでつなぎ、ピアノは強い打鍵が目立ちます。中間の展開部では走り出すところも現れます。そういう箇所では速いながらもショ パンなみのルバートも聞けます。そしてまたゆっくりに戻って終わります。 第四楽章では速度こそ特急ではないもののリズムが不均等なので、ピアノのスタッカートが連続する展開など、ちょっとスケルツォ的な楽しさがあります。 チャレンジ・クラシックス2012年の録音です。新しいだけにピアノがきれいです。軽くて明るいフォルテピアノの特徴が最もよく出ている盤だと思います。高域がはっきりとし、目の前に出て来ます。いかにも好録音という感じでオーディオ的に面白いかもしれません。弦はときにきつめに感じる場合もあります。 INDEX |