|
Pathétique
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」聞き比べ  取り上げる CD23枚: チェリビダッケ/カラヤン('71/'76/'84/'88)/ムラヴィンスキー/ショルティ/ハイティンク/デュトワ /ヤンソンス(バイエルン放響/オスロ・フィル)/ネルソンス/ゲルギエフ/ミュンフン/アバド/ジュリーニ/フリッチャイ/マルケヴィチ /オーマンディ/ノリントン/ティルソン・トーマス/クルレンツィス/ネゼ=セガン 交響曲第5番 op.64 三大バレエ組曲「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」 幻想組曲「ロメオとジュリエット」 CD 評はこちら(説明を飛ばします) 人気のチャイコフスキー
アメリカで一般の人にクラシック音楽の話題を振るとほとんどがチャイコフスキーのことを思い浮かべるようであり、それは多分夏のタングルウッド音楽祭で「1812年」序曲の大砲を毎年撃つからじゃないか、などと適当なことをすでにどこかで書きました。あるいはピアノ協奏曲がボストンで初演されたからかもしれませんが、いずれにせよクラシックを代表するほど人気のある作曲家です。そしてその序曲に加えて、今やディズニー映画によって英語タイトルまで流通している三大バレエ組曲、スリーピング・ビューティー、スワン・レイク、それにクリスマス定番のナットクラッカー(眠れる森の美女/白鳥の湖/くるみ割り人形)、前述のピアノ協奏曲第1番、第4〜6番の交響曲などがこの作曲家の有名曲です。
その代表作
中でも第6番「悲愴」は最後にしてこの人を代表する重要な作品でしょう。このページでもいつかはやらねばと思いつつ、実は腰が引けてました。あらためて聞き直してみると、やっぱり名曲です。弦楽四重奏の「アンダンテ・カンタービレ」はすでに取り上げていたのですが、悲愴については壮大過ぎてたくさん聞き比べるだけの勇気が奮い立たなかったのです。美しい音楽ではあるものの、作品には固有のバイブレーションがあり、これは何よりも絶望の曲でもあります。それを抽象的に表すならマーラーとか何とか、他にいくらでもあるでしょうが、なりふり構わず明言してるのはシューベルトの「冬の旅」か、この「悲愴」ぐらいでしょう。絶望を感じさせるものには日常の幻影を吹き飛ばしてくれる威力もあるのですが、それに対峙するにはこれまで相応のエネルギーが要ると思ってました。ゴッホの「星の夜(星月夜)」を見たいと思ってニューヨーク近代美術館に行ったとき、思いがけず隣の大きなモネの睡蓮の方に安らぎを覚えたことがあります。命を削ったような孤独を感じさせる作品はこちらもそんな気持ちにさせるものです。そしてこの曲も、最後が死ぬように静かに終わるという形は前代未聞であり、ファンだったマーラーが自身の第9交響曲の終わりで真似て、「死ぬように」と実際に楽譜に書き込んでいるぐらいなのです。本当にそういう曲かどうかはともかくとして。 絶望と自殺は直接的に関係があります。うつ病というもの、現代では二週間続くと誰でもそう診断されてしまうけれども、チャイコフスキーもそうだったとされます。双極性障害という意見もあって、こういうのは分かったようで分からない話です。ゴッホもそうだし、一代で会社を大きくした社長さんたちも皆、気質分類的に言えば同じことになるのでしょう。自殺についてはどうかというと、その説も一時期ありました。ゲイであることが発覚して司法に強要され、砒素を飲んだとされたときがあったのです。死因については現在は以前からのコレラ説の方が有力だそうですが、これらの考えは何度も入れ替わって来ており、歴史というものは過去の出来事に仮説を立てて作り直したりしますから、また変わるかもしれません。 「悲しい」の正体
一方でチャイコフスキーは死を大変恐れていたという話もあります。当たり前だけれども、恐れないで自殺したアーサー・ケストラーという作家もいたりはするわけです。死は存在のエネルギー的変化であるに過ぎないと言って服毒自殺を計りました。その考えはいいとして、同時にいわゆる「死に至る病」でもあったので同情の余地もあります。 それで思い出されるのは実存主義的な「絶望」です。仏教の「一切皆苦」とどのぐらい一致するんだろう。もうこの地上には戻って来ませんという段階まで来てるなら自殺はしないことでしょう。他人の気持ちは分からないけれども、チャイコフスキーの絶望はどちらでもなさそうにも感じます。「悲愴」を聞くと、どこか人懐っこさを感じるという人は多いのではないでしょうか。大抵の人間にとっての絶望は「存在そのものに組み込まれた苦に気づく」というようなことではなく、現象的には概ね、仕事か愛情の問題に還元されるものです。破産して生活できなくなる恐れや過労、ケストラーのような深刻な病気や幻覚の命令以外では、人が死を考えるほど悩むのは孤独感やパートナーに関係する情愛の問題がほとんどです。チャイコフスキーが同性愛者であったことは、ロシアの愛国心に訴えるあのプーチンですら認めている事実であり、偽装結婚が破綻した後にモスクワ川(ヴォルガ川支流)に腰まで浸かって凍死しようとした話は有名です。ちょっと太宰治みたいです。 彼らの悩みには今も昔も性的マイノリティにしか分からない過酷な一面があるのでしょうが、「悲愴」で感じる悲しみには、どっぷりと浸かりたくなる独特の甘い雰囲気も含まれているように思います。それは同時に親しみやすさでもあり、長らく彼の音楽の特徴とされて来た叙情的メランコリー、あるいはロマンティック、もしくはセンチメンタルさの本体です。「ロマンティック」というのは語源学的には恋愛感情に関係する言葉です。すでに名前を出したので比べてみると、色恋沙汰で有名だった太宰治にもちょっと似たところがあります。ゲイなら三島由紀夫の方かもしれませんが、そこはまたメンタリティが違います(ここに名前を出した人は診断上は皆同じ範疇に入れられてしまう可能性もあることでしょう)。
太宰には独特のシニシズムがあります。鋭い批判精神を隠して笑顔で近寄るような人懐っこさがあり、そこに独特の甘さが加わります。身近な女性たちがそうだっただけでなく、多くの人が魅惑されるポイントです。自己憐憫と言うと言葉が悪いので自己陶酔としておきますが、チャイコフスキーにも同じようなシニカルなところ、眠い聴衆を驚かせるピアニシモからの突然の金管の炸裂などがある一方で、すすり泣きながら絶望に酔う心地良さがありはしないでしょうか。そして、そんな風に演奏する例が多いかと思います。 本人の死と同じ頃に発表された「人間失格」は文学であって、映画にすると別物になります。それは巧者で陶酔的という意味でちょっと似た雰囲気のあるフィッツジェラルドにしても、ゲイで太宰が好きだったというカポーティにしても同じだけれど、映画のように時間の流れが提供される音楽はよりダイレクトに感情を味わうことができるので、語り口の上手な「悲愴」は我々を心地良く酔わせてくれます。そういう性質に従ってロマンティックに、またマーラーのように演奏するということが長らく行われて来たわけです。つまり極度に遅くしたり、大きな抑揚を付けたり、音を長く延ばしたりということです。もちろん、それを嫌って学究的にやる指揮者の中には、作曲者の速度記号にこだわった原典主義を貫き、古典派のように演奏する人もいます。 虐待経験?
近年の研究においては、主にアメリカでのことですが、太宰の作品は性的虐待を受けて来た人の文学だと捉える風潮があるようです。乳母や下女、下男かららしく、それが文体にも表れているというのです。一方でこれも #MeToo 関連のアメリカでの流行において、ゲイであったチャイコフスキーは少年に性的虐待を加えていた側だという主張もあります。PC 運動と同じで行き過ぎるとおかしなことになるものの、面白い共通点ではあります。虐待は連鎖するし、加害者と被害者は同じ問題を共有しますから、両者に同じ心理的特徴が表れていてもおかしくありません。虐待の加害者も被害者も、受け入れられていないという孤独な感覚では共通しています。それなら、自己憐憫と罪悪感が背中合わせになっていることや、表面的に取り繕う癖、後年の性的放蕩なども虐待に関係する心理だということでしょうか。チャイコフスキーの心的傾向の根底にあるものについては憶測の域を出ません。虐待を受けたという記録があるわけではなく、分かっているのはゲイであって少年と関係したことだけです。しかし同性愛についても(現在の社会的受容の環境においては)同じことが言えるのかもしれません。罪悪感や自分をシニカルに嘲笑する感覚は社会通念に対して性的欲求が真っ直ぐではないという本人の自覚に関係があるかもしれず、孤独感と自己憐憫はありのままに受容されなかったことに関連するかもしれません。これは性的虐待にも性的マイノリティにも等しく関わり得る問題です。間違えてはいけないのは虐待が同性愛の原因だとする考えで、これは完全に除外する必要があります。
しかしここまで言っておいてなんですが、これって何も性的オリエンテーションや虐待に付随する問題などではなく、愛されること一般のテーマではないでしょうか。ありのままに愛され、受容されていないという感覚や孤独感は誰しもが人生の一時期に感じ得ることです。自我のあり方に関わる度合いの高い芸術にとっては、どの作品も個々にテイストが違うだけであって、太宰治やチャイコフスキーに共通して感じられるどこか甘い麻薬のような感覚も、取り立てて言うほど特殊なものではないとも言えます。 「悲愴」は苦しみを理解してほしいと訴えて来るように聞こえますが、苦しいとはいっても一般にほとんどの苦しみは肉体的な痛みとは違い、その瞬間には存在しません。それは往々にして自らが苦しみだと定義づけた経時的なシチュエーションの中に沈み込んで行く誘惑に落ちることであって、そうした誘惑を感じるのは、よほど突き抜けでもしない限り我々の置かれた普遍的な状況です。音楽には瞬間に永遠を見るようなインスピレーションから創られるものもありますが、ロマン派以降に比重が大きくなってきたのはこうした自我感情の発露の部分であり、それがさらに進むともはや感情でもなく、知性によって作曲する種類の現代音楽へと至ります。それも自我拡大という観点から見れば同じ一つの流れとしての成り行きなのです。
チャイコフスキーの略歴
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーの略歴ですが、1840年にモスクワからシベリア側の内陸に入ったウラル地方で鉱山技師の家庭に生まれ、小さい頃から音楽に興味があってピアノも弾けました。その後法律を勉強して役人になり、本格的に音楽を学んだのは二十一歳になってからであり、その四年後には音楽理論の講師になっていました。未亡人のパトロンがいました。ムソルグスキーやボロディン、リムスキー・コルサコフなどの民族楽派五人組には入らず、その 影響を受けました。
「悲愴」Path?tique は作曲者が付けたがっていた名前であり、人生そのものを扱った作品だと言っていたようです。生涯で最高の出来映えだとも語っていました。そして五十三歳時の1893年、初演された九日後に亡くなっており、曲はその翌日にも演奏されました。太宰の「人間失格」と同じ構図です。因みにフランス語の Path?tique は英語の Pathetic とは違い、ただ悲しく痛ましいという意味ではなく、「崇高な」という肯定的なニュアンスも含まれるようです。この語はチャイコフスキーの「悲愴」に何らかの光を当てるでしょうか。一度作られた作品は受け取る側に解釈の幅を与えます。案外思いがけない一面が隠されているのかもしれません。 楽曲構成 これについては大変技巧的な曲だということもあり、素人に解説できることはほとんどなさそうです。作曲家としてオーケストレーションの妙という話になるといつもベルリオーズやラヴェルの名が挙がりますが、チャイコフスキーもなかなかのものだそうで、その才能もあって前述のように音楽を本格的に勉強し始めてたった四年で音楽理論の講師になるほど理解が速かったのでしょう。 第一楽章は第四楽章と並んで人気があり、かつ重要な部分です。曲全体の構成と同じように静かに始まり、途中で盛り上がってまた静かに終わるのですが、悲愴ではなく悲壮感漂う重い進行にロマンティックなアロマがブレンドされてるように聞こえることが多いです。したがってどの演奏者も特に念入りにここを調整しています。中程には寝ている聴衆をびっくりさせるような突然の大音響が仕組まれています。
第二楽章は何気なく聞くとワルツで、よくあるパターンだなと思って拍子を数えると3ではなく5だぞということになる不思議な曲です。ロシアの舞曲にはよく見られるものらしいですが、一般に五拍子と言えばジャズの「テイク・ファイブ」でしょう。コマーシャルにも使われたので誰しもが耳にしたことがあるに違いありません。 作ったデイブ・ブルーベックはジャズメンの中でも高い教育を受けた人で、ミヨーの弟子でもあり、アフリカ系のビバップのプレイヤーが即興命なのに対して、作曲能力が高かったので「プロフェッサー」の異名を取るほどでした。その曲は五拍子のものとして最も認知されたナンバーとなりましたが、それ以前の五拍子ともなると、悲愴のこの第二楽章が有名なものとしては最初じゃないでしょうか。これは当時としては先進的なことであり、チャイコフスキーの技法はそのようにリズムに対するセンスが特に秀でたもとなっています。
第三楽章は悲愴というより皮相的な元気の良さを見せるスケルツォで、ある種躁状態であるかのように明るく、途中からは騒々しいほどの元気良さを見せます。騒々しいはちょっと言い過ぎだとしても、金管が印象的なばりっとしたメロディをファンファーレのように吹き鳴らすものであり、こういうドラマティックな音遣いは有名なピアノ協奏曲や4番の交響曲の出だしでも見られる、この作曲家の一大特徴である気がします。人気の秘訣という意味ではジョン・ウィリアムスみたいでもあります。逆にハリウッドの映画音楽はチャイコフスキーやストラヴィンスキーにルーツを持っていると言えるのかもしれません。
第四楽章は前述の通り、第一楽章と同様にこの曲の嘆きの情緒を決定づけている楽章です。果敢に戦ったけど成し遂げられなかったといった風情の絶望的激高が一度挟まりますが、全体には終始泣いては慰めるような調子であり、最後にはコントラバスに心臓の鼓動を模したような動きが聞かれ、「死ぬように」消えて行きます。ここで語られているのは苦しみの先に想定される死だとも理解できますが、もしそうなら、それは恐らく本当の死ではなく、恐れるがゆえの死への憧れなのでしょう。死は単に死であって、語られません。
演奏の傾向と評価 以前キリスト教系の人と話をしていたら突然「無辜(むこ)の民」という言葉が出て来ました。無罪の意味だけど、流浪のユダヤ人を指す語として旧約聖書の訳語にあるのでしょう。これと似て「悲愴」に関連して頻出する難解な用語が「慟哭(どうこく)」です。声をあげて泣くことであり、あるいはこれもクラシック評のボキャブラリーなのかもしれません。「嗚咽(おえつ)」という語を使う人もいます。したがってチャイコフスキーの「悲愴」という曲はベルリオーズの幻想交響曲と同じように、演奏においては大きな起伏が求められるようです。こうして泣き女のような表現が演奏の見事さの基準となり得る一方で、金管などの鳴りっぷりの「野蛮なまでの」豪快さで度肝を抜くことも大切です。肝臓は一つしかないから抜かないでほしいけど、でもこうした剛直、剛胆、豪放、轟音のゴウな表現、ド迫力や弩級のドな演奏って、本当にチャイコフスキーらしいのかとちょっと思うところもあります。ゲイの人の一部のタイプと相関性があるメンタリティなのかもしれませんが、作曲家自身はむしろ虐げられたものへの同情心に満ちた繊細な心の持ち主だったとも言われているからです。そして面白いことにこの曲、実は演奏次第でいかなる雰囲気にでもなります。怒りに満ちた爆発や悲しみはもちろん、諦観であったり、洗練された美であったり、人智を超えた壮大な力も描けます。あるいは面白いことに、短調のこの曲の本質だと思っていた暗さとは正反対の、充実した幸せな感覚すらも表現できるほどの容れ物の大きさがあります。実際のところそうした点もあり、また上手く気持ちを切り替えられたこともありで、絶望の曲である「悲愴」を聞き比べる作業も、初め思ったのとは違ってこちらの気分が影響を受けることはありませんでした。 ここでのコメントは、純粋に好みの問題から激情的な演奏に対してはあまり好意的には書けませんでした。一般の評価軸とは逆になってるかもしれませんが、演奏の特徴が分かるようには心がけたつもりです。また、ベルリオーズなどは録音年代順にしましたが、ここでは思いつくまま順不同となっています。
  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Sergiu Celibidache M?nchner Philharmoniker ♥♥ チャイコフスキー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 セルジュ・ チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ 別格と呼んでもいいでしょう、これだけ異なる空間に存在するような演奏です。「悲愴」のページを作ることを考えたとき、もうこれ一枚だけにしてしまおうかと思ったぐらいで、個人的にはこの曲を聞こうかという場合はほぼこの演奏です。 チェリビダッケの晩年の一連のシリーズはどれもテンポが大変遅いですが、これもそうです。しかし遅いからといって思い入れたっぷりの誇大なものかというとそんな種類ではありません。遅い景色の中にこそ見えてくるものがあるという狙いなのでしょう、速度記号などお構いなしの純音楽としての説得力があり、多くの人は別の曲を聞いているように思うはずです。そんな手に出てまでも納得させてしまう人はこの指揮者以外にいないかもしれません。このページでは色々褒 めてきたのでファンだと思われるかもしれませんが、誰のファンでもありません。もちろんこの人の演奏が全ていいわけでもないわけで、遅くて間が抜けている ように感じる場合もあるはあるのですが、「悲愴」では緊張感が保たれています。ベートーヴェンの第九に2、4、6番あたりと、同じチャイコフスキーの5番 なども素晴らしい演奏だと思います。若いときは変わり者で弱い音だけで演奏していた時代もあり、録音嫌いで有名でした。喧嘩っ早いので重要なポストを逃し たかもしれず、晩年になってすら他の演奏者を酷評する口の悪いところもあったそうです。 どういう演奏でしょう。言葉にするのは難しいです。環境音 楽か、あるいは立ち止まって絵画を見てるのか、と思う瞬間があるのも事実ですが、最後の楽章な どただの嘆きではなく、我々の置かれた真の状況を自我の逃げや策略を剥奪して見せてくれるような力に圧倒されます。ロマンチシズムのかけらもありません。 チャイコフスキーというカンバスの上に描き出した、人の力の及ばない壮大なものという感じがしました。 第一楽章は25分もかかる遅い演奏で、また間も長いです。 でも録音が良いこともあり、遅いのはどの音も美しく響かせるためだとも思えます。決して走りま せんが、力が抜けてしまうこともありません。ただ、ずっと同じテンポというのではなく、興奮に従ってやや速める柔軟性は聞かれます。そして遅いからといっ て悲嘆にくれているような思い入れとは無縁なのに、なぜか納得させられてしまうのです。各楽器の構造もよく分かります。音に浸る喜びもあります。突然の フォルテの後はテンポが大分速くなり、そこだけ聞くと他の演奏でもあり得るテンポながら、クライマックスの音の洪水はただものではない気配です。 第二楽章は案外普通のテンポで、内声部がよく聞こえます。 軽い舞踊という概念ではなく、最後まで淡々と行きます。 第三楽章はこの楽章としてはやはり遅いです。それゆえにブ ラスの受け渡しがホルストの惑星かと思われるようなフレーズがあったりして、色々発見がありま す。そしてここも遅いままフォルテに差し掛かると独特の気迫です。最後はお祭り山車の行列の周りで太鼓を叩いて踊ってるかのようです。 第四楽章は、最初こそ案外普通のテンポに思えるものの、速 めるべきところでも速まらず、感覚が狂います。そしてやはり大変遅い展開になります。この楽章 こそが聞きものです。盛り上がって行くところが壮大で、一度若干速まり、またひどく遅くなり、一音ずつ鳴らされて行って頂点となります。なんで感動してる んだろうと不思議に思うのですが、悲しいとか何とかそういう主観的な感情ではありません。不思議な夢の中で迷い、まやかしの時間が流れて行く我々の世界そ のものを見せてくれているのかと、ちょっと哲学的な気分になります。全ては壮大な夢なのです。こういう音楽は聞いたことがありません。チャイコフスキーが これは人生を表した音楽だと言っていたのを何を大袈裟なと思っていたのですが、ああそうだったのかと納得してしまいました。最後の音が消えて行ってから間 を置いて拍手が鳴り始め、しばらく鳴ってから抑えがたいような興奮の叫びが巻き起こります。 1992年の EMI のライヴ録音で、音は大変良いです。若干中低音に膨らみのあるバランスですが大変自然であり、その場にいるようでホールの感覚が分かります。目の覚めるよ うな分解能というわけではないものの弦もナチュラルです。このレーベルのデジタル録音にはあまり好きでないバランスのものも多い中で、この録音嫌いの指揮 者の下でどういうセッティングだったのでしょう。昔のフィリップスやマリンソンのデッカの音に感心してきましたが、このシリーズも全然悪くないです。 Spectral Design AudioCube technology と書いてあり、それはブレーメンにあるソフトウェアの会社で Cubase VST(波形編集ソフトウェアのプラグイン) などを作ったスタインバーグ関連のようですが、どう編集しているのか詳しいことは分かりません。レコーディング・エンジニアはゲラルト・ユンゲ、ファイナ ル・マスタリングがハルトウィグ・パウルセンとヒルマー・ケアプということで、全てドイツ系の人です。 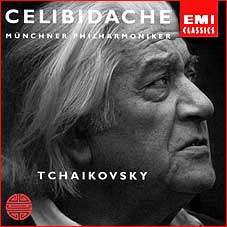 Tchaikovsky Symphony No.5 op.64 Sergiu Celibidache M?nchner Philharmoniker ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第5番 op.64 セルジュ・ チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ 「悲愴」がチャイコフスキー最大の傑作なら、次に来るのは第 5番かもしれません。死の五年前の作品であり、その前の4番の十一年後というタイミングで作曲 されました。これも熱い愛好者の方がいらっしゃる名曲ですし、技術的に解説できる知識もないのでやめておきますが、「悲愴」に似たところもありながらあれ ほど悲痛な部分がなく、美しいメロディ満載で聞きごたえのある気持ちの良い曲です。この二曲があればシンフォニーは OK などと言ったらファンの方に叱られるでしょうけど、ついでと言うのもなんですが、同じチェリビダッケのものを一枚だけ挙げてみます。表現は「悲愴」と同様 であり、どの点かは分かりませんが「悲愴」より名演だという人もあったぐらいです。やはり別格の凄さがあると思っているのですが、いかがでしょうか。他の 時期のではなく、このときの録音がです。個人的には他の演奏ならこの曲聞かなくてもいいやぐらいの気に入りようながら、どの指揮者も傾向は「悲愴」と同じ ですから、他の人の5番の演奏は「悲愴」のコメントを参照していただきたいと思います。 録音は1991年で、コンディションも同じで優れて自然な 音です。   Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Herbert von Karajan Wiener Philharmoniker ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ヘルベルト・ フォン・カラヤン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ 「悲愴」の名演奏と昔から言われてきた有名なものは二つあっ て、一つはムラヴィンスキーの録音、そしてもう一つがカラヤンということになります。ただしカ ラヤンはセッション録音だけで7回もやっており、手に入る他の音源も加えるとその倍以上はあるという状況で、どれが一番かも意見が分かれるところです。大 まかに言うとベルリン・フィルの EMI71年盤派と DG76年盤派でしょうか。とにかくカラヤンはこの曲及びチャイコフスキーは好きだったようで、彼の気質にも演奏スタイルにも合っているのか、「悲愴」と 言えばカラヤンというだけでなくその逆も言えたりして、あるいはカラヤンはやっぱりリヒャルト・シュトラウスとチャイコフスキー全般でしょうという声も あったりします。演奏スタイルと言いましたが、チャイコフスキーに関してはデビュー当時のベートーヴェンなどで聞かれたスピーディで颯爽としたスタイル (それに一番近いのは64年のベルリン・フィル盤でしょうか)というよりも、もう一つの方のロマン派スタイル、テンポは決して速くはなく、「カラヤン・レ ガート」などとも言われた特徴と重なる妖艶かつ濃厚に歌わせる方 のチャンネルにチューニングされているものが多いようです。したがって「悲愴」については最も分かりやすいのがカラヤンの演奏だということになるでしょ う。 ところがここではひねくれたことに、最初に取り上げるのは ウィーン・フィルとの録音の方です。このページはフェイバリットという観点で書いているからそ うなるわけで、カラヤンの「悲愴」で最も完成度が高いのはどれかと言えばベルリン・フィルとの最後のスタジオ録音である76年盤に異議はありません。それ でも自分で聞くなら断然こっちなのです。これはセッション録音としては7回目ということで最後になります。1984年というと亡くなる五年前で、ベルリ ン・フィルとちょっとぎくしゃくして疲れた後、ウィーン・フィルと録音しだした時期になります。このタイミングの録音には正直で情感のある案外良いものが 多いような気がします。これも例外ではなく、ラスト・コンサートのライヴ録音が悠然とし過ぎたところも感じられるのに対し、こちらはカラヤンのお別れの挨 拶のような趣です。やたらにダイナミックという感じではなく、かといってデュトワのような優美さでもなく、ヤンソンスのように楽しくもありません。感情と してはニュートラルよりは哀しみの色を残しているように聞こえ、明るく突き抜けた達観というよりはそこはかとなく孤独を感じさせる、正に諦観という演奏で す。ピアニストがピアノを弾くのと違って、指揮者の場合、特定の感情を表したかったらその旨をオーケストラに伝えなければいけません。孤独な情感をたたえ た表現と言ったってバッファ回路が挟まってるわけです。しかしそのことを分かった上で、なおかつその場の振動数を皆が自然に共有するという事態も私は起こ り得ると思います。 76年盤に比べればアンサンブルの乱れも若干あるでしょ う。でもそういうことは全く気になりません。フォルテでの歯切れはありますがもはや大声では叫ばず、あちこちで感慨深く振り返っているような風情であり、 一つひとつ丹精を込めて行くフレーズに感動します。今回はカラヤンに思い切って??を付けました。表現としては落ち着いてしなうようによく歌っているので すが、そこにこそ正直さを感じます。 目をつぶって指揮棒を振ってる姿をさんざんカメラに撮らせた自意識の強いジェット機パイロットの操縦意欲はどこへ行ったのか、力任せにせず慈しみ愛おしむ ような終楽章が素晴らしいです。 第一楽章は深々としたやわらかいウィーン・フィルの音が魅 力的です。この楽壇のやわらかな抑揚に負うところもあると思いますが、よく歌わせており、思い 入れたっぷりのロマンティックなところはむしろありません。ありのままという感じでどこも走らず、なおざりにするフレーズもありません。クレッシェンドし てフォルテに入っても激情をぶつけるような力は出さず、本来ならば速く駆けるように過ぎるフレーズもゆったりと歌って行きます。 例の静かな後の一撃以降はテンポも上げ、力強さは十二分に あると言えます。こうしたところでアンサンブルの切れの良くない部分が出てくるように言う人も あるようですが、自然な演奏ってこういうものでしょう。とり直す必要は感じなかったのかもしれません。静まって終わるところも変な思い入れがなく、 淡々と肩の力が抜けています。 第二楽章は絶品です。ゆったりやわらかく、力を抜いてしな やかに歌って行きます。でも往時のカラヤン・レガートというのともまたどこか違う雰囲気であ り、ドイツ的な重い拍でないのも良いです。角が丸く、五拍子だけどまるでウィンナ・ワルツのようです。カラヤンからこういう素直な音が聞けるのはうれしい 限りです。途中の短調に移るところもゆったりで悲壮感を漂わせず、諦観を感じさせますが、また舞曲に戻って静かなやさしさに抱擁され、テンポを自在に緩め つつ静かに終えます。 第三楽章は軽快なテンポになり、ラストコンサートのように 重いことはありません。単体でここだけみれば枯れた演奏だとは思わないでしょう。力みも深刻さもないけれども、十分な力強さがあります。後半には明るい爽 快さも加わります。 第四楽章は前の楽章の勢いで開始します。出だしのテンポは 遅くなく、弦楽の駆け上がりを経てため息のテーマが出る辺りからゆったりした波長になり、ふっ と力を抜くところなどが出て来ます。長調に変わって鮮やかな秋の気配がすると、次のフォルテでも走らず、そのままゆったりと歌って行きます。力を込めると 悲痛な歌になる短調の嘆きのパートに入っても静けさをたたえ、少しもの悲しい感じになります。そしてクライマックスのクレッシェンドではもう一度力を 込め、銅鑼が鳴った後は静かに消えて行きます。脂ぎったところはどこにもありません。 録音も84年と新しいだけに、またウィーンフィルというこ ともあってふくよかな良い音です。ただしふくよかと言ってもフォルテにおいて高い弦がキンとし たきつめの音になる瞬間があります。アナログ時代からドイツ・グラモフォンの技術者にあった音色の好みだと言える一方で、よりはっきりしているのはデジタ ル初期特有の、機器へのセッティングが追いついてない状態のバランスだということでしょう。84年というのはちょうどそんな時期です。出た当時の西ドイツ 盤を持っていますが、その後色々リマスターされたものが出回っているようです。そしてどれが良いかは難題であり、デジタル・リマスターのページで は色々と比較したのですが、今回は全部を比べているわけではないのでちゃんとしたことは言えません。新しいものの音の違いについては、大まかに言ってリマスターで変わることと、盤質が違うことの二通りがあるのですが、音のバランスが大きく変わるのはリマスター作業の方です。カラヤン・ゴールド・シリーズ (ジャケットがカラヤンの顔になっている)は本国 DG で OIBP という名称にしてリマスターしましたよ、と宣言しているものであり、オリジナル・ジャケットのもの(チャイコフスキーが碁盤の目の上に黄昏れている)のう ち最近のプレスは、リマスターについてはされているに違いないのに何も触れられておらず、国内盤は盤の材質やプレスの違いばかり宣伝しています。 SHM-CD とか UHQCD などといった具合で、他にもまだ種類があったようです。全部集めるのは愚かしい感じがします。CD とその CD を CD-R に焼いたものとを聞き比べてみると違いがわずかに感じられますから、盤質によって音が変わることはあるでしょう。しかしリマスター作業で音をいじるのに比 べれば無視できる差だろうと思います。これは自分でイコライジングをしてみれば分かります。盤質の違いを実際に確かめるには同じデジタル・マスターから作 られた通常盤と高品質盤とを聞き比べる必要がありますが、マスターが同じかどうかは公表されていません。メーカーがなぜデジタル・リマスタリングでの技術 者を発表せずに盤質のことばかり言うのかは商売的には分からなくもありませんが、どこか騙されているようでクリアじゃないし、相変わらず日本は材質などの 細部の違いばかりに目が行くなあと感心もします。 今回聞き比べたのは最初の西ドイツ盤(1985)とカラヤン・ゴールドの OIBP リマスター盤(1993国内盤)、UHQCD (2017)です。ゴールド・シリーズは記録面に金が使われているため盤面が金色をしており、UHQCD 盤はガラス CD のフォトポリマー技術を応用した新しいポリカーボネイト製だそうです。 音質ですが、オリジナル盤はデジタル初期の少し賑やかな癖が聞かれるもので、中高音にホーンの ような付帯音があるように明 るく張り出して響き、それがブラスの強い音になると耳に痛くなります。一点ではないでしょうから周波数バンドのどこかを言うのは難しいですが、一般に強過 ぎて耳が痛くなるのは3KHzより上から6、7KHz前後までです。 OIBP 盤はそのホーン鳴きのような癖が取れています。しかし相変わらず中域の張り出しはややあり、低音もよく響きます。そのためオリジナルと比べて耳の痛い感じ は大分やわらいでおり、低音のレベルが明らかに強いのかどうかは分からないながら、コントラバスのピツィカートも一番目立って聞こえます。バランスが良い です。 UHQCD 盤は低域がややバランス的に後退したかのように響き、弦がシルキーな艶をもって滑らかに聞こえます。耳に痛くなるよりも上の高域成分(8KHz以上)が はっきりしているかのように繊細さも出ていますが、オリジナル盤のようなホーン鳴き、もしくはゴールド盤のような中域の張り出し感が少なく、強いブラスの音 での耳の痛い感じが一番少なくなっているのでありがたいです。高域の特定の部分を抑えているようです。しかし結果的にやや音像が後退し、静かな部分でのふ くよかさが減って、滑らかだけど多少細身に感じられるバランスになっているとも言えます。耳にやさしく弦がきれいなのが UHQCD、自然な中域バランスで低音も豊かに聞こえるのが OIBP 盤といったところでしょうか。個人的には80年代初期のドイツ・グラモフォンらしい癖を持っているこの録音に関しては硬い高域が苦手なので、UHQCD 盤が最も良く聞こえました。フォルテで絞るか音を大きくしないで聞くなら OIBP かもしれません。以前のページでは反対に通常盤より OIBP や高品質盤の SHM-CD の方が高域がきついケースをレポートしている通り、これはシリーズによる固定的な癖ではありません。OIBP の中域バランスでフォルテの金管の金属音をもっと抑え、弦の高域は UHQCD並み、中低音をわずかに+2dB ほど上げるとベストな気がします。あるいは UHQCD で低域をややブーストする方がいいでしょうか。 今回は発売年度の新しい通常盤や以前高域強調を感じたポリ カーボネイトの SHM-CD などは比較しませんでした。しかし通常ジャケット盤についてはどの時点からかは分かりませんがリマスター作業はされているようです。MP3 レベルのストリーミングでしか確認していないのではっきりしたことは言えませんが、ロメオとジュリエットが組になっている盤(2007)も最初のプレスと は違うバランスのように聞こえます。新しい通常盤が最も無難な可能性もあります。したがって大雑把に言えるのは、この「悲愴」の録音については、新しくリ マスターされた盤の方がきつさが減ってバランスが良くなっている傾向があるだろうということです。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker 1976 ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ヘルベルト・ フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1976)♥ これぞカラヤンの代表盤です。ベルリン・フィルとしてのス タジオ録音の最後になります。71年の EMI を推す人も多いようながら、技術的にも完璧で細部まで彫琢され、磨き込まれているし、いわゆる「カラヤン・レガート」の特徴も最大限に表れています。人工 美の極地と言われた時代の演奏で、録音についても巷ではフェーダー操作で強弱をつけたり楽器ごとの音圧を調整したりの細工が疑われ、生とは別のバランスに なっていることについてもよく指摘されています。しかしそれも含めて音はそれ以前の録音よりきれいなのであり、フェーダー・クレッシェンドはともかくとし て、マルチマイクでとことんやればこうなると思います。何より見事な完成度です。最もカラヤンらしいのはやっぱりこれでしょう。 演奏スタイルとしては前述の通り、颯爽としたスピーディー なものではなく、十分に歌わせるとともにダイナミックでもあります。表情が徹底的に管理され、 手を抜いた箇所がないという印象で、下品な強調はありませんが、やり足りないという人もまたいないでしょう。第二楽章ではカラヤン・レガートも聞かれま す。それはやわらかくつなげて行き、フレーズ単位で部分的にぐっと遅く表現したりはあるものの、波のように強弱やテンポを揺らすという意味ではありませ ん。音形としては案外真っ直ぐでゆったりしており、あくまでも音を滑らかにつなげて行くという感じです。第三楽章も71年盤のようには走らず、形が整って います。一方であちらはストレートに熱い演奏であり、ベートーヴェンではストレートな初期の録音の方が自分も好きではありますが、もっと前のめりなのと録 音の問題もあり、チャイコフスキーについてはそういうのが良ければ何もカラヤンでなくても、と思わないでもありません。熱いのがお好きな方向きだと思って ますが、個人的にはどちらの陣営にも組しません。両方否定せずに比べて喜べば良いと思います。 録音についてですが、前述の通りベルリン・フィルの中では 一番良いと思います。やや奥に引っ込んで中域寄りのバランスであり、その中域に独特のソリッド な艶と反響が乗ります。そしてフォルテではやや高弦が乾いてきつくなります。幻想交響曲などと同様にこの頃独特の音ですが、それは DG の癖であると同時にこのホールのせいかもしれません。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker 1971 チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ヘルベルト・ フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1971) 76年の新録音より断然こっちだ、と言う人が結構いらっ しゃるようです。セッション録音なのにストレートで、ウィーン・フィルのものと同じように恐らく あまり部分的なとり直しをしていないのでしょう、マイルスのマラソン・セッションみたいに一気に片付いたのかもしれません。カラヤンだと思って聞くとびっ くりするぐらいちょっと前のめりであり、ライヴのような白熱した感じと若干の荒削りな肌触りがあります。つまりいくらか乱れがあるという意味ですが、とに かく珍しく興奮度が高く、激しい演奏です。この日はいったいどうなっちゃったんでしょう。第三楽章ではどんどん走って行きます。一方で第二楽章はそこだけ 設定はやや遅めではあり、それでもスローなパート全体に言えることとして案外あっさり歌っていて、うねるような濃い表情ではありません。すでに六十三歳で はありますがある意味若々しく、小細工をしません。60年代の素早く颯爽と流れるダイナミクスともまた違うのですが、これが良い人には無二の録音でしょ う。個人的にはこれよりも64年のベルリン・フィルによる4回目の DG 録音の方かなとも思いますが、何よりもエキサイティングな演奏をお探しの方はまずこの CD を手に入れてみてください。 71年 EMI ということで、録音の質としてはこのレーベルらしいところもあると思います。バランス的には低音も出てはいるのですが、高域成分がややライヴな明るい音に なって張り出して来ます。そしてフォルテで若干頭打ちになってガヤガヤと濁る箇所があるのが残念です。ステレオ初期か50年代にあった音にも近いと言える し、クリュイタンスやミュンシュの EMI 録音にもこういうのがありました。EMI にしても DG にしてもフィリップスやデッカと比べると惜しいことも多かったので、音響に特化していたカラヤンですが気の毒な気もします。この録音もちょっと耳が痛いの で破綻しているとも言えるのですが、でも恐らく好きな人には気にならないことでしょう。迫力があるようにも聞こえます。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker 1988 チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ヘルベルト・ フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1988) 「ラスト・コンサート」と銘打ったシリーズの一枚で、 1988年の最後の来日公演におけるサントリー・ホールでのライヴ録音です。亡くなる一年ほど前ということになります。ブラームスの1番に圧倒されたの で、そちらはすでにレポートしました(カラヤンのラスト・コンサート)。 悠然とした演奏です。第一楽章は案外遅くないテンポで入っ て初めは淡々としていますが、その後スローダウンします。フォルテへと盛り上げる場合は強くは なりますが、スピードは上げません。力はあります。遅いところはゆったりと歌わせます。黄昏という感じです。ライヴということもあり、端々が揃うわけでは ないですが自然です。スーパーマンが人間らしくなったという感じでしょうか。力はありつつ淡々と運び、そして悠然と終わります。 第二楽章もゆったりで遅いテンポです。切れのあるものでは ない、やや重いリズムでやはり淡々と行きます。華やかさ、軽妙さはなく、舞曲といっても愉悦ではなく、離れたところから静かに舞踊を眺めているという風情 です。 第三楽章も出だしでは大変遅いとは言えないテンポですが、 全体には遅めであり、やはり一歩ずつ走らずに進めます。中程の盛り上がりでも過度に元気よくは やりません。一音ずつ力は込めますが、覇気があるというものなのかどうか。何だか性質が全く違ったベームの晩年のスローダウンのようで、作為なく雄大で す。 第四楽章はこの演奏で最も魅力的なところです。やはりゆっ たりと力を抜いた枯れた運びであり、間も十分に取ります。ラスト・コンサート、正に別れの挨拶 のようなのはこの楽章です。静かでやわらかい抑揚で、諦めつつ認めるような、ある種のやさしさが感じられます。息の長い音が続き、盛り上がりで力は入るも ののテンポはゆったりのままです。もう終わりだよ、と言っているみたいで何か感じるものがあります。ワーグナーのように悠然としているとも言えるでしょう か、明るく軽くなって純化されて行く諦観ではなく、深刻な現実認識は残しながら、悲嘆するのではなく重いまま手放して行きます。最後の盛り上がりは雄大で す。そして呼吸するのも大儀な感じで大きく粘り、正しく最後の息を引き取るように終わります。 東京でのライヴ録音は全体に艶のある音ではありません。 フォルテでドライになると同時にリミッターがかかったようにも聞こえます。でも貴重な記録です。 ここまででいくつかの録音を端折って見て来ましたが、カラ ヤンはこのように一人であらゆる波長の演奏を聞かせてくれました。なかなかないことです。その 意味でも「悲愴」はカラヤンの歴史であり代表作であって、その打ち込みようは大変なものだったと言えるでしょう。常にきらびやかな衣装を纏って楽壇に君臨 していたイメージがありますが、元来この人はナイーヴなほど繊細で真っ直ぐなところがあるのかもしれません。それを守るためかどうか、いつも何らかの武装 をしなきゃいられなかったのでしょう。本来は音楽的にもとりたてて強烈なスタイルを持っておらず、ストレートな表現をしがちなところを、敢えて時代ごとに 仮面というと悪いけれども、いくつもの異なった様式を模索してきた、そして晩年にはそれが少し外れかかった時期があった、そんな風に理解するとこの様々な 顔の「悲愴」の演奏も腑に落ちるのではないかと思います。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Jewgenij Mravinskij Leningrad Philharmonic Orchestra ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 エフゲニー・ ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ カラヤンと並んで「悲愴」の定番であり、かつ高い人気を誇 るのがムラヴィンスキーとレニングラード・フィルのものです。ロシアの音楽だから本場ソ連の楽 団だという考えにも合致しています。そしてやはり悲愴の基準であることは間違いのない名演でしょう。厳しい演奏です。切れが良く、深刻なほどの切実さを感 じさせ、熱いけどクールです。そのクールの正体は冷たい空気を吸い込むような感触で、それはオーケストラの音色にも表れています。ブラスですら鋭く冷やり と輝き、バリバリと野性的なのです。木管がウィーン風とフランス風で違うなら話は分かるけど、金管楽器などにそんな違いがあるのかな、などと思ったりもし ますが、それらの楽器に全く詳しくないので分かりません。でもその昔にこの演奏を実際に聞いたときにもやはりそんな音に聞こえて驚いたものでした。5番の 方でしたが、あの一度静かになってからバカンと来るところなど怖くて、椅子から飛び上がりそうなほどビクついてしまいました。ホールのせいもあったかもし れませんが、どうなんでしょう。 贅肉がなく筋肉質に引き締まり、往時のソヴィエトの体操選 手のような徹底して鍛えられた技を見せられているようです。しかしそれでいてよく歌っていま す。それは強い感情が乗った歌で、余分な抑揚はないけど決してさらっと流しているわけではありません。力のこもった表情がある、それが熱い部分です。 第一楽章からボルテージの高さを感じます。強く駆け上がっ て行く弦には切実さがあります。テンポは中庸からやや速めに寄っており、常に少し走ろうとして いるようです。といってアッチェレランドも長いスパンの大袈裟なものはなく、短くて一触即発といった趣であり、常に心突き動かされるといった風情です。し たがってクレッシェンドも短くぐっと強めます。心情を吐露するような歌の部分も思いがこもった強めの抑揚があり、少し緩めてはまたぐっと緊張することを繰 り返します。突然のフォルテは一撃で驚かせ、そこから圧倒的な速度で駆けて行きます。金管のクールで荒削りな音は激しさを求める人を満足させる一方で、誇 大な表現には堕ちません。 第二楽章は速めのテンポでさらっと流しますが、優雅で軽い という感じではありません。中間部で静まるところではテンポを落とすものの、どこかに興奮を隠しています。 第三楽章も速く、きびきびしています。リズムは軽いけど覚 醒しており、やはり力を隠している感じです。短く畳み掛けるようなフォルテは歯切れ良く、興奮度が高いもので、本気で頭から叱られてるような迫力がありま す。そして駆けるように終わります。 第四楽章は決して遅くなく、冷気を感じるほど引き締まって います。最弱音から抑えきれないといった風情で激して行きますが、それは音型からすれば累進的 に音を強めてわずかにアッチェレランドするもので、浸るような甘い嘆きとは全く様相を異にするものです。また、強くアタックするように最初の音を当ててく るフレーズもあり、 中程のクレッシェンドではむしろややテンポを落としながら強めて行く手法で強く揺さぶられます。ラストの消え方も溺れるところはな く、悲観でもなく、事実を突きつけられるように終わります。 1960年のドイツ・グラモフォンのステレオ録音です。こ のレーベルだし古いしで音も厳しいかというとさにあらずでコンディションは良く、全く不満がありません。カラヤンの71年より断然良い音じゃないでしょう か。これもいろんなリマスターと盤質のものが出ています。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Sir Georg Solty Chicago Symphony Orchestra チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ゲオルグ・ ショルティ / シカゴ交響楽団 ムラヴィンスキーを取り上げた勢いでというのもおかしいで すが、引き締まった切れの良い演奏という共通点で思いつくのはショルティかもしれません。でも 実際に聞き比べてみると似て非なるもので、米ソの違いとは言わないもののその波長はムラヴィンスキーのあのメタル・ブルーのような寒色系ではありません。 十分に歯切れ良くダイナミックでテンポも遅くない演奏なのですが、あそこまで深刻な緊張が常にみなぎっている切迫感はないのです。辛口かもしれないけど感 情的には中立であり、力がこもる箇所でも抑えがたく二次曲線的に立ち上がるというよりも、メリハリを付けて激しくやる感覚です。ショルティと言えば上手で 乾いた音のシカゴ響をコントロールしてのエッジを効かせた胸のすくような運びで知られてきた指揮者で、特にこれら70年代の演奏ではそんな波長が前面に出 ています。そんなショルティの「悲愴」は、大仰ではないけどスポーツライクな、ダイナミックなのが好みの人向きです。 第一楽章はムラヴィンスキーよりテンポは遅めで始め、途中 から速度を上げます。例によって気短かなほどリズムがパンッ、パンッと切れる運びです。中程の盛り上がりでの鋼のような切れ味は、西側でムラヴィンスキー に匹敵するのはこれぐらいかという気もします。 第二楽章には案外やわらかさのある歌があります。テンポは 軽快なもので、ムラヴィンスキーのように興奮した感じはなくて舞曲らしいとも言えるでしょう。 第三楽章は速いテンポで歯切れ良く駆けて行き、痛快です。 深刻さは感じません。 第四楽章も深刻さはあまり感じさせずに流して行き、フォル テの部分では直球ながら、三楽章ほどの痛快激烈な感じはやや少ないかもしれません。静かな部分での表情や緊張感はあまり出さない人だなという印象です。 1976年のデッカの録音です。アナログですが、70年代 のショルティの一連のセッション録音は大変ダイナミックであり、後のものより良いように思います。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Bernard Haitink Concertgebouw Orchestra, Amsterdam ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ベルナルド・ ハイティンク / アムステルダム(ロイヤル)コンセルトヘボウ管弦楽団 ♥♥ 次は本命の一つで、有名どころのカラヤンとムラヴィンス キーより個人的好みを言わせてもらえばこちらの方が好きです。チェリビダッケの次ぐらいでしょう か。一時期この指揮者について心ない悪口を言う人たちもいましたが、特徴がないのではなくオーソドックスであり、楽曲本来の姿を余すところなく見せてくれ るのです。誰でも当たり外れはありますが、幻想交響曲やライヴの第九、この「悲愴」などはハイティンクの録音の中でも完成度が高く、覇気もあって充実した 演奏です。1929年アムステルダム生 まれの指揮者で、もう高齢のために引退したとのことであり、近頃はまた再評価の機運が高まっているのかもしれません。「悲愴」はまた録音が最高に良いもの でもあります。 ちょっと余分な話ですが、一般に中庸で楽譜通り、特徴がな いなどと多くの人がネガティブに感じる演奏は、ひとり指揮者の解釈というよりも、演奏者の音に 感情が乗らないときの演奏である気がします。どんなときに気が乗らないかは楽団員に聞けば色々あるでしょうが、もちろん指揮者のせいもあるでしょう。そし てこれがライヴで盛り上がるときなどのように熱気が上がって来ると皆が良い演奏だと思うようになり、最大まで行くと乱れて激情的な熱演になります。団員の 中にはアンコールでは派手にやろうとする人もいるようで、そういう熱いのが好きな聴衆も多いでしょう。それなら具体的にどういう形なら熱気があると言える のでしょうか。物理的に言うと案外限られたものであり、フォルテの最大音量は自ずと限界があるのでそれ以外の部分を小さくするダイナミックレンジ、強いア クセント、累進的(二次曲線的)なクレッシェンドなどはディナーミクと言われる音量軸に関わる要素です。テンポの揺れ、タメ、アッチェレランド(速くす る)、最大音の音符の前後の間とフェルマータなどはアゴーギグと総称される時間軸に関わる要素です。それならばあらかじめそういう熱気の形に指示しておく こともできるでしょう。ここから全力で走って行って、最後のフォルテの前で大きく間を空けてから、ドン、と行きますよ、そのように振りますからついて来て ください、さあ練習してみましょう、という具合にです。そういうのを、下品というかどうか分かりませんが、本当に楽員が熱くなっているのと熱くなった形を しているだけなのの違いは分かるでしょうか。ある種の神秘主義になるのでそれを科学するのは難しいですが、分かる場合もある気はします。その上で、そうい う仕掛けをしないのがオーソドックスな演奏ということになるのでしょう。 ハイティンクの「悲愴」ですが、第三楽章を除いてテンポは ややゆったりで、一つずつ解きほぐして行くようなところがあります。そしてそのちょっとおっと りした歌の中から情感が湧き出してくる演奏です。力まず丁寧に一つひとつの動機が示され、主旋律以外の内声部の線が並んで聞こえるような分離も味わえま す。それは分解するというほど恣意的ではない自然さを有しており、曲の構成がよく分かりつつ聞いていて心地良いものです。また、悲痛な感情で無理押しして 来ないのでリラックスして音の美しさに耳を傾けられる運びだとも言えます。その方がこの曲本来の姿だと思うのですが、それは受け止め方の違いかもしれませ ん。ところがそれでいてこの「悲愴」、フォルテでの迫力も十分過ぎるほどあるのです。ショルティでもないですが、歯切れ良さすら感じられます。乱れないけ ど熱があるという感じです。ゆったりで強いところも力が入っています。ただ無用にあおったりしないだけであり、底から情熱が盛り上がるような終楽章も素晴らしいです。 第一楽章はあるべきものがあるべきところに収まっている パーフェクトな感じです。中程過ぎでは速いテンポに切り替わり、力強く大変歯切れが良いです。フォルテの盛り上がりの激しさは注目に値し、テンポが前への めるところもあります。 第二楽章は特に軽快なテンポというわけではなく、リズムも軽くはありませんが、中庸ややゆったりの穏やかな舞曲です。語尾を伸ばすような処理も聞かれます。 第三楽章は前の楽章より軽快です。ここは大変溌剌と元気が良く、乗れていると思います。やわな演奏ではなく、迫力が十分にあります。 第四楽章は柔軟さのある歌わせ方で自然に気持ちが乗って来ます。静かな部分でスローダウンして行く表現と滑らかでたっぷりとした表情があります。そして そこから息の長い最初のクレッシェンドが来ます。訴え過ぎず暗くなり過ぎない純粋な響きが美しいです。クライマックスの盛り上がりは白熱しています。やわ らかい銅鑼の後、終わりも過度に喘がせず、あるべき姿で美しく消えて行きます。 録音が素晴らしいです。1978年のフィリップス、アナロ グ最後の頃です。フィリップスはデジタル録音のノウハウを消化し終えた頃にレーベルとして消滅 していますので、アナログ最盛期の音はこのレーベルで最も良かったものと言えるでしょう。同じハイティンクでデッカのジェームズ・マリンソンによる「幻 想」の録音と比較してみるのも面白いかもしれません。残念ながらこのアルバムについては自分の CD にはレコーディング・プロデューサーらの名前は出ていませんでしたが、フィリップスの技術者たちもマリンソンに負けず劣らずの自然なバランスの音で収録し てきました。この「悲愴」では「幻想」より弦の高い倍音が素直に伸びて前に出ており、より低い基音部分に艶の成分となる余分な余韻が付かないのでさらっと した自然な艶に感じられます。そしてドイツ・グラモフォンとは違う豊かでライヴな中低域がやわらかさを感じさせるバランスにしており、ここをもう少し引き 締めてその下の重低音を強調し、弦と木管により艶を聞かせるようにするといかにもハイファイな音になります。しかしデッカの明晰な方の録音にありがちなそ うした音にしないこのアルバムは、より耳で聞いたオーケストラのバランスに近いと言えるでしょう。いかにものフィリップス・サウンドです。マリンソンの 「幻想」もいかにもデッカという平均的なデッカの音よりはフィリップスに近い自然なバランスで似ていますが、弦の音に若干の違いがあります。もう少しヴァ イオリンが奥に引っ込んでホールトーンが加わり、時折倍音の成分だけが自然な艶で細く浮き上がるといった趣です。それもまたリアルなオーケストラの姿で す。ホールも楽団も違いますから両トーン・マイスターの狙いの差だけとも言い切れませんが、いずれにせよこのハイティンク盤、「悲愴」のベスト録音の一つ でしょう。 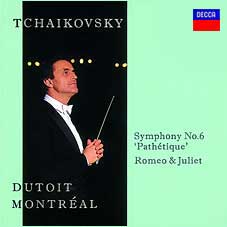 Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Romeo and Juliet Charles Dutoit Orchestre Symphonique de Montreal ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 幻想序曲「ロ メオとジュリエット」 シャルル・ デュトワ / モントリオール交響楽団 ♥♥ これは最も美しい「悲愴」でしょう。穏やかで繊細な抑揚で あり、ハイティンク盤と並んでもう一つ、きばらない系の見事な演奏です。きばらないといっても フォルテの表現が弱いとか、そういう意味ではないので誤解してほしくないのです。その点もハイティンク同様、そこだけ聞けば歯切れ良く迫力は十分ありま す。歯を食いしばるような凄い演奏を求める人にはだめでしょうが、フランス系カナダ人のデュトワの演奏にはオペラ系とは違ったセンスの良い独特の歌心があ り、「悲愴」に付き物だと思っていた自己陶酔は感じられません。純粋に曲の美しさに浸っていられるものであって、案外これこそが本来のこの作曲家らしいあ り方なのじゃないかとも思えてきます。繊細だったチャイコフスキー自身は生きてたらこういうのと激情的な演奏のどっちを喜んだでしょう。自分を見せられる ようなものは嫌がるかもしれませんが。 第一楽章は静かにやわらかく入ります。歌わせ方がきれいな のは幻想交響曲と同じです。弱い者に同情する壊れやすく繊細なチャイコフスキーを描けているよ うに思います。歌のセンスが独特で、弱めるデリカシーにふくらませるやわらかさが洗練されており、やり過ぎないところがいいです。この人アルゲリッチの旦 那さんだったのですね。テンポを上げて歯切れも良いフォルテに至りますが、そこからまた大きく緩めて行きます。そこでも歌は上品で押して来ず、こちらから 思わず聞き耳を立ててしまいます。流れが気持ち良く、感情的にもゆったりとしています。この間合いが好きな人には無二の演奏と言えるでしょう。 第二楽章は涙で曇る目で恨めしそうに舞踏会場を見るような 演奏ではありません。力の抜けた優雅な舞曲で、たゆたい流れる水のようです。消え入り方にもデリケートな表情があります。 第三楽章は小声で囁くように始まります。テンポは軽快なも ので、リズムにも軽さがあります。拍の一つひとつにドイツ系のような重みがないのです。待ち構 えていたような盛り上がりの迫力はありませんが、余裕のフォルテは楽しくもあります。小気味良くはぜる大人のスケルツォと言えるでしょう。 第四楽章では必要以上に嘆きません。涙がこみ上げてくるよ うな表現の部分も表題的にではなく、純音楽的に鳴らします。ふわっとした膨らみのある抑揚で流 して行きますが、息の長い音の流れに身を任せると、どこまでもやわらかく包み込んでくれます。ラストの盛り上がりへの長いクレッシェンドは有機的で、過大 な思い入れのないラストの消え方も良いです。 1990年デッカの録音は弦がシルキーで艶やかです。明晰 な分離が得られて明るく響きますが、音色はしっとりとしています。バランス的には上の部分が違 いますがフィリップスのハイティンク盤同様に中低音がよく響き、一瞬似た音と思うときもあります。コンサート・ホール的な自然さも感じられる優秀録音で す。 ロメオとジュリエットが入っていて、それもこの曲のベスト かと思える美しい演奏です。 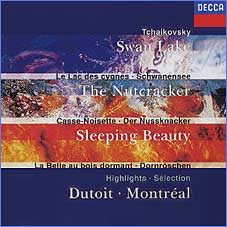 Tchaikovsky Ballet Suites The Swan Lake・The Nutcracker・The Sleeping Beauty Charles Dutoit Orchestre Symphonique de Montreal ♥♥ チャイコフス キー / 三大バレエ組曲「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」 シャルル・ デュトワ / モントリオール交響楽団 ♥♥ 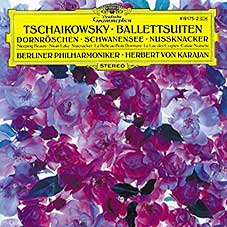 Tchaikovsky Ballet Suites The Swan Lake・The Nutcracker・The Sleeping Beauty Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker ♥ チャイコフス キー / 三大バレエ組曲「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」 ヘルベルト・ フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ デュトワ盤が出たところで、有名な三大バレエ組曲も取り上 げます。チャイコフスキーのメロディーで恐らく最も有名なものだと思います。これこそ可哀想な もの、きれいなもの好きのチャイコフスキーの魅力が最大に発揮された音楽と言ってもいいのではないでしょうか。ベジャールを一度だけ見たことがあるだけで バレエのことは全く分かりませんが、この作曲家の三大バレエ音楽はバレエという芸術における三大でもあるようです。ロシアで学び、ドイツでプロで食べてい たダンサーの方とお話をしたら、やっぱり白鳥の湖なんかは皆の最終的な憧れであり、どんなに技術的に完璧でもプリマになるにはそれに見合うオーラ、努力で はクリアできない条件、その他色々厄介な関係などが必要とのことでした。舞台の端で石のように固まってる役の人も羨望の眼差しを投げてるとのことです。 この組曲、聞いたことがあるメロディーばかりだと思いま す。特に「くるみ割り」はやかましい部分がなく、心地良く口ずさみたくなる旋律がずっと続くの で、よくそこからかけたりしています。舞台照明を担当する人によると、クリスマス・シーズンになるとこの曲のメロディーを耳たこなほど聞くと言いますが、 一般的には日本ではまだこの時期と言えば第九の方かもしれません。 チャイコフスキーと言えばカラヤン、ということで、この三 大バレエ組曲もカラヤンの演奏が定番です。そしてそれがやっぱり見事なのです。ベルリン・フィ ルとのものは録音が1971年、「くるみ割り人形」だけが66年です。他にウィーン・フィルとのものが人気があり、様々なリマスター盤が出ています。そち らは65年の録音で「くるみ割り人形」だけが61年です。両方持っていてどちらもいいと思いますが、ウィーン・フィルとの録音は 96KHz 24-bit と書かれたデッカ・レジェンズ・シリーズのリマスター盤ながら録音状態はベルリン・フィルとのものの方が新しい分だけ若干良いようです。少しだけイコライ ジングしたくなりましたが、大変ダイナミックな演奏で細部まで磨かれ、心地良く歌っていて長らく定番でした。 それに対してより新しい録音でもっと音の良いものはないも のだろうかと思っていたところに出会ったのがデュトワ盤です。前述のような彼の特徴が最大限に 発揮され、大変美しくて新定番となりました。カラヤンとの違いはメロディーの歌わせ方が少しだけゆったりでふわっと繊細なものであり、落ち着いて聞けま す。カラヤンの方はもう少しダイナミックであり、テンポを軽快にして滑らかに磨いた曲があるといった感じなのです。遅くない分ドライブの効いたところもあ り、 弧を描いて立ち上がる伴奏部分などがリズミカルで心地良いです。そのテンポの方がいいように思える曲もあるし、デュトワの歌の方がきれいだと思う曲もあり ます。デュトワ盤の録音は1991/92年のデッカで、高い弦の倍音が繊細に美しく響きます。文句なしにきれいです。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Mariss Jansons Symphonie-Orchester des Bayericher Rundfunks ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 マリス・ヤン ソンス / バイエルン放送交響楽団 ♥♥ この曲が演奏次第でもどんな曲にでもなることが分かる一枚 です。前のハイティンクとデュトワも純粋にオーケストラ曲としての美しさを見せてくれましたが、 このヤンソンスの新しい録音はただひたすら演奏する楽しさに浸っていたらどうなるかを見せてくれる希有なものだと言えます。「悲愴」と言えば鬱々として常に悲しく、 絶望もしくはそこに憧れるような波長の曲と理解されているでしょうが、これを聞いていると充実した喜びに包まれます。最近のヤンソンスはずっとこういう波 長を感じさせてくれていますが、この仕事が好きなのでしょう、素晴らしいことだと思います。この指揮者は元々ロシア文化圏ラトヴィアの出であるものの、そ れでイメージされるような一般的な括りには入りません。 派手な仕掛けがなく、正直で気持ちの良い美しさに満ちてい ます。若い時の方がテンポの切り返しなどもっとはっきりした傾向があったはずです。正々堂々としていて明るさと肯定するやさしさに満ち、一緒に酔おうよ 言ってるようで、まるで別の曲を聞いているみたいです。 第一楽章は大変ゆったりと、やわらかい弾力をもって始まり ます。しかしテンポを速めるところでは感情を込めて速め、チェリビダッケの一徹な遅さとは違う 柔軟性があります。自在に伸び縮みするのです。落ち着いていると言うと熱がない演奏のように聞こえますが、そうではありません。ピアニシモの後の例の爆発 も物々しくはやりませんが、しっかり鳴らして行きます。 第二楽章はやや重さはあるけれどもやわらかな五拍子の舞曲 です。揺らめくような動きがあり、繰り返しごとに強くしたり弱くしたり、よく表情がついています。やはり明るく、充実した喜びを感じさせ、慈しむように終 わります。 第三楽章は力で行かず、余裕があります。落ち着いて一つひ とつ鳴らして行くうちにだんだん楽しくなってきます。この楽章もこんなに真っ直ぐ喜びが湧いてくる演奏は初めてであり、躁状態の空しい乱痴気騒ぎでは決し てありません。 第四楽章も自己憐憫に落ちない充実感があります。ゆったり 大きく包み込むような包容力があり、わざと劇的にするようなところがなく自然な呼吸で運んで、 その中で自然に速くなるところもあります。そして途中の盛り上がりでは大変感情のこもった熱演となり、やや引きずるように重く終わります。 (マリス・ヤンソンス氏は2019年11月30日、心不全により76歳で逝去されました。) 2013年の BRクラシクス自前の録音は目の覚めるような音というわけではありませんが、たっぷりとした自然なやわらかさがあり、弦も木管も瑞々しい良い音です。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 マリス・ヤン ソンス / オスロ・フィルハーモニー還元楽団 ♥ 昔はレニングラード・フィルも振ってたヤンソンスですが、 世界的指揮者となる足掛かりはオスロ・フィルでしょうか。「悲愴」も演奏の形としての完成度の高さではこちらかもしれません。高域がよりクリアでセッショ ン録音っぽいのもあります。 全体のテンポ設計に大きな違いはありませんが、旋律線を くっきり歌わせ、より歯切れが良い印象です。ティンパニの目立たせ方や細かな音と表情に注意が行 き届いています。この頃らしい美点として、最初の楽章からテンポを切り返しての伸び縮みがありますが、熱い感じはしながらも作為というところまでは行きま せん。当時から堂々たる実力だったと思います。バイエルン放響との録音と比べると流動感はより少なく、より丁寧な運びです。 第二楽章は一つひとつの音が明晰に鳴り、流動的なリズムと 抑揚が聞かれます。喜びを感じさせるという点では2013年盤がいいですが、こちらの方がよりクリアでしょう。 第三楽章は軽快です。滑らかさはありながらも弾むように歯 切れ良く、フォルテではダイナミックです。 第四楽章もバランスの良い感性度の高い演奏です。 1986年シャンドスのスタジオ録音です。残響があり、ラ イヴ録音よりも高域に艶が感じられます。録音バランスは大変良いと思います。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Andris Nelsons City of Birmingham Symphony Orchestra ♥♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 アンドリス・ ネルソンス / バーミンガム市交響楽団 ♥♥ 同じくラトヴィア出身の期待の指揮者、1978年生まれの ネルソンスです。世代から言うと最近の派手なパフォーマンスを見せる何人かの人たちと同じです が、ヤンソンスに教えを受けてもおり、この人はそういう方向ではないもう少し地道なアプローチに思えます。2014年のルツェルン音楽祭でのブラームスの 2番のライヴが良かったのですでにレポートしました(「ブラームス交響曲1〜3番」)。バーミンガム・シティ・オーケストラ、ボストン・シンフォニーなどの音楽監督、現在はライプツィヒ・ ゲヴァントハウス管弦楽団の楽長も務めているようです。 これも大変いいのです。自然な抑揚が瑞々しい演奏です。心 に美しい風景画のような完成された美を持っている人で、その景色には熱い情熱も秘められている といった印象です。消え入るような弱音に繊細さがあり、第一楽章で金管の持続音を強く長引かせるように吹かせることでバックからフロントへと引っ張り出し て来たり、第四楽章でも同様に背後のブラスの動きをクローズアップするような動きが見られるなど、控えめながら効果的なアイディアもあって知性を見せま す。画が心の中で明確な形を持っているのでしょう。しかしトータルではスコアを生き生きと音にして行くストレートな熱い演奏で、作為は感じさせません。音 の形をカラヤンと比べるならよりふわっとした強弱の抑揚が呼吸のよう付くという感じです。速いテンポで歯切れ良く進めるフォルテの部分では軽さもありなが ら直截であり、昔からの四角なドイツ流とはちょっと違うようです。第二楽章は若干さらっとした肌触りであっさりそつがない舞曲となり、第三楽章も力を抜い て軽快に、あるべき姿で進めます。両端楽章に対するこうしたコントラストはドラマチックな物語を求める人にはもの足りないかもしれませんが、大変良いと思 います。終楽章には大きな表情と力がありますが、それでもどこかにやさしさの感じられる正直で繊細なチャイコフスキーです。 2010年オルフェオのセッション録音です。さすがにも やっとしたところのない優秀録音で、明晰ながら輝き過ぎない自然さもあり、最近のデジタル録音でスタジオ収録だとこうなるというのがよく分かります。 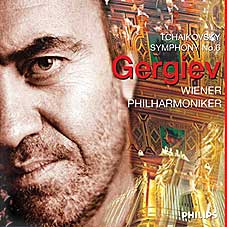 Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Valery Gergiev Weiner Philharmoniker ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ワレリー・ゲ ルギエフ / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ 大変人気の出た演奏です。ロシア人ということもあってかカ ラヤン、ムラヴィンスキー以来の注目だったかもしれません。そしていくつか録音が出ている中でこの盤はウィーンフィルの音が魅力的であり、大変完成度の高 い万人に勧められる演奏だと思います。 第一楽章はウィーンフィルらしい音で包み込むように始まり ます。録音が大変良く、表現もよく歌っています。始まりはゆったりですが速まろうとする意志も 感じられます。夢見るようなやわらかい歌が粘るフレーズとともに聞かれ、皆が言うほど激しい演奏ではないのではないかと感じます。甘い音の魅力とでもいう か、伸び縮みもあり、ムラヴィンスキーより振幅もある一方で強い緊張のエネルギーを感じさせるものではないのです。突然のフォルテ以下も力づくという感じ はせず、それでいて十分に迫力はあります。アゴーギグも猛然と走るほどではないけれどもテンポを上げて行くところがあって、またぐっと遅くして行く伸び縮 みが熱演の形になってはいますが、我を忘れるというほどではなくてコントロールが効いています。十分にロマンティックな熱も感じられつつ崩れないのが良い ところでしょう。締めくくりは大変ゆっくりと終えます。 第二楽章はやわらかい舞曲でテンポはやや軽快です。リズム の扱いも軽やかで大変納得します。 第三楽章は速めのテンポで進めます。ここもリズムの扱いが 軽い感じです。そしてだんだん熱が入って来て、頂点では大変力強く溌剌としています。奇を衒わ ない真っ直ぐな表現であり、この楽章でのスケールの大きさはロシア系かなという感じです。終わりがけに一度音をぐっと弱めるところがあり、そこだけが ちょっと工夫という感じで意外かもしれません。爆発的に終わります。 第四楽章になるとゆっくりになり、大きな起伏で歌い始めま す。途中でテンポをぐっと速めるところに熱っぽさもあり、第三と第四楽章は両方とも白熱してい る印象です。そしてこの楽章でも急にぐっと弱める表現が見られます。中程過ぎに来るクライマックスの部分では大変にまくります。終わりに向けてもシリアス な感じは十分にあるという意味で正攻法の、全く良く出来た「悲愴」だという印象です。 2004年フィリップスのムジークフェラインでのライヴ録 音(現デッカ・レーベル)ですが、最初に述べた通り大変魅力的な音です。 ゲルギエフはこのウィーン・フィル盤以外にも出ており、一 部にはそれらの方が彼らしくて良いのだという声もあるようです。この後2010年にマリインスキー歌劇場管弦楽団と出している盤は遅く引きずったりタメた りのより激しい表現がありますが、完成度という意味では個人的にはウィーン・ フィルの方かなと思いました。両端楽章での興奮度は高い印象で、音が鳴り響き続けているような圧力を感じます。アッチェレランドもより激しく、オーケスト ラが違うせいか聞いた感じ同じ人かどうか分からない印象です。一種荒削りなところがあり、そこが魅力なのでしょう。第三楽章も大変元気です。自前レーベル ですが残念ながら若干音が割れ気味な傾向もあるようです。 一方でウィーン・フィルの前の97年にはフィリップスの録 音でサンクトペテルブルク・キーロフ歌劇場管弦楽団との演奏を出していました。マリインスキー管との演奏ほどまでではないかもしれませんが、やはり VPO 盤よりは遅く引きずったりする様子で、両端楽章でのスケール感と力もよりあるかもしれません。第三楽章もやや賑やかです。音はマリインスキー管盤より良い ように思います。 他にも2015年に若者たちで構成されたヴェルビエ祝祭管 弦楽団による録音も存在します。 ロシアの演奏家については、プレトニョフとフェドセーエフ が終楽章での作曲家の「アンダンテ」の指示に従っているのだという話がウィキペディアなどに書 いてあります。アダージョでの演奏がほとんどだということなわけですが、聞いてみるとこれがよく分かりませんでした。特別速めのテンポという感じはせず、 他の演奏者でもよくある運びだったからです。それでというわけではないのですが、このページではロシア系の演奏者をあまり多くは取り上げていないと思いま す。一部では熱く語られるようではあるものの、申し訳ありません。 ムラヴィンスキーの弟子であったネーメ・ヤルヴィとエーテ ボリ交響楽団による2004年の BIS 録音も聞きました。特に変わったことをする演奏ではなく、遅くないテンポで流し、音の大きくなるところでは引き締まった動きを見せて師譲りのドライで畳み 掛けるような迫力があります。過剰に歌わせるところがない人で、典型的ロシア系の熱演というのとはまた違った種類の演奏だと感じました。録音が良いのが印 象的です。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Myung-Whun Seoul Philharmonic Orchestra ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 チョン・ミュ ンフン / ソウル・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ 悪いことをしたなら適切な形で謝ったり償ったりした方がい いと思います。謝ったつもりで許してもらえないときは考えてみる必要もあることでしょう。逆切れして別の形で仕返しをするのは子供です。しかし戦後補償の 話となるといつまでも紛糾するのはどういうことなのでしょうか。政治として何が公平かという議論に関わる気は毛頭ないけど、歴史の解釈には正解がないのか もしれません。日 本と韓国は兄弟みたいなものなのだから、どうか仲良くやってほしいものです。 萩焼の美しい茶碗が好きです。あれは朝鮮半島から連れて来た陶工によって作られたものです。マイセンに影響を与えた伊万里焼だってそうです。こんなことを 言うといろんなものが朝鮮半島由来で、言語系統の近さはもちろん、建築、お酒の杜氏も秦氏などに関係があるし、演歌だってそっくりな歌が韓国にあります。 芸能関係でお世話になってるだけでなく、国の象徴的な存在ですら血縁があるとご本人が仰ったそうです。渡来系というのは朝鮮半島を経由して来た者全てとい うことかもし れないけど、天孫降臨や天津神にだってその説はあります。 さて、韓国の素晴らしい演奏です。指揮者のチョン・ミュン フンは世界で幅を利かせているマネジメント会社に反旗を翻したフランスに認められて登場して来 た韓国人で、ここで演奏されているオーケストラはソウル・フィルハーモニー。レーベルはドイツ・グラモフォンです。感情的に大変熱い「悲愴」です。第四楽 章がかなり思い入れの大きな遅い運びで、それが個人的にはちょっとだけ違ったので?としましたが、そこを除けば二つ付けたかもしれません。しかし一般的に はその第四楽章こそが好きという人の方が多くいらっしゃると思います。 ゆっくりな部分では波に揺られるように上下して伸び縮みす る心のこもった歌があり、形の上ではちょっとフランス流儀かと思うほど起伏をつけています。滑 らかな音も相まって大変魅力的です。洗練というのとも幾分異なるし、大変熱いのですが、力任せに激情をぶちまけるような雑な感じはしません。ある種韓国ド ラマに見られるような情のストレートさというか、エモーショナルに入り込んだという意味でスケールの大きな演奏です。極東の楽団が頑張ったというお情けレ ベ ルでは全然なく、韓国の人は同じアジアでも積極的な表現を恐れないのだということに感銘を受けます。世界最高水準の個性ある名演とすべきでしょう。 第一楽章はふわっとやわらかい抑揚でゆったりと、あまり力 を込めずに始めます。間が大変大きいところもあります。そして弦が駆け上がる頃には軽く切るリ ズムに自然に切り替わって行きます。ゆっくり歌う部分では粘るような十分な抑揚で、もう少しさらっとでもいい気がするときもあるものの作為はなく、自然で 嫌みがありません。突然のフォルテの前では夢見るような運びですが、一撃の後は一気に走るかと思いきや踏みとどまる見識を見せます。大抵の人は走るのです が、面白いです。その後で速めて行くところも感情が乗って自然であり、金管の吹かせ方にはアクセントがあって細部の工夫が知的です。後半の盛り上がりには 本当に感動します。力づくではない大きな息遣い、熱は感じさせるけど荒々しさは感じさせないと言ったのはこの部分です。 さらっと軽快ながら柔軟によく歌う第二楽章は理想的です。 軽快で大変速い第三楽章もいいです。この二つは両端楽章の強い思い入れとはコントラストを成すように設定されているのでしょう。 第四楽章は遅く、かなり誇張がありますのでちょっと抵抗が あると言えばあるのですが、その世界に入り込んでしまうと案外良く聞こえてきます。幻想交響曲 のときには正体をつかみ切れなかったのですが、「悲愴」はメンタリティとしてもこの人に合っているのか、なるほどと少し了解できた感じがします。聞き終え るとああ久しぶりにこの曲で感動したなという気持ちになりました。 2011年の録音は弦の音が滑らかで固まらず、繊細に響い て大変美しいです。ドイツ・グラモフォンですが硬いところがなく、低音もよく出ていて全体に瑞々しい優秀録音です。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Claudio Abbado Wiener Philharmoniker ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 クラウディ オ・アバド / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ♥ これも人気のある、また評価も高かった演奏です。「悲 愴」ってどんな曲って言われたらカラヤンとこれをお勧めしてもいいでしょう。ムラヴィンスキーのよ うな禁欲辛口ではなく、イタリア人らしくよく歌い、各声部が分解されていて盛り上がりもくっきりとしている意識の高い演奏です。アバドをあまり褒めたこと がなかった気もしますが、これは彼の良い所が前面に出た名演ではないでしょうか。細部まで注意が行き届いた完成度の高さという点ではカラヤンの76年盤と 並ぶ一方で、同じイタリアでもムーティのようにオペラの匂いのする絶唱型の指揮者ではありません。それを言うなら分解的なジュリーニはもっとそうかもしれ ませんが、こちらはより表現に意欲的でバランスの取れた感じがあります。 第一楽章は中庸のテンポで入ります。管と弦が、イタリア的 というのではないでしょうが明るくきれいな録音です。くっきりとした歌があり、内声部もよく聞 こえる明晰なところはジュリーニとも共通しますが、分解的というよりもより抑揚がついて有機的であり、クレッシェンドでフォルテに至るところは力強く浮き 立つようにやります。チェロなどに大変よく歌わせているのも特徴で、テンポの変動もあります。盲目的な熱い情熱というよりも、もっとよくコントロールされ ていながら歌心があり、細部に注意が向けられている完成度の高い演奏と言うべきでしょう。例の突然のフォルテもしっかり揃っています。とにかく細かくよく 表情がついており、颯爽とした若さと言うべきなのか、苦悩というよりも鮮烈という感じです。 第二楽章もよく歌わせつつやや速めのテンポで進めます。そ のテンポを上手に変動させる上、リズムにもすごく弾力があり、波のような伸び縮みとかではない もののよく流動してます。ここでもチェロの歌が前面に出てよく聞こえるように録音されています。セッションならではでしょうか。明るい弦が爽やかできれい です。管も輝いてピツィカートもくっきりしていますが、録音の面ではやや作られ感があると言うべきでしょうか。マルチマイクのセッションらしいです。しか しそれが明るい日差しのようでこの盤の魅力でもあります。 第三楽章でもピツィカートなどがよく響いて細かな弦の動き が聞こえます。リズムも歯切れてくっきりです。そのくっきりとした感触は羽根のように軽いもの ではないながら、動きは軽快です。つまりフレーズごとに表情を切り替える巧者なところがあり、ブラスの内声を聞かせつつクレッシェンドする技もあります。 明るく明晰なので全ての動きが見えます。全体の進行は安定しており、走ることはありません。 第四楽章ですが、ここもくっきりと旋律線が動き、内声部と の対比が分かります。旋律自体はよく歌っており、若者の情熱のような盛り上がり方をします。こ のときアバドは40歳です。思い切って弱める表情など、やり過ぎなぐらいの箇所もあり、クライマックスの楽章という意識があるようで、ミュンフンもそうで したが第一楽章より表現が大きくなっています。この演奏で最も良く出来た楽章でしょう。大変感情を込めているのに重くなり過ぎないラストもいいです。最後 まで暗さがない演奏です。 1973年ドイツ・グラモフォンです。音についてはすでに 述べましたが、生の自然なやわらかさというよりもグラモフォンらしく輪郭のくっきりとした明る い音の録音です。弦と木管には艶が乗り、残響はほどほどある方です。アバドはこの後86年のシカゴ響とのソニー盤もあるし、ライヴも出ていますが、この ウィーン・フィルのものが彼の美点がよく表れているのではないかと思います。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Carlo Maria Giulini Los Angeles Philharmonic Orchestra チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 カルロ・マリ ア・ジュリーニ / ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 アバドと来たらジュリーニでしょうか。第一次大戦の年に生 まれて2005年に九十一歳で亡くなったイタリアの指揮者ですが、欠点がないほどに誰からも尊 敬される人だったということです。欠点がないと言えば、ある著名な心理学者で医者だった人の話を思い出します。その人の知り合いにどこから見ても欠点がな いように見える男性が一人だけいたそうで、疑ってかかったというのです。その学者は人間の気質を四つに分類した類型モデルを唱えていたのですが、その男性 は論理においても秀でており、感情も成熟しているという具合に、どこにも弱点がないように見えていておかしいと思った、ということです。しかしあるときそ の男性の奥さんを見たら、男性がその奥さんの分まで奪ったかのように性格破綻しており、なんだそこでバランスを取っていたか、それみたことかと思ったそう です。そこまで悔しがらなくてもいいのに、その学者も自我のレベルでは普通の人間なんだな、と感じた覚えがあります。優れた人っていると思うし、パート ナーと二人でバランスを取ることがあるかどうかは分かりませんが、ジュリーニはどんな人だったのでしょうか。 演奏面からそれを探って行くのは難しいというか、ほとんど 無理でしょう。仮に特徴を言うことはできても、それと人格との関連性はさほど明白ではありませ ん。イタリア人御三家と言われる指揮者はアバド、ムーティ、ジュリーニかもしれませんが、単純に表現してオペラ的な歌のムーティ、歌がありつつ構成にも気 を遣うアバド、などと言うなら、ジュリーニは最もとっつきにくいというか硬派に思える人で、楽曲を分解するようにやるジュリーニ、とでもいったところで しょうか。それを単純にドイツ的構成力などと言って良いものやら疑問に感じるものの、残り二人とはちょっと次元が違うところがある気はします。一言で特徴 を言い難い人なのです。低音弦などでリズムを取る伴奏部分の拍がかくかくと区切れ角張っているところがドイツ的だとは言えるのかもしれません。そこが個人 的にはジュリーニで最も気になるところでもあるのですが。 一方で歌はあるのです。ここで取り上げる「悲愴」と同じ LA フィルとやった「田園」などは旋律線を滑らかに歌い、しなやかに延ばすフレーズも聞かれて美しいものです。それをイタリア風カンタービレとみなして、イタ リア流とドイツ流の融合とする向きもあります。ウィーン・フィルとのブラームスはもっと「カンタービレ」風かもしれません。ただ数年違いの LA フィルとの同曲では違った表現になっている箇所も聞かれます。そういう風に録音によって差が出るのもこの人にはよくあることです。それが指揮者の指示の違 いなのか、オーケストラが元々持っていた歌い方の癖なのかということは私には分かりません。片方の演奏について、下手なオーケストラを鍛えたら感激して言 う事を聞くようになった成果だという説も読みましたが、鍛える前と後にその場にいたわけではないし、そういうことも自分には言えません。上手いオーケスト ラだってばらけることもあるし、セッション録音ではとり直しをするから揃うところもあります。 「分解的」の方の意味はスコアを徹底解明するということです から、教えを受けたトスカニーニとも比べられるかもしれません。トスカニーニが速いテンポで激 情的に引き締まってるとすると、ジュリーニは、少なくとも若いときを除けば、遅いテンポで歌わせつつ分解します。マーラーの9番あたりが代表作でしょう か。恐らくこんな風に言葉で分解するのも一面しか理解しない浅薄な見方でしょうが、音の構成の内部に秘められた味わいを引き出すと言われるように、どの音 もじっくりと納得が行くまで鳴らし切るといった風情で、音符が合わさったときの一つひとつの独特の響きを全てクリアにするところが最大の魅力でしょう。ブ ラームスの第4番の第二楽章などを聞いているとそれが分かる気がします。それであってもチェリビダッケがときにそうであるように、普通の解釈では少し速ま るところでも一定の遅さで貫くことで、何かを強く提示しようと挑むような圧力を感じさせるものではありません。同じような音の形であっても、恐らくですが ジュリーニにはあまり独自の表現を狙うような攻撃性はないのであって、もっと内省的に音そのものの方に目が行ってるのだろうと思います。そこが品の良さに も感じられるところです。 結果的に、音の流れを見て凡庸だと思わないなら、難解だと いうことになります。分かるか分からないかで聞き手の成熟を問う試金石のように言う人もありま す。ジュリーニの演奏は一部で熱愛するファンがいますが、どのポイントで彼らは支持しているのでしょうか。直接本人に会った音楽関係者は人柄を褒めるし、 その場にいて指示を聞き、出て来た音を聞けば明快に意図が分かるでしょう。実際生でこの人の演奏を聞いたら、あるべきところにあるべきものがあるという単 なる正確さを超えた音の美しさ、奏者が感激して出す力のこもった充実の音色に感動するに違いありません。でも前知識なく録音を聞いてファンになる人もいる でしょうから、そういう人は鋭敏な耳を持っているのかもしれません。 このようにある種の客観性を持った説明しがたいところのあ るジュリーニの演奏、ときに強迫的なぐらいに即物的に聞こえる瞬間もあります。そしてただ知性 的だという範囲を大きく超えた恐ろしく丁寧なところ、頑なまでに細部にこだわってスコアを正確に音にする追求の姿勢を考えると、ある種の天才に見られる ASD 的な人かと思わせますが、人の心に自然に飛び込んで掴んでしまう対人能力や、ウィットと冗談、家族の皆が証言する愛すべき人という話を聞くと、どうやらそ うではなさそうです。一瞬にして人を魅了してしまうところがあるようで、皆の目の輝きが変わり、演奏者の中には一緒にやりたくて遠くから馳せ参じる人もい たほどだそうです。アシスタントだったチョン・ミュンフンも多くのことを学んだという教え上手でもあります。この尊敬される人格はどのように作られたので しょうか。兵役で残酷なものを見て平和主義になり、逃亡罪で終戦まで隠れていたという経験からでしょうか。鋭敏であることは間違いなく、音楽の背後にあ る、我々の分からないことが見えているのかもしれません。元から裕福な家庭に育った人には独特の優雅さと洗練があったりしますが、最後の貴族と呼ばれた ジュリーニの見識にもそんなこととの関わりがあるでしょうか。帽子のせいじゃないと思います。 さて、「悲愴」ですが、ショーマンという性質からは最も遠 く、最近の一部の若い指揮者とは反対に非商業主義の演奏だと言えるでしょう。すでにご紹介した 通りテンポは全体に遅めで、一つひとつの音を丁寧に解きほぐして行きます。ポップでなく、哲学です。哲学というとチェリビダッケを思い出しますが、これも 前述のようにちょっとアプローチが違います。似ているのは自分の感情の高まりによっては安易に動かさない演奏だという点で、スコアの高まりに従うのであっ て、間に一枚コントロールする何かが入っています。あるときはそれが鈍さに感じられ、あるときは独特の緊迫感を生み出します。興奮を探さないで音の美しさ に目を向けると良さが分かってくるかもしれません。一見分かり難いけれど、これは他にない個性の「悲愴」です。 第一楽章は冒頭からファゴットを朗々とよく歌わせます。 ゆったりなテンポで一つひとつ音をくっきりさせながら運びますが、その後順当に速度を上げたりし ます。譜の解釈の通りです。アクセントをつけながらリズムを明確にし、主題の歌の部分は過剰ではないけれどもよく歌います。トータルでは遅めのインテンポ と言えるでしょう。どこかに冷静な頭脳が働いているせいであまり熱くならないようにも聞こえます。フォルテでも走らず、内声部をよく聞かせたりしていま す。とにかく曲の造りがよく見える演奏です。 第二楽章では角張りはしない適度なやわらかさはありなが ら、直線的でややゆったりめの進行です。音符がよく分かりますが、やはり覚めた感覚の舞曲とも言えます。 第三楽章も遅めのテンポでくっきりと拍を区切りながら分解 的に鳴らします。 第四楽章も同じです。ゆったり歌わせますが、揺れ動く感情 を乗せるというよりも建築物のようです。ここでは曲の作りに対して自然に高まる感情要素があま りないように感じられます。音の情動ではなく、やはりスコアの構造を見ているのでしょう。先の心理学者の気質分類で言うなら、感情よりも理性が勝つもの の、努力して感情も十分コントロールできるようにまでなった人であり、直感的というよりも、感覚的な人なのかもしれません。 1980年のドイツ・グラモフォンです。デジタル最初期の 録音になり、大きな音ではきつく感じられます。演奏スタイルに相応しいかどうか、残響はある けれどもあまり被らない方です。演奏の趣旨から、もしフィリップスの最善の録音のようなやわらかく自然なバランスだったら、あるいは少なくともウィーン・ フィルとのブラームスぐらいだったら?を付けていたかもしれません。そこだけがちょっと残念なところです。 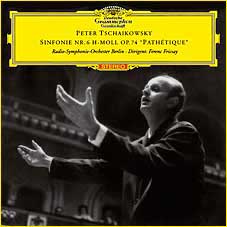 Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Ferenc Fricsay Radio-Symphonie-Orchester Berlin チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 フェレンツ・ フリッチャイ / ベルリン放送交響楽団 人によってはムラヴィンスキーやカラヤンではなく、これこ そが「悲愴」のベストだと熱く語ることのある演奏です。夭折した指揮者が死の四年前に収録した ステレオ録音で、スタイルは戦前のドイツ・ロマン派を思わせるものであり、引きずるように拍が重く、一瞬遅れるところもあります。猛然と走ったりはしませ んが感情に従い、デモーニッシュに揺れるテンポと抑揚でフルトヴェングラーを思わせます。どこか物々しいところさえ感じさせる起伏の大きな熱演であり、カ ラヤンの71年盤とは違って泣いているように深くうねる強弱が付いています。論理的なタイプの人が好みそうなジュリーニやノリントンとは反対の極とでも言 うか、こちらは深く情に浸りたい人向きかもしれません。 興奮や激しさが演奏に表れるという場合、二つの位相がある と言えるでしょうか。歯切れ良い音のダイナミズムと、もう一つは情緒スケールとでも言うか、耽 溺するほどの入れ込みようです。まるで怒りの激しさか泣きの激しさかみたいな話ですが、世の中には怒りからではなく楽しくてバンバン叩くのがやめられない 人もいます。ダイナミックな側の代表としてはカラヤンの71年盤、ムラヴィンスキー、ショルティなどが入るかもしれません。ムラヴィンスキーとショルティ にも秘められて冷たく燃える炎の情念とスポーツライクという緊張の種類の差はあるものの、もう一方の情緒的カテゴリーに入るのはこのフリッチャイとミュン フンあたりでしょうか。ミュンフンは最後の楽章が遅くて大変情熱的ですが、フリッチャイは中二つの楽章も含めてどこを切っても熱をもって情緒的です。では 二つの位相の両方ともがマックスなのはどれでしょうか。そういうのもあるとは思いますが、ここでは触れていない演奏かもしれません。 最初の楽章からふわっと山を作るような大きな抑揚で、拍は 決して軽く弾む種類ではありません。強くなると速まりますが、テンポはトータルで遅い方です。 間が大きく、フレーズは重く引きずります。ビブラートをかけ、静かなパートではたっぷり歌わせます。正に泣いているようであり、思い切り遅くして表情を付 けるところもあります。ある種洗練されているミュンフン以上のものを求めている人にとってはこれほど思いを叶えてくれる演奏はないでしょう。 第二楽章もゆったりたっぷりで、第三楽章もそこそこ速くは なりますが軽快ではありません。第四楽章も然りですが、この「悲愴」をいわゆる「爆演」と言う向きもあるながら、「爆」が文字通り爆発のようなダイナミズ ムを言うのであれば、フリッチャイのはそういう陽性で乾 燥した拡散エネルギーではないと思います。揮発性ではあるかもしれませんが、即物的ではなく、湿りを感じます。伸び縮みして走りはしますが、フルトヴェン グラー/バイロイトみたいに猛然とダッシュすることはなく、重厚です。終わり方も荘重深刻と言えるでしょう。マーラーの第九に記されたように「死ぬよう に」消えて行きます。これが好きなら他には ありません。 1959年のドイツ・グラモフォンで、初期のステレオ録音 です。この時期は音が乾いて感じるものもありますが、DG には案外そうではない録音もあり、この人の中では音が良いものに入ります。LP 時代に廉価版で出ていたモーツァルトの大ミサが大変良かったなというのがこの指揮者について思い出すことですが、好きかどうかは人によるとして、この「悲 愴」もこの人の代表作です。この曲の演奏史の中でも外せない名演でしょう。 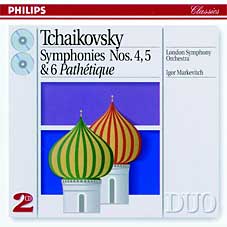 Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Igor Markevitch London Symphony Orchestra チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 イーゴリ・マ ルケヴィチ(マルケヴィッチ)/ ロンドン交響楽団 ロシア生まれで奇才と言われたマルケヴィチ (1912−1983)はお国もののチャイコフスキーあたりが得意とされているので「悲愴」は外せないかもし れません。メリハリがあって激しい、鋭さのある演奏です。細かなテンポ上の細工がよく効かせてあり、静かなときも常に燃え立とうとしているかのようで、離陸寸前のジェット機みたいに、熱くなると待ち構えたように浮き上がって速くなります。巧者な人という印象です。 第一楽章はゆっくりとファゴットを棒のように吹かせる出だ しから、抑え切れずに走り出すというメリハリが印象的です。フォルテでは短く切れる金管に鋭さ があります。全体にゆっくりなところは抑え気味にゆったりよく歌わせ、熱くなるところは急にぐっと力が入ります。例の突然のフォルテは間をあまり取らずに 鋭く速く行きます。その後の盛り上がりも大きめのアゴーギグで、火のように興奮度が高い演奏です。ちょっと怒り系のような気がしないでもありません。 第二楽章は軽快なテンポでさらっとしていながら、途中で語 尾を緩めたりの工夫があります。 第三楽章は中庸のテンポながらくっきりとしたリズムの区切 りに特徴があり、よく表情が付いています。後半は走らないですがテンポを揺り動かし、背後のブ ラスを強調したりする工夫があります。自然さを求めるアプローチとは反対に色々やってある楽章で、大変エネルギッシュです。 注目の第四楽章ですが、ここもテンポは遅くなく、興奮した ようによく伸び縮みします。やはり熱くなると速くなり、最後はスローダウンします。 マルケヴィチは1953年のドイツ・グラモフォンのモノラ ル、1983年の N響などが出ていますが、1962年のこのフィリップス録音は代表的なものとして長く語られてきました。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ユージン・ オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団 オーマンディと来ればフィラデルフィア・サウンド、という 刷り込みで受験知識みたいに覚えてしまっていますが、いざどういう演奏かと聞かれると案外あや ふやだったりします。一般にはゴージャスな艶のある弦と、金粉をまき散らしたようなきらびやかな金管の音がイメージされるのでしょうか。 1981年の録音を聞いてみました。1899年生まれで 1985年没ですから、死の四年前ということになります。彼のレパートリーの中では「悲愴」が褒 められることもあります。出身はハンガリーでユダヤ系のアメリカ人指揮者であり、ご本人は「フィラデルフィア・サウンド」という言い方がずっと気に入らな かったようです。二十二歳のときにアメリカに一人で置いてきぼりにされ、その後アメリカン・ドリームを地で行って成功を掴んだという逸話があります。 豪華絢爛というよりもオーソドックスな演奏であり、また、 流れる音の呼吸があるというよりも、一つひとつの音とフレーズをくっきりと丁寧に鳴らして行く 種類です。そのせいで各パートがどうなっているかがよく分かります。ジュリーニのような凝縮感はあまり感じないかもしれませんが、テンポはどちらかという とゆったりめのインテンポです。そしてそれは、どこかコンテストで完璧な技術を見せる上手な吹奏楽のようにも聞こえます。貶めるつもりで言ったのではない のですが、リズムの伸び縮みを一切加えないでマーチのように進めるからでしょうか。こういうリズムの取り方はどこかで聞いたことがあるような気がします。 よくよく思い出してみると、大公のところでレポートしたイストミンやホルショフスキらのピアノ伴奏は少なくともそんな感じだったかもしれません。この当時 の特定のグループの人に共有された感覚なのかどうか分かりませんが、楽観的と言われる通り、暗さは感じさせません。 レーベルはデロスのデジタル・マスター・シリーズです。 キャロル・ローゼンバーガーのベートーヴェンとか、音は大変良かった印象があります。ここでは明るい金管が前に飛び出すバランスで、残響は多くありませ ん。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Sir Roger Norrington Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 サー・ロ ジャー・ノリントン / シュトゥットガルト放送交響楽団 ピリオド奏法というのか、ノン・ビブラートによる演奏で す。後期(広義の)ロマン派のチャイコフスキーでもそうあるべきかというと、常にビブラートをか けるという演奏方法はごく最近のことなので歴史的には正しいでしょう。ノリントンは大変学究的かつ個性的に演奏する人で、ここでも面白いアプローチで「悲 愴」を聞かせてくれています。チャイコフスキーについても彼は多くの演奏がロマンティックにやり過ぎると考えているようで、冒頭で速度記号にこだわる話を 書きましたが、一番に該当するのはこの人です。 出だしのテンポは速めですが、最初の区切りが来たところで の大変長い間からして個性的です。音だけ聞くと古楽器かと思うようなノンビブラートの弦が美し く、かと思っているといつの間にかテンポが遅くなってきて、案外標準的なところに落ち着きます。そしてそこから先はこの人らしいちょっと癖のあるユニーク なところが出てきます。音符をいくつかのまとまりで分けてその間を切ったり、部分的にスラーを無くしたり、ピチカートを強調したり工夫するのですが、それ とも楽譜がそう読めるのでしょうか。レガートの主旋律の背後で金管がパッパー、パッパー、パッパーと切れたリズムを取っているのをくっきりと聞かせたりも あり、まるで立体のパ ズルのようです。皆が情動が突き上げるようにもつれながら駆け上がるクレッシェンドのパートを直線的にさらっと流したりもします。このテイストは何でしょ うか。ただロマン派の垢を落としただけの学究的な態度という範囲は越えているように感じるのです。大衆受けを狙った派手さとも違っていて、もう少し自分の 世界に入ったクールさがあって、嬉々とした好奇心に満ちているようです。人によってはおどけて聞こえるかもしれませんが、本人は真面目でしょう。この人の ファンがどうなのかは知らないながら、学問等の仕事に就いている人が好みそうな頭脳的プレイである気はします。情緒の霧がすっきりと晴れ、アッチェレラ ンドしても盲目的に熱くはなりません。ありがたいです。でもどこかさばさばしたところがあって新説を学会に発表する学者のようです。感情的要素が欠落して いると言ったのでは非難の言葉になるとしても、現代音楽にも行ける知性がある、あるいはそういう興味を古楽に振り向けているとでも言いましょうか。フリッ チャイの反対の極の一つでしょう。明晰であり、なかなかない種類で私は楽しめました。 ヘンスラー SWR レーベル2004年の録音で音は見通しが良く透明です。 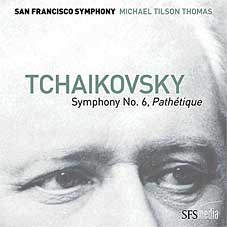 Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony ♥ チャイコフス キー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 マイケル・ ティルソン・トーマス / サンフランシスコ交響楽団 ♥ チャイコフスキーがゲイならティルソン・トーマスはどうで しょう、などと言うと差別的でしょうか。そういうつもりはないのですが、音楽芸術を扱うのにそ の土俵での比較はカテゴリー錯誤かもしれません。ファッションセンスが良く、年齢を感じさせない華やかな人という印象のティルソン・トーマスですが、性的 指向はともかく、 その繊細で攻撃性を感じさせない演奏は、どこかでチャイコフスキーとつながるものがある気もします。 自前のサン・フランシスコ SFS メディアによる2017年の録音ですが、残念ながらこれは配信のみで、CD クオリティも含めて192KHz24bit まで選べるものの CD にはなっていません。とりあえず例外として扱います。 人によっては平板に感じるかもしれない完成された演奏だと 思います。大変きれいな音です。全てのパートが見渡せるクリアなもので、ブラスも割れません。 自然なホールトーンというよりも、弦も木管も金管もベストな音で個別に捉えたようなきれいさです。セッション録音なのでしょうか。表現の方も同様に細部ま で見渡せる完璧で落ち着いたものであり、細やかさも感じられます。曲がどうなってるか知りたければこの演奏を聞けば良いでしょう。そしてそれ以上 に美しいものです。 第一楽章は艶のあるきれいな音でゆっくり抑揚をつけて歌わ せます。一フレーズずつくっきりさせて決して走らず、一音たりともなおざりにせず美音で形にし て行きます。フォルテでも全体の音の形が崩れないように鳴らしているように聞こえます。途中そのフォルテの前で大変遅くなります。 第二楽章は明るくくっきりとした舞曲です。一点の曇りもな く、ここでもフォルテで力を込め過ぎません。 第三楽章も明晰なリズムでくっきりしています。 第四楽章はスコアの全ての音を明確に美しく鳴らし切ること を目標にしたような演奏に聞こえます。ゆったりとしてどこまでもクリアです。テンポは遅く、ど んなときも崩れません。きれいな演奏の代表としてデュトワ盤をすでに挙げましたが、そちらが滑らかにつながりつつ前後に動きのある抑揚の美しさなら、こち らはクリスタルのように静的な意味で音色と形が美しいのです。どちらもデリケートな味わいであることは違いがなく、好みの問題ですが、少年時代にデリケー トで傷つきやすいものを愛でていたチャイコフスキーはどちらが好みだったでしょう。  大まかに21世紀に入った頃から、いくつかの分野では洗練 よりも庶民好みの派手なものが主流になってきた気がします。オーディオ製品の音の傾向もそうい うところがありますが、分かりやすいのは自動車の形でしょう。買い替え促進の周期変化とも言えるものの、80年代に真四角だったものが90年代には端部が 絞られ、2000年前後には有機体のような曲面構成でシンプルになりました。そして新しい世紀が胎動するとまた逆転して、プレスラインを多用した多面体構 造になって行き、グリルのファミリーフェイス化と樹脂メッキの進歩で装飾が増え、ヘッドライト材質の変化と LED の普及から形の自由度に拍車がかかって、二十年ぐらいかけて大変華美になってきました。デザイナー視点では大人から小学生の隈取りデザインへと退行したも のと言われかねませんが、こういう流れは技術革新によって消費者側の需要に細かく対応可能になった商業主義を見ているということなのかもしれません。物欲 に左右されないミレニアル世代だとか、スノーデンやら報道管制から外れた VICE の台頭やらという話を聞くと逆方向じゃないかとも思えてきますが、世代の社会的性格論などは初めから切り口がいかがわしいのであって、「ドゥー・イット・ フォー・ザ・グラム(インスタ受け狙いだけで行うこと)」や ソーシャル・メディアでの他人の目を気にする様子を見れば、ああやっぱりそっちの流れか、とも思えてきます。今後行き着くところまで行けばまた戻って来る のか多極化するのかは分 かりませんが。 この21世紀のトレンドはクラシック音楽界もちょっとだけ 似てるかもしれません。前の世代にもレニー・バーンスタインやグレン・グールドなど、新しい自 我のスタイルを印象づける人たちがいましたが、最近の世代の中にはよりサービス精神に溢れた思い切った表現をする人も出てきているようです。これはリー ダーの形の変化ではなく、指揮者のみならずソロイストもそうです。そしてこんなことを言っておいて次に CD を紹介したのではなんだか悪く言うように聞こえるかもしれませんが、好みはともかくとして、人々の気持ちを上手く捉えるというのは上から押しつけの権威主 義ではないわけで、大変民主的な態度だとも言えます。二十年後も同じ演奏をしているかどうかは人によるとしても、ポップに、ロック的に乗れる音楽に近いと も言えるでしょう。   Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Teodor Currentzis MusicAeterna チャイコフスキー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 テオドール・クルレンツィス / ムジカエテルナ 1981年生まれのベネズエラの指揮者グスターヴォ・ドゥ ダメルもその幻想交響曲の録音を聞いたときに同じような傾向を感じたのですが(「悲愴」はまだ 出してないようです)、このぐらいの年代の人にはメリハリをつけ、ポップで分かりやすく強調された表現を見せる一つの傾向があるように思います。78年生 まれのアンドリス・ネルソンスは違うものの、72年生まれのギリシャの指揮者、クルレンツィスもそんな一人と言ったら大雑把過ぎるでしょうか。2004年 に創設されたロシアのアンサンブル、ムジカエテルナを率いて人気が出て来ているようです。 アクセントの付け方が違います。工夫があるのです。そして 何気なく進めて行ってフレーズの最後で強く強調したり、繰り返しの二回目をぐっと弱くしたり、 ふわっと飲み込まれるようなピアニシモのエアポケットを作ったりします。また、不均等なリズムでスウィングしたり、大変に長い間を空けたりもありで、とに かく表情が大きいです。まるで映画の効果音 楽のような感じに狙いが明確です。それは第 二楽章も同様で、バックの弦の音をスタッカートで切った上で目立たせたり、第三楽章ではリズムを不均等に強調して面 白く乗れるようにしたりしています。最終楽章でもやはり繰り返しの二回目を消えるようにやらせ、泣いて息が切れるみたいな抑揚にしたりして飽きさせませ ん。 2015の録音でレーベルはソニー・クラシカルです。なん と現代でもセッション録音のようであり、音が良いことへの期待を裏切りません。  Tchaikovsky Symphony No.6 op.74 "Path?tique" Yannick N?zet-S?guin Rotterdam Philharmonic Orchestra チャイコフスキー / 交響曲第6番 op.74「悲愴」 ヤニック・ネゼ=セガン / ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 1975年生まれのカナダの指揮者です。この人もクルレン ツィスと表情の大きさにおいてはちょっと似た感じもします。少なくともネルソンスよりけれん味 があるだろうと思うのです。楽譜通りにやるのも違いが分からないけれども、こういう風に表情豊かなのも違いを言うのが難しく感じるわけで、それぞれに強調 する箇所や手法は異なるとしても、明るさに目が眩んだように、恐らくまだ自分が上手く読み取り速度を合わせられてないのだと思います。敢えて言えばリズム に工夫を加えて面白くしたり 裏の音を強調したりといった仕掛けよりも、感情によって速度を動かすという意味でのアゴーギグによってドラマチックにぶつけてくる感じでしょう か。カナダという土地柄に関係あるかどうかは分かりませんが、クルレンツィスよりも真っ直ぐで強く、情熱方向に寄った起伏の大きさを感じさせます。例えば ドゥダメルが全ての武器を一度に使って攻めて来るのに対して、クルレンツィスは技のデパートであり、あらゆる手を順次用いて激し さを表現するなどということが言えるのかもしれませんが、この二人の違いを上手く表現できないのはまだ許していただくとして も、このネゼ=セガンまで含めるのはやっぱりいけないのかもしれません。 ゆったりと入って間を空けます。途中興奮したように加速し、一瞬のスタッカートも交えて奮い立ったりします。かと思えばすごく遅くして間を空ける場面もあります。強いところでは速く爆発的に、静かなところは遅くたっぷりと間を取ります。木管のフレーズ後半を一部強調したり、ふっと弱める強弱の表情など、工夫と思い入れがあります。ドラマチックを演出していると言える面もあると思いますが、爆発的で大変速いフォルテはやはり多くの人に好まれるでしょう。スケールの大きな熱演が好きならネルソンスやクルレンツィスよりこちらでしょう。 ドイツ・グラモフォン2012年の録音ですが、ライヴ収録 全盛時代にこちらもお金のかかるセッション録音です。元が取れるほど売れる見込みなのだと思います。 INDEX |