|
クラシック音楽ファン向きのジャズ?
ビル・エヴァンスとその他の人たち Jazz for Classical Music Fans? Bill Evans and Other Musicians  取り上げるプレイヤー 26人:シャニ・ディリュカ/ ジャン=イヴ・ティボーデ/ ビル・エヴァンス/ トミー・フラナガン/ オスカー・ピーターソン / クレア・フィッシャー/ ドン・フリードマン/ デニー・ザイトリン/ キース・ジャレット/ チック・コリア/ ハービー・ハンコック / スティーヴ・キューン/ エンリコ・ピエラヌンツィ/ アラン・パスクァ/ フレッド・ハーシュ/ ティエリー・ラング/ ミシェル・ペトルチアーニ / ジョバンニ・ミラバッシ/ ブラッド・メルドー/ ミシェル・ビスチェリア/ ステファノ・ボラーニ/ マルチン・ボシレフスキ / ヨーロピアン・ジャズ・トリオ/ デイヴ・グルーシン/ パット・メセニー/ ヤン・ガルバレク タイトルではクラシック音楽の愛好家が特に好むジャズがあるかのごとくですが、答えは横へ置いておくとして、そんなことがよく言われるのは事実です。そしてその際に真っ先にあがる名前の一つにビル・エヴァンスがあるのではないでしょうか。有名なジャズのピアニスト (1929-1980) で、フランス印象派の音楽にも近いようなその音はクラシックの素養があったからだとも言われます。ジャズの話をしたのではこのページの今までの慣例からは脱線ですし、この分野で何かを言えるほど知識もないのですが、それでも今回は特別にジャズの演奏家をちょっとだけ覗いてみようと思います。旋律とハーモニーの観点からも美しく、リズムと即興が主体となるジャズのイディオムに慣れていない人でも心地良くていつまでも聞いていたくなるようなアルバム、しかも決して安っぽくはないものを何点かご紹介しようと思うのです。いわゆるお洒落なジャズ、といいますか。 因みにそういうジャンルは英語ではリラクシング・ジャズ、スムーズ・ジャズ(90年代以降)、カクテル・ジャズなどと言われることがあり、日本語ではソフトジャズとも呼んで、「カフェやバー、ホテルのラウンジに流れてるようなジャズ」と表現する人が多いようです。気にすることはないけど、本格を自認するファンからは馬鹿にされてしまい、一方でビル・エヴァンスをそこに含めると、今度は反対に叱られる危険性があります。それ専門のミュージシャンと思われる人たちもいることなので、ここではちゃんとジャズのカテゴリーに入る人たちを、キース・ジャレット、ティエリー・ラングからマルチン・ボシレフスキまで、ピアノを中心に見て行きます。
ビル・エヴァンス他の CD 評はこちら(ジャズの解説を飛ばします)  Road 66 Shani Diluka Shani Diluka (pf) ロード 66 / シャニ・ディリュカ シャニ・ディリュカ(ピアノ)  Conversations with Bill Evans Jean-Yves Thibaudet Jean-Yves Thibaudet (pf) ワルツ・フォー・デビー〜ビル・エヴァンスに捧ぐ / ジャン=イヴ・ティボーデ ジャン=イヴ・ティボーデ(ピアノ) ビル・エヴァンスの翻訳 このページでジャズを取り上げる言い訳としてまず思いついたのが、クラシックのピアニストによるビル・エヴァンスの音楽です。言い訳にするのは失礼なのですが、本格的にジャズも弾けることで有名な演奏家としては、エヴァンス流儀ではないけれども古くはウィーンの奇才、フリードリヒ・グルダや指揮でも有名なアンドレ・プレヴィンがいます。最近の人としては、すでにグリーグの協奏曲のページで取り上げていたパキスタン生まれでモナコ育ちというシャニ・ディルュカの一枚、「ロード66」(写真上)の中にエヴァンスの有名曲、ワルツ・フォー・デビーが入っていました。この人特有のたっぷりとしたロマンティシズムと憧れを未来に投げるようなメンタリティが人によってはどうかなと思わなくもないですが、アメリカの作曲家の曲ばかりを集めた一枚で、大変きれいな音が続きます。 フランスのクラシックのピアニスト、ジャン=イヴ・ティボーデも「ビル・エヴァンスとの会話(邦題「ワルツ・フォー・デビー〜ビル・エヴァンスに捧ぐ)」というアルバムを1997年に出しています(96年録音/写真下)。61年リヨン生まれで超絶技巧についても語られる人ながらファッション界でも有名だそうで、写真を見るとすぐに気づくだろう通り、この方もゲイのようです。そういう話を毎回するのもなんだかですが、この方面に繊細な感受性の持ち主が多いことは事実。フランス生まれということですから自分としてはラヴェルが気になるところで、それでもラヴェルのページで取り上げなかったのは全く個人的な嗜好の問題でした。この人にはリズムをくっきりと切って粋にスタッカートを使い分ける独自の表現があり、また自在に歩調を変え、あるフレーズだけ音を飲み込むようにすっと弱める手法も聞かれます。そういうところが個性的であり、逆にそんな風にラヴェルを題材にして自身のセンスを見せてくれるようなところが好みではなかったのです。でもそれはあくまでも自分の聞き方であり、単に技巧に優れるだけではない、詩情溢れるピアニストだと思います。 この CD、出だしからきらびやかで、あでやかな香水の香りがする音楽という印象です。装飾が華やかであり、それが確かな技巧に裏打ちされて正確に鳴らされます。したがってすでにエヴァンスに馴染んでいる人にとってはエヴァンスの音楽には聞こえないでしょう。これらは即興なのでしょうか。いずれにせよ楽譜に決められた音ではない点でクラシックのピアニストが持つ表現は越えていると思います。何に似ているのかというと、ジャズというよりはポピュラー音楽のピアノに近く、思い当たったのはやはりシャンソンでした。フランス人の血は争えないとは言いたくないのですが、昔レコードで聞いた、ホテルのレストランで弾いていたというボルドー生まれのピアニストの音を思い出しました。ケ・セラ・セラもセ・ラヴィもシャンソンではありませんが、なんかそんな「なるようになるさ、人生そんなもの」とサラサラと流すアンニュイな感覚が、それこそバーかホテルのラウンジから聞こえてきてもおかしくありません。元々ヨーロッパ風なところがあると言われたエヴァンスの音楽がよりヨーロピアンになったと言ってもいいでしょう。ムード音楽では片付けられない技巧派のシャンソン・エヴァンスです。 ではクラシックとジャズでは、ピアノの弾き方としてはどう違うのでしょうか。即興かどうか云々という話を除いてです。このジャン=イヴ・ティボーデはジャズっぽくはないと書いたわけですが、具体的に言うならば拍の遅らせ方や裏拍の問題はまずあるでしょう。それは仕方ないとしても、例えばジャズで装飾を付ける場合、拍と拍の間に小気味良くぎゅっと飾りを畳み込みます。しかしこの人のシャンソン的とも言える弾き方では、元々の何分の何拍子という運びがルバートのように延び縮みして、その駆けたり止まったりの動きの中の止まっている部分に自在な装飾がずらずらっと入って来ます。それが玉を連ねるように豊穣なのです。別の言い方をすれば、ジャズは拍の入りを微妙に遅らせたりはあるものの、全体のリズムは一定に推移するイン・テンポ (速くなったり遅くなったりしない)です。一方でクラシックのピアニストはテンポを延び縮みさせ、強弱も弱い方をぐっと抑えたりするのが常套的手段です。両者は相容れません。無論クラシックもバロックから古典派ぐらいまではイン・テンポだったし、ルバート奏法にしても基本は音を遅らせたら残りの小節は速めてバランスを取り、全体のテンポは一定というのが基本でした。あのショパンでさえ左手は等速リズムだったという説もあるようです。ただロマン派以降の作品ではテンポを大きくずらしたり、消え入るようなピアニシモの表現が出て来るようになりました。フランス流儀のルバートで有名だったコルトーからサンソン・フランソワまで、テンポの延びたり縮んだりはピアニストにとって当たり前の武器になって来たのです。 したがってここでのジャン=イヴ・ティボーデの演奏は、 ジャズ耳の人には変な音楽に聞こえるかもしれません。しかしテンポ処理はそんなものでも全体にはゆったり波打たせてフレンチらしくよく歌っており、思い入れたっぷりで夢見るような風情があります。ゴージャスで耳に心地良い音楽です。デッカの録音で音もきれいです。 余談ですが、クラシックのピアニストがビル・エヴァンスに近づく方向とは真逆に、ビル・エヴァンス自身がクラシック音楽に近づいた録音というのもあります。「ビル・エヴァンス・トリオ・ウィズ・シンフォニー・オーケストラ」というタイトルのもので、1965年録音の盤(Verve 1966)です。珍しくエヴァンスがクラシックの曲を取り上げており、バックはオーケストラです。この年代、ことオーケストラとなると最高の録音コンディションではなくなってしまいますが、グラナドス、バッハ、スクリャービン、フォーレ、ショパンなどをトリオで弾いていて、バッハはオーケストラ部分がなければジャック・ルーシエみたいでもあります。メロディアスなのでクラシック愛好家には聞きやすいかもしれません。ただ、曲目構成のせいかオーケストラ伴奏だからか、ジャズ・ファンからの評価は低いようです。トリオの部分はジャズの演奏としてもしっかりしたものだと思いますし、オーケストラも安っぽくならずに上手にまとめているのですが、やはり一昔前の白黒映画の背景音楽のような懐かしい響きではあります。 さて、こうしてエヴァンスに捧げるクラシック畑のピアニストを少し聞いてみて感じるのは、この種類の音楽は情感たっぷりに弾く誘惑が強いのだろうということです。演奏家自身もそういう質の人の方が絶対数が多いのかもしれないですが、あらためてビル・エヴァンス本人の演奏に接すると、それが決して甘さのないものであることに気づいて驚くわけです。あれほどメロウなジャズのイメージがあってクラシックの愛好家がこぞって聞きたがり、流しておくとその場の雰囲気を盛り上げるものでありながら、決して情に流されていない。あの耳に心地良い音楽の魅力はどうやら甘く弾くところから出て来るのではなさそうです。 そんなわけで、ここからはビル・エヴァンス本人の演奏に移って行きます。ただその前にもう少しジャズの一般的なことと、それがクラシック音楽と異質である点について書いてみます。知っている人には余分な話なので飛ばしてください。  やっぱり気になる、クラシック愛好家向きのジャズという考え クラシック・ファンの愛好するジャズがあるか、という話についてやはり考えてみることにします。 といってもクラシックの曲が含まれてるジャズなら好きだろう、という単純なことではありません。そして、それとちょうど反対にジャズ・ファンの愛好するクラシックがあるか、という設問も立てられます。そもそも色々なファンがいていいのだから、大雑把な傾向の話に過ぎませんが。 後者でまず思いつくのは、ジャズを愛好する人たちの中には、クラシックでは「技巧派」と呼ばれる曲やピアニストを好む傾向が潜んでいはしないか、ということです。理由は後で述べますが、例えばリストやラフマニノフの3番の協奏曲とかになるでしょうか、ピアニストで言えば技術の鮮やかさが印象的でバリバリ弾いてるように聞こえる瞬間もある人たち、古くはホロヴィッツ、アルゲリッチ、ポリーニ、ベルマンかもしれないし、新しいところはこのページでは扱ってない可能性もあるのでその方面に明るい人に任せるとして、まずそんな傾向がありはしないか。必ずしもジャズがそういう音楽だと言ってるわけではないのです。ただ、仮にそんなファンがいらっしゃったとして、その方たちはクラシックの中でも静かでメロディアスな曲や、繊細な抑揚こそすべてというピアニストは苦手、あるいはつまらなく感じるかもしれません。 一方で、クラシック音楽を愛好する人がジャズを苦手とする傾向があるとすれば、それはどんな点なのでしょ う。こういう問題はそれぞれの音楽の成り立ちと演奏のされ方にヒントがあるかもしれません。恐らくですが、現代音楽の好きな人を除いて、メロディときれいな和音の配列を心地良く感じるクラシック音楽の愛好家にとって、ジャズのなかでも最も取っつき難いのがいわゆる「ビバップ bebop」傾向の強い曲ということになるのだろうと思います。「バップ」とも略されます。クラシックの現代音楽に当たるフリー・ジャズを除けば、です。つまりフリー系とビバップ要素の強いものは一般に苦手に思われてるだろうということです。フリー・ジャズの方は一時期の流行であって、ちょうど十二音技法とパラレルでジャズの中でも好きな人が聞くものなので横へ置くとして、ビバップの方はジャズの根幹に関わります。アルト・サックスのチャーリー・パーカーとトランペットのディジー・ガレスピーが切り開いたなどと言われますが、それは広義の「モダン・ジャズ」の幕開けであって、モダン・ジャズというのはニューオーリンズのディキシーランドやスウィングなどの古い形を除けば、ジャズと言ったら一般にはまずこれという、いわゆるジャズです。 そうなると、そもそもが最もジャズらしいジャズはクラシック愛好家には敷居が高いということになってしまうわけですが。 そしてビバップ、このいわゆるジャズ音楽の中心にあるのが「コード進行だけが決まっている即興演奏」ということになります。辞書のような話ですみません。そしてその周辺要素として、メロディー楽器もまるで打楽器のように扱う方法、そうやってリズムを中心にして旋律や和音のきれいさを求めない傾向、めまぐるしく即興のフレーズを詰め込むスポーツのような腕比べ合戦などがあるでしょう。 これらクラシック音楽愛好家が取っつき難いだろうビバップ的要素がどこから出て来たのかとなると、二つほど考えられます。一つはビバップが「プレイヤー中心」の反発のムーブメントだったということ、二つ目としては、アフリカ系のミュージシャンの持つリズムへの傾斜とバイタリティーのようなものが想定されるということです: 技術としてのジャズ ジャズがプレイヤー側の視点を中心に展開しがちだということは、クラシック音楽のように楽譜にあらかじめ書かれているわけではないところから来るわけですが、それはジャズに詳しい人たちが常に演奏技巧や流儀を論じる方向に行く傾向からも分かります。この曲きれいだよ、とは言いません。すごい曲だよ、と言います。そして普通にピアノを習いましたというクラシックの愛好家よりも、ジャズで楽器を触る人の方が音楽理論はよほど知ってます。ジャズは音を自分で選んで行くから知らないでは済まされないのです。それもあってクラシックの人はメロディとハーモニーで聞きがちだし、ジャズの人は技法に目が行きがちなのだと思います。だから実際に演奏をする人たちの間ではいつも「あの音を出せるか」や即興の入れ方が話題になりますし、「この展開から次にあの音に行くのはちょっと新しい」などと、あらゆる可能性が探求され尽くしたかのような現在でも、他の人がやらない展開を見せられるかが勝負どころであるようです。こうして他との差異を求めるのは理性の営みです。そしてそもそもが、ビバップのパイオニアたちはビッグバンドのマンネリ化した音楽に反発して即興演奏を始めたのでした。 黒人音楽として ブラック・ミュージックかどうか、という二つ目の点になってくると、そもそもファンキー、ブルージーというのはアフリカ系の人がやって来たジャズについて今もよく形容される言葉で、白人の演奏でもそう評されることがあります。ジャズにはそういう感覚が残っているのです。そして、これは今や差別用語のように響く言葉ながら、わが国のジャズ評論の中で長らく言われてきた分類には「黒ジャズ/白ジャズ」というのがありました。ことビバップに関してはそれと黒ジャズはほぼ同義語になるのですが、リズムと技巧、即興が中心になりがちなのがアフリカ系(黒人)ミュージシャンで、メロディとハーモニーを重んじるのがコケイジャン(白人)のジャズマンだ・・・そう簡単には言えないにせよ、なんかそんな流派の分類が存在するし、文化のルーツによっての違いは未だにあるぞという話です。 本来アフリカの草原ではトーキングドラムの叩き方で遠くまで情報伝達をしていたわけで、聞けばその音はまるでビバップの即興のようです。ラップ・ミュージックが言葉でリズムを取るように、彼らにとって音楽は会話に近い感覚なのでしょう。ですから叩く方についてはアフリカ系の人の血の中に素晴らしい能力が織り込まれているのかもしれません。クラシックでも難解なものや現代音楽を嗜むと本格ファンのように思われがちなのと同様、ジャズの世界ではメロディアスでキレイだから好き、などと言うと馬鹿にされる傾向があります。波及してそれがジャズ・ファン全体の風潮だとしても、元々はアフリカの文化に関係があるのかもしれません。昔ほど差別がなくなって来ている現代でもアフリカ系の人たちが自分たち自身でブラックらしくあろうとする感覚は残っており、白人にも人気があったホイットニー・ヒューストンが黒人らしくない音楽だと酷評され、追い詰められて行ったというのは記憶に新しいところです。 黒っぽい、はこと音楽に関しては死語ではないわけです。 他の流派の方が聞きやすい? もしビバップのようにプレイヤー側が中心になって即興テクニックを競うもの、ではないジャズの方がクラシック愛好家には受け入れやすいということならば、ビバップに対抗して出て来たクール・ジャズやその延長線上にあるウェストコースト・ジャズという流派に分類されるミュージシャンの方が馴染めるでしょう。事実、コマーシャルなどで「タイム・アウト」が有名になったデイヴ・ブルーベックなどはクラシック・ファンの口からもよく聞かれる名前で、メロウな泣きのサックスで知られるスタン・ゲッツやアート・ペッパーなども全てその引き出しに入れられます。この人たちはみな白人です。 エヴァンス派 ビル・エヴァンスも白人ですが、何派か、という上辺の形式はあまり意味を持たないかもしれません。ひとつには彼には色々な要素があることと、例えば歴史学の定説が何十年かしてすっかり塗り替えられるまでは「事実」だと思われているのと同じで、元来派閥自体が一つの見方に過ぎないからです。たとえそれが覆らない定説であっても、実際に聞いて感じられるのはミュージシャンの生の個性による違いです。 でもとりあえずビル・エヴァンスはピアノの流派としては元祖、エヴァンス派、などと言われます。これと対立するのが、彼より前からずっと主流だったパウエル派、です。二大潮流だとされます。バド・パウエルという黒人ピアニストはビバップを中心的に担った人で、リズムと即興技巧重視です。そしてクラシック音楽の素養があったエヴァンスは印象派のような和声を導き入れたとよく言われます。そんな彼がジャズの世界で決して軽んじられないのは、一時期マイルス(・デイヴィス)のバンドにいたからでしょうか。でも「あのエヴァンスだって、マイルスんとこにいたんだよ」は実は逆の話であって、マイルスの方こそがエヴァンスを必要としていたのだという見方もあります。決して軽んじられない革新的なアイディアも持っていた、ということでしょう。 何系の民族の血を引いているのかということが気になるのであれば、エヴァンスは母が東欧のスラヴ系の人、父がウェールズ(イギリス)系とのことです。 エヴァンスのソロについて やっと WIKI に書いてあるような話も終わり、本当にビル・エヴァンスの CD を取り上げるときがきました。ところがその前にまだ一つ・・・ジャン=イヴ・ティボーデはピアノ・ソロでした。それなら比較の意味でビル・エヴァンスもなぜソロをまず出さないのか(出しません)、についてです。 言い訳ばかりになりますが、それはエヴァンスのソロはちょっと雰囲気が異なるからです。トリオ演奏のときと違って音数が多く、間が詰んでいます。前のめりでアグレッシブな感じなのです。一人多重録音のものだけではありません。本当のソロ・アルバムもです。実は多重録音のアルバムが出る前からソロの録音はしていて、それはジャズ・ピアノのソロというものが一般に浸透するより前の60年代の出来事なので彼の偉大な一歩を示していると言えるのでしょうが、どうやらその攻撃的な波長が災いしてお蔵入りになっていた事情があるようなのです。そしてそのこと自体はプロデューサーの勘違いでもったいない話だったとしても、ここではクラシック音楽のファンでメロディアスなものを好む人に紹介するという考えなので、ソロでないもののご紹介、となるわけです。 しかしこの件、本格的にジャズに突っ込んでる人に話すと真逆に否定されてしまうかもしれません。「エヴァンスのソロってちょっと聞き難いよね」と持ちかけると、「何を言ってるの、それこそが面白いんだよ」と返ってくるのです。普段懇意にしてもらっていて色々教えていただいている飲食店のご主人にそう指摘され、そうか、と思いました。彼はジャズ・ギタリストなのです。この記事自体が恥ずかしい限りですが、エヴァンスのピアノは三拍子と四拍子を混ぜたりして大変新しいことをしている、と言われてしまいました。その話で有名なのは「アット・ザ・モントルー・ジャズ・フェスティバル」の「いつか王子様が」でしょうか。常に実験精神に満ちていて高度なことにチャ レンジしていたエヴァンス、彼自身もソロについては特別な考えを持っていたようです。ですからジャズを分かる人はトリオの演奏よりもむしろソロにこそ興味を持つでしょう。キース・ジャレットのソロがジャズのプロからは敬遠され、トリオが評価されるのとは逆転の構図です。そしてクラシックの愛好家でもアグレッシブな技巧派の演奏者を好まれる方(むしろその方が人口は多いのかもしれません)や、技法に明るくて現代音楽を楽しむ知識をお持ちの方にとっても、ビル・エヴァンスはソロの方が面白いかもしれません。  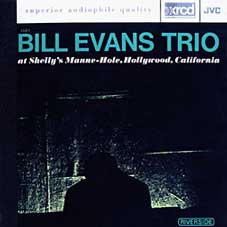 Bill Evans At Shelly's Manne-Hole ♥♥ Bill Evans (p) Chuck Israels (b) Larry Bunker (d) アット・シェリーズ・マン・ホール / ビル・エヴァンス・トリオ ♥♥ ビル・エヴァンス(ピアノ)/チャック・イズレイエルズ(ベース)/ラリー・バンカー(ドラムス) ビル・エヴァンスでこれが一番などと言ったら、ジャズ通の人から反論されてしまうでしょうか。というのも、ビル・エヴァンスの最高傑作とされるのはリバーサイド四部作と呼ばれるものであって、この CD はそこに入っていないからです。リバーサイドというのはレーベル名で、その四部作は「ポートレイト・イン・ジャズ」、「イクスプロレイションズ」、「ワルツ・ フォー・デビイ」、「サンデー・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」です。それらは1959年の二月から61年の六月にかけて収録されたもので、なぜそれが定番かとなるとまずこの話が必ず出て来るのですが、このときのベーシストがイタリア系アメリカ人のスコット・ラファロだからというものです。その人のベースはただ低音を伴奏で弾いて行くスタイルではなく、主旋律を受け持つピアノと同等の動きで対話をしており、それは「インタープレイ(相互作用)」と呼ばれてジャズ史のなかでも画期的な出来事だとされているからなのです。その後のピアノ・トリオは皆この方向に行きました。確かによく聞いてみると言われる通りで、すすり泣くような高い音でベースがメロディー・ラインを歌うかのようにピアノと絡みます。素晴らしいと思います。 でもあえてこれを出します。このアット・シェリーズ・マン・ホールの方は1963年ですが、実は61年の7月の深夜にハイウェイを逸れた車が激しく立木に衝突炎上するという事故でラファロは亡くなってしまいました。そのショックで数ヶ月の間エヴァンスは演奏ができなかったといいます。そしてこの録音はその痛手から立ち直った頃のものです。それでジャケットもそんな失意のエヴァンスを象徴するうつむいた黒い影の人物になっているのですが、音楽の方は聞いていてそんな感じはしません。場所がシェリーズ・マン・ホール、ドラマーのシェリー・マン(エヴァンスと共演もしました)のジャズ・クラブで行われたもので、歩道に星が埋め込まれているハリウッドのウォーク・オブ・フェイムから南東に歩いて数ブロックのところです(今はありません)。LA の空気もあるのか、リラックスして聞こえるゆったりめのナンバーが多く、美しいメロディの聞きやすいスタンダードが主体であり、通しで聞いても飛ばしたくなる曲がありません。それでいてデリケートな歌で安っぽさが全然ないのです。クラシックから入る人はまずここから聞くのをお薦めします。ベースはラファロの代わりにチャック・イスラエル(イズレイエルズ)、ポール・モチアンのドラムに代わってラリー・バンカーというメンバーで、確かに高音で掛け合うように動くベースとは違いますが、落ち着いてて良と思うし、みんな二十五歳で死んだラファロの鍵括弧付きの業績ばかり言い過ぎるんじゃないでしょうか。そのインタープレイにしたって、自然に出て来た彼の個性だと見ても良いと思います。その後の流れを作ったかどうかはともかく、イズレイエルズにはイズレイエルズの大人の個性があります。 その場にいるような生々しい音は最新録音と見まごうばかりです。スティックを落とす音などすぐそこにいるようだし、楽器の音色もきれいであり、その意味でもエヴァンスを聞き始めるのにいいと思います。ここでジャケットの写真を取り上げたのはビクターの XRCD のもので、このシリーズは音に潤いがあってはっきりしており、日本のリマスターとしては珍しくハイ上がりにならず大変良かったのですが、リヴァーサイド四部作の方は今も出ているのにこの盤についてはどうやら廃盤のようです。通常盤でも元録音がいいので気にすることはないかもしれません。 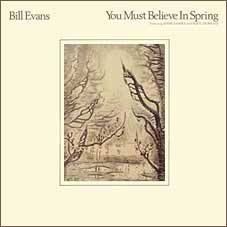 Bill Evans You Must Believe in Spring ♥♥ Bill Evans (p) Eddie Gomez (b) Eliot Zigmund (ds) ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング / ビル・エヴァンス ♥♥ ビル・エヴァンス(ピアノ)/ エディ・ゴメス(ベース)/エリオット・ジグムンド(ドラムス) さて、次も初期(スコット・ラファロとの時期)の傑作を飛ばして、ずっと後のエヴァンスです。死後に発表された晩年の作で、1977年。三年後には療養せずに悪くした肝臓のせいで亡くなるのです。五十一歳でした。ドラッグ・アビューズが原因とされていますが、小説家の自殺かジャズマンのドラッグか、というぐらい当時麻薬の問題はこの世界の人につきまとっていました。王様と言われるヘロインの禁断症状は煙草の比じゃないというのに二十代で自ら納屋にこもってやめたマイルスはやはり偉かった、ということでしょう。よく言われるのはエヴァンスは身内を続けて亡くしているということで、内縁のパートナーは彼の行動が原因で自殺しています。薬物にせよ他の何にせよアディクティヴの人はスローな自殺と言われ、彼もそう言われたわけですが、原因が何か、罪悪感があったかどうかは分からないながら、自らの健康はどうでもよかったようです。 そしてこの頃のエヴァンス、以前とは風貌が違っているのです。5、60年代は当時流行の上が黒ぶちになった眼鏡をかけ、バック・トゥー・ザ・フューチャーのマーティのお父さんであるジョージ・マクフライそっくりにオールバックにしてました(「エニバディ・ホーム?」のいじめっ子、ビフの帝国は実現してしまいましたが)。インタビューでの話し方までちょっと口の中で喋るように(麻薬で傷んだ歯を見せないためだという説もあります)小声でセンテンスを切らずに続けるところも自信のないマクフライみたいですが、70年代にはがらっと変わって長髪に髭、色付きか大きくて四角い眼鏡という、これまた当時の音楽関係者がみんなそうだったスタイルになります。メキシコの麻薬王みたいかもしれません。 どうでもいい話になりましたが、それでは音楽は変わったのかというと、確かにちょっと孤独な音に感じる瞬間があります。何かを諦めたかのようにもの憂げな瞬間。でも抗しがたい澄んだ美しさです。人気のない夜の裏通りで石畳を音もなく雨が濡らすという風情です。最後の二曲を除いてマイナー・キーではあります。しかしこれが一番重要なことなのですが、ビル・エヴァンスの音楽は私生活がどうあれ、常に少し覚めた観察眼を内に秘めていて、決して感傷に陥ったりしないということなのです。このアルバム、技巧にも前衛にも傾かず、少し速いところでもクールな風が吹き抜けて、最初から最後まで統一された美に彩られています。エヴァンスのエヴァンスらしい、到達点と言っていいでしょう。「ウィー・ウィル・ミート・アゲイン」の途中から激情がほとばしるところにはっとします。ラストの「シーム (Theme)・フロム M.A.S.H」での、テーマが提示された後の小気味良い展開部は乗れます(十四歳の書いた歌詞に引きつけて考えるのはどうなんでしょう?)。CD ではその後にボーナス・トラックが入っていますが、いつも思うのだけどバランスを崩します。テイク1と2を続けて入れられるよりはましだし、LP 時代のものは収録時間が短いのでサービスしてくれてるのでしょうけど。 パーソネルはエヴァンスのピアノの他、ここでのベースはエディ・ゴメスで、前述のチャック・イズレイエルズの後にトリオのメンバーになった人です。ラファロとは違った意味で元気が良いことで知られていますが、ここでの演奏は案外シックで目立ちません。ドラムスはエリオット・ジグムンドです。77年のこのアルバムはリマスターがどうこう言わなくても元から録音が素晴らしいです。  Waltz for Debby Bill Evans ♥♥ Bill Evans (p) Scott LaFaro (b) Paul Motian (ds) ワルツ・フォー・デビイ / ビル・エヴァンス ♥♥ ビル・エヴァンス(ピアノ)/ スコット・ラファロ(ベース)/ ポール・モチアン(ドラムス) それでは今度こそ、リバーサイド四部作の中からの一枚で す。ベースのスコット・ラファロが活躍しています。録音は1961年6月で、シリーズの最後になります。そしてこの「ワルツ・フォー・デビイ」はエヴァンスの代表アルバムにして彼自身の曲でもあります。ジャズの CD としても最も売れた一枚なのではないでしょうか。四部作の中で最も聞きやすく、メロディアスなナンバーが揃っています。残りの三作について言えば、評価の高い「ポートレイト・イン・ジャズ」中で旋律的かつスローな構成を持つ曲は、有名な「枯葉」以外には 「ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ」 や「いつか王子様が」であり、「イクスプロレイションズ」には「ホーンテッド・ハート」があり、「サンデー・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」では 「アリス・イン・ワンダーランド」ぐらいでしょうか。このアルバムの方がラファロのプレイを聞かせる意図で先にリリースされたということは知っておいてよいとは思いますが。その点反対に「ワルツ・フォー・デビイ」中でタイトでアドリブ部分が多いのは「マイルストーン」一曲ぐらいであり、それも聞き難いものではありません。残りは静かで美しく、ショパンやドビュッシーが好きという人も納得して通しで浸っていられるでしょう。最初の「マイ・フーリッシュ・ハート」からどこか懐かしく静かな世界に引き込まれます。 ついでに言うのもどうかと思いますが、ワルツ・フォー・デビーという曲はその後ずいぶんたくさんのミュージシャンにカヴァーされています。どれがいいか探すのも楽しいかもしれません。印象に残ったものを一つだけ挙 げさせてもらうとアール・クルーのがあります。ビル・エヴァンスを尊敬し、エヴァンスを目指したいと語ったこともあるフュージョン系のアコースティック・ギタリスト(彼の楽器はいわゆるクラシック・ギター)で、ジャズの本道の人からは軽んじられるし(フュージョンだから)、その曲が入っているデビュー・アルバムの「アール・クルー(1976)」と二枚目の「リビング・インサイド・ユア・ラヴ」をコンピレーションすれば粋なアルバムが作れるものの、全体としては今やちょっと時代を感じさせます。デイヴ・グルーシンのプロデュースを離れた後 はムード音楽寄りなのもあったりで、結局この企画で CD 単位では挙げづらい人です。しかしワルツ・フォー・デビーは本家と比べてもしっとりと美しく、伸び縮みするリズムを感じつつ、伴奏部分の分散和音をアルペジオで加速度的に往復装飾する彼独特の指遣いに揺られて夢見心地になります。それはスパニッシュかフラメンコぽい技法なのかもしれないけど、哀愁のマイナーではなく憧れるようなメジャー・コードでやるところが個性的であり、スペイン・ギター名曲集よりも案外自分はこっちの方が好きかもという、この曲の私的ベストです。二枚目の方にも同様に幻想的な静けさを感じさせる美しいナンバーがあります。 ワルツ・フォー・デビーを歌で聞きたいなら、スウェーデンの歌手、モニカ・ゼダールンドが歌ってビル・エヴァンスが伴奏しているものもあります(「ワルツ・フォー・デビー/モニカ・ゼダールンド・ウィズ・ビル・エヴァンス」1964)。そちらはシックなイズレイエルズ時代のトリオで、ベースがチャック・イズレイエルズ、ドラムスがラリー・バンカーです。これもいいです。 脱線しましたが、エヴァンスのこのアルバム「ワルツ・フォー・デビー」はヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴです。1935年から続いているこの名門ジャズ・クラブはブルーノートとともにニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジにあります。ワールド・トレード・センター(現 One WTC)とエンパイア・ステート・ビルの中間ぐらいの位置です。ジャズ・クラブなので飲食しながら聞くスタイルですが、前述のシェリーズ・マン・ホールのときとは違い、お客さんが話に興じて笑う声が聞こえたりします。その後彼の演奏は伝説化されたので、後世のピアニストたちはこのクラブで演奏することに特別の意味を見出すことになります。 ボーナス・トラックにガーシュウィンの「アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー」が入っており、先ほどはボーナス・トラックは要らないと言っておいて、ちょっとうれしいです。サマータイムと並んで有名なガーシュウィンのこの曲は、シチュエーション、歌詞ともになんとも凄いものです。 独自にリマスターされた XRCD のものがこのアルバムについてはまだ手に入ります。以前から持っていた輸入盤と聞き比べたときは別物かと思うほど自然で潤いのある音に驚き、戻れなくなったのを思い出します。でも最近の通常盤はまた違うのかもしれません。  Affinity Bill Evans and Toots Thielemans ♥ Bill Evans (p) Toots Thielemans (hca) Larry Schneider (fl, as, ts) Marc Johnson (b) Eliot Zigmund (ds) アフィニティ / ビル・エヴァンス&トゥーツ・シールマンス ♥ ビル・エヴァンス(ピアノ)/ トゥーツ・シールマンス(ハーモニカ) ラリー・シュナイダー(フルート/アルト&テナー・サックス) マーク・ジョンソン(ベース)/ エリオット・ジグムンド(ドラムス) ハーモニカの大御所とやったものを一枚。残念ながら通しで聞いて全部ソフィスティケーテッド・サウンド、とも行かないバリっとしたナンバーも多少挟まってるかもしれませんが(♡にします)、少なくともハーモニカのトゥーツ・シールマンスとの部分はどれもすごく粋なものばかり。1978年ですから「ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング」の後、エヴァンスももう残すところ少なくなってきた頃のアルバムです。 シールマンスはブリュッセル出身のベルギー貴族で1922年生まれ、2016年に亡くなっています。ジャズのハーモニカの第一人者ということで、その熟達のテクニックは驚くばかり。初めて聞くと何の音だろう、アコーディオンかバンドネオンなどの鍵盤付きの楽器かなと思ってしまうほど正確な音階は、どんなに速くてもくっきりとしています。クロマチック・ハーモニカというスライド・レバーで半音が出せるものなので、弦で言うところのポルタメントのように中間をずらす音も自由自在。それがまたジャジーな雰囲気を盛り上げるのです。ギター・シンセのハーモニカ風サウンド(?)では似たものも聞いたことがありますが、本物で出来るとは。水に滲んで行く水彩絵の具のようであり、ふわっと漂って心に沁みます。ジャズ畑ということから当然かもしれないけど、ジャズのイディオムを完璧に身に付けたスケールの崩しとアドリブのリックが、まるでピアノのようによどみなく飾りをつけます。ため息の出る美しい展開で、エヴァンスの隠れた名盤でしょう。 それならこんなすごいなハーモニカ、この人以外にいるのかというと、思いつくのはホリー・コールのアルバム、「ドント・スモーク・イン・ベッド」で吹いていたハワード・レヴィ(1951年生まれのアメリカ人)ぐらいでしょうか。「テネシー・ワルツ」は見事でした。他にも若い世代の何人かは技巧的にシールマンスを凌駕すると言われていて、そのうちの一人はシールマンス本人も激賞なのですが、ジャズは技術の新しさを競う側面がありますから、いくら正確でも細切れの音階ではきれいと思えない場面もあるでしょう。したがってブルーノートでしっかり歌うことを恐れないのはその二人、ぐらいでしょうか。「アフィニティ」、シールマンスとエヴァンスが同じ質だからかどうか、息の合った名人芸の競演です。 これも録音が新しいしスタジオ・セッションなので音は透明です。  Undercurrent Bill Evans & Jim Hall ♥♥ Bill Evans (p) Jim Hall (g) アンダーカレント / ビル・エヴァンス&ジム・ホール ♥♥ ビル・エヴァンス(ピアノ)/ジム・ホール(ギター) 「底流」とか「心に秘めた」という意味のタイトルで、女性が着衣のまま浮かんでいる水の中を捉えた印象的なカヴァー写真ですが、ピアノのエヴァンスとギターのジム・ホールだけによる渋くてクールな一枚です。このちょっと質の似たところがあるとも言える二人が絡み合う、異なる旋律楽器によるデュオは歴史的にも傑作の一つです。甘いギターの音が堪能でき、通しで聞け、特にジャズに明るくないクラシックの愛好家でもきれいだと思うはずです。夜の音楽という感じですが、上のアルバムに続いて「親密な語らい」と表現するのがぴったりです。「心に秘めた(Undercurrent)」もそんな様子を表しているのかもしれません。1962年のアルバムです。 2013年に亡くなったジム・ホールはモダン・ジャズ以降でウェス・モンゴメリーとも並び称されるジャズ・ギターの第一人者。今のジャズ・ギターの拍の取り方を最初に打ち出した人なんだそうです。ジョージ・ベンソンやパット・メセニーよりも先輩の世代になりますが、美しいハーモニー、やわらかく繊細なタッチでクラシック音楽も題材としてよく取り上げ、アルビノーニのアダージョ(Lament for a Fallen Matador 邦題「哀愁のマタドール」)もやったし、「アランフェス協奏曲」は彼の代表作となりました。来日したときのその曲のプレイは派手なバックがなく、また違った趣きで良かったのを覚えています(「ライヴ・イン・トーキョー」として出た CD では LP 時代にカットされていたその曲が入っています。曲自体は1959年にマイルスもやっています)。 ジャズ・ギターについて言えば、クラシックの人が思い浮かべるガット・ギター(クラシック・ギターやフラメンコ・ギター)とは違い、「フル・アコースティック」と呼ばれていてもエレキ・ギターです。つまりピックアップがあって電気で増幅しているのです(だからコンデンサーを変えると音色が変わるなんて言われます)。元の形がアコースティック・ギターで空洞のあるものをフル・アコースティックと呼んでいるに過ぎません。ロック・ギターのようにボディに空洞のないタイプはソリッドと呼ばれますが、ジャズではフル・アコースティックとソリッドの中間である「セミ・アコースティック」ぐらいまでがよく使われるようです。音量も稼げるけれどもまろやかな音色に特徴があります。 他にエヴァンスが旋律楽器と共演しているアルバムではスタン・ゲッツとのもの(「スタン・ゲッツ・アンド・ビル・エヴァンス」)もきれいで聞きやすいですが、テナー・サックスをバリバリ吹かずに美しく歌わせるゲッツに関しては「スタン・ゲッツ・プレイズ」(「星影のステラ」に始まり「ボディ・アンド・ソウル」などのメロディアスなナンバーばかりの1952年の一枚)や「ゲッツ/ジルベルト」(グラミー賞に輝いて大ヒットとなった1963年録音のボサ・ノヴァ・アルバム)などメロウなのが他にもたくさんあるし、ジャズでは王道の金管楽器でもありますので、ここでの趣旨から名前だけ挙げておくにとどめます。  エヴァンスの前及び同世代 ビル・エヴァンスの CD を取り上げて来ましたが、それ以前の世代でも旋律とハーモニーの美しさを感じることのできるジャズはもちろんありました。活躍時期は同じでも年齢は先輩にあたる1919年生まれのジョージ・シアリング George Shearing は イギリス生まれの盲目のピアニストで、スタンダード・ナンバー「バートランドの子守歌」の作曲でも知られます。ジャズ・ヴァイオリンの大家ステファン・グラッペリと共演したりもしました。ジャンルとしてはクール・ジャズのカテゴリーに入るようですが、録音の多くにはストリングスが入ってたりしてちょっと違和感があるでしょうか。でもこの人の1981年の「アット・アンバサダー・オーディトリアム」 というアルバム、古い話ながら、レーザー・ディスクで出てたのですが粋なものでした。DVD も出ましたが CD になったかどうかは定かではありません。アンジェル・ロメロのギター、ブライアン・トーフのベース、最初に挙げたエヴァンスの CD の会場のオーナーであるシェリー・マンのドラムスで、ビル・エヴァンスもやった「オン・ア・クリア・デイ」なんか、弓で弾くベースも加わって幻想的でした。LAの北東にあるパサデナでのライヴですが、ないものを褒めても仕方ありませんので、1989年の「ピアノ」はいかがでしょう。ソロのアルバムです。 「カクテル・アルバム」なんていうあまりいい意味じゃない言葉もあるようだし、ホテルのラウンジみたいなんて言うと安っぽく聞こえますが、お洒落です。エヴァンスより印象派的かもしれません。 エヴァンスの前、及び同世代の代表的なピアニストを列記してみます: ジョージ・シアリング トミー・フラナガン オスカー・ピーターソン クレア・フィッシャー ドン・フリードマン デニー・ザイトリン ジョン・テイラー  Moodsville 9 The Tommy Flanagan Trio Tommy Flanagan (p) Tommy Potter (b) Roy Haynes (ds) ムーズヴィル 9 / トミー・フラナガン・トリオ トミー・フラナガン(ピアノ)/ トミー・ポッター(ベース)/ ロイ・ヘインズ(ドラムス)  Jazz Poet Tommy Flanagan ♥ Tommy Flanagan (p) George Mraz (b) Kenny Washington (ds) ジャズ・ポエト / トミー・フラナガン ♥ トミー・フラナガン(ピアノ)/ ジョージ・ムラーツ(ベース)/ ケニー・ワシントン(ドラムス)  Tommy Flanagan Plays the Music of Harold Arlen ♥ Tommy Flanagan (p) George Mraz (b) Connie Kay (ds) Helen Merrill (vo) トミー・フラナガン・プレイズ・ザ・ミュージック・オブ・ハロルド・アーレン ♥ トミー・フラナガン(ピアノ)/ ジョージ・ムラーツ(ベース) コニー・ケイ(ドラムス)/ ヘレン・メリル(歌)  Lady Be Good … For Ella Tommy Flanagan ♥♥ Tommy Flanagan (p Peter Washington (b) Lewis Nash (ds) レイディ・ ビー・グッド / トミー・フラナガン ♥♥ トミー・フラナガン(ピアノ)/ ピーター・ワシントン(ベース)/ ルイス・ナッシュ(ドラムス) ジャズを愛好する人にとってビル・エヴァンスはいくらきれいでも悪いことを言えない人のようですが、その後の世代となると時々軽くあしらう声もあるようです。単に世代だけの問題でもないのでしょうが、クラシックならモノラル時代からのバックハウス、ギーゼキング、ハスキルあたりは良くてもその後は認めないという姿勢に近いかもしれません。しかしトミー・フラナガンなら文句はないでしょう。というか、リバイバル人気なのか最近熱いファンの方もいらっしゃるようです。生まれはエヴァンスとほぼ同じ1930年。2001年には亡くなっています。アフリカン・アメリカンのピアニストで、ジャンルは WIKI では「ビバップ、ハードバップ、メインストリーム・ジャズ」となっています。 まるでショパンみたいですが「ピアノの詩人」とも呼ばれ、変幻自在の名伴奏者であり、ジャズの錚々たるプレイヤーたちと共演して名盤を生み出して来ました。ジャズの王道を行く人ということで間違いないでしょう。 「オーヴァーシーズ」が代表作にして常に高評価なアルバムながら、ちょっとバップ(バッピーと言うとブラック・ヤッピーの意だそうです)かもしれません。 ジャズの本道の人はともかく、トミー・フラナガンはこれだよ、と言われたからこれを買って、その後フラナガンそのものを聞かなくなっている人も陰に隠れて存在しているのではないかと思います。もったいない話。それでクラシック愛好家に聞きやすくてあまりジャズジャズしていないものをとなるとソロかもしれませんが、ソロはこの人の初のソロ・アルバムが日本の企画で DENON から出ました。ハービー・ハンコックと同じ構図で、「アローン・トゥー・ロング Alone Too Long(1977)」です。これ、語り口がエヴァンスとは違ってブラックの文化を感じる人もあるいはいらっしゃるでしょうか。しかし後の時代のプレイヤーのような気難しい音は使いませんし、リズムに乗った即興もホーンで来られるような威圧感はなく、楽しさが溢れていると言っていいでしょう。スローな部分では「詩人」の美しさも感じられます。ただ、表題曲はそうでも必ずしもリリカルな面が全編に溢れている種類ではないかもしれません。ブラックの文化などと言いましたが、この人が叙情的に語るときの美しさときたら、バド・パウエルの叙情性などとは系統が違い、ホワイトのエヴァンスすら凌駕するかという静けさがあり、微かなもの悲しさをため息の出るようなデリケートな音でやわらかく転がすように聞かせます。そういうのは案外セッションでの録音かもしれません: 「ジャズ・ポエト」の中の「ラメント」、「グラッド・トゥ・ ビー・ハッピー」とか、アルバム「プレイズ・ザ・ミュージック・オブ・ハロルド・アーレン(オーバー・ ザ・レインボーの作曲者)」の最後、「ラスト・ナイト・ホエン・ウィー・ワー・ヤング」での一曲だけのヘレン・メリルの伴奏部分のプレイなんか素晴らしいです。「レイディ・ビー・グッド」中の「エンジェル・アイズ」、「アローン・トゥー・ロング」、「イズント・イット・ア・ピティ」もいいです。リズムに生きた呼吸があって自在に動くところが、どうかすると均等に推移しがちな白人系の拍の取り方とは違うかもしれません。しかしもはや白とか黒とか言ってる場合じゃありません。洗練とはこういうことでしょう。 アルバムとしては今挙げた三つ、「プレイズ・ザ・ミュー ジック・オブ・ハロルド・アーレン(1978)」と「ジャズ・ポエト(1989)」、「レイディ・ビー・グッド(1993)」はどれも録音が良いですし、全部が全部メロウな曲ではないですがフラナガンのアルバムの中では続けて聞いてリラックスできる種類でしょう。ジャズ・ポエトは掲載の新しいジャケットの方がリマスター版のようで、音が若干くっきりしている印象です。いい曲が揃ってます。レイディ・ビー・グッドはフラナガンが長く伴奏をしてきたエラ・フィッツジェラルドの曲を後年彼女に捧げたアルバムです。元が歌ものだけにメロディアスです。プレイズ・ザ・ミュージック・オブ・ハロルド・アーレンではジョージ・ムラーツのベースが小気味良く聞かせます。この歌うムラーツ、お好きであれば「コンファメーション(1977/78)」もお薦めです。「イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド」なんていかがでしょう。他にも沁みるスローが何曲かあります。ドラムを叩くのはコルトレーンと活躍したエルヴィン・ジョーンズです。 少し古い音でも良いなら「ムーズヴィル9(1960)」が 「オーヴァーシーズ」と並んで高く評価される一枚です。「オーヴァーシーズ(1957)」とは 近い時期ですので、これこそがあの時代の本物なのだ思うことも可能です。ムーズヴィルというタイトル、日本語のいわゆるムード、雰囲気の意味で mood を使い、ville は接尾語で「〜というもの」だそうです。したがって「ムードのあるもの」という意味です。これはこのレーベル(プレスティッジ)が各ミュージシャンごとにバラードを中心とした曲を集めて作ったアルバムのシリーズなのです。9は企画の9番目、他にもレッド・ガーランドをはじめコールマン・ホーキンスなどたくさん出てますから、なんだこのシリーズを集めればきれいジャズはこと足りるんじゃないか、という考えもあるでしょう。どうなんでしょうか。そしてトミー・フラナガンの「ムーズヴィル」、静謐さでは後年のプレイの方がやや勝るかもしれないながら最初から最後までほぼスタンダードのバラードで、一曲目は軽快、最後から二番目のみオリジナルとなっています。トミーのこの手のもののベストかどうかはともかく、センチメンタルに傾かず、寛げます。  Walking the Line Oscar Peterson Trio ♥♥ Oscar Peterson (p) George Mraz (b) Ray Price (ds) ウォーキング・ザ・ライン / オスカー・ピーターソン・トリオ ♥♥ オスカー・ ピーターソン(ピアノ)/ ジョージ・ムラーツ(ベース)/ レイ・プライス(ドラムス) トミー・フラナガンを出してきた勢いで、と言ってはなんですが、やっぱりオスカー・ピーターソンにも触れるべきでしょう。ビル・エヴァンスのような音楽という意味からすると「キーボードのマハラジャ」という異名をとるこの人、元来はノリノリの音楽だと思われてるので意外かもしれません。1925年生まれで2007年に亡くなったカナダのピアニストです。ビル・エヴァンスより四つ上ですが、エヴァンス派でもパウエル派でもありません。ピーターソンはピーターソンで、流儀として言われるのは「スイングの要素を持ったまま超絶技巧でモダナイズした」というもの。スイングって何でしょう。曖昧な言葉なのは意味が多岐にわたるからでもありますが、ここで言うのはリズムの種類ではなくて、ジャズの古い演奏様式のことです。聞いてて感じるのは、時々昔のディキシーランドだとかブギウギ、スイングなんかのピアノの叩き方に似た調子良いのが混じるところです。一方で超絶技巧の方はすぐ知れる話で、スピード感溢れる絢爛豪華な装飾に目が覚まされます。グリッサンドでないときも隣り合った音を時々折り返しながら、ティリリリリリと連続して上下させる音速の運びはすぐ彼だと分かるものです。 そしてこの O.P. ことオスカー・ピーターソン、またまたもってジャズ愛好家の方から軽く見られてきた経緯があるようなのです。クラシックでは豪快な技巧派こそが尊敬され、指がもつれたりきれいな抑揚が売りだと思われたりすると色々言われますが、超絶技巧なのに O.P. が軽く見られるのはどうしてでしょう。マイルスと違って仕掛け面で出遅れたからでしょうか。録音が多いから、というならネヴィル・マリナーと同じながら、「語り口がいつも同じ」というのは表面の理由な気がします。だって他のプレイヤーたちも似たようなものだからです。人気のトミー・フラナガンと何が違うんだろう。答えは恐らく、あの「幸せな音」のせいなんじゃないかと思います。フラナガンのような「脇役の名人」なら名を挙げるだけで知ってる感じになるんで昔から重宝されて来ましたが、超絶技巧だったら強面でないとだめなのでしょう。幸せは自我の栄養にならないのに、ピーターソンにはマイルスのような影がないのです。ジャズは元々日陰者の反乱であり、ブルーノート自体がすでに貧困と抑圧のブルーだったわけです。でもニューオーリンズのお葬式みたいにそれを跳ね返すオーラこそがこの人の素晴らしいところで、聞く者を幸せにしてくれます。O.P. を愛する人は風評なんて気にしないでしょう。 取り出しましたるは「ウォーキング・ザ・ライン」というアルバム。ピーターソンのベストは絶対これであり、その中の「ザ・ウィンドミルズ・イン・ユア・マインド」というナンバーだと勝手に信じてます。小気味良いドラムの音だけで始まってベースがそっと加わり、そこにピアノが乗ってきた後は元歌が何だか分からない猛スピードで駆け抜けるスリリングな曲です。憂いを含むクールなマイナー・キーで徹頭徹尾涼しい顔。力んでやかましくなるところは一切ありません。この乗りに乗る感じを何か動くものに喩えたいですが、真夜中のニュルブルクリンク・ハイスピード・コーナリングというところでしょうか。胸のすく思いです。そして中程から速度を保ったままささやくような調子にトーンを落としてフェード・アウトして行きます。これ以上格好いい曲って世の中にないよ うな気がします。 アップテンポの曲を取り上げてしまって申し訳ないですが、このアルバムには「ワンス・アポン・ア・サマータイム」、「アイ・ディドゥント・ノウ・ホワット・タイム・イット・ワズ」という魅力的なスロー・ナンバーがあり、トータルでスキップしたくなる曲が一切ないという完成度です。アルバム・タイトルはどういう意味なんでしょう、walk the line は対立したものの中間を取る、極端なものの微妙なバランスを取るといった意味で、警察が飲酒運転の摘発でドライバーに白線の上を歩かせることも含まれると同時に「セルフ・コントロールの鍛錬」というニュアンスもあるのだそうです。1970年 MPS でのレコーディングです。メンバーもいいです。  We Get Requests The Oscar Peterson Trio ♥ Oscar Peterson (p) Ray Brown (b) Ed Thigpen (ds) ウィ・ゲット・リクエスツ / ザ・オスカー・ピーターソン・トリオ ♥ オスカー・ピーターソン(ピアノ)/ レイ・ブラウン(ベース)/ エド・シグペン(ドラムス)  Quiet Now: Time and Again Oscar Peterson ♥♥ Oscar Peterson (p) and others 「クワイエット・ナウ: タイム・アンド・アゲイン」/ オスカー・ピーターソン ♥♥ オスカー・ピーターソン(ピアノ)他 それではオスカー・ピーターソン、一般にはどんなアルバムがお薦めなのでしょう。ソロならばこの人の手の内が分かる、かもしれないですが、そのソロ・アルバム「マイ・フェイヴァリット・インストゥルメント」には「リトル・ガール・ブルー」があります。バラードで、静けさの中に憂いではなくて充足感と幸せが漂います。きらきら輝くスローでの装飾。オスカー・ピーターソンはこの波長です。楽しいときも、静かなときも。 別のページで触れていますが(「ポーギーとベス」)、「プレイズ・ジョージ・ガーシュウィン・ソングブック」もいいです。ガーシュウィンのナンバーを集めたもので、彼のレコーディングの幕開けはこうした曲からでした。「ソングブック」と付く方は本来1959年にヴァーヴから出たもので、一般に手に入るものでは二度目になります。その前のは1952年クレフ・ レコーズからのもので「プレイズ・ジョージ・ガーシュウィン」。どちらもタクシーの中で流れたローカルラジオに魅了されて彼のマネジャーになった大物、ノーマン・グランツのプロデュースでした。CD ではこの二枚が一緒になっています。演奏スタイルと音が揃わないので自分としては後年の方の一枚(前半)だけあればいいのですが、LP 分だけだと短いからサービスしてくれてるのでしょう。だぶった曲を違う演奏で聞けるというのも悪くはないかもしれません。超絶技巧がどうとかではなく、歌心溢れる静かでお洒落な一枚です。 1959年の同じ企画は他にもあり、トミー・フラナガンのところでも取り上げたオーバー・ザ・レインボウの作者ハロルド・アーレンの曲のアルバム、「プレイズ・ザ・ ハロルド・アーレン・ソングブック」もリラックスして聞けるきれいなナンバーがそろっています。オーバー・ザ・レインボウはトミー・フラナガンよりゆったり歌います。他にもコール・ポーター、デューク・エリントン、ジミー・マクヒュー(オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート/アイ・キャント・ ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ)、リチャード・ロジャース(マイ・ファニー・ヴァレンタイン)、ジェローム・カーン(スモーク・ゲッツ・イン・ユア・アイズ/イエスタデイズ)、ハリー・ウォーレン&ヴィンセント・ユーマンス、アーヴィング・バーリンなどのアリバムがあり、全部の中から好きなナンバーを集めて一枚にしたら、ジャズ評論家も喜ぶ極上のカクテル・アルバムが出来上がるかもしれません(その意図のものが聞きたいのであれば下記の「クワイエット・ナウ: タイム・アンド・アゲイン」が最初からまとまっています)。 そして落ち着いて聞けるピーターソンのベスト・アルバムとしてはやはり「ウィ・ゲット・リクエスツ」と、もう一つ「クワイエット・ナウ: タイム・アンド・アゲイン」を挙げます。 「ウィ・ゲット・リクセスツ」(写真上)はスロー・バラード 中心でボサノヴァもあり、彼のイケイケどんどんでない部分を代表するジム・デイヴィス(最後の曲 "Goodbye, J.D." の 「J・D」)・プロデュースの一枚です。誰もが推薦盤として真っ先に挙げます。この中の「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」は曲自体がいいですが、 バッハの「主よ人の望みの喜びよ」の旋律で締め括られる楽しい計らいで、クラシック・ファンも嬉しいんじゃないかと思います。「タイム・アンド・アゲイン (曲名)」はこれもお洒落なスロー・ナンバーです。 1964年、ヴァーヴでの最後の録音で、ライヴの雰囲気で お客さんからのリクエストに応えるような格好をとったスタジオ収録です。 「クワイエット・ナウ: タイム・アンド・アゲイン」(アルバム名/写真下)の方は2000年に出たコンピレーションもので、タイトル通り全て静かな曲が集められている夜のアルバムです。硬派なファンの方は静か過ぎてメリハリがないとか、カクテル・アルバムだとかいって相手にしないかもしれません。でもお洒落な BGM として流しておきたいとき、リラックスして美しいメロディに浸りたいときは断然これが一番です。どこまでも繊細で荒っぽい音が出て来ないもので、それもこのピアニストの特質なのです。一般には超絶技巧が前面に出るピーターソンの、あまり注目されてない一面でしょう。アルバムには最初にソロのところで触れた 「リトル・ ガール・ブルー」も入ってます。やさしくてなんとセンスがいいことでしょう。曲をコンパイルしているのはカナダのピアニストにしてアレンジャーでもある女性、リニー・ロスネスです。 この「クワイエット・ナウ」は上記プレスティッジの「ムーズヴィル」同様にスロー・ナンバーばかりのものとして2000年前後にヴァーヴが出したシリーズで、他にもあります。「クワイエット・ナウ」というのは後述デニー・ザイトリンが作ってビル・エヴァンスが好んで弾いた曲の名前ですが、このシリーズの中にはエヴァンス版もあります(クワイエット・ナウだけだと別のアルバムとなり、後ろにネバー・レット・ミー・ゴーが付きます)。二台のピアノが賑やかに聞こえがちなのと録音面でここでは取り上げませんでしたが、トリオ以外でのソロ、オーヴァーダブしたもの、ジム・ホールとのデュオなどでのスロー寄りの曲が集まってます。他にも泣きのスタン・ゲッツ、ボサノバの生みの親アントニオ・カルロス・ジョビン、元気な曲も多いアフリカ系の有名なシンガー、エラとサラのバラード集など、色々とあります。「ヒアズ・トゥ・ライフ」の方が有名ながら、ピアノ弾き語りの魅惑の声、シャーリー・ホーンなどはいかがでしょうか。  Alone Together Clare Fischer ♥♥ Clare Fischer (p) アローン・トゥゲザー / クレア・フィッシャー ♥♥ クレア・フィッシャー(ピアノ) トミー・フラナガンより二つ年上の1928年生まれで2012年に亡くなったクレア・フィッシャーは、クレアといっても男性。アメリカのピアニストで、トミー、O.P. とは違ってエヴァンス派と言われます。つまりエヴァンスより一つ年上でもエヴァンスの影響を受けたとされるわけですが、果たして様々な経歴を持つこの才能豊かな人にそういう見方が正しいのでしょうか。あまり知られてないかもしれないけど、亜流どころか個性的でいいピアノだと思います。特にソロの「アローン・トゥゲザー」が多様な表現のソロで、歴史に残るものじゃないかと感じます。 出自はフランス、ドイツ、アイルランド系スコットランド人、およびイギリスの文化背景を持った両親ということですから、ビル・エヴァンスやキース・ジャレットとも重なります。クラシックの作曲経験があり、大物ジャズ・ミュージシャンと共演し、ラテンに通じ、ポップ系のアレンジャーとしても引っ張りだこだった人です。 あまり知らずに晩年のビル・エヴァンスのトリオ演奏、「ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング」あたりを聞いて想像すると、エヴァンス本人の前のめりなソロよりもこちらの方がエヴァンスのソロなのかな、と思うかもしれません。マイナー・キーの曲が多く、一部に短調でも楽しさを覚える瞬間もあるにせよ、トータルでは明るい音ではありません。晩年のエヴァンスにも近い深く沈潜した思いを感じる運びです。はっきりしたリズムと力強さがありながら、硬質な叙情性を示すナンバーもあります。その中には重めで均等なリズムがいかにもアフリカ系ではない印象を与える部分もありますが、コード選びはブルージーで、力強く押したりもします。かと思えば叙情的な後期ロマン派のピアニッシモか、はたまた印象派かという静かで内省的なフレーズも挟まります。それがまた大変きれいです。しかし、例えばもっと後のエンリコ・ピエラヌンツィやアラン・パスクァなどに時折表れるようなキャッチーなメロディ・ラインは聞かれず、その外しようはより現代の人のようであり、それでいて外すために外す不自然もなく、意外さがあって美しいのです。 手法としては小節単位を超えたテンポの緩急や強弱の付け方が、最初に取り上げたジャン=イヴ・ティボーデのようにクラシック的かもしれません。セブンスや複雑なテンション・コードは駆使しますが、前衛の汚い音は一切出しません。リズムは変幻自在だけど特に異種混合の実験というわけでもなさそうだし、どういうコード上でどんなスケールを展開するかの分析は専門家に任せるとして、感覚的にはビル・エヴァンスよりも面白いかもしれません。ちょっと似たところもあるハービー・ハンコックのソロ同様に心を捉えられました。 「イクセプト・フロム・カノニック・パッサカリア」ではだんだん盛り上がって来る内に秘めた情熱に圧倒されます。こういうラテン・パッションのような息の長いクレシェンドはこの人の特徴です。ネーミングも含めてクラシック音楽の伝統を知ってる気もするし、これ、本当にすごい曲だと思います。 ドイツの MPS レーベルで1975年の録音です。95年には同じくソロの「ジャスト・ミー」も出ましたが、音の切れ間がない印象の曲も含まれており、完成度ではこのアローン・トゥゲザーの方が上かなと感じました。 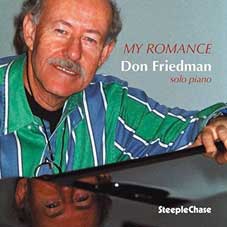 My Romance Don Friedman Don Friedman (p) マイ・ロマンス / ドン・フリードマン ドン・フリードマン(ピアノ) クレア・フィッシャーを挙げるならドン・フリードマンもでしょうか。1935年サン・フランシスコ生まれで日本では人気があり、やはりエヴァンス派に分類する人もいるようです。一緒に活動したことはなさそうだし、むしろ他のピアニストたちとの交流があって、出発点ではバド・パウエルの影響も受けているようだけど。音的に見てそっちだということなのでしょうか。無理やりパウエル派とエヴァンス派に分けるのはやめた方がいいのかもしれません。 「サークル・ワルツ」が有名なアルバムで、そこに入っているタイトル曲はメロディを展開させず、抑えたトーンで断片的なフレーズを繰り返しつつ、ベースが区切る一定のリズムに微かな叙情を絡ませるといった趣きです。バラードでは一瞬の哀愁や諦観を感じさせるコード展開はあるにせよ、甘さを控えた独特の底光りする美しさがあります。曲によってはやや抽象的な音遣いも見られ、そういう部分でも叫ばず、やはり抑制が感じられます。速いパッセージもクールに飛ばし、ちょっと大人で通好みな人です。 一方で他のアルバムではストレート・アヘッドな辛口のアップテンポもあり、ビル・エヴァンスよりも前衛的な音を使ってバップ風なのもやるので、本格ジャズ・ファンの評価も高いのだと思います。 ここでは「マイ・ロマンス」を取り上げます。1996年のソロ・アルバムです。独特の和音を連続させる展開で、やや回想的で物悲しい調子はあるものの感傷には陥りません。そしてきれいな歌をうたっていても、時々夢を覚ますような抽象的な音を混ぜます。シャイなのか途中から駆け足になったりもして、ちょっと苦みの効いた愛の歌といった趣きです。タイトルに引っ掛けて解釈するならば、色々経験した大人の現実認識をベースに語るのだけれども、どんな目に遭ってもロマンスへの感受性は捨てない人の回想録といったところでしょうか。ほろ苦くてきれいで、この味が好きな人には堪えられないでしょう。個人的にはもう少しためて落ち着いてほしいところもあります。  Denny Zeitlin Homecoming ♥♥ Denny Zeitlin (p) ホームカミング / デニー・ザイトリン ♥♥ デニー・ザイ トリン(ピアノ) 1938年生まれのデニー・ザイトリンはちょっと異色の人で、ボロディンみたいな二足のわらじというか、本業がカリフォルニア大学(UCSF)の精神医学の教授です。本人たちにすれば当たり前なのだろうけど、学者さんもこのレベルになると概念を整理して、相互関係を即座に理解する力を持ってる人もいることでしょう。それを音楽に振り向ければ様々な表現様式の構造を容易に見抜くこともできるに違いありません。オスカー・ピーターソンのところで語り口がいつも同じようになるのはどんなミュージシャンも変わらないと言いましたが、中にはどれがその人の本当の姿だか分からなくなるほど様々な顔を持つプレイヤーもいます。ザイトリンはそういう種類の才人でしょう。とにかく何にでも合わせられ、バップな即興に満ちたエネルギッシュなものからフュージョン風エレキもの、フリーの技法を駆使したものもあれば、知的かつ叙情的なバラードもやります。不思議な音にも好奇心があるのかウェイン・ショーターも取り上げます。ECM からはオーネット・コールマンの曲も入った硬派な側の ECM らしい音をチャーリー・ヘイデンと聞かせます。ビル・エヴァンスに曲を提供する作曲家でもあります。そうなるとどの顔が素顔なのかが気になるのです。 有名なアルバムは事実上のファースト・アルバムでピアノ・トリオの「カセクシス(1964)」です。タイトルは誰が付けたのか精神医学用語。出だしを聞いた瞬間はデイヴ・ブルーベック風だと思いましたが、その後の展開はあの近づきやすいクール・ジャズではなく、ドライブの効いた堂々たるものでした。意外なスケールとコードのスパイスを効かせたバラードは覚醒と叙情のバランスが良く、分かりやすいメロディーに堕しないように注意を払った独特の世界ながら、基本にはきれいな音を志向する感性があるように感じます。全体によく練れた作曲だと思うし、ジャズの本道で頑張った感はあります。調性感が薄まる前衛的な展開にも突っ込む一方で、不思議な音の魅力があるのです。デビュー間もなくでこの完成度を見せたのでは皆が驚いたのも頷けます。 複雑な暗い影が差す「ラウンド・ミッドナイト」、「リトル・チルドレン、ドント・ゴー・ニアー・ザット・ハウス」は魅力的です。どんな家なんでしょう、スヴェンソンじいさんの黄色い家かな。そして十五分越えのラストの「ブルー・フェニックス」が、全てを盛り込んだ最大の意欲作かもしれません。
でも理性とスピリチュアリティは別なわけで、知的試みではなく情緒的水準はどうなんでしょう。この才能豊かな音楽家はボロディンのように繊細でしょうか。もっとずっと後、2000年代に入ってからのアルバム「ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ(2001)」や「ウィッシング・オン・ザ・ ムーン(2009)」なんかを聞いていると、旋律線はよりシンプルで分かりやすい方向に洗練されて来ている気がします。それまでもチャーリー・ヘイデンとの「タイム・リメンバーズ・ワンタイム・ワンス(1981)」に入っていた「エレン・デイヴィッド」などで、息を呑むリリシズムを聞かせることはありました。様々な顔を持つデニー・ザイトリンの心のホームグラウンドはどこなのでしょう。 「ホームカミング(1986)」というジャストな名前のアルバムがあります。ソロです。ここでは前衛的な試みはなされていません。それもそのはず、ポール・ウィンターの環境音楽のレーベル、リビング・ミュージック・レコーズから出てウィンダムヒル系列で売られているのです。ソロだからというよりもそのことが大きいのかもしれません。しかしメロディーを禁欲しないで歌ってこそその人の情緒的な地が見えて来ます。案外この CD、この人の素顔ではないでしょうか。あるいは素顔などというもの自体が幻想かもしれないけど。 まず思ったのは、なんかデイヴ・グルーシン的な音だなということでした。西海岸に住んで洗練された叙情性を出そうと思い、メロディーを追うとこういう音になるのでしょうか。曲の構造は違うけどハーモニーの好みと空気感が似ています。からっと晴れたカリフォルニアのどこかの都会で、午後の光がテラスのテラコッタに反射して窓から差し込んでるみたいな。ちょっと元気がいいのは表題曲と「ブラジリアン・ストリート・ダンス」ぐらい で、他は繊細で美しいです。それともこれもウィンダムヒル路線としてやって見せてることでしょうか? ジャズの評論家は褒めないでしょう。でもセピア色の世界にきらきらした光が同居してるのは個性的です。時々複雑な音も使うけど気難しくならず、懐かしくはあっても感傷に至りません。精神科医って変わった人も多くて必ずしも精神的に大人だとは限らないけど、この人には幼児期のトラウマは感じられず、情緒的にはこなれている印象です。だから安心してこの音の万華鏡に身を任せられます。他の楽器とのセッションでは技巧的な側面も出していますが、このソロを聞くと決してアフリカン・ルーツではないと分かります。ゆったり延び縮みする平滑なリズムと静かで洗練された感覚はエヴァンスに通ずると言っていいでしょう。締め括りの「クワイエット・ナウ」は彼が作ってビル・エヴァンスが有名にしました。エヴァンスのアルバム・タイトルにすらなっており、そこだけではなく何度も取り上げられた持ち歌であり、もはやエヴァンスの曲だと思われてるんじゃないでしょうか。  Stairway to the Stars Denny Zeitlin Trio ♥♥ Denny Zeitlin (p) Buster Williams (b) Matt Wilson (ds) ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ / デニー・ザイトリン ・トリオ ♥♥ デニー・ザイトリン(ピアノ)/ バスター・ウィリアムス(ベース)/ マット・ウィルソン(ドラムス) ムード満点の前掲「ホームカミング」こそをザイトリンの素顔だと言い切るのは無理があるかもですが、トリオ演奏でもう少しジャズ的なものも挙げます。「ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ」です。ビル・エヴァンス・トリオの叙情的な運びが好きな人にもお薦めです。スローなスタンダードが中心ですが、サンタモニカと LA 中心部の間にあってほぼ LA とも言えるカルバーシティでの2001年のライヴです。暴れん坊な曲と言えばロリンズ発のビバップ定番リズム・チェンジ、「オレオ」の一曲のみで、これを入れることでジャズだぞ、と言ってるかのようです。ただ甘いだけでなく、メンバー三人のインタープレイが楽しめるアルバムでもあります。 全体としては「ホーム・カミング」で聞かれるリリカルな歌をもう少し洗練された形で堪能できます。エヴァンスのような影はないですが、複雑なコード進行を使い、同じように感傷から外れています。キース・ジャレット・トリオもいいけど、ザイトリンはテクニカルなパートでも熱い感じがしないので、キースともまた違った個性だと思います。精神的に安定しているのでしょうか、光を感じさせます。きらきらとしていながら静けさがあり、その美しさは何にも代え難いです。後でご紹介するティエリー・ラングやマルチン・ボシレフスキと並んで、ビル・エヴァンス以外で歌の波長が最も気に入ったトリオ演奏です。特に表題曲の「ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ」とスタンダードのバラード「アイ・クッドハヴ・トールド・ユー」はため息が出ます。could have は後悔の場面で使われる表現だけど、ここではもはや懐かしい残り香に過ぎません。 これよりもっと即興のスリルを感じさせ、ほどほどに聞きやすいものをお求めならデビュー作にして代表作の「カセクシス」、その次でもう少しメロディアス路線に行った「カーニバル(1964)」、日本のジャズ・レーベル「ビーナス・レコーズ」から出たジャケットが武家屋敷前の雪景色になっている「音楽がある限り As Long As There's Music(1997)」あたりでしょうか。尖ってない最近作もいいかもしれません。 さて、これ以外のピアニストで同世代となると、1942年生まれで2015年に亡くなったイギリスのジョ ン・テイラーがいました。ちょっとまた毛色の違う人で、必ずしも聞きやすくはないかもしれませんが、ソロの「ソングス・アンド・バリエーションズ(2005)」は独特の美を感じさせるアルバムです。冷んやりとした空気感を漂わせる曲が多く、時々立ち止まりながら歩くように聞こえます。数音弾いては間を空けるリズムが独特なのです。ECM らしいクールなサウンドですが、甘さがなく覚醒しており、寡黙で超然とした孤独を感じさせます。濁った音が静かに出るときは夜空の月に薄く靄が掛かるようですが、それがいかにもイギリスっぽいと思ったり、北欧を感じさせたりします。それで環境音楽かと思っているとそのグレイッシュな音をきつく出してきます。こうした不思議な調性感は奥さんでヴォーカルのノーマ・ウィンストン(ワードレス)とトランペットのケニー・ホイーラーとのトリオでも維持されているようです。知性の人だと思います。  エヴァンスの後の世代 エヴァンスの後の世代ではどうでしょう。もっぱらピアノの話をして来ているのですが、金管以外でソロを張れる旋律楽器と言えばマイナーなヴァイオリンやフルート、クラリネットなどを除けばピアノかギターということになり、数の上では圧倒的にピアノだからです。そしてビル・エヴァンスのすぐ後の世代を代表するピアニストといえば、有名なのは三人です: キース・ジャレット チック・コリア ハービー・ハンコック お互いにライバルであったり、一緒に演奏し合ったりしていますが、共通するのはエヴァンス同様、三人ともマイルス・デイヴィス(1926-1991)のバンドにいた、ということでしょうか。  帝王マイルス それでまたちょっと話が逸れますが、このマイルスという人、やっぱりジャズの帝王と言われただけあって影響力の大きい存在でした。クールにしてもハード・バップにしてもモード・ジャズにしても、いつも様々なムーブメントの先頭に立って来ており、マイルスのこのアルバムをもって新しい時代の幕が上がった、などと言われるのです。それは恐らく、彼自身がそういうシーン・チェンジの場面に意図的に居合わせようとしていたということだと思います。ジュリアードに入れるほど裕福で頭が良く、マネジメントの能力があり、何か他人とは違うもので勝負したい、と常に思っていたようです。音楽の理解力は並外れています。ビバップ(モダン・ジャズ)が始まった当初は駆け出しでしたが、鋭い嗅覚で変化を敏感に嗅ぎとり、技術は必ずしも一番ではなくても一番乗りを目指しました。おれ様のいいとこ取りじゃないか、という話ですが(マイルスのインタビューでは一人称は「おれ」と訳されています)、一番だとか、他者との違いを出して形ある成果を求めようだとかは、良くも悪くも自我の力です。コンサートで目撃しましたが、マイルスはアドリブの場面になると、そこを受け持つバンドの一人と一対一で向かい合って「おれとさしで勝負しろ」と迫る有名な仕草をしました。迫られた方はプレッシャーだったという話もあったのだけれど、でもあれも「おれ」一流の愛の表現だったのかもしれません。自分らしい音楽を追求したくて彼のバンドから抜けたがってたプレイヤーもいた一方で、型破りも認めてくれた。いつ首になるかヒヤヒヤしてた人もいます。それもこれも広い意味では人を育てていたことであって、たくさんの有名プレイヤーがマイルスの元から世に出ました。 マイルスってキレイ? マイルスの CD についてはここでは取り上げません。トランペットだし、ハーモニアスなものばかりでもないからです。火花を散らすアドリブ合戦や技法の歴史的意義をすっ飛ばしたのではマイルスの芸術に正しく接する方法とは呼べないでしょう。ただ、聞こえて来る情緒的側面が気になる人だってもちろんいるとは思います。ある人 にとってのマイルスの音楽は、痛みを隠しつつ斜に構えて開き直ってるけれども時々叫びをあげる心のように聞こえるかもしれません。魂の叫びだという人もいるでしょう。それがしんどい場合があると同時に共感も呼び、そのクールでちょっと孤独な音に酔いしれるのは案外難しくありません。だから枯葉(1958)やラウンド・ミッドナイト(1956)、ブルー・イン・グリーン(ビル・エヴァンスの曲/1959)はいいし、アルミのカップをポコっと嵌めたトランペットでチーンと静かなエレジーを吹くスローなマイルスだけが好きという人もいるはずです。十八番のマイ・ファニー・ヴァレンタインだって、傑作とされる後の方(1964 CBS)の刺さる音はいいに決まってるけれど、最初の方(1956)が好きだという声も聞きます。そういう人はプレスティッジのマラソン・セッション*四枚からバラードだけを抜いて一枚に焼いただけで満足してしまうかもしれず、その友人にはシーツ**なしでコルトレーンの「バラード」(1961/62 Impulse)と添い寝したいと思ってる人がいるかもしれないのです。二人の間の会話は、マイルスってすごくキレイ、です。 *「クッキン」、「ワーキン」、「リラクシン」、「スティーミン」の四枚。コロンビアに移籍した後、前のレーベルだったプレスティッジと約束していた録音がなされずに残っていたので、続けてあっという間に録音し終えたというもの。マイルス・デイヴィスの代表作。 **シーツ・オブ・サウンド:高速で音を連ねて吹くジョン・コルトレーンの奏法の呼び名。コードを無視して連ねるので抽象的な音遣いとなる。「バラード」はそういう難解さがなく、初心者に薦められることが多いアルバム。   Creation Keith Jarrett ♥ Keith Jarrett (p) クリエイション / キース・ジャレット ♥ キース・ジャレット(ピアノ) エヴァンスの後の世代三人も、みなマイルスのバンドから出たという話をしていたのでした。ではその三人のピアニストのうち、バップが苦手でクラシック音楽が好きな人たちに受けそうなのは誰でしょう。恐らくキース・ジャレットじゃないでしょうか。クラシックのピアニストとしての録音もあるから、というわけではありません。でもそれは事実で、バッハの平均率やフランス組曲など、ジャズ風ではなくてあくまでもクラシカル・ミュージックとしてたくさんリリースしています。その評価の方は、是非聞いてみてください。あくまでも一般論として言うならば、ジャズ・ピアニストがクラシックをやるといったってハンデをもらえるわけではありません。即興で次の音を選ぶ能力は使えないし、初めはクラシックのピアノを練習したにせよ、決められた譜の中でテンポと強弱を選んで行く術を学び直さなければならないでしょう。異なった分野で両方突出するのは難しいことだと思います。でもキース・ジャレットはクラシック音楽への傾斜がかなり大きいようで、デビューちょっと後にはオルガンによる即興もやっていました。ジャズの即興というよりはクラシックのオルガニストがやるモダンな即興のようでしたが、その出だしで提示されるテーマはまるでバッハのコラールです。二枚組の LP だったディスク1の A 面は懐かしくも美しく、そこばかり何度も聞いていたのを思い出します(Hymns/Spheres1976)。 キース・ジャレットはWW2終戦の年生まれ。アメリカ人ですが、父はフランスもしくはスコッツ=アイリッシュの子孫、母はハンガリー系という人です。そして三人のうちでなぜクラシック音楽的だと申し上げたかというと、第一にメロディアスでロマンティックなハーモニーを感じさせるからなのです。甘くてちょっと悲しい叙情性が基本にあるメンタリティです。自己陶酔的とも言えるでしょうが、それがまたきれいなので、好きな人にはたまらないところだと思うのです。ビル・エヴァンスを除いてリリック(叙情的)という言葉がこれほど似合うジャズ・ピアニストもいないでしょう。アドリブ部分でのリズムの取り方も、伴奏の和音をずっと一定間隔で歩くように鳴らし続ける場面が見られ、ジャズの語法というよりもクラシック音楽の運びのようです。その点ハービー・ハンコックはもっと弾むリズムの伸び縮みが挟まっていて、数少ないソロの即興でもよりジャズ的に聞こえます。チック・コリアとなるとまたちょっと違うけど、その独特の言い回しがやはりクラシック的とも言えない気がします。 60年代から活躍していましたが、マイルスのバンドに入ったのが70年、その後 ECM に見出されてピアノ・ソロのアルバムを出し始め、一般に評価されるようになりました。注目を浴びた事実上最初のものは「ソロ・コンサート(1973)」と言えるでしょうか。すぐ後の「ケルン・コンサート(1975)」は大変売れ、ソロ・ピアノによる即興演奏という独自のスタイルはその後も日本公演での「ダーク・インターヴァル(1987)」、バッハのように始まる「パリ・コンサート(1988)」など、どれも話題になりました。しかしいくらマイルスのバンドにいたとはいえ、売れ方がそんなだったからか演奏マナーからなのか、クラシック好きの人たちとは反対に、本格のジャズ関係者たちからの評価は最初あまり高いものではなかったようです。「スタンダーズ(1983)」の二枚のアルバムが出て以降に見直されたんじゃないの、という意見をジャズ・プレイヤーの方からは聞きました。因みにそのスタンダーズ、Vol.1 の方がより本格の人に気に入られ、Vol.2 はメロディ・ラインのきれいなものを好む人に喜ばれるようです。「ネバー・レット・ミー・ゴー」が静かで美しいからでしょう。最初の曲と三曲目も、また特に最後の「アイ・フォール・イン・ラヴ・イージリー」も同じ周波数であり、したがってこのページで挙げるなら2の方をお薦めすることになります。 このいわゆるスタンダーズ・トリオ(キース・ジャレット/ ゲーリー・ピーコック/ジャック・ディジョネット)のアルバムは「スタンダーズ・ライヴ (1986パリ)」、「イン・ノルウェイ」など他にも出ていて、「ライヴ」は人気があります。この中の「ステラ・バイ・スターライト(日本盤ではこれをアルバム・タイトルにして「星影のステラ」となっています)」で弾きながらキースが出している声を聞くと、彼がどんな感覚で弾いているのかが分かる気がします。 ここで写真を掲げた最新の「クリエイション」は2014年に行われた各地(東京/トロント/パリ/ローマ)のコンサート演奏を選りすぐったものであり、「ソロ・コンサート」に始まった彼独自のスタイルの到達点だと思います。前述スタンダーズ・トリオなどの活動を除いてキース・ジャレット芸術の集大成と言ってもいいかもしれません。曲はゆったりしたものが多く、「ソロ・コンサート」以来どのソロの即興でも聞かれた、同じフレーズを繰り返して冗漫になるところがありません。ビル・エヴァンスとは違ってモダンへの意欲も見せ、若干グレイッシュな和音も繰り出しますが、それも感覚的に受け止められる範囲内であり、「酸いも甘いも噛み分ける」という表現で言う「酸い」の部分なのでしょう。能力を見せるための前衛ではなく、センチメンタルさもいつもよりは少ない気がします。 それでも彼一流の耽溺の美というか、波長を合わせると麻薬的な魅力があります。マーラーなどのロマン派の音楽みたいです。そういう意味でバックグラウンド・ミュージックにはどうかと思いますが、クラシックのハーモニーが好きでジャズのイディオムに慣れていない人でも美しさは感じられるでしょう。病に倒れた直後に録音したという、次にご紹介する「メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー」の方がより濁った音が出なくて聞きやすいでしょうが、まずこちらを重要作品として取り上げます。ただ、病気から回復してからはまたちょっと鎧を身に付け始めたところもあるようです。同じ時期の大阪公演では聴衆のマナーに怒って中止したとも聞きました。緊張の中で湧いて来る音を待つタイプの音楽家なので、ノイズがストレスになるようです。グールドと同じようなうなり声を上げて弾く人で、感極まると「あー」と気持ちの良さそうな音が漏れるのですが、聴衆が同じ音を出すのは許してくれないのかもしれません。 全体としては、聞いた感覚を具体的にはどう表現したらいいのでしょう、まず(ジャケット写真同様の)暗い群青の海に置き去りにされたような低音が響きます。承認を求めるインナーチャイルドなのか、涙に曇る目を通して世界を見、光を求めるところがこの人の芸術のような気がして来ます。「救済」のテーマと言うのでしょうか。ベートーヴェンの「闇から光へ」のようなドラマ性があるのです。ただ、苦しさがベースにあるのは同じでも、光の部分にはうっすら追憶と憧れのベールがかかっています。きれいです。聞く者によってはそれが慰めであり、そこにこそ麻薬的な求心力が生まれるのだと思います。六曲目の東京でのトラックなど、まさに苦を越えて純化された美に満ちており、力強い感動が込み上げて来ます。以前よりも情感が深まっていますから、既出のソロ・コンサートしか聞いていない人にもお薦めします。時が磨いて少しだけ枯れたキース・ジャレット、いいです。
 Melody at Night, with You Keith Jarrett ♥ Keith Jarrett (p) メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー / キース・ジャレット ♥ キース・ジャレット(ピアノ) キース・ジャレットは1996年に壊れてしまいました。原因不明とされているので心因性とは言えないながら、ストレスが関係しているともされる慢性疲労症候群(CFS)という病に取り憑かれ、激しい疲れに襲われて喋る気も失せる状態だったようです。ピアノが弾けるまで回復したとき、闘病生活を支えてくれた奥さんに贈りたいということで自宅で録音をとりためたのがこのアルバムです。最初は一般に出すつもりはなかったようです。ジャケットの写真は花の差してある窓辺の花瓶と窓とがアウトフォーカスになってるモノクロ写真ですが、静養中に部屋の中から外の方を眺めているキースの目線なのかもしれません。 人間壊れてるときはぎらぎらした意欲がなくなり、構えを降ろして武装解除状態になってしまいます。自我が働かず、その人の素が出て来やすいのです。アルバム中の曲に引っ掛けて Blame It On My Ego([私を責めないで] 私の自我を責めて)とでも言いますか。自我は人間に必要なものだけど、それに乗っ取られると病理を生みます。そして病気になるとたとえ意地悪な人でもスクルージさんのようにやさしくなってしまい、また元気が出て来ると意地悪な人に戻ります。稀にそのときのことを教訓にしてやさしいままの人もいますが。 ここではキース・ジャレットの素の歌が聞けます。素だけにやさしいです。癒されます。聞きやすいと言われないためにがんばった不協和音なんて一つも出て来やしません。それは武装ですから。病気になって現代音楽を聞こうという人もまずいないでしょう。かくて分かりやすい旋律線だけが残りました。まるで赤ちゃんをあやすオルゴールのように、そっとやさしい子守歌です。 でもちょっと過去を懐かしむ波長が混じるのはどうしてでしょう。壊れ切って大きな穴が開き、そこから天国の光が差しているのではありません。失われたものを愛で、少しだけ寂しさを響かせつつ諦め、許しています。素の状態でこうなのですから、キースはそういう人なのでしょうか。これは疲れた心を慰めている音楽です。自分のパートナーにこんな風に言ってるようなものかもしれません: 「今日はいい天気で空気が澄んでるよ、庭でリラックスしたら。ぼくが後で温かい飲み物を持って行ってあげる。明日はきれいなところに連れてってあげるね。 見渡す限りの平原で、遠くに雪を被った山が見えるんだ。でもそこまでは丘が襞になっててね、実は小さな町や村が隠れているんだよ。見えないんだけどね、笑いさざめいている人々の暮らしがあるんだ。そういうもの全部がきらきら輝いてる気がするよ」
どのソロを聞いても感じるあの甘い傷心の原点がここにあります。武装解除されたやわらかい心の襞、デリケートなキースの世界に浸ってください。根本にあるメロディのセンスはジョージ・ウィンストンの「あこがれ/愛」にも近い、などと形容したら褒めたことになるでしょうか。タイトル通り、おやすみ前の夜の音楽です。なんか疲れちゃった人、これを聴くと温かい涙とともに力が湧いて来るかもしれません。 1998年録音です。自宅でとったといったってキースの自宅ですし、現代のことですから良い音です。このページでご紹介する CD は硬派はジャズ・ファンからしたらどれも病院食みたいなものかもしれませんが、それでもこれを♡一つにしたのは個人的なもので、真実を見る強さよりも慰めに寄ってるからということと、完成度は「クリエイション」の方かなと感じたからです。しかし「クリエイション」よりはこちらの方が間違いなく音階的にずっと聞きやすいですから、クラシックからジャズの世界に今から入ってみたいという方にはこっちを先にお薦めします。  My Song Keith Jarrett ♥♥ Keith Jarrett (p) Jan Garbarek (ts, ss) Palle Danielsson (b) Jon Christensen (ds) マイ・ソング / キース・ジャレット ♥♥ キース・ジャレット(ピアノ)/ ヤン・ガルバレク(テナー/ソプラノ・サックス) パレ・ダニエルソン(ベース)/ ヨン・クリステンセン(ドラムス) もっと初期のキースで、しかもピアノ・ソロではなくてよりジャズらしいカルテットによる演奏です。キースのピアノにサックス、ベース、ドラムスという構成です。でもここで敢えてホーンものを取り上げたのは生きいきとした幸せな波長がとてもいいからです。このアルバム、あまりにきれい過ぎてジャズ・ファンの人たちは褒めません。でも構いません。どこか芯に覚めたところのあるビル・エヴァンスに対してキース・ジャレットは逆で、抽象的なパートが終わって音階的なものが出て来るといつもつくづくロマンチストだなと思って来ましたし、基本的には重たい暗さも支配しています。しかしここでのキースは全く違います。ソロ・ ピアノのときのように憧れているんじゃなくて、過去も回想せず、今この瞬間の喜びに沸き立ち、踊っているのです。どうしたことでしょう。いいことがあったのか。でもこの77年頃に録音されたアルバムが皆その波長というわけではないので、ここでのメンバーといると居心地が良かったのかもしれません。一般にソロではその人の性質がダイレクトに表れるのに対し、セッションは共演相手の影響を受けるものです。ニューロン発火のタイミングが相互に同調するという話もあります。キース・ジャレットは特に、他者とのインタープレイにおける感受性が高いのかもしれません。 メロディ・ラインを受け持っているヤン・ガルバレクに負う部分も大きいでしょう。ソプラノ・サックスという楽器は元々きれいだけど、ヤンのは個性的な音色であり、透明というか、独特の細身な艶があります。倍音成分に含まれる高い周波数の音は人をリラックスさせる効果もあります。この強面でいつも笑わずに写真に収まるサキソフォン奏者、音楽活動のスタート時点では後輩だったものの、心理的にはキースの方が頼ってるのかもしれません。分かりませんが、ここではいつもむずがっている子供がすっかり安心してるみたいなところがあります。 幸せな波長と言いましたが、特に四曲目の「カントリー」、これを聞いていると喜びが湧き上がって来ます。悲しいときには明るい曲を聞く気にはなれず、悲しみは悲しみが癒す親和性というものがあるとされますが、前述の「メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー」が壊れたキースが自分を修復してる音楽としてそういう同質性を持っているとしたら、こちらはそれとは反対に肯定的な波長で明るく励ましてくれます。二曲目と続けて聞いたら天にも昇れます。 タイトル曲であるその二曲目の「マイ・ソング」も大変美しいメジャー・キーのバラードで、同じ波長の初々しさがあります。 五曲目の「マンダラ」一曲だけはフリー・ジャズの即興の要素が強く、不協和音で押して来ますが、こういう意欲的な曲が入ってるからアルバムの価値が上がるという意見もあるようです。フリーが分かると玄人かどうかはともかく、裸の王様せずに一回だけごめんなさい送りしてもいいと思います。 メンバーはテナーとソプラノのサックスがヤン・ガルバレク、ECM の看板の一人でキースより二つ年下の、ポーランドの血も引くノルウェー人です。このアルバムは彼がリーダーかとよく思われるようです。ベースのパレ・ダニエルソンはスウェーデン人、ドラムスのヨン・クリステンセンもヤンと同じくノルウェーの人で、彼らはキース・ジャレットの「ヨーロピアン・カルテット」として知られています。他に「アメリカン・カルテット」と呼ばれるメンバーもいて、ほぼ同時期に「残氓(The Survivor's Suite1976)」というアルバムを出していて魅力的な演奏ですが、ヨーロピアン・カルテットとは毛色が違い、アドリブに寄ったよりメイン・ストリー ムのジャズかなという印象です。 ECM1978年。キース・ジャレットのやさしさを感じさせる至福の一枚です。キースのアルバムで一番好きです。  In Concert, Zürich, October 28, 1979 Chick Corea and Gary Burton ♥♥ Chick Corea (p) Gary Burton (vib) イン・コンサート・チューリヒ 1979年10月28日 / チック・コリア&ゲーリー・バートン ♥♥ チック・コリア(ピアノ)/ ゲーリー・バートン(ビブラフォン) キース・ジャレットとよく比較され、ライバル同士と目されているピアノがチック・コリア(1941-2021)です。41年生まれということでキースより四つ上です。前述の通り二人ともマイルスのバンドにいましたが、チックが先でキースが後、わずかに重なる期間があります。技法の比較は手に余るのでこの人の印象だけを述べる と、キース・ジャレットのように覆いを取ると甘いロマンティシズムを感じさせるという性質ではありません。独特の語法があって、即興での音の選び方がちょっと宇宙の彼方というか、連続した音符を上下させるのではなく、度数(音程)の離れた音を往復してめまぐるしく飛び散るような音遣いです。ジャズで馴染んだリック(決めた言い回し)を積み重ねてるのとは全く様子が違っていて、なんか口の中で弾ける懐かしいキャンディ、「ポップロック」みたいです。そうやって無重力空間をパチパチと等速直線運動して行く。天才ジャズ・ピアニストという形容が誰よりも似合うこの人らしいところです。昔タモリがチック・コリア風に簡単に弾けるピアノというのを紹介してたけど、上手にその特徴を捉えていた気がします。ジャズをやってた人たちは皆「チック・コリアか?」とふざけて、目と首をグルグル回してアブストラクトな印象を強調してたりしたものです。そういう語法をフリーという言葉で括っていいかどうかは分からないけど、彼が面白がって世に出すミュージシャンには技巧的でバリバリ弾くけど間の感覚が欠落してたり、情緒要素が希薄な人がいたりして、彼自身が叙情的には生きてなさそうに思えて来ます。 でも一方でメロディアスになるときにはこれが大変きれいなのです。この総合ジャズ芸術のピアニストは自身の活動をエレクトリック・バンドとアコースティック・バンドとに名前分けしたり、フュージョンの先駆けとして「リターン・トゥ・フォーエヴァー」を大ヒットさせたりもしてましたが、リリカルなのは案外電化系のアルバム の方かなという気もします。なかでもラテン、特にスパニッシュの風味が加わるときはそうで、彼の血にイタリアとスペインが入ってるからでしょうか。一方でアコースティックの活動ではよりジャズ的かつアバンギャルドになる印象で、ソロ・ピアノのアルバムも何枚か出していて美しいインプロヴィゼーションが聞けますが、必ず前衛的な曲が挟まれています。例外的にアコースティックなのにため息が出るほどきれいなのが、今回一枚だけご紹介するものなのです。 ちなみに代表曲とされて人気のあるものは「スペイン」です。マイルスやジム・ホールも取り上げた、ロドリーゴのアランフェス協奏曲をテーマに使った変奏曲のようなもので、それをカヴァーしたミュージシャンは非常に多いとのことだけど、それはロドリーゴ風というのとは違うのでしょうか。 さて、取り上げるのはちょっと古めですが、1978年にチューリヒで行われた、ビブラフォン奏者のゲイリー・バートンとのデュオ・コンサートを収録したものです。72年にはリターン・トゥ・フォーエヴァーというバンドで同名のアルバムを録音してヒットさせましたが、同じ年には「クリスタル・サイレンス」 というアルバムもありました。それは「リターン・トゥ・フォーエヴァー」の中にある曲名でもあり、それがゲイリー・バートンとのデュオです。企画したのは ECM レコードのマンフレート・アイヒャーです。アイヒャーは元ベルリン・フィルのコントラバス奏者にしてジャズもやる人で、自身のレーベルを69年に発足させたばかり。大変な目利きで、アフリカンなスタイルではなく、ハーモニアスで美しいジャズを独自のセンスで展開しています。当時「アイヒャーのクリスタル・サウンド」などと言われましたが、その透き通った音の最初の記念碑がその「クリスタル・サイレンス」ではないでしょうか。ここでご紹介する「イン・コンサート」はそれと同じ内容のものをライヴでとったものです。そちらの方がドライブが効いているので取り上げました。ライヴを聞いてからスタジオ録音の方を聞くと、曲によってはちょっと間が抜けているように聞こえるものもあるからです。 なんという美しさでしょう。クリスタル・グラスのように透き通った音のヴァイブにチック・コリアのピアノも硬質にとれていて、合わさってぞくぞくする響きです。はじけるリズムで趣きは違うものの、クラシックで言えばちょっとモーツァルトの晩年のグラスハーモニカのように澄んだ世界です。特に「クリスタル・サイレンス(曲)」は幻想的です。チック・コリアの最も美しい歌が聞けます。 それにしても ECM のアイヒャー、レコード会社が音を奏でるわけではないし、すでに活動していたミュージシャンに録音させるわけだけど、キース・ジャレットもヤン・ガルバレクもパット・メセニーも、この ECM が世に出して来たと言っても良いのではないかと思います。最近はクラシック音楽の録音もしており、アンドラーシュ・シフの一連の CD はクラシック・ファンの宝物でもあります。  Herbie Hancock the piano ♥♥ Herbie Hancock (p) ザ・ピアノ / ハービー・ハンコック ♥♥ ハービー・ハンコック(ピアノ) ビル・エヴァンスのすぐ後の世代のピアニスト三人のうち、 最後はハービー・ハンコックです。1940年生まれなのでチック・コリアの一つ上、キース・ ジャレットの五つ上という年齢からいって、あるいはマイルスのバンドに在籍していた年度からしても先に取り上げるべきだったかもしれませんが、クラシック耳から入ると最もジャズの雰囲気が感じられるだろう人なのでこの順にしました。それは三人のうちで唯一のアフリカン・アメリカンだということよりも、むしろこのピアニストが他のミュージシャンとの対話を楽しんでいる様子からそう感じます。というのも、リーダー・アルバムやヒット曲のどれもが伴奏に回っており、ホーンが前面で活躍しているのです(ジャズのセッションをやってるときの彼は「新主流派」new mainstream と呼ばれます)。一方でそういうストレート・アヘッドなものばかりでなく、フュージョンでも先頭を切り、DJ スクラッチを入れたヒップホップに走ったりもしたし、ジョニ・ミッチェルをトリビュート(賞賛)したアルバム「リヴァー」ではグラミー賞も取り、本人に加えてノラ・ジョーンズまで出て来たりとポップな話題にもなりました。前述したクレア・フィッシャーの影響を受けたと本人は語ります。ジャズメンからは何やってるか分からないほど凄いと恐れられますが、いつも周りに誰かがいて賑やかな人です。 しかしそんな風に他のプレイヤーを立てる(アレンジャーに徹する)ので、ではハービーのピアノってどんなピアノ、ということが分かり難い事態も起こっていたのではないでしょうか。門外漢にしてカクテル・ジャズの好きなクラシック・ファンとしては、何度か聞いて「ハービー、なんか得意じゃない」だったりもする。確かにちゃんと聞いてた人には60年代から「スピーク・ライク・ア・チャイルド」、「グッバイ・トゥ・チャイルドフッド」など、静かにピアノが語る部分を持つ曲はあったわけだし、マイルスの有名な「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」でも大変魅力的な演奏だったわけで、弾き方をコピーしてみるようなミュージシャンなら分かってたことでしょう。それでも上記「リヴァー(River : The Joni Letters 2007)」で見せていたようなデリケートな音遣いについては、どれだけの人が以前から予想してたでしょう。ボーナス・ トラックに入ってる「ア・ケース・オブ・ユー」(アマゾン系/日本盤)なんか、リリカルに歌いつつ感傷に陥らず、キース・ジャレットともチック・コリアとも違います。例えばチック・コリアの叙情性が「スパニッシュ・クリスタル・ファンタジー」なら、キース・ジャレットのは「クラシカル・ロマンティック・ エレジー」かもしれません。それならハービーは何だろう。「コスモポリタン・インティメート・リリック」でしょうか。なんだかさっぱり分かりませんが、決して ECM が狙うような人じゃないながら、アフリカン・ルーツをイメージさせない瞬間もあります。いわばハービー・ハンコックのもう一つの顔です。 そしてその顔がすでに凝縮されていたのがここでご紹介する美しいソロ・アルバム、「ザ・ピアノ」です。正直最初はこの人の別のページをめくった気がしました。ジャズ・ピアノのソロ・アルバムの中で自分は気に入って一番よく聞いているかもしれません。でも果たしてハービーの一枚としてこれを出して来るのはどうなんだろうとも思います。この CD は賛否両論あり、特にジャズの愛好家からは彼らしくないという声が上がるからです。もう少し前衛的に弾いたら評価されるのでしょうか。加えて日本に来たときに日本のレコード会社がおねだりして製作したものなので、本人がこういうのを出しても平気だったかどうかも分かりません。その後も専属レーベルからソロは出てません。チック・コリアとのデュオはありますが、あれはまた二人の会話を聞くものなので趣旨が違うでしょう。 最初の音が鳴り始めた束の間(これはベースラインをなぞる動きでしょうか)、次に不協和音が続きそうな雲行きに「お、レニー・トリスターノばりのアブストラクト路線か!」と思うものの杞憂とあり、そこから一気に魅了されて、終わっても三回ぐらい続けて聞きたくなります。このときハービーは気分が良かったのでしょうか。リラックスした感じが伝わってきます。自分のレーベルじゃないし、日本で頼まれただけだから評価への気負いもなかった、のでしょうか。スタンダード・ ナンバーを元にした即興では元歌が分からなくなることはありません。崩しのフレーズで滝のようにジャズっぽい音運びが出ますが、ファンキーではありません。 大変美しい音楽なのだけれど、実際の音の感じは何と表現したらいいのでしょう。協和音が時折モダン調の抽象的な挿入句で中断されたりはします。結局我々は調性と不協和のバランスを楽しんでいるのでしょう。どのぐらいの比率が心地良いのでしょうか、ときどき雲がかかり、また晴れます。フリーのような無調ではなく、小まめな転調による調性のぼかしがあります。ウェイン・ショーターのアルバムでも味わうような彷徨う感覚ですが、それはクラシック音楽の関係調への予定調和的な転調ではなく、意外な方へ少しずらして、またずらして移ろい漂って行く、という感じです。つまり輪切りにした個々の瞬間はきれいな和音です。それがもっと短くなって複雑なテンションを次々繰り出してるようなところもあります。結局セブンス(四和音)に加えてときに五和音その他の個性的なコードを、解決したりしなかったりしながらどう挟むかがプレイヤーの個性なんでしょう。そしてそれら全体がパズルのピースになって心地良いリズムに揺られて行きます。こうして言葉にしてしまうと最近の音楽は皆同じかもしれませんが、ジャズの人はこういう種類、どうやって説明するのでしょう。クラシックの愛好家が作曲家の決めたメロディの動きと和音の面白さで音楽を判断するのに対して、ジャズはコードにせよスケールにせよ最初に決めた規則からの逸脱を楽しむので、規則を知らずに聞いている者には雲をつかむような話です。やはりこの人について言われる「モード・ジャズ ≒ 新主流派」なのでしょうか。 ここでのハービーは音の選択に迷いが出ているなどと言う人もいるようですが、素養がない自分はそんな風には思いませんでした。バランス感覚とセンスを感じるし、セッションの現場で培ってきた感覚でしか弾けないんじゃないかと思います。コードの選び方もいいと思います。今までホイットニーみたいに「白っぽい」とバッシングされるのが怖くてこういう音を出さなかったのかな、などと考えてもみますが、全然違うかもしれません。でも仮にそうだったとしても、彼は十分ジャズの中心で来ましたから、大丈夫でしょう。そういえば上記のジョニ・ミッチェル自身の音楽もちょっとモード風でした。大雑把にメロディ・ラインとコード進行の結びつきが緩いという点に過ぎませんが、ミッチェルの場合は歌ってる音符に対応して推定されるコードを無視し、伴奏を弾いてる感じに聞こえたりもします。そんな意味でハービーの音楽とも相性がいいのかもしれません。 因みにジョニ・ミッチェルはカナダの歌手で、多くのジャズ関係者が曲を取り上げ、共演もしています。「ボス・サイズ・ナウ(青春の光と影)」など、詞の内容も時を俯瞰する眼差しを感じ、心打たれるものがあります。ハービーのアルバムではウェイン・ショーターと二人で、静かに光るような美しい時間を共有しています。アルバム「リヴァー」自体をここで取り上げなかったのは歌が多いからで、その「ボス・サイズ・ナウ」に「スウィート・バード」、「ソリチュー ド」、「ア・ケース・オブ・ユー」のインストゥルメンタル路線で通してくれればよりクールだったかなと個人的には思ったりします。人の声というのは誰しも否応なく注意を向けてしまうようにできていますから。でも大変魅力的な一枚ですからぜひ聞いてみてください。 話を戻してザ・ピアノ、録音は1978年です。技術者は日本の人ではないけどレーベルは日本のソニーです。ブルージーな「ブルー・オータニ」はあのホテルの名前です。元々ダイレクト・カッティングの企画だったようですが、CD はレーザーで板から起こしたのではなく、アナログ・テープでもとってたのでしょう。素晴らしい音です。最近のデジタル録音と比べてもずっと良いような気がします。ECM などとは違ってクリスタル・クリアーには固まらないピアノの音で、ピンと張って自然な艶があり、やわらかさも感じさせます。 ハービー・ハンコックという個性、どんな瞬間も暗くならず、胃にもたれずでさらっとしているところはアフリカ系の美点かもしれませんが、仮にそうであれ、日本人らしいとかジャズらしいとか黒人らしいとかのこだわりは排他的ですから、そういうものに縛られずに自分らしくいてほしいと思います。エヴァンス以降のジャズ・ピアノ即興三人衆の中では、この人の感性が個人的には一番好きです。環境も良かったのだろうけど、リラックスしていて誰よりリズム感に満ち、濁りのない美しさがあります。叙情的だけど爽やかな一陣の風が吹き抜けて行きます。  その他のピアニスト ビル・エヴァンスのすぐ次の世代を代表するハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレットの三人以外のピアノでハーモニー重視の音を聞かせるのは誰でしょうか。レーベルで言うならその種の路線は CTI と ECM でしょう。辛口のジャズファンからはイタリアの CAM や日本のヴィーナス・レコーズなども聞きやすいと思われてるかもしれません。CTI は ECM とは方向性が違いますが、クリード・テイラーのレーベルです。有名なアーティストとしては前述したギターのジム・ホールがいます。ジャズとして筋の通ったプレイヤーながらアランフェス協奏曲などは映画音楽のようなアレンジがされていました。フルートのヒューバート・ロウズは「アフロ・クラシック」というアルバムでクラシックの作曲家の曲を取り上げていて、ちょっと電化されてるけど美しかったのでよく聞きました。そしてメロウなサックスのグローヴァー・ワシントン・ジュニアも盛んに「お洒落」と言われていたし、歌もうたってポップなジョージ・ベンソン、フュージョンのアレンジャーとして有名なボブ・ジェームスもいます。聞きやすいものが多いのでこのレーベルから探すのも一つかもしれませんが、ピアニストとなるとぱっと思いつきません。 そうなるとやはり ECM を見るということになります。代表的な人を挙げてみます: ポール・ブレイ スティーブ・キューン スタンリー・カウエル エグベルト・ジスモンティ リッチー・バイラーク アート・ランディ ポール・ブレイ Paul Bley はカナダのピアニストで、生まれが1932年なので他の人たちより若干上、そんなこともあってかキース・ジャレットに影響を与えたとも言われますが、それは現代音楽=ポスト・フリーの雰囲気が混ざるところかもしれません。クラシック寄りでそっち方面を知る、ちょっと難しいもの好きの人たちからの支持があるようでした。若いときの写真は「理由なき反抗」のジェームス・ディーンが成長してニヒルになったように格好良いです。カーラ・ブレイの夫であり、元々フリー・ジャズ系の活動をしていた人です。アルバムは「オープン、トゥ・ラヴ(1973)」が有名で、不協和音でない部分ではピンと張った独特のクールな空気感があり、そこはかとない叙情が感じられます。 スタンリー・カウエル Stanley Cowell は1941年生まれのアフリカ系で、ハービー・ハンコック同様に「新主流派」に入れられるようです。ジャズの感覚がより濃いでしょう。 1947年ニューヨーク生まれのアート・ランディ Art Lande は「ルビサ・ パトロール(1976)」が有名ですが、もはやジャズというよりも管楽器が出て来るクラシックみたいなところがあります。一方でソロのアルバムでは歌い回しがイージー・リスニングのように聞こえる瞬間もあります。 リオデジャネイロ出身のエグベルト・ジスモンティ Egberto Gismonti はギタリストでもあり、多才な人で独 自の音楽を作ります。同じく1947年生まれです。独特のリリシズムがあって美しいのですが、ラテンのリズムと混じり合ったエネルギッシュな曲もあり、アストル・ピアソラ以上に才気煥発過ぎて CD 一枚通しで環境音楽的に聞くにはきつい面もあることでしょう。 残るはこのレーベルでキース・ジャレット、チック・コリアに次いで人気があり、クラシック系の人からもきれいだと言われる二人です。それはスティーブ・ キューンとリッチー・バイラーク。しかしどう取り上げていいのか迷うところです。リッチー・バイラーク Richie Beirach は上記二人と同じく1947年生まれ。キース・ジャ レットの二つ下ということで、ほぼ同世代のアメリカ人です。音の感覚というのはそれぞれ好みがあり、このピアニストこそがビル・エヴァンスの正統な後継者だと言う人もいます。最初に有名になったアルバムはソロが「ヒュブリス(1977/邦題は「パール」)」、トリオが「エルム(1979/初リーダー作は「イーオン」1974)」です。中でも「ヒュブリス」の最初の曲「サンデイ・ソング」は人気があります。ピアノの音が独特の艶で録音されていて「粒が立っている」と評される点もポイントが高いのでしょう。複雑なコードを駆使すると 言われることもある人ですが、メロディ・ラインが形成される度合いはスティーブ・キューンよりも大きく、そういう節で行ったら次はこうなるよね、と思わせつつ、しかしその解決に向う線を途中で切るようなところがあります。どこかへ向かいそうで向かわない感覚です。即興での迷いという次元の話ではないので、そういう好みなのでしょう。サンデイ・ソングはかなりメロディ完結に近いですが、試し弾きをしてるような感覚で異種の音を挿入して来たりします。波が寄せては返すように何度も繰り返しのトライがありつつなお解決が延期され続け、そうした意図的に回避されてる感覚に対して好き嫌いが分かれるミュージシャンである気がします。ポール・ブレイ同様無調へと向かう傾向の曲も聞かれます。  Steve Kuhn Remembering Tomorrow Steve Kuhn (p) Joey Baron (ds) スティーヴ・キューン / リメンバリング・トゥモロウ スティーヴ・ キューン(ピアノ)/ ジョーイ・バロン(ドラムス) さて、代表で取り上げるのはリッチー・バイラークと並んで ECM で人気のあったもう一人、スティーブ・キューンです。ここにご紹介するガイド・マスト(支線塔)のカヴァー写真のは、彼が1995年に ECM に戻って来て録音した総括編にして、ちょっと波長の変化した一枚です。というのも、1938年ブルックリン生まれでハーバード卒のドイツ系のこのピアニスト、ECM でのレコーディングは74年のソロ・アルバム「エクスタシー」とカルテットによる「トランス」を皮切りに、77年に出た「モーティリティ」(邦題「レイン・フォレスト」)などが人気を得たものの、その後同レーベルを離れていたからです。これら初期のアルバムはその後廃盤状態が続きました。今でも「トランス」を除いた二枚は手に入り難いですが、それらが集められて歌入りの「プレイグラウンド」と合わさった三枚組の「ライフス・バックワード・グランスィズ」というのも出ました。 ソロの「エクスタシー」はヨーロッパの音楽の系譜を受け継ぐ作りで叙情的であるとか、やはり「印象派っぽい」などと言われて来ました。果たしてどうでしょう。音の選び方や繰り返しが多いところがサティのようだと言われればそうかもしれませんが、もはやジャズではないな、ぐらいは最低限言えるでしょう。面白いのはこのソロ・アルバムの頑張り具合、この人の他の時期の作品とはちょっと違います。本人がアイヒャー(ECM)好みに弾いたんだと言ったという話も出てますが、本当なのかどうか。クールさに加えて前衛的な展開が挟まっています。 そもそも現代においてはきれいなメロディを歌ってるだけだと安易だと言われます。かといって完全な無調は嫌がられますから、前衛的な音を混ぜるさじ加減は難しいところでしょう。ポール・ブレイにせよリッチー・バイラークにせよ、適度なスパイス料理のときもあればハバネロ・ソースの場合もあります。しかし濁った音(波長が整数比にならない)の感性は人間発達してないので、聴感の優れた演奏者が感覚的にその音を選ぶことがあったにしても聴衆には聞き分けられ ず、ただ怒りや焦り、不安といったネガティヴな感情を喚起しがちです。こういう前衛的な音の即興遊びはピアノでは簡単です。タモリもチック・コリア風をやってましたが、ペダルを踏んだまま左手のグーで低い音を任意に叩き、右手で適当なメロディを鳴らせばもうそれらしい爆発の表現となります。不協和音は隣り合ったキーの共鳴ですから拳骨は好都合なのです。絶対音感や音に色を感じる共感覚の持ち主以外にはシドレミでもレミファソでも同じです。スティーブ・キューンがそんなレベルの低いことをやってるわけではないですが、「エクスタシー」ではジェット機の離陸タービンを間近で聞くような音も聞こえます。 でも後に彼はそういう音を出さなくなるのです。ストリングスを用いた「プロミス・ケプト」はまるでパット・メセニーのプロデュースした映画音楽みたいだし、最近のトリオ演奏「トゥ・アンド・フロム・ザ・ハート」など、懐かしいスタンダードという感じでムード満点です。無理をしない大人になったのでしょうか。最もスティーブ・キューンらしい部分って、どれなんでしょう。 「リメンバリング・トゥモロウ」に話を戻しますと、これは上記二つの間をとって、抽象性にもイージーにも行かない一番バランスのとれたアルバムであるような気がします。聞いていて心地良い時間が過ごせるのです。旧作の「ザ・レインフォレスト(「モーティリティ」所収)」も「トランス(「トランス」所収)」も 「シルバー(「エクスタシー」所収)」も入っているのに、みな破綻なく透明なサウンドです。アンサンブルものでは旧作にはフルートも入っていましたが、今回はあくまでもピアノが中心。スピード感とリズムの良さが前よりも感じられます。一つ言えるのは、このアルバムではシンバルの音が目立つということです。効果的ですが、人によっては過剰な感じがするかもしれません。 ではどういう音楽かとなると難しいですが、アイス・ブルーというかグレイシャー・ブルーというのか、全編ちょっとクールな短調系の青白い色が響いていて、途中で半音ずれて行くような進行と一瞬のメジャー・トライアドの挿入、四和音の複雑さに逃がす処理とが相まって悲しい短音階の波長には浸らない、という感じです。そしてそのピアノの音の質自体も ECM らしいクリスタルな印象があります。リッチー・バイラークのようにメロディーの流れを途中で切っているようには感じず、同じフレーズが飽和して、少しずつ形を変えつつループになって続いて行きます。つまり同様に典型的なメロディーラインの完結はないのですが、きれいな音で構成されたユニットが繰り返される感覚なのです。リッチーよりも濁りがなく、スピードの揺らぎもなくて、リズムが一定な感じはよりジャズらしいとも言えるでしょうか。ボサノヴァっぽく聞こえる曲もあれば、アランフェス協奏曲のように哀愁の混じるのもあります。キース・ジャレットみたいに精神的なドラマで押すところはなく、友達を呼んでの食事会のバックにも使える環境音楽的な心地良さがあります。作品と対峙して聞く音楽ではないけれどもチープにもならない、言葉にしづらい音のコレクションです。  エヴァンスの次の次の世代 ビル・エヴァンスの次の世代を代表する三人、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キースジャレット以外で ECM から出していた人を取り上げました。ではそれ以外のレーベルの同世代、あるいはもっと新しい世代のピアニストでエヴァンスが好きな人にも聞けるかもしれないのは誰でしょうか。生年順に列挙してみますと: エンリコ・ピエラヌンツィ アラン・パスクァ フレッド・ハーシュ ティエリー・ラング ミシェル・ペトルチアーニ ジョバンニ・ミラバッシ ブラッド・メルドー ミシェル・ビスチェリア(ビシェリア) ステファノ・ボラーニ マルチン・ボシレフスキー といったところでしょうか。簡単にご紹介して何人かを CD とともに取り上げます。好みがありますので全員を公平には扱えないのはご了承ください。  Ballads Enrico Pieranunzi Enrico Pieranunzi (p) Marc Johnson (b) Joey Barron (ds) バラッズ / エンリコ・ピエラヌンツィ エンリコ・ピエラヌンツィ(ピアノ)/ マーク・ジョンソン(ベース)/ ジョーイ・バロン(ドラムス) エンリコ・ピエラヌンツィは1949年生まれでキース・ジャレットの四つ下なので、最近の人とも言えないでしょう。むしろベテランと呼ばれるローマ生まれのピアニストです。クラシック音楽の素養があり、自らもその方面に興味があると語っていて、ガーシュウィンやドビュッシーにも挑戦しています。そのためもあってかメロディの運びは大変きれいで分かりやすく、クラシック音楽の愛好家には特にお薦めです。そういうきれいなところでは弾むリズムというよりもゆったりとした拍の取り方に特徴があるように思え、ビル・エヴァンスよりずっとヨーロピアン(非アフリカン)でしょうか。キース・ジャレットやフレッド・ハーシュ以上にジャズのリズムとは思えないときもあります。連続して同じ音符や隣り合って続く音を鳴らす好みもあるようで、現代的な趣向を凝らしているとき以外はチック・コリアのようにあちこち音程が飛ぶような弾き方ではありません。その意味でもジャズっぽくないと感じる方もおられるでしょう。キース・ジャレット同様に音を繰り返しながら待っているような瞬間も聞かれます。 しかしこの人の一番の特徴はなんといってもオペラの国のカンタービレ精神というのか、豊かな歌を持っているところです。それがときにメロドラマティックに響いたり、ちょっとセンチメンタルに感じられたりするかもしれません。ニーノ・ロータかエンニオ・モリコーネかという親しみのあるメロディで、ミュージカルのような歌い回しに聞こえることもあります。そしてこの人の歌を高く評価する方であれば、ヨーロピアン・ジャズ・トリオなども嫌いじゃないはずです。ピル・エヴァンスとも活動して来たドラムスのポール・モチアンやベーシストのチャーリー・ヘイデンとも演奏するし、ちゃんとバップしててフリーっぽい曲もやるので一緒にするなとおっしゃるかもしれませんが、それならそれでヨーロピアン・ジャズ・トリオも可哀想な気がします。 アルバムは60以上も出ていて、どれがベストかは分かりません。ジャズ・ファンからはカクテル企画だと言われるでしょうが、静かできれいなものには「バラッズ(2004)」があります。ビル・エヴァンスの最後のベーシストを務めたマーク・ジョンソンが加わっています。「ホワッツ・ホワット」というソロ・アルバムもありますが、そちらは甘いメロディどころか、ずいぶん頑張ってるので本格の人向けでしょう。そんな風にジャズの本流として異を唱える人のいない盤ではなくて、まずこちらのバラード集なんかを聞けば、このピアニストのメロディ・センスが分かるでしょう。それで気に入られたのなら、この人は CD の数が多いので、トレジャー・ハンターが巨大な宝箱を見つけたようなものです。  Alan Pasqua The Interlochen Concert ♥ Peter Erskine (ds) Alan Pasqua (p) Darek Oles (b) ジ・インターロッケン・コンサート / アラン・パスクァ ♥ ピーター・ アースキン(ドラムス)/ アラン・パスクァ(ピアノ) ダレク・オレス(オレシュキェヴィッチ/ベース) アラン・パスクァもビル・エヴァンスが好きならこの人も、という話の流れでよく出て来るピアニストだと思います。1952年生まれのイタリア系アメリカ人ですが、ジャズだけでなくロック系の仕事もこなすし、作曲もするし、Wiki によると CBS ニュースのテーマも作ったとか。でも今回ここで取り上げるアルバム「ジ・インターロッケン・コンサート(2009)」は趣旨に反するかもしれません。ジャズのセッションとしていいものを、というよりも力点はリリカルで美しいメロディーをという話だったはずですが、それなら他のアルバムを選ぶべきだと思うからです。例えばソロの「ラシアン・ペザント(1999)」、その名もずばり「ソロ(2006)」、「ソリロクィー(2018)」など。あるいはピーター・アースキン名義のトリオ演奏「ライヴ・アット・ロッコ(2000)」あたりの方が適していると思います。じゃ、どうしてそっちを挙げないのかというと、単に歌い回しの個人的な好みの問題からです。自分には少しきれい過ぎるというか、感傷的なところはなくて、温かくてとてもいい波長なのですが、ピエラヌンツィほどじゃないにしても、下降旋律で降りて来て終わるところなどが若干ベタに感じてしまうときがあるのです。メロディーの好みは人それぞれ、感じ方も千差万別で、気に入る方には他にない魅力的なものとなるでしょうから、ぜひ上記のアルバムも聞いてみてほしいと思います。どこか懐かしいような、美しい音楽です。 そしてこちらのインターロッケン・コンサートというアルバ ム、インターロッケンというのはミシガン州のミシガン大学よりはずっと北の方、ミシガン湖に近い西側の町の名前です。そこには芸術高校があって、名義の上でこのアルバムのリーダーであり、ウェザー・リポートのメンバーでもあったドラムスのピーター・アースキンはその学校の出身です。アースキンとアラン・パスクァはインディアナ大学で一緒だった縁で70年代にそのアースキンの高校で一緒に演奏しており、このアルバムは久しぶりにそこで行われたセッションだったようです。だから聴衆にパーソネルを紹介しているのもアースキンです。 リラックスしたいい雰囲気のセッションです。アラン・パスクァは誰かと合わせるときに呼吸を上手につかむタイプなのでしょうか。メンバー同士気が合ってるのかもしれません。いろんな意味でレベルの高い演奏である気がします。ピアノは力まないタッチでコロコロまろやかであり、アタックを微妙に遅らせて伸び縮みさせる拍の取り方が自在です。ナット・キング・コールやそれに倣ったダイアナ・クラールにちょっと似た瞬間があるでしょうか。クラシカル・ピアニストのようなピエラヌンツィとは全く違うタッチです。リズム感があって心地良く、「オータム・ローズ」なんか特にそうですが、それこそが独特のリラックス感をもたらす軽さにつながっているのだと思います。メロディに関しては、ときに重みと暗さを除いたキース・ジャレットのような歌を聞かせる人なが ら、このリズムについては全く別です。思うに白人系ミュージシャンはあまりこの方面の感覚を持ち合わせていないケースが多いのですが、この人は天然で発揮している印象です。自分を追い込まず常に楽しくて、ホワイトのピアニストとしては最もセンスがある一人ではないでしょうか。 それに加えて録音の加減かピアノの音に潤いがあり、やわらかさと艶のバランスが絶妙です。ハービー・ハンコックの「ザ・ピアノ」とも比べられるでしょう。タッチの繊細さがよく分かって退屈しないので、「ザ・ミュージック・オブ・マイ・ピープル」や「ブルガリア」、「コン・アルマ」のようにちょっと抽象的な音を聞かせ、コード進行に音を詰め込むバップなナンバーでも美しく、面白く聞けてしまいます。こういう現象は滅多にないことです。 本来白熱するところでも呼吸があり、微妙な強弱をつけるからかもしれません。音に隙間があって安らげます。 一方でスローなバラード・ナンバーはこの上なく美しく、ソロのアルバムで見せていたようなムード・ミュージック的な歌は絶妙に外していてセンス良く感じ ます。「オータム・ローズ」、「ウィチタ・ラインマン」、「バルセロナ」と三曲堪能できます。この路線でまるごと一枚に集まっていれば♡♡にするところです。自分としてはこのままで二つでも、クラシックの愛好家向きというページの意図から一つ減らします。  Alan Pasqua My New Old Friend ♥ Alan Pasqua (p) Darek Oles (b) Peter Erskine (ds) マイ・ニュー・オールド・フレンド / アラン・パスクァ ♥ アラン・パスクァ(ピアノ)/ ダレク・オレス(オレシュキェヴィッチ/ベース) ピーター・アースキン(ドラムス) 流しておいて心地良くいられるという意味では、こちらのアルバムの方がむしろ良いかもしれません。ソロ・アルバムのようなキャッチーな歌にはならず、抽象路線にも傾かずにバランスがとれています。ちょっと前衛的な音で始まるのは四曲目の「オール・ザ・シングス・ユーアー」一曲で、それも軽やかなので気持ち良く聞けてしまうという、ぼぼバラード尽くしの一枚です。思うことがあるとすれば三曲目の「ハイウェイ14」でバックに女性の声を被せることぐらいでしょうか。そこだけ CTI ですか。州間国道14号って、シカゴからイエロー・ストーンのワイオミング側入口まで行っている道ですが、どうしてスキャットしちゃうのでしょう。思い出があるのかな。 ビル・エヴァンスのアルバム・タイトルにもなった「ユーマスト・ビリーヴ・イン・スプリング」に始まり、前述の「インターロッケン・コンサート」にも入ってた「ウィチタ・ラインマン」と「バルセロナ」も聞け、チャップリンの曲でナット・キング・コールも歌った「スマイル」で締め括られる、スタンダード曲とオリジナルで構成された2005年リリースのアルバムです。「インターロッケン」が良くて先にご紹介はしましたが、むしろこちらの方をこの人の代表作とすべきでしょうか。
 Solo Fred Hersch ♥ Fred Hersch (p) ソロ / フレッド・ハーシュ ♥ フレッド・ ハーシュ(ピアノ) フレッド・ハーシュは1955年シンシナティ生まれのユダヤ系のジャズ・ピアニストで、クラシックのようなオーケストラものの作曲もする人です。HIV 感染はスコット・ロスやフレディ・マーキュリーのように以前なら死が避けられませんでしたが、最近は薬によって状況は変わり、この人は一時昏睡に陥ったものの回復して活動できるようになったそうです。死に直面したその出来事以前と以降とで、彼の音楽が変わったかどうかは自分には分かりませんが、最近の活動は本人も大変満足しているようです。その音楽は詩情とか叙情といった言葉でよく言い表され、エヴァンス派がどうとか言うべきではないにしても、日本の通販サイトでは「これを買った人はこれも」の項目にビル・エヴァンスが登場することもあるようです。 スローな曲で静けさが際立つピアノだと思います。短調好みというわけではないけれどもやや寒色系です。モノトナスに感じる瞬間もあるものの、ポン、ポンと音符の間を空けて叩くときの風情が良く、歌もののアレンジや伴奏での静謐さも素晴らしいと思います。クラシックで言えば古典派以降の感情を吐露するような物語性、抒情詩のような雰囲気を持ちます。ただ、この人についてはこちらがあまり理解の及ばないところもあり、多くは語れません。それでも言ってみるならば、歌を抑えた感覚が根本的に違うにせよ、ピエラヌンツィ同様にタッチはクラシックのピアニストのようです。クラシック畑にも微妙に揺れる人はいるわけですが、少なくとも最近の演奏を聞く限りでは、前述のアラン・パスクァのようなジャズ特有のリズムの延び縮みは感じません。恐らくその真面目な拍子と、フレーズを繰り返しながら少しずつ展開させて行くキース・ジャレット風の運びとによって、テンポのある曲ではちょっと息苦しくなる瞬間があります(感じ方次第です)。セロニアス・モンクが好きなのか、ハーシュには現代音楽っぽい運びも結構あって、よりハーシュに感じてしまうのです。 一方で彼が作曲したコンサート用の作品はまさにクラシック音楽で、美しいハーモニーが堪能できます。ジャズではフリーっぽいものに興味があっても、クラシックにおいてはモダンの方へは行かず、新ウィーン楽派のずっと手前で踏みとどまるようです。ただコンサート用ということでもあり、ピアノを弾いているのはフレッド自身ではなく他の人が多くなります。ナクソスから出ている2007年録音の「フレッド・ハーシュ/コンサート・ミュージック 2001- 2006」がお薦めです。夢見るような後期ロマン派といった風情の曲が並び、「バッハのコラールによる24の変奏曲」ではマタイ受難曲のあの有名な旋律が展開されて行きます。ヴァイオリンとチェロが加わった室内楽作品もあります。この盤以外にも最近は韓国のピアニスト、ユンビ・キムによる「ハウス・オブ・メニー・ルームス/ニュー・コンサート・ミュージック・バイ・フレッド・ハーシュ(2017)」というのも出ています。部屋の多い家といってもウィンチェスター銃の幽霊屋敷ではありません。チャイコフスキーのテーマに始まり、ラフマニノフかという叙情性も表れた、ロマンティックな作品群です。 現代音楽のような音の入らない別の選択肢は歌です。マンハッタン・トランスファーの歌手、ジャニス・シーゲルの歌うアルバム「スロー・ホット・ウィンド(1995)」はフレッド・ハーシュがピアノを弾いています。ファンキー/ブルージーな部分のない清涼感のある歌い方で、ハーシュの方は伴奏者としての才能がよく表れています。 ソロ・アルバムはいくつも出していますが、例えば「アローン・アット・ザ・ヴァンガード(2011)」にはシューマンに捧げられた「パストラール」もありますし、「メモリー・オブ・ユー」は静かできれいな曲です。4、8、9曲目で若干難しい音が出て来るぐらいでしょうか。一方で「オープン・ブック(2017)」にはこの人の美点がよく発揮されています。その霧にかすむ森のジャケット写真の通り、全体に統一されていて ECM 風のクールで幽玄な世界です。偶数番の2、4、6曲目では若干聞き難い音も出るし、バラード調ばかりというわけではなくて、弾むような陽気さが出るところもあります。 しかしこの人の曲で魅力的だったのはジョニー・ミッチェルの名曲「ボス・サイズ・ナウ」かもしれません。ここでご紹介する上記カヴァー写真のアルバム、「ソロ(2014)」で聞くことができます。前述のハービー・ハンコックがウェイン・ショーターとやったもの(「リヴァー/ザ・ジョニー・レター」所収)と比べるのも面白いと思います。あそこまでアレンジが効いて大人のスパイスがかかってない分、元歌のメロディの美しさが堪能できます。この曲は元から素晴らしいのですが、歌詞はこんな具合です: 「今、雲を両側から眺めてた。上からと下から。そしてどうしたものか、今なおそれは雲の幻影であって、思い起こすに私には、雲というもの自体が何なのだか全く分かっていない」。 そしてその「雲」が「愛」に代わり、「人生」に代わって行きます。ジョニー・ミッチェル本人の歌うアルバムではオーケストラ伴奏の同タイトル盤「ボス・ サイズ・ナウ(1999)」が良いのでぜひ聞いていただきたいと思います。フレッド・ハーシュは最近この曲を気に入っているのか、コンサートで何度も取り上げているようです。そしてその彼のバージョンもまた、彼のレパートリーの中で最も感動的なものではないかと思います。 このパルメット・レーベルのアルバム、ソロとしては十作目で、トータルで大変魅力的なものです。ハーシュの CD は現代調の曲を挟むので聞き難い、などと述べました。でもこのアルバムついては気になりません。むしろ数あるジャズ・ソロの中でも光ってる一枚なのです。最初の「オ・グランジ・アモール」から美しく、二曲目のエリントン楽団の「キャラバン」も馴染みのメロディ進行で楽しめるし、モンクの「イン・ウォークト・バド」も存外にきれいです。ジェローム・カーンのスタンダードでシナトラも歌った「ザ・ソング・イズ・ユー」も心に響きます。聞けない曲がない上、最後が圧倒的な「ボス・サイズ・ナウ」なのです。 マサチューセッツに近いニューヨーク州のウィンダム・シビック・センター・コンサート・ホールでのライヴで、このときは完全に集中できたと本人も書いています。音の良さについてはハービー・ハンコックの「ザ・ピアノ」とアラン・パスクァの「ジ・インターロッケン・コンサート」がやわらかい艶を捉えていて良いと書きましたが、このフレッド・ハーシュのライヴ盤も反響は多めながら似た傾向で、良いピアノの生の美しさを味わえます。普通はもう少し固まって硬質になる録音が多いものです。倍音の共鳴が聞こえます。
ソロではなく、トリオでのスロー・バラードも魅力的です。 美しいピアノが語り出し、しばらくしてベースがお腹に響くようにうなってブラシがシュッシュッと鳴り出すと堪りません。アルバム「サンデイ・ナイト・アット・ ザ・ヴァンガード(2016)」の中のポール・マッカートニーの曲「フォー・ノー・ワン」などいかがでしょう。ラストのアンコール曲、「ヴァレンタイン」もいいです。 でもトリオ演奏としてより面白いと思えたのはむしろ、「ハートソングス(1989)」の方かもしれません。クラシックのピアニスト同様に拍の頭のずらしやリズムの揺れがない、などとはじめに書きました。基本はそれがこの人の弾き方だと思うわけですが、この80年代終わりの演奏は案外そうでもないことに気づきます。弱音の中にデリケートな抑揚があり、表情がより豊かに聞こえる気がします。たまたまでしょうか。速いパッセージにも静けさが染み込んでおり、力が抜けています。若さゆえか、最近のものとは違ってバラードのメロディ・ラインを追わない独特のクールな美学に貫かれています。「ボス・サイズ・ ナウ」が最も好きだとしても、この雰囲気も個性的でいいです。ピアノの音がきれいなのもこのアルバムの利点です。これは病気からの回復後には軽妙さが失われた、と言える現象なのでしょうか。あるいは後年には何かを悟り、ジャズっぽいリズムに乗るよりも、真っ直ぐであることの方が自分らしいと思った、ということでしょうか。  Thierry Lang Trio Private Garden ♥♥ Thierry Lang (p) Ivor Malherbe (b) Marcel Papaux (ds) プライヴェート・ガーデン / ティエリー・ラング・トリオ ♥♥ ティエリー・ラング(ピアノ)/ イヴォール・マレベ(ベース)/ マルセル・パポー(ドラムス) ビル・エヴァンスを最も愛するというピアニスト、ティエリー・ラングは1956年生まれのスイスの人です。経歴としてはローザンヌ大学とベルン大学でピアノと作曲を教えていてブルー・ノートからも CD をリリースしているということぐらいしか分かりません。音の作り方はビル・エヴァンスよりもメロディー・ラインを表に出してつないで行く傾向は感じられるので、そういう意味ではよりスムーズ・ジャズ側に寄っているという言い方も出来るかもしれませんが、エヴァンス以降でそれに匹敵するリリシズムを感じさせるという点で最も魅力的なジャズ・ピアノではないかと思います。形ではなく伝わって来る感覚としては、リリカルできれいでありながらそこはかとない至福感というか、感謝というか、静かに落ち着いた感覚があってこだわりがありません。今この状態でいいんだ、という肯定的なものも感じます。楽しんで弾けているのでしょうか。ハービー・ハンコックの叙情的な部分にもちょっと似た波長を感じるときはあるけれども、ロマンティックな音を響かせる多くのジャズ・ピアニストにはより湿り気があり、強い憧れや切望、心の葛藤を伝えて来る人たちが多い中で、このティエリー・ラングは軽さにおいて格別なものがあります。技巧に走ってやかましくもならず、安っぽい旋律にも流れず、この人こそ待っていた人だ、という意見も分かります。 その中でも「プライヴェート・ガーデン(1993)」は彼の代表作でしょう。このアルバムは彼の経歴の中で比較的初期のものながら完成度が高く、日本でも人気がありました。これを聞いていると、フレッド・ハーシュの静かなときなどとは違った意味で常に静けさのある人だなと思います。クールとかクリスタルとか、そんな冷たい北欧的なものではなくて、すっと力が抜けた独特の美しさがあり、とても洗練されています。
具体的には、いかにもバラードという感じでもないけど全編スローに寄っています。エネルギッシュなバップもフリーの叫びも出て来ません。民謡音型のようなメロディーもありません。それでいて特定の音節を繰り返す曲でもなく、きれいな何小節分かの歌があります。それは例えて言えばマイナー・キーから少し上へずらして転調し、メジャーのセブンスを挟むことで諦観のような軽さをもたらすようなもので、ありきたりのムード音楽的な感傷は免れています。要素に分解したような「ステラ・バイ・スターライト」も、ゆったりした「ジャイアント・ステップス」も元の曲のようには聞こえず、統一された色を持っているのです。一枚通しで大変上質な環境音楽だとも言え、時々かけては浸っていたくなるウィンド・ベルのような心地良さがあります。
メンバーは彼の名を冠した初期のトリオで、イヴォール・マレベのベース、マルセル・パポーのドラムスです。このベースもスイスの人で、あまり話題に上ることがないようですが、すごくいいと思います。レーベルはスイス・モントルーのプラニスフィアや、フランスのフレモー&アソシエ、エレファントなどとして出ています。日本盤もありました。
ただ、このティエリー・ラングという人、洗練されたリリシズム以外の顔も多少は持っていたようで、一時期そんな要素がいくらか現れた瞬間もあるように思います。それはビル・エヴァンスが時折バップの火花散る側へ行ってジャズ・ファンの信頼をつなぎとめているのとは反対の方角で、ロマンティックな歌謡をそのままなぞったようにメロディアスで分かりやすい、ニューエイジ音楽寄りとも言えるものであり、したがって熱いジャズ・ファンには安っぽいといって首を傾げられることとなりました。クイーンのマネージャーによるピアノ・ソロ、「ガイド・ミー・ホーム(1999)」にはコンフォーティングな甘い音があるような気がします。「リョーバ(2007)」、「リョーバ・リバイズド(2010)」はスイス・アルプス、グリュイエール地方の牛追い歌であるラン・デ・ヴァッシュ(リョーバ)を題材にとってスイス人のノスタルジーを誘い、民謡特有の親しみやすさが出ています。それがストリングスの伴奏に乗り、夜明けのトランペットも泣いて、まるで映画音楽かムード・ミュージックのように響きます。その路線はまだ他にも少しありましたが、試行錯誤だったのか、レコード会社の要望だったのかは分かりません。でも最近になってまた少し、ストレート・アヘッドな方へと戻って来たでしょうか。以下ではそんなティエリー・ラングの、主観ではありますが、洗練された響きが感じられる方のアルバムを続けて何枚か取り上げてみます。
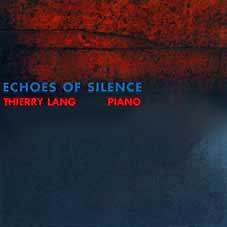 Echoes of Silence ♥♥
Thierry Lang (p)
エコーズ・オブ・サイレンス ♥♥
ティエリー・ラング(ピアノ)  Between a Smile and Tears ♥♥ Thierry Lang (p) Ivor Malherbe (b) Marcel Papaux (ds)
ビットウィーン・ア・スマイル・アンド・ティアーズ ♥♥
ティエリー・ラング(ピアノ)/ イヴォール・マレベ(ベース)/ マルセル・パポー(ドラムス)  Thierry Lang ♥♥
Thierry Lang (p) Heiri Känzig (b) Marcel Papaux (ds)
ティエリー・ラング ♥♥
ティエリー・ラング(ピアノ)/ ヘイリ・カンジグ(ベース)/ マルセル・パポー(ドラムス) 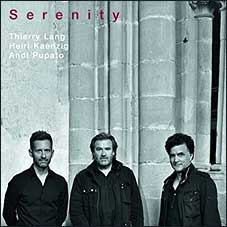 Serenity ♥♥ Thierry Lang (p) Heiri Känzig (b) Andi Pupato (ds)
セレニティ ♥♥
ティエリー・ラング(ピアノ)/ ヘイリ・カンジグ(ベース)/ アンディ・プパート(ドラムス)  Moments in Time ♥♥ Thierry Lang (p) Heiri Känzig (b) Andi Pupato (ds)
モーメンツ・イン・タイム ♥♥
ティエリー・ラング(ピアノ)/ ヘイリ・カンジグ(ベース)/ アンディ・プパート(ドラムス) 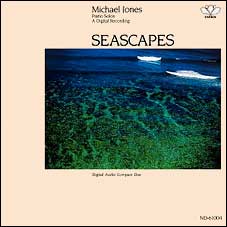 Seascapes ♥♥ Michael Jones (p)
シースケープス ♥♥
マイケル・ジョーンズ(ピアノ) 「エコーズ・オブ・サイレンス(1996 Planisphere)」はピアノ・ソロで、これは実にいいのです。メロディアスだけどメロディーに流れ過ぎず、ジャズのピアノ・ソロとしても最も美しいもののの一枚と言って良いのではないでしょうか。半分がオリジナル曲です。この分野ではまずキース・ジャレットが思い浮かぶかもしれません。キースのソロはロマンティックでややセンチメンタルな美しいメロディーを聞かせて人気がありますが、同じリズム、同じフレーズの音を気に入って延々と繰り返す場面もあったり、フリーに近い不協和音を混ぜて来たりもします。馴染まない人にはやかましく感じる種類の、より即興のジャズらしさがあるというのでしょうか。上で触れたフレッド・ハーシュも、情緒的にはメランコリックでもう少し悩みのある感覚が出ており、やはりより難しい音を混ぜる傾向があります。ピエラヌンツィに加えて二人ともジャズ・ピアノとしてはリズムが不均等にはじけるのではなく、クラシック寄りかと思われる拍の真っ直ぐさを聞かせる方ではあるのですが。しかしこのティエリー・ラングの場合はリズム感は良い一方、そうしたいかにも本格ジャズという気負いは感じられません。感傷に溺れたりもしませんが、前述の通りメロディー・ラインはより浮き立つ傾向があり、幾分ニュー・エイジの音のつかみ方、例えば、ウィンダムヒルのジョージ・ウィンストンだとより歌謡的になるにしても、ナラダから出ているマイケル・ジョーンズの中でも安易なメロディぽくはない「シースケープス」(すぐ上の写真/ジャズじゃないので番外編です)あたりに似ているような静謐な美しさがあります。ブルー・ノートとリズム偏重でないきれいなジャズのソロ・ピアノは、環境系/ニューエイジ・ミュージックとの境界がぼやけて来るということです。何だか却って分かりづらいでしょうか。このティエリー・ラング、十分にジャズの即興だし、それでいて、そう感じさせる部分でも濁った音は出しません。
録音年が前後しますが、「ビットウィーン・ア・スマイル・アンド・ティアーズ(1991 Plainisphare)」はプライヴェート・ガーデンの前のアルバムで、あのヒット作と同じ旧トリオによる聞きやすくてお洒落なジャズです。そういう意味ではホテルのラウンジ的というか、外資系企業のコマーシャルのバックにも流れていそうな音楽であり、実際自動車関連のでこれによく似たサウンドのものが使われていたのを聞いた覚えもあります。グルーヴ感のあるベースが心地良く響き、美しくもご機嫌なドライブが楽しめます。メジャー・スケールの洗練されたジャズであり、少し懐かしい感じもして、でも感情的には突っ込み過ぎず、落ち着いた高揚感があります。オリジナル曲は二曲です。
「ザ・ブルー・ピーチ(1994 TCB)」ではビル・エヴァンスの「アフィニティ」で触れたトゥーツ・シールマンスが見事なハーモニカで「マイ・フーリッシュ・ハート」を吹いています。途中にいかにもジャズのトリオ、というインプロヴィゼーションが聞けるナンバーも挟まります。したがってクラシック音楽ファンでリラクシング・ジャズのみをお求めの方にはあまりお薦めではないかもしれません(画像は掲げていません)。
ブルー・ノートから出したアルバム、「ティエリー・ラング(1996 Blue Note)」も甘くなり過ぎないものです。ベースがヘイリ・カンジグに変わりました。スタンダード・ナンバーは二曲、ザ・ブルー・ピーチのとは別の「マイ・フーリッシュ・ハート」が聞け、ビル・エヴァンスとはまた違った大人っぽさです。ラングのオリジナル曲は四曲。「エンジェル・フライ」は弓でベースを弾いてリヴァーブをかけたような音や鳥を模した効果音などが入るものの、これも途中からはジャズです。他にもエヴァンスの曲(Comrade Conrad)もあり、歴史あるジャズのレーベルですからより本格なジャズの演奏になっているわけで、8曲目はタイトルも "Bop Boy" であり、正にバップな味を出してるし(ボブ・ミンツァーの曲だけど、オリジナルは2002年録音?)、最後は「ラウンド・ミッドナイト」です。そういう意味では上記のザ・ブルー・ピーチ同様クラシック耳の人が最初に入るのには向かないかもしれないけど、決して聞き難いものではありません。ブルー・ノートには他にも数枚あるようながら、これについては現在は廃盤で、中古盤探しとなります。
「セレニティ(2013 Universal)」はベースに加えてドラムスも以前とはメンバーが変わったトリオでやっており、一時期のジャズ・ファンが離れた現象の後に回帰して来たものと言えるでしょうか。最初の一曲のみチャーリー・ヘイデンで、残りは全てオリジナル曲です(ベースのカンジグ作一曲を含む)。ECM のクリスタル・サウンドみたいなピアノの導入で始まり、あの洗練された懐かしい感触の旋律が戻って来ました。十分にメロディアスで物語を語るような流れのラインだけど、感傷に陥らず、きれい過ぎる安っぽさや予想できてしまう安直な進行はありません。旧トリオのビットウィーン・ア・スマイル・アンド・ティアーズと同じ路線です。これにも弓を使った鯨の鳴きのような音が使われる幻想的なイントロの「スイス・マウンテン・スメル」といった曲があります。北欧系のジャズで好まれそうなマイナー・スケールの「ウーンズ」は心の傷を意味してそうながら、湿り気はあっても深刻過ぎはしません。
「モーメンツ・イン・タイム(2015 Universal)」も新生トリオによる演奏です。全曲オリジナルで(メンバーの曲含む)、少しブルーな感じで始まります。ドラムのアンディ・プパートはパーカッションとも書かれており、ビブラフォンをはじめ色々な音が聞けます。「モビーディック」では今度は電子音でしょうか、本当に鯨の声を模した音も聞かれます。リリカルで初々しい歌があるタイトル・トラックが聞けたり、前のメンバーとは違った雰囲気のベースが活躍する曲があったり、取っつき難くはないけどジャジーな雰囲気に溢れるナンバーも入っていたり、バランスがいいです。
 Michel Petrucciani Michel Petrucciani ♥♥ Michel Petrucciani (p) Jean-François Jenny-Clark (b) Aldo Romano (ds) ミシェル・ペトルチアーニ / ミシェル・ペトルチアーニ ♥♥ ミシェル・ペトルチアーニ(ピアノ) ジャン=フランソワ・ジェニー・クラーク(ベース)/ アルド・ロマーノ(ドラムス)  Flamingo Stéphan Grappelli / Michel Petrucciani ♥♥ Stéphan Grappelli (vn) Michel Petrucciani (p) Georege Mraz (b) Roy Haynes (ds) フラミンゴ / ステファン・グラッペリ&ミシェル・ペトルチアーニ ♥♥ ステファン・グラッペリ(ヴァイオリン)/ ミシェル・ペトルチアーニ(ピアノ) ジョージ・ムラーツ(ベース)/ ロイ・ヘインズ(ドラムス)  Solo Live Michel Petrucciani ♥♥ Michel Petrucciani (p) ソロ・ライヴ / ミシェル・ペトルチアーニ ♥♥ ミシェル・ペトルチアーニ(ピアノ) ミシェル・ペトルチアーニ(ペトルシアニ:仏)について書くときに、まずその障害のことに触れるのがいいのかどうかは分かりません。でも誰しもが気づくこととして、遺伝的に骨の折れやすい病気があって、写真で見る通り身長が高くありませんでした。この病気では重症度によって長く生きられない人もおり、ペトルチアーニも二十歳までしか生きられないなどと宣告されながら1999年に三十六歳で亡くなっています。イタリア系フランス人の1962年生まれのピアニストで、アメリカでも活躍しました。この人もまたビル・エヴァンスの後継という言葉で片付けてしまうのは当たらない人でしょう。 このピアニストの特徴を言えというなら、誰もが気づく点ながら、まずその強靭なタッチのことが浮かびます。でもすっと鳴り止んで音が澄んでいるので、強い音でもやかましくはありません。この粒立ちの良い打鍵は、後でご紹介するステファノ・ボラーニがジャズ・ ピアニストとしては珍しく力の抜けたタッチで進めるのとは正反対です。リズムを主体にする音楽だからでしょう、元来クラシックのピアニストよりもジャズの人は平均的な打鍵が強い方に寄っている場合が多く、そのせいもあって音色が独特の艶を帯びて聞こえたりもしますが、そんなレベルでもありません。何か命を削るような、と言っていいほどにバラードですらエッジが立っています。もろい骨を心配してこちらが力が入ってしまいますが、これも障害と余命宣告に関連づけていいかどうか、考えさせられてしまいます。 上掲の赤いジャケットの方は、事実上のデビュー(二度目の録音)となる自身の名を冠した1981年のアルバムです。十八歳のときながらもう完璧に仕上がってます。父親の影響で小さいときからあらゆるジャズを暗記してたというのがあるのでしょう。 最初の曲からスピード感溢れるドライブで「あれ、オスカー・ピーターソンか?」と思ってしまいます。それにしてはあの後ろでミーミー歌う声が聞こえないぞ、と。目をつぶって聞いたら白人のピアニストだとは思わないような揺れるリズムと思い切りの良さがあり、とにかく楽しい。思春期の背伸びには縁がないらしく、常に今の瞬間にあって音だけを聞いており、頭に何かを浮かべて弾いたりしないので、次々と鍵盤にきれいな花が咲いて行くようです。上下上下と連続して転がす自在な装飾と透明感のあるコード選択に肯定的な力を感じます。その前向きなところもピーターソンと似た感じです。使うピアノがスタインウェイなのはベーゼンドルファー好みのピーターソンとは違うのですが。でも技巧面以外でそんな比較をする声は聞かないし、むしろビル・エヴァンスを引き合いに出す人が多いようです。果たして似てるでしょうか。ヴィレッジ・ ヴァンガードのライヴなど、エヴァンスを意識してるアルバムですら、自分には別物に聞こえます。暗さや影は感じさせず、いつも力一杯楽しんでいるようです。 そしてこの人、気難しい音で押す仮面も被りません。二つあるオレオの録音ですら、確かに一つはかなり気合いが入ってるものの、もう一つはリラックスしており、現代調にやり過ぎません。後述する「ソロ・ライヴ」の「キャラバン」ではフリーのパーカッシブ奏法みたいな音をダンパー・ペダルを踏んで(足が届かないので専用の機械を使っています)一瞬雷のように出しますが、それすらも選んだ音に聞こえます。ふりをする時間も燃焼し尽くしてたのでしょう、不満を爆発させることがありません。 スローな曲でも泣きやつぶやきはなく、光があります。二曲目の「酒とバラの日々」は聞いたことのない種類の音に思わず熱くなります。くっきりとした強さの美です。また、最後のナンバーなどの気迫で押す曲も含めて、何を聞いてもうるさい音を感じさせません。これも何かになってみせる必要がないことから来る、構えのない音でしょうか。月並みな感想ですが、確かに「命の輝き」かもしれません。 1908年フランス生まれのジャズ・ヴァイオリンの第一人者、ステファン・グラッペリとの共演盤「フラミンゴ(1995)」はメロディ・ラインをヴァイオリンが受け持つので、グラッペリのアルバムのように思うかもしれません。リラックスの種類がいつものペトルチアーニとちょっと違います。写真の嬉しそうな二人は何だろう。グラッペリを初めて聞いてみるのにもうってつけで、甘くジャジーなヴァイオリンが堪能でき、そのタメのある流麗な音の流れに身を任せられる粋な一枚です。時の一瞬のきらめきというのでしょうか、グラッペリはこの二年後に、ペトルチアーニは三年半後に亡くなっています。 ソロについては「100ハーツ」やエリントンの曲を集めたものなどいくつか出ていますが、最後のアルバム「ソロ・ライヴ(1997)」を挙げます。フランクフルトでのライヴです。「ベサメ・ムーチョ」と彼が得意としていたエリントンの「キャラバン」以外はオリジナル曲で構成され、このピアニストの総決算のような CD です。 こうして最初のアルバムと最後のソロを掲げてみたわけですが、これらを聞いて、ああ、と思う方はきっと他も聞かれることでしょう。オリジナル曲ばかりで他の楽器と合わせたもの、シンセを被せたもの、お父さんのギターとやったデュオ、ベースのニールス・ペデルセンとのリラックスしたデュオなどがあり、多様でどれも魅力的です。ちょっと白熱した一枚、「ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」の中の「トラブル」ではピーターソンみたいに転がす装飾を呼吸のように緩めて行って自在です。そして深まりつつ展開するバラードに感動します。同じブルーノートから出たアルバム「ピアニズム」では11分にもなる叙情的な「ザ・プレイヤー」も聞けます。 ジョバンニ・ミラバッシ Giovanni MIrabassi ジョバンニ・ミラバッシといえば YouTube に「ハウルの動く城」を弾いてるのが聞けたりします(「プリマ・オ・ポワ(2005)」という自分のアルバムでも取り上げています)。1970年ペルージャ(イタリアの真ん中、アッシジの近くの町)生まれのピアニストで、そういう曲をやるサービス精神とラブストーリーの俳優のようなルックス、甘く悲しいメロディで特に日本で人気なのだとか。エヴァンスを尊敬してピエラヌンツィに影響を受けたというその音運びはこの曲にぴったりな気がします。生まれはイタリアですが、パリ在住です。カンツォーネやシャンソンではこういう短調の曲が好まれる傾向があり、ミラバッシには実際にクレア・タイーブの歌う「シャンソン・プール・デュマン(明日への歌)/ベルナール・ディメイへのオマージュ(2016)」というシャンソンの伴奏をしているアルバムもあります。完璧なシャンソンです。演奏家としてはジャズの範疇に入るのでしょうが、軽やかで弱いタッチも使い、シャンソンのように助奏が終わると歌になるメロディ志向な曲が多い人で、「アウト・オブ・トラック(2008)」もそうだし、「ライヴ・イン・ジャーマニー(2014)」では、部分的には抽象的な音も混ぜて甘さ控えめのジャズ・アルバムになってはいますが、基本は同じでちょっとイル・ディーヴォのような分かりやすさがあると思います。潜在的に人気要素を持っているのでしょう。また、革命歌ばかり集めたユニークな企画のソロも話題をさらっているようです。因みに「アニメッシ」という国内企画のジブリ・アルバム(アニメ・ソング)もあります。ご本人弁ではナウシカを見て育ったのだとか。この人の音楽が好きな方はピエラヌンツィやヨーロピアン・ジャズ・トリオなども聞いてみられると良いと思います。ミラバッシ、 ちょっとアンニュイできれいなメロディの、素敵なイブニング・ジャズです。  Brad Mehldau Songs: The Art of the Trio, Vol. 3 ♥ Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) ソングス: ジ・アート・オブ・ザ・トリオ Vol. 3 / ブラッド・メルドー ♥ ブラッド・メルドー (ピアノ)/ ラリー・グレナディア(ベース)/ ホルヘ・ロッシ(ドラムス) エヴァンス以降のジャズ・シーンで辛口のジャズ・ファンから最も支持を得ているように見えるのが1970年生まれでニューヨークで学んだピアニスト、ブラッド・メルドーです。フレッド・ハーシュに師事しましたが、影響を受けたピアニストは多岐にわたり、ファンになるかそうでないかの好みが分かれる人でもあると思います。エヴァンスの叙情性を求める人に対しては期待に応える一面もあるにせよ、それだけではないのでジャズ評を書く人からも受けるのでしょう。それは理知的な部分、実験的な好奇心です。大変才能豊かなのだと思います。同じく才人で精神医学の教授でもあるデニー・ザイトリンが自分を客観視する目を持っており、「何にでもなれるよ」とシーンごとにカメレオンのように擬態してしまうのに対して、メルドーは常にこの人らしい音を出すのですが、それが何かはすぐに了解できない複雑さを持っています。また、ロックを取り入れたりクラシックの曲をやったりもするので、そういう箇所を探す楽しみもあるようです。 予備知識なしで初期のアルバムを聞いたときの印象はどうでしょう。コードを意図的に外す音の度合いが多めで、縦(和音構成)ではなく横(時間)方向の音を時々抜く傾向に気づきます。左手は一拍に一つずつポン、ポンと押さえ、それに八分音符で二、三音加えて走り出す動きを見せては止まります。ちょっと不思議な崩しだなと思うかもしれません。そしてそうこうしてるうちに耳に入って来るのは、このピアニストは右手と左手で別の旋律を弾く人だ、という情報です。あるプレイヤーの方は「頭の中がデュアル・コア・チップなんじゃない」と言ってました。そうなのか、と思ってもう少し後のアルバムを聞いてみると確かにそうなっている。再度初期のものに戻って聞き直すと、崩しと感じてたものが今度は二旋律の萌芽に聞こえてきます: 右が旋律を弾いているときに左は夢遊病のように歩き回っている。最初それは伴奏が時々展開してるな、ぐらいの印象だったのに、実は左手が次第に自由度を獲得して旋律へと進化して行く過程だったのです。そして低音と高音が交互に進行するように聞こえて来て、ああそうだったのか、両方をオーバーラップさせて行くと右手と左手が別の旋律を弾いてることになるんだ、という理解に至ります。あるいはまだこの時の段階では弾き方の無意識な癖に過ぎず、後に意識して完成させて行ったのかもしれないけど、初期とその後のアルバムとはつながっていたと気づくのです。 演奏時期の特徴を二旋律技法の観点ではなく、表情の変化という面で捉えるなら、初期のアルバムには普通のメロディ進行の聞きやすい曲があるけれども、後の方になってくるとそれが無くなり、より複雑で抽象的な展開になると言えるでしょう。音を具体的に言うのは難しいのですが、静かなところでも上昇音の最後に半音下げて曇り空を生み出したり、ときに雨降りの鉛色の空のような音を出したりします。雨降りも美しいながら、それが好みなのか、ありきたりのコードを避けているのかは分かりません。そのコードの選択も、基本の四和音で言うなら CM7 などの明るい方ではなく、フラットにずらした音を含む濁りを持った音、これは単なる印象に過ぎないのですが、例えばマイナー・メジャー・セブンス、ハーフ・ディミニッシュト・セブンス、ディミニッシュト・セブンスのような甘さ控え目を好むようです。あるいはもっと隣り合った音を含んだものでしょうか。メロディ側も迷走するように不協和音へ一瞬走り込んだりします。クラシックで喩えるなら十二音技法に入りかけた曲が少々、でも多くは新ウィーン楽派までは行かない近現代のマックス・レーガーかバルトークぐらいまでか、といった感じです。ビル・エヴァンスがそう評されるような印象派風ではないし、それでもドビュッシーで言うならより前衛的になった曲に近いでしょうか。ところが、歌う段になると案外これが素直な感性の持ち主なのかなとも思ったりもします。つまり土台のメロディ感覚が風変わりなのではなく、プロフェッショナルな改造が色々施されている感じです。こうした傾向は初ソロ・ピアノの「エレジャイアク・サイクル」あたりから後、この人が高い評価をされてきた99年から2000年頃にはすでに顕著な気がします。 順を追って見てみましょう。デビュー・アルバム「イントロデューシング・ブラッド・メルドー(1995)」は最初にしてちょっと頑張った印象があるかもしれません。「マイ・ロマンス」一曲はちょっとエヴァンスの静かなときに似ています。エヴァンス風も示しておいて、そこからもっと新しいことをやりますよ、という宣言なのかもしれません。でも右手と左手が別旋律を奏でるというところまでは行きません。 その後に出した「アート・オブ・ザ・トリオ」という五つのアリバム・シリーズの Vol.1(1996)ではより聞きやすくなり、「ブレイム・イット・オン・マイ・ユース」と「アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥ・イージリー」は美しい旋律が聞けるナンバーです。Vol.2(1997) はかのヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴなので、「ムーン・リヴァー」と「ヤング・アンド・フーリッシュ」を除いては張り切ってアグレッシブになっているようです。 Vol.3(1998)が今回カヴァー写真を掲げたお薦めの一枚です。ここでまたいったん大変聞きやすい和音に戻り、CD として最初から最後までリラックスして聞いていられます。特に「エグジット・ミュージック・ フォー・ア・フィルム」、「フォー・オール・ウィー・ノウ」、「ヤング・アット・ハート」は美しいバラードです。 とはいってもこのアルバム、右手と左手が別旋律を描く技法を初めてはっきり打ち出してきた一枚でもあるのです。凝った仕掛けが施してあってなお、クラシック愛好家の方にも薦められます。あるいはこれに前述の Vol.1 も加えていいかもしれません。これら二つはブラッド・メルドーのものとしては珍しくメロウなバラード集の雰囲気を持つ CD です。 そしてこの後には、このピアニストが評論家を含めて演奏者にまで高く評価されることになる、試みの時代がやって来ます。人気のある Vol.4 (1999)は再度ヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴ。よりエネルギッシュに大きな技に挑戦してるような印象です。それからこの人の頂点のように言われる「プレイスィズ(2000)」や「ラーゴ(2002)」、「エニシング・ゴーズ(2002)」、「ハウス・オン・ヒル(2002)」などが出て来るのです。「プレイスィズ」は旅行した各地の印象スケッチという形をとったアルバムで、これに関しては甘い音ではないけれどもきれいだと思う瞬間があります。 しかし右手と左手が別の旋律を奏でるから凄いという例の話は、正直よく分かりません。そうなってることは理解できます。流れる時間の中で拍の取り方やコード選択を次々と処理して行くジャズ・プレイヤーの間では「できる、できない」の差が出ます。現代音楽のように「分かる、分からない」の話になってきて、そうなると素人にはその場で何が起こってるのかすら了解できないのです。したがって演奏者に尊敬される種類の演奏者を素人が論じる場合には、常に危うさがつきまといます。感覚で聞く鑑賞者にとっては、二つの旋律を合わせるというアイディアも、エヴァンスが二つの拍子を混ぜるというのと同じで、あまり興味の湧かない試みのように思えることでしょう。レニー・トリスターノの左手がベースの真似をする曲、「ビカミング」や「デリバレイション」、「G マイナー・コンプレックス」あたりが先駆になるのかもしれませんが、メルドーのそういうアルバムを聞くと、ポリフォニックな調和ではなくて、コントラストを生み出す狙いがあるように聞こえます。それはラヴェルがヴァイオリン・ソナタで試みた声部の対比とやや似た感覚です。 余分な説明に突っ込んでしまいましたが、このままでは言葉足らずなので補足しますと、バッハなどのポリフォニー(対位法)は右手と左手のうち片方が主でもう一方が従という関係ではなく、別々に同じ形で動いてハーモニーを成しているのですが、ラヴェルのソナタは二つの楽器に時間差でお互いを模倣させつつ絡み付かせることで、却って両者の相容れない性質を強調する意図で書かれたものでした。ブラッド・メルドーの右手と左手が別々の旋律を弾くという試みは、アート・オブ・ザ・トリオ Vol.3 ではまだ両手がハーモニーを形成してますが、より後の作品ではなんというか、本能的衝動から一緒になってはみたものの気が合わなかった夫婦のように聞こえたりもします。北欧の人みたいに別々に行動してても愛し合ってるのかもしれませんが。そしてメルドーが凄いと言われることの中身は、それをラヴェルのように二つの楽器が別々に弾くのではなく、一人のピアノでやってみせることでしょう。しかもジャズは即興だからなお大変なのです。前もってある程度は頭の中で組み立ててはあるのだろうけど、作曲家が時間をかけて楽譜に書き込むのとはわけが違います。ただ、聞いて心地良いかどうかは別の話であり、人によって異なる気もします。「お洒落」な音の正体であるジャズの四和音やテンションは必須のスパイスですが、二旋律技法はどうでしょう。でもやっぱりここは大いに感心しておくべきなのでしょう。
「10イヤーズ・ソロ・ライヴ(2004−2014)」四枚組では「アイム・オールド・ファッションド」や「メディテーション」シリーズのような静かな曲もあるながら、左手で同じ和音を小刻みに叩き続けているところもあり、そんなときはずっと音が鳴り続けてる気がします。キース・ジャレットとは根本的に違うピ アニストだという意見もあるようですが、その部分では近いものを感じました。 さらに、クラシックを取り込んだものもあります。ブラームスの間奏曲を弾いてますし(上記「10イヤーズ・ソロ・ライヴ」)、「ラヴ・サブライム (2006)」ではメルドー作曲のコンテンポラリー・クラシカルのような歌曲をソプラノ歌手リニー・フレミングが歌っています。「ラヴ・ソングス (2010)」はアンネ・ゾフィー・フォン・オッターとの共演で、「アフター・バック(バッハ/2018)」はバッハを弾いておいて変奏をかけて行くものです。そのジャケットはリチャード・エガーのブランデンブルク協奏曲のような螺旋階段の図柄になってます。 一方で編曲者としての才能を発揮しているアルバムもあり、「ハイウェイ・ライダー(2009)」では最初に管が出て来るとエバーハルト・ウェーバーの編曲ものかと思ったり、声やシンセが出てくるとパット・メセニーの一人オーケストラかと思ったりもしました。フレッド・ハーシュの多様なやり方と比べるのも面白いでしょう。 さて、最後に主観的な印象ですが、ブラッド・メルドーは明晰な人なのだろうと思います。数学的に物事を捉える力があり、細かな設計図が頭に入っている職人のようです。完成度の高い形を追求し、作り上げるものはときに騙し絵のように巧緻であり、あるいは他の作品への喩えが仕掛けられた文学のようです。人々にどう受けとめられるかを察し、表現の技術も頭脳に見合って高いレベルです。きれいだから音楽を聞く、という聞き方ではこの人の真価を半分も理解できないかもしれません。きれいではあっても、それは感性というよりも設計の美です。音楽に乗ることが好きでピアノを弾いているのかといえば、もちろん楽しんでいるでしょう。でもどう作るかにより熱中してるのかもしれません。そういう意欲的な音作りなしではアーティストとして出て来られないから自分探しをしているという苦労もあるでしょう。ただ、自分としては実験的な野心は苦手だし、天才の音楽は理解力を超えています。現代ジャズの牽引者、ブラッド・メルドーは間違いなく天才なのです。  Blue Bird - Music for the Film Concert Michel Bisceglia ♥ Michel Bisceglia (p) Werner Lauscher (b) Marc Lehan (ds) ブルー・バード ー フィルム・コンサートのための音楽 / ミシェル・ビスチェリア(ビシェリア)♥ ミシェル・ビスチェリア(ピアノ)/ ワーナー・ラウシャー(ベース)/ マーク・ルハン(ドラムス) キース・ジャレットからブラッド・メルドーまで、ほとんどのジャズマンがいわゆる難しい音を混ぜたがるものですが、それが比較的少なく、全くないアルバムもある人です。1970年生まれのベルギーのピアニストにして作曲家、ミシェル・ビスチェリア。日本の著名な評論家の方が「パイゼル・ミウ Paisellu Miu」を紹介されて日本で成功したのですが、それはカンツォーネに分類されるのでしょうか、ロッコ・グラナータという、ビスチェリアと同じくイタリア生まれでベルギー国籍の歌手がカラブリア方言で歌う同名の曲がまずあって、編曲をしていたのがビスチェリア本人だったということで、自身のアルバムでも取り上げたようです。歌の方の演奏で参加していたハーモニカのトゥーツ・シールマンスは「イタリアのブルース」と呼びました。短音階の調べは世界中の民謡に共通しています。日本では、童謡「赤い靴」から古賀政男を経て、阿久悠が活躍した頃までの歌謡界の哀しい系サウンド、あれに近しい感性を持っていると言えるでしょう。アルバム「インナー・ユー(2006)」を聞いてみてください。 ミシェル・ビスチェリアの代表盤が何かはよく分かりません。スタンダード・ナンバーが聞けるアルバム「ザ・ナイト・アンド・ザ・ミュージック(2004)」は意外性はないかもしれませんが、聞きやすくて良いと思います。正統なジャズの演奏もたくさんやっており、「ミシェル・ビスチェリア・20イヤーズ・レコーディングス(2017)」はコンピレーション・アルバムで、彼の色々な面をバランス良く網羅しています。前述の「パイゼル・ミウ」も入っています。 他にこの人らしいものでは、彼が手がけた映画のための音楽「ブルー・バード(2015)」があります。サティのように静かにポツンポツンと間をとってピアノが鳴らされ、正にブルーなマイナー・キーで進んで行く美しいトリオ演奏です。「パイゼル・ミウ」のように歌の感傷には傾かず、その静寂は特筆に値します。騒々しいジャズが嫌いな人にとっての一服の清涼剤でしょう。あらゆるジャズ・アルバムの中で最も静かな一枚かもしれません。そしてこの人の中で最もオリジナリティを感じたものでもあります。  Stefano Bolani Stone in the Water ♥ Stefano Bolani (p) Jesper Bodilsen (b) Morten Lund (ds) ストーン・イン・ザ・ウォーター / ステファノ・ボラーニ ♥ ステファノ・ボラーニ(ピアノ)/ イェスパー・ボディルセン(ベース)/ モルテン・ルンド(ドラムス) マイナー・スケールのメロディの性質を「泣き、感傷、自己憐憫、耽溺」などと言えば、ネガティヴな含みを持たせているように聞こえます。「演歌のようだ、民謡みたい」ならそれ自体ニュートラルだけど、ジャズの形容だとどうでしょう。しかし予想のつけやすい展開の嘆きの旋律は人間にとっての血液のようなものですから、「ゴッドファーザーのテーマみたいな親しみのある短調」と言っておけばよいでしょう。今まで見て来たエヴァンス後のピアニストの中にはイタリア系が五人登場しました。エンリコ・ピエラヌンツィ、アラン・パスクァ、ミシェル・ペトルチアーニ、ジョバンニ・ミラバッシ、ミシェル・ビスチェリア。それに加えてこのステファノ・ボラーニで六人目です。ボラーニは1972年ミラノ生まれのピアニストですが、これら六人の中で歌の国イタリア人の面目躍如、とはならず、前述の方向へも流れないのは二人。ペトルチアーニとこのステファノ・ボラーニだけです。でも方法論が違います。ペトルチアーニは常に今この瞬間にいて振り返らないので、その光をもって泣きを超越します。一方でボラーニはそもそも典型的な短音階に陥りません。ちょっと不思議な音の運びなのです。何かの元旋律に髭を生やした改造ではなく、独特の音の世界を構築します。わずかに現代調の地球外和音に入りかけて一呼吸でやめておくようなところもありますが、 旋律の流れも選択するコードも浮遊感があってきれいです。それが自然なバランスでこの人の言葉になっているので、単純な旋律をいじっただけには聞こえないのです。懐かしく、既視感に驚くような、高い所から俯瞰するような静けさで、大変魅力的です。普通の意味で叙情的というのとは違うけど、十分に有機的です。一瞬の北欧情緒だったりラテンの穏やかな影だったりもします。実際のコードで言わずに表現するのはなんと難しいことでしょう。とにかく味わってみてください。 そして何よりの特徴は、ジャズ・ピアニストには珍しいことながら、力の抜けた静かなタッチが前面に出ることです。クラシックのピアニストのようだという意味ではピエラヌンツィも同じですが、ボラーニは拍の問題ではなく、タッチがほんとに静かなのです。加えてやわらかく歌うような抑揚で弾きます。これは彼がクラシックの曲をやるとき、ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」においても同じでした。音の選び方も含めてすべてにおいて騒がないクールな目線。ある種枯れたというか、ロマンチストではない醒めた感覚から来るのかもしれません。 特にそのクールな美しい空気感がよく味わえるのは ECM から出ている CD でしょう。まるでアイヒャーの期待に応えているかのように聞こえるかもしれないけど、元々彼の中にあるものだと思います。そのピアノを認めたエンリコ・ラヴァ名義の「タチ(2004)」も渋いトランペットが静かに吹かれていいですが、後半でちょっとフリーっぽい音も出ます(不思議と美しく感じます)。ちょっと言い忘れましたが、上記のような特徴の他に、この人はフリー・ジャズっぽい運びとラテンの香りの引き出しも持っています。ブラジル人とやっているものもあります。有名なボサノヴァの歌手、カエタノ・ヴェローゾの出て来るのもあるし、むしろ最近はそちらの路線が本業でしょうか。 選んだ CD は「ストーン・イン・ザ・ウォーター(2009)」。すでに曲調の説明はしているので付け加えることはないですが、このアルバムにはエネルギッシュなフリー系の曲がなく、複雑な音が出ても聞きやすいので通しで心地良くいられます。 ソロも出ています。「ピアノ・ソロ(2005)」です。この人の音の感覚がよく分かると思います。「インプロヴィゼーション」というシリーズものの曲では難解な音も駆使します。 ブラジル人のマンドリン奏者とやった「オ・ケ・セラ (2012)」は二曲目でフリーっぽい音が出ますが、ファドのような哀愁系のものも聞けるブラジル音楽となっています。最近の ECM では「ジョイ・イン・スパイト・オブ・エヴリシング(2013)」もあり、やはりラテンっぽい乗りのいい曲が聞けます。二、三、五、六、九曲目はフリー・ ジャズのフレーバーがあります。ベース、ドラムにテナー・サックス、ギターを加えたボラーニの曲によるアルバムです。ECM 以外でもラテン系の音楽は出しています。  January Marcin Wasilewski Trio ♥♥ Marcin Wasilewski (p) Slawomir Kurkiewicz (b) Michal Miskiewicz (ds) ジャニュアリー / マルチン・ボシレフスキ・トリオ ♥♥ マルチン・ボシレフスキ(ピアノ/ヴァシレフスキ) スワヴォミル・クルキエヴィッツ(ベース)/ ミハウ・ミスキエヴィッツ(ドラムス) ポスト・ビル・エヴァンスとは言わないけど、印象派にも近い音の選び方の美しさにおいてエヴァンス以後のピアニストの中で最も気に入った一人は、上記ティエリー・ラングもよかったけれども、マルチン・ボシレフスキ(発音はヴァシレフスキが近い)かもしれません。今まで取り上げて来た人たちの中では最も若い世代である1975年ポーランド生まれです。出て来た頃はアイヒャー好み路線か癒し系の一人ぐらいに思われてジャズの昔からのファンにはあまり注目されてなかったような気もするけれど、最近は世界的に正統のジャズとしても高い評価を受けているようです。何が気に入ったといって、センスがいいのです。曖昧な話だけど、コードの選び方も、導入するメロディの感覚もです。具体的に説明するのは難しいので深入りはしない方がいいにせよ、たとえ簡単なメロディーひとつでもコンピューターにいいものが作れないように、美を要素に分解して合成するのではなく、創造的なプラスの何かがないと曲作りはだめなのでしょう。少なくとも言えるのは、センチメンタルなありきたりの歌にはなりません。セブンスをきれいに使います。よくあるラドミソシ、みたいな音がクリアに響くだけでぞくっと来ます。加えて独特の静けさがあります。その点については一つ前のステファノ・ボラーニと何が違うんだという話だけど、もし比べるなら、ラテンになってるとき以外はボラーニの方が少し暗めで割り切れないような、幾分醒めた音を出す傾向があるでしょうか。ボシレフスキはもっと透明で、協和音に寄っています。 もっと言うなら、音に間があります。特に最初の二枚ぐらいは全体に力が抜けており、ゆったりと進んで静謐さに満たされています。そしてペール・カラーの響きというのか、感覚的に言えばわずかにブルー・グリーンがかったモノトーンの静けさの中で鮮やかな花が開いて行くように、叙情的なフレーズが現れて来ます。起伏のある構成も見事です。キース・ジャレットに憧れてこの道に入ったという人ながら、ジャレット風というよりも、ECM 的と言われても仕方はないかもしれません。アイヒャー(ECM の創立者)に見出されて有名になったわけだし、ボシレフスキ本人も ECM のレコードは好きで全部集めて来たと言ってるぐらいです。でも媚びてレーベルに合わせるのではなく、彼なりに活動して来てアイヒャーに気に入られたのでしょう。その後のぶれない活躍を見れば分かると思います。以前は「シンプル・アコースティック・トリオ」として活躍しており、後になるほど洗練されては来るものの、基本的にスタイルは同じです。その創立メンバーを変えず、ECM レーベルから出すようになってから自身の名を冠したトリオに名義変更しました。どのアルバムも魅力的ですが、順を追って少し見ます。 ECM の最初のアルバム、「トリオ(2004)」はメロディ・ラインをくっきり出すことには慎重ですが、断片化された美しい響きに満ちています。ジャズの環境音楽的な一枚とは言えるかもしれません。この中ではっきりとしたメロディーの線を持つ曲は「シスターズ・ソング」ぐらいでしょうか。一曲目の「トリオ・カンバセーション」の最初の音から ECM のクールな空気感に浸されます。その短い導入を経て二曲目「ハイパー・バラッド」に入りますが、旋律こそキャッチーではないものの美しいバラードです。「ドラム・キック」以降の三曲はフリーの要素を持った不協和な音が出ます。こういうのは現代のジャズマンにとって、他できれいなメロディを出してもヨーロピアン・ジャズ・トリオ的な路線だと思われないための保険、もしくは税金みたいなものかもしれません。また、一音間違えても誰も気づかない曲はどれも同じに聞こえるにせよ、そこから調性が戻って来たりすると、悪い男がやさしかったみたいに情にほだされます。「エントロピー」は題からするとフリー路線かと思いますが、ポスト印象派ぐらいの不思議な和音を連発しつつも美しい曲です。最後は「トリオ・カンバセーション」に戻り、軽く不思議な終わり方をします。 二枚目のアルバム、「ジャニュアリー(2007)」が上に写真を掲げたものです。「トリオ」よりも全体に美しいメロディーが出て来るようになりつつ、静けさという点では同様であり、聞き難い曲が少ないので取り上げました。他のアルバムもすべて♡♡を付けて出したいところですが、エヴァンスの叙情性を求める人に向けてという意味でこのようにしました。 叙情的なスロー・ナンバー「ザ・ファースト・タッチ」の静かな低音で始まります。映画音楽のアレンジかと思わせるムードだけど、ボシレフスキの曲です。 次はゲーリー・ピーコックの「ヴィニエット」ですが、これは聞いたことがあるかもしれません。ピーコック名義の売れたアルバム「テイルズ・オブ・アナザー」に入ってました。スタンダード・トリオと同じメンバーなのでキース・ジャレットの曲という印象があるかもしれません。ほの暗い情動を抑えたような叙情性が感じられます。 「シネマ・パラディーゾ」は映画「ニュー・シネマ・パラダイス」の主題曲。エンニオ・モリコーネですが、センス良くまとめています。 「ダイアモンズ・アンド・パールズ」はプリンスの曲で、またまた洗練された音の運びです。 「バラディナ」はポーランドのジャズ・トランペッターの曲で、ボシレフスキは94年に彼のセッションに参加しています。途中でジャズらしい展開をして一瞬無調っぽい音も出ますが、概ねバップの盛り上がりの範囲内であり、メロディアスではないにしても全体にはきれいな曲だと言えます。 五曲目の「キング・コーン」はカーラ・ブレイです。この曲だけは頑張った前衛っぽいナンバーです。キース・ジャレットもよくこういう音遣いをしてました。 ベース・ソロで始まる「ザ・キャット」は再びボシレフスキのオリジナル。わずかに複雑な音を混ぜますが、抑えてクールに進行します。 表題曲の「ジャニュアリー」もオリジナルで、ジャケット写真のような暗い幻想的な雰囲気のある曲です。写真は一瞬原発に見えてしまいましたが、そんなわけはありません。後ろでベースが絡み、ピアノが時々高いきれいな音を出して、不思議な美を醸し出します。吐く息が白くなるような、正に ECM 的な音です。静かに消えて行きます。 中テンポで流れて行く「ザ・ヤング・アンド・シネマ」もオリジナルで、ラストはトリオ三人の名義になっている短いエンディング「ニューヨーク2007」。これは録音場所と年でしょうか。 三枚目は「フェイスフル(2010)」で、前作までと変わらない波長ながら、ここへ来て若干力強さが増したかなという印象です。次作もそうなのですが、時期によってトリオがこう変化しているのか、アルバムの個々の出来なのかは分かりません。力強いといっても美しい叙情的なナンバーには変わりがありません。ただそんな中でもメロディが前面に出るものは少なく、「アン・デン・クライネン・ラディオアパラート」と「バラード・オブ・ザ・サッド・ヤング・マン」の二曲ぐらいでしょうか。スロー・ナンバーでも起伏のある旋律はあまり形成しない傾向です。 前者は一曲目に来るものです、スティングを聞かれる方にはお馴染みでしょう、アルバム「ナッシング・ライク・ザ・サン」の中の最後の曲で、ハンス・アイスラー作です。スティングでは「ザ・シークレット・マリッジ」というタイトルになっていました。ここではこのバンドらしい美の世界です。 二曲目の「ナイト・トレイン・トゥ・ユー」は短いフレーズをループにして繰り返しながら即興を展開して行き、途中で燃え上がる意欲的な曲です。彼らにしては静的な美の追求よりはエネルギッシュな方へ振ったジャズらしいものです。ジャズ・ファンは必聴だけど、メロディアスなのが好きな人は飛ばしていいでしょう。 タイトル曲「フェイスフル」はオーネット・コールマンからのものです。でもフリー・ジャズとして有名な人だからと恐れるには足りません。これも美しいです。 「バラード・オブ・ザ・サッド・ヤング・マン」はサッドと言っても全編マイナー・キーではなく、時々影が差すけれども憧れるようなバラードです。 「オズ・ギゾス」、「ウォーク・アップ・イン・ザ・デザート」、「ルガノ・レイク」もスロー・ナンバーながら、全体に陰ったやや暗めのトーンです。しかしキース・ジャレットのように理解を求めて訴えて来る性質ではありません。 「ビッグ・フット」ははっきり前衛的で、「モザイク」もメロディ展開はしません。これら二曲は演奏者側の論理としては面白く、硬派なジャズ・ファンからも受けると思います。 その後スウェーデンのサックス奏者ヨアキム・ミルダーが加わった「スパーク・オブ・ライフ(2014)」が出ました。サックスが入るとまた趣が変わるもので、こちらはちょっとマイナー調の複雑な音に満ちたアルバムとなりました。 懐かしいような音で始まるオープニングの 「オースティン」にははっきりしたメロディがありますが、ここだけは今までの路線、ピアノ・トリオの演奏です。その後「スドヴィアン・ダンス」でサックスが登場し、ちょっと哀愁系の渋い曲となります。タイトル曲の「スパーク・オブ・ライフ」もその流れで、泣きのサックスが静かに歌います。その後も全体にこうしたトーンでまとまっている気がします。メジャーともマイナーともつかないコードの往復でどっちへ展開するか分からず、きれいだけどメロディを読ませない作りの「スリー・リフレクションズ」、少しブルージーでスローな「スリープ・セイフ・アンド・ウォーム」などです。 一方で「メッセージ・イン・ア・ボトル」は繰り返しで構成される暗い音が展開し、ちょっとしたメロディに発展するマイナー・キーのバップな曲です。秘めた力で進む「スティル」もジャズの硬派なファンが好きそうだけど、フリー・ジャズではありません。「アクチュアル・プルーフ」になると、これもテクニカルなナンバーながらアナーキーな音が加わり、ジャズらしい目の詰んだ即興を聞かせます。こうした高エネルギーな曲はジャズのバンドがこの先の時代を乗り切るために必要でしょう。面白いのは5、60年代に完成された技法をジャズの基本として、それを上手く再現できることを見せるのが21世紀になっても必須だということです。カテゴリーとして完成されているのです。 2016年に録音された「ライヴ」がその後出ましたが、そちらは一曲を除いて「スパーク・オブ・ライフ」からのナンバーで、その一曲というのは一つ前の「フェイスフル」からの「ナイト・トレイン・トゥ・ユー」です。 そしてこの記事に書き加える形になりますが、6作目で2019年録音の「アークティック・リフ Arctic Riff」と7作目で同じく2019年録音ながら発売はその一年後になった「アン・アタンダン En Attendant」も出ました。前者はテナー・サックスのジョー・ロヴァーノの加わったアルバムです。その個性と楽器の特徴も表れて本格的な即興を楽しむ曲が多く、いわゆるジャズ好きの人向けと言えるので、メロディアスな路線を期待する人には厳しいかもしれません。一方で「アークティック・リフ」の方はトリオによる演奏で、本格もあるけどこの人たち独特の美を堪能できるものとなっています。メンバー三人による「イン・モーション」という三部作の曲があり、ボシレフスキーらしいセンスの「グリマー・オブ・ホープ」があり、カーラ・ブレイとドアーズの曲がそれぞれ一曲ずつ、そしてバッハのゴールドベルク変奏曲の第25変奏も聞けます。短調の静かなやつです。バッハの提示の部分もいいけど、即興の展開部分の見事さを聞いてほしいと思います。
マルチン・ボシレフスキ、冒頭でエヴァンス以降で大変注目の人、というようなことを言いました。本道のジャズとしての評価も高くなって来ているピアニストとそのトリオなので、カクテル・アルバムのように聞きたいなら全アルバムからメロディアスなナンバーだけ選って来ないといけないし、そういうのもどうかとは思うのですが、クラシック好きにも是非挑戦してみてほしいジャズだと思います。
 Orange City European Jazz Trio ♥♥ Karel Boehlee (p) Frans van der Hoeven (b) Roy Dackus (ds) オレンジ・シティ / ヨーロピアン・ジャズ・トリオ ♥♥ カレル・ボエリー(ピアノ)/フランス・ホーバン(ベース)/ロイ・ダッカス(ドラムス) ついに今度は、今まであまりよろしくない意味合いで何度も引き合いに出してしまって申し訳なかったヨーロピアン・ジャズ・トリオです。悪気があったわけではなくて、巷にはそういう声があるからなのです。「クラシックの名曲からポップスのヒット曲、日本の歌まで、何でもこなすオランダの量産トリオ」みたいに紹介されます。メロディー路線で口当たりのいいカクテル・ジャズのように思われていて、かつてのケニー・ドリューの地位を引き継ぐような扱われ方でしょうか。本格ジャズ・ファンを自認する方や評論家方面には認めない発言をされることもしばしば。両者とも特に日本で人気がありましたが、実際そのようにプロモートされて来ており、ヨーロピアン・ジャズ・トリオの方は日本向け企画で成功しました。でもプロモーターが音を生み出したわけではありません。オランダの人たちですが、元々ちゃんとしたジャズ・ミュージシャンなのです。ちゃんとしたと言うこと自体失礼でしょう。別段イージー・リスニング用の甘い感性で出て来る人種とかがいるわけではないということです。どんな世界でもそうだけど、有名になるには色々な力学が作用するもので、一般の人が何となく「実力」という言葉で信じてることもそれほど単純なものではないはずです。このトリオの初代ピアニストはカレル・ボエリーという1960年生まれのオランダ人です。ここで二度ほど名前を出したハーモニカの名手、トゥーツ・シールマンスの晩年の伴奏者でもあります。そして残りのメンバーはこのトリオとは別でしたが、最初の頃のアルバムに 「スイッチ(1984/邦題はミスティ)」というのがあり、聞いてみるとストレートなジャズです。名義は「トリオ・カレル・ボエリー」となっています。メロディばかり分かりやすく追いかけてるわけではなく、各パートのソロが即興を繰り広げるところあり、エネルギッシュにバップしてるパートありで、スピード感溢れる運びからスローまでメリハリがあります。"J.E.S.T. " なんていかがでしょう、これぐらい弾けるもんなら悪口も言ってみれば、という感じです。レーベルはオランダのタイムレス。詳しい事情は知りませんが、これに目をつけて日本向けに企画し直したのが初代メンバーによる「ヨーロピアン・ジャズ・トリオ」のようで、結成は1988年です。その後続々と今はなき日本のレーベル、アルファ・ジャズからアルバム・リリースが続いて人気を獲得して行ったのです。だからオランダ生まれの日本育ちですが、仮に批判する人たちがこのミュージシャンたち自身を槍玉に上げているわけではなく、パッケージが気に入らないんだという話にせよ、それによって売れたんですからそれも縁なのでしょう。ご本人たちも日本の聴衆には感謝してるのかもしれません。 初代のピアニストは1995年に二代目のマーク・ヴァン・ローンに代わり、トリオは現在まで活動を続けています。残りのメンバーは同じです。新しいピアニストは1967年ハーグ生まれの同じくオランダの人で、初代の方が好きという声もあるようながら、よくその精神を受け継いでいて能力もセンスも同等な気がします。アンダンテぐらいの中程度のテンポでボサノヴァの運びのように流して行く曲が多いので、間を長くは空けないところも二人はそっくりです。 でもまずは初代のピアノによるアルバムで一番良かったと思うものを取り上げます。「オレンジ・シティ(1989)」です。半分近くがオリジナル曲です。「スイッチ」と同じオランダのタイムレスからのリリースですが、実はそれは焼き直しで、元は日本のアルファ・レコーズが出した「スウェーデンの城 (Chateau En Suede)」です。このトリオ名での二作目になります。因みに最初のアルバムは「ノルウェーの森(Norwegian Wood 1989)」で、小説でも有名なタイトルながらビートルズの曲からとったものなので、とりあえず関係ありません。さて、その「オレンジ・シティ」だけど、日本盤の「スウェーデンの城」とは曲順が違います。「ネイチャー・ボーイ」も入ってません。でも配列センスがこちらの方が個人的には好きです。日本盤は「エリノア・リグビー」で始まります。これが一番と言う方もいらっしゃるメロディアスな曲です。それとか日本盤タイトル曲である「スウェーデンの城」などの、旋律のくっきりしたものの方が日本の人には受けやすいのでしょう。オランダ盤の方はこのピアニストの性質がよく分かるオリジナル、「オレンジ・シティ」が一曲目で、ベタに歌を狙わない粋な曲です。ここにもエリノア・リグビーのモチーフが入っているように聞こえるけど、まあ、どちらでもいいでしょう。どっちにせよこれらのアルバム、最初から最後まで安っぽくならず、洗練された美しい曲揃いで惚れぼれします。ティエリー・ラングの「プライヴェート・ガーデン」のセンスにちょっと似てるでしょうか。いや、それと似てるのはむしろ後述の二代目、マーク・ヴァン・ローンの方でしょうか。 具体的な中身ですが、デイヴ・グルーシンのソロみたいな「マイ・シップ」もいいし、「ホワット・ザ・ヘック」もタイトでクール。「ユー・ドント・ノー・ホワット・ラヴ・イズ」 はブルージーでいい雰囲気が出てます。「ジェントル・ブレイン」や「パッセージ・オブ・ジャコ」は静かで美しいです。同じくきれいなメロディで始まる「ビュー ティフル・ラヴ」は崩しと展開がすごい。このバンドを敬遠する人にも是非聞いていただきたい出来なので、判官びいきでブーストしたと思われても ♡♡ とします。 このピアニストとアルバムの雰囲気が好きなら、次の「バル セロナの炎(1990)」もいいかもしれません。やはり半分ほどがオリジナル曲です。さらにその後のディズニーものを集めた「ビューティ・アンド・ザ・ ビースト(1992)」は廃盤のようです。 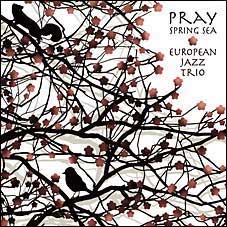 Pray / Spring Sea European Jazz Trio ♥♥ Marc van Roon (p) Frans van Der Hoeven (b) Roy Dackus (ds) 祈り〜春の海 / ヨーロピアン・ジャズ・トリオ ♥♥ マーク・ヴァン・ローン(ピアノ)/フランス・ホーバン(ベース)/ロイ・ダッカス(ドラムス) 二代目のマーク・ヴァン・ローンのピアノによるものも一枚。確かにこのバンド、メロディをサービスしてくれ過ぎなところも盤によってはあります。レコード会社の意向なので仕方ありません。でもクールなのもあるのです。「祈り〜春の海(Pray / Spring Sea2012)」です。日本向けのタイトルですが、2009年には「ジャパネスク」という日本の曲ばかり集めたアルバムを出したばかりでした。そちらはサービス精神満載のかなり聞きやすい路線のもので、横道に逸れますが「花」とか「いとしのエリー」なんかも入っていました。「花」や「この街」みたいな沖縄の音楽は、ドミファソシドの音階に乗せて「なんくるないさー」と、人生のはかない真実を静かに歌われると沁みます。サザンの「いとしのエリー」は海外の人も取り上げやすい音階なんでしょう、レイ・チャールズの日本盤ボーナストラックにも入っていて(ラスト・アルバム「ジーニアス・ラヴズ・カンパニー」 2003-04)、「これってブルースだった?」という感じでした。桑田さんってメロディ・メーカーです。 一方でこの「祈り」ですが、震災の翌年ですし、タイトルからしてもそういう意味なのでしょう。レコード会社の意向が少し緩んでいるのかどうか、最初の「プレイ」の複雑にして美しい進行からして安易な方に向かいません。オリジナル曲なので、ピアニストの性質も分かります。誰もが知ってる「四季」の冬の第二楽章を意外な運びで聞かせるところ、ラテン・フュージョンのリズムかというアルハンブラの思い出も渋いです。お正月の琴の名曲「春の海」も取り上げてますが、曲の構造を良く知って途中から展開させていてクリエイティブです。緩急があって安っぽいメロディーに堕しないのです。「イースト・オブ・ザ・サン」も本格でしょう。十分ジャズだと思うんですが。スティングの名曲「フィールズ・オブ・ゴールド」もやってくれ、「ミッドナイト・サン」は半音ずつ下りながら複雑な和音で展開されて行く面白い作りです、そして何よりもボロディンの「中央アジアの平原にて」の、あの二つの隊商のメロディが近づいて擦れ違うアイディアを上手くジャズにしているところはうなります。静かで神秘的なマル・ウォルドロンの「クワイエット・テンプル」、「サムウェア(ウェスト・サイド・ストーリー)」は原曲をアレンジしており、最後が「ふるさと」です。ここは東北の傷ついた人たちを思いやってくれてるのか、唯一最初と最後にメロディをしっかりと聞かせてますが、途中では自由に展開しています。その中間部分での展開、先代のピアノの方が好きという方はどう思われるでしょう。前記のアルバムと比較してみてほしいです。こういう風にはそう弾けるものではないのではないのでしょうか。職人という言葉がぴったりします。ピアニストとして初代のボエリーと差別するわけには行かないので、これも♡♡です。 この人たちのアルバムで他に面白いものでは「哀愁のヨーロッパ」もあります。パット・メセニー以降で実際の演奏者たちから最も高い評価を得ている若手ギタリストの一人、ジェシー・ヴァン・ルーラーが参加しているという企画ものです。 ヨーロピアン・ジャズ・トリオ、ジャンルではフュージョンに分類されることもあるやもしれません。ジャズなら毎度一回きりの芸術に対峙するように聴くべきだという人もあるでしょうけれども、美しくて本格ならそれ以上言うことはありません。
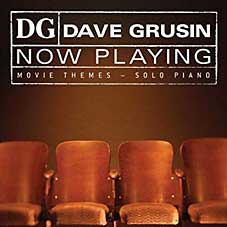 Now Playing Movie Themes - Solo Piano Dave Grusin ♥♥ Dave Grusin (p) ナウ・プレイング:映像テーマ集 / デイヴ・グルーシン ♥♥ デイヴ・グルーシン(ピアノ) 今度こそ、ジャンルはフュージョンになるかもしれません。でもピアノ・ソロでフュージョンって、肝はどこにあるのでしょう。デイヴ・グルーシンを持って来ました。フュージョン界の大物にして影のアレンジャーです。でも、フュージョンというと案外ボブ・ジェームスあたりが浮かぶでしょうか。あるいはウェザー・リポートやスパ イロ・ジャイラでしょうか。デイヴ・グルーシンは今ひとつポピュラーじゃないかもしれません。シャカタクのファンだったという人に話したら、聞いたことないと言ってました。かくいう自分もアール・クルーが出て来たときに、そのアレンジを担当したということで知ったのでした。映画音楽もたくさん手掛けてます。ゴールデン・グローブ賞に輝いたミシェル・ファイファーがセクシーに活躍してた「ザ・ファビュラス・ベイカー・ボーイズ(邦題は恋のゆくえ 1989)」、ご覧になったでしょうか。ピアノはデイヴ・グルーシンで、グラミー賞を取りました。印象に残ってます。ここで取り上げるアルバム「ナウ・プレイング:ムービー・シームズ ー ソロ・ピアノ(2004)」は彼の映画音楽を集めたものながらそれは入ってないけれども、ヘンリー・フォンダの最後の演技が見られた「黄昏(オン・ゴールド・ポンド)」で始まります。そして「ミラグロ/奇跡の地」、「ハバナ」、「トッツィー(イット・マイト・ビー・ユー)」、「チャンプ」、「ザ・ファーム」と続きます。 何と表現したらいいのだろう。この人独特の、きらめく光の中に諦観が滲むような音楽です。「黄昏」のテーマにはぴったりです。ジャズっぽい意味での「お洒落」の代名詞のような音。ジョージ・シアリングを現代的にしたような、あるいはバート・バカラックのメロディにも通じるような、ちょっぴり懐かしい運び。もの悲しいまで は行かない、微かな哀感と感謝の入り交じった音楽です。あるいはシャンソン・ピアノのカリフォルニア版でしょうか。憧れが含まれるとしても手の届かないものではなく、一日の終わりにオレンジの空を見上げてるみたいな印象です。お父さんはラトヴィア出身で、ユダヤ系の血も少し入っており、コロラドで育った人のようです。 デニー・ザイトリンのソロのところでこの人と似てる部分があると書きましたが、それは主に上記のようなスローでお洒落な曲の運びとコードの使い方についてでした。でもそれだけではなく、二曲目の「ニュー・ハンプシャー・ホーンパイプ(黄昏1981〜)」も、これはイギリスのフォークダンスのリズムだけれども、ザイトリンのアルバム・タイトル曲「ホームカミング(1986)」と似てる気がします。 それから四曲目の映画「ミラグロ」からのナンバー、「ルピタ」を聞いていると、メロディは違うけれどもこれも何となくグリーグの叙情小曲集の「蝶々」や「トロルの行進」の続きの曲かと思えて来ます。他にもヨーロピアン・ジャズ・トリオのところでも、「マイ・シップ」がデイヴ・グルーシンのようだと言ってしまいました。もともとクラシックの演奏家の家庭に育ち、クラシックもジャズも学んだ人なので、いろんな顔に喩えられるけれども、とにかく叙情的できれいなんです。 蛇足ながらピアノだけでなく、彼がアレンジしていて色々な楽器が出て来る、トータルでフュージョンしてるアルバムも挙げてみましょう。「ナイト・ラインズ(1984)」 がいいです。それと前に触れたアール・クルーのデビュー・アルバムとその次の二枚目とが、フュージョンでは私的ベストです。「ナイト・ラインズ」では、最後の「ボサ・バロック」がクラシックとボサノヴァの融合で、大変美しいです。このアルバム、電子音と打ち込みなのはなんだかだけれど、デイヴィッド・サンボーンやマーカス・ミラー、フィービー・スノウといったミュージシャンも参加しています。日本版のジャケットはきれいだったのに、WTC ビルが崩壊してオリジナルに戻ってしまいました。あれは浅井慎平の写真だったようです。でもクライスラー・ビルが目立つオリジナルのアールデコっぽい絵の方も、よく見るとシルエットの WTC が右側にちょっとだけ描かれてます。  What's It All About Pat Metheny ♥♥ Pat Metheny (g) ホワッツ・イット・オール・アバウト / パット・メセニー ♥♥ パット・メセニー(ギター) ビル・エヴァンス以降のピアニストたち、そしてちょっとフュージョン寄りの人までいくつか見て来ました。クラシック愛好家のためのお洒落なジャズということなら、何もピアノだけと限ったものではありません。他はどうなんでしょう。でもそうなるとものすごくたくさんあって、スムーズ・ジャズみたいな方面も含めて、最近の演奏者には知らない人もいっぱいいます。なので次に好きなものを少しだけ挙げてみます。 メロディとハーモニーを出せる楽器ということで、ピアノの次に来るのはギターでしょう。でもギターは弾く人でないと細かなテクニックの違いが分かりません。件の飲食店のご主人にしてジャズ・ギタリストの方がこんなことを教えてくれました。ポピュラーは一拍を八分音符二つに分割して二つ目合わせで裏拍を取りますが、「ジャズは三連符で三分割にして、ジョー・パスまでは三つ目合わせで頭も揃える、ジム・ホール以降はその頭を円分割で60度分ほどまで遅らせる乗りとなり、ポップスの二分割を全体に少し遅らせたようなリズムが常識となった」というのです。全く驚いてしまいます。何となくのイメージでジョー・パスだとかジム・ホールを捉えていたからです。キース・ジャレットがクラシックっぽいリズムに聞こえることもこの話に関係があるようです。 でもそんなことを知らなくても、好きなギタリストは分かります。パット・メセニーです。ただし、メセニーはギタリストが尊敬するギタリストでもあるので、自分が好きなのはもう一つの顔、曲作りとアレンジでのメロディー・メーカーとしてです。ライヴ・アルバム「トラヴェルズ」の 中の「ファーマーズ・トラスト」なんかすごくきれいです。鳥を模した効果音が入ってますが、広大な農場のトワイライトというのでしょうか。澄んだ空気感を感じさせる真っ直ぐな叙情で、こういう歌のセンス、いいと思います。同じく懐かしさを覚えるデイヴ・グルーシンのきらきらしたハリウッドっぽいきれいさと比べるなら、中西部というか、もっと土っぽくて素直で、カントリー・ミュージックのスローな曲にも通じるような感覚です。 この人を知ったのは本人のバンド、パット・メセニー・グループとしての三作目である「オフランプ」からです。初めてライヴを見たのは何人かが出るジャズ・フェスティヴァルの屋外で、他のミュージシャンの番のときにすぐ隣の観客席に来て一緒に聞いてるのに気がつきました。その場にいた他の女の子も気づいてサインを求めると、にっこり笑顔で応じたものの紙がなく、その子が取りに行ってる間にさっと立ち去ったのが印象的でした。騒ぎになったら演奏者に失礼だからでしょう。余分な話だけど、いずれにせよシンセも加わってしっかり作り込まれた美しいサウンドというのがその頃の印象で、アルバムで言えば「パット・メセニー・グループ(1978)」、「アメリカン・ガレージ(1979)」、亡くなってしまったライル・メイズとの共同名義になってる「アズ・フォールズ・ウィチタ、ソー・フォールズ・ウィチタ・フォールズ(1980)」、前述「オフランプ(1981)」などは好んで聞きました。特に後ろ二つは叙情的です。でもクラシックの愛好家に馴染めるのはその路線よりももっとアコースティックな、楽器そのもので勝負してるものでしょうか。ギターを弾く人たちに必ずリスペクトされるギタリストはジム・ホール、ジョージ・ベンソン、ジョン・スコフィールドなどで、それに加えて必ずこのパット・メセニーも入ると最初に触れました。でもそうした側面に光が当たるアルバムは、この人の場合はジャズ・ファン以外には決して聞きやすいものではありません。後年の一人多重オーケストラや、映画音楽的な方向のものも初期のフレッシュな印象はなく、ちょっと違うでしょう。 そこで今回取り上げる一枚目は「ホワッツ・イット・オー ル・アバウト(2011)」。ギター・ソロのアルバムです。この前に「ワン・クワイエット・ナイ ト(2003)」というのが出ていてそれも良かったですが、こちらの二作目の方はオリジナル曲のない、ポピュラー・ミュージックなどからのカヴァーだけで構成されたもので、聞いたことのある有名曲ばかりです。サイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」で始まるけれど、特別に作ってもらった42弦ギターで弾いています。そのキュービズムの絵みたいな三本ネックの形から「ピカソ」と呼ばれている楽器です。アコースティック・ギターなので、ジャズのパット・メセニーを知っている人にとってはちょっと印象が違うかもしれません。それ以外は少し低い音の出るバリトン・ギターが中心です。 スチール弦はクールでナイロン弦は温かく、とにかく静かで美しい音楽です。全編メロディアスで気難しい音は出て来ません。パットが聞いて育った音楽だからでしょうか。ポール・マッカートニーの「アンド・アイ・ラヴ・ハー」が最後に入っていてそれが人気なようですが、他もいい曲揃いです。カーペンターズもあればバート・バカラックもあります。バート・バカラックといえば希代のメロディ・メーカーで、「アルフィー」はぐっときます。自身のライヴ・アルバムでは嗄れた声で歌い、曲の合間に喋る声も枯れていて、数多い結婚歴をジョークのネタにして力の抜けたトークで聴衆を笑わせてたのが印象的でした。 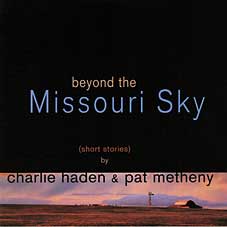 Beyond the Missouri Sky Pat Metheny & Charlie Haden ♥♥ Pat Metheny (g) Charlie Haden (b) ビヨンド・ザ・ミズーリ・スカイ / パット・メセニー & チャーリー・ヘイデン ♥♥ パット・メセニー(ギター)/ チャーリー・ヘイデン(ベース) パット・メセニーの二枚目は「ビヨンド・ザ・ミズーリ・スカイ(ミズーリの空高く 1996)」です。ベースのチャーリー・ヘイデンとのデュオで、言い出したのはヘイデンの方なので「パット・メセニーの」と言えるかどうか分かりませんが、チャーリー・ヘイデンはキース・ジャレットのアメリカン・カルテットのメンバーでもあり、ジャズ・ファンならお馴染みの人です。2014年に亡くなりました。このアルバムはグラミー賞を受賞しました。二人はどちらもミズーリ育ちということで、こんなタイトルになったみたいです。ご両人のオリジナル曲が中心です。楽器はピックアップで電気増幅された普通のジャズ・ギターとアコースティック・ギター、それにスチール弦のものも一部出て来ます。ベースは弓で弾かれることもあります。そしてオーバーダブでもう一つのギターを加えたり、シンセで軽く彩ったりした曲もあります。 ジャケットは夕焼け空の赤い雲の下に広がる大平原で、農場の建物とウィンドミルが遠くに見えているものです。あれは水を汲み上げているのです。故郷のミズーリなのでしょう。オクラホマは行ってもミズーリは行ったことないけど、写真を見ただけで懐かしい気がして来ます。そして曲の方も正にそんな感じのアルバムだと言えるでしょう。ドラムを抜いたギターとベースの語らいです。そっと小声でささやくような静かな音楽で、上記の「ホワッツ・イット・オール・アバウト」のクリアでクールな印象よりも、もっと親密さが前に出た温かい感じです。子守歌代わりに寝る前に聞く人もいるようです。 オリジナル曲が中心と言いましたが、ヘンリー・マンシーニだとか、マルチン・ボシレフスキでも出て来た「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ、 「シネマ・パラディーゾ」なども演奏しています。エンニオ・モリコーネです。そこでは大変ゆったりと、弓で弾くベースの低い持続音に乗せて風景画のように聞かせます。アメリカのフォーク・ソング、「ヒーズ・ゴーン・アウェイ」もやっています。こうした音の世界がメセニーの、あるいはヘイデンの原点なのでしょう。 最後の「スピリチュアル」はチャーリーの子供、ジョシュ・ヘイデンの曲で、前述の「ファーマーズ・トラスト」的なナンバーです。もうこれはジャズではなく、カントリーでしょう。カントリー・ミュージックを聞く日本人の人口は少ないと思います。だから保守派のレッドネックの音楽で、バンジョーが元気よく鳴ってフィドル(ヴァイオリン)が装飾し、鼻声のおじさんが歌う音楽みたいなイメージかもしれません。でも実は幅が広くて、スローな沁みる曲もあるのです。ジャズのルーツではないけれども、アメリカ人の中に脈々と流れるインスピレーションの源泉です。なんと素直できれいなんでしょう。静かに胸が熱くなります。 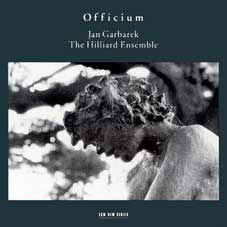 Officium Jan Garbarek / The Hilliard Ensemble ♥♥ Jan Garbarek (ss, ts) The Hilliard Ensemble (cho) オフィチウム / ヤン・ガルバレク / ヒリアード・アンサンブル ♥♥ ヤン・ガルバレク(ソプラノ/テナー・サックス)/ヒリアード・アンサンブル(合唱) ビル・エヴァンスから始めて、クラシック音楽の愛好家にも聞きやすいジャズ畑の CD を見て来ました。最後は最もクラシック寄りな響きの宗教曲です。タイトルは「オフィチウム」。サービス、セレモニーの意味のラテン語で「聖務日課」と訳されるカトリックの祈りであり、ここで歌われるクリストバル・デ・モラーレスの曲も含まれる祈祷書「死者の聖務日課 Officium defunctorum」のことです。このアルバムはドラムが入らず、静かな聖歌にサックスの即興が絡むものですが、150万枚売れたのだそうです。どのぐらいって、ポップスの凄いのには歯が立たないけど、クラシックならカラヤンの最初の全集に入ってる「第九」や、カルロス・クライバーの「運命」ぐらいです。こういうののミリオン・セラーは珍しく、Wiki によれば ECM のセールスで一番なのだとか。これぞ「癒しの一枚」と呼べるアルバムです。 聖歌に別のものを混ぜるアイディアならそれまでにもありました。例えば元々ジャズで後にニュー・エイジ/環境音楽系のサックス奏者になったポール・ウィンターも、グレゴリオ聖歌とアフリカの歌が、ちょうどボロディンの「中央アジアの平原にて」でのロシアとモンゴルの隊商みたいに出会う、人類愛的な「ウビ・カリタス」を直前にやってました。「オフィチウム」が出た1993年はグレゴリオ聖歌が流行した年でした。スペインのシロス修道院の CD が突然売れ、あっという間に25万枚に達したけれども、どうして売れたかは分からないという事態も起きました。天使か聖ヤコブの悪戯なのでしょうか。そしてこちらの「オフィチウム」は、「ウビ・カリタス」とは違ってサックスの即興によるところがジャズのカテゴリーであり、その分野の人にとっては特に興味の湧くものだと思います。 ここでソプラノとテナーのサックスを吹いているのはヤン・ガルバレク。キース・ジャレットの「マイ・ソング」のところで既に触れました。1947年生まれのノルウェー人で、ECM レーベルを代表するサックス奏者です。独特の少し硬い輪郭を感じさせる透明なサキソフォンの音色はとても美しいものです。このサックスという楽器、聞きやすい方の流れはアート・ペッパー、スタン・ゲッツ、そこからフュージョン/スムーズ寄りに進めばデイヴィッド・サンボーン、グローヴァー・ワシントン jr. 、ケニー・Gとなるでしょう。ニュー・エイジ系なら先ほどのポール・ウィンターがそう言われるけど、このヤン・ガルバレクは元来そういうソフトな路線ではありません。ご本人はコルトレーンの「カウントダウン」に感激してこの道に入ったと言います。 ヒリアード・アンサンブルは古楽の好きな人にはプロ・カンティオーネ・アンティクァ(1968)、キングス・シンガーズ(1968)、タリス・スコラー ズ(1973)、タヴァナー・コンソート(1973)などと並んでお馴染みの名前かもしれません。皆イギリスの古楽合唱団で、ヒリアード・アンサンブルの 結成は1974年です。四人で構成されており、キングス・シンガーズの六名と並んで他のグループより人数が少ないユニットです。数が少ないと透明な音が出やすいです。 演目については、「グレゴリオ聖歌にサキソフォンが合わさった」という紹介のされ方をします。でも厳密に言えばグレゴリオ聖歌というよりも、ルネサンス期の作曲家によるグレゴリオ聖歌を土台にした合唱曲に、と言った方が近いでしょう。グレゴリオ聖歌も二曲ほどありますが、それらは単旋律であり、ここでは和音となるポリフォニーの曲が中心的に歌われています。最初と真ん中、そして最後の曲がルネサンス後期のスペインの作曲家、クリストバル・デ・モラーレス(1500 - 1553)の「主よ、私を見逃してください」で、それがこのアルバムの基調です。三回演奏されている最初と最後はサックスの即興の違うバージョンのもので、真ん中はモラーレスの曲そのものでサックスが入りません。原曲に敬意を表し、また即興の土台を見せているのでしょう。それ以外は初期ルネサンスのギヨーム・デュファイと作者不詳の曲などです。 クリストバル・デ・モラーレスは大変魅力的な作曲家です。クラシックのファンなら、なにもサックスなんか入れなくても原曲で心洗われる美しい音楽じゃないか、とおっしゃるかもしれません。でもこの記録的なヒットとなったアルバムも聞いていただきたいと思います。修道院での静かな祈りと瞑想の音楽が、より現代の呼吸で立ち上がって来ます。現代の、の内訳は強さ、恐らくは何かの感情の強さです。静かな合唱が続くところで感極まって突如訴えて来るエネルギーの高いサックスにはっとして、揺さぶられます。同意を求めずに澄み切っており、泣いているとも叫んでいるともつかないけれども圧倒するのです。何の感情でしょう。タイトルから行けば「死への思い」となりますが、浄化の雨に打たれ、聖なるものへ突き抜けようとする求道者を見るようです。 INDEX |