|
ガーシュウィン / ラプソディ・イン・ブルー
George Gershwin Rhapsody in Blue 
取り上げる CD20枚: ブラレイ/various artists/ワッツ/バログ/ラベック(duo)/バーンスタイン(’59/’82)/プレヴィン (’60/’71/’84) /ガーシュウィン(ティルソン・トーマス)/ティルソン・トーマス(’82/’97)/ラベック(シャイー)/ドノホー(ラトル)/ロルティ(デュトワ) /ナカマツ(タイジック)/ボラーニ(シャイー)/ハンコック(ドゥダメル [ビデオ] /Gershwin's World) CD 評はこちら(曲の解説を飛ばします) 「ポーギーとベス」とジャズ・スタンダードのページはこちら 「パリのアメリカ人」のページはこちら クラシックとジャズ、別々のファン ジョージ・ガーシュウィン(1898-1937)はクラシックのアメリカの作曲家として最も有名で人気のある人でしょう。印象派よりも少し若い世代になるものの、いわゆる現代音楽ではなく、「クラシックとジャズを融合させた音楽」などと言われます。それならば、両方の分野の愛好家に好かれているかというと全くその通りながら、クラシック音楽のファンとジャズ・ファンとの間では、彼のものとして認識されている曲が異なるという事態も引き起こしています。ピアノでの活動を基に歌曲(いずれも劇に関するものだけど)もたくさん書いた人なので、クラシック・ファンとしては「ラプソディー・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」などの管弦楽曲やピアノ曲の作曲家であるのに対して、ジャズ・ファンにとっては、ジャズのスタンダード・ナンバーとなっている歌曲のメロディーこそがガーシュウィンなのです。 不都合な真実 クラシックの作曲家としては、真っ先に語られるエピソードがあります。ガーシュウィンはピアノの人であってオーケストラの作曲は最初不慣れだったため、あちこちに頼んで教えてもらおうとしたのです。色々な人に当 たったようだけど、有名な作曲家の中にはストラヴィンスキーとラヴェルがいます。ストラヴィンスキーに「お願いします」と頼んだときは、反対に「君の年収はいくらなの?」というように聞かれ、これこれですと答える と、「それならぼくが教えてもらわなくちゃね」と返されて断られたとされ、一方でラヴェルには「君はもう十分に一流のガーシュウィンなのだから、これから二流のラヴェルになることはないと思うよ(伝達者によって表現が多少違います)」といって断られたというのです。大変面白いけれども、実はこれ、事実と違うところがあるかもしれません。ストラヴィンスキーの方については本人が否定して「それはラヴェルから聞いた話だよ」と言ったのだとピアニストのルービンシュタインが回顧録で書いていて、それをクラシックのゴシップねたが得意な小説家、ノーマン・レブレヒトも広めています。そしてこの話にはそっくりそのままのシェーンベルク・バージョンもあります。厳格で気難しいシェーンベルクのこともガーシュウィンは受け入れていて、ビバリー・ヒルズの自宅でテニスをし合う仲だったのだとか。 ラヴェルのこの対応については、友人が昔、ラヴェルは皮肉屋で意地悪だからそういう冷たいこと言うんだ よ、などと言ってましたが、ラヴェル好きとしてはそれについてはちょっと違うんじゃないの、と思ったのを憶えています。ガーシュウィンは1926年と28年にパリに行っていますが、その間に熱心に勧めてラヴェルを ニューヨークにも呼んでいます。また、ラヴェルもガーシュウィンを高く評価しており、親切にも同じフランスの作曲家で当代きっての音楽教育者であったナディア・ブーランジェに紹介状を書いているのです。ガーシュウィンはその後実際に彼女を訪ねて習おうとしました。ところがそのブーランジェ自身もラヴェルと同様に、彼が弾くのを聞いた途端、クラシックの厳格な和声指導なんかしたらせっかくの彼のそのジャズ風のスタイルがだめになっちゃうんじゃないかと心配して、そのためにわざわざパリに住もうとまでしてたガーシュウィンの求めを断ったといいます。結局ガーシュウィンはすでに一流だったわけで、それでもあちこち頭を下げて教えを請うたのは、彼の謙虚な人柄の表われでしょう。 少なくとも言えることは、ラヴェルもガーシュウィンも、お互いに敬意を持っていたのだということです。 ガーシュウィンのピアノ協奏曲(1925)にはラヴェル風の音があり、「パリのアメリカ人(1928)」でも、ウィリアム・デイリーが編曲したピアノ版で聞くとよく分かりますが、3分半〜4分ぐらいのところで急に弱くなる部分での和音展開など、まるでラヴェルみたいです。反対にラヴェルの方も同じく自身のピアノ協奏曲(1930/31)において、ガーシュウィン流を取り入れたかと思うようなジャズ風のアレンジを聞かせています。そして偶然だけど、二人は同じ年に亡くなっています。 ジャズの特徴? ジャズの作曲家として語られることの内容ですが、この場合のジャズというのは、時期から言っても、一般に ジャズといったら思い浮かべる、5、60年代に隆盛を極めたあの「モダン・ジャズ」のことではありません。 あれはビ・バップと呼ばれる種類で、コード進行だけ決まっていて自由に即興を競い合うというスタイルです。 ガーシュウィンの時代のジャズというのはもっと前のものです。でも我々が普段何となくモダン・ジャズの語法だと理解しているような複雑なコードも、実は1920年代には大方出揃っていたとも言えるわけです。こういう話を出すとややこしくなるけれども、ジャズを成立させた要素としては、ニューオーリンズのアフリカ系の人たちのブラスバンドの演奏、ブルース、ラグタイムなどが挙げられます。 ブルースは19世紀末頃の、これもアフリカ系の人々の強制移住(労働)と望郷、生活苦を反映するムードに 満ちた音楽です。日本で流行ったブルースは恨み節的なところは多少似ているけれど、多分別物であり、演歌と 同じ根のものでしょう。 ラグタイムというのは、構造を理屈で言えば、「ズン・ター、ズン・ターのマーチのリズムで、ターの部分を和音にしてそこにアクセントを置くことで強拍/弱拍を逆にした左手に対し、やはり強弱拍を裏に取った乗りの良いメロディを右手が弾いて、時々は平行和音を連続させて叩くようなピアノ音楽」とでもなるでしょうか。何のことだか、という感じですが、昔の映画、「スティング」でスコット・ジョプリンの音楽がテーマ曲として使われ、聞かされれば誰もが耳に覚えのある状況だと思います。因みにスコット・ジョプリンもアフリカ系です。 ブルーノート 話を戻して、それならばジャズに共通する要素は何かというと、リズムにおいては4拍子の2拍と4拍にアクセントを置くオフ・ビートや、拍を少しずらし、遅らせて入るような裏拍の呼吸があります。この辺の用語はジャズの人には定義が別にあり、またオン/オフ・ビート、アフター/バック・ビート、アップ/ダウン・ ビート、表/裏拍といった日本語の使い方は混乱を極めるので、大雑把に言えば、です。 それに対して音階の方では「ブルーノート」という特徴があります。ドレミで言うと「ド・♭ミ・ファ・♯ファ・ソ・♭シ」のマイナー・スケールと「ド・レ・♭ミ・ミ・ソ・ラ」のメジャー・スケールがありますが、よくブルーノート・スケールとして表される「ド・レ・♭ミ・ミ・ファ(♯ファ)・♭ソ・ソ・ラ・♭ シ・シ・ ド」という表記において、♭ミとミのように両方が書かれているのは、本来はその間の音程がブルーノートだからなのです。一般には「ミと(ソと)シがフラットになった音階」というような言われ方をされます。聞とちょっと暗いムードのメロディーになります。そしてこれに合わせる和音(コード)の方は「ブルース・コー ド」と言い、C7、F7、G7(♯9)、A♭7などといったように、7が入るセブンス・コードで、複雑な響きになります。何だかじゃまくさくなって来ましたけれども、ジャズに共通する点としては単純に「ブルーノー トだ」ということにしておきましょう。ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」のブルーというのも、この「ブルーノート」のことです。 活躍した時代 ブルックリンでガーシュウィンが生まれたのは、電気で動くハインツの工場が初めて出現し、ライン生産化へ と向かおうとしていた1898年です。その三年前にはドヴォルザークが三年間の滞在の後に入れ違いでニュー ヨークを離れて行きましたが、ドヴォルザークはアメリカ滞在中にジャズの萌芽のようなアフリカ系の人々の音楽に興味を示しています。そしてその後ガーシュウィンが本格的に活躍した1920年代は「ジャズ・エイジ」とも呼ばれています。ジャズ・エイジという言葉自体は、その世代であるスコット・フィッツジェラルドから来ます。一人の女性をおびき寄せるために夜な夜な盛大なパーティーを開き続ける男の物語を華美な文体で綴ったあの「グレート・ギャツビー(1925)」の作家であり、当時は物語同様の華麗で退廃的な時代だったとされているのです。第一次大戦後の好景気に沸き、ニューヨークは世界経済の中心でした。見せびらかすための消費 (conspicuous consumption)という風俗も社会現象として常態化したと言われています。29年の大恐慌まで の間の、日本で言えばバブル期のようなものでしょう。別名は「ローリング・トゥエンティーズ(狂騒の20年代)」。小説では「失われた世代」、美術建築では「アール・デコ」に当たります。102階建てのエンパイヤ・ステート・ビルや、ラプソディー・イン・ブルーのジャケットによく使われる銀張り(ステンレス)の竹の子みたいなクライスラー・ビルが着工され、エレベーターはもちろん、電話もありました。コンピューターこそタイプライターだったけど、オフィス街では和製英語でいうところの OL も出現し、飛行機はまだ旅客が始まったばかりだったものの、機内での映画上映も試みられています。鉄道網はすでに全国に張り巡らされており、自動車は個人所有されていました。ラジオも掃除機も、洗濯機だってありました。当時のタイムズ・スクエアのネオン・サイン溢れる夜景など、ビルの様式が闇に紛れる写真だとまるでいつのものか分かりません。中流以上ならある意味、今と何ら変わらない生活だったのかもしれません。 
家系と暮らし どこにでも載っている話ですが、ライフ・ヒストリー的なことを以下に少し。ガーシュウィンはユダヤ系ウク ライナ人の家系で、父親は本人が革職人、母親は毛皮職人のファミリーに生まれていて、お母さんの側が当時の 反ユダヤ主義的な風潮をきらってアメリカに移住した後、それを追うようにお父さんもロシアの兵役を逃れて ニューヨークにやって来ました。そして二人は結婚し、お父さんは婦人靴の工場での監督になったのですが、関 わる企業によって28回もアパートを引越したというのですから、子供にピアノを買ってあげられるぐらいの余裕はあったけど、アメリカのユダヤ人として現在想像されるような富豪の家庭ではありません。 ガーシュウィンは四人兄弟(兄、弟、妹)で、二つ年上の兄のアイラとは作詞家と作曲家というコンビで後年 活躍しました。生まれた場所はブルックリン(ニューヨークの一部で、マンハッタン島から東側のイースト・リ バーを渡った対岸の地区)でも、育ったのは主にイディッシュ劇場街でした。そちらはマンハッタン区内の、地 図では右寄りの、主に下の方で、南突端のウォール街まで行かない辺りです。そこはユダヤ人の劇場がイディッシュ(ユダヤ)語の劇からシェークスピア、ミュージカルのようなものまで常時上演していたところです。ガーシュウィンの家庭は、父親は音楽が好きだったかもしれないものの全く音楽的な環境とは言えないものでしたが、兄弟はよくそうした劇場に出入りはしていました。ジョージの方がエキストラとして劇に出演したこともあったようです。 悪ガキ 少年時代はいわゆるストリート・ギャングで、仲間と走り回ったりローラー・スケートをしたりするだけでな く、街をうろついて商店から盗みを働いたり、殴り合いの喧嘩をしたり、放火までやったようです。音楽的な環 境ではなかったと言いましたが、十歳頃に学友のヴァイオリン・リサイタルを聞き、突然に「自分の残りの人生 はこれだ」と音楽の道を決めてしまったといいます。帰って来るなり両親に熱心にピアノ・レッスンを受けさせてくれと頼み、十二歳のときに父親が兄のためにピアノを買うと、その兄は興味を示さなかった一方で彼の方は あっという間に弾けるようになってしまいました。悪ガキだった自分を音楽が変えたのだ、とまで本人が述べて います。 ティン・パン・アレー 十五歳で学校をドロップアウトし、ソング・プラガー(デモンストレーター)という職に就きます。それは楽 譜の出版社や楽譜店などに雇われて、販売促進のために出版された新譜を弾いて聞かせる仕事です。そうした出版社が立ち並ぶ地区はティン・パン・アレー(通り)と呼ばれました。あちこちで演奏する音が食器や鍋を叩いてるみたいにうるさかったから、あるいは「調子の狂ったピアノ」という意味のスラングから付いた名前で、場所はマンハッタン島の左右の中心、セントラルパークを下ってタイムズ・スクエアよりさらに少し南に行った辺りで、現在のブロードウェイの劇場街より南、イディッシュ劇場街だった地区よりは北になります。彼の楽器はもちろんピアノでした。音楽に興味を持ってから数年しか経っていません。普通は三、四歳から始めなければ大成しないと言われるのに、です。そしてガーシュウィンはこの時期にラグタイムの音楽をポリマーのように吸収します。 ピアノロール 十八歳からは自動演奏ピアノの会社、エオリアン社で技師として働き、数々の収録をこなすと同時に自分の曲 も録音しました。それはデュオ・アートというピアノロールで、この点については CD のところで触れます。作曲も行っており、彼のポップスの分野の歌である「スワニー」がヒットを飛ばしたのはこの頃(1919年)です。当時ブロードウェイの人気歌手だったアル・ジョンソンが歌ったことで有名になったのでした。わずか30分ほどで作り上げたにもかかわらず、音楽家として最初にその名を世に知らしめた作品であり、今なお軽快なメロディーで最も人気のある曲です。 ラプソディ・イン・ ブルー 代表曲であり、ここで取り上げる「ラプソディー・イン・ブルー(1924)」を世に問うたのはガーシュウィンが二十六歳のときです。協奏曲ではないけれどもピアノとオーケストラの曲で、オーケストラはまだ苦手だったので、その部分は「グランド・キャニオン組曲」で有名なグローフェに頼みました。 作曲に至った経緯が面白くてよく話のねたになるのですが、ガーシュウィンがビリヤードに興じていると、1 月4日付のニューヨーク・トリビューンを読んだ兄が割って入って来たのです。その新聞記事は、ポール・ホワイトマンが近々「アメリカ音楽とは?」というタイトルのコンサートを開き、その中の一曲にガーシュウィンのジャズ・コンチェルトがある、と告げていました。ポール・ホワイトマンは当時有名なジャズとダンスのバンドのリーダーで、以前一緒に仕事をした関係でガーシュウィンを気に入っており、確かに少し前にそんな作曲依頼をして来たことがあるのですが、そのときはスコアを直してる十分な時間もないだろうからということで、丁寧に断っていたはずなのです。わけが分からないので翌日電話をすると、ホワイトマンは、ライバルが自分のアイディアを盗んで同じようなコンサートをやる計画なんで、ぐずぐすしてる暇がないんだよ、と言い訳しました。 既成事実を作るなんて、やり手です。ガーシュウィンは説得され、期限までに五週間を切っていたところで、二週間で書き上げました。したがって初演はホワイトマンのバンドでやったわけで、その後二台のピアノ用、ちゃんとしたオーケストラ用が数パターン、ピアノソロ用など、色々なバーションの楽譜が出たけど、最初はジャズ・バンドとピアノという構成でした。冒頭のクラリネットが音程をずり上げながら吹くところがトレードマークながら、あれもジャズ・バンドのクラリネットが面白半分にやってみせたのをガーシュウィンが気に入って採用したのでした。それと、グローフェは当時、ホワイトマン・バンドのピアノ担当で編曲者だったので手伝ったのです。でも本番の演奏はガーシュウィン本人がやりました。 作曲の仕方についても話題になります。たった二週間で書き上げたというのもすごいけど、曲想の得方も独特 です。実は構想としてはすでに一年前の1923年に持っていました。兄のアイラとミュージカルの試験興行の ためにニューヨークからボストンまで出かけたときのことを、ガーシュウィンは後に伝記作家のアイザック・ゴールドバーグに語っています: 「それは汽車に乗っていたときのことで、ガタンゴトンという鋼鉄のリズムが響いていました。私は時々ノイズ のただ中に音楽を聞くということがあるのですが、そのときは突然に聞こえて来たのです。紙に書かれた形でさ え見えました。ラプソディーの完全な構成が、始まりから終わりまで。(中略)それを私はアメリカ音楽の万華 鏡のようなものとして、巨大な人種のるつぼとして、同じもののない国の活力として、都会の熱狂として聞いたのです。そしてボストンに着くまでの間に、現実の楽曲そのものの形ではないけれども、曲の明確なプロットを得ていました」 ドヴォルザークも汽車の雑音にインスパイアされていますから、二人はちょっと似たところがあるのでしょう か。そしてモーツァルトもかくやというこの、曲全体が丸ごと聞こえ、見えるかのような能力については、彼の 才能の性質という観点から後で触れます。 ポーギーとベス その後の1935年、三十七歳のときにはもう一つの代表作、「ポーギーとベス」を世に出します。サウス・ カロライナのアフリカ系の人々のどん底生活を描いた異色のオペラです。劇中の歌、「サマータイム」は大変有名になり、ジャズのスタンダードとしてしょっちゅう歌われ、演奏されています。しかし発表時には評判は芳しくありませんでした。 不適切な関係? ガーシュウィンは結婚しませんでした。でも十年来付き合ってた女性がいました。作曲家のケイ・スウィフト という人で、一つ年上で既婚者です。ケイの方は結局彼との関係に専念するために離婚までするのですが、それ 以上進まなかったのは、スウィフト嬢がユダヤ系じゃなかったせいでガーシュウィンの母が彼女を気に入らな かったからではないか、という説もあります。そして長い付き合いの間には、ガーシュウィンは他の女性たちと も色々関係を持っており、子供もいっぱいいたとかいう噂もありますが、叩けば金粉の埃ぐらいは出ると思いま す。狂騒の時代からショービズの世界で売れっ子の天才ソング・ライターであり、あのハンサム・ガイの上にお 金持ちで、寂しがり屋の甘えん坊だったのです。ストレートだったらそうならない方に理由が要りそうなので あって、罪証を集めてごまめの歯ぎしりしたって所詮は届かないと思います。色々な意味で人気者だったことは 間違いありません。  早過ぎた死 もう一つ、モーツァルトと似ているのはその短い生涯です。三十八歳までしか生きられませんでした。脳腫瘍 でした。1936年、それは死の一年前ですが、ニューヨークで生まれ育ったガーシュウィンは LA に移り住みました。映画音楽の依頼があったのでハリウッドにやって来たのです。ビバリーヒルズで借りている自宅のテニスコートをシェーンベルクに使わせていたのもこの頃です。因みに映画のタイトルは「シャル・ウィー・ダンス」。でも役所広司やリチャード・ ギアの方ではなくて、フレッド・アステアが主演の全く別のお話です。 病気の兆候が出だしたのは翌年の初めで、まずひどい頭痛でした。それと同時にゴムやごみが燃えるような匂 いがするという嗅覚幻覚が現れました。気分は乱高下して食べ物はこぼします。モントゥーと自身のピアノ協奏曲を演奏しているときはうまく弾けなくなり、意識消失を経験しました。そして7月9日に家で倒れて入院し、昏睡状態となってしまいます。神経外科医が必要だということになり、その分野のパイオニアからある医者が紹介されますが、その人はワシントン D.C. の東のチェサピーク湾でボート・フィッシング中だったので、迎えの船を出し、飛行機をチャーターして LA まで呼び寄せて、それから11日の未明に5時間の手術を行って腫瘍を摘出しましたが、意識は戻らずにその朝に亡くなりました。 特殊な気質? さて、光陰矢の如しです。人生は墓石に刻まれた二つの年号の間に置かれたたった数センチのダッシュに過ぎ ないという見方もありますが、普通の人よりさらに短いガーシュウィンのライフ・ストーリーも、外から眺めれ ばざっと以上のような話です。しかしそれはそれとして、一つ思い当たることもあります。彼の感情生活のあり方 についてなのですが、まず、色々な作曲家に頭を下げて作曲技法を教えてくださいと言って回るあたり、謙虚過ぎて売れっ子作家のプライドは感じられません。それは良いとしても、世間で敬遠される人とも意に返さず友達になります。音楽の捧げ物のページからの続きでシェーンベルクが意地悪だとか言ってるわけじゃ全然ありません。あの厳格な十二音技法の発案者も愛情問題において過去に傷ついた出来事があったようで、責めるのも気の毒な話です。どういう理由にしろ表面で頑になっている人を非難しても、その人自身を見たことにはならないわけです。しかし付き合い難い人というものが存在しているのもまた事実で、どうやらガーシュウィンは強く自我が突出した人と対面しても、テフロンみたいに引っ掛からなかったようだ、というのです。この誰に対しても人懐っこく、まるで違う形態で生きてるかのような感覚は、別に悟ってるわけじゃないと思います。それはひょっとすると、あの現象じゃないんだろうか。 そう思って見てみると、やっぱり似たようなことを考える人はいるものです。医大の精神科の教授がフィラデ ルフィアの新聞に書いているようですが、ガーシュウィンは ADHD だというのです。注意欠如/多動性障害という発達障害です。根拠はたくさん挙げていますが、まず、子供時代に衝動的に喧嘩ばかりしていたことがその一つ。それと、もう一つは雑音を気にせず窓を開けて作曲していたこと。それらは確かにそうかもしれないけれども、しかし残りは、「パリのアメリカ人」関連でクラクションの音にこだわってフランスからタクシーの部品を持ち帰ったこと、汽車の音を一瞬で曲のテーマとして聞いたこと(その中には映像記憶を思わせる記述もありました)、リサイタルに接しただけで一念発起してあっという間にピアノが弾けるようになったことなどで、それらはむしろ ADHD というよりも ASD(自閉症スペクトラム)の方に近い感じもします。しかし両者は共存してサヴァン(発達障害の天才)のような人を生み出しているのですから、細かいことはいいでしょう。そして別に病気とも言えないし、ICD や DSM の診断基準にしたって原因を特定せずにラベルを張り付けているだけであって、音楽を聞くためにはどうでもいいことです。ただ、確かにガーシュウィンはそう分類されるように普通の感覚の人じゃなかった、とは言える気もします。アレグリのミゼレーレを一度聞いただけで楽譜に起こしたモーツァルトも愛すべき変わり者だったし、生涯一人の女性をあきらめ切れなかった蒸気機関マニアのドヴォルザークも、またちょっと傍系にしろ仲間である可能性があります。図抜けた天才というのは大なり小なり、こういう具合にこだわるポイントも感情の受け止め方も万人とは違うタイプの人である場合が多いのです。 情感的な特徴は? では、そういう種類の天才の一人であるガーシュウィンの音楽、聞いた限りでのエモーションの部分、心のあ り方としてはどんな印象を与えるのでしょうか。これは診断基準と一対一対応という単純なものでは全くない し、逆にこの種の才能の中には、揃えた音で機銃のように叩くことに執心して感情要素が感じられない演奏家も いたりしますから、全く関係ないと言えるのかもしれませんが、彼の魅力としてよく言われるのは、その賑やか さ、快活さです。ルーツの一つに黒人哀歌のようなブルースを持つジャズを取り入れながらも、また、ラグタイムという形式に由来する部分をも超えて、それは確かに屈託がなく、乗りの良いものです。明るくて、人懐っこく て、しかし一番に思うことは、その底抜けに陽気に踊るブラスの喧騒がふと止んで静かになるところでの、爽や かでいてどこか懐かしいようなあの感覚です。繊細な呼吸があり、ほんの少しだけ寂しさが混じるかどうかとい う温かい充足感に包まれるのです。以前に全く同じことを別の作曲家の描写で触れたのですが、晴れた夏の日 の、都会の夕暮れみたいです。窓から仰ぎ見るオレンジの空にスカイラインがくっきりと、これからの解放され た時間に思いを馳せます。ルイ・アームストロングの “What a Wonderful World” とも少し似た雰囲気でしょうか(陽気な葬式で有名な地方出身の歌手だからかと思うと、曲を作ったのはユダヤ系の二人組です)。それがガーシュウィンの場合、オーケストラ以外の曲、ジャズでスタンダードとなった歌のメロディーの性質としても、独特の肯定的な魅力を放っているように思うのです。 クラシックの作曲家でこれに多少でも似た傾向の情感を感じさせる人はというと、時代も形式も全く違うの に、今上で触れた「別の作曲家」である、ヘンデル、が思い浮かびます(Handel Goes Wild)。あの曇りのないメロディーのセンスで、という意味でです。もう一人挙げるとすると、リヒャルト・ シュトラウスも頭の隅をかすめますが、才能の形がちょっと似てるモーツァルトなんかどうでしょう。やっぱり要素がある気がして来ます。人懐っこく調子良くて、晩年はクリスタル・クリアーに軽く駈けました。ガーシュウィンと同じように重い感情のドラマへの執着に欠けています。では、反対の性質となると、これも先に述べたガーシュウィンのテニス友達、シェーンベルクでしょうか。無調の曲は音を平等に扱う理論によって感情の要素が消されてしまうので、「浄 夜」ぐらいでしか分かりませんが、あとはマーラーとか。ベルリオーズやスメタナ、ヤナーチェク、シベリウス、バルトーク、ショスタコーヴィチなども無理に分類すればそちら側に入るかもしれません。 ジャズでは、マイルスなんかはガーシュウィンとは全然違っていて、悔しさを梃子にするような引っ掛かりの強さがあります。実験精神も哀愁の部分もそんなところから出てくるのかと思えます。バンド内で向かい合って勝負を挑む演奏スタイルが物語っているでしょう。美しい叙情性がありながら耽溺しない悲しみを表すエヴァンスも、感情的こだわりを突き抜けた軽さとは違います。一人挙げるとすれば、オスカー・ピーターソンが近いでしょうか。プレヴィンが最も高く評価する超絶技巧のピアニストであり、彼はガーシュウィンのことも気に入っていて、「ヒズ・ソング・ブック」という形で複数回録音しています。 結局どの世界でもガーシュウィンのような陽性の叙情を感じさせる人は少ないもので、それだけにこの夭折の 作曲家、まさに得難い存在なのです。すごく世俗的なのに天上界のような、この上なく美しい瞬間を見せてくれ ます。  George Gershwin Piano Works 〜Rhapsody in Blue (piano solo version) Frank Braley (pf) ♥♥ ガーシュウィン / ピアノ曲全集 〜ラプソディー・イン・ブルー(ピアノ独奏版) フランク・ブラレイ(ピアノ)♥♥ 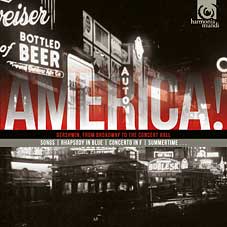 America! Vol.2 Gershwin, from Broadway to the Concert Hall Various Artists ♥♥ アメリ カ! 第2巻 ガーシュウィン、ブロードウェイからコンサート・ホールまで 様々なアーティストたち ♥♥ ラプソディー・イン・ブルーは、一般にはピアノとオーケストラの曲です。ですからそこから始めるべきかもしれませんが、ピアノ独奏版(1927)もあって、賑やかなオーケストラがない分だけ、案外静かに曲本来の姿を味わうことができます。変化球だけどその方がいいと言うと、やっぱりへそ曲がりでしょうか。でもピアノの部分での演奏面で最も良いと思ったものの一つがたまたま独奏版だったこともあり、まず最初はオーケストラ抜きのバージョンからご紹介します。CD ジャケットの上の写真のものです。 フランク・ブラレイはフランスのピアニストです。ご紹介できるほど何も知りませんが、1968年生まれ で、写真を見るとまるでロッカーみたいです。経歴はいっぱい書いてあるけれどそれでは何も分からず、ドビュッシーのときのアラン・プラネス同様、またしてもハルモニア・ムンディからリリースされたこのガーシュウィンのピアノ曲全集で驚いたという状況です。ジャズはアメリカだけど、案外フランス人の演奏って合うところが元々あるように思うのです。ふわっとゆったり山を描くような歌謡的センスがあって、四角四面にやらないところがいいのでしょう。拍を粋に崩す仕方がジャズのリズムにも合います。後で取り上げるラベック姉妹も良かったですし、この曲はやってないけどフランソワだってジャズっぽいとも言えるではないですか。 でもそうやって文化で一 括りにすると個々の演奏者の個性に対して申し訳ないことになってしまうので、ちゃんと言い直します。このブラレイの演奏は、まず力で押したりぶつけたりする方向ではありません。静かな歌が終わって場面が変わり、次に強い音の連続で印象づけるパッセージへと入って行くところなどでは、多くのピアニストが最初の一打からコントラストを付けて思い切り強く叩くものです。しかしブラレイは 最初は弱く始め、そこから加速度的に盛り上げる余裕を見せることで動きを演出します。それは同時に繊細な感受性を思わせるもので、歌を一辺倒ではなく、微 妙な陰影をつけて歌ってみせるこの人独特の感性の表れでしょう。どこを取ってもデリケートな表情に満ちていて、最高のラプソディ・イン・ブルーです。客観的に言えば、テンポはややゆったりの部分が多いでしょうか。リズムには自在な伸び縮みがあります。オーケストラ付きのものではティルソン・トーマスの最新の録音が良かったけれど、これは独奏版ながら一番かけたくなるラプソディ・イン・ブルー最大のお気に入りです。要約すると、とにかく洒脱です。 ハルモニア・ムンディ 2004年の録音で、ピアノの音は輝き過ぎず、自然で美しいものです。この点もベストと言えます。 カップリング曲がまたい いのです。ラプソディー・イン・ブルーと並んで有名な「パリのアメリカ人」をピアノに編曲したものが入っていて、これが何とも魅力的な響きです。作曲者自身が作り上げるときは こういうイメージなのでしょう。元々ピアノの人ですから。編曲はウィリアム・デイリーという同時代のアメリカの作曲家で、フレッド・アステアの舞台も担当したようです。1928年にガーシュウィンが作曲してすぐに編曲したもののようで、翌1929年に出版されています。 そして何より、ソング・ ブック(18のヒット歌曲集)があります。出世作であるスワニー、ス・ワンダフ ル、ザ・マン・アイ・ラヴ、ドゥー・イット・アゲイン、オー・レディ・ビー・グッド、魅惑のリズム、サムバ ディ・ラヴズ・ミー、アイ・ゴット・リズムなど、ジャズのスタンダードとなった有名曲がほとんど聞けます。歌なんだから元気なサラ・ヴォーンとかで聞けばいいのかもしれないけど、ピアノの方が洗練された叙情という感じできれいです。 ガーシュウィンのピアノ 曲がほぼ全部聞けてしまうのも嬉しいところです。惜しい部分があるとするなら、オ ペラ「ポーギーとベス」の中の有名な「サマータイム」が聞けないことぐらいでしょうか。元々ガーシュウィン がそれをソング・ブックの中に収めていないので仕方ありません。そしてそれよりも問題なのは、CD としての手に入れ難さでしょう。ゴールド・シリーズで出たものなのでまた再販されるとは思いますが、今のところ供給の谷間で在庫を探すのが多少苦しいです。新品は本国フランスのアマゾンでまだ定価で買えるものの、国内だと中古が出るの待ちという状況です。とりあえずストリーミングで聞くことはできるのですが。 一方、それよりも多少まだ在庫が豊富なのは写真下のものです。ただしこちらにはフランク・ブラレイのラプ ソディー・イン・ブルーは入っていないのが残念なところで、したがってここで挙げるのは本来おかしいのです。二枚組で写真上のピアノ曲全集とは内容が異なっているのだけど、一枚目はそのブラレイを中心にしたソング・ブックなどが聞けるものであり(ピアノ作品集)、「パリのアメリカ人」も入っていて全集ともほとんど同じ内容となっています。ジャズでスタンダードとなっている粋な歌もののピアノ演奏を堪能したいなら、これは頭からそ の18のソング・ブックが入っているので選曲はばっちりです。何よりもありがたいのは、ピアノはマイケル・シェパードになるのですが、最後に「ポーギーとベス」による大幻想曲というものが来ており、そこには「サ マータイム」も含まれていることです。編曲を得意としたアメリカの作曲家でピアニスト、アール・ワイルド(下記トスカニーニやフィードラー盤の演奏者)によるものです。 ラプソディー・イン・ブルーは二枚目(管弦楽作品集)にあり、それはリンカーン・マイヨーガのピアノによる オーケストラ伴奏のものです。二枚目のそれ以外の曲はジョン・ナカマツによるピアノ協奏曲(後で触れますが、この人もいいピアノを弾きます)、キューバ序曲、それからこれまた「サマータイム」がアルト・サックス(アル・ガロドロ)とピアノ(リンカーン・マイヨーガ)で聞ける、グローフェ編曲の「ポーギーとベス」第1幕:「サマータイム」があります。 実はこの CD、ハルモニア・ムンディの企画による「アメリカ!」というシリーズの中の Vol.2 に当たり、ガーシュウィンを集めた二枚なのです。サブ・タイトルは「ガーシュウィン、ブロードウェイからコンサート・ホールまで」となっています。オペラやミュージカルのナンバーを歌手が歌っているようなものを除いて、これでほぼガーシュウィンの主だった作品が聞けてしまいます。因みにシリーズの Vol.1は「避難の地」というタイトルで、レフュジーなので移民というよりも「難民」に近いニュアンスであり、自国での難を逃れてアメリカに渡った人た ちの音楽が集められています。ドヴォルザークは避難とは言えないけど、様々な作曲家が並んでおり、ラフマニノフやプロコフィエフ、ストラヴィンスキー、バルトークなどもあります。Vol.3 は「モダンからポップアートまで」です。バーバー、コープランド、バーンスタイン、ジョン・ケージなんかも入ってます。各シリーズはばらばらに買えます。  George Gershwin Solo Piano Music 〜Rhapsody in Blue (piano solo version) André Watts (pf) ♥ ガーシュウィン / ピアノ独奏曲集 〜ラプソディー・イン・ブルー(ピアノ独奏版) アンドレ・ワッツ(ピアノ)♥ 上でピアノ独奏版のラプソディー・イン・ブルーとソング・ブックが入ったものを取り上げましたので、 それ と同じ組み合わせで昔から出ていて長らく聞いてきたものにも触れてみます。アンドレ・ワッツの演奏です。た だ、今はストリーミングでは聞けるものの、ガーシュウィンのみのアルバムは CD としては出ていないようで、彼の全集か中古の LP のみなので、こういう趣旨の先駆的なアルバムとして参考までに、ということです。 写真を見ても分かるよう に、アフリカ系の血筋である珍しいクラシックのピアニストで、こういう人は昔ド ン・シャーリーがいたぐらいで最近のグッドイヤーまであまり多くはないと思います。1946年のドイツで、 ハンガリー人のピアニストのお母さんと米軍の下士官の間に生まれたとのことです。ナチを倒したアメリカ軍って、終戦の年はすごく光ってたことだろうと思います。街を解放する米兵と感極まってキスをしてる地元の女性たちの映像は見たことがあるかと思います。あれはもちろんそれだけでは終わらなかったわけで、翌年にその結晶として誕生した婚外の赤ちゃんは何万人規模ということであり、生命の物質化した優生戦略を目撃している感があります。でもそれはアンドレの神聖な誕生を揶揄しているのではなくて、一般論です。 ジャズを取り入れたガーシュウィンの曲だからピアニストもアフリカ系の血が入っていた方がいい、などという見方も、黒人はスポーツが強いと決めてかかるのと同じで根拠のない差別的な話です。したがって血筋が関係するかどうかは不問ですが、このアンドレ・ワッツの演奏、ソング・ブック(18曲中の13曲)のスタンダード曲ではよく歌って繊細な抑揚があり、テンポも速過ぎずでフランク・ブラレイのピアノと多少似たところもあります。ブラレイの方がもう少し不定形の揺れと崩しがあるかどうかなという微妙なところですが。でも実はこの人、元々はリストが得意な超絶技巧型のピアニストなのだそうです。改めて他の作曲家の演奏に接してみると、それが何となく分かります。というよりも、このアルバムの最初に入っているラプソディー・イン・ブルーでは、他のメロディアスなヒット歌曲とは違って歯切れ良く強靭な大技も見せます。最初はゆったり入ってやわらかい呼吸もあるのですが、強く叩くところは速くて案外元気な押しが聞かれるのです。ブラームスのコンチェルトなどではバーンスタインともやっていて、堂々と四つに組んで相性も良さそうです。それでいて歌の部分は細やかな抑揚が魅力的という、両面ある人だということを改めて認識しました。剛毅なタッチも表現の幅を広げる武器であって重要なわけであり、きらきらしたガーシュウィンというのは本来の姿でしょう。あくまで個人的な好みはそちら方向ではないとしても、そういう軟弱な意見は横へ置いておいて、このワッツというピアニスト、最近あまり名前を聞かないけど是非チェックしてみてください。♡は歌曲の方だったら二つ付けるところです。盤自体が今や稀少であり、この記事はラプソディー・イン・ブルーについてなので、ここでは一つにしておきます。この作曲家の魅力を教えてくれた貴重な一枚です。 1976年 CBS コロンビアですが、録音のコンディションは十二分に良いです。  George Gershwin Rhapsody in Blue (piano solo version) József Balog (pf) ♥♥ ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー(ピアノ独奏版) ヨージェフ・バログ(ピアノ)♥♥ 録音年代が前後しますがこれも同じような企画で、ラプソディー・イン・ブルーのピアノ独奏版にソング・ブックの曲などを集めたものの中で大変魅力的な一枚です。ピアニストのヨージェフ・バログは1979年ハンガリー生まれのピアニストで、ワッツと同様ハンガリー系ということでやはりリストは得意としているようであ り、技巧派だと言われるらしいですが、確かに胸がすく歯切れの良さでスピード感のあるパートも聞かれます。でもワッツのがつんと来る強いタッチよりも軽さがある気もします。区切るように遅く叩くところは出ません。そしてワッツ同様に、絶妙な揺らしと間の遊びは持っており、むしろそれがより大胆なほどで、自由自在という感じです。待ってため、反対にスイングして走り、つんのめって止まりと、ジャジーというのか、歌のセンス、リズム感がすごくあるのです。ガーシュウィンはそういうセンスのない人が弾いても面白くないでしょう。そしてそんなところも速くまくるところも、聞いていて大変心地良く乗れます。フランク・ブラレイのような静けさと物腰のやわらかさ、落ち着きに寄った曲線美という方向ではなく、雑味は全くないけど活きがいいものです。 嬉しいのはベリル・ルービンシュタインの編曲による「サマータイム」が聞けることです。「アメリカ! Vol.2」に入っていた二曲とはまた違ったバージョンで、こちらの方が多くのピアニストに弾かれているかもしれません。ソング・ブックからは18曲中7曲にとどまりますが、有名なメロディーばかり選りすぐってあって十分堪能できます。最後にアール・ワイルドによる「ガーシュウィンによるヴィルトゥオーゾ・エチュード」なるものが入っています。確かにパラピロタラリラリッ、と指が回り過ぎるような派手な飾りが余分に付いたところもあるけど、モダン・ジャズだってテクニックを競うような即興で埋め尽くすわけですから、インプロヴィゼーションでないだけでクラシックで同じことをやってるとも言えます。しっとりして美しい楽曲として楽しめる部分も多くて、これもソング・ブックみたいに名旋律集のような趣があっていいです。 2017年フンガロトンの録音です。きらきらと大変きれいなピアノの音が楽しめます。どちらかというとコーンという系統の音ですが、コーンじゃ何言ってるか分かりませんから、高周波の細かな倍音を最大拾うというよりも、少し硬くまとまって艶のきれいに出る種類と言ったらよいでしょうか。ちょっとジャズ・ピアノで聞かれるタイプの録音に近いでしょうか。やわらかくシックという方向ではありません。かといって耳に痛いほど金属的にはならないので、この小気味良い演奏にいい感じでマッチしていると言えます。 フンガロトンはハンガリーで昔から有名なレーベルながら、DG やデッカといった大手ではないので、出てそんなに経ってなくてもハードとしては手に入れやすくないみたいです。米国からはまだ送ってくれるようだけど、中 古がどんどん出て来るような枚数出てる種類でもないと思うので、やはり手軽なのはインターネット経由でしょ うか。  George Gershwin Rhapsody in Blue (for two piano) Katia & Marielle Labéque (pf) ♥ ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー(二台のピアノ版) カティア & マリエル・ラベック(ピアノ)♥ 二台のピアノによるスコアも存在しています。初演の後でガーシュウィン本人によって書かれており、同じ 1924年のものです。ラベック姉妹についてはこの五年後にオーケストラと合わせて演奏したデッカ盤も存在 しており、現在はそちらの方が有名かと思いますので、ここでは内容だけにとどめます。一つだけ触れると、こ ちらのオーケストラなしのデュオ・アルバムは当時50万枚以上売れ、彼女たちを有名にしたものです。 強弱の陰影がよくついて、速く駈けるところとまちを持たせたゆったりの歌との間で揺れ動くコントラストが しっかりとあります。ブラレイよりは畝の付け方が分かりやすくてさらっとしてるかもしれないけど、ワッツよ りも多少意外性の崩しというか、不安定寄りのなし崩しの駈け出しというのか、フランス人らしい(と言いたくなる)リズムの自在な動きも見せており、小粋で味わい深いのです。緩める情緒の流れが多少漸進的ではなくて階段的な印象もあり、かなりゴージャスで華やかな方の演奏であると思います。ワッツほどではな いけど案外ダイナミックで、静けさという点では若干ブラレイが好みかなとも思うものの、ピアノ二台ということもあって一台よりもやはりボリューム感と厚みが感じられます。所々でもう一人が加える不思議な音や、増強されたリズム・セクションの刻みが聞けて良いです。 1980年のフィリップス録音で、このレーベルらしく煌びやか過ぎず、それでいて芯はくっきりとした好録音です。この人たちのタッチもあるのでしょうが、重なるフォルテではかなり強靭な音も出ます。 上の写真はオリジナルのもので、カップリングはピアノ協奏曲(2台のピアノ版)ですが、その後では組み替えでサマータイムやアイ・ラヴズ・ユー・ポーギー、あるいは「パリのアメリカ人」など、別のものと合わせた盤も出ています。 さらにこの三十年後の2011年には新しい録音も出ました。コンビは元気に活躍しているようです。 レーベ ルは KML Recordings となっていて、カティア・マリエル・ラベックの頭文字を取った自前スタジオでの録音レーベルのようです。昨今はどこもこういう風ですが、その関係もあってか大手の通販サイトでは現在入手不可という扱いになっており、稀に中古があるかという現状なのが残念です。カップリングはウェストサイド物語でした。 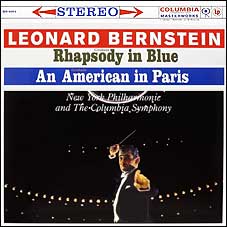 Gershwin Rhapsody in Blue Leonard Bernstein (pf/cond.) Columbia Symphony Orchestra 1959 ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー レナード・バーンスタイン(ピアノ/指揮)/ コロンビア交響楽団  Gershwin Rhapsody in Blue Leonard Bernstein (pf/cond.) Los Angeles Philharmonic Orchestra 1982 ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー レナード・バーンスタイン(ピアノ/指揮)/ ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 ここからはちゃんとオーケストラ版の方です。この曲にはガーシュウィン本人と初演のホワイトマン・バンドの1924年の SP 録音がまずあり、音は古いけどオリジナルはどういう風に演奏されていたかが分かります。因みに本人の肉声も聞けるものがあります。彼の性質が表れているかどうか、聞いてみてください。モノラル期では技巧派ピアニストでこの曲で有名になったアール・ワイルドとトスカニーニ /NBC交響楽団の1942年の録音(クラリネットはベニー・グッドマン)が話題になり、ステレオ初期になると、同じくアール・ワイルドとアーサー・フィードラー/ボストン・ポップス ♥ の1959年の RCA リビング・ステレオの名録音があります(演奏、この時期としては音質、ともに大変良いです)。 それ以降の演奏となると、ガーシュウィン自身がユダヤ系アメリカ人だったために、同じ出自の人たちが多く出しているし、受けてもいるようです。バーンスタイン、プレヴィン、ティルソン・トーマス、レヴァイン、スラットキンなどです。その中でも特によく話題になるのがバーンスタイン盤でしょう。古い方はアール・ワイルドのフィードラー盤と実は同じ年で、私見ではあちらの方がガーシュウィン自身のピアノのスタイルに近いようにも思えるのですが、人気は圧倒的にバーンスタインです。ショービズの世界という共通点もあるからでしょうか。アメリカではこの業界のトップ・バナナ(大立者)にして台風の目であり続けた人であり、ウェストサイド・ストーリーの「トゥナイト」など、作曲者としても素晴らしいメロディー・メーカーで、いつもそれを聞くと大した才能だなあと思って来たものです。昔のことですが、オーケストラで演奏している親しい人がある日、その楽団がバーンスタインの指導を受けたと目を輝かせて言いました。その舞い上がりようときたら、「とにかく凄い人で、立ってるだけで存在感があって、ジョークなんか言って堂々としてる」とか何とか、音楽に関係ないところで滅法褒めまくるわけです。奥さんがありつつゲイであることも隠さず、ロマンティック・リレーションシップは煌びやかです。きっとそんな風に言いたくなる魅力があるのでしょう。そう、それは得難い体験だったね、と一回り大きく喜んでおくべきところを、そうは振舞いつつも、英語のジョークとか本当は分かんなかったでしょ、と内心嫌なやつになってお門違いな嫉妬心を覚えた記憶があります。 だからバーンスタインの CD をこれまであまり取り上げて来なかった、わけではないと天にかけて誓えますが、ちょっと登場回数が少な過ぎたでしょうか。メリハリのある大きな演奏をする人です。指揮者としてカラヤン以上に熱烈な支持者がいるということは、はまると抜けられない急所があるはずであり、それが分からないと天才が分からないことになってしまいます。一方で分かりやすく乗せてくれるサービス精神がありますし、それこそ日本の オーケストラが苦手とするような振り幅の表情があって良いと思います。野球選手も実物に接するとオーラの大きさに圧倒されると言います(測定はできません)。大谷選手などもさぞかしワンッ、と熱いんでしょう。その感覚は会ってみないと分からないわけで、この指揮者にしても、名声があるから褒められるという事態にはあきれないことにして、やはり凄い人だったに違いありません。 バーンスタインの録音は主に二つあります。1959年のコロンビア交響楽団とのもの(写真上/オリジナルの LP ではパリのアメリカ人とのカップリングで、CD ではそれに「グランドキャニオン組曲」が入ってたりします)と、1982年の LA フィルとのデジタル・ライヴ盤(バーバーの「弦楽のためのアダージョ」などとカップリング)です。 レー ベルは旧がコロンビア=ソニー、新がドイツ・グラモフォンです。 ファンの方はこのうちどうも初出盤の方を高く評価されるようですが、その理由は自分にはよく分かりませんでした。どちらも同じように表情の濃い、重さのある演奏です。モダン・ジャズはリズム進行は一定なのですが、「ジャズっぽい乗り」などと言われる場合の特徴として、テンポを軽快自在に揺らすということがあります。ジャ ズ名人のプレヴィンにしてもティルソン・トーマスにしても、ラプソディー・イン・ブルーでジャズ寄りと言われる録音は皆そうです。つまり、途中で駈け出したりするのです。ところがこのバーンスタインの場合は同じ振り幅の大きさはあっても、ゆっくりに落とす強調が目立つ点で他の演奏者とは全く違います。スタッカートを交えて速くなるところももちろんあるものの、粘るような方向で揺らすマナーが独特なのです。静かなパートでゆっくりやる人は珍しくない一方で、そうでないところも低速で強調するからでしょうか。その点についてはピアノ演奏だけでなく、指揮も担当してるのでオーケストラのパートでも同じです。 今までバーンスタインについては、よく感情設計の行き届いた人という印象が先に立っていたこともあり、今回初めて気がついたのですが、ここではガーシュ ウィンにしては随分真剣に押す感覚があります。何か精神的にしんどいことと闘ってたのかもしれません。 そして新旧の録音を敢えて比べるならば、新盤の方がトータル・タイムは長く、強く強調する音があって気宇壮大です。一方で旧盤の方には若干の軽さと形が整ったところがあるような気もします。どちらがいいかとなると好みながら、性質として大して違わないならば録音が良い方が一般にはお薦めだと思うのですが、いかがでしょう か。もちろん旧盤もくっきりとした音になっていてコンディションは悪くありません。新盤は新しいだけに、ライヴでも録音がよりきれいです。人によってはごちそうさまかもしれないけれども、これこそがガーシュウィンの真骨頂という方もいらっしゃると思い ま す。 よく見ると新盤のジャケット、ツインタワーが小さく写っています。展望デッキのチケット、捨てられずに持ってたりします。愛すべきレニーはそれを知らずに済みました(1990 年に亡くなっています)。  Gershwin Rhapsody in Blue André Previn (pf) André Kostelanetz and His Orchestra 1960 ♥♥ ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー アンドレ・プレヴィン(ピアノ)/ アンドレ・コステラネッツ&ヒズ・オーケストラ ♥♥ プレヴィンは元からジャズの名人です。ジャズでキャリアを始めたのですから。そしてジャズとクラシックの両方で一流という人は、このプレヴィンをおいて他にないでしょう。有名なジャズマンも褒め称えています。ジャズ・ピアニストとしてどれだけ高い能力か知りたければ、We Got Rhythm: A Gershwin Songbook, André Previn and David Finck ♥♥ というドイツ・グラモフォンから出ている1997年録音のアルバムを是非聞いていただきたいです。そちらは本格ジャズですからジャケットは取り上げませんが、ピアノを弾くガーシュウィンのイラストで、目が八分音符、耳がト音記号になってるものです。というわけで、プレヴィンはこの曲にはぴったり、なのですが、クラシックの演奏家になってからは、案外形の崩れがない、繊細な息遣いはあるけどアゴーギクの変化(テンポ変動)の点で派手なことはしないパフォーマンスが 多くなった気がします。その棲み分けは見識ながら、ラプソディー・イン・ブルーではそうなる前の彼が聞きたいわけです。録音としては最初のが1960年のコロンビア、二回目が71年の EMI、三回目が84年のフィリップスのデジタルで、ここでまず最初に取り上げるのは60年盤です。 これが結局プレヴィンの演奏としては一番な気がします。プレヴィンがピアノで、指揮はアンドレ・コステラ ネッツ、管弦楽は彼の管弦楽団という構成です。コステラネッツはポップスや映画音楽を得意とした人で、 ジャ ズ・バンド、というわけではないですが、1901年生まれでガーシュウィンの時代の空気を知ってる人です。 この曲の依頼と初演がホワイトマンのバンドだったわけで、あちらもジャズ・バンドとは言われますが同じような性格の団体でしたから、オリジナルの雰囲気が感じられる演奏と言えるでしょう。ヴァイオリン・ソロがキュンと泣いたり、しなやかにたわむリズムがいかにもで、マッチングはばっちりです。プレヴィンのピアノについては、後年の録音が割と正統派のおとなしいものなのに対して、こちらは若くて(三十一歳時)ジャズを中心にやって来た彼らしい、乗りの良いグルーヴが聞けるものです。 具体的にはテンポが伸び縮みするわけです。そして速度を緩めるところはあるけれども、その場合もバーンスタインのようにヘヴィ級の強調とはならない、すっと遅く静めて間を取る軽快な動きの一環という感じです。駈けるところでは自由自在な楽しさが溢れています。それでもプレヴィンの元からの性質なのか、どこか洗練された味もある気がします。 1960年の録音ということで音が心配かと思いますが、写真の盤は2006年にリマスターされており、良いバランスとなっています。ピアノが多少オフにも聞こえるものの、リマスター前の元の音源が乾いてややハイ上がりのかっちりした音でしたから、この方が潤いがあって良いです。元々アメリカの録音ははっきりしているので、いじっても上手く行くようです。ガーシュウィンが最後の年を過ごしたハリウッドでの収録であり、コロンビア原盤のソニー・レーベルです。カップリングはピアノ協奏曲です。  Gershwin Rhapsody in Blue André Previn (pf/cond.) London Symphony Orchestra 1971 ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー アンドレ・プレヴィン(ピアノ/指揮)/ ロンドン交響楽団 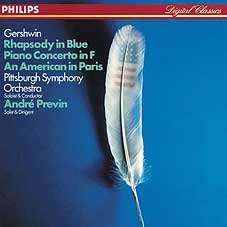 Gershwin Rhapsody in Blue André Previn (pf/cond.) Pittsburgh Symphony Orchestra 1984 ♥♥ ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー アンドレ・プレヴィン(ピアノ/指揮)/ ピッツバーグ交響楽団 ♥♥ プレヴィン二度目の録音は EMI で行った1971年のもので、四十二歳のときです(写真上)。三回のうちでタイム的には一番長く、落ち着きがあります。オーケストラには欧州の重さも出て来ていて、シンフォニックな大きさが感じられる演奏となっています。ピアノの演奏には相変わらずメリハリはありますが、初回のような軽さ、自在さは減じてオーセンティックな感覚になって来ました。「パリのアメリカ人」とピアノ協奏曲がカップリングされています。 三回目は84年のフィリップスの録音で、音質的にはこれが最も良いと思います(写真下)。オーケストラは ピッツバーグ響で、アメリカのものに戻りました(単にそのとき音楽監督だった楽団でやっていたに過ぎません が)。冒頭のクラリネットも、途中のもって行き方も少し軽く、あまり粘らせません。テンポも初回とほぼ同じに戻りました。ただ、ピアノの演奏マナーは、動きはあるけれども自由自在さは多少減り、初回よりも洗練されていて、聞き方によってはおとなしくて品があります。しっとりとしているというのでしょうか。弱音がきれいで、やわらかさも感じられます。テンポ以外、形としては二回目に近いです。トータルでは、オーケストラとピアノによるクラシックの作品としては最も完成度が高いとも言え、初回とは雰囲気が違って大変悩みましたが、別の意味で良いので♡♡にしました。ああ、プレヴィンはクラシックのピアニストになったのだなという感じであり、大人の味わいです。五十五歳のガーシュウィン、ということでしょう。そして、これも「パリのアメリカ人」とピアノ協奏曲のカップリングです。ピアノ協奏曲はラプソディー・イン・ブルーの翌年に、グローフェの手は借りずに自身でオーケストレーションを試みた作品であり、独学でやり遂げるという天才ぶりを発揮しています。それでもまだ方々に頭を下げ、「技法を教えて」と頼んでいたわけです。  George Gershwin plays Rhapsody in Blue George Gershwin (pf) Michael Tilson Thomas (cond.) Columbia Jazz Band ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ジョージ・ガーシュウィン(ピアノ) マイケル・ティルソン・トーマス / コロンビア・ジャズ・バンド 次に、ユダヤ系アメリカ人演奏者第三弾のマイケル・ティルソン・トーマスに移りますが、その最初としてまず彼のピアノではなく、なんとガーシュウィン自身のピアノ演奏で、録音も1976年という、新しくてコンディ ションの良いものについて触れます。それは自動演奏のピアノロールにオーケストラが後出しで合わせたものです。バックはティルソン・トーマスのジャズ・バンドであり、小粋な崩しが理想的です。ピアノ独奏版のロールからパートを抜き出して上手にオーケストラ版として使っています。 実はこのウェブサイトの 最初の記事で、このアルバムのピアノの音については勢い余ってネガティブな物言いをしてしまいました。基本的な認識の点では変わらないところもあるのですが、ここで思い切って改めようと思います。特にリマスターされてジャケットに黄色い縁取りがされたもの(写真)については、ハイが強調されたこともあって眠い感じはないし、きれいなタッチに聞こえるところも多いです。4、5キ ロか ら7、8キロヘルツの間で上手に調整すると、その分だけブラスの輝きはきつめになるけれども、ピアノは倍音が強調されてくっきりとした音になります。 普通に聞いたら人間が弾いている感覚が十分あって、機械の演奏だとは感じられないレベルであり、楽しめる上にガーシュウィンの弾き方も分かって大変価値のある一枚だと思います。 特にテンポの動きは機構的にガーシュウィンの演奏そのものだと言えます。言いたかった問題点はもっぱら タッチ、強弱の点についてなのです。ピアノロールには種類があり、ガーシュウィンの時代にはその後期型であるリプロデューシング・ピアノという種類が出て来ていました。以前のものは強弱が再現出来ませんでしたが、そのタイプになってからはできるようになりました。アメリカは「デュオ・アート」のエオリアン社、アンピコ社、ドイツのウェルテ=ミニョン社などのメーカーが競い合っていたのです。しかし強弱が再現できるといっても、元の演奏者そのままのタッチかどうかは怪しいものです。録音時に強弱のあり方を記録できるアンピコには A や B などのタイプがありましたが、どちらもスイッチの切り替えや自動化される部分のちょっとした仕様が違うだけで、クレッシェンド、ディミヌエンドは空気圧によって無段階連続的に大きくなったり小さくなったりするものの、始まってから何秒でその行程が完了されるかによって異なる幾つかの種類から選ばれるようになっており、単音に至ってはそこにゲートが設けられるようにして ppp から fff までの7段階ほどに局限しています。本来のピアニストのタッチが無段階で多彩なのに対して、まあ必要最小限というところでしょうか。そしてデュオ・アート に関しては録音時に演奏者の強弱は自動的には記録されず、見ている技術者がメモをしておいて後から段階分けをして再現するので、強弱はあっても、原理的には奏者のニュアンスとは別物となります。そしてガーシュウィンは十八歳のときにデュオ・アートのエ オリアン社で技術者として仕事をしており、そこと専属契約を結んでもいますので、彼のピアノロールはほとんど全てがデュオ・アートのものなのです。ここでのラプソディー・イン・ブルーも1925年のデュオ・ アートです。1932年のアンピコ B で演奏している同曲の映像がウェブにも出ていたりしますが、どの段階がアンピコなのか分からないし、タッチはより曖昧に聞こえます。そんなわけで、強弱についてはこの CD、参考にしかならないでしょう。でも面白い企画という点ではこれ以上のものはありません。 ピアノロールの説明が長くなってしまいましたが、そのピアノ演奏で分かることは、ガーシュウィンその人の演奏は、テンポは軽妙自在に動かすスタイルで、 当時のジャズの、あるいはラグタイムの、かもしれませんが、時代の雰囲気がある一方で、性質としては案外素直に聞こえるということです。ピアニストとして節度があり、崩れ過ぎずに大変洗練されているのです。軽くルバートしながら、一連のフレーズの最後の音の前で少し間を取ってからコツン、と遅らせて強めに叩く傾向も聞かれ、技術者が正確に再現しているのであれば当時のピアニストに共通する運びのようでもありますが(SP 録音でははっきりしません)、バーンスタインのように遅く粘らせる強調というよりは、むしろさらっと走り出すようなところが多い感じです。そのせいで、その速くなるところに後で合わせるオーケストラが苦労しているというコメントも見受けられるものの、オリジナルの1924年録音でも多少そうだし、他の演奏者のジャズ・バ ンドとのセッションでもそんな具合に走っているので、これはスタイルの問題なのだろうと思います。その気ままに駈ける感じは、どうやらプレヴィンも、ティルソン=トーマス自身のピアノも踏襲しているようです。 コロンビア原盤 CBS/ソニー・クラシカルの1976年の録音は上述の通り、オーケストラは抑えて、ピアノはくっきりと、という編集ができればパーフェクトながら、コンディションは良いです。カップリングは元は「パリのアメリカ人」でしたが、CD 化し、またリマスター盤が出るに及んで色々と組み替えがあり、ものによってはボーナス曲が含まれたりもしています。 余談ですが、ソング・ブックの演奏も、ピアノロールによるガーシュウィン自身のものが出ています (Gershwin Plays Gershwin / The Piano Rolls, Nonsuch1995)。「パリのアメリカ人」も入っています(ピアノだけの版を本人が弾いてます)。グールドの ‘Re-Performance’ 同様、最終的にヤマハの Disklavier に起こしており、タッチが多少眠いのは仕方ないとして、本人のテンポ感覚を知るための参考にはなるかもしれません。案外等速というか、元からジャズ畑の人の弾き方よりはずっと端正です。ここに入っているソロ版のラプソディー・イン・ブルーも含めて、上でティルソン・トーマスとやってる演奏ともまた幾分印象が異なりました。  Gershwin Rhapsody in Blue Michael Tilson Thomas (pf/cond.) Los Angeles Philharmonic ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー マイケル・ティルソン・トーマス(ピアノ/指揮) ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 1982  Gershwin Rhapsody in Blue Michael Tilson Thomas (pf/cond.) New World Symphony Orchestra ♥♥ ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー マイケル・ティルソン・トーマス(ピアノ/指揮)♥♥ ニューワールド交響楽団 1997 ガーシュウィンのピアノロールではなく、ティルソン・トーマス自身のピアノによる演奏がその後二つ出ています。ロスアンジェルス・フィルハーモニックとの1982年盤(写真上/CBS コロンビア=ソニー・クラシカルのデジタル録音)と、ニュー・ワールド交響楽団との97年盤(写真下 /RCA)です。その前のピアノロールの録音共々、スコアは1924年のオリジナルのジャズ・バンド版を使っています。グローフェは関わったけど、二年後に補筆完成させたオーケストラ版ではありません。初演のジャジーな雰囲気にこだわっているようです。 マイケル・ティルソン・トーマスはバーンスタインより二十六、プレヴィンより十五歳下のアメリカの音楽家 で、LA でユダヤ系の家庭に生まれ、ハリウッドで育った人です。祖父はロシア出身だけれども、若いガーシュ ウィンも通ったイディッシュ(ユダヤ語)劇場のスターであり、後にニューヨークで自身のシアターを営んでいます。そこではガーシュウィンの兄弟たちも仕事を始めました。また、祖母も女優であり、親族にはガーシュウィン本人と友達だった人もいます。父親はブロードウェイの舞台主任で、祖父と父は共にガーシュウィンにピアノを習ったのだそうです。ショー・ビジネ スには元々縁のある環境だったと言えるでしょう。そのティルソン・トーマス、指揮者としては美的に洗練され、構成のしっかりした整った演奏が印象的だった一方で、近頃の熟成ぶりは目覚ましく、内的なテンションに満ちて配慮の行き届いた敏感な演奏は完璧で目を見張ります。1996〜2020年までサンフランシスコ交響楽団の音楽監督で、現在は桂冠です。 ハリウッドでは亡くなる直前にガーシュウィンも仕事をしていたわけです。それと、上記のような環境でその空気を吸って生きて来たこともあり、さらにガーシュウィン自身のピアノロールに合わせて指揮をした経験もありで、ティルソン・トーマスこそこのラプソディー・イン・ブルーをやるのにぴったりな人、という言い方もできるかもしれません。 二つの録音のうち LA フィルとのものは、どういうのでしょうか、前に録音したガーシュウィンのロールを意識したアクセントが聞かれ、しかしそれよりも軽量感と敏感さがあって、多少前のめりでかなり素早い動きが目立ちます。音符が混んで幾分せかせかした感じに急ぐところもあります。 テンポの揺れは大きく、いわゆるジャズっぽい演奏です。ジャズの本家プレヴィンと比べると、その一番ゆったりな二度目の録音はもちろん、最初のジャジーなプレイにおいても、プレヴィンの方が余裕をもって揺らしており、重さとまでは言わないけれども自由な中にもフレーズに節度があります。それでもこのティルソン・トーマスも、続けて聞いていると割とかっちりと凝縮しているというか、詰まって聞こえるところがあります。それはゆっくりの方に大きく振る印象が薄いからでしょう。堅くて生真面目な演奏という意味ではなく、十分にスウィングしていて、途中でたわんだりはしっかりとあり、速いところでのみ、多少テンションに耳が行くわけです。あまり良く思ってないような物言いになってしまいましたが、平坦で優等生的な運びではなくて大変いいです。魅力ある演奏です。 一方で後発のニュー・ワールド交響楽団とのものはびっくりするぐらい良かったです。よりリラックスして自在に音を揺らし、間の取り方も大胆になって、ガーシュウィン自身のピアノの構えのない雰囲気に近い気がします。ただしそれはあくまでも雰囲気の問題であって、テンポはもっとゆったりになっており、最初のガーシュウィンのピアノのものから順次、トータルタイムでそれぞれ2分ほど長くなって来ています。つまりピアノロール版より4分ほど遅いわけです。延び縮みする抑揚の、延びる方の側が大胆になると同時に、落ち着きが出て来たとも言えるでしょう。ガーシュウィンの弾き方を知っていてテンポの動かし方が似ているアール・ワイルド(アーサー・フィードラー/ボストン・ポップス 1959)と比べると、ティルソン・トーマスが軽い質で柔軟な感じであるのに対して、技巧派のワイルドは形は似ていてももう少し強靭な部分があるでしょうか。 同じようにジャズのフィーリングが味わえる演奏で素晴らしかったプレヴィンの最初の盤の活気と比べると、 特にそのゆったり揺らすところが印象的です。といっても、同様に遅いところがあるバーンスタイン盤とはこれまた全く違って遊んでいるような軽さが際立っており、それでいてジャズ・ピアニストのハービー・ハンコックがやるほどに大胆な遊び感覚でもなく、同じように自由で楽しげながら、細かなもって行き方に洗練された美も感じさせます。説明が難しいです。でもこの録音、ラプソディー・イン・ブルーのオー ケストラとのものではベストの演奏じゃないでしょうか。聞いてて乗れるしくつろげます。 ニュー・ワールド交響楽団はフロリダにティルソン・トーマスが設立した、若い世代の育成を目的としたオーケストラです。 1997年の RCA の録音がまたこの曲最高という出来です。しなやかで豊かな低音に自然で艶やかな高音、ブラスは元々がそういう音だから十分ビビッドだけれども、大きな音で聞いてもやかましさを感じません。細かい音も拾い、ピアノの倍音も繊細です。プレヴィンのフィリップス盤とラベック姉妹のデッカ盤も大変優秀な録音だったけど、これはその上を行くかなとも思います。カップリングの「パリのアメリカ人」とピアノ協奏曲は98年のサンフランシスコ交響楽団とのもので、協奏曲のピアノはギャリック・オールソンです。録音技師は全てドイツ人のマーコス(マルクス)・ハイラントで、リマスタリング・エンジニアも同一であり、音的には統一性があります。 これ以外にもユダヤ系アメリカ人のパフォーマーによる演奏はレヴァイン盤やスラットキン盤など他にもまだあり、それぞれに良い演奏だと思いますが、このページではファンの方にお任せということで割愛させていただきます。  Gershwin Rhapsody in Blue Katia & Marielle Labéque (pf) ♥♥ Riccardo Chailly The Cleveland Orchestra ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー カティア & マリエル・ラベック(ピアノ)♥♥ リッカルド・シャイー / クリーヴランド管弦楽団 オーケストラなしのデュオによるラベック姉妹の演奏は上ですでに取り上げました。一方この盤はその連弾の上に管弦楽が付いていて、我々が最も馴染んでいる形に聞こえていますが、連弾の楽譜にはオーケストラのパートも あるわけですから、ピアノがその部分を弾かないのに二人いるというのはこの人たちの盤独自のものです。ガー シュウィンにはそういう版はなかったと思います。 ラベック姉妹はフランスの人たちで、作曲家のラヴェルと同様にピレネー山脈に近くてスペインにも跨がる民族系統不明のバスク地方出身です。1950年と52年生まれですから双子ではなく、マルグリット・ロンからピアノを習ったというイタリア系の母に幼少期から手ほどきを受け、最初は現代音楽の分野から始めました。事実上のデビューのような形になるのは80年録音の上記オーケストラなしの方のラプソディー・イン・ブルーのアルバム・リリースで、50万枚以 上売れたという出来事です。ジャケットでは二人並んで顔が写っている意匠が定番である通り、美人姉妹ということで人気が出たと言えるのでしょうが、それだけではなくて実力もしっかりとある人たちです。そしてもう一つ。彼女たちはジャズも弾けるようです。バーバラ・ヘンドリクスがガーシュウィンを歌うフィリップスの1981年のアルバムでは、リズムは真っ直ぐながら堂々とジャズの伴奏を務めています。 結論から先に言ってしまうと、ここで取り上げるデッカのラプソディー・イン・ブルーはフランク・ブラレイ、プレヴィンの二つの録音、ティルソン・トーマスのニューワールド・シンフォニー盤などに混じって、同曲の最も魅力的なパフォーマンスの一つだと 感じています。その演奏マナーについてはすでにピアノだけのデュオのところで述べていますが、基本的にはそれと変わりません。切れの良い技術的にダイナミックなところと、フランス出身らしい動きのある小粋な拍節が聞かれ、歌も洗練されています。後で触れるロルティのようにさらさらと前のめりに速く駈けるようなところは少なく、バーンスタインのように遅くがっちりと音にする方向にも寄らずなので振り子は大きくはないものの、リズム感の良い揺れが絶妙です。別の言い方をすれば表情豊かで優等生ではないながら、恣意的な崩れはなくてどこも的確な乗りというのでしょうか。パーフェクトなバランスです。 オーケストラなしの80年盤と比べるとどうでしょうか。基本的には変わらないと言った通りですが、オーケストラが鳴らすパートではピアノは休みます。 オーケストラは元気な部分も多いので、全体としては強いタッチの元気なピアノという印象はむしろ薄れているかもしれません。しかし同じくピアノが活躍するパートで比べると必ずしも静かになったわけではなく、むしろよりくっきりとした音色が目立つところもあったりして、弱音に沈む表現が多いのはピアノ連弾による旧盤の方かもしれません。このオーケストラ伴奏盤は大変まとまりの良い感じがします。 そして言い忘れてはならないのはバックのオーケストラです。これが大変魅力的なのです。クリーヴランド管が巧いのはもちろん、 指揮者のシャイーはオペラ的な歌が得意という印象がありましたが、ここではそのしっかりとした上手な抑揚と立体感のある運びが実にいいのです。この盤のポイントの一つです。 1985年のデッカの録音は相当な優秀録音です。ガーシュウィンの管弦楽曲での一番の一つだと言っていいでしょう。それもこの盤の大きなポイントです。デッカなのでフィリップスより輝き過ぎるかと思うと必ずしもそうではなく、くっきりと鮮度が高いものの、耳に痛いまでは行かずに艶と張りがあって明るく、ピアノも粒立ちが良くて透明感があります。グランカッサなどの低音はやわらかく低く、肉付き良く鳴り渡ります。レコーディング・エンジニアはコリン・ムーアフットとなっています。カール・ ベームの「ロマンティック」交響曲(ブルックナーの4番)を担当した人です。 カップリングは定番の 「パリのアメリカ人」はまずあり、それがまた同曲一番かという出来だし、それから優しくて美しい「子守歌」が聞けます。元々は弦楽四重奏用のものを弦楽合奏にしたもので、これが入ってるって多くはないので嬉しいです。そして二週間のキューバ旅行の後にすぐに書き上げた「キューバ 序曲(1932)」もあるけど、シャイーのこの演奏、これもこの序曲のベストの一つじゃないでしょうか。ガーシュウィンは現地の音楽に接して大変興味を持ち、インスピレーションを掻き立てられたようです。ボンゴやマラカスなどのパーカッション楽器が取り入れられています。パリのアメリカ人のときのタクシーのホーンと同様に、それらの楽器を現地から持ち帰ったということだけど、まったく何でもあっという間に吸収してしまう人です。元気の良さと同時にこの作曲家らしい叙情も聞けます。こうして「ラプソディ・イン・ブルー」だけでなく、「パリのアメリカ人」も キューバ序曲も最高の演奏と録音で聞けてしまうこのアルバム、大変お得な一枚と言えます。  Gershwin Rhapsody in Blue Peter Donohoe (pf) Simon Rattle City of Birmingham Symphony Orchestra ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ピーター・ドノホー(ピアノ) サイモン・ラトル / バーミンガム市交響楽団 これ、ラトルも外せないんじゃないでしょうか。といってもピアノはラトルのお気に入りのイギリス人ピアニスト、1953生まれ のピーター・ドノホーであり、曲としてはそちらをメインに考えるべきではありますが。 バーミンガム時代のラトルは光ってました。最近もまたロンドンで活躍していて新しい録音もいくつか出て来てますが、オーケストラの解釈においては大変知的で工夫が効いており、過剰な振りは見せないけど当時の他のオーソドックスな解釈の指揮者の間にあっては独特の目立ち方をしてました。そういう巧者なところは、ジャズ的なリズムの曲でも実力を発揮するのではと期待させます。そして期待に違わず、管弦楽はメリハリが効かせてあって、急に強くしたり速くしたりと意欲を見せ、頑張っています。ジャズバンドの演奏というのとは違いますが、クラシックのオーケストラとしては表情が豊かだと思います。 一方でこちらが中心と言ってもよいピアニストのドノホーですが、逆にイギリス紳士とは言わないけれども品が良く、繊細に歌いつつもはみ出したことをしないまとまりがあります。比較的あっさりさらっとしたピアノで、フレーズを前に倒し気味に駈ける方がどちらかというと得意で、ためは使わず、ジャズの揺らしとかではないまとまりの良さを見せています。クラシックのピアニストとしての良識を発揮しつつ表情もよくついている演奏だと言えるでしょう。特に弱音が大 変きれいだと思います。 レーベルは EMI で、録音は1986〜87年です。しっかりした水準の録音です。カップリングはソング・ブック18 曲全部とピアノ協奏曲です。  Gershwin Rhapsody in Blue Louis Lortie (pf) Charles Dutoit L’Orchestre Symphonique de Montreal ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ルイ・ロルティ(ピアノ) シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団 このページではデュトワのオーケストラものは高確率で♡♡を付けて来た気がします。繊細な歌のセンスで比較的ゆったりきれいに歌わせるところが好みだ し、楽譜を分解して読み込んでいるのか、混んだところでも音がダマにならず、透明度高くよく構築された音楽を作るレベルの高い人という印象です。過度に感情的に押したりもしません。ガーシュウィンの有名曲も管弦楽曲のジャンルですから自然と期待がかかりますし、不思議とフランス風の演奏が合ったりする作曲家でもあり、フランス文化の香りが高いデュトワならなおさら良さそうです。関係ないですが、何となくレヴァイン盤とジャケットの意匠が似てます。 そしてオーケストラはやはりテンポはゆったりめに始め、しっとり滑らかによく歌わせています。このラプソ ディー・イン・ブルー、これはカナダだけど欧州伝統の音作りというか、正統派の管弦楽という感じに仕上がっています。デュトワはどちらかと言えばどっしりと伝統の中にはまっているタイプの人ではない印象ですが、これが案外、ジャズ・バンド風ではない正統クラシックでやるとこうなるか、という出来になっていて興味深いものでした。 ピアノを受け持っているロルティはフランス人かと何となく思ってたけど、実は1959年生まれのカナダのピアニストでした。ラヴェルではその繊細な崩し方の癖があまり好みではなかったけど、ジャズっぽい曲だといいかもしれません。 聞いてみたところ、そのピアノはまず軽量、という印象が最初に来ました。バーンスタインなどとは反対の指向性です。テンポの崩し手法はありますが、全て前倒しに、省略的に駈ける方向の表情のつけ方です。その速くさらさらっと行くところはドノホーより顕著です。それに合わせてオーケストラも、その部分ではかなり速くなります。押し付けの強くない種類の演奏ということで、基本はゆったりが得意なデュトワとはその面だけは反対ながら、繊細な印象を与えるところでは等質で、相性が良いとも言えるでしょう。 1988年のデッカのデ ジタル録音です。割と華やかな管弦楽に対して、軽くて少し引っ込み気味のピアノのバランスであり、かといって音はオフではなくきれいに響いています。ブラスやシンバルは高温がしっかりしています。取り立てて変わったところはないバランスだけど、水準以上の録音だと思います。多少明るめでしょうか。 カップリングは「パリの アメリカ人」と、交響的絵画「ポーギーとベス」、キューバ序曲というものです。  Gershwin Rhapsody in Blue John Nakamatsu (pf) ♥♥ Jeff Tyzik Rochester Philharmonic Orchestra ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ジョン・ナカマツ(ピアノ)♥♥ ジェフ・タイジック / ロチェスター・フィルハーモニック管弦楽団 これも大変魅力的なラプソディー・イン・ブルーです。1968年にシリコン・バレーのサン・ノゼで生まれたピアニスト、ジョン・ナカマツは両親の名前からしても日系のようですが、ヴァン・クライバーン・コンクールの初のアメリカ人優勝者です。そしてこのガーシュウィンのアルバムは彼の出した中で最もヒッ トしたものではないでしょうか、ビルボードのクラシック部門のトップに輝いています。 演奏の方ですが、そのマナーは日系とか何かそういうことを心配する必要はなく、堂々としたアメリカ人の、アメリカ文化を十分に吸収したスタイルと言って良いと思います。こういう曲の歌心を捉えられる能力を備えた人です。元々はクラシック畑の人のようです から(他に出てるアルバムは全て純クラシカルの曲ばかりです)、根っからのジャズの人のイディオム、リズムの取り方や揺らしとは多少違うかもしれませんが、大胆にテンポを動かしつつ大変乗りが良く、強弱も自在でスタッカートなどの使い分けも意のまま。小気味良いグルーヴで言うことがないです。軽過ぎはしないけど深刻さと押す感じもありません。ジャズ・ピアニストがよくやる、部分的にスキップするような拍の崩しだって混ぜて来ます。この人は元々子供の頃から茶目っ気があって、ガーシュウィン同様に近所を走り回る悪戯っ子だったりしたのでしょうか。それでいて速いパッセージではきれいに揃えて流れるよう に、クラシカル分野のピアニストらしい技術と品の良さも感じさせます。大胆なのに上質。ガーシュウィンとしては両面あって理想的ではないでしょうか。弱音のデリカシーと叙情もあり、これはいいです。 オーケストラを指揮しているジェフ・タイジックはトランペット奏者でもあり、様々な曲をジャズ・フレーバーのポップなオーケストラに編曲することで有名な人です。曲に相応しい布陣だと思います。 2006年ハルモニア・ムンディ USA の録音も優秀です。芯はありつつ輝き過ぎず、適度な艶のあるピアノの音が堪能できます。オーケストラも 華やかになり過ぎてやかましいということがありませ ん。SACD ハイブリッドです。 カップリングはピアノ協 奏曲とキューバ序曲です。  Gershwin Rhapsody in Blue Stefano Bollani (pf) ♥♥ Riccardo Chally Leipzig Gewandhaus Orchestra ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ステファノ・ボラーニ(ピアノ)♥♥ リッカルド・シャイー / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 次はジャズ・ピアニスト による演奏です。でもジャズを弾く人が皆同じなわけはなく、一人ひとりがその独自の個性で弾いていると言った方がいいでしょう。ここで取り上げるステファノ・ボラーニは、ジャズの人としては珍しく力の抜けたタッチが聞かれ、やわらかく歌うように運ぶところのあるピアニストだと思い ます。すでにジャズのページ(「クラシック音楽ファン向きのジャズ?」) ではこの人のアルバムに触れていました。1972年ミラノ生まれで、様々なジャンルのミュージシャンと組んだり、かなり実験的な試みをしたりしています。イタリア人だからといって熱いカンタービレというわけではなく、情緒に流されず、浮遊感のあるちょっと不思議な音選びで、静けさがあって懐かしい感じがします。同じイタリアのジャズ・ピアニスト、エンリコ・ ピエラヌンツィがオペラの歌心でメロドラマティックに、多少センチメンタルなまでに耽溺するのとは違います。ガーシュウィンには楽譜があるので即興でコードを選ぶというわけには行かないはずなんけど、それでもこの人らしい同じ性質がクラシックの分野でも発揮されるでしょうか。 バックはラベック姉妹の盤でも見事な演奏を聞かせていたシャイーの指揮で、ヨーロッパ伝統のオーケストラ、ゲヴァントハウスです。 ピアノは案外重く始まり、やわらかく優しい方の音になっています。初めのうちは、間を空ける運びはやはり ジャズの人かな、延び縮みがあって延びる方が独特だなと思って聞いていました。やはりタッチは繊細で、キーを強く叩くジャズ・ピアニストの傾向、もしくはヴァーチュオーゾ的なところは感じられません。奥底にどこか上品さがあるのです。しかし段々この人 の本領が発揮されて来ます。まず右手と左手をわざとずらして同期を外すような手法が聞かれ、これなどはクラシックの人には思いつかないというか、手が出せない分野でしょう。フレーズに節を作るのもそうです。やはりガーシュウィンはこういう方が面白いです。そしてその世界はどんどん展開されて行きます。即興のフ レーズを瞬間的に作り出して飾りとして加えて来るのには驚きました。禁じ手はどうやらないのです。楽譜から完全に外れて音を作り出しているところもあります。そういう箇所では当然元とは別のコードになってるわけで、その響きですが、彼のジャズ・アルバムで不思議なトーンの和音を多用していたのを思い出させ るような種類です。 さらにエスカレートして来て、だんだん止まるように遅くして、オルゴールが鳴り止むときのような効果で次のパッセージに引き渡したりします。そうしたオルゴール効果は、静かなところで高いキーを叩く少し調子外れな展開としても聞かれます。キーが調子外れなだけでなく、叩き方も均等に叩かず、壊れたようにずらしながらです。こうなると誰も真似できないでしょう。ジャズ界でもこういう感覚でやれる人は多くないのです。クラシックのピアニストには逆立ちしても真似できない世界です。跳ねるようなスタッカートへの切り替えも自在で、走ったり止まったり。ハンガリーのヨージェフ・バログもそういうのは得意だったけど、これはひらめき勝負のショーです。そして強い音もしっかりと出しますが、それでも繊細な感性を持った自由人という感じなのが面白いです。このボラーニの演奏、技ありという意味でラプソディー・イン・ブルーで最も感心したピアノということになりました。 オーケストラもよくぞこの世界について来れたものです。パーカッションは独特の目立ち方で普通じゃないし、ブラスなんかジャズ・バンドみたいな崩しがあります。ヨーロッパは今やジャズ・ミュージシャンの宝庫でもあるわけで、伝統的な一流のオーケストラはこういう対応もできるのかと驚きます。全体に遊びが聞かれ、この音楽的理解力は指揮者共々並大抵のことではない気がします。シャイーがすごいのか、オケがすごいのか、とにかく見事です。 一つちょっとだけ残念なのは録音です。決して悪くないのですが、オーケストラは同じデッカのデュトワ盤と同様に明るく、もうちょっと生の潤いがあった方が良いかぐらいにハイが前に出るので、結構元気です。ブラスもパーカッションもくっきりと輪郭が立ち、しゃんと上まで、華やかに伸びています。それはそれでいいです。一方でピアノはあまり高周波が目立つバランスではなく、どちらかというとしっとり系で、音が引っ込み気味で目立たない方向なのです。逆だといいんだけど、オーケストラに多少音響面で負けてる面もあるように感じました。2010年の比較的新しいライヴ録音です。 カップリングは交響組曲 「キャットフィッシュ・ロウ」(ポーギーとベス組曲/S.ボーエン編曲/この中の キャットフィッシュ・ロウの部分には、ヴァイオリンのソロで泣くように始まって色々な楽器に受け渡される「サ マータイム」が入っていますし、「フーガ」は何だか春の祭典のようです)、ピアノ協奏曲(1925)、リアルト・リップルズ(1917/ラグ)です。  Gershwin Rhapsody in Blue Herbie Hancock (pf) Gstavo Dudamel Los Angeles Philharmonic ガーシュウィン / ラプソディー・イン・ブルー ハービー・ハンコック(ピアノ) グスターヴォ・ドゥダメル / ロスアンジェルス・フィルハーモニック もう一人、ジャズ・ピアニストの演奏を見てみます。でもこれは CD ではなく映像配信であって、DVD ですらないので参考までです。ビデオ・オン・デマンドのメディチ TV や各種ストリーミング、YouTube でも見ることができます。そういうことなので♡マークの対象外とします。 2011年の音楽祭のライヴで、演奏はハービー・ハンコックのピアノにドゥダメル指揮の LA フィルです。ハービー・ハンコックはマイルス・デイヴィスのバンドにいたことのある有名なプレイヤーで、ジャズ・ファンなら皆知ってる人です。これも上のリンクのジャズのページですでに美しいソロのアルバムを取り上げていたのですが、美しいという形容が一番ぴったり来る人というよりも、コードの選択から何から先が読めないし、凄過ぎて何してるんだか分からない、とジャズやってる人は言ってました。ジャンルを超えて様々なタイプの演奏家とコラボレートするのはステファノ・ボラーニと同じで、いわゆるジャズのセッションでも、ホーンのバックに回ったりするので性格が分かり難いことは事実でしょう。系統を言うのも難しいですが、音の選び方ではクレア・フィッシャーの影響を受けているようです。 ここでの演奏は、面白いです。思うままに遅くしたり走ったりのテンポ設定で、好きなだけ間を空けます。途中で止まりそうに怠けたり、突然スキップしたり、茶目っ気たっぷりというのでしょうか。叙情的なところで大胆にスローダウンしてうんと静かにやるきれいさはあったりするものの、これはもう、ガーシュウィンというカンバスの上で安心して楽しいお絵描きをしてるのであって、理屈抜きで一緒に楽しむのが最善です。指揮者のドゥダメルもピアノ独奏の部分で 「なんか気になるぞ」というようにだんだん彼の方に体を傾けて来て覗き込んだり、「ほう、そうやる?」と驚いた顔をしてみせたりニヤけたりで、その打ち解けた姿はご機嫌なときのジャズマンのようです。ドゥダメルは振りが大きい人なので特に得意な方ではなかったけど、これは楽しそうでいい感じです。 そういえばちょっと似た感覚で大胆な動きをするピアニスト、ラン・ランも自身のアルバムでラプソディー・イン・ブルーを取り上げていて、そこではこのハービー・ハンコックと二台で競ってます。それが何となく息が合っていて、やっぱり案外面白いわけです。そっちは CD が出ています。  Gershwin's Worold Herbie Hancock ♥♥ ガーシュウィンズ・ ワールド / ハービー・ハンコック ♥♥ もう一つ、ハービー・ハンコックのガーシュウィンのアルバムがあります(CD です)。「ガーシュウィンズ・ワールド」というタイトルの1998年のもので、こちらは完全にジャズの様式なので、普段からハービーを聞くなどしてジャズの世界の言葉遣いが分かる人には面白いかもしれないけど、クラシック耳の方にお薦めできるかどうかは謎なので軽く触れるだけにします。そういうことを抜きにすればいいアルバムだと思います。オープニングはまるでサンタナの「キャラバン・サライ」みたいなパーカッションで、次の曲は、今マイルスのバンドにいるのかという感じのミュート・トランペットをテナー・サックスが受け取り、そこにどこかひんやりとした、いかにもなコードのピアノが抽象的に絡むといういつものハービー・スタイルです。また、おしゃれなコード進行に伴われたボーカルもあり、ジョニ・ミッチェルのサマータイムも聞けます。スティーヴィー・ワンダーの歌とハーモニカにウェイン・ショーターのサックス(フリーっぽいです)もありで、この人のアルバムらしく様々な世界の有名人がたくさん参加していて、この分野で大変ヒットしたアルバムです。美しいピアノ協奏曲の第二楽章がガーシュウィンではなく、ラヴェルになってるのが面白いです。見事な運びで、ジャズの即興がどういうものかがよく分かります。そして最後の曲には、この人の洗練された叙情性のあり方がよく表れています。 |