|
「ポーギーとベス」
+ ガーシュウィンのジャズ・スタンダード曲 Porgy and Bess + Jazz Standard Songs of Gershwin 
John's Diner with John's Chevelle 2007, John Beader, Transformed
ジャズ・スタンダード曲はこちら 「ラプソディ・イン・ブルー」のページはこちら 「パリのアメリカ人」のページはこちら ポーギーとベス ガーシュウィンの代表作として「ラプソディ・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」などの管弦楽作品、「スワニー」などのジャズ・スタンダード曲と並んで、最も有名なものに「ポーギーとベス」があります。1935年に作曲されたオペラです。ストーリーはデュボーズ・ヘイワードというサウス・カロライナの小説家が書いたもので、それを読んだガーシュウィンが面白いと思って共同でオペラにすることを提案し、兄のアイラが作詞をして三人で作り上げました。三人とも白人なのに、話はアフリカ系の人々の生活であり、ガーシュウィン自身はフォーク・オペラと呼んでアフリカ系の人々のみでの上演を望みました。スティーヴ・マーチンのおかしなコメディ映画に「天国から落ちた男(The Jerk)」というのがあって、黒人の大家族に育てられた白人の主人公が変な格好で踊って自分は黒人だと主張する無茶な設定になってましたが、この三人組のオペラは、どうやったらこんなにリアルでディープなアフリカ系住民の世界を描き出せたのでしょうか。人種への偏見に基づいているという意見もあるようですが、それは今日的人権の観点でしょう。 物語は虐げられたというか、社会的な差別を受けた貧しいアフリカ系の人々が住むサウス・カロライナの海岸沿いの地区(フロリダ半島の付け根を少し北に上がったチャールストン)、1920年代のキャットフィッシュ・ロウで巻き起こる騒動を扱っており、その世界らしい愛憎劇となっています。貧困と差別、賭博と犯罪、麻薬の蔓延が話の横糸というか背景に存在していて、ストーリーの縦糸も大事だけど、恐らくは全体としてそうした世相を描いた作品だと言えるでしょう。主な登場人物は、足が悪くて自分の力で稼げないので乞食になっているポーギーと、彼が恋心を寄せている女性で給仕の仕事をしている薬物中毒のベス、その情夫で港湾労働者の暴力的な大男クラウン、ベスに薬物を売っている売人のスポーティン・ライフ の四人です。大変シュールです。 あらすじ あらすじは以下の通りです。最初の大きな事件はクラウンが賭博で喧嘩をして相手を殺してしまうという場面で、警察から逃れるために彼は逃げます。するとベスは内縁の夫が逃亡してしまったので、ポーギーの愛を受け入れて一緒に生活することにします。 しばらく経ったある日、キャットフィッシュ・ロウの住人たちはボートで離れ島にピクニックに行くことを計画します。ポーギーは足が悪いので残ることにし、ベスは出かけます。しかし島には逃亡中のクラウンが身を隠しており、ベスを茂みに連れ込んでしまいます。結局ベスはクラウンにまた身を任せます。 後日熱を出して島から帰って来たベスをポーギーが看病していると、そのクラウンがベスを取り戻そうと島から戻って来て、そこで二人はもめた結果、今度はポーギーがクラウンを殺してしまいます。警察には否認したものの、黒人なら理由なく犯人に仕立て上げられもする世界であり、ポーギーは連れて行かれて一週間勾留されます。 その間に売人のスポーティン・ライフはポーギーが一、二年は食らうだろうと言い、そそのかして薬物をベスに与えます。元々彼も女としてのベスを狙っていたのです。一週間後にポーギーが戻って来ると、ベスはスポーティン・ライフの言いなりになって一緒にニューヨークへ行ってしまっていました。ラストはポーギーが足を引きずりながら、あるいは山羊の引く荷車に乗って遠路ニューヨークへとベスを探しに出かけるところで終わります。 さて、この CD のページではオペラは基本的に扱いません。筋書きを見せるものは見るものであって、音楽だけ聞くものではないという考えからです。もちろんそんな考えを押し売りするつもりはありませんが、ここでは DVD を一枚取り上げるだけにします。この劇は特に、見ないとそのすごさが分からない種類でもあると思います。 ただ、このミュージカル寄りだともされるこのオペラ、その中には独立して魅力的なナンバーもあるわけです。印象的で有名になった歌はいくつかあるながら、アリアとして美しいメロディーといえば二つ、「サマータイム」と「アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー(一人称なのに三単現の S が付いているのはアフリカン・アメリカンの言葉だからです)」でしょう。 サマータイム このうち「サマータイム」はガーシュウィンと言えばこれ、という具合に代名詞的な存在とな り、ジャズのスタンダード・ナンバーにもなっています。漁師ジェイクの若い妻、クララが赤ん坊を抱きながら歌う子守唄で、後にハリケーンでジェイクの船が 転覆し、助けに行ったクララ共々死んでしまった後に、ベスもその子に歌って聞かせます。内容はこうです: 「夏の間、暮らしは楽さ。魚は跳ねて、綿は育つ。父さんは金持ちで、母さんは別嬪だよ。だから、しーっ、かわいい赤ちゃん、泣かないでおくれ。いつかはこんな朝のあるときに、お前も立ち上がって歌い出してさ、翼を広げて空に舞い上がる時が来るんだろうね。でもその朝までは、何だってお前を傷つけることはできないのさ。父さんと母さんがそばについてるからね」 生活の苦しい、気だるい感じで最初は歌い出され、後には赤ん坊が孤児になるという境遇の中で絞り出されるように悲しく歌われるのです。やるせない諦めのムードが漂います。 アイ・ ラヴズ・ユー・ポーギー 「アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー」の方も、メロディーは大変きれいだけど、どうしようもない歌です。女性の自立してなさでは演歌レベルですが、自分の側の愛着に基づくとも言えない点ではさらに上を行くでしょう。暴力の匂いもします。情夫クラウンのことを念頭に、ベスがポーギーに歌います。その意味するところは、省略して大体こんな感じです: 「愛してるわ、ポーギー。彼に私を連れて行かせないで。もしあなたが私を守れるなら、私はここにいたいの。いつか彼が私を呼びに来るって知ってるのよ。彼 は私を捕まえて、抱きしめて、そしたら私は消えてしまうも同然よ、ポーギー。彼がやって来たら、私は行かなきゃいけないって分かってるの」 メロディーの編曲 こうした曲たちを「見る」のではなく、メロディーを聞きたいという需要を満たすものとして、抜粋された編曲ものも存在します。 交響組曲「キャットフィッシュ組曲(1936)」は作曲者自身が編曲したオーケストラ曲で、 前のラプソディ・イン・ブルーのページで取り上げた CD では S・ボーエン編のものがステファノ・ボラーニとリッカルド・シャイーの演奏する盤に入っていました。 交響的絵画「ポーギーとベス」はロバート・ラッセル・ベネットの編曲で、ルイ・ロルティとシャルル・デュトワの盤に組み合わされてました。 また、「ポーギーとベス」による大幻想曲はアール・ワイルド編曲のピアノ曲で、「アメリカ! Vol.2」に入ってました。他にも二台のピアノ用の編曲でパーシー・グレインジャーの「ポーギーとベス」による幻想曲、というのもあります。 ジャズ によるポーギーとベスの有名な録音 それ以外にも聞けるものは色々ありますが、器楽編曲ではなく、ジャズ畑の人が歌ったものとして最も有名なのは、エラ・フィッツジェラルドとサッチモ(ルイ・アームストロング)によるスタジオ・アルバムです。 1959年のヴァーヴのモノラル録音で、オペラから選曲してラッセル・ガルシアがオーケストラ に編曲しました(このス コアには全曲版もあり、1956年の録音でポーギーがメル・トーメ、ベスがフランシス・フェイというものが存在します)。エラ・フィッツジェラルドはアフリカ系のジャズ・シンガーの大御所で、百戦練磨の老練な歌いぶりが有名です。ため息混じりでや れた場末の感じを出すのは得意であり、特にその音を引きずるようにずり上げたり下げたりする手法によって気だるい感じを出します。だからこの「サマータイム」なんかまさにうってつけかと思いました。ただ、この録音では時々コマーシャルなどでも耳にするルイ・アームストロングの哀愁のトランペットの後で、思いの外素直に、やわらかく歌っています。もっと濃いのを期待される方も多いかと思います。一方で サッチモがその後を引き継ぐ構成になっている歌の部分は、彼らしい独特の温もりを感じさせるだみ声(太い基音を伴ったしゃがれ声)で味わいがあります。 もう一つ印象的だったのはレイ・チャールズとクレオ・レーンによる1976年のジャズ・アレンジのアルバム です。レイ・チャールズはご存知かと思いますが、1930年生まれのソウル・ミュージック畑の盲目のシンガー・ソングライターです。ジャズ・シンガーじゃないけど、あのアフリカ系独特の声帯から発せられる、少しかすれた平たく力強い歌声と温かい雰囲気がいいです。この盤の「サマータイム」で は彼の方が先に歌い、女性が後に続くようになっています。後半のクレオ・レーンはこれまたハスキー・ボイスのため息混じりで、この曲にぴったりです。イギリス国籍のクレオ・レーンはジャマイカ人とイングランド人の間 に生まれているので、完全なアフリカ系を望んだガーシュウィンの狙いからは外れるけど、カー リー・ヘアーで見た目もそれらしいし、雰囲気があります。スキャットで有名なミュージカル女優です。そしてこの部分の歌のメロディー・ラインは多少アレンジされているので、意外性もあるかもしれません。レーベルはロンドンでステレオ ながら、これはどうやら単独では CD になってないようです。レイ・チャールズの「トゥルー・ジーニアス」という6CD アルバムで「サマータイム」だけが聞ける状況でしょうか。 サマー タイムのジャズとクラシックの名唱 ポーギーとベス全曲ではなく、「サマータイム」単独でのジャズ/ポップスの名唱は、などと言い出すと、それは収拾がつかないことになるだろうと思います。 録音はそれこそ山ほどあるからです。個人的には時間だけ過ぎて、これぞという好みのを何となく見つけられずに来ました。一般には悲劇や絶唱という意味でビリー・ホリデ イやジャニス・ジョプリンが絶対と言う方が多くいらっしゃると思うし、またそれは器楽だとジャズの帝王、マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーン(モダン・ジャズの開祖チャーリー・パーカーの案外聞きやすいのもあります)、オペラではキャスリーン・バトルなどの定番を出 すのと同じようなことになるのかもしれません。定番という意味では、先に挙げたエラ・フィッツジェラルドがアフリカ系のジャズ・ボーカルにおける最も有名なものですが、他にも生年順でアニタ・オデイ、サラ・ヴォーン、カーメン・マクレエなどもよく名前が聞かれます。あるいはニーナ・シモンであるとか。白人では日本で特別人気のある気だるいハスキー、ヘレン・メリルやペギー・リーかもしれません。それとももっと最近のノラ・ジョーンズ辺りでしょうか。もちろんそれらが最高かもしれないし、逆に知られざる誰それを発掘したぞ、という方もあるでしょう。探す楽しみのある曲です。ただしジャズ畑の新しい人は、自身のアルバムでいきなりこの種の曲をリリースして来たりはしないでしょう。多少なりとも名が売れてからが多いと思います。 それとこのぐらいのスタンダード曲ともなると、まんま歌うということも滅多にないわけで、歌本来のあり方を聞かせるというより、歌い手本人の個性を見せるための曲になっているところがあります。メロディー・ラインが分かり、素直に曲のきれいさを 堪能できるものがいいとなると、比較的最近の人ではベースも弾けるオーストラリアのニッキ・パロットぐらいでしょうか。もっと探すなら、これはもう、アフリカン・アンセスターではなくてコケイジャンで、本格ジャズ路線ではなくてグッドルッキング系のシンガーなどに見つかる傾向が高いと言えるかもしれません。見てキュートだったりセクシーだったりする歌い手さんはそこから注意が逸れないようになのか、決してテクニックを見せてばか走ったりばりばりやっつけたりしないし、崩し過ぎも避けることが多いようだからです。今さっとウェブでビデオを当たってみると、パパラッチに苦しむぐらいの人気女優、スカーレッ ト・ヨハンソンが上手に歌ったものや、シンガーソングライターのラナ・デル・レイの、プロモーショナル・ビデオのような映像があったりします。そのように映画向けだとか、あるいはむしろ素人に近い立場の人の歌の方が元歌らしいかもしれません。他にも、売り出し中で目を楽しませてくれるような人も何人もいたし、ノルウェイの「ゴット・タレント」みたいな番組で、八歳の少女が大人顔負けの妖艶さで歌っているどっきりもありました。 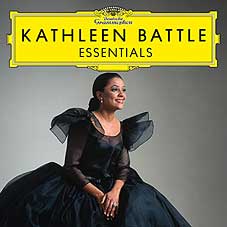 Summertime Kathleen Battle (s) ♥♥ サマータイム / キャスリーン・バトル(ソプラノ)♥♥  Summertime Barbara Hendricks (s) ♥♥ サマータイム / バーバラ・ヘンドリクス(ソプラノ)♥♥ オペラ歌手の名前も出たのでクラシックの歌手についても触れますが、上記のキャスリーン・ バトルは、振る舞いにおいては女王様のようだと言われるものの、オペラの声質で言うと軽い方のリリコ・レッジェーロに入るため、肝っ玉系ベルカントではなく、細く抑えたところから伸びる美しい声でゆったり歌い、力では押さずに洗練されていて、やはり定番と言われるだけのことはあります(写真上)。 アフリカ系シンガーに限定されるわけですから、他では同じ年生まれのバーバラ・ヘンドリクスもいます。対照的に UNHCR(難民問題)の親善大使を務める人ですが、ラベック姉妹の弾く見事なジャズ・アレンジのピアノに乗って歌う1981年のフィリップスのアルバムがいいです(写真下/ CD はありますが、現在は廃盤のようです)。元々透明で力のある声ながら、三十二歳のこのときは適度な気だるさを出し、若さと静けさも感じられて聞き惚れます。役のクララっぽくもあります。それともアルバムのコンセプトでしょうか。声質としてはバトルと同じリリコ・レッジェーロながら、少し低い感じもあるでしょうか。75年のマゼール指揮のポーギーとベス全曲盤でも歌っていて、そっちはもっと力強いです。他にもオーケストラをバックにしたメドレーもあり、そちらも甕の空洞に共鳴するような朗々とした響きがあり、カラスじゃないけど高く跳ね上がるところの金色の声はオペラの醍醐味です(そのマリア・カラスは 声質分類上は股がるところがあり、この曲では張り上げる系ではなく、清潔で完成度が高いです)。 一方で三つ年上で2019年に亡くなったジェシー・ノーマンは、ウェブでは音が遠いライヴが聞けるけど、CD はどうもないようです。ノーマンはドラマティコという声の分類になるので、上の二人よりも基本パワフルな歌唱です。 アフリカ系オペラ歌手として最初に有名になったと言える1927年生まれのレオンティン・プライスもポーギーとベスで評価されました。ただ、CD としては現在は彼女のコンプリート・アルバムで聞けるのみです。リリコ・スピントに分類されるソプラノで、低めの強い声です。サマータイムは YouTube でも聞けます。 見事な歌唱でグラミー賞をもらったハロリン・ブラックウェルについては下のラトル盤のところで述べます。 ポーギーとベスの映画 DVD と言いながら大分脱線しました。映像で見ることができるポーギーとベスは、古くは1959年のアカデミー/ゴールデングローブ/グラミー賞受賞の映画がありました。オットー・プレミンジャー監督で、音楽はアンドレ・プレヴィンが担当しました。配役はシドニー・ポワチエのポーギー、ドロシー・ダンドリッジのベス、サミー・デイヴィス・ジュニアのスポーティン・ライフというもので、サマータイムを歌う歌手はクララの部分がダイアン・キャロル、ベスの部分がアデーレ・アディソンです。通常はクララのパートが中心に考えられますし、サウンド・トラックでの伴奏の入り方も曲順もクララのパートのようですが、ひょっとしてベスが歌う第3幕担当のアデーレ・アディソンなのでしょうか、甘い声で漂うようにやわらかく歌うソプラノは高くてきれいです。低い音のパートは多少太く響かせるけれどもビブラートはあまり大きくはありません。この少し甘えるようなふわっとした雰囲気、技巧的ではないけどサ マータイムとしては相当魅力的な方に入るのではないでしょうか。一方でダイアン・キャロルはプレヴィンのピアノでジャズ・バージョンとして歌った録音を残しており、そちらはキーがぐっと下げてあってまず音域が違います。同じく甘い節回しではあるものの、全体に太く感じられ、震わし方も大きくてなんだか別の声みたいなのです。 しかもサウンド・トラックの名義は役のドロシー・ダンドリッジになってるので、クレジットそのままに上げてるビデオ・クリップもあったりして混乱します。 しかしいずれにしても残念なことに、この映画は公開後にガーシュウィンの遺族から抗議を受けるなどしてお蔵入りになり、基本的にその後 DVD などは出ない状況です(ガーシュウィンの兄でオペラの脚本を書いたアイラとその妻が「つまらない作品」だと評価したという説と、そうでないという説があり、いずれにしてもガーシュウィン・アンド・ヘイワード・エステーツ=遺産財団が許可していません)。一部非英語圏の外国語バージョン(状態の良くない海賊盤)もあるようですが、そちらは手には入れていません。ちゃんとした形のものは米国議会図書館では閲覧できるそうです。サウンド・トラックの方は CD でも出たことがあり、聞くことができます。  Gershwin Porgy and Bess Simon Rattle London Philharmonic Orchestra (DVD) ♥♥ ガーシュウィン / 歌劇「ポーギーとベス」全曲 サイモン・ラトル / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団(DVD)♥♥ そんな状況で、現在スタンダードとなっているのが、ここで取り上げる1988年録音(リリースは89年)のラトル盤です。これは映画ではなく、テレビ用のセットのようなところで撮影されています。実際の舞台とも似ていますが、そのままではなく、もう少し手が込んでいて映画的です。映画ほどは実写っぽくないにしても、大変きれいな画像でカメラワークもいいです。演奏はサイモン・ラトル指揮のロンドン・フィルハーモニックで、ポーギー役はウィラード・ホワイト、ベスはシンシア・ヘイモン、デイモン・エヴァンスのスポーティン・ライフであり、最初に「サマータイム」を歌うクララはハロリン・ブラックウェルです。第3幕でのベスの方(ハイライト盤の CD ではカットされています)は多少オペラ的な方に寄った歌い方だけど、このハロリン・ブラックウェルは90年にグラミー賞をもらったメトロポリタンのスターで、この「ポーギーとベス」のクラシックのオペラ演奏盤の中では大変真っ直ぐで清楚、高くよく伸びる透き通った声であまりオペラティックな感じはしません。やれてないんで雰囲気が違うなど、色々言う人はあるだろうけれど、若いクララにはぴったりでしょう。元々がベルカントのすごいやつは苦手なので、これは主観的な評価ながら、この分野での「サマータイム」の歌い方としてはきれいさにおいてベストな気がします。 そんなわけで、映像による「ポーギーとベス」はこの盤が良いと思っています。レーベルは EMI で、音もいいです。 そして「ポーギーとベス」は映像自体が少なく、この後には2009年のサンフランシスコ・オペラの DVD が出てるぐらいでしょうか。そちらは舞台そのままを撮影したもので、そういう形で見たい方には朗報でしょう。ポーギーはエリック・オーウェンズ、ベスはラキタ・ミッチェル、スポーティン・ライフはチョンシー・パッカーです。「サマータイム」を歌うクララは1984年 LA 生まれのエンジェル・ブルーで、力強く張りがあり、やはりオペラの歌い方独特の魅力があります。 現代のジャズ・シンガーによるガーシュウィンのジャズ・スタンダード クラシックの歌を取り上げたところで、今度は本当にジャズの歌をやるべきでしょう。「サマー タイム」だけではなくて、です。前のページでも述べた通り、ガーシュウィンはジャズの世界ではソング・ライターであって、スタンダード・ナンバー(様々なジャズ・ミュージシャンが常に演奏する定番曲) の生みの親だからです。そうなると歌っている人は実にたくさんいるわけです。誰を選んだらいいんでしょう。器楽も含めればガーシュウィンの曲ばかりを集めたアルバムというのもいくつかはあるものの、数はさほど多くありません。 また、ジャズの歌い手には、ジャズに限らず声というもの一般の特性かもしれませんが、本当にそれぞれの好みが出るものです。一方の端には技術が見事な力一杯の熱唱があり、もう一方の端には整ったきれいな歌や女っぽいセダクションが存在するとするなら、前者を好む人は、後者にはソウルがなくてつまらな いと言うだろうし、反対に後者を好む人は、前者は赤ん坊の泣き声みたいに注意を引こうとするのでうるさいと言うでしょう。もちろん誰しもが認める権威というものは存在します。この分野のオーソリティーは上記のエラ・サラ・アニタらということになります。でも、アフリカ系だからとか時代だからとか言うつもりもないけれども、ときに野趣溢れるタフネスや、熟達した妖艶という路線はひとまず横へ置いておきたいと思います。彼女たちが見事なのはもちろんですが、もう少し新しい、現代のジャズ・ボー カルの女王にしようと思うのです。 女王としてぱっと思いつくのは二人、まず2002年にアルバム「カム・アウェイ・ウィズ・ミー」で大ヒットを飛ばしたノラ・ジョーンズがいます。ビートルズ関係で有名になったインドのシタール奏者、ラヴィ・シャンカルの娘で、独特な軽さを含んだ眠たげでアンニュイな少女のかすれ声は何を聞いても彼女だとすぐ分かるものですが、デビュー当時はノラ・ジョーンズ・ショックみたいな形で、あのずらしてブルーノートへとずり上げる歌い方が一世風靡しました。完全なジャズというのとはちょっと違うかもしれないけど、ヒットの後ではホリー・コールまでもが同じようなスタイルに聞こえるアルバムを出したりして、意図的かどうかはともかく、驚いたものです。ホリーはノラの前に人気があったジャズ・シンガー(これもジャズ畑の人が仲間と認めないことがあります)で、 ギーンとした男声寄りの音も出し、低くかすれて喋るような歌い方なので似てなかったからです。そしてそのノラ・ジョーンズだけど、現在の時点で新しいジャズ 歌手に言及する場合、「彼女以降のジャズ・シーンでは」みた いな言い方になったりもするので、女王が何人もいるのは変だとしても、その一人であることは間違いないでしょう。ガーシュウィンとしては「サマータイム」 がウェブにたくさん上がっています。でも CD とかでは売ってないようです。好きな人はみんな困ってるんじゃないでしょうか。これから出るのかな。 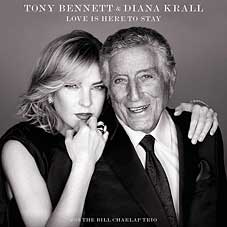 Love Is Here to Stay Tonny Bennett & Diana Krall Tonny Bennett, Diana Krall (vo) ♥♥ Bill Charlap (p) Peter Washington (b) Kenny Washington (ds) ラヴ・ イズ・ヒア・トゥ・ステイ トニー・ベネット&ダイアナ・クラール ♥♥ トニー・ベネット / ダイアナ・クラール(ボーカル) ビル・ チャーラップ(ピアノ)/ ピーター・ワシントン(ベース) ケニー・ワシントン(ドラムス) そうなるともう一人の女王、ダイアナ・クラールです。1964年カナダ生まれで、ノラ・ ジョーンズより十四歳上の世代ながらデビューは93年、90年代の半ばに人気が沸騰しました。現在全世界で1500万枚のアルバム・セールスを記録していま す。関係ないけどエルヴィス・コステロの奥さんです。この人については、どういう路線が好きなジャズ・ファンもきっとその歌唱力を認めない人はいないでしょう。しかも雰囲気がすごくあります。元々そっちが始まりだっ たピアノが達者で、ジャズの弾き手として一流です。この辺はナット・キング・コールとも似てますが、弾き方もその流派ということでそっくりです。コロコロとした音で自在なリズム感を見せ、それだけで見事なものであり、しかも歌いながら完璧に弾けます。 歌そのものはどういうのでしょう、「官能」とかよく表現されてるけど、確かに崩した歌い回しや力の抜き方、少しかすれた声は大変色っぽいながら、意識して媚を売るような嫌らしさは全くなく、性質としては案外さっぱりしてるように感じます。ブルージーだけど深刻にならないのです。昔のジャズの大御所もいいでしょうけど、軽くて粋なガーシュウィンのスタンダードを聞きたいとき、この人はやっぱりベストな感じがします。今や「ポスト・ノラ・ジョーンズ」の若手も色々出て来てるようながら、そちらはジャズの専門家にお任せです。 さて、この人にはガーシュウィンの曲が集まったアルバムというのがあるので、ここではそれを取り上げることにします。と言っても、ダイアナ・クラール単独ではなく、トニー・ベネットとのデュオです。大変有名な人なのでご存知かとは思いますが、トニー・ベネットは1926年生まれのポピュラー音楽のシンガーです。こういうスムーズな美声の伝統といえば、マイクを使うソフトな声(クルーナー・スタイル)の開祖、ビング・クロスビーなんかをまず挙げるべきなのでしょうか。それからペリー・コモ、フランク・シナトラも入れていいのかな、ナット・キング・コール、アンディ・ウィリアムス、バート・バカラックは作る方なので除くとして、最近のマイケル・ブーブレまで色々といます。その中でトニー・ベネットは、滑らかに長くつなぐというよりも、短く跳ね上げてフレー ズを言い切るような粋なところもあり、アメリカ最高のボーカリストと言われています。何よりも「アイ・レフト・マイ・ハート・イン・サンフランシスコ(想い出のサンフランシスコ 1962)のヒットで知られると言った方がいいでしょうか。あの曲は確か「トムとジェリー」にも出て来てました。ジェリーがハンカチ振って歌ってた記憶です。チビクロサンボと同じでアフリカ系のメイドが出て来るんで今や放映されないのかもしれない けど、あのアニメって太平洋戦争の前年からあったんですね。あんなの見て笑ってる余裕の国に爆弾落としに行ったわけです。横道に逸れましたが、そんなトニー・ベネット御大、2018年のこのアルバム(ヴァーヴ・コロンビア)では九十二歳ということになります。さすがに最盛期の美声というようなわけには行かずに高音に上げるところが多少苦しいですが、実に大したものです。雰囲気があります。低めのダイアナ・クラールとは声質というか、発声が似てる気がする瞬間もあって面白いです。ダイアナがやさしく合わせてる気もするけど。 この曲集、聞いていると、ダイアナ・クラールのファンなら「あ、この曲も、あの曲も彼女自身のアルバムで聞いたぞ」という事態になると思います。ですから彼女のガーシュウィンを取り上げても良かったのかもしれないけど、「ス・ワンダフル」にしても「ドゥー・イット・アゲイン」にしてもタイトル曲にしても、それぞれ別のアルバムに分かれて入っており、このデュエットのようにガーシュウィン・アルバムとはなってないのです。ガーシュウィン生誕120年記念として企画されたので、こちらの方が珍しいわけです。ですからダイアナがお好きな方はガーシュウィンの曲以外もいいですから、それら個別のアルバムを是非聞いてみてほしいと思います。ボサノヴァ集とかも出てます。それと、彼女の「サマータイム」は、題材を元に即興を見せるジャズのこと、元歌のようにメロディー・ラインを立たせるような歌い方ではなく、リズム主体の速い展開の曲として披露していますから、前述の通りあのオペラの「サ マータイム」みたいなのを、という感覚の人には「ちょっと違う」となるかもしれません(デュオには入ってません)。 曲目は以下の通りです: ス・ワンダフル マイ・ワン・アンド・オンリー バット・ノット・フォー・ミー ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット(首尾よく行けば) ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ アイ・ガット・リズム サムバディ・ラヴズ・ミー ドゥ・イット・アゲイン アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー ファッシネイティング・リズム(魅惑のリズム) ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー(誰にも奪えぬこの想い) フー・ケアズ? ボーナス・トラック: ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイング・オン(いつの頃から) ア・フォギー・デイ(欧州・日本版)/オー・レディ・ビー・グッド(一部米版) ガーシュウィンのスタンダード・ナンバーをジャズ・ピアノで聞く 次にスタンダードを歌で聞くのではなく、ジャズのピアニストが弾いたものにも触れてみます。トランペットやサックスでというのもジャズの王道だけど、ピアノはガーシュウィンも弾いていた楽器で、軽やかで粋な表現も得意であり、聞きやすくもあります。  George Gershwin Piano Works Frank Braley (pf) ♥♥ ガーシュウィン / ピアノ曲全集 フランク・ブラレイ(ピアノ)♥♥ 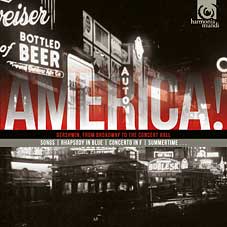 America! Vol.2 Gershwin, from Broadway to the Concert Hall -18 Songs Frank Braley (pf) ♥♥ アメリカ! 第2巻 ガーシュウィン、ブロードウェイからコンサート・ホールまで 〜ソング・ブック(18曲) フランク・ブラレイ(ピアノ)♥♥ その前に一つ、ラプソディ・イン・ブルーを扱った前ページですでに取り上げていたものですが、ガーシュウィン自身が譜にした「18のソング・ブック」をもう一度挙げておきます(写真上下ともに同じ曲が入ってます)。これはジャズではなく、クラシックのピアノ演奏になるし、また、スタンダードとしてピアノで弾かれる曲の全てがこの曲集に入ってるわけでもないのだけれど、ジャズとして演奏される元の形だからです。ただしこの盤のパフォーマンスのあり方については前ページで書いた通りなので、曲目のみを記します: ザ・マン・アイ・ラヴ アイル・ビルド・ア・ステアウェイ・トゥ・パラダイス ス・ワンダフル アイ・ガット・リズム ドゥー・イット・アゲイン クラップ・ヨー・ハンズ オー・レディ・ビー・グッド ファンシネイティング・リズム(魅惑のリズム) サムバディ・ラヴズ・ミー マイ・ワン・アンド・オンリー ザット・サートゥン・フィーリング スワニー スウィート・アンド・ロー・ダウン ノーバディ・バット・ユー ストライク・アップ・ザ・バンド フー・ケアズ? ドゥー・ドゥー・ドゥー ライザ  Oskar Peterson Plays George Gershwin Song Book Oskar Peterson (p) Ray Brown (b) ♥♥ Ed Thigpen (ds) Barney Kessel (g) オスカー・ピータソン・プレイズ・ジョージ・ガーシュウィン・ソング・ブック オスカー・ピーターソン(ピアノ)/ レイ・ブラウン(ベース)♥♥ エド・シグペン(ドラムス)/ バーニー・ケッセル(ギター) さて、ジャズの方です。前の記事でガーシュウィンの曇りのない叙情のあり方について、同 質なところのある陽性なジャズ・プレイヤーをもし挙げるならオスカー・ピーターソンかも、というようなことを書きました。1925年カナダ生まれの超絶技巧で有名なピアニストで、2007年に亡くなっている人なのですが、そのアルバムとして一番好きなのは「ウォーキング・ライン(1970)」であり、中でも「ザ・ウィンドミルズ・イン・ユア・マインド」という曲はゴキゲンだという話をジャズのページ(「クラシック音楽ファン向きのジャズ?」)でも触れました。一般には「キーボード のマハラジャ」などと言われ、グリッサンドのように連続して高速で駈け巡る指遣いがトレードマークながら、静かなバラードも大変味わいがあります。 そしてここで取り上げるアルバムはずばり「オスカー・ピータソン・プレイズ・ジョージ・ガーシュウィン・ソング・ブック」です。ここでのピーターソンはびっくりするほど、あの豪速のマハラジャではありません。落ち着いたリラックスしたマナーでガーシュウィンのメロディーを取り上げて行きます。ジャズの凄技を期待する人には多少物足りないかもしれないけど、軽く転がしてお洒落でセンス良く、何ともいい味出してます。こんな静かな O.P.もあるんです。 CD アルバムとしては LP 時代の録音二枚が合わさったものとなっており、前半の12曲が1959年のステレオ、後半の12曲が52年のモノラル録音です。レーベルはヴァーヴです。 曲目は6曲重複がありますが、ステレオの方だけ記すと以下の通りです: イット・エイント・ネセサリー・ソー ザ・マン・アイ・ラヴ ラヴ・ウォークト・イン アイ・ワズ・ドゥーイング・オール・ライト ア・フォギー・デイ オー・レディ・ビー・グッド ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ ゼイ・オール・ラフト レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ サマータイム ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット(首尾よく行けば) シャル・ウィー・ダンス? モノラルの方にはギターが加わります。ちょっとテンポ感が違うでしょうか。ステレオ録音と同じものに加えて以下の曲が別にあります: ファッシネイティング・リズム(魅惑のリズム) サムバディ・ラヴズ・ミー ストライク・アップ・ザ・バンド アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー ス・ワンダフル アイ・ガット・リズム 奇しくも合計18曲となりますが、ガーシュウィン・オリジナルのソング・ブック18曲とは内容が少し異なっています。 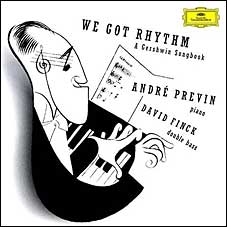 We Got Rhythm A Gershwin Songbook André Previn (p) David Finck (b) ♥♥ ウィ・ ガット・リズム / ア・ガーシュウィン・ソングブック アンドレ・プレヴィン(ピアノ)/デイヴィッド・フィンク(ベース)♥♥ ピーターソンを尊敬してやまなかったアンドレ・プレヴィン。クラシックの指揮者として知られているけど、ジャズから始めてそっちも一流という、ただ一人と言ってもいいような存在です。その彼がガーシュウィンの生誕100年を記念してジャズのアルバムを出しました。ベースを伴ってピアノで即興を見せていま す。前のページでは本格ジャズだからということでジャケットを掲げずに済ませましたが、やはりここで取り上げることにします。ガーシュウィンのジャズ・ピ アノとしてはどうしても外せないでしょう。ピーターソンの穏やかに終始する温かい運びとは違い、こちらも温かくはありつつ、しっかりと攻めます。 余計な説明かもしれませんが、ガーシュウィンが楽譜にした18曲から成るソング・ブックの曲とは違い、(モダン)ジャズはインプロヴィゼーション(即興)による演奏であり、楽譜通りではありません。コード進行という大枠が決まっていて、その上で各楽器がその場で自在にメロディー部分をオリジナルとは変えて演奏します。コード(和音)が弾ける楽器(ピアノやギター)の場合では、二つの楽器があって同時に同じコードを弾くのでもなければ、他のメンバーが混乱しない限りはその基本のコード進行から少し外してみせても構いません。あるいは同じコード運びを守っているならメロディー部分を全く別の曲から拝借して来て埋め込んでもいいし、ソロの見せ場だったらそれこそ何やっても OK です。そんなわけで、元歌は何なのか聞き手はたいていは了解できますが、譜にすると全く別の曲なのです。クラシックの演奏の善し悪しはディナーミクやアゴーギクといった音の「出し方」に依存しますが、ジャズの場合はどんな音で展開させるかが腕の見せ所ということになります。 ここでのプレヴィン、1曲目と9曲目の出だしだけはちょっとだけフリーに寄ったかのような(そこまでじゃありません)音の選択で意欲的に始めますが、全体には聞きやすいです。それでいて彼のジャズの才能が炸裂していてありきたりになりません。それについて言葉で解説を試みるとややこしいことになるし、適任でもありません。ただきれいにメロディーをなぞったものではなく、ちゃんとモダン・ジャズとしての仕事をしているので、どうやってるのか聞いてみてください。見事です。曲目は以下の通りです: ゼイ・オール・ラフト サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー オー・レディ・ビー・グッド ア・フォギー・デイ ドゥー・イット・アゲイン / スーン アイ・ガット・リズム エンブレイサブル・ユー ヒー・ラヴズ、シー・ラヴズ / アワ・ラヴ・イス・ヒア・トゥ・ステイ レディー・ビー・グッド: ファッシネイティング・リズム(魅惑のリズム) イズント・イット・ア・ピティ ボーイ・ホワット・ラヴ・ハズ・ダン・トゥー・ミー / アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー ラヴ・ウォークト・イン ザ・マン・アイ・ラヴ ファニー・フェイス: ス・ワンダフル 録音は1997年(98年がガーシュウィン生誕100年で、その年に発売)のドイツ・グラモフォンです。  Tommy Flanagan Lady Be Good… for Ella Tommy Flanagan (p) Peter Washington (b) ♥♥ Lewis Nash (ds) トミー・フラナガン レディ・ビー・グッド… フォー・エラ トミー・フラナガン(ピアノ)♥♥ ピーター・ワシントン(ベース)/ ルイス・ナッシュ(ドラムス) これもジャズのページで取り上げた一枚で、ガーシュウィンは二曲しか入ってないのでどうかとは思うのですが、いいピアノなのでまた挙げます。そしてその二曲はまた、すごくお洒落です。 トミー・フラナガンは1930年生まれで2001年に亡くなったジャズの名ピアニストです。数々の有名プレイヤーたちの伴奏をして彼らを引き立てて来ましたし、「ピアノの詩人」などとも呼ばれます。アフリカ系の人ですが、そのピアノはエネルギッシュにリズム主体で押しまくるものではなく、ソフィスティケーテッド・サウンドとでもいうか、ホワイトのピアニストにも聞かれないほどに繊細でエレガントな音の運びを見せます。結局人種なんて関係ないわけです。このアルバムはジャズ・シンガーの大御所、エラ・フィッツジェラルドに捧げたものなので、歌ものの曲ばかりで聞きやすく、ガーシュウィンのナンバーである表題の「オー・レディ・ビー・グッド」と「イズント・イット・ア・ピティ」以外はエリントンやポップス/ロック、映画からの曲となっています。上記ピーターソンのぬくもり、プレヴィンの技ありともまた違った味わいです。 1993年録音のヴァーヴです。 |