|
ショパン / ピアノ協奏曲第1番

取り上げるピアニスト 46人 CD 50枚: フェイバリット・ピアニスツ(解説を飛ばします) フランソワ/パレチニ('99/'00)/ツァハリアス/アックス/白神/リヒター=ハーザー/ルービン シュタイン/ピリス/ペライア ショパン・コ ンクールの優勝者たち ステファンスカ/ハラシェヴィチ/ポリーニ/アルゲリッチ/オールソン/ツィマーマン('78/'99)/ダン・タイ・ソン/ブーニン /ユンディ('06/'17)/ブレハッチ/アブデーエワ('10/'12)/ソンジン・チョ/ブルース・リウ 師と先人たち(19世紀生まれのピアニスト) ローゼンタール/ホフマン/レヴィーン/ネイガウス/ホルショフスキ/ブライロフスキ その他の名手たち(20世紀の巨 匠〜新しい世代まで) アラウ/マガロフ/バッカウアー/ボレット/リパッティ/ギレリス/シフラ/ヴァーシャーリ/フー・ツォン/ アシュケナージ/ルイサダ /クピーク/ベレゾフス キ/ルイージ/キーシン/ネボルシン/トリフォノフ/リシエツキ ショパン・ピアニストたち(19世紀の大家から現代まで、ショパン弾き16人を聞いてみる)はこちら ピアノの詩人と呼ばれるショパン。ピアノを弾く人にとってまず避けて通れない存在であり、弾かない人にとってはあれこれ評し難い作曲家です。演奏の面から言えば、古くから伝説的なピアニストが活躍し、コンペティションでは若者が試されて来たし、個性豊かなアプローチによって世界中のアーティストが自分の絵を描いて見せるカンバスであると同時に、その姿の再現を試みられる一人の人間でもあります。どんなピアニストがどんな風に弾いて来たのか、ちょっと比べてみようと思います。 作曲家のこと
生まれたのは1810年で、1849年に亡くなっています。ロマン派の最盛期に活躍した作曲家ということになります。ポーランドの人ですが、あまり言われないものの父親はフランス人です。三十九歳で結核(他の病気説もあり)で亡くなったので、モーツァルトやシューベルト、メンデルスゾーンに次ぐ短命であり、ガゼボの「アイ・ライク・ショパン」みたいに奇麗な壊れものであって、ちょっと憧れ切ないみたいな印象かもしれません。一方でピアノの可能性をぎりぎりまで試すような技巧家としての顔も持っています。 ピアノ協奏曲第1番で比べる
一般的な名曲の話として、ラフマニノフの2番の次にロマンス映画に使われそうな美しいメロディーのピアノ協奏曲といえば、ショパンの1番です。特に甘い第二楽章は映画向きです。モーツァルトの「短くも美しく燃え」(スウェーデン映画で使われた第21番の第二楽章)は一つ前の古典派の曲で、同じロマン派の他の曲としてはチャイコフスキーとグリーグも有名だけど、前者は出だしのドラマが売りなんであり、後者はロマンスというよりも、その内気な作曲家の中では技巧的で最も勢いの良い作品です。一方でショパンには2番というのもあるけど、叙情的で完成度が高いとなるとやっぱり1番でしょう。クラシックの入門曲にだってなります。そして何よりこれ、有名なショパン・コンクールの本選での課題曲でもあるのです。二十歳のときに作った、この作曲家をいの一番に代表する曲です。演奏時間の短い小品が多いショパンの作品の中で2番と合わせて唯一の大曲であり、ショパンの最高傑作と言ってもいいでしょう。
したがってこの曲でショパン弾きたちを比較するのはいい考えではないでしょうか。面白いことに敢えてこれを弾かないピアニストもいるけど、甘くきれい過ぎるからか、それともショパンをリスト的に見てるからでしょうか。でもそういう場合は他の独奏曲で皆が弾くような作品によって比べればよいのです。歴史的な名人、19世紀のパハマンやコルトー、ジル、コチャルスキといったショパンの弟子たちや、ホロヴィッツなど、この曲の録音がない大家については次の記事で取り上げます。 作曲の背景と恋
それではピアノ協奏曲の1番はどんなロマンティックな想いから生まれたのでしょう。折しもウィーン経由でパリへと旅立つ直前ということもあり、故郷ポーランドへの告別の感情が込められているとする向きもあるようです。しかしそういう大枠だと愛国心的な同一化の話で終わり、具体的な中身は見えて来ません。この頃のショパン自身の私生活、恋愛事情などはどうだったでしょうか。 元々彼はいわゆる神童タイプであって、ピアノ演奏によって注目を浴びることで世の中へ登場して来ました。そして二十歳までワルシャワをベースに活躍し、その後より一層の飛躍の場を求めて、最初はウィーンへ、そしてそこで成功しなかったのでパリへと出て行きます。しかしその前に初恋の人というのがいて、それがワルシャワ音楽院の同級生で声楽をやっており、後にオペラ歌手になるコンスタンツィヤ・グワトコフスカです。出会いの場は十九歳のときの発表会で、一方的な一目惚れでした。その後努力して彼女とは実際に知り合いになりましたが、ずっとお友達レベルのまま。淡い秘密の恋状態でした。女性として、彼女の側では感づいていたのでしょうか。国を出るときに送別会で歌ってはあげたけど、後から彼の思いを人伝てに聞かされて驚いたという話もあれば、指輪をあげた(もしくは交換した)という説もあります。このあたりは脚色もされがちなところでしょう。いずれにしても若く切ない成り行きではあります。ピアノ協奏曲は二つあって第2番の方が先に書かれているのですが、その第二楽章は彼女への想いを込めたものだと本人が語っています。第1番については何も触れられてないものの、時期的にはほぼ同じ頃の作です。グワトコフスカを想ってたに違いありません。 ショパン弾きの師たち
さて、話を演奏比較の方へ戻しますが、どんなピアニストがいるのでしょうか。ピアノという楽器が完成された時期からして、その主な作曲家はリスト、ショパン、ラフマニノフといったところでした。その中でもショパンはピアノの王様なので、有名な演奏家やピアノの先生などが文書や古い SP などによってショパンの弟子の系譜に当たり、その人なりに誰かを師と仰いで流儀を取り入れたりして、弾き方について研究しています。なのでここでもそうした弟子たちの何人かは取り上げてみます。 コンクールの優勝者たち でも日本において人気のある演奏者は恐らくポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、ブーニン、といったところでしょう。ブーニンはブームの反動で今はさほどでもないのでしょうか。いずれにせよ全てショパン・コンクールの覇者です。いわゆる「音楽的」な演奏と言われるような、心情やリズムの揺れにおいてセンスの良さを見せる人が早い段階で落ち、技術的にミスがない楽譜通りの人が優勝するケースもあるとは聞きます。でもこの人たちについて触れないわけには行きません。 以下にショパン・コンクール(ポーランドのワルシャワで五年おきに開かれます)の歴代優勝者を第1回から順に挙げてみます: レフ・オボーリン(1927 ソビエト)
アレクサンダー・ウニンスキー(1932 ソビエト [ウクライナ])
ヤーコフ・ザーク(1937 ソビエト)
ハリーナ・ツェルニー=ステファンスカ/ベラ・ダヴィドヴィチ(1949 ポーランド/ソビエト) アダム・ハラシェヴィチ(1955 ポーランド) マウリツィオ・ポリーニ(1960 イタリア) マルタ・アルゲリッチ(1965 アルゼンチン) ギャリック・オールソン(1970 アメリカ) クリスティアン・ツィマーマン(1975 ポーランド) ダン・タイ・ソン(1980 ヴェトナム) スタニスラフ・ブーニン(1985 ソビエト) 1990 と 1995 は一位なし リ・ユンディ(2000 中国) ラファウ・ブレハッチ(2005 ポーランド) ユリアンナ・アブデーエワ(2010 ロシア) ソンジン・チョ(2015 韓国) ブルース・リウ(2021 カナダ) 曲のオーケストレーションについて また、ショパンの協奏曲のオーケストレーションについては、ショパンはピアノの人であってそっちはだめだった、あるいは、他の人が書いたのだろう、などとよく言われます。そして出来の悪いとされるスコアを演奏者側で手直ししたり切り詰めたり、ナショナル・エディション版があったり室内楽版でやったりで、違う音が聞かれる場合もあります。個人的にも「冒頭でティンパニが豪壮に鳴るのは音響的にどうなのか」などとツァハリアス盤などで感じたりすることはあったりするものの、多くの聞き手にとってはさほど不満に感じることはないのではないかと想像します。 取り上げる順番ですが、今回ここでは、特に見事だと感じた演奏、好みだった演奏の CD を最初に持って来て、それからショパン・コンクールの優勝者、19世紀の大家、その他の20世紀生まれのピアニスト、という並びにしました。最初の項目に入れたいけれどもコンクール優勝者でもあるブルース・リウについては、2番目のコンクールの項目で扱っています。当たり前ではありますが、ピアニストの数だけその演奏を好む聞き手もいます。絶対的に優れた演奏というものはありません。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Samson François (pf) ♥♥ Louis Fremaux Orchestre National de l’Opera de Monte-Carlo ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 サンソン・フランソワ(ピアノ)♥♥ ルイ・フレモー / モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団 「フランソワのショパン」のページでピアノ独奏曲の CD をご紹介した際に、ショパンはもうこれだけあれば良いと言って終わっていました。 今回の協奏曲でも同じことを言いたい気もします。ただ、誰にでもお薦め出来る盤ではありません。個性が強過ぎて一般的には変な演奏だからです。助奏が終わってピアノが初めて出て来るとき、それまでの速度を無視してゆっくり弾き出すところで驚くと思います。後からオーケストラが合わせに行ってるぐらいです。それにこの協奏曲については彼らしさが全開でないかもしれません。録音は二つあって、ここで取り上げる新しい方は特にそうでしょう。加えて1965年の EMI ですから、金管とか高い弦とかの鳴り方がベストではありません。それでもやはり、独特の魅力に溢れています。 サンソン・フランソワは1924年生まれのフランスの神童型のピアニスト。戦後に活躍し、1970年に四十六歳で心臓発作によって亡くなっています。コルトー門下でマルグリット・ロンに習いました。反抗的で先生泣かせの個性的な表現が特徴です。十九歳のとき、そういう弾き方なのに第一回のロン=ティボー・コンクールで優勝したのは驚きだけど、やはり本来はその予定ではなく、すったもんだあったようです。一般には「詩人のインスピレーション」などと言われていて、クラシックだけ聞く人には分かり難いけれども、実はこの運び、ジャズの音だと言ってよいと思います。ジャズは即興の世界だけど、彼は案外ジャズも弾けたのかもしれません。実際に好きだったとは言っています。 そんな時代とタイプに相応しく、愛煙家の酒飲みであり、「クレイヴンA」というブランドの煙草を常に離さない人でした。国産愛好が多いフランス人としては珍しく、猫のおしっこ臭くて甘い味のフランス煙草ではなく、イギリスものです。バーンスタインと並んで紙巻きを手にした写真が多い気がします。最近は没後五十年ということで CD54枚ボックスも出たようです。 演奏はジャズの音だと言いましたが、ジャズの場合、刻むビートは不均等割ながら進行自体はメトロノームのように一定であり、それに対して各楽器は頭を遅らせて入ったり、遅れを取り戻すように速めたりと揺らして独特のリズムをつけ、そこに即興フレーズを加えます。ジャズ・ピアニストでもキース・ジャレットやフレッド・ハーシュのようにジャズ的でない拍を聞かせる人はいるけれども、それでもリズムは常に一定で、流れの帳尻は合っています。そしてそういう風に拍を盗んだり、その分を戻したりというやり方は本来のルバートの定義に近いとも言えるでしょう。フランソワの天才肌の正体はこのジャズっぽいリズムの取り方にあるのです。一方でクラシックで標準となっている広義のルバート表現は、ビート部分のメトロノームそのものが変わり、比較的長いフレーズに渡ってスピードが増したり遅くなったりします。またバロック時代ならともなく、即興の飾り音符を加えて崩すことは今はあまり行いません。この話はクラシックのピアニストであるフランス人のジャン=イヴ・ティボーデが ジャズのビル・エヴァンスの曲をやった CD のところですでに触れていました(「クラシック音楽ファン向きのジャズ?」)。もちろんクラシックの曲ですから、フランソワの1番が小節をまたいだ長スパンの加減速をしないわけではなく、一定の部分を拡大して見ればの話であってあくまでも程度問題です。そして別の見方をするならば「ジャズ的」なこのフランソワの崩しに関しても、それを同時に「フランス的」だと言うことも出来るでしょう。あんな風に波のように揺れるのはフランス人好みですから。斜に構えて明晰で、感傷のもやをまとわないこの洒脱さは他の文化では考え難いと思います。でも真面目にやる人を横目でからかうトリックスター的な雰囲気があるので、嫌いな人は受け付けないかもしれません。 そしてフランソワの揺らぎが感情の起伏に従ったものかというと、それも作曲家の喜怒哀楽というより、本人のリズム感覚に従っている結果だと言えるでしょう。それでいて恣意的に感じないのは不思議です。グールドとも違うし、先生のコルトーにもロンにも似てません。コルトー流に彼の揺れを「19世紀的」と呼ぶ人もいるようだけど、そうかもしれないし、全然違うかもしれません。 1965年の EMI です。ART処理によるリマスターで蘇りました。最新録音とは違うけどステレオだし、これだけバランスを整えたのですから立派です。70年代のカラヤンの録音でもお馴染みの現象でブラスが賑やかになって耳にきついのは致し方ないものの、ピアノの部分は新しい録音と比べても引けをとりません。音を気にしないならジョルジュ・ツィピーヌ/パリ音楽院管弦楽団による57年のコロンビア盤もありますが、特にマニア的な関心がないならこちらで十分なのではないかと思います。2番の協奏曲とカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Piotr Paleczny (pf) ♥♥ Jerzy Maksymiuk Orchestra Sinfonia Varsovia ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ピオトル・パレチニ (ピアノ)♥♥ イェジー・マクシミウク / シンフォニア・ヴァルソヴィア フランソワさえあればもう他はいらないなんて言いながら、これは理想的なショパン演奏だと思います。端的に言えば流麗かつロマンティックで、熱いです。結構強いタッチで力強くもあるけど繊細さもあり、何より弾いていること自体が楽しそうです。リズム感が良く、速く流しているところにも自在な表情があります。知らない名前だったので聞き直してしまいました。でも音楽が生きていて、やっぱり感情が乗って来てどんどん聞き入ってしまいます。こうなると病気がちで弱々しいショパンではないけれど、本人だって結核で弱ってたからであって、精神は本来こうかもしれません。そしてもう一つ大事なことは、ひたむきで嘘のない、暖かい人柄を感じさせるということです。 ピアニストのピオトル・パレチニはショパン・コンクールの覇者ではなく、その審査員をやっているポーランドの重鎮です。その方面で有名なのは「戦場のピアニスト」で人気を誇るヤノシュ・オレイニチャクの方かもしれませんが、是非こちらも注目していただきたいです。1946年生まれでショパンでは3位 (1970年/このときの1位はギャリック・オールソン)、その他のコンペティションにも五つほど参加しており、全て入賞です。でも優勝者より味わいがあります。3位だったときの録音は聞いてないけど、もしこの盤と同じ水準で落ちてたとしたら大変でしょう。パーフェクトだと思えます。このページでは二番目に取り上げたけど一押しです。世界中のコンクールで活躍し、教育活動にも従事しており、審査員として浜松にも来たことがあって日本の人も教えているよ うです。 この曲は十八番なのでしょう。何度も録音しています: 1981年 ヤツェク・カスプシク/ポーランド国立放送管弦楽団盤(ポルスキ・ナグラニア・ムザ) 1988年 カジミエシュ・コルト/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団盤 (展覧会の絵と組/サントリー・ホール・ライヴ/キャニオン・レコーズ) 1991年 カジミエシュ・コルト/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団盤 (キャニオン・レコーズ/Emergo classics B.V.) 1999年 カジミエシュ・コルト/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団(アコール) 2000年 イェジー・マクシミウク/シンフォニア・ヴァルソヴィア盤(ベアルトン) 2015年 弦楽五重奏編曲盤(ダックス・レコーディング・プロデューサーズ) 日本のキャニオンとフランスのアコールを除いては全て本国ポーランドのレーベルです。キャニオン・レコーズのものは現在は二枚とも廃盤のようです。そしてこれらの CD 以外にもライヴが YouTube に上がってたりします。そして上記のうち最初の二つは聞けてないものの、残りの中で一番良かったのは2000年の録音で、それより少し端正な感じの99年のが次点という印象でした。ここで取り上げているその2000年のイェジー・マクシミウク/シンフォニア・ヴァルソヴィア盤は本国では賞を取っており、金メダルのコインみたいな丸い印が三つ(一つはノミネートの意味)、誇らしげにジャケットについてます。使用しているスコアは以前のパデレフスキ版に代わってこの頃に完成され、2010年に正式刊行されたナショナル・エディション(エキエル版)です。ポーランドの国家事業であり、色々不備があると言われて来たオーケストレーション問題の最終回答という見方もあるようです。28ユーロほどで購入できます。 演奏スタイルとしては洗練されている次のツァハリアスよりもいかにもショパンという感じの、アゴーギクの大きさのあるものです。水を得た魚の本場の演奏で、自在な伸び縮みがあり、ときに意外なところで乗せてくれたりします。技巧だけで素っ気なくこなすのは我慢ができない人なのだと思います。感情の襞に深く入り込むという意味では若々しくもあるので、ショパンの二十歳の恋心を描き切って余りあると言えます。内側で同じものを追ってるのでしょう。自身の心の動きと表現の間にフィルターがないとも言えます。 第一楽章から一貫しているけれども、途中スローダウンするところでたっぷりと弾きます。揺らしについては ショパン的ルバートと言うのか、テンポをブロックごとに分けて走ったり、ゆったり歌ったりの変化を付けます。オーケストラの演奏もピアノの性質と合っており、見事です。 第二楽章でも深く揺れる表情が大変きれいです。フランソワみたいな細かいジャズ的な揺れではないですが、大きく波打つ表情はポーランドでのショパン解釈の伝統であり、ヤン・リシエツキのような若い世代にも聞かれます。この楽章、本当に心洗われます。 速い第三楽章はかなり強いタッチで切れがあり、艶の乗った美音でくっきりと弾いて行きます。体格もいいのでしょう、ピアノが鳴り切っており、ラストに流れ込む迫力がすごいです。ショパンはこうやるんだという自信がみなぎっています。 2000年ベアルトン・レーベル(ポーランド)の録音で、音も素晴らしいです。オーケストラは潤いがあって良いバランスであり、ピアノの艶もきれいです。探し難いかもしれませんが、国内の販売網で買えるし、本国直送もあります。廃盤ではないようです。サブスクライブのサイトにもあります。カップリングは2番の協奏曲です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Piotr Paleczny (pf) Kazimiez Kord Warsaw National Philharmonic Orchestra ♥♥ ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ピオトル・パレチニ (ピアノ) カジミエシュ・コルト /ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ パレチニは一回性の霊感的演奏をするタイプのようなので、録音によって楽章ごとのタイムが異なり、それぞれに表現も少しずつ違います。こちらは廃盤だけど、ストリーミング等でも聞けるので取り上げました。組み合わされている2番のコンチェルトについては、ピアノを弾いているのはポーランドの女性ピアニスト、エヴァ・ポブウォッカ(1957-)です。それも大変良い演奏です。ゆったり歌い、ポーランドのショパンの伝統を受け継いでいてよく揺らしつつ、適切な抑揚がついています。繊細さもあり、はったりのない真っ直ぐな叙情はパレチニとも比べられます。よりやわらかさがあるでしょうか。オーケストラが若干薄手な響きながら録音も良いです。ただ、この人の1番も別の盤で出ているものの、そちらは録音のコンディションがあまり良くはありません。1984年でオーケストラの音が薄く、シャリっとした響きなのが残念です。 因みにパレチニの弦楽五重奏編曲盤についても言うなら、そちらは反響があり、ピアノの音がフォルテピアノっぽく響くというのか、独特で遠い感じに聞こえます。表現としては、揺れながら前へ前へと向かう覇気が感じられる2000年盤よりは落ち着いており、室内楽部分の構成と余白の長さの違いもあるものの、全ての楽章で他の録音よりもタイムが2、30秒長いようであり、ゆったりに聞こえます。 さて、この盤でのパレチニの1番の演奏は、第二楽章が若干速くなってるかなというぐらいでタイムもあまり変わらず、スタイルとしては2000年盤と同じと言ってよいでしょう。違いはより素直で端正な感じがするところです。聞いていると起伏の点でややおとなしく、一つひとつのフレーズをじっくり進める歌い方がみられます。ドライブ感をもって前へ流れる軽いところが少なく、それが感情的な熱さという意味でより落ち着いて聞こえるのです。特に第二楽章でそうです。しかし逆に形の点では完成度が高いとも言えるでしょう。個人的には2000年盤でこちらは二番手となりますが、他の演奏者と比べれば水準は高く、これだけ聞けば素晴らしいので♡♡にしました。第三楽章の追い込みではポーランド盤に譲るかとは思います。 1999年の録音でフランスのレーベル、アコールから出ていました。上記の2000年盤と比べると、ピアノのタッチはあちらの方が強く聞こえ、粒が立った感じの録音だけど、全体のバランスではこちらも劣ることがなく、むしろオーケストラの弦の響きはきれいなぐらいかもしれません。これはこれで大変魅力的です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Christian Zacharias (pf/cond.) Orchestre de Chambre de Lausanne ♥♥ ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 クリスティアン・ツァハリアス(ピアノ/指揮)/ ローザンヌ室内管弦楽団 ♥♥ 最も美しいショパンの1番かもしれません。微細な心の動きを表す揺らぎがあり、強弱の呼吸と合わせて真似のできない感覚を音にしたレベルの高い演奏で、大変洗練されています。有名ピアニストにこだわらないなら、この曲の最初の盤として上記のパレチニ盤と並べて一押しです。パレチニには情熱的な乗りがあるとすると、こちらはセンスで勝負。特に静かな歌の部分に魅力があると言えるでしょう。 クリスティアン・ツァハリアスは1950年、インド生まれのドイツ人ピアニストで、ラヴェルの弟子であるペルルミュテールに習いました。芸風は師とは大分異なると思います。そしてこの人もコンペティションの覇者ではありません。ジュネーヴ国際音楽コンクールでは2位(1969/そのときの1位はペーター・エフラー)、ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールでも2位(1973/そのときの1位はウラディミール・ヴィアルド)、そして今は存在しないパリ・ラヴェル・コンクール(Ravel Competition in Paris)で優勝(1975)という経歴です。国際コンクールに騙されるのはやめましょうと言いたくなります。それが大きな役割を果たしてるのはもちろんです。才能を拾い上げて機会を与えています。でも音楽家としてのセンスを持ってる人が優勝者以外から出ることも多いのです。大手のレーベルは1位と契約し、残りのマイナーなレーベルが中身で勝負の人を拾います。ここでツァハリアスを出しているドイツの MDG は大手ではないけれど、良いアーティストを揃えているところです。そして今回のショパンはピアニストの弾き振りです。 演奏ですが、出だしでティンパニが目立つのは個人的には違和感があります。音程を合わせてある最初の音は立派で良いけど、その後のドラムロールはもっと静かにやってほしいです。でもそれは好みだし、録音の加減もあるでしょう。何より一瞬のことであり、ピアノは細かな動きと弱めの表情が繊細です。所々に出す崩しがリズムを感じさせます。多くの演奏者がためる方向でアクセントを付け、その遅れ分を取り戻すように駈けますが、ツァハリアスはそれだけでなく、拍の頭で微かに早める方にも崩すことで独特のデリケートな味わいを生んでいるように思います。真似しようと思ってもなかなかできないやり方です。そしてそんな自在な表情に加え、やり過ぎない絶妙のバランス感覚も備えています。恐らくこの人には、楽曲全ての部分で細かなところまで理想的な姿があらかじめ 見えており、どこをどうするべきかを正確に把握してるのでしょう。もし抑揚表現への理解力を表す知能指数のようなものがあるなら、相当高い数値になると思います。他のどんなピアニストより設計図がしっかりしており、技術も高いので、それを自然に表現出来ています。そしてそれは感情表現の様式なので、パレチニのようにその場で湧いて来る種類ではないとしても、心もこもっているのです。レベルの高い演奏です。 第二楽章も静けさの感じられるデリケートな表情がいいです。複雑な波の中で揺られて行きますが、ロマンティックになり過ぎません。詩的で、かといってフランソワほどエキセントリックではなく、若いショパンの心の揺れをやさしさをもって表現します。続く第三楽章も変わりません。表情を付けられる適切なテンポで、指が回ることを見せようなどとはしません。技術がないのではなく、速過ぎては知りようのないフレーズ途中での動きを感じさせます。リズム感が良く、速くも遅くも自由自在という感じです。 2004年の録音で、MDG(ムジークプロドゥクツィオン・ダブリングハウス・ウント・グリム) は音が良いことでも知られています。そしてここの特徴で贅沢なゴールドディスクです。スタジオ録音です。ピアノは過度に輝かないバランスで良いです。買うときに販売サイトで Zacharias Chopin Piano Concertos と検索しなければならなかったりしますが、廃盤ではなくて安定供給されています。2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Emanuel Ax (pf / 1851 Érard) Charles Mackerras Orchestra of the Age of Enlightenment ♥♥ ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 エマニュエル・アックス(ピアノ/1851 エラール)♥♥ チャールズ・マッケラス / エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団 これも完成度が高くて繊細な表現力があり、音も良いという点で一番に薦められる録音です。そして最大の特徴は使用しているピアノがショパンが愛用していたメーカーの、その時代のものだということかもしれません。1851年フランス製のエラールで、ショパンの音が聞けます。ショパンは二つのピアノを愛用してましたが、もう一つはプレイエルで、そちらはその社長の御曹司、カミーユが許嫁を奪ったとしてベルリオーズが殺害計画まで立てたという会社のピアノです。イギリス式のシングルアクション構造から一度キーを完全に戻さないと同じ音は打てないため、 ショパンは気力の充実しているときしか弾かなかったといいます(そのピアノを使った録音についてはすでに「静かなタッチ」のページでボーグナーのノクターン集をご紹介していました)。それに対してこちらのエラールの方はダブルアクションという、現代のピアノの基本となった機構を開発した上で備えていました。音も大きく出せてダイナミックレンジが広くなります。音色の点ではそれぞれに良さがあるので、聞き比べてみるのも面白いかもしれません。現代のピアノに慣れた耳にはどちらもその前身であったフォルテピアノに多少寄った音に聞こえるとは思いますが、エラールの方が今の楽器に近い艶を持っているでしょうか。それとこの演奏、合わせるオーケストラの方もピリオド楽器の楽団です。ただしロマン派ショパンの時代であり、バッハやモーツァルトで聞かれることがあった、せわしないピリオド奏法のイントネーションはもちろん採用していません。 エマニュエル・アックスは1949年生まれの、ポーランド=ユダヤ系でアメリカ国籍のピアニストです。ピアノはポーランドとカナダで、アメリカに移住してからはジュリアードでポーランド系の先生に学びました。古典から現代まで幅広いレパートリーを持った人です。1974年の第1回アルトゥール・ルビンシュタイン・コンクールで1位でしたが、速いところで指が回るのはもちろん、ヨーヨー・マともよく一緒に活動して息の合った反応の良さを見せています。ポーランド生まれだからというだけでなく、ショパンは理想的かもしれません。 演奏の具体的なあり方ですが、この人も揺らしが見事です。速さを追求せずに緩める表情を付けるツァハリアスとは違い、速いパートでは高い技術に支えられて高速でさらさら流すところもあるため、両端楽章を聞いているだけだとピアノの音の違いにばかり目が行き、揺らしの表情は聞き逃してしまうかもしれません。でも第二楽章ではそれがよく分かります。間合いが自在でありながら洗練されており、魅力の点でツァハリアス盤と並びます。その歌い回しはどうでしょう。静謐で、早めたり遅らせたりの絶妙なリズム感がありながら自然であり、もうそれしかないという完璧さです。ショパンの最高のルバートでしょう。遅らせては帳尻を合わせて戻す一方だと情緒的にたっぷりした感じになるのに対して、前述の通り所々で先打ちも出すと、その独特のリズムによってはかなさや粋な感じが出て来ます。ツァハリアスと同様にそんな感性を身につけているので、このアックスの緩徐楽章も魅力的です。 1998年のソニー・クラシカルの録音は音の点でも最優秀と言って良いでしょう。この CD は二つの協奏曲にソナタやバラード、マズルカといった主だった独奏曲が聞け、ヨーヨー・マらとのチェロ・ソナタやピアノ三重奏まで入っていて一枚の値段というお買い得6枚組です。他に日本盤では1番と2番の両協奏曲をカップリングした一枚ものも出ていました。2番の協奏曲はピリオド楽器のオーケストラ伴奏という意味で響きも良く、室内楽的な味わいの次の白神典子盤と並んでその曲の最も美しいものの一つだと思います。 アックスはこれに先立つ1978年にも RCA にオーマンディ/フィラデルフィア管 ♥ と協奏曲二曲を録音しており、そちらは通常のピアノとオーケストラによるものでした。録音も良く、モダン楽器の方が良い方にはお薦めです。表現は基本的には同じで、第三楽章でオーケストラがゆったりやるところもあるものの、揺らし方はよ り控えめです。比べれば若干薄味で形の完成度が高い、インターナショナル・スタンダードという感じでしょうか。静けさを感じさせるデリケートな味わいも同じで魅力的です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Fumiko Shiraga (pf) ♥♥ Jan-Ingwe Haukas (b) Yggdrasil Quartet ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 白神典子(pf) ♥♥ ヤン・インゲ・ハウカス(ダブルベース)/ ユグドラシル四重奏団 これは驚きというか、予期せず見事なパフォーマンスに出会えた感じだったのが白神典子(しらがふみこ)です。日本のピアニストをあまり取り上げられて来られなかったのでよかったと思ったのも束の間、調べるとこの人、生まれは日本でも六歳からずっとドイツ育ちとのことでした。残念ということも納得ということも特にないのですが。1967年生まれで、これについては大変残念ながら、2017年に四十九歳で乳がんのために亡くなっ ているようです。 日本人のピアニストといえば、大御所は中村紘子でしょう。実はショパンの1番の協奏曲、初めて知ったのは彼女の演奏でした。たまたまあった LP を聞いてなんと美しい曲だろうと思い、演奏に関しても全く不満がありませんでした。いくつかあるようだけどどの録音だったのだろう、見本盤のスタンプが押されたものであり、比較的若いときのものだったに違いありません。十六歳の1960年にイギリスで演奏した着物姿の映像があるけれども、その頃の真っ直ぐな表現に近かったと思います。現在手に入る複数の CD を聞き比べるのも楽しいかもしれません。インターネットでは2009年の N響とのものも見ることができます。六十五歳のときの円熟の演奏で、そちらは案外大きめの表情があって意外でした。弱音はより弱く、やわらかく弾いていて思い入れがあり、隣り合わせの音を連ねる場面では間隔・強弱ともに均等な日本の美はまだ持っていながらも、延ばす方向で表情を付けます。また、遅らせた音を思い切って強く叩く場面がある一方、かなりの間を置いてから大胆に弱めるところも聞かれます。フレーズ全体に渡って大きくスローダウンしたりもします。師匠譲りのロシアン・スクールの情緒だと言えるのかもしれません。着物を着ていた少女はあの後、ずいぶんロマンティックな表現を磨いて行ったものです。 その中村紘子はショパンやチャイコフスキー・コンクールの審査員を何度も歴任して来た人で、その舞台裏を描いた本で大宅壮一ノンフィクション賞も取っています。読みましたが、面白い比喩や教養ある引用を駆使し、男言葉の毒舌も散りばめた日本文壇っぽい語り口です。嫌味がなく、ストレートな感じがするのはピアノと同様、この人の性質なのでしょう。でも時は流れ、2016年に七十二歳で亡くなってしまいました。 白神典子の話でした。では果たしてこの移民のピアニストは、かつて中村紘子もそうだったような和の美を体現していると言えるのでしょうか。二十九歳のときの演奏です。一つひとつの音のつながりが均等ではなく、どの部分も息をしています。ワールド・スタンダードと言えるでしょう。大きな崩しはなく、ツァハリアスよりも揺れは少ないのでフランソワのような「鬼才」とは言われないことでしょう。変わってるのがいいとも限りません。内側の感覚に従って自らは透明になり、湧き出す奔流を解き放つのも名演です。人としての性質に関してはよく分からないけど、馴染めない環境で自分探しの旅をして来たからでしょうか、凛とした芯の強さが感じられ、どこか求道者のような趣もあります。 具体的に言うと、速度の揺らぎが絶妙です。真似して習得できるものではないセンスを感じます。少し重く粘るようなところもあるけれども、それも美点です。ふわっと速度を緩め、そこから感情の高まりとともに自在に速まる呼吸があったりもします。したがって第二楽章での感情の乗せ方はため息の出る見事さです。タッチに微妙な変化が付き、スタッカートが何音か続くところも単純にならずに不均等さを混ぜ、かすかに弾みます。最上質のロマンツェ・ラルゲットです。 そしてこの盤はピアノ六重奏版です。こうした取り組みは他の演奏者でも聞かれ、ピオトル・パレチニ盤(取り上げていないもの)、ジャン=マルク・ルイサダ盤、ダニール・トリフォノフ盤、ジャンルカ・ルイージ盤などがありますが、大抵は「弦楽五重奏+ピアノ版」です。こちらも英語にすれば chamber version なので同じだけど、この白神盤は本来のオーケストラ・パートでもピアノが鳴っているという編曲が独特です。ルイサダ盤のようにオーケストラ部分のみを「四重奏+コントラバス」のようにすると普通だけど、こちらはより室内楽を聞くような感じになります。 使用しているピアノはヤマハ製です。コンサートグランドではないようです。ヤマハを好んで使う有名ピアニストにはピリスなどもいますが、弱い音を駆使するせいかコンサートでは若干オフに響いてた記憶があります。ヤマハを「キラキラした音」だと言う人もいるけど、確かに高い方で強く叩くと硬くキンと響く場合はあるでしょう。それを金属的と表現してしまうと、スタインウェイの倍音を説明するときと同じように感じます。でもああいうやわらかい響きの奥にきらっとした芯があり、それが艶の成分になるような音ではなく、完成度の高い均質で透けない色の輪郭によって表面がかっちりと見えるような強度と真面目さのある音です。同じく日本のシゲル・カワイの、シルクのようにしっとりした艶をまといながらも余分な倍音を乗せない透明な響きというのとも違います。最後にヤマハを選んだグールドがこつんとした音を響かせてる瞬間もあった気がします。調整すれば独特の丸い艶のある真珠のような音色も出せるにせよ、抑え過ぎると今度は綿でくるまれたようになります。この出方には好みがあるでしょう。ここでの録音ではわずかに反響のある中音もあり、硬い方ではなくて落ち着いた音に聞こえています。そもそもコンサートグランドと比較してはいけないと思います。小型のピアノというのは、ショパンのサロンでの演奏を意識したのでしょうか。 1996年 BIS レーベルの録音コンディションは大変良いものです。カップリングは2番の協奏曲で、出だしから正に室内楽の喜びが味わえ、2番の魅力を再発見するかのようです。ピアノ六重奏版ゆえにブラームスの室内楽のような厚みも感じさせて魅力的であり、ショパンはオーケストレーションに問題があったというのもこの曲については少し言えるのかなと思ったりもします。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Hans Richter-Hasser (pf) ♥♥ Hans Rosbaud Südwestfunk-orchester Baden-baden ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ハンス・リヒター=ハーザー(ピアノ)♥♥ ハンス・ロスバウト / バーデンバーデン・フライブルク南西ドイツ放送交響楽団 個人的好みによる番外編です。モノラルで、バックのオーケストラの音も割れるのでお薦めは出来ません。 ジャケットの写真はハンス・ロスバウトです。現代音楽への理解が深く、正当に評価されて来なかったと言われることのあるオーストリアの指揮者であり、五つの楽器を弾きこなし、古代も含めた世界の文学を原語で読み、科学雑誌から学ぶのが趣味だったという高度な才能を持った人で、この CD が企画として取り上げているのです。またピアニストとしては、この盤はショパン弾きとして名高いニキータ・マガロフが演奏する、カップリングの2番の協奏曲の方が目玉なのかもしれません。マガロフはフィリップスから70年代(1974〜78)に独奏曲全集、62年に1番の協奏曲を出していましたが、2番はないと思われていたところに、この指揮者のシリーズであらためて出て来たからです。そちらは1951年の録音です。 一方で、第1番の協奏曲を弾いているのは1912年生まれで80年に没したドイツのピアニスト、ハンス・リヒター=ハーザーです。この人はあまり知られてないかもしれません。十六歳でデビューしたものの、ナチの時代に高射砲部隊で戦っていて技術を落とし、その後再起したという話が wiki に載ってるぐらいで詳しいことは分かりません。8.8センチ砲でも撃っていたのでしょうか。映像で振り返られるヒトラーの軍隊は悪の権化として扱われますが、一兵士としては、皆と同じ人間が狂気へと否応なく駆り立てられて行ったのだとしか言いようがないでしょう。ピアニストとしてはショパンよりもベートーヴェンなどのドイツものの方が有名だったようです。かっちりとした後期ソナタやカラヤンとのブラームスの協奏曲などを聞いてみたけれども、録音はともかくとして、何といってもこのショパンの第二楽章での力の抜けた軽やかな歌が大変良いのです。 演奏ですが、ダンパーペダルというよりは会場の反響によって音が持続する一方、静けさがあり、香り立つような繊細な表現が聞かれます。無理のない抑揚のつけ方ながら平凡ではありません。具体的には細かな揺れではなく緩やかな揺らぎあり、面白い強調を入れるところや遅らせて大きく震わせる部分もあります。皆がそうするところで敢えて装飾を加えずに運ぶ場面にも出会います。でも分かり難いので喩えにすると、レースのカーテンが穏やかな風になびいて、その向こうで光がきらきら踊っています。あるいは、街の賑わいをにじみのある望遠レンズで見ているような感覚でもあります。原色の点を並べつつもやわらかい印象派絵画の光の表現のようだと言ってもいいでしょうか。却って分かり難くなってしまったでしょうか。第二楽章について見れば、力が抜けていると同時にアタックがほんのわずかに遅れるところがそう感じさせる一因かもしれません。落ち着きがあって感傷的ではなく、ちょっと並ぶもののない種類です。私生活は知らないけど、恐らく名声だとか自分を見せてやるだとか、そういうクライマー的な欲はこの時点で超えているのです。動乱の時代を生きた人のこの軽やかでやわらかい音には感じ入るものがあります。居心地良く思えるものだけを求め、周囲にすでにある美しさを見出して満足しているのだろうと思います。 マイナスのことも言うなら両端楽章では指がもつれて怪しい箇所もいくつかあります。技術に目が行くファンとっては俎上に乗らないレベルでしょう。個人的にもモノラルの録音は好んでは聞かない方だし、♡♡を付けたステファンスカ、 アブデーエワ、ネボルシンなどを後ろに並べておいて、このリヒター=ハーザーだけ最初のグループで取り上げるのも不平等です。でも古さを押してでも最初にここに置こうと思った特別な魅力があることも確かなのです。 第二楽章のことだけ具体的に触れましたが、第一楽章でもやわらかく繊細に崩し、流動的なフレーズである一方で、音には軽さがあってくっきりとしています。やはり力で押して来たりはしません。第三楽章の速いパッセージも、技術的な意味ではなく、軽々と流しています。 1961年のスタジオ・モノラル録音で、レーベルはヘンスラー SWR クラシックです。コンディションは上記の通りで、多少もやがかかったように聞こえるところもあります。そんな状態でもピアノさえきれいに聞こえてれば楽しめるなら聞いてみてほしいです。純粋に心に響いた一枚であり、ショパンのこの曲で最も聞きたいのはこの演奏の第二楽章かもしれません。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Arthur Rubinstein (pf) ♥♥ Stanislaw Skrowaczewski The New Symphony Orchestra of London ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)♥♥ スタニスラフ・スコロヴァチェフスキ / ロンドン新交響楽団 ショパン弾きの権威である19世紀ポーランド生まれのピアニスト、ルービンシュタイン (1887-1982)については、そのタッチの重さ、所々で立ち止まるような拍の取り方が苦手で長らく敬遠して来ました。でもちょっと聞いただけで食わず嫌いになるのはまずかったとラフマニノフの協奏曲では思い直したのでした。そしてこのショパンでも同じことになりました。特に最初は当のショパンで苦手に思ったにもかかわらず、あらためてこの晩年 に録音した協奏曲を聞いてみて評価逆転、こういう風に弾ける人って他にいないんじゃないか、ぐらいのお気に入りになってしまったのです。 七十四歳のときの演奏です。最大の美点は緩やかなパートでの枯れた味わいですが、まずは最初の楽章からです。さらさらと速弾きするところが意外でした。そういえば「大公」にも駈けるところがあったのを思い出します。間をとって遅らせ気味に叩く重さはほとんどありません。テンポを自在に伸び縮みさせて力を抜き、むしろ軽さを感じさせるほどです。 さて、素晴らしかったのは第二楽章です。ゆったりながら力が抜けており、案外さらっとした感触で耽溺しません。ただ、達観はしてるけど、どことなく寂しさを感じているような雰囲気が漂って来ます。何と言うのか、はかなく壊れ行くものを大切に守っているような、あるいは、それが真実だから受け入れるけどまだ諦めたわけじゃないんだ、というような。前向きとは言わないけど思わず引き込まれる美しさで、他の演奏では聞いたことがありません。余裕の揺らしは気持ちを乗せて行くというよりも、興奮を抜いて行くもので、秋の日の夕暮れ前の明るい光のようです。これはもう若いショパンの憧れではなく、その体を借りた別の告白でしょう。一度作者の手を離れた作品はこういう風にやってもいいのです。技術の意味ではなく、これは芸の到達点であり、最も美しいラルゲットの一つです。 第三楽章は指を回して素早く弾いたりせず、速いところでも細かな揺らぎを加えますが、以前のようなアクセントは出しません。この人としては案外真っ直ぐ力まずに流して行きます。全盛期の録音の方が技術面では良いという考えもあるかもしれないけれども、聞いていたいのはこちらの方です。 RCA1961年の録音はバランス、音色ともに申し分がなく、ほぐれていて艶のある音なので大変心地が良いです。リマスターも効果を発揮しているのでしょう。四年後のフランソワのより音はずっといいです。 これ以前の録音としては、アルフレッド・ウォーレンシュタイン/ロスアンジェルス・フィルとの53年のモノラル盤が定評があります。六十六歳時の演奏です。第二楽章で比べると、間を空けてから強めに打ったり、立ち止まるように拍を遅らせるところが顕著で、多少引っ掛かる印象です。若いときの方がテンポが速い分、その脈動もはっきりと目立っており、個人的にはそれが重く引きずるように感じられたわけです。でも別にもったいぶってるわけじゃないでしょう。あるいは19世紀的なルバートとして一括りにされるものかもしれませんが、それならその奏法で有名なアルフレッド・コルトーと比べてみると違いがはっきりします。 コルトーは遅いところはずいぶん遅く、弱いところではしっかりと弱くしており、フレーズの切れ目でもたっぷりと間を置く一方、もっと滑らかに、波のように全体に延ばしたり走ったりしています。情熱的な感じがします。間を空けて拍をため、こつんこつんと遅らせることを繰り返すのではありません。ではルービンシュタイン独特の、この止まるような節回しが美しくないかというとそういうわけでもなく、聞いているうちに案外癖になって来るから不思議です。 それ以外にもバルビローリ/ロンドン響とのものや、ワルター/ニューヨーク・フィルとの演奏も出ています。それらも61年盤より速い揺らしという点では共通しています。
 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Maria João Pires (pf) ♥♥ Emmanuel Krivine Chamber Orchestra of Europe ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)♥♥ エマヌエル・クリヴィヌ / ヨーロッパ室内管弦楽団 ピリスもいいです。1944年ポルトガル生まれのピアニストですが、弱音を駆使し、ダイナミックな立ち上がりとたっぷりとした抑揚があるのに、どこか素直で真っ直ぐな感じがします。丁寧でやさしくて、暖かみも感じられます。ケンプに師事した人であり、フランソワやボレットなどのように鬼才と呼ばれるひらめきタイプの演奏ではないけれども、大変気持ちが良いです。個人的な好みから言えば多少思い入れが大きい気はしますが、録音もきれいです。 第二楽章ではやわらかく入ってそこから湧き上がるように強める表現や、すっと弱める情感豊かな音遣いが聞かれます。ゆったりとしたテンポで、表情としては大きめなのにわざとらしくは感じません。波のように繰り返し訪れる感情の高まりと鎮静が心地良いです。沸き立つような揺れをともない、速くなるところではドラマチックな感じがする一方、表現としての意外性はないかもしれません。 第一楽章も同じような弾き方で一貫しており、トータルでは落ち着いているとも言えるでしょう。第三楽章もテンポは遅め、走らないで一つずつ丁寧に陰影を付けて行きます。 1997年ドイツ・グラモフォンのセッション録音です。ヤマハが好きな人ながら、楽器については書いてありません。結構くっきりとした音です。 旧盤も存在しています。アルミン・ジョルダン/モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団による1977年のエラート盤です。そちらの方が運びはより軽やかでさらっとしています。テンポもトータルでは速めですが(全楽章でタイムは短い)、部分的には逆転して遅く感じるところもあります。フレーズの終わりで音を延ばして間を取ったりするからです。でも弱める音のデリケートさなどは新盤と基本的には同じだと言っていいでしょう。感情表現は素直です。物理的に真っ直ぐ弾いて行くフレーズもあり、ちょっと日本の演奏家のように聞こえる瞬間もあります(例えば第二楽章で三分半以降に来る、二度フレーズを繰り返して二回目に装飾が入る初回の部分など。中村紘子もそう弾いてるのがあります)。したがって素直で初々しいのが良ければ旧盤ということになるでしょう。1番と2番が一枚に揃ってるのも利点です。新録音の方の2番は同じときには入れておらず、92年にプレヴィン/ロイヤル・フィルと録音しています。両者をまとめて一枚にした CD も出ていますが。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Murray Perhahia (pf) ♥♥ Rubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 マレイ・ペライア(ピアノ)♥♥ ズービン・メータ / イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 ペライアも良いのです。1947年生まれのユダヤ系アメリカ人ピアニストで、ショパンだからといって大きく崩すルバート様の表現はしませんが、デリケートな表情があります。アゴーギクについては遅らせる方向のためは駆使します。早まるように駆ける拍は出しません。したがって落ち着いて聞こえます。テンポは緩徐楽章でもさらっとしてやや速めです。しかし他のところでも述べたのですが、独特の秋の景色のような情緒があります。決して耽溺しないのに少し悲しい音が響きます。技術的に言えば小声に落とす弱音の使い方と関連があるのでしょうが、いつもなのでこの人の波長のように感じて仕方がありません。悪いのではなく、そこが最も美しいポイントだとも言えます。そういう感情を共有したいかどうかは人それぞれでしょう。大変洗練されていて上品で、速いパートでは軽快であり、自在な動きと強弱で囁く最上質なショパンです。 1989年ソニー・クラシカルのライヴ録音です。派手さのないピアノの音できれいな録音です。最後に日本のブラボー先生に負けない俊敏さでテル・アヴィヴの聴衆の歓声が楽音に被ります。79年のニューヨーク・フィルとの旧盤もあります。 ショパン・コンクールの覇者たち  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Halina Czerny-Stefanska (pf) ♥♥ Vaclav Smetácek Tonhalle Orchester Zürich ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ(ピアノ)♥♥ ヴィトルド・ロヴィツ キ / ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 ここからはコンクール優勝者を見て行くことにします。まず最初は、しばらくの間リパッティだと信じられて来た人の演奏です。どうしてそういうことになったのか分かりませんが、1966年に EMI からその録音が出された後、71年に出たイギリス盤には「指揮者とオーケストラは不明だけど、ソロイストはリパッティ(ディヌ・リパッティ 1917-1950/ルーマニアのピアニスト)に間違いない」という趣旨のことが書かれていたのだそうです。それを BBC が81年になって放送したところ、聞いていたリスナーがヴァーツラフ・スメターチェクの指揮したチェルニー=ステファンスカの50年代初期のスプラフォンの録音に似てると投書して来て、調べてみてそれが証明されたということです。日本ではその盤をリパッティのものとして評論家がこぞって褒めたようだけど、 馬鹿ばかしいというよりも、正体が分かった後に当のステファンスカ盤が忘れ去られた方が残念です。 ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ(1922-2001)は戦後最初のショパン・コンクール(第4回1949年)に優勝したポーランドの女性ピアニストで、ショパン弾きとして演奏活動を始めましたが、第2番のコンチェルトは好きではないので弾かないなど、当初のレパートリーは少なく、録音もいくつか出したけれどもさほど有名になったとは言えません。でもこの人の第1番、良いのです。ここで取り上げるのは当の間違えられた録音ではなく、この CD セットにそれとともに入っている、より新しい方の録音です(パデレフスキ版による生誕150周年記念の20枚組旧ショパン作品全集での演奏も同じ)。どうせならコンディションの良いものの方を選ぶべきでしょう。 最初にレコード会社が間違った表記をしたことを除けば、人々が混同した件については仕方がないと思います。この人の演奏、出だしの確固とした足取り、素早く駈け降りて来る次の下降音型、途中でゆったり歌わせる表情など、形の上でかなり似ています。ここでは新録音を取り上げますが、問題になった方の録音ではよりピアノの音の輪郭がくっきりしているせいもあり、リパッティのタッチに近づいて聞こえるとも言えます。そもそも目隠しされて聞かされた演奏でピアニストが誰だか分かる人などどれだけいるでしょうか。例えばバラードの1番でミケランジェリとツィマーマンの演奏をかけられたとします。 二人に抱くイメージがまるで性質の違うものとして別の引き出しに入れられていたとしても、どっちがどっちか分からなくなっても当たり前な気がします。 この新盤の方のステファンスカ、リパッティと比べるとよりやさしさがあり、ふわっと包むような感覚で家庭的です。今の自分を満足して受け入れているというのか、穏やかな感じがします。リパッティの方が作品そのものをクリスタルな美で表現しているかもしれないけど、リストではなくショパンには、このステファンスカのようなアプローチが合っている気もします。ロジーナ・レヴィーンほどロマンティックにためを効かせず現代的ながら、女性が進出するのがまだまだ難しかった時代、世界的名声は得なくても満足して生きた人なのでしょうか。 第一楽章に関しては旧録音と同じ傾向ではありますが、音色に加えて抑揚にもよりやさしさが感じられます。くっきりはしてるけど、区切って輝かせ過ぎたりしないタッチであり、前に押して来ません。ゆったり歌わせるところでは包み込むようなやわらかさがあります。一息ついて少し遠くから眺める目線とも言えるでしょうか。軽やかで、アゴーギク、ディナーミクともに、これ以上自然にはできないでしょう。それが第二楽章にも当てはまり、見事にソフトな癒しのロマンスです。このときのショパンはコンスタンツィヤ・グワトコフスカに憧れ、旅立ちに際して後ろ髪を引かれる思いもあっただろうし、本人は「美しい春の月の光に照らされた瞑想の気分と懐かしさ」を表したかったと語ったけど、明るい春のそよ風です。第三楽章も軽く弾んで楽しく、優美な感覚に満たされています。 旧盤はヴァーツラフ・スメターチェク/チェコ・フィルとで1955年の録音でした。こちらは1960年のステレオで、音は大変良いです。最新録音と同じとは言わないまでも、この水準なら問題はないでしょう。少し春霞のような薄い反響が乗るけれども、それがまたきれいに聞こえる録音です。弦も潰れず、ピアノは硬質になり過ぎずに華やかさが感じられて、噴水の水が跳ねるようです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Adam Harasiewicz (pf) Heinrich Hollreiser Vienna Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 アダム・ハラシェヴィチ(ピアノ) ハインリヒ・ホルライザー / ウィーン交響楽団 1955年のショパン・コンクール(第5回)で、前回に引き続き本国ポーランド人として優勝したピアニストです。1932年生まれ。せっかく1位になったのに、審査員のミケランジェリが2位のアシュケナージの方が上だと言って降板してしまうという事態になりました。水を差されて本人はどう思ったでしょう。その後国際的に活 躍して録音も残したものの、大変有名になったとも言い難い感じです。日本では CD も安定リリースされていません。元々が売れる人に共通した派手さで勝負するタイプではないこともあるでしょう。したがってこの人らしい語法というのは明記し難いです。でもいい演奏をします。特に独奏曲は味わいがあります。深く歌って揺れもあり、繊細な表情も聞けます。同じフィリップスから全集を出したマガロフも派手に崩すタイプではないので似た路線ではありますが、比べればハラシェヴィチの方がよりくっきりなのに軽く、フレーズの途中で早める処理が聞かれるのに対し、マガロフの方はやや強さを感じさせる一方で全体としてはやわらかく、ゆったり聞かせる曲があったりします。時期によって若干弾き方が異なるのかもしれないけど、2010年までかかって録音した NIFC レーベル(ポーランド・ショパン協会)のマズルカなど大変良いし、もっと前のフィリップス時代の録音である「別れの曲」も自然ながら思い切った表情があり、この親しみやすいナンバーを奇をてらわずに聞かせるベスト・パフォーマンスかと思います。 ただ、この企画では第1番の協奏曲で比べているわけで、そうなるとハラシェヴィチの1番はステレオ最初期の1959年の録音であり、オーケストラに合わせている面もあるのか独奏曲ほどには自在な動きが少なめです。2番の方はデジタル時代になった91年に米レーザー・ライト(デルタ・ミュージック)から新しい録音が出ています(カジミエシュ・コルト/ ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団)。一音ずつ分離の良いタッチで間を取りつつ落ち着いて進める魅力的なもので(第二楽章は白眉です)、ぜひ1番の方も再録音してくれないかなと思ったりします。なぜかその盤でカップリングになっている1番はハンガリーのピアニスト、シャーンドル・ファルヴァイ(1949-)によるものなのです。前述リパッティと間違われたハリーナ・チェルニー=ステファンスカと同様、そちらも黙って聞かされるとハラシェヴィチと勘違いするかのような演奏ではありますが。 さて、その1番の演奏です。ニュートラルで癖が少ないものと言えるでしょう。同じようなことを下記のネボルシン盤でも言ってるけど、それと比べるとよりタッチに力が入っていてくっきりしています。コンクールのファイナルでの演奏はもう少しやわらかく聞こえた気もしたので、録音の加減もあるかもしれません。この盤では余分なことはしないけれども明晰に、通常速弾きするところもさほど走らずに丁寧に音にして行きます。一音ずつが分 離しており、多少かたかた弾かれる感じです。もう少し滑らかでさらっと流した方が好みではあります。 そしてその端正な抑揚についてつぶさに見ると、フレーズの途中で瞬間的に駈けるというか、短く切り上げる表現にやや特徴があります。一続きの歌をうたって来たところで、十分に延ばさずに次につなげる音符が出るという意味です。結果的に力が抜けてあっ さりに感じます。一方で一般的なためも効かせます。ただしショパンらしいルバートと言うよりももっと控えめな印象です。第二楽章では音節の終わりでかなり速度を落とすところもありますが、基本は同じであり、スムーズに延ばさない短めの末端処理が聞かれます。トータルでは伝統的なイディオムからは外れていない抑揚であり、端正ではあってもさすがはポーランドの人だなと思わせます。 1959年のフィリップスです。良い録音が多いレーベルだけど、時期が時期なので少し古さを感じさせます。上に掲げたジャケット写真は顔が分かるように古いアナログ LP のものにしましたが、その後リマスターされた CD も出ました。ただ、現在入手できるのはフィリップス系(デッカ・レーベル)の全集10枚組ぐらいのようです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Maurizio Pollini (pf) Paul Kletzki Philharmonia Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 マウリツィオ・ポリー ニ(ピアノ) パウル・クレツキ / フィルハーモニア管弦楽団 1960年にショパン・コンクールで優勝したポリーニです。これはその直後にスタジオ収録されたもので、その後彼はこの曲を録音していません。長らく名盤とされて来たこの人の原点です。1942年生まれのイタリア出身で、当時十八歳。ご存知の通り、ポリーニは技巧に優れたピアニストとして人気の人であり、ショパン・コンクールの方もこの後アルゲリッチ、ツィマーマン(75年)ぐらいまでの間、一つの黄金期を迎えました。彼以 外に超絶技巧を讃えられるピアニストとしては、古くはホロヴィッツ、ミケランジェリ、それからツィマーマン。同世代にはカツァリスもいます。技巧というのは表現の基礎であり、建物で言えば鉄筋やセメントでしょう。だから「技巧派」という表現スタイルも本来は存在しないのだと思います。でもこの人を聞いていると分かる気もします。 その後色々賛否が分かれたポリーニだけど、これはキャリアの最初であり、最も若々しい演奏ということになります。後年にはないものがあるという人もいますが、この人らしい個性はこのときから変わらと思います。最初から完成されていたと言ってよいのではないでしょうか。あっさりとしていながら表情もよく付き、技術の方は当時の審査員が「誰もこんな風に弾けない」と言いました。天才だと思います。サヴァンの類なのか、ちょっと普通の人とは成り立ちが違う気がします。指が回るなどと言うのも憚られるほど、難しい部分でも嬉々として超速で、粒を揃えてきれいに弾き切ってしまいます。そしてそう弾くことがこの人の中で最大の快感なのではないかと想像します。そういう箇所にさしかかるのを待ち構えてるように感じるからです。誰かにやめろと言われるまでいつまでもバラバラと弾いていたいのではないでしょうか。カツァリスにもちょっと似た側面があるけど、このショパンでは分かり難いかもしれません。どっちにしても好きこそ物の上手なれで、楽しいのはいいことです。 では、緩やかなパートはどうでしょうか。例え話ですが、冗談というものを理解できない教授で、でも講義では満場の生徒をどっと沸かせる冗談を言う人がいるそうです。ちょっとそういう種類に似てるのかもしれません。こんなことを言ってもいいのかどうか。教授はたゆまぬ努力で人が何に笑うのかのパターンを研究し、その境地に達したのであり、それはもはや芸術です。ではポリーニはというと、やや薄味ながら見事な抑揚があります。完璧と言ってよいでしょう。ただ悪くとらないでほしいのですが、ある種シームレスで見事なコラージュではないかという気もします。この曲のこの部分を最も良い形で演奏しているのはどんな例か。そこから最善のパーツを集めて来た。だから美しい写真だけで構成されたパーフェクトな作品なのです。借り物とも言わないけど内側から吹いてきた風ではなさそうに思えます。個人の感想です。でも今や人間の棋士は AI に勝てない時代であり、デジタルも情報量が増えればアナログより滑らかになります。これを超えるものは出ないかもしれません。 1960年の EMI です。現在は ART リマスターされています。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Martha Argerich (pf) Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 マルタ・アルゲリッチ (ピアノ) シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団 ポリーニの次の1965年にショパン・コンクールで1位だったのがアルゲリッチです。凄い人です。1941年生まれで、受賞時は 二十四歳でした。ポリーニに続く超絶技巧第二弾であり、ブエノスアイレスのつむじ風。近頃はユジャ・ワンなどとも比べられたりするようです。でもこのページではあまり取り上げてない何人かのうちの一人です。昔「夜のガスパール」のオンディーヌの終わりで驚いて以来、時計が止まってしまったからです。 ここでジャケット写真を掲げたのは1998年のデュトワとの盤です。その指揮者デュトワとは一時期夫婦関係でしたが、このときは離婚した後です。でも長年の同志の大人の関係で、仲は良いようです。 コンクール優勝の三年後に録音したアバド/ロンドン交響楽団盤(1968年ドイツ・グラモフォン)の旧盤を褒め、こちらを評価しない声もあるようです。切れ味がなまったからとのことのようだけど、そうは聞こえません。確かにアゴーギクは前の方が素直であり、より軽やかで直線的に駈けるところが鋭さに感じられます。ですからそう信じるなら直感に従ってそちらを選んでほしいと思います。対して新しい方は、意図してよりショパンらしいルバートをおごってあげてるようです。でもさらに強靭になった一面もあります。これ以上切れたら斬鉄剣です。 とにかく迫力ある演奏です。その緊張感と爆発性は怒ってるのかと心配になるほどです。怒ってるようには聞こえないユジャ・ワン同様、この人も怒りがあるわけじゃないと思いますが、例えて言うなら蒸気機関車のシリンダー内圧が高まり、バルブ開放とともにスチームが噴き出す勢いで弾く感じです。蒸気機関を馬鹿にしてはいけません。蒸気ロケットも打ち上げは6Gを超えます。速いところは稲妻のように速く、ゆっくりのパートでのポーカーフェイスな場面でも圧は変わりません。開放された最初のフォルテが前述のラヴェルの一撃であり、その後は止まらないのです。ただ、同じ技巧派でもポリーニがやめられない速さだとすると、アルゲリッチは見せる速さでしょう。まるで格闘家が鍛えた型を披露するかのごとく「ここまで弾けてる技を見なさい」と注意を喚起しています。完璧な技巧と切れの良さは挑戦者の戦意を喪失させます。そういう趣味の男性票のみならず、コンクールは即決1位でなければ嘘です。激しいものに人々は惹きつけらますから、今後も人気は衰えることがないでしょう。がつんと戦闘モードの武闘派ショパンです。 1998年。前の盤から三十年後、五十七歳時のデッカの録音です。見事な音です。最近アルゲリッチは本人とは性質が大きく違う韓国のピアニスト、イム・ドンヒョクを気に入り、母性を発揮して面倒を見ているといいます。その昔は本物の親子だったのでしょうか。時代を超えた愛の物語です。ドンヒョクのショパンも探したけど、2番だけで1番は出てないようです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Garrick Ohlsson (pf) Jerzy Maksymiuk Polish Radio National Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ギャリック・オールソン(ピアノ) イルジー・マクシミウク / ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 1970年のショパン・コンクール、前回のアルゲリッチの次に覇者となったのはアメリカ人のギャリック・オールソンです。次のツィマーマンとの間に挟まれてあまり聞かれてないかもしれません。少なくとも日本では人気がない様子です。真面目な演奏なので不公平でしょう。 第一楽章ではがっちりとした力強さで断言するように出る場面もあり、ショパンというよりはむしろベートーヴェンかという堂々とした弾きぶりです。落ち着きがあり、決して走りません。間違いがないように確実に音にして行くという姿勢が感じられます。 基本的にはテンポ・ルバートによって揺らしたりする大きな抑揚表現はありません。
第二楽章も素直に真っ直ぐに弾き、間をとって遅らせることで表情をつけます。一つひとつのフレーズが丁寧です。トリルもゆっくりなのでやや生真面目な感じとなり、軽さはありません。渋い枯葉色というか、アースカラーの味わいです。聞きようによっては訥々としてるようにも感じられ、未来へのときめきではなく、過去の物語を淡々と喋ってるような感触です。 第三楽章でも走り出したりしないのは同じで、速いパートでも確実に音にして行きます。 1975年 EMI の録音です。2番の協奏曲とカップリングになっています。コンクールではこのとき二位が内田光子、三位が上でご紹介したピオトル・パレチニという順位でした。オールソンはこの後、2009年収録の新しい映像も出しています。そちらはアントニ・ヴィト/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団がバックを務めました。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Krystian Zimerman (pf, cond.) ♥ Polish Festival Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 クリスティアン・ツィマーマン(ピアノ/指揮)♥ ポーランド祝祭管弦楽団 ショパンの協奏曲での一番人気ではないでしょうか。1975年のショパン・コンクールで優勝したことと、ショパンと同じポーランド人であること、完璧な技巧を持つ一方で録音の少ない完全主義者であること、ピアノそのものへの知識が深く、美しい音色を奏でること、そしてこの二度目の録音は長い準備期間を経て構想を練ったものであり、自身が指揮をし、オーケストレーションにも手を加え、精鋭のオーケストラ・メンバーを集めて臨んだ録音であることがその理由だと思います。カードは揃いました。 ラフマニノフの2番でもグリーグでもこの人を取り上げ、きれいな音色で自在に弾き分ける魅力から♡♡を付けて来ました。ここでもその感触は変わりません。でもこのショパンでは、というよりショパンだからこそでしょうが、彼らしいたっぷりとした抑揚がより強くついているので一つ減らしました。個人的な好みの問題であって良くないという意味ではありません。これが好きだという人が今後も圧倒的に多いだろう名演です。
どんなに速くても音色が見事にコントロールされており、正に完全なるパフォーマンスだと思います。この人の録音でいつも感心する、炊き立てのご飯のような美味しそうな艶と芯、独自と言っても良いほど抜けのあるきれいな高音がここでも堪能できます。それだけでもう他を圧倒しています。それでは抑揚のつけ方はというと、速いところは正確で、言うことがありません。19世紀的なショパンのルバー トを期待する時代でもないので、崩しのないクリーンさも美点であると思います。でも情感がないかというと、あります。ちょっと外連味のある間を取り、大きな楽節単位で速くなったり遅くなったりします。消えそうなほどのピアニッシモもサービスしてくれます。緩徐楽章ではたっぷりと遅く、大きな表情を付けます。それならばロマンティックで耽溺するような運びかというと、ロマンティックだけれども耽溺とは違います。それが面白いところです。 どうしてそうなるのでしょうか。恐らくこの人は熟練の職人なのでしょう。己が巧みな技を自覚して喜びを覚えることはあるけど、内側から湧いて来る音楽の喜びに任せて行く感覚とは多少違うのかもしれません。情緒たっ ぷりな形で歌っているその瞬間に、音と音の間に元素が存在していないかのようであり、宇宙空間を音たちが慣性によって等速直線運動で散って行きます。無機質というより、抵抗を生み出す感情という媒質からの自由を感じます。ただ、それは本人が感情を感じることが出来ない結果ではなくて、ちょっとだけバランス感覚が違うのでしょう。 別の表現にします。赤いバラを持って恋人(聴衆)に会いに行くのです。何を差し出し、どんな言葉をかければ恋人が喜ぶかは熟知しています。でもどこか醒めていて、愛される喜びには感心がありません。母からの傷の仕 返しをするドン・ファンの恋愛ゲームではなく、その道の熟練者として甘い言葉をかけます。綿密な設計図があり、その上で相手の心を見ながら次の手を繰り出します。相手はめろめろになります。自分は酔わずに相手を酔わせるのです。でも悪意ではなく、喜ばせたいだけです。このように相手を喜ばせたいという場合、本当は相手の喜びイコール自分の喜びなのに、その間にそのことに気づき難くするフィルターが介在しているかのようです。バラに愛着があるわけではなく、ナイフを隠したピエロでもなく、甘いケーキの職人は甘くない顔のやさしいおじさんだった、ということなのでしょう。 似ているピアニストがいるだろうか。より感情的要素が希薄なポリーニとは別物だと思うし、一見似たところのあるカツァリスとも違います。この感触が共通するとすればただ一人、ベネディッティ・ミケランジェリでしょう。感情を燃焼させる速度は違うけど、同じように技巧派で完全主義と言われる彼もまた、甘くたっぷりと歌いつつ冷静です。両方が弾いていて直接比較できるバラードの第1番など、聞き比べると面白いと思います。政治意識が強く、親日家で、震災後は多くのチャリティー・コンサートをしてくれたそうです。 1999年のトリノでの録音で、レーベルはドイツ・グラモフォンです。このときツィマーマンは四十二歳。上述の通り、素晴らしいピアノの音が堪能できます。オーケストラの伴奏も良いバランスです。2番との黄金のカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Krystian Zimerman (pf) Carlo Maria Giulini Los Angeles Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 クリスティアン・ツィマーマン(ピアノ) カルロ・マリア・ジュリーニ / ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 新盤が表現意欲に溢れると思うなら、デビューしたての二十一歳のときならどうでしょう。ショパン・コンクールの三年後の初々しい演奏です。 弾き振りではありません。新盤ほどテンポを緩めたり間を大きくとったりはないし、消え入るピアニシモもそこまでではありません。微かなテンポの伸び縮みはあるけれども端正だと言えるでしょう。ピアノの音色自体は同じようにこの人らしくて美しいです。艶よりはキンとした金属的な方に少しだけ寄っています。新盤の方が磨かれた感じがするものの、これも良い音です。違うのは録音の加減でしょうか。演奏に関しては基本的な傾向は同じながら、こちらのより素直な抑揚の方が好まれる場合もあると思います。個人的にも音を考慮せずに形だけ言うのであればこっちの方が好きかもしれません。爽やかで丁寧です。 ただ、より自然な形ではある一方、音の中に「ないもの」を求める高い理想のようなものを感じます。完成度を追求する姿勢ゆえでしょうか。新盤でも聞かれる甘い歌は最初からあります。人物の予備知識で言うのではないけれども、相手と譲歩して上手くやる人というよりは、欲しいもの以外は要らないというストイックさがあります。要求条件が厳しいので、自分が本当に望むものを求めるのか条件で選んで行くのかという、この先の葛藤を予感させます。直感的にそう思うに過ぎませんが。 1978年のドイツ・グラモフォンで、アナログ録音です。新盤の方は弦の艶に特徴がありましたが、こちらはグラモフォンの標準的なバランスを持った良い録音です。同じく2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Dang Thai Son (pf) ♥ Frans Bruggen Orchestra of the 18th Century ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ダン・タイ・ソン(ピ アノ)♥ フランス・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ ツィマーマンの次の回、1980年のショパン・コンクールで優勝したのは1958年ハノイ生まれ、ベトナム出身のダン・タイ・ソンです。戦争でアメリカに勝った初めての国ですが、ショパン・コンクールでアジア人が1位になったのも初めてのことでした。しかしもし仮に中国本土のピアニストに特有のものがあるとしても、この人にはアジア人らしい特徴は感じられません。それともベトナムの文化に詳しくないことで見落としてる癖のようなものがひょっとしてあるのでしょうか。このコスモポリタンな感覚について、フランス統治が長かったからだなどと言うのもどうかと思います。モスクワ音楽院で学んだ経歴を持っており、洗練された豊かな表現力を備えていま す。 ショパンの協奏曲は看板にしているのか、何度も演奏しているようです。CD もこれより前の1992年にイェジー・マクシミウク/シンフォニア・ヴァルソヴィアによるビクター盤が発売されており、やや大きめのためが聞かれる一方で自然な抑揚があり、第二楽章などゆったりやわらかい印象なのでそちらを取り上げようかとも思いま した。でも廃盤のようであり、結局代表盤であるこちらにすることとなりました。 この演奏はブリュッヘンの18世紀オーケストラという古楽器楽団がバックを務めており、その大御所の指揮者に合わせたのかどうか、古典派を扱う場合のピリオド奏法に近い抑揚となっています。前倒しの拍と素早く駆けるところが聞かれるのです。こんな風に何にでも合わせられる対応力はすごいと思います。それなら、素の状態でのこの人の演奏マナーはどうなのでしょう。ちょうど同じ年にソウルで行われた演奏会の模様が動画になってましたので、まずそちらから見てみます。現代ピアノと現代オーケストラによるものです。こちらの古楽の演奏はそれと同じ傾向を根の部分で持っており、そこに少しだけピリオド奏法のアクセントを施したものと言えます。
速い楽章では結構速く、遅らせる間はあるけど拍を前倒しにした走りは見せません。フレーズの後半で速めるところはあります。そしてその遅らせ方ですが、かなり大きめです。キーシンほどじゃないけど一音ずつくっきりとさせる弾き方になっています。スタッカートも出します。トータルでは結構熱く、整然と弾くタイプではなく、熱情型かと思われます。ぐんぐんと力を乗せて来るのです。 第二楽章は結構粘って遅らせる表現が目立ちます。92年盤より感情的起伏が大きいです。かといってやり過ぎ感はありません。スムーズに流すのではなく、フレーズごとにためて間を取り、節を作るように表情を加えて行くので脈動的です。また一音ずつがくっきりしてるので、きらきらと流れるように下降して来る音型さえも分解されて聞こえます。というわけで、どうやら元々がピリオド奏法的に聞こえる流れを持った人のようなのです。 そしてこの古楽奏法的な新盤の録音でも基本は変わっていません。ソウルでの演奏様式の上に、小節の頭を揃えずに少し早めたり遅くしたりしています。遅くする場合はその分の遅れを駈けて取り戻します。ジャズっぽいフランソワのような揺らしとはまたちょっと違い、常に細かくリズムに乗ってる感触でもないけれども、ピリオド奏法という目で見ないなら自在なアゴーギクとは言えるでしょう。頭の拍で遅らせる手法はジャズと共通しているとも言えます。トータルではいわゆるピリオド奏法ほど大袈裟ではなく、丁寧な崩しです。この感覚は心地良いです。緩やかなフレーズ全体をスローダウンさせるような、フランソワにはない種類の大きなルバート的発想も出て来ます。若い頃よりも表現の幅を広げて来ているのだと思います。ソウルのときと同様、第二楽章ではやり過ぎとまでは行かな大きな表情を付けます。そしてそれでいて決して感傷に溺れません。丁寧さと崩しが両立している見事な演奏だと言えるでしょう。 最大の特徴と言ってもいいのが使用しているピアノです。エラールの1849年のもので、その音はエマニュエル・アックスの1851年製と比べるとよりフォルテピアノのようであり、コン、ピンとした響きです。1836年製のプレイエルを弾いているミシェル・ボーグナーの方(前述の独奏曲集)にむしろ近いぐらいに聞こえます。ショパンが愛用したこの二つのフランスのピアノ自体が、一般的なスタインウェイなどと比べると相互に似ている独特の音とも言えますが。 2005年のライヴ収録で、レーベルは NIFC(ポーランド国立ショパン協会)です。古楽オーケストラの響きが大変良く、弦の美しさではアックス盤を上回るかもしれません。ただ、咳は若干多めです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Stanislavovich Bunin (pf) Tadeusz Strugala Warsaw Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 スタニスラフ・ブーニン(ピアノ) タデウシュ・ストゥルガラ / ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 ご存知ブーニン・フィーバーのブーニンです。実はあまりご存知でなくて、当時はなぜ騒がれているのかがよく分からなかったのですが、どうやら NHK でショパン・コンクールのテレビ番組を放映したせいのようです。ロシア(当時はソ連)生まれでダン・タイ・ソンの次の回、1985年のコンクールに十九歳で優勝したブーニン。おじいさんはショパン研究の第一人者にしてギレリスやリヒテルの先生である有名なピアニスト、ゲンリッヒ・ネイガウス(後で触れます)であり、加えて両親も共にピアニストです。そして受賞三年後にドイツに亡命して活動しようとしたのですが、残念なことにどこのレーベルも相手にせず、大人気だった日本で、東芝 EMI が CD を出すことになりました。そして日本発で世界に広がるかと思いきやそれも成らず、その後も日本のレーベルからのみリリースするという状況が続いたようです。そんなこともあり大変な親日家で、震災のときも何度もチャリティー・コンサートをやってくれました。ショパンを最も得意としています。 なぜヨーロッパでは受けなかったかという話はデリケートだし推論の域を出ないので、ここでは演奏を聞いた感じだけをなるべく客観的に述べるにとどめます。本人が語るように日本の聴衆の方が耳が肥えていたのかもしれないし、武満徹の褒める通りかもしれません。 ショパンの1番の協奏曲の録音に関しては、ここで取り上げるショパン・コンクールその時のもの以外にもいくつもあります。その後に日本のレーベルから出た、翌年の昭和女 子 大でのライヴ盤(外山雄三/NHK交響楽団1986ビクター)、2001年の札幌ライヴ(カジミエ シュ・コルト/ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 EMI ジャパン)、2009年サントリー・ホールでのライヴ盤(アントニ・ヴィト/ワルシャワ国際フィルハー モニー管弦楽団/ユニバーサル・ジャパン)などです。今回は最初の二つのみを聞きました。 まずは比較の意味で N響との方から行きますと、これが翌年なのにすでにコンクールのときとは表現が違っています。ゆったりとした運びで表情がたっぷりと大きく、大変遅く感じる瞬間もあります。弾ませることはなく粘るようなレガートが聞かれ、しかしピアノの音自体は芯のあるくっきりとした音であり、主拍でないところでこつんと強調するアクセントが特徴的です。テンポ・ルバートと呼べる動きもします。第三楽章の速いところでは表情を保ったまま情熱的に走り、弾むような表現もあって明晰です。これを恣意的とするのは評価なのでそうは言いません。表現意欲に大変富んでいます。一般には個性的と恣意的の境界にあって、評価の分かれる演奏ということになるかもしれません。 一方で上にジャケットを載せたコンクールでの演奏はそこまでの思い切った表現ではありません。それでも念を押すようにくっきりとはしており、表情が大きくてたっぷりとしているところは同じです。速いパッセージは一音ごとに分離しており、隣り合わせに連続する上昇/下降音符もついてもそれが別の音だと分からせるかのように、艶のある音でくっきりと区切ってパキパキ弾いて行きます。こういうタッチはショパンでは昔から時々行われて来ました。一つの表現手段として確立されているのでしょう。マガロフからダン・タイ・ソン、キーシンに至るまで、時々聞かれるものです。粒が立っていてグリッサンドのようではないので、さほど速弾きを意識させない運びでもあります。 個人的にブーニンの演奏はどうかと聞かれたら、その表情の必然性はよく分からないというのが正直な感覚です。ひょっとしてブーニンにはおじいさんやロシアン・スクールの伝統に反発したい気持ちがあったのでしょうか。恣意的と言っても良いほど大胆なグールドがいつまでも人気なのに対してブーニンが流行現象だったのもよく分かりませんが、ここでフランソワに♡を付けるのにブーニンに付けないのは単に感覚的な問題です。しかしその後に現れて来た大きなアクションの若手演奏家たちのマナーを考えると、この人は少し登場が早かったと言えるのかもしれません。 1985年独カプリッチョ・レーベルです。JVC でも出ていました。カップリングは24の前奏曲 op.28 です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Li Yundi (pf) Andrew Davis Philharmonia Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 リ・ユンディ(ピアノ) アンドルー・デイヴィス / フィルハーモニア管弦楽団 ブーニンの後二回続けて1位が出なかったショパン・コンクールで、2000年度に久しぶりに優勝したのが中国のピアニスト、リ・ユンディです。中国人としては初であり、十八歳で最年少優勝(ポリーニとは何ヶ月か違ったのでしょうか)でもありました。その方面で人気があるのかどうかは分からないけれども、写真で見る通り韓流スターみたいです。2006年以降は本土から香港市民に変わったそうです。雨傘の女神も大変なことになってしまいました。アーティストは今後どうなるのでしょうか。 ついでに触れるのもなんですが、同じ中国のピアニストとしては世界的コンクールの優勝者ではないものの、ユジャ・ワンとラン・ランが人気です。このうちユジャ・ワンの方は明るく爽やかで良いものの、ショパンはまだほとんど出してません。個性的なラン・ランはブーニンと同じような感覚を覚えるので熱烈なファンに任せましょう。反対に揺らし崩しのない丁寧な演奏のエリック・ルーもいますが、そちらもやはりまだ協奏曲は出してないようです。
艶が乗って適度にくっきりした音で、さらさらと始めます。表現は割合あっさりしている方かも、と最初思いました。後の受賞者ソンジン・チョのように感傷的な美に浸るものではありません。ただ、元々の性質としては素直なのかもしれませんが、音の上では工夫を凝らしているところがあると気づきます。十倍に拡大して言うなら、遅らせる「ため」があり、それを使った揺らしを全体に施します。フレーズの途中で速度を緩めたり間を取ったりする表現に特徴があるのです。もっと正確に言うなら、小節の頭はジャストに叩き、そのまま次の音を待つ時間を設けます。そしてそれがフレーズの最初だけでもなく、次の小節でもその次でも続くため、歌が中程で延びるような独特の感覚 (そして詰めて戻す)があるのです。じらされてるような感触です。それは大きく延びては走るコルトーの緩いスプリング・ルバートとも違い、区切られた時間内で意外性をもって細かく揺らすフランソワとも異なります。どこのパートにも万遍なく抑揚を施すところが西欧的な表現とは違う気がします。 それとは別に、ふわっと弱めるきれいさ、瞬間的に感情が激したようにスポットで強める表現も見られます。速いパートが続くところは真っ直ぐで、タッチがくっきりしていて粒立ちの良い音です。 第二楽章もフレーズの中程で間を取るのは同じであるため、表情過多ではないにもかかわらず、独特の叙情性を発揮して歌う感じになります。自然に前に流れるのをダムで制御しつつ解放しているような感覚です。ピリオド奏法を部分的にスロー再生したようだ言うべきでしょうか。この人らしい個性です。強弱は割合はっきりと付け、特に弱音は第一楽章同様、すっと弱めて繊細な感じになるところがあります。 第三楽章はスタッカートを交えた意欲的な表現で、本物のように強烈ではないけれども、やはり亜ピリオド奏法的に崩して行くところが面白い効果を発揮します。それが純粋に好きかどうかで評価が分かれるでしょう。 2006年録音のドイツ・グラモフォンです。このときユンディは二十四歳。カップリングはリストの協奏曲第1番です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Li Yundi (pf, cond.) ♥ Warsaw Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 リ・ユンディ(ピアノ /指揮)♥ ワルシャワ・フィル ハーモニー管弦楽団 この人はその後、2017年にも弾き振りの新盤を出しました。出だしでは同じような表現かと思いましたが、こちらの方が多少素直になっているようです。緩やかなところに差し掛かると、例のフレーズ中程でふわっと弛ませる歌の感覚が現れて来るところはあります。その呼吸が個人的には必ずしも好きではなかったのだけど、でもほとんど気にならなくなりました。 第二楽章ではより遅く感じます。そして前より素直になった分だけ、出だしの p からしばらくの間、閉店のオルゴール・ チャイムのように聞こえてしまい、一度そう思えるとゲシュタルト崩壊でそう聞こえ続けてしまいました。ほとんど真っ直ぐな展開であり、そこに微かに癖が加わります。こういう音を洗練されたチャイニーズ・リリシズムと呼んで良いのでしょうか。でも黙って聞かされたら今度は欧州のピアニストだと思うかもしれません。 色々言いましたが、大変美しい演奏です。正直さとやさしさがあって旧盤より気に入りました。個性的だった表現が後退して真っ直ぐ丁寧になって来た方を褒めるのも気の毒な気もするけど、自らそうなって来たわけだからそれは当たらないでしょう。それとは反対に若いときに直線的で、歳とともに抑揚が大きくなるのはよくあることです。ピリスなんかそんな感じです。そうした内容に関して、表現の技を磨いて来た足し算か、自信がついたことで素が出た引き算かを見極めるのは難しいです。
第三楽章も同じ歌の傾向はあるものの、やはり2006年よりはおとなしい運びです。洗練させる方向で成長するタイプの途上の姿なのだと捉えようと思います。こうして聞いている限り、他の中華系ピアニストより素直な分好みです。カップリングは2番の協奏曲です。 ピアノの音は旧盤よりやわらかい艶が聞かれ、大変良いと思います。レーベルはワーナー・クラシックス・ ジャパンです。DG から離れてしまったようです。おとなしくなった表現がこの人本来のあり方だとしたら、人気の点で今後が少し気になるところではあります。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Rafal Blechacz (pf) ♥ Jerzy Semkow Royal Concertgebouw Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ラファウ・ブレハッチ (ピアノ)♥ イエジー・セムコフ / ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 リ・ユンディの次の回、2005年のショパン・コンクール覇者です。色々なサイトにショパンの再来などと書いてあったりするみたいですが、なるほど少し寄り気味の目に長めの髪、やさしそうな雰囲気がショパンに似てるかもしれません。ツィマーマン以来のポーランドの人ということもあるのでしょう。演奏の方は奇をてらわない抑制の効いたピアノと言われるようだけど、果たしてどうでしょうか。 理想的な速度と粒立ちの良い音で始まります。全く素直な展開なのかなと思うと、中国系ではないものの、こ の人も前出のユンディと多少似ていなくもない、メロディの中程で遅らせてゆっくり歌わせるところがあったりします。揺れというよりも、その部分でクローズアップして表情を付ける感覚で、ゆったりになるとそれを出して歌う傾向があります。そういう部分ではかなりしっかりとした抑揚が付いています。ショパンでやるのですから、納得の解釈なのだろうと思います。 第二楽章は大変ゆったりとしていて大きな表情があり、フレーズの切れ目での間も長く取ります。遅らせながら浸るような運びで、テンポと形はツィマーマンの新盤にも似ているものの、ツィマーマンのように自分は覚めている感覚ではなく、かといって感傷にどっぷり浸る感じでもないもので、抑揚が大きい割には平静です。高度な職人であるツィマーマンのようなかっちりとした自我構造ではないのかもしれません。巧緻な感じはせず、基本は素直な人という印象です。その結果、好みよりは情緒纏綿型寄りであるにもかかわらず嫌味はなく聞こえました。耽溺せず、やさしく丁寧に扱う品の良い抑揚があり、弱める弱音もきれいです。 第三楽章は粒立ち良く並んだ明晰な響きの美音で、飛ばし過ぎず、表情が消えることもなく自然に進めます。軽々と弾いているように聞こえるのは巧い証拠でしょう。 ドイツ・グラモフォン2009年のライヴ収録です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Juliana Avdeeva (pf) ♥♥ Antoni Wit Warsaw Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ユリアンナ・アブデーエワ(ピアノ)♥♥ アントニ・ヴィト / ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 2010年度のショパン・コンクールで優勝したのは1985年生まれ、ロシアのユリアンナ・アブデーエワで、四十五年ぶりの女性の受賞でした。スイスでも学びましたが、師はいずれもロシアの人だったようです。結論から先に言うと、この人はショパン・コンクールの覇者の中でも大変良かったです。前後何回かの受賞者たちと比べても表現に無理がなく、内側とつながった情感を表せる人のようです。教わったり試行錯誤したりせずとも感覚はすでに持っているピアニストなのでしょう。逆に言えば、ゆっくり方向に崩す癖はあるものの変わった振りではないため、大衆の目からすると華がないように見えるのかもしれません。それを裏付けるように、最近の優勝者であるユンディ、ブレハッチ、ソンジン・チョ、そしてこのときに3位だったトリフォノフまでが受賞後に大手ドイツ・グラモフォンと契約しているのに、アブデーエワは洩れています。それだけでなく、実はオールソンとブーニン以外、ポリーニ以降はアルゲリッチ、ツィマーマン、ダン・タイ・ソンらも皆契約していたのでした。容姿だって良いはずなのに気の毒です。でも目利きのミラーレが代わりに出したので、分かる人には分かるから却っていいのでしょう。協奏曲も同レーベルから出してほしいところです。 これはコンクールでのライヴです。熱い感動が伝わります。そういう状況ゆえにキーの間違いをどうこういう問題ではないし、録音も大変良いです。ポーランドのショパン弾きの代表としてピオトル・パレチニ盤をこの曲のベストの一つとしてすでに挙げました。あの揺れて真っしぐらな運びとはまたちょっと違った、遅らせつつじっくりと進める一面があるものの、じわじわ込み上げて来る情熱においては似た部分も感じました。この大舞台でも萎縮せずにそんな乗りを発揮するところに圧倒されます。アルゲリッチ以来の女性優勝者ながら、煽るような性質はありません。 第一楽章は所々でゆったり歌わせ、丁寧で落ち着きがあります。抑揚のつけ方に神経を逆なでするところが一切ありません。嘘がないので大変好感が持てます。予測不能な動きや不均一なリズムでの揺らしが効いてるタイプとは言えないわけで、大変揺れてはいるけれどもショパンに粋さやはかなさを求める人向きではないでしょう。この人の性質だろうと思います。 第二楽章では表情を大きめに付けているのに自然で、あるべきところにあるべき音があります。スタッカート表現も出すけれども、全体ではゆったりとした揺れに安心して気持ちを預けられます。力で押し切らないデリケートさがあり、大変魅力的なラルゲットです。 第三楽章になるとだんだん乗って来ます。ここは大変感動的でした。リズム感良く遊んでいる感じがありつつ切れがあり、一方で落ち着いた表情も聞かれます。ただ走るだけではなく、抑揚表現の豊かさを感じるのです。非常に速く弾くところも出て来るけれども、きれいに揃っていて安定しています。生では一つや二つかすりが出るのは当たり前であり、問題にすべきことではないと思います。後半の乗りと白熱具合には圧倒されます。一番だと言ったっていいぐらいだし、コンクールでこんなのを聞けることは滅多にないでしょう。 レーベルはポーランド国立ショパン協会 NIFC です。ピアノはヤマハだけど、艶のある明晰な粒の音で鳴らしています。かなりダイナミックなタッチだと思います。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Juliana Avdeeva (pf) ♥ Frans Bruggen Orchestra of the 18th Century ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ユリアンナ・アブデーエワ(ピアノ)♥ フランス・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ こちらは同じアブデーエワでも二年後の録音です。1849年製のエラールのフォルテ・ピアノを使っています。ショパンのピアノだからということで、エマニュエル・アックスやダン・タイ・ソンと同様です。ダン・タイ・ソンの方とは同じレーベルの企画でもあり、バックも同じブリュッヘンと18世 紀オーケストラ(古楽器)となっています。楽器も同一でしょうか。ただしこちらはセッション録音です。 初頭ではあっても19世紀の音楽を、古典派と似たピリオド奏法でやるのはどうでしょうか。モーツァルトについてはあのアクセントに馴染めませんでした。でもアブデーエワはその古典派の解釈ほどではなく、ここでは上手にピリオド奏法のエッセンスを取り入れて演奏しています。恐らくそういう時代の曲も弾いたことがあるのだろうと思っていたら、インタビューでそう答えているのを読みました。ダン・タイ・ソンがどう身につけたのかは知らないけれども、あれと同じぐらいに、アックスよりも幾分はっきりと、駈けたり立ち止まったりの動きが聞かれます。あまり大きなものではありません。アクション(構造)から来る持続しない響きとペダルの使用法の違い、音量の小ささとによって、こういう楽器は独特の弾き方が要求されるものだというのはその通りだろうと思います。ノン・ビブラートのオーケストラも当時としては正しいし、響きはその方が美しいです。 第一楽章は最初からフォルテピアノ特有の音に耳が行きます。独特の艶があって、ちょっとリュートのような響きです。ピリオド奏法の語法も加わって多少不均等なリズムが出ますが、やり過ぎはしません。走らず落ち着いていて、真面目さを感じさせるこの人の弾き方は相変わらずです。脈動するように弱めるところもあります。楽器の聞こえ方も関係するでしょうが、弱音はかなり小さくしていて劇的な印象です。遅いフレーズがやや強調されて遅いのも彼女の特徴でしょう。やはり崩し方に抵抗を覚えるようなところはなく、丁寧に音にして行きます。 第二楽章は自然です。落ち着いていて奇をてらわず、細やかな表情があって大変良いです。 繰り返しになりますが、然るべきところに抑揚があり、適切なテンポ設定で進みます。これもロシアン・スクールの伝統の一部と言えるのかどうか、ピリオド奏法の揺れが若干出ることを除いては、この前後何回かの優勝者の中でも最も安心して聞いていられるものです。ややゆったり方向に寄って表情が大きめなのが持ち味でしょう。 第三楽章は慌てず丁寧に音にして行くところに好感が持てます。派手でなくて良いわけだけど、こういう本物路線の今後はどうなんでしょうか。コンクールのライヴでのような後半の熱い乗りは聞かれず、完成度高くまとめています。もちろんライヴではないので弾き間違いも見当たりません。 2012年収録で、前出のと同じ NIFC レーベルです。スタジオ録音ながら中音にファーンと聞こえる反響が乗り、ときにややこもったオーケストラに聞こえる瞬間もあります。古楽器のヴァイオリンの、線の見えるような倍音が心地良いです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Seong-Jin Cho (pf) Gianandrea Noseda London Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ソンジン・チョ (チョ・ソンジン/ピアノ) ジャナンドレア・ノセ ダ / ロンドン交響楽団 2015年のショパン・コンクール優勝者です。ソウル生まれの韓国の人で、大抵はどこかへ海外留学をしてる例が多いのに、自国で技を身につけたということです。この国の音楽教育は進んでいるのかもしれません。速いところは流れるようによどみなく、自在な強弱があってライヴ映像でも破綻を見せないことから、歴代受賞者の中でも相当高い技術を持っているのではないかと思います。そういう部分では特に癖のある弾き方もしません。では特徴はというと、これは楽譜通りの優等生では全くなく、大変個性があります。どう言ったものでしょうか。ツィマーマンの新盤での第二楽章の運びが好きな方にはお薦めです。しかもツィマーマンは職人として自らは醒めているのに、この人は心からの歌をうたっているとも言えるでしょう。そしてその歌い方こそがこの人らしいところです。 どこかに憶えのあるイントネーションなのです。それをもし「韓国的」と言ったら褒め言葉になるでしょうか。カナダのテレビ番組で飛行機の墜落原因を究明するシリーズがありますが、大韓航空の副操縦士がミスを知っていながら目上の機長に指摘できず、そのまま落ちたという回では、パイロットとコパイロットの席に並ぶ二人に朝鮮王朝時代の衣装を着た姿がオーバーラップするという効果を使ってました。ああいうのは褒め言葉とは言えません。日本語表記のチョ・ソンジンは「朝鮮人」と同じ発音になるので誤解されて炎上を招いたという話もあり、個人的には韓国文化に差別的な人がいることを残念に思っているので、感じたことを正直に表現するのはちょっとデリケートです。 でも恐れずに言えば、演歌のようなメンタリティを感じるところがあります。これは日本の人も同じだけれども、それを抑えて優等生的な方へ向かう割合が多いのに対して、韓国の人はストレートに出すことに抵抗がないようです。朝鮮半島にもトロットと呼ばれる演歌そっくりの音楽が存在しており、それは「泣き」の感覚を持っています。アルゲリッチが面倒を見ているイム・ドンヒョクにも感じられ、もう少しで涙をこぼしそうなほど感情に入り込みます。指揮者のチョン・ミュンフンにも聞こえます。そんな中でソンジン・チョについて特に印象的だったのは、自らへの陶酔的な眼差しでしょうか。アルゲリッチの場合とは形が違います。技術の高さを激しさで表すというより、きれいに弾いている自分への自信のようなものが聞こえる気がします。これはあくまでも主観であっ て、弾き手にその属性があるとは断言しません。 泣きの感覚と一口に言ってしまえば、それは韓国や日本に限らず、東アジアにある程度共通した性質のように思えます。情緒過多になるのは発達心理的には自制心を身につける前の子供に共通する特徴であって、文化の差ではないという見方もあるし、反対に自己責任での競争が激しい環境では感情を抑える成熟が早く、自由がなく抑圧が大きい環境では遅れることから、国や文化にも環境差があると言うこともできます。ダン・タイ・ソンやセシル・リカドなど、ベトナムとフィリピンのピアニストには「泣かない」例外もありました。また、短調のペンタトニック(民謡の五音音階)や人懐っこく感傷的な傾向は実はヨーロッパにもあり、哀愁のフラメンコ、ポルトガルのファドがそうだし、ショパンの生まれたボヘミア地域からロシア、北欧の一部まで「泣き」は聞かれます。ツィマーマンの歌謡性もルーツとしてはそういうところから出たものかもしれません。もちろん欧米文化圏でも日本人のように丁寧で素直な演奏や、思い入れたっぷりの「泣き」表現をする人はいます。前者の例はアダム・ハラシェヴィチ、あるいはフランス系のステファン・デ・メイという人はかなり素直です。後者では同じくフランスのエリザベス・ソンバート、ロシア系アメリカ人のオルガ・カーン、そしてコンペティション優勝者であるベラ・ダヴィドヴィチなどがたっぷり歌う感じがするわけで、結局国ごとのばらつき具合の問題ではあります。でももしアジア人の特徴というものがあるとするならば、コンクールでアジアの人が上位をさらう時代になって来たことについて考えてみることも悪くはないと思います。今後は人権と労働環境の厳しさに耐えられるアジアがピアニストの供給国になり、東洋式のアクセントが標準になって行くのだと中村紘子は主張しました。ヨーロッパ人には受けないだろうけど、フィジカルと呼ばれる CD の売り上げでは日本は高い割合を占めており、人口の多いアジアの内需だけでそうしたピアニストたちは食べて行けるかもしれません。その市場で売れるならドイツ・グラモフォンも契約するでしょう。 ソンジン・チョの演奏です。第一楽章の速いパッセージではツィマーマンにも引けを取らない技巧があると言って良いでしょう。速いながらに表情を持たせる余裕すらあります。そして速度が緩んで静かな歌の部分が入って来ると、途端に大きな抑揚をつけて歌い上げるようになります。このたっぷりと自信に満ちた叙情性は好きな方にはたまらないものだと思います。
第二楽章にはそれが全体に現れて来ます。ちょっと小山実稚恵さんを思わせるような運びでしょうか。コンクールで3位だった中国系シンガポール人でアメリカ国籍のケイト・リュウも思い入れたっぷりなところは似ています。でも元来そういう楽章ではあるので、速いパッセージの途中で情緒が顔を覗かせることに比べたらインパクトは少ないです。美しく輪郭の立った艶のピアノに魅せられます。これだけのニュアンスが出せるなら抑揚表現だけでもコンクールで勝てるかもしれません。意外なところで表情が付いて神経が逆撫でされる感覚はありません。ただたっぷりとしています。 因みにこの人が1位を取った年の2位はカナダのシャルル・リシャール=アムランでした。誠実な印象で個人的には良いと思いました。同じようにゆったりよく歌っているものの、もっとすっきりとした情感の表し方です。ヨーロッパ文明圏では大抵はここまででしょう。アナレクタ・レーベルから両協奏曲の CD が出ています。立体的な厚みと低音のやわらかさがあり、ピアノの音はしっとりとした優秀録音です。そちらもご紹介すべきだったでしょうか。ソンジン・チョですが、第三楽章も弾むようなリズム感と切れの良さが見事です。とにかく巧いと思います。 2016年のドイツ・グラモフォンで、セッション録音です。やや硬質な艶があり、ピアノの粒立ちが良いです。オーケストラのはっきりした弦とグラマラスな鳴りも気持ち良いものです。特にピアノの音はツィマーマンとも比べられるし、エッジもくっきりしてピンと張りのある透明なもので、この曲の中でも際立ってきれいです。そ して演奏自体も、この水準で弾かれたらアジア的であろうがなかろうが賞に通さない方が間違いでしょう。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Bruce (Xiaoyu) Riu (pf) ♥♥ Andrey Boreyko Warsaw Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ブルース・(シャオユー)・リウ(ピアノ)♥♥ アンドレイ・ボレイコ / ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団 コロナの流行で一年延期されていた2021年度の第18回ショパン・コンクールが開かれ、結果が出ました。ちょっと前代未聞の出来だったと思うので早めに触れることにします。発表されたばかりでまだ CD はないですが、近いうちにポーランド国立ショパン協会(NIFC)からファイナルの実況盤が出ることでしょうし、王手レコード会社が契約してセッション録音もリリースされるかもしれません。それまではジャケットは白紙にしておきます。 表記の指揮者と楽団はそのファイナルのものです。 * 年が明けて CD が発売されました。ジャケット写真を差し替えておきます。録音はウェブで配信されたものより当然ながらバランスが良いです。オーケストラ部分では最初中低音の反響が多少大きめで、やはりライヴなのでブラスの重なりも完全に透明ではないなとは思いましたが、それはフォルテの一瞬のことであり、聞き進むと生らしいやわらかさの感じられる大変良いバランスだと気づきました。ハイは出しゃばらないですが、リズムを取るときの床からの重低音の反響まで聞こえます。そして決して金属的にならないまろやかでピンと張った艶を捉えたファツィオリのピアノの音が何より素晴らしいです(因みにこのとき2位のアレクサンダー・ガジェヴが弾いたシゲル・カワイの音が負けず劣らず純粋で、演奏の良さとともに驚きました)。オーケストラ共々ナチュラルで、この近年の実況録音シリーズでもベストでしょう。皆が総立ちになって叫ばずにはいられなかった最後の声もリアルに入っています。聞き直して再度鳥肌が立ちました。レーベルはポーランド国立ショパン協会(NIFC)です。 優勝はブルース・リウ(Bruce Liu)です。1997年パリ生まれの二十四歳で、「劉」という漢王朝由来の名前は中国系かと思いますが、モントリオール音楽院で学び、ダン・タイ・ソンに師事しているカナダ人です。 インターネットで聞きました。とんでもない才能が出て来たものです。コンクールの優勝者が必ずしも最も音楽的だとは限らないと書いたものの、この人についてはそんなことは微塵もありません。パリ生まれの中国系というとヨーヨー・マが思い当たるけれども、マ同様にアジア人という縛りは全く感じさせず、感傷に倒れもしないし楽譜通りの真っ直ぐさでもありません。同じくパリで活躍するシュ・シャオ・メイの国際的な感覚とも比較できるでしょうか。個人的な感想ながら、歴代優勝者の中でも最も表現力のあるピアニストではないかと感じます。上手だった前回優勝者と比べてどちらが上かは分かりかねますが、他のコンテスタントがしばしば指を引っ掛ける本戦において技術的にほとんど完璧な上、全く緊張を見せずに堂々と自身の表現を聞かせていたことに驚きます。あの場であそこまで完成形を見せる人は記憶にありません。バックのオーケストラも感心しきりで、コンサートマスターの笑顔や夢見るような眼差しが面白いほどでした。 そのピアノ表現ですが、ファツィオリのきらきらし過ぎない音で、まず最初に独特の軽さを感じました。大変繊細な感性の持ち主という印象です。奇をてらわず個性的なのですが、手法としてまず気がついたのは、流れるフレーズの中で所々で拍をわずかに遅らせるやり方です。そして逆に一音間隔を詰めて前へ倒したり、下降中に不均等に崩しを入れたりもしますが、やり過ぎず絶妙なバランスで色を付けて行くセンスの良さがあります。つまり伸び縮みの複雑なリズム展開なのです。そしてそこに大変デリケートな強弱が加わり、微細な情感を持続させる感覚の流れがあります。ふわっと弱めて遅く抜く間合いが聞かれ、今正に生きて呼吸している感じがします。どのフレーズ、どの一音もお留守になる瞬間がありません。気持ちのテンションが続くというのか、惚れぼれしながらずっと惹きつけられます。 静かな第二楽章がまた、これ以上ないデリケートな味わいです。内側から湧き上がる情感があっても決して安っぽい感傷に浸りません。ここでもやはり一瞬ふわっと緩める運び、はっとさせられる弱音が聞かれます。それらは心からの歌になっています。レベルが違い過ぎるでしょう。面白いのはキーを押した指をそのままビブラートをかけるヴァイオリンの指板みたいに揺する仕草です。ピアノを弾く人はやったことがあるのではないでしょうか。音には表れないけど音楽をどう捉えているか分かるし、何よりもこれをやりたくなる気持ち、すごく理解できます。曲想の変わり目の水琴窟のようなところも絶妙です。 第三楽章でも驚きは止まりません。今度はリズム感の良さに圧倒されます。どの楽章も元々このリズム感の良さがベースになってますが、まるでジャズの覚えでもあるのかというわずかな拍のためとずらし、凹凸のある叩き方、不均等な音符の配置が聞かれます。切り替えて繰り返しの二回目はスタッカートにする遊びもあります。この跳ねるような動きは何と言ったらよいのでしょう。弾んだり弾まなかったり思うがままで、無限に諧調があってその間を複雑に揺れ動くようです。剛直な超絶技巧家の時代は終わりです。そしてそんな風に乗っているときの楽しそうな表情は、それが瞬間的に内側から湧いたものだということを表しています。強弱の上でも、虚を突かれるような弱いパッセージの下降に瞬間的に入ったりもして、もはや舞踏の喜びを感じます。上で取り上げたパレチニも乗ってたけど、第三楽章でこんな表情を付けられる人はいないし、コンペティションでここまで自由な表現も聞いたとがありません。目の肥えた聴衆も驚いたらしく、最後の音が鳴った瞬間に爆発的な歓声が起こって異例のスタンディング・オベイションとなりました。指揮者も興奮し、嬉しそうに演奏者の両腕を抱く仕草が見られました。 言葉ばかり多くなって語彙が追いつかなくなってしまいましたが、今回のリウの演奏、この曲のベストかもしれないと思える至福の時間でした。よくショパン本人が乗り移ったなどと言うけど、このことでしょう。一位なしの年もあった中で歴代と比べても文句なしの優勝です。大手のニュース番組がこの優勝者の名前に触れずに下位の入賞者だけ取り上げるなら報道の公正さがありません。取り急ぎ書かせていただきました。 (10/21/2021) 後日談ですが、このときのベルギー人のピアノ調律師のインタビューを聞きました。リウ本人が魅せられてこのピアノを選んだのだそうで、トリフォノフが入選したことも話題だったかもしれないけど、歴史の浅いメーカーであるファツィオリとしてもショパン・コンクールの優勝者を出すという大変な名誉に輝いたことになります。そしてこれ以降、このピアノを買った(値段非公開のルールがある高価なものです)という人が動画を挙げたりして、今まで知らなかった多くの人にこの名前が知れ渡るきっかけになったようです。スタインウェイ同様にタッチが軽く、より甘くやわらかい部分がありながら透明感と色彩変化を持ち合わせる素晴らしいピアノのようで、CD での録音ももっと増えると面白いと思います。
師と先人たち(19世紀生まれのピアニスト)  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Moriz Rosental (pf) Frieder Weissmann Staatskapelle Berlin ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 モーリツ・ローゼンタール(ピアノ) フリーダー・ヴァイスマン / ベルリン国立歌劇場管弦楽団 次は往年の名ショパン弾きという区分に入る人たちを取り上げます。19世紀生まれのこれらのピアニストは協奏曲の1番を録音してないケースも多いので、そうしたショパンの弟子たちなどの演奏については次のページで覗くことにします(「ショパン・ピアニストたち」)。パハマン、パデレフスキ、コルトー、ジル、コチャルスキといった人たちのことです。 モーリツ・ローゼンタール(1862-1946)はポーランド出身のユダヤ系アメリカ人です。コチャルスキと同じくカロル・ミクリの弟子なのでショパンの孫弟子に当たりますが、その後リストの弟子であるラファエル・ヨセフィとパハマンの師でもあったカール・タウジヒに習ったのでリストの孫弟子でもあり、ショパンとリストの両方の血を受け継いでいるかのように言われます。かと思いきや、さらにリスト本人にも就いているので「リストの弟 子」というのが一番輝かしい肩書きでしょうか。リストはレシェティツキ同様にたくさんの弟子を持っていて、録音が聞ける人は他にもいますがローゼンタールは特に有名です。そしてローゼンタールの弟子にはホルヘ・ボレットがいます。アルトゥール・ルービンシュタインも一時期習いました(ルービンシュタインは他にもリストの孫弟子のカール・バルトにも師事)。それではこのローゼンタール、当代随一の技巧家とされ、ショパンの系列としてレガートと弱音に特徴があると言われたり、リストの系列として輝かしい音という人がいたりしますが、この録音状況ではどうなのでしょうか。確かにエッジの立った音で強いタッチなのだろうというのは分かりますが。 この人で最大の特徴のように思えるのが、17、8世紀のバロック音楽で聞かれるノー ト・イネガルのリズムに近い運びです。これは次のホフマンにも若干聞かれます。イネガルは拍を均等に割って行くのではなく、二つずつ組で片方を長く、もう一方を短くします。その程度は様々ですが、モダン・ジャズのリズムもちょっと似たところがあります。フランソワのところで彼がジャズのようだと言いました。それはリズムの流れを一定速にした中で前後に揺らすという意味合いでした。しかしこのローゼンタールの場合は、いくつかの音符にまたがる速度変化で歌を揺らすというよりも、一個一個のリズム単位の中で規則的に長いと短いを作り分けるような感じの揺れなのです。つまり自在に大きく揺らすのではなくて短く揺らす。クッ、クッ、クッと細かく周期的にふらついて脈動するように聞こえます。フランソワの方がそれより多少長い周期にまたがり、パハマン、コルトーとなると一定の拍の流れを無視してもっと全体に延びたり縮んだりします。だからローゼンタールはルバートというよりも、個々の区間では真っ直ぐ弾いてるように聞こえます。それでいて、同じくこの時代としては真っ直ぐに近いコチャルスキよりも不均等なリズムの分、癖があるように感じられるのです。 そしてそれによってどこか素直な感じには聞こえなくなります。ただしこのローゼンタールにもゆっくりにして延ばすパッセージもありますから、やはりトータルではいわゆるルバート奏法の一種と言った方がいいのでしょう。こういう違いを正確に表現するのは難しいです。全体の印象としては醒めていてひねりが効いており、それでいて大仰にはならないという感じでしょうか。 それとは別に、パハマンやジル、ロンほどではないですが、まるで癇癪のように強い一 撃で強調を入れる 箇所もあります。晩年の中村紘子にも多少そんな癖が 出まし たから、これは何かこの時代の空気というか、メソッドなのでしょうか。フレーズの後ろ の方でコーンと強 めるアクセントが聞かれたりするのです。中村さんは 誰か 彼ら巨匠の仲間の生まれ変わりかもしれません。 第一楽章は速く、くっきりと始めます。弾むようにスタッカートを交え、その後は上記の独特の間を置くリズムが表れますが、コルトーのように全体を覆う波のルバートはありません。速いところはかなりの速度で、遅くするフレーズでは大胆に 遅く、それらはブロックごとに区切られた感じです。 第二楽章はそのイネガル様の不均等なリズムがよりはっきりと分かります。主に左手に表れますが、右もつられることがあります。ルバートというよりも、細かなリズムの跳ねが一定に繰り返されて行きます。進行は等速で、やはり覚醒感があります。弱音も使うのに明晰であり、ロマンティックな感触はありません。中間部の速くなるところでは力を入れずに速いかと思うと、反対にぐっと強める強調を入れた盛り上がりを聞かせたりもします。強打はかなりのものです。歌の終わりではしっかりと区切るような間も空けます。 他にこの曲の録音としては、この楽章だけのフランク・ブラック/NBC交響楽団による1937年のものもありますが、もう少しゆっくり叙情的になるものの雰囲気は似た傾向です。 第三楽章は強調したスタッカートでくっきりと運びます。思い切って強いところとゆっくりのフレーズが混じり合っているけど、全体には速めで真っ直ぐな印象です。エッジが利いてきらきらしています。強調の入れ方が独特で癖が強く、動きはあっても落ち着いた感じはありません。 録音は1930、31年です。音質は相応です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Josef Hofmann (pf) John Barbirolli New York Philharmonic ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ヨゼフ・ホフマン(ピ アノ) ジョン・バルビローリ / ニューヨーク・フィルハーモニック ヨゼフ・ホフマン(1876-1957)はローゼンタールと同じくポーランド出身のユダヤ系アメリカ人ピアニストで、アントン・ルービンシュタイン(アルトゥール・ルービンシュタインとは別人)に学びましたが、その前から神童として有名でした。門下にラン・ランやユジャ・ワンなどがいます(彼らはゲイリー・グラフマンを通じてホロヴィッツの系譜だと言っているようです)。また、発明家でもあったようです。ホロヴィッツの前の超絶技巧 家とされます。 確かにばらばらと超速で目の覚めるような弾き方をします。そのハイテンションで叩き続ける音がどこかで聞いたことがあるなと思うのだけど、ポリーニでしょうか。どうかすると機械音のようにも聞こえる(主観です)、止むことのない勢いがちょっと似た感じです。スケルツォ第2番 op.31 やワルツ第1番 op.34 などの話です。譜面から大きく離れない演奏だと言われることもあります。しかしこの人はポリーニのように感情的要素が希薄な感じはしません。何しろショパンはバラード第4番の、途中で崩壊するほど激しくなる1938年の演奏が一番有名なのです。感情を揺さぶる情熱的な表現をする人であることは間違いないです。しかし全てがそうだというわけでもない。それならばホロヴィッツに似てるのかと言われると、ホロヴィッツもばりばり速いながら微妙な揺れはあり、晩年は批判もあったものの詩情と言うのか、独特の掠れたような叙情が粋だったりもしました。それともまた ちょっと違う味わいです。 このホフマンという人、インスピレーション系の激しさは基本にあるけどルバートはせず、形は端正なところが多いです。くっきりしてやわらかくはなく、音を延ばしたりせず明晰です。フレーズ後半を速く弾き飛ばすところもあり、落ち着きがある方ではないでしょう。ちょっとおどけたような表情もあって、常に駈けようとしているようです。 ピアノ協奏曲第1番は19世紀生まれのピアニストとしては最も速いでしょうか。この時代に醒めてるのは珍しいと思います。第一楽章はスタッカートを交えた均等な速弾きで始まり、一方でメロディーはそれよりゆっくり弾く傾向があって所々間を取りつつ進めます。 細かな伸び縮みは少ないと言えるでしょう。気持ちがはやるように早め、また速めるところがあります。そうやって駈けるところもリズムは均等で癖は少ないです。速いところとゆっくりのところのコントラストが強く、でもルバートという感じではありません。 第二楽章はスキップしてるみたいに弾み、粒立ちの良い音で切れのあるフレーズを聞かせます。それは軽やかさとも言えるけれども、うっとり情緒に浸ろうとする者を醒めさせるような運びです。拍の強調が主に左手にあり、トトッ、トトッというリズムで脈動するので夢見心地にはなれないのです。ローゼンタール同様、昔のイネガル奏法にも似た、二つずつ組の音符で拍ごとに延び縮みさせるリズムだと言えます。独特の面白さがあって、部分的に強く打つ音とスタッカートを混ぜて盛り上げて行きます。一方で一旦ゆっくり歌うように膨らませると、帳尻合わせで後半のフレーズを大儀そうに急いで片付ける弾き方もします。そんなところはちょっとパハマン風でもあります。それでも全体としては大きく延び縮みさせるのではなく、平均して真っ直ぐな流れと言えます。 第三楽章ではアクセントが強く出ます。グールドかというスタッカートがあり、意外なほどゆっくり、明晰に打鍵して行くフレーズが聞こえます。大胆に強調された強い音です。細かな揺れはないですが、やはり独特の脈動するリズムが聞かれます。 1938年のライヴ放送録音で、拍手が入ります。レーベルはイタリアのウラニアです。演奏者の特徴は十分に分かるものの、時期も時期なのでネイガウスよりもコンディションは厳しいです。それにしては良い音と言った方がいいでしょうか。多少割れたような賑やかさがあります。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Rosina Lhévinne (pf) ♥ John Barnett Alumni of the National Orchestra Association ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ロジーナ・レヴィーン (ピアノ)♥ ジョン・バーネット / ナショナル交響楽団卒業生協会 チャイコフスキー国際コンクールの初回で優勝したヴァン・クライバーンや中村紘子の先生であるロジーナ・レヴィーン(1880-1976)はロシア生まれのユダヤ系アメリカ人ピアニストで、ジュリアードで教えた人です。デビュー当時のクライバーンの品の良さは彼女のマナーをいくらか受け継いでいるのかという気もします。中村紘子によると、徹底した教え方だけどやさしかったそうです。同じくピアニストだった夫のヨゼフ・レヴィーンを立てて自分は演奏活動をしないでいたので音源は少ないですが、ショパンのこの協奏曲は得意としていたようで代表的な録音となっています。そして知らずにいて意外だったけど、これが素晴らしいものでした。決して大げさな演奏ではないものの、全て語り尽くされてる感じもします。スタイルはほとんど19世紀的ではなくて現代の洗練され た形に近く、ロマンティックではありますが極端なルバートもなければ技巧を見せるような傾向もなく、絶妙のバランス感覚を保っていて我で押しません。デリケートでやさしさ溢れるものです。 速いパッセージも滑らかで、余分な力が入ってない第一楽章はアシュケナージもかくやというきれいさながら、アシュケナージと比べるならそのラフマニノフの2番の最初の録音ぐらいの話です。後で触れますが、この曲でのアシュケナージは踊ってますので。バランス良くまとまっているという意味で比べられる同時代の人としては、次のネイガウスあたりか、ブライロフスキも含めて良いかというところで、その中間的な揺れ具合です。 まず第一楽章からです。飾りがなくてよく抑揚が付いており、切れと滑らかさのバランス、緩めるところの間合いの良さが印象的です。一つひとつの音が濁らず重ならず、コルトーなど古くからの人たちとは違います。あるべきものがあるべきところに収まっていて繊細さもあり、リヒテルやギレリスともまた違う雰囲気です。ロシア流の 力で押し切るマナー、体操選手のようなアクロバティックなアレグロはありません。また、控えめであっても優等生とも違います。 第二楽章はためが大きめでゆったり落ち着いています。わずかに遅らせる揺れを持たせた味わい深い運びです。穏やかであり、一つひとつの音を丁寧に扱っている印象で、それでいて装飾音を入れたりする箇所も聞かれて面白いです。リズムには多少の粘りがあるものの重くは感じさせません。切れの良さを求める種類の聞き手の中にはこれを退屈に感じる人もいるのでしょうか。しかしただ夫を立てて生きて来た良き先生というレベルなんかじゃないと思います。 第三楽章も走らず、一つひとつくっきりと丁寧に鳴らして行きますが、かと思うと軽やかに流すところも出ます。どこをとっても良く出来ています。 1961年録音のヴァンガード・クラシックスです。ステレオ初期ながら弦の響きが若干薄っぺらいぐらい で、大変良いコンディションで聞けます。ピアノの音は良いです。指揮者の解釈も適切でよく寄り添い、叙情的です。オーケストラはワシントンのナショナル・オーケストラのメンバーだった人たちを集めたもののようです。 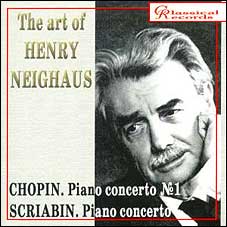 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Heinrich Neuhaus (pf) Alexandre Gauk USSR Radio Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ゲンリッヒ・ネイガウス(ピアノ) アレクサンドル・ガウク / ソビエト国立放送交響楽団 ウクライナ生まれのドイツ/スウェーデン系で、ソ連時代に活躍したピアニストです(1888-1964)。ショパン研究の第一人者で、リヒテル、ギレリス、ルプーの先生であり、孫はあのブーニンです。協奏曲の第1番は名演として知られています。癖のない 均整のとれた演奏です。 最初の楽章から軽やかで明晰に、弱音も駆使していて古さを感じさせない表現です。音が良ければ現代の人か と思うぐらいで、微かな揺れと拍の頭にアクセントを置くリズムが聞かれます。ロシアン・スクールの始祖のような人ながら、豪放で強いタッチ、超絶技巧にたっぷり歌わせるセンチメンタルな叙情の組み合わせという、後のロシアのピアニストっぽくはない弾き方です。洗練されています。 第二楽章がまたいいです。強い音と弱めるところを自在に織り交ぜ、格調高い演奏で す。ここも現代人の弾き方と変わりません。あっさりした表現でフレーズを粘らせず、大きくはないけどテンポ変化が自在なところと、弱音のやわらかさが見事です。大切に守るように、やわらかく包みながら転がすパッセージに魅惑されます。湧き上がる情感もあり、区切りで角張ったところがない自然体です。後ろ三分の一で鳴る区切りのチャイムもさりげなく、その後も声高にならず、大きく揺らしたりもしません。リズムの不規則性もあまり出しません。第三楽章は力を抜いて軽々と進めます。 1951年の録音です。ロシアのクラシカル・レコーズというレーベルで、メロディア原盤のモノラルです。他にもイギリス APR レーベルや DENON からも出ています。コンディションは良いですが、もちろん現代の録音のようには行きません。 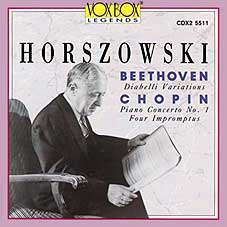 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Mieczyslaw Horszowski (pf) Hans Swarowsky Vienna State Orchestra/Philharmonia ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ミエチスラフ・ホルショフスキ(ピアノ) ハンス・スワロフスキー / ウィーン国立歌劇場管弦楽団 ホルショフスキ(1892-1993)はポーランド出身のユダヤ系アメリカ人ピアニストで、大変長生きをして、ほとんど最後まで演奏活動を続けていたという人です。そのためか晩年は日本でも「これ以上情感の感じられるピアノはもう聞けない」などという高い評価が聞かれました。ショパンの弟子であるカロル・ミクリに学んだ母に手ほどきを受け、レシェティツキの弟子になりました。したがってショパンとベートーヴェンの曾孫弟子という言われ方をします。ピーター・ゼルキンやマレイ・ペライアのお師匠さんです。 間を詰めて弾く前のめりなところがあります。心の器が感情で一杯になって溢れそうなのかもしれません。よく言われる通り、確かに情緒的です。走ってタッチが雑になるのも厭わないという感じです。加えて思い入れのあるスポット的な弱音が聞かれ、揺れのアゴーギクがあります。リズムを不均等にずらすのではなく、テンポを動かすという感じです。強弱面でもかなり脈動があります。コルトーと同じ時代のショパンらしいルバートなのかもしれないけど、拍を倒して前にのめる感じが大分違います。 第二楽章は周期的な強い音によって区切られたリズムが聞かれ、所々で盛り上がります。強くなると水の中から浮き上がって来るようにその部分でタッチがくっきりします。そんな具合で流れは脈動的です。最初の楽章では溢れる感情で一杯になってたことからすると予想を裏切り、ずっと弱音でロマンティックに弾く感じではありません。脈はあっても全体にこの楽章ではあまりテンポ変動がなく、案外平静とも言えるでしょうか。 第三楽章は飛ばさず、弾むようなリズムで区切って行きます。時々強打を見せますが、第一楽章のような前のめり感はなく、さばさばした運びです。 1953年の録音はコルトーらよりずっと良いコンディションで、オーケストラの弦など、もっと後の録音かと思わせるところもあります。反響はかなりあり、歪みっぽいところは少ない方ながら微かにはあるようなので、トータルでクリアな録音とまでは言えないかもしれません。レーベルは Vox Box レジェンズです。他にもモノラル・バージョンも出ており、そちらの音はいかにもその時代なりのこもった響きに聞こえます。ということは、この盤が何か細工してあるのでしょうか。同じ音源なら有難いことで、ずいぶん上手くやったものだと思います。楽団名は盤によっては State が Municipal だったり Orchestra が Philharmonia だったりするものの、Wiener Staatsoper Orchestra のことではないかと思います。 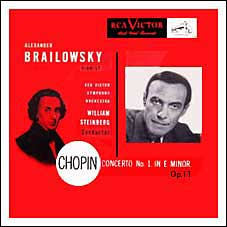 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Alexander Brailowsky (pf) ♥ William Steinberg RCA Victor Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 アレクザンダー・ブライロフスキー(ピアノ)♥ ウィリアム・スタインバーグ / RCA ビクター交響楽団 ブライロフスキー(1896-1976)はルービンシュタインと並んで20世紀を代表するショパン弾きで、ウクライナ出身のユダヤ系アメリカ人。パデレフスキと同じくテオドル・レシェティツキ門下です。これがまたパデレフスキの演奏と並んで何とも魅力的です。速い部分は真っ直ぐ速いですが、メロディアスな部分ではネイガウスほど現代的にニュートラルではなく、やや大きいながらもほどよいためを効かせてしっとりと歌い上げます。揺れも今のピアニストよりは大きいけれども、ルバートというよりももっと短めのスパンで動かします。基本は間を取って遅らせることによる表現で、前へ走ることはありません。強弱においては大変繊細なニュアンスがあり、独特の味わい深い情緒が現れます。モノラル時代の録音なので♡一つとしましたが、演奏としては大変気に入りまし た。 第1楽章ですが、出だしからけっこう速く走るところがあります。一方で緩い部分は揺らし方にリズム感があって心地良いです。これをルバートと言うなら実に適切なルバートです。ためはしっかりながら大きく崩すことはありません。タッチははっきりしており、かといってマガロフほどのくっきりさではなくて流れがあります。弱める表現もデリケートで良く、静かなパートに入ると速度を緩め、繊細な表情で耽溺せず、どこかさらっとした風合いです。そこからまた速くなると今度は軽やかに感じます。 第二楽章は始まりはくっきりとした音で、微かな揺らしと強弱が心地良いです。そして弱音に潜るところが大変弱くて繊細です。フレーズの後ろで緩めるテンポ処理であり、その緩め方自体は大きめです。ゆったりした感じがします。19世紀的なルバートによる崩しと見ると決して大きくはないけれども、自在に動き、前へ後ろへと伸び縮みして揺れます。弱める音でもやはり溺れないところが大人っぽく、やさしさも感じられます。フランソワのようなジャズ的な乗りではないし、コルトーみたいに速いところと遅いところの差が大きく、速くなると拍の頭がなし崩しになるようなこともなく、穏やかです。スタッカートも表現として適切に用い、ルービンシュタインの若いときのように所々で間を置く重いタッチでもなく、さらっとしています。総括して言えば、ちょっと古くて大きめの表情かもしれないけれど、今の若い世代に時々聞かれる恣意的な抑揚ではない演奏です。大変デリケートな味わいです。 第三楽章ですが、跳ねるようなリズム感で快調に流して行きます。タッチはくっきりとしていま す。 1949年の RCA モノラル録音です。1枚ものもあるけど国内で手に入りやすいのは8枚組、10枚組のセットの方でしょうか。この時代ですからオーケストラの音はそれなりながら、ピアノは結構きれいで聞けます。ユリウス・プリュヴァー/ベルリン・フィルとのドイツ・グラモフォン盤も出ています。そちらは1928年の録音です。リマスターによって針音が取り除かれており、案外聞きやすいものの、表現は大きく異ならないので音の点で新しい方がいいと思います。28年の演奏は表現上ゆっくりのところでもう少し揺れが大きく、弱め方もはっきりしているように思います。コルトーの時代の音だなという感じで、より弱く潜るのです。センチメンタルではないけどデリケートで壊れやすい印象はあります。したがって形の上で均整が取れているという点でもやはり新録音に部があり、トータルで穏やかに感じます。 その他の名手たち(20世紀の巨匠〜新しい世代まで) 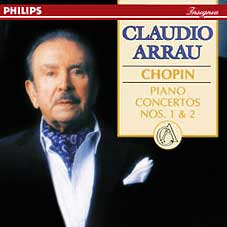 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Claudio Arrau (pf) Eliahu Inbal London Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 クラウディオ・アラウ(ピアノ) エリアフ・インバル / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 チリで生まれてドイツで学んだアラウ(1903-1991)はドイツ音楽の権威のように言われます。ショパンは柱ではなかったかもしれないけど、録音も残していて褒める人もいます。形は違うけどちょっとバックハウスに期待するような感じでしょうか。協奏曲第1番の録音はクレンペラー/ケルン(コローニュ)放送交響楽団による1954年の録音もあるものの、モノラルだし、緩徐楽章ではゆったりして間の取り方の大きい、ちょっとごつっとしたフレーズの癖がありますので、同じ傾向ではあるけれどもそれよりは多少スムーズな新しい方の1970年盤を挙げます。個人的には生真面目な権威の人というような気もしています。 第一楽章は遅い楽章と比べれば、確固とした力は感じるけれども比較的真っ直ぐな入りです。途中で遅くなる部分に来ると第二楽章で述べるのと同じ特徴が出ます。ピアノはフィリップス録音ということもあり、輝き過ぎず、適度な弾力があって輪郭の感じられる艶の乗った音です。それがまず魅力的です。 第二楽章は旧盤と解釈は似てますが、比べるならばより滑らかに流れます。テンポは遅く、所々に大きめの間を置いて悠然と弾いて行きます。それはそれはたっぷりとした運びなのだけど、なぜかロマンティックには感じさせません。どちらかというと生真面目で、間違いがないか周囲をじっくり観察しながら歩調を緩めて歩くといった趣です。歌のフレーズの後ろで遅くして長い間を取る傾向からそう聞こえるのでしょう。その部分ですごく弱める表現もあります。そうした大きな間と、それ以外のパッセージの間でバランスを取るように、ルバート様の伸び縮みも聞かれます。全体には節があって訥々とした印象であり、やはりどこかドイツ流の厳めしさを感じます。一時期のルービンシュタインの節回しが苦手だったこともあり、単なる好みの点から♡は付けませんが、落ち着いてじっくり弾く姿勢が好きな方には良いと思います。 第三楽章は飾りのトリルのところで間を取って崩します。それが独特のスパイスになっているなという感じです。跳ねるようなリズム進行で、かなり強さのあるタッチです。ここでもピアノの音に透明で艶つやしたところがあって美しいです。 フィリップスの1970年録音で、音は前述の通りでバランスが良く、管弦楽は弦に湿り気のあるやわらかさも出ています。録音面では相当上位に来るかと思います。2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Nikita Magaloff (pf) ♥ Roberto Benzi Orchestre des Concerts Lamoureux ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ニキータ・マガロフ(ピアノ)♥ ロベルト・ベンツィ / コンセール・ラムルー管弦楽団 マガロフ(1912-1992)も19世紀生まれでこそないものの昔からのショパン弾きとして有名で、良き教師でもあったようです。ロシア人ながら元々はジョージアの貴族の家系であり、ラヴェルとは友人関係でした。ショパンの弟子だったジョルジュ・マティアスの弟子のイシドール・フィリップに学びましたので、その系列ではあります。イシドール・フィリップはリストの弟子筋にも習ったためリストの系譜とも言えるかもしれません。いずれにせよ、ショパンとリストの専門家です。奥さんはヴァイオリンのヨーゼフ・シゲティの娘で、シゲティといえば甘い情緒を好まない新即物主義(ノイエ・ザッハリヒカイト)であるとされるように、マガロフもやはりロマンティックに傾かない簡潔な表現に特徴があると言われます。それは確かにある程度はその通りだと思います。70年代にフィリップスから出したショパンの独奏曲全集は大変音が良く、演奏マナーは曲自体に語らせるといった感じです。飾りを付けないで真っ直ぐ弾く葬送行進曲は圧巻で、その全くぶれない運びから立ち現れる厳かな情感に身震いするほどです。この曲の一つの理想的な表現でしょう。 個々の表現の特徴だけど、一音ずつをくっきりとさせ、クリスタルのように透明な輝きで弾いて行く独特の魅力があります。基本はあまり崩さず、速いパー トでは微かに揺れるリズムがあります。したがってルバートの徒ではなく、個人的には好きだけどパデレフスキの弾き方を認めなかったようです。でもノイエ・ザッハリヒカトというのはショパンのこの協奏曲ではどうでしょう。そういうタグ付けはあまり意味がないんじゃないでしょうか。少なくともシゲティに似ているという気はしません。 協奏曲の第1番です。第一楽章は力強い入りです。わずかなためを効かせ、一音ごとに明確に独立させて弾きます。一方で結構ロマンティックな弱音があり、そういうところではテンポも緩めます。大きく崩す人ではありませんが、ゆっくりなところではテンポを動かし、速めたり緩めたりで強弱もしっかり付けます。そんなマナーは ちょっとだけコルトーの時代の香りがします。なし崩しに拍の頭を前倒しにして走ったりはしません。割合かっちりと弾き、基本の流れはさほど伸び縮みさせない方でしょう。ただ、速いところはちょっと慌ただしいのであまり好みではありませんでした。 第二楽章はなかなか素晴らしいです。多少ごつっと振りの大きい感じはあるものの表情豊かであり、走る部分の表現と違っていて二面性があると思いました。この人の中では一つのものなのだろうけれども。淡々と始め、フレーズの終わりで少し延ばし気味にします。ここも一音ずつエッジを効かせて独立させるように弾くのが特徴で、静けさに輝きが加わります。それがこの人の緩徐楽章の最大の特徴でしょうか。ころころと粒立ちの良い音で、すっと弱め、テンポも落とすものの飲み込まれるような弱音は使いません。明るくきらきら光るけど枯れた印象 もあります。比べるならばリヒター=ハーザーの景色のようにカーテンの向こう側でではなく、晴れて空気の澄んだ日の屋外がクリスタルのように輝く演奏です。 第三楽章では、今度は走らずに、ややリズムにアクセントを付けながらくっきりと弾いて行きます。やはり個々の音がきらきらしてきれいです。基本は落ち着いているけどリズム感が良く、真面目ながら遊びもあって、軽く跳ねるように弾く場面も聞かれます。 1962年のフィリップスの録音です。音は良いです。カップリングは2番の協奏曲ですが、弾いているのはマガロフではなく、クララ・ハスキルです。マガロフの2番は長い間出ておらず、前出のハンス・リヒター=ハーザーとの組み合わせでやっと出たのです。その盤のリヒター=ハーザーを薄いカーテンの向こう側の輝きと表現しました。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Gina Bachauer (pf) ♥ Antal Dorati London Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ジーナ・バッカウアー(ピアノ)♥ アンタル・ドラティ / ロンドン交響楽団 ジーナ・バッカウアー(1913-1976)。あまり聞かない名前かもしれません。ソルトレークで開かれる彼女の名が付いた国際コンペティションについて知ってる人は知ってるかもしれないけど、ユタ交響楽団とよく共演したからだそうで、検索しても CD の業者は出て来ても個人的に言及してる人はあまりいないという状況です。これは英語圏でも似たようなものです。でもコルトーに師事したからショパンの系列だし、ラフマニノフ本人の弟子でもあります。ギリシャ/オーストリア系のギリシャ人ピアニストです。シューマンみたいに法律を学んだこともあるそうです。 硬質な響きできっぱりしていて、気品があって決して取り乱さない美しい演奏です。第二楽章だけの運びを聞いていると、テンポを揺らさずに一つひとつ丁寧に運ぶところが一瞬日本の人みたいだと思ったりもするけど、ちょっと違うようです。静かに運ぶところに品格が漂い、かっちりとしていて透明さを感じます。筋が通ってるというのか。日本の人にそういうのがないと言ってるわけじゃありません。弾き方に大きな崩しがないのでどうと描写をするのが難しいタイプです。ショパンだからルバート、ないです。でも緩やかな楽想の部分に大変魅力があります。普通だけど個性があると言ったら矛盾でしょ うか。硬さがあってもやさしさがないというわけでもなく。感受性があって、明晰でフラットなのが持ち味です。 第一楽章はくっきりと区切ったスタッカート気味の音で入り、結構男性的だなと思わせます。その後もやはりはっきりしたタッチのピアノの音に耳が行き、その分所々の弱めが効いて来ます。急に声を落とすように弱音になって囁くところもあり、独特のきれいさです。テンポを動かすことはほとんどありません。堅固なフレージングで一つひとつ丁寧であり、同じ女性で同程度に癖の強くないエヴァ・クピークと比べると真逆です。あんな風にやさしい弱音を駆使してやわらかく延び縮みさせる演奏ではありません。 第二楽章は透明感があって芯の通ったところがなんともきれいです。ピアノが前へ出る録音でもあり、コーンと響く明快な音で進めるのは前の楽章と同じながら、こうしたゆったりしたパートでは男性的というより、今度はむしろ素直さを感じさせます。やわらかい弱音で行くのもいいけれども、こういうきらっとした音で静かなのも美 しいです。アゴーギク面では揺らしは特になく、オーソドックスな運びです。一方で、弱いところはかなり弱めるけどやはりやわらかく飲み込まれる印象はありません。拍の頭で決して急がず、全体に落ち着きがあってテンポはゆったりめ。所々で聞かれる強いタッチ以外ではほとんど癖はなく、きっぱりとしていながら十分にデリケートです。 第三楽章になると、今度は少しためと走りを混ぜてリズムを付けます。このコントラストによってただべったり真面目に弾いてるわけではないのだと思わされます。オーケストラは歯切れが良いです。 1963年のマーキュリー・リビング・プレゼンスです。当時の最優秀録音もさすがにちょっと古くはあり、オーケストラに限って言えば弦の高音はきつめです。でもピアノは金属的になり過ぎません。2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Jorge Bolet (pf) ♥ Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ホルヘ・ボレット(ピアノ)♥ シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団 顔の雰囲気が似てるからということではなく、フランソワと比べられる奇才と目されていた(あるいはそうなるまでに長い間注目されていなかったという説もあります)、超絶技巧の持ち主とされるピアニスト、ホルヘ・ボレット。昔はフランス読みでボレ、もしくはボレーと言われていたこのキューバ生まれのアメリカ人は、第一次大戦の1914年生まれで90年にエイズで亡くなっています。フランソワより十歳年上。リスト直系の弟子(アレクサンドル・ジロティとモーリツ・ローゼンタールに師事)で、主にリストの録音が残っているけれども、ショパン弾きでもありました。年季の入った節回しがある人、という印象です。 技巧については触れないので抑揚のあり方に注目します。独特の味わいのある歌のセンスを持った人です。どう言うのでしょう、流れ作業ラインの熟練労働者みたいに、進んで行く音楽の時間的経過に対して余裕で構えながら自在に拍を取って行きます。裏拍気味に遅らせる場合もあれば、やや前倒しにするときもあり、一筋縄で行かないところはフランソワと似ていなくもありません。でもジャズ的なリズム感というわけでもなく、もっと微妙です。また、ダンディズムとでも言うのか、美意識から来るのだろう覚醒感があり、緩徐楽章ではゆったり方向で抑揚を付けているにもかかわらず感傷とは縁がありません。独自の揺れを武器に、感情に曇る目では見えないような繊細な美を追求していると言えるでしょう。 したがって第二楽章のロマンツェは穏やかで詩情があります。静かに語るように、覚めたまま回想するように進みます。ぱっと聞くとどこからこの感覚が発しているのか分からず、いったい何者なんだろうかと気になる運びです。揺らいでいるのに達観しており、何事にも乱されない境地であるかのようでありながら、まるで違う気もします。 大変良いので♡♡にしたいところだけど、両端楽章の速くなるところで頑なに前へとドライブをかけない抵抗感を感じ、そこが個人的には気になったので一つ減らしました。技巧をひけらかしたくない気分だったのかもしれません。信号のない大通りを車が縦横に行き交う中、大丈夫とばかりにゆったり横断しているみたいです。個人的に馴染めなかっただけで、この辺は好みによると思います。第二楽章だけだったら最初に取り上げたでしょう。フランソワばかり特別扱いし過ぎでしょうか。
1989年のデッカの録音です。かっちりとした輪郭で粒状の艶のあるピアノがきれいです。オーケストラも良好で、デジタルになってからという新しさがありがたいです。昔ベヒシュタインのセールスマンから自社のピアノ使いとしてカツァリスとホルヘ・ボレットの名を聞きましたが、ここでもベヒシュタインなのでしょうか。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Dinu Lipatti (pf) ♥ Otto Ackermann Tonhalle Orchester Zürich ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ディヌ・リパッティ(ピアノ)♥ オットー・アッカーマン / チューリヒ・トーンハレ管弦楽団 写真を見るとやさしいドラキュラかと思ってしまうリパッティ(1917-1950)。ルーマニア人と聞けばなるほどと思います。でも1958年のフィルムがその映画の代名詞になっている有名なドラキュラの俳優、クリストファー・リーはイギリスの人。実はその一つ前があります。1931年のアメリカ映画で、ベラ・ルゴシが演じてました。この人はハンガリー人とされるけれども生まれはルーマニア。やっと辻褄が合いました。じゃあどこが似てるんだろう。真ん中分けで後ろに撫でつけた髪型のせいで額の両側がバックしてるところと、落ち窪んだ目と眉が接近してるせいで目の周りが黒く見えるところ、鼻筋と唇が細くて真っ直ぐなところです。全体としては端正な顔立ちです。でもこんな取り違えをするほどリパッティの演奏の方も端正なスタイルであり、一時期はハリーナ・チェルニー=ステファンスカという、これまた端正な演奏をするポーランドの女性ピアニストと混同されてました。取り違えにはもう一つの原因があって、白血病に似た血液の癌であるホジキンリンパ腫によって三十三歳で亡くなってしまったリパッティは伝説的な人気を誇っていたということです。ジネッタ・ヌヴーや ジャクリーヌ・デュプレ、指揮者のグィド・カンテッリやフェレンツ・フリッチャイ、イシュトヴァン・ケルテスなどと同じことです。だからどうしてもその演奏が聞きたい。それで間違えてまで録音を探したのでしょう。 系譜としてはコルトー門下で、コルトーが特別にかわいがった人でした。しかしまるで正反対ぐらいに演奏スタイルは違い、ネイガウス、ロジーナ・レヴィーンも入るでしょうか、あるいはマガロフといった人たちと同様に19世紀的なルバートはせず、録音は古いけれども古さを感じさせないマナーであって、言ってみれば現代のニュートラルな表情をすでに持っています。というよりも、この人は若くして亡くなっているからそう思われないだけで、長生きしてればデジタル時代が始まった頃には六十代前半、カラヤンなんかよりも十近く若いのです。「現代のピアニストでは味わえない」と評されてもロマン派の生き残りではありません。こう書いて来るとリパッティに好意的でないように聞こえるかもしれないけど、実は素晴らしい演奏だと感じます。現代の録音水準だったらベスト・ パフォーマンスの一つでしょう。 ふわっとフレーズを緩めてゆったり歌い上げるところや、揺れながら速めつつ強くする表現もあるものの、格別癖が強いわけではありません。比較するならロジーナ・レヴィーンのやさしさより芯があり、マガロフほどきらきらせず、ネイガウスの格調高さに近い気がして比べると、もっとテンポ変動があって弱音を効かせます。情感の湧き上がるところでの硬質なタッチも特徴かと思います。透明度が高くて品があって、大変美しい歌です。本当にいい音で残っていたらと残念な気がします。正確に弾く指の技術を除いては、この時代でショパンの表現ってもう完成されてたのかなと思えて来ます。 第一楽章のピアノは重みと区切りを付けた確固とした提示に続き、素早くさらさらと舞い降りて来る下降音型で始まります。古い録音だと構えると、実はあまり癖を出さずに弾いていることに気づきます。最新録音で聞いたら最近のショパン・コンクールかと思うかもしれません。4分頃から始まる静かなパートでは所々の音符を抜くようにためて遅らせる場面が現れ、ちょっとした表情を感じるものの、トータルでは癖の強いルバートはありません。音が良くないのであまり美音であるかどうかには意識が向かないけれども、本来はかなりきれいな音なのではないかと想像出来ます。 第二楽章。白眉です。最初は表情を抑えて小声で、テンポは中庸です。そしてデリケートに弱めて遅くし、そのまま間を延ばす運びが聞かれます。余韻がなんとも味わい深いものです。いつも明快なタッチで弾くのではなく、やわらかく抑えるところがあるのです。ネイガウスと同じく、ここまで完成度の高い演奏ではその人の癖を言う のは難しいけど、意外性はないながら揺れ方は上品で的確、所々で浮き上がるように強くしてクリアなタッチを聞かせたり、あるいは真っ直ぐ情動的なクエッシェンドを聞かせたりします。全体としては端正で大袈裟なところがないながら、楽譜通りの散漫なものとは全く違います。 第三楽章は割とはっきりしたタッチで軽々と弾いて行きます。かなり速弾きです。上手な人だったのか、ライヴなのに鍵盤に指を引っ掛けるようなことは少ないです。 1950年のコンサート収録です。EMI から出ており、Art 処理をしたリマスター盤もあります(上の写真)。大して違わないけどその方が聞きやすいと思います。本当にもう少し良い音だったらと思います。惜しいです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Emil Gilels (pf) ♥ Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 エミール・ギレリス(ピアノ)♥ ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団 ロシアン・スクール、もしくはマナー、メソッドと呼ばれる流派があります。それがベートーヴェン以来の伝統の冷凍保存なのかどうかはともかく、一つの流れを作って来たロシアの音であり、それを完成させた形で代表する一人がギレリス(1916-1985)なのだろうと思います。強さとやさしさのある演奏です。鋼(はがね)と言われた歯切れの良いタッチを落ち着いた表現の中に封じ込めたような、とてもきれいに磨かれた音を出す人で、強いところは毅然としており、テクニックは完璧とされました。特にショパン弾きというわけではなく、ベートーヴェンに定評があったけれども、この1番の協奏曲は見事です。速度を落として消え入るようなたっぷりとしたロマンティックな表現が聞かれるものの、それが気にならなければこの曲のファースト・チョイスになるかもしれません。ウクライナ生まれのユダヤ系で、ネイガウスに師事して戦後から活躍しました。ソ連のピアニストとしては西側でも活躍し、心臓発作で六十八歳で亡くなりました。注射の後だったという話もあ り、謎の死だとされています。伝統と格式いうか、そういう暗殺が当時も多かったようだし、最近のノビチョクのこともありますから即座に否定するわけにも行きません。 第一楽章はまず輪郭のはっきりとしたクリアなピアノの音が印象的です。同じ強いタッチでもバックハウスの録音とは違い、芯があって艶やかで、大変きれいな音色です。一方で表現は落ち着いていてむやみに駈けず、一音ずつをなおざりにしない丁寧さが感じられます。余分なことはせずに弾いて行くところに好感が持てます。加えて静かな部分では時々拍にしっかりとしたためを施し、山を作ってフレーズ終わりで緩めるロマンティックな表現も聞かれます。ピアニシモも透き通った音で、オーケストラの弦の高音で耳が痛くなりそうな箇所があるところが60年代なりというぐらいで、大変美しいです。 第二楽章では、テンポは初めさほど遅くはなく始まりますが、すぐにゆったりになります。矛盾した言い方だけど、くっきりした透明な音でやわらかく弾きます。 いい音です。表現としては歌の後半で緩めるたっぷりとした表情をつけ、やはり一つひとつを丁寧にこなして行きます。揺らして遊んだりはしません。フランス流に崩すのではなく、終止たっぷりとした情緒があって細やかな配慮が感じられるので、これこそが最も美しいロマンツェだと感じる方も多いと思います。後半静かになってからも飾らず正直に弾きます。こうしたパートでは、リヒテルが自らの感情に没頭しているとするならば、ギレリスは相手にやさしく語って聞かせる感じです。 第三楽章も同じく明確な音の運びですが、ややテンポとリズムが軽くなります。基本はこの人、真っ直ぐな性格なのだと思います。ライバルのリヒテルは色々非難したけど、好感が持てます。この二人、どちらがどちらに嫉妬したかについては真逆の意見があるので、先入観を持たずに演奏を聞いてみる必要があるでしょう。それぞれに違いがあるとしても個性です。字の美しさとは違い、音には人柄が表れると思います。 1964年コロンビアの録音です。すでに触れましたが、オーケストラの響きが若干薄くてトゥッティでの弦がきつめになるところが一瞬あるものの、ほぼ良好なバランスであり、ピアノの音は大変きれいです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Gyorgy Cziffra (pf) ♥ Gyorgy Cziffra Jr. Orchestre National de France ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ジョルジュ・シフ ラ(ピアノ)♥ ジョルジュ・ シフラ Jr. / フランス国立管弦楽団 安部譲二に一瞬似てるかなと思う風貌のシフラはちょっと変わっていて、ロマの出身です。ロマというのはいわゆるジプシーのことです。ユダヤ人と似たところのある流浪の民であり、ボヘミアンという呼び方もあります。あまり知られてないけれどもナチの時代には同様にたくさんの人が殺された歴史もあります。今は定住者が多く、ヨーロッパ全土に広がっているけど色黒で黒髪の人が多く、南インドが起源ともされます。「エジプシャン」がなまって「ジプシー」になったという説もあります。以前スペインに行ったとき、公営駐車場に車を停めようとしたら誰かが先導してくれました。でもドアを開けたらバスケットが差し出され、お金を要求されます。こういうのが一般的なロマのイメージでしょう。マイノリティーで経済状況が思わしくない、今も被差別の人々なのです。フラメンコ・ギターをかき鳴らして一晩中パーティーで騒いでいるような疲れを知らないタフなイメージでも知られ、元々ストリート・ミュージシャンのような一面もあります。このジョルジュ・シフラ(1921-1994)もフランス人の血こそ流れてるもののハンガリー出身のロマであり、コンクールに優勝して出て来た正統派のお坊ちゃんお嬢ちゃんとは違います。小さいときにバルやサーカスで即興演奏をして有名になり、貧乏から腕一本で世に出ました。国外脱出しようとして刑務所に入れられ(ハンガリーは東側です)、強制労働させられるなど命がけだったこともあります。一方で、リスト音楽院で習った先生の系統からリストの弟子筋ともされ、そのリストの華麗な演奏には定評がありました。 さて、そのシフラだけれども、まずはその超絶技巧を絶賛する人がいます。でもそれはリストの演奏での話であって、19世紀ロマン派が得意でショパンもよく弾いていたけど、この協奏曲の1番を聞いている限りでは全 くそんな感じはしません。そしてこの曲自体はかなり気に入っていたようで何度かの録音を残しています: マニュエル・ロザンタール/フランス国立管弦楽団 1963年/フィリップス ジョルジュ・シフラ Jr./フランス国立管弦楽団 1967年/パリでの演奏がテレビ放映されたもの ジョルジュ・シフラ Jr./パリ管弦楽団 1968年/EMI ジョルジュ・シフラ Jr./フランス国立管弦楽団 1969年/ローザンヌでのライヴ/クラーヴェス ジョルジュ・シフラ Jr./モンテカルロ歌劇場国立管弦楽団 1976年/EMI 演奏は基本的にどれも同じ傾向ではあります。即興に強い人なので毎回違いはするのですが、出して雰囲気が同じということです。第二楽章の静かな場面で割合運びが素直なのは、ロザンタールが指揮するフィリップス盤でしょうか。モンテカルロ管との EMI 盤もいい演奏だけど、もう少し癖が出ます。どれが最高ということもないけれども、録音のコンディションが最も良いのは1969年のクラーヴェス盤だと思うし、ストリーミングで安定して聞けるので、ここではその盤の写真を掲げました。ジョルジュ・ シフラ Jr. というのは指揮者である彼の息子さんです。一緒に牢獄に入って死にかけた後、父と一緒に音楽活動が出来るようになり、嬉しそうに指揮している姿を映像で見ることができます。ピアニストである父の方も息子のオーケストラだと安心出来たのだろうと思います。残念ながらジュニアは81年に火事で亡くなり、落胆した父親はすっかり意欲をなくしてしまったそうです。 一言で表現すれば、とにかくリラックスして楽しんでいる演奏です。シャワーを浴びながら鼻歌を歌っているかのように気分良く乗っています。それは第二楽章などのゆったりしたところはもちろんですが、両端楽章の速いパッセージでもさほど変わりません。具体的にはふわっと速度を緩めるところが出て、それもかなりしっかり遅く歌って音も弱めます。そうした部分が気分に任せて続くので、テンポは伸び縮みすると言えます。パハマンの揺れとも、コルトーのルバートとも、フランソワの外しとも違う、気ままでご機嫌な波長です。 第一楽章はやわらかく夢見るようで、この楽章だからといって力が入ったり駆けたりはしません。所々に粋な揺らしを加えて進め、全体のテンポはゆっくりな方で表現が大きく聞こえます。この感覚に乗れるととても気分の良い演奏です。ルバート様の動きがあるとは言っても、速いパッセージでは間を入れずにさらさらと飛ばす瞬間もあります。かと思うと一転してスローでやわらかくする、そんな感じです。 第二楽章は遅めのテンポで静かにやわらかく、フレーズごとに力を抜いて弱めます。形の上ではちょっとわざとらしいぐらいの波があるのだけれども、嫌味には感じません。フレーズの途中で延ばして緩めたりもあり、コントラストを付けてたっぷり歌わせます。思わせぶりというよりも、情緒は安定していて勝手に気持ち良く酔っている。お酒で言えばほがらかな酔いです。その自在に歌に乗ってる感覚はパレチニに似てなくもないけど、形はもっと崩れています。セオリーにはまらずに崩れるという点で言えば、取り上げなかったけどラン・ランにも似てるかもしれません。でももっと自由でしょうか。 第三楽章は力を入れずに軽々と飛ばします。子犬の戯れのようです。楽しくてお洒落です。苦難の人生だったようだけど、ずいぶん楽しく波乗りするものだと思います。そしてこんな和気あいあいの気分も81年までだったかと思うと、変わって行かないものはないのだなと感じます。その後十年ちょっとでご本人も卒業だったわけだけど、再会できたのでしょうか。 この盤は69年録音のクラーヴェスで、時間的には先ながら76年の EMI 盤より音のバランス的にきれいに聞こえる気がします。ライヴなので最後に拍手が被ります。これ以外の録音は単発ものは廃盤になっていて手に入り難く、この人の全集の中にまとめて入ってるのがあるぐらいです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Tamás Vásáry (pf) ♥ Jerzy Semkow Berliner Philharmoniker ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 タマーシュ・ヴァーシャーリ(ピアノ)♥ イェルジ・セムコフ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年生まれ、ハンガリー出身のヴァーシャーリは深々とした情緒をたたえて弾く人です。ラフマニノフの協奏曲(全集)は評価が高いです。ショパンの方は真面目に取り組んだオーソドックスな演奏だけどロマンティックでやわらかく流し、霧立ち込める中での募る想いといった風情があります。それでいて形の上では大きなルバートで崩したりはせず、劇的に強めたりもしません。やさしく丁寧に、伝統的なバランスを保って表現します。あるいは耽溺気味だと感じる人もいるかもしれません。しっかり浸りたいけど大仰なのは嫌という人にはベストだと思います。 第一楽章ですが、最初は案外速いテンポでさらっと行くのに驚きます。しかし強弱の表情はしっかりあります。時間軸方向の揺れは大きい方ではありません。小節の頭で一音弾いてから間を延ばす語法と、すっと力を抜いてやわらかくする弾き方に特徴が出ます。でも正統派の安心できる抑揚表現です。一音ずつしっかりと音にしていて走ることはありません。 第二楽章はオーケストラの導入からたっぷりと遅く、抑えた弱音で始めます。遅らせる「ため」と、それを取り戻すようにわずかに速める息遣いがオーセンティックで、ショパンらしいルバートの揺れを薄めた形で聞かせます。音が少し遠いこともあり、叙情的なムードが溢れています。夕焼けのオレンジの光に大気中の塵が反射して、少し靄がかかったような美しさと言いますか。ピアノは粒立ちの良いくっきりした音ではなく、芯はあるけどソフトな音色です。ゆったり味わいながら進んで行き、やわらかさの点で最も美しい演奏だと思います。 第三楽章も力を抜き、余裕をもって進めます。やわらかさは相変わらずで、少し速いところでも緩徐楽章のようです。真摯な印象も変わらずです。 1963年のドイツ・グラモフォンの録音は新しくはないですが、前述の通り、このレーベルにしてはやわらかくて艶の成分が強過ぎません。やわらかいがゆえに所々でブラスのエッジが浮いて聞こえるし、強いタッチのと きにはピアノも芯を覗かせるけれど、全体としてはソフトな印象です。トゥッティでは古いなりにオーケストラに多少の荒っぽさは出ます。ちょっとライヴです。2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Fou Ts’ong (pf) Muhai Tang Sinfonia Valsovia ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 フー・ツォン(ピアノ) ムー・ハイ・タン / シンフォニア・ヴァルソヴィア 1955年のショパン・コンクールで3位に入った中国人ピアニストです。そのときの1位はアダム・ハラシェヴィチ、2位がアシュケナージでした。なぜこの人を取り上げるかというと、中村紘子の言う京劇のような中国の面白いアクセント、中国人に共通した国民性のような弾き方があるのかどうか、そしてどのぐらいの割合でそうでない人がいるのかに興味が湧いたからです。まあ、数人聞いたって分からないし、そういう癖を仮定して見ようとする態度こそが当該の性質を作り上げているとも言えるわけですが。1934年上海生まれということで、今活躍している同国の若手ピアニストたちよりずっと上の世代であり、草分け的な存在と言えるでしょう。華僑でもお馴染みの裕福なインテリの家庭に生まれ、両親は文革で迫害されて自殺に追い込まれてしまったということで、中国国内で育ったけれどもヨーヨー・マなどとも共通する感覚を持っているのかなと想像しました。同じような背景を持ち、同じ上海で15年後に生まれた亡命ピアニスト、シュ・シャオ・メイはマと同様に国際的な感覚を持つ人です。フー・ツォンはアジア系でない演奏家たちとも親交があり、気が合ってよく一緒に活動していたという話もあります。イギリスに亡命したまま帰れず、2019年にコロナ・ウィルス感染によってロンドンで亡くなってしまいました。 結論から言えば、聞き始めてしばらくはインターナショナルな基準に則ったコスモポリタンな演奏かと思いました。ところがしばらくして緩やかに歌わせる部分に差しかかると、独特の癖を感じるようになります。どこか聞き覚えがあるもので、ずっと後の2000年のコンクールの覇者となったリ・ユンディの、ドイツ・グラモフォンの旧盤の方にどうやら少し似ているようです。ユンディの方が性質としてもう少しあっさりしている気もしますが、拍の頭でためて遅らせるところがあり、それがリズムの先頭の音だけではなく、万遍なく多くの音符に広がって出 る傾向があります。そしてその遅らせる手法は感情表現として現れて来ているので、感情を込めて歌わせようとする部分が歌の前の方だけでなく、中ほど以降でも続きます。まるで盛り上がりが後ろに移動したかのような錯覚を覚え、ちょっと不思議な感覚になりました。これはローカルな傾向と言っていいのでしょうか。同じ熱さではなくてもラン・ランにも違った形で認められる気がします。スポット的な強調ではなく、どこにでも抑揚を込める傾向と言った方が適切でしょうか。ユジャ・ワンにはそういうところがありません。彼女は超絶技巧で馳ける高速パッセージ、力強く歯切れるところ以外では大きな抑揚はなく、素直です。 フー・ツォンのもう一つの特徴は重みのある響きです。これはホールの残響や録音の具合もあるにせよ、ペダルワークと指の残し方に関係していると思います。常にライヴに鳴り響いている感じがあり、ための作り方と相 まってスケール感があります。トータルでは味の濃い、おいしい中華料理を食べたという満足感につながるかと思います。 第一楽章から重さがあって、感情的に大きな起伏を感じます。でも最初は特に癖があるようには思わず、遅らせることで歌の山が後ろにずれる感覚は覚えるものの、この楽章についてはどうこう言うレベルではありません。ユンディの個性が強く出たときやラン・ランに比べれば、欧州系と言われても気づかない程度です。 第二楽章は途中途中で緩める割合が大きくなります。立ち止まるとまでは行かないものの、濃い表現です。タッチの面では角がはっきりと聞こえるので、力はあるのではないかと思います。前述の通り、フレーズの後半に重心があって遅れて盛り上がる感覚や、歌って行って途中で間を空けて遅くするところが聞かれます。音響的にはややライヴで、弱音は響きの中に埋もれる傾向です。どの部分にも隙がなく表情が付いているので、コントラストが強い感じにはなりません。 第三楽章は音を切らずに続けるところが印象的です。レガートと言うか、速いところでも指を残すのか、ダンパー・ペダルもしっかり使っているのか、音符全体で鳴らし切るような感覚です。そのライヴ感が重さにつながるところがあり、大きな音で続けて聞いていると、おいしくてもお腹いっぱいに揚げ物を頂いたようになりがちです。これは個人的感想ですから、一般には気宇壮大と言えば良いでしょうか。 1989年のデッカの録音はライヴによく響き、オーケストラはやや太い音です。コンディションは良いです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Vladimir Ashkenazy (pf, cond.) Deutsches Symphonie Orchester Berlin ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ウラディーミル・ アシュケナージ(ピアノ/指揮) ベルリン・ドイツ交響楽団 亡命したての頃にラフマニノフの2番で素晴らしい演奏を聞かせていたアシュケナージ、ロマン派の曲では人気がある人だと思います。でもショパンの1番に関しては長らく録音がありませんでした(コンクールで弾いた第2番は1965年に録音しました)。やっと出したのは1997年、六十歳になってからです。そして後年は指揮活動が中心になってピアノは若手に弾かせていましたが、2020年に引退しました。1955年のショパン・コンクールでは2位だったけれども、優勝じゃなかったことに抗議してミケランジェリが審査員を辞めたという話は有名です(1位は第1番を弾いたアダム・ハラシェヴィチ)。そんなわけで、ショパンの協奏曲は期待されるものでした。 1937年生まれです。この人はユダヤ系ロシア人といっても、豪胆なテクニックとたっぷり甘い情緒という典型的なロシアのマナーではなく、ソ連にいた頃は派手なことはしないけど繊細な歌も持っていました、と言えるのはそのラフマニノフの2番の最初の録音を聞いてからで、テクニックについては折り紙付きです。コンクールのときはバリバリ弾いていたと評する人もいます(実況盤も出ているのでなるほどと確認できます)。そして西側に亡命してからの演奏は、コマーシャリズムに追いつこうという意気込みなのか、ときにちょっと大胆に表情を付けてやってみたりし、それからしばらくして出したラフマニノフの新録音ではまた昔の流儀に戻ったかのようにさらっとした味わいになりました。したがって色々遍歴して鮒釣りに還って来たのかと思ったわけですが、でもこれを聞くとどうやらそんな単純なことでもないようです。 第一楽章では素直な運びながら表情がたっぷり付くところもあります。所々でスタッカートのスパイスが出るのか、と感心もしました。第二楽章に入っても真っ直ぐな運びは変わらず、そこまでなら色々やってみて初心に戻ったのだと信じたままでいられます。時々アクセントを付けて崩す部分が見られるものの、むしろ以前よりストレートになった感じです。知らずに聞いたら日本の演奏家かと思うほど端正に音符を揃えて弾くところも出たりして、むしろ若いときの中村紘子かと思ったぐらいです。晩年の彼女は時折一音だけ強く強調する癖もありましたが、こちらのアシュケナージにはやさしさがあり、控えめであることの美徳を感じます。 ところがです。第三楽章に入るとどうしちゃったのかというほど跳ねるリズムに調子を付け、スタッカートを交えて遊んでみせるではないですか。自由になれたのかもしれません。思い切りジャズっぽいとも言えるほどで、今 度はグールドかバッケッティかという軽妙さです。とにもかくにも意外だったのがこのアシュケナージのショパンでした。細かな描写はやめておきますが、こういうのもあっていいと思います。百面相とも言えるけど、持ってる人です。 1997年、デッカの録音です。カップリングは2番で、そちらは二十七歳時の録音です。アシュケナージのピアノの音はコンペティション・ファイナルのもデッカに録音したいくつかも、強く叩くからか高音が薄手で華やかな音色に聞こえる場合がありました。反対にラフマニノフの2番のコンチェルトの最初の録音はしっとりしているし、ここでの二曲のショパンもそこまできらきらし過ぎることはありません。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Dvořák Piano Quintet op.81 Jean-Marc Luisada (pf) ♥ Quatuor Talich ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ドヴォルザーク / ピアノ五重奏曲 op.81 ジャン=マルク・ ルイサダ ♥ ターリヒ四重奏団 1957年チュニジア生まれのフランス人ピアニストです。ショパンの孫弟子に師事しているのでその系統と言え、ショパンを得意としています。1985年のショパン・コンクールで5位でした。ブーニンが勝った年です。審査の結果に不服だったようだけど、もちろんそういうことも起こり得ます。表現力に秀でたものがなくてもミスをしない方が合計点が上に来るという採点の問題を指摘する人もある通り、勝った人がいい演奏をするとは限りません(ブーニンが不当だと言っているわけではありません)。ただしご本人が言うのはどうなんでしょうか。 このルイサダという人も、ショパンのファンにとっては外せないピアニストだと思います。内向的な気質を感じさせ、軽い動きのあるセンスの良い人という印象です。ショパンの繊細な面を期待通りに味わわせてくれます。 静かなパートで内気な繊細さを感じさせるピアニストと言えば、他にもブレンデル、ペライア、最近のアシュレイ・フリップなどが思い当たります。このうちブレンデルはショパンを得意とせず、ほんの少ししか出していませんが、ルイサダの表現はこのブレンデルの緩徐楽章にも少しだけ似た湿り気があり、かといってペライアほどの悲しみは感じさせません。また、ペライアはこの曲ではさほどではないものの、細かいテンポの揺らし方に絶妙な動きがあります。そして1988年生まれのイギリスのピアニスト、アシュレイ・フリップ(グレアム・ブックランド/レーゲンスブルク大学室内管弦楽団/独スペクトラル)はより形が整っていて理性的な印象です。消え入るようなピアニシモに特徴があるこれら三人を比べる場合、かなり耳を澄ます必要があります。ルイサダの他二人と違う特徴は、時折さらさらっと前に駈ける表現があるところです。拍の区切りを前へ倒すのです。そして反対に間を とって速度を緩める度合いも大きめです。19世紀的ルバートというほどではないにしても、結構揺らすところにショパンらしいポエジーが表れるもので、弱め方も大変デリケートです。個人的には少し振りが大きい気はするものの、そんな表現の幅が人気のポイントなのでしょう。 それともう一つ、この演奏は室内楽版で、ピアノ六重奏です。有名なチェコのターリヒ四重奏団がバックを務めます。オーケストラによるのではない、その音の静けさも大きな魅力です。 第一楽章は結構力強く、やや粘りのある導入に続いてさらっとした下降音が続くかと思うと、切り替えてやわらかく、そっと弾く感じになります。そしてその後、途中で速めて軽さを出すところと、ゆっくり丁寧に表現する歌とが波のように交互にやって来ます。この振れ方のセンスが好きかどうかはそれぞれあるにせよ、全体的に抑揚の付け方はつぼを押さえていて奇妙に感じるようなイントネーションはありません。尾の長いリタルダンドで静めるところも繊細です。 第二楽章は力が抜けていて所々でためる拍を混ぜます。そして間を大きく取って速度を緩めつつ、弧を描くような抑揚が全体を包みます。手弱女ぶりという印象です。ペライア、アシュレイ・フリップ、シャルル・リシャール=アムランなども同じだけど、有名ピアニストに共通する我の強さ、コンクールを勝ち抜くたくましさという意味では目立たない人かもしれません。ビロードのように滑らかで、壊れやすいがゆえに包み込むようなやさしさがあります。そっと一人でため息をついているようです。それを霞がかかっていると表現すると否定的なので、ピントは合っていて輪郭はくっきり見えるソフトフォーカスレンズの世界という感じでしょうか。録音のせいもあるけど、エッジを立ててきらきら輝かせるのとは反対です。 第三楽章は速度を伸び縮みさせて軽やかさを出しています。所々で一瞬立ち止まる一方、前のめりにはなりません。 1998年の RCA の録音はやわらかく、少し被ったようなシルキーさがあります。ブレンデルに似てると言いましたが、フィリップスのブレンデルの録音のようなフォルテでの硬質な芯はありません。 ●カップリングはドヴォルザークの室内楽の名作、ピアノ五重奏曲第2番 op.81です。ドヴォルザークのページで取り上げようかと思ってましたが、シューベルトの「ます」とも同じことで、ピアノ五重奏という形式はピアノ に負けないように弾くため、高音弦がきつくならない録音にするのが難しい曲です。でも第二楽章ではもの悲しくて大変印象に残る叙情的な旋律が聞けます。この CD はショパンの方もピアノ六重奏版であり、通しで室内楽の味わいを堪能できる一枚となっています。 ドヴォルザークの op.81については他にもこのページの最初の方で取り上げた名手、クリスティアン・ツァハリアスとライプツィヒ弦楽四重奏団による盤(弦楽四重奏の名曲と同名の「アメリカ」と呼ばれる弦楽五重奏曲第3番 op.97 と組/2003 MDG)と、アンドラーシュ・シフのピアノにパノハ四重奏団によるもの(名曲かどうかは見方次第だけど、ピアノ四重奏曲第2番 op.87と組/1997 テルデック)もお薦めです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Ewa Kupiec (pf) ♥ Stanislaw Skrowczewski Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 エヴァ・クピーク(ピアノ)♥ スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ / ザールブリュッケン放送交響楽団 エヴァ・クピークは1964年生まれのポーランドのピアニストです。お国ものということでポーランドのショパン解釈のあり方を見ることになるのかもしれませんが、いわゆるショパンらしいテンポ・ルバートがしっかりという感じでもなく、女性的と言うのは今時どうか分からないけど、上品でやわらかく、素直さも感じられる魅力的な演奏です。 第一楽章はオーケストラが表情過多に感じるほど遅めなのが気になりますが、ピアノは派手な細工はしません。最初はどっしりとした音で始め、すぐに繊細な動きの感じられるやわらかい表現が現れます。すっきりした味わいながら、テンポが自然に速まったり遅くなったりする呼吸は後で触れるネボルシンよりもあります。それは滑らかにつながって波のように運ぶものであり、弱音の魅力に溢れています。弱いところで遅くする度合いが大きいので、ネボルシンを描写するときの「ほとばしる透明な湧水」という感じではありません。少し逡巡しながら、そっとささやくように進めます。静かなパートではやや表情がしっかり傾向ながら、ピアノの音はしっとりとして軽さも感じられます。 第二楽章はこの人の魅力がよく出ていると思います。さらっとした運びで弱音を生かし、興奮して瞬間的に少しだけ早める間合いにときめきます。やさしくて静かで、一つひとつの音を愛おしむように弾くところが大変良いです。他の演奏者でよくあるように、所々に大きな間を空けるような無粋なことはしません。滑らかにつないで遅くなり、また速くなる。その繊細な伸び縮みに魅力を感じます。子守唄のようでもあり、身を任せている心地良さが あるのです。 第三楽章ですが、ここもきばらないタッチです。弱く、それより強くと変化を付けながら滑らかに小声で進めます。速い楽章であるという感覚よりも先に、静かに流れる音のやわらかさにうっとりします。しかしオーケストラがまたしてもちょっと大きな強調を入れて癖を感じさせます。ピアニストよりもこの指揮者の方こそを褒める向きもあるようですが。もちろん二人の性質が異なるところにちょっと驚くというだけの話です。 ドイツのウームス・クラシックス(Oehms Classics)2003年の録音です。残響が目立つ方ではなく、弦は割合とはっきり前にせり出し、低音も出ています。新しい録音のようだけどオーケストラに関しては多少アナログ時代の古めのバランスにも聞こえます。ピアノは倍音は捉えながらもやや遠い響きです。芯に細い金属的な音が混じる瞬間が聞かれる一方でまろやかさもあり、艶も適度できれいです。軽さと明るさ、ソフトな感触がバランスして感じられます。 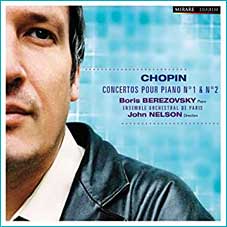 Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Boris Berezovsky (pf) ♥ John Nelson Ensemble Orchestral de Paris ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ボリス・ベレゾフスキ(ピアノ)♥ ジョン・ネルソン / アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 体格も手も大きそうで、力と技巧に優れてるとも言われるし、腕組みなんかしてるとアクション・スターかなと思う風貌でもありますが、聞くと力技というのとは違います。素直で真っ直ぐながら大変センスの良い表現をする人だと思います。洗練されているのです。1969年モスクワ生まれで90年のチャイコフスキー・コンクールで優勝しました。 第一楽章はペダリングで区切りを付け、表情は大きくないけど見事にきっぱりとした入りです。粒の揃ったきれいな音でさらっと進めます。この曲のスタンダードな運びであると言っていいでしょう。流れるように下降する音の列に艶があって美しいです。他の人と比べて大きくためは取りません。それが率直な印象につながり、かといって前のめりでもなく、人によってはそっけなく感じるかもしれないけどポーカーフェイスでもありません。 第二楽章は最初の一音が弱く、一瞬失敗したのかと思いましたがそういう表現でした。早める方にも遅らす方にもわずかに揺らしながら清潔に歌って行きます。間は大きくはありません。その薄味で初々しいところが若いショパンにぴったりかもしれません。こういうゆったりした楽想のパートでの表情において、この人はセンスが良いとラフマニノフでも思いました。元々持っている感覚だと思います。 第三楽章は力を入れずに歯切れ良く、軽快なテンポで進めます。軽やかです。リズム感とクレッシェンドの入り方もいいです。かなり速い方でしょうか。 2007年ミラーレの録音です。ピアノは金属的にならないぴんと張ったきれいな音です。オーケストラのバランスは標準的だけど良い出来でしょう。2番とのカップリングです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Gianluca Luisi (pf) ♥ Ensemble Concertant Frankfurt ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ジャンルカ・ルイージ(ピアノ)♥ アンサンブル・コンチェルタント・フランクフルト 弦楽五重奏版で、室内楽らしい良さを持った一枚です。ピアノの表現もシックで魅力的です。ジャンルカ・ルイージは1970年生まれのイタリアのピアニストであり、イタリアではコンペティションでいっぱい優勝しているようだけど、ショパンやチャイコフスキーでの覇者ではありません。バッハが得意のようです。 MDG からのリリースです。 第一楽章ですが、出だしの弦は一音ずつよく区切ったアクセントで弾かれます。お国柄でしょう。ピアノもくっきりしていながら軽さがあります。ペダルの使い方と録音のせいか低音があまり響かないため、一瞬ピリオド楽器かというような響きにも聞こえますが、高音は別です。音像は少し遠めでしょうか。弱音の扱いがきれいで、一音抜けるように弱く弾いたりするところがデリケートだし、敢えて速度を落として運ぶ弱いフレーズも繊細です。その速度を緩めるという手法がこの人の表現上の特徴かもしれません。テンポを前後に大きく揺らすタイプの演奏ではありません。力で押し切らない丁寧な音の扱いが聞かれます。 第二楽章には力の抜けたやわらかな空気感があります。タッチは案外はっきりしているけど、静かで落ち着きがあります。フレーズを丁寧に一つずつ音にして、いぶし銀の味わいというか、しっとりした光沢で独特の渋さがあります。多少霞みを被ったようなやわらかい録音で、エッジが立たないところからそう感じる面もあると思います。でも途中短調に転じるところから強いタッチではっきりした表情に変え、コントラストを付けたりもします。そこでは皆がはやるように速度を上げるのに敢えてそうせず、毅然とした強さをもって感情の変化を示します。そんな風に走らないところもシックさにつながっているのでしょう。多少鄙びた感じの魅力的な運びです。速度を緩めて間を取る手法は前の楽章と共通しています。 第三楽章では最初から室内楽の響きの美しさを感じさせます。ピアノはスタッカートで軽く間を取りつつ、トリルを速くまとめてリズム感を付けます。タッチはかなり強く、反響の付いた音の中ではそれが多少ハレーション を起こしたように聞こえます。弦のアタックはきつめです。ドイツ流にかっちりしているとも言えます。 2010年の MDG の録音です。音のバランスは上に述べた通りです。ドイツの修道院でセッション録音されました。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Evgeny Kissin (pf) Dmitri Kitaenko Moscow Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 エフゲニー・キーシン(ピアノ) ドミトリー・キタエンコ / モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 神童と呼ばれた人です。最近のヤン・リシエツキと比べてみるのも面白いかもしれません。ショパンの協奏曲は有名で、あちこちで評価が高いです。音楽学校でアンナ・パヴロフナ=カントルという女の先生一人に就いて勉強し、コンクールには出ませんでした。1971年モスクワ生まれのユダヤ系で、イギリス/イスラエル人です。 ジャケットを見て驚くわけですが、このとき十二歳です。先生が女性だと母性をくすぐられるでしょう。でも演奏は子供っぽくありません。音楽の抑揚は年齢に関係なく、出来る人は出来るもののようだけど、それと感情的 発達とがどうリンクしているかは必ずしも明白ではありません。子供の方が感情的に成熟していて親の矛盾を鋭く見抜くことはよくあるし、早くに亡くなる子供が大人もたどり着けない悟りの境地を見せることもあります。人は生まれたときから同じスタートラインではないと思わせられるところです。ただ、このキーシンの表現については、人生経験によって共感能力を発達させ、音楽に深い情感を感じているのか、あるいはただリズム感覚が優れているのかはそれぞれが自分の感覚で聞いて確かめるのみです。感じ方は様々なので結論はありません。 テンポは軽快な方で、くっきりと明晰なエッジの効いた音で弾きます。フレーズの頭でなく後半にアクセントを施して所々こつんこつんと強調を入れます。輪郭のある音を際立たせる意図なのでしょうか。延び縮みはしっかりあって驚くほど自分の呼吸になっており、リズム感を持ってるなと思わせます。特徴は前へと急ぎ足の方向に出る武器を持ってるところです。一瞬の走りもあります。堂々とした抑揚でありながら、ちょっと不安定な心の動きも出して見せるあたり、ショパン弾きとして注目されるのも分かります。華麗できらきらと輝いています。 よく大人になったらただの人みたいに言われたりもするけど、その後の2011年のライヴ映像も見ることが出来ます。そこでは独特の引っ掛けるリズム(ため)があったりするもののセンスは保っており、きらきらしたタッチと強いアクセントは健在です。若いときの方がさらっと速いとは言えるでしょうか。
第一楽章はくっきりとした強いタッチが印象的です。念を押すような粘りとさらさら流すところとがあり、トータルではあまり遅くありません。軽やかというのとも違うけど、独特の揺れを持たせて拍を切り上げ、前へと小走りになるところがあります。それでも焦りは感じさせず、没入もしない爽やかな味わいです。自分の歌をすでに身につけています。 第二楽章ではその少しだけリズムを速める独特の呼吸がお洒落に感じます。ここも思い入れたっぷりではなく、やはり音はくっきりしていてきれいです。しっかりと揺らします。でも誰かの生まれ変わりだとしても19世紀的なルバートとは違います。少なくともコルトーのような伸縮ではありません。パレチニらに聞かれる伝統的なポーランドのショパン解釈だとするのもちょっと違うでしょう。微妙に遅くしたり速くしたりで、遅くする一方の表現をする人が多い中で個性的です。落ち着きを求め、浸りたい人には向かないと思うけど、とても十二歳とは思えない表現者です。 第三楽章は多少前のめりで、相変わらず輪郭の立った音で快調に進めます。かなり思い切って強弱を付けているけど嫌みではありません。速いところでも抑揚が付き、この楽章らしい弾んだ感じが出ています。ゆっくり静かに持って行く部分とのコントラストが活きます。 1984年のメロディアの録音です。音はピアノについてはくっきりとしており、弦は多少ドライで前に出るながら、オーケストラの音も良いです。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Eldar Nebolsin (pf) ♥♥ Vladimir Askenazy Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 エルダー・ネボルシン(ピアノ)♥♥ ウラディーミル・アシュケナージ / ベルリン・ドイツ交響楽団 エルダー・ネボルシンは1974年生まれのロシアのピアニストで、スペインで学んだ人です。特別癖がないニュートラルな表現が魅力的な、主観性を排した演奏です。エッジが立ち過ぎす、やわらかく飲み込まれ過ぎもしないタッチで、純粋に音の構築物としてありのままに音楽を聞いている心地良さがあります。前にも言ったけど、それを蒸留水と表現すると味のない意味になり、真水と言うと政治絡みになり、ミネラル・ウォーターみたいと呼ばれて喜ぶ人もいないの困ります。良い意味で言いたいわけなので、おいしい湧水とでもしておきましょう。ショパンだからといって伝統的なルバートを試みたりはせず、繊細な味わいがあるのです。 ネボルシンは実はこの曲を二回録音しています。これは1994年(十九歳時)の最初のデッカ録音で、十五年後の2009年(三十四歳時)にはナクソスからも出しています(アントニ・ヴィト/ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団)。ただ、両端の楽章での解釈はさほど変わっていないものの、新盤の方はピアノの艶の出方が多少違ってしっとりめになり、第二楽章ではより表現が大きくなっています。各部のためと、次の小節に入る前で置く間が大きく、テンポも若干遅くなっているようです。嫌みはないし、個々のフレーズは相変わらず揺らさずストレートではあります。したがってそれだけ聞いている限り不自然さは感じず、人によってはそちらの方がむしろ鮮やかに聞こえるかもしれません。でもあの純粋な湧水のような魅力はやはり旧盤の方があると感じました。トリフォノフが新盤で表情を付けようと試みたのと同じ構図です。ですのでここではデッカの旧盤の方のみを取り上げることにしました。 第一楽章は癖のないクリアな入りで、途中から速度を落としますが揺らしはあまりありません。ピアノの音が大変きれいです。ゆっくり歌うところも清潔で、これといった個性は感じないけど洗練されているのが個性という感じです。 同じようにすっきりとした演奏でも、ベレゾフスキより多少遅い表現に寄っています。 第二楽章は実に心地が良い中庸の、ややさらっとめのテンポで入ります。弱音が印象的であり、デリケートな強弱を付けるものの素直な表情です。個人的にラヴェルなどはあまり個性を出さずにさらっと弾いてほしい気がしますが、このショパンでもそうされてみると美しいということが分かります。軽くて胃にもたれず、あっさりだけど素材の味がする健康な料理のようです。人によっては淡白過ぎると感じるでしょうか。 第三楽章はあまり速くは流さず、粒立ちの良い美音が生きるようにくっきりと弾きます。リズムも感じます。純粋な音の喜びに浸れる運びと言えるでしょう。 1974年のデッカの録音です。ピアノが澄んでくっきりとした美音です。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Gyorgy Cziffra (pf) ♥ Wojciech Rajski Polish Chamber Philharmonic Orchestra ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ダニール・トリフォノフ(ピアノ)♥ ヴォイチェフ・ライスキ / ポーランド室内フィルハーモニー管弦楽団 オーケストラで演奏してる知り合いにピアニストは誰がいいか聞いたらトリフォノフだと言うのです。1991年生まれのロシアのピアニストで、チャイコフスキー・コンクールで優勝しました。ひょっとして見た目なんかも関係あるのかなと失礼ながら思っていると、髭生やした後はかっこいい、それがない若いときはオタクっぽいなどと言います。ショパンの1番の演奏について聞くと、最初のショパン・コンクールでの実況のやつがルックスに反して一番良かったとのことでした。三種類あるのです。その実況盤(2010/トリフォノフは3位で、1位はアヴデーエワ)と、その後すぐに録音した弦楽合奏版(2010/ここで取り上げます)、そしてドイツ・グラモフォンから後で出したもの(2017/プレトニョフのオーケストレーション)です。 感想としては、一番前のめりで熱くなっており、表現はシンプルというのが最初のコンペティション・ファイナルの演奏で、確かに魅力があります。気迫のある運びを評価基準にしているならその盤になるでしょう。その次の弦楽合奏版はほぼその表現を引き継いだ形ながら前のめりさ、熱さが落ち着いた感じです。新しい録音の方はどうでしょうか。髭を生やしてみるのと同じように表現も変えて自分らしさを模索したのでしょうか、前二者とは違って少し派手な方へ進んでいます。個人的な好みからすると後退しました。 基本は素直な感性の持ち主なのだと思います。幾分内向的な感じもあり、繊細で女性的というのか、ばりばりと押して来るタイプではなさそうです。その真面目な性質には好感が持てます。ただ DG の新盤になると、よりゆっくりで個々のフレーズに表情を加えるようになって来るわけです。以前取り上げたラフマニノフの2番も同様の推 移です。特に第二楽章ではもっと弱音に寄せ、大変ゆっくりであり、間も大きく取って思わせぶりな感じがします。それはちょっとツィマーマンの新盤のようでもあります。ピアニストも個性のある顔を看板にしなければばらないので大変です。元々が真っ直ぐだと、後から表情を付けるには苦労があるのではないでしょうか。録音が一番良いのは新盤なので個人的には複雑だけど、また変わって行くだろうとも思います。それにツィマーマンは大人気なわけで、その新盤も思い入れのある演奏が好みな方にはうれしいでしょう。あざといショーマンではないところは好きです。 そして上に写真を掲げた弦楽合奏版の方です。色々出ている室内楽版の中では最もオーケストラ版に近い音の構成で、ただ響きが室内楽という感じになっていて魅力的です。ショパンのこの曲はこういう風にこぢんまりとしてた方がいいんじゃないかとも思います。落ち着いていて品が良く、少し俯き加減のきれいな演奏であることがこの盤の良いところです。さらっと流れてやわらかく、繊細でほとんど癖がありません。 第一楽章はオーソドックスな入りで、輝き過ぎないピアノの音が美しいです。表情は清潔で落ち着きがあります。弱音が繊細であり、スローなパートはかなりゆったりで内向きながら湿っぽくはなりません。間と浮き沈みの脈動があり、ことさら特徴のある弾き方でもないけれども、そのぎりぎりの均整美が良いのです。 第二楽章は弱音で少しだけ歩調を緩めるデリケートなところがあり、静けさを感じます。穏やかに自分に向かって語る感じです。少し夢の中にいるような感触もあるでしょうか。やわらかくて内側から上品な艶が出る音はファツィオリなのでしょうか。はらはらと舞い降りる音型の部分では、ためらいつつ流される木の葉のように音が偏って遅れます。瞬間的なイネガル奏法のように二つ組で間を空けながら揺らしているのです。こういう表情は後に彼がより強調することになります。でもこのぐらいのバランスに抑える方が好みです。また、消え入るような音の連なりにも揺れが加わっていて大変美しいです。それを逡巡するようできれいだと言ったら変かもしれないけど、なかなかのロマンチストです。 第三楽章は繰り返しの強弱でリズムを取り、室内楽的な伴奏に合わせた落ち着いた運びです。 2010年の録音で、レーベルはポーランドのダックス・レコーディングです。ややオフで残響が抑えられ気味のバランスですが、やわらかくて室内楽らしい味わいがあります。ピアノの音はしっとりしていて独特のきれいさがあります。  Chopin Piano Concerto No.1 op.11 Jan Lisiecki (pf) Haward Shelley Sinfonia Varsovia ショパン / ピアノ協奏曲第1番 op.11 ヤン・リシエツキ(ピアノ) ハワード・シェリー / シンフォニア・ヴァルソヴィア 神童と騒がれた人で、録音時の年齢十三歳という新人のデビュー・アルバムです。1995年生まれのヤン・リシエツキはポーランド系カナダ人ということで、ショパンは期待されますし、実際この CD は「ショパンと彼のヨーロッパ」音楽祭での一場面です。現在はドイツ・グラモフォンと専属契約しているそうです。写真を検索すると、ハリー・ポッターの少年役もいつの間にか大人になってた、という感じの青年の姿になっています。 堂々たる表情の大きさと揺らしがあり、予備知識なしで聞いたら十三歳だとは誰も思わないでしょう。音楽の才能は年齢に関係ないことのまた一つの実証例でしょう。ショパンも二十歳でこの曲を作ったのだし、こういう若さ溢れる演奏の方がそれらしいのかもしれません。この後サービス精神をより発揮させて大胆な方へ行く人か、若者らしいロマンティックな抑揚を抑え、即興的な複雑さを開拓して行く人かは今のところ分かりません。それとも崩しの形が似ていなくもない同じポーランドの大御所、パレチニのように熱いショパンの大家になるのでしょうか。 数の上で言えば年齢と共に表現が大きくなって行く一般的傾向がある気はします。いい演奏家になってほしいと思います。 第一楽章はショパンのルバートと呼んでよいのでしょうか。テンポとディナーミクに揺らぎを加えますが、突飛なものではありません。 歌の第二楽章ですが、テンポは最初遅い方で、ためが大きめです。夢見心地の運びでたっぷりとした表情ながらも軽さがあります。思い込みの靄の中に沈んでいるわけではありません。途中からテンポが速まると揺れが出 て、自在な表情を見せるようになります。ポーランド流のショパンの動かし方であり、フランソワやボレットのように不思議なリズム感で幻惑するものではありません。四分の三ほど行ったところでの区切りのチャイムは大変遅く弾き、水琴窟のようで驚きます。でも全体には恣意的になる境界の内側であり、嫌味は感じません。駈けるパッセージも一音ずつ音の輪郭が立っており、かと思うとふわっとやわらかく緩めるなど、表情豊かです。若さがあって清潔で、病的な感じは全くしません。 第三楽章は間の取り方とスタッカートによって驚きの跳ねを見せるところから始まります。個性を出そうとする試みで、この遊びのフレーズにはびっくりしました。面白いし、乗れなくもありません。アシュケナージも面白かったから、どこかにこうする根拠があるのかもしれません。グールドほどエキセントリックではなく、バッケッティの天然のリズム感覚とも違うようだけど、軽くて良いです。ほぼ同じ世代、四つ上のトリフォノフの強調の仕方と比べてみると何か共通点が見つかるでしょうか。 2008年 NIFC(ポーランド・ショパン協会のレーベル)の録音です。ここは同じデザインのジャケットで違う弾き手の録音をたくさん出しています。音は新しいだけに破綻がありません。指揮者はピアニストのハワード・シェリーで、ラフマニノフやモーツァルトで素晴らしい演奏を披露してくれていたのでこの曲も聞きたかったですが、残念ながらピアニストとしては出していないようです。カップリングは2番の協奏曲です。やはり同じ音楽祭でのライヴ収録です。 INDEX |