|
サン=サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」
クラシックの入門曲15  取り上げる CD 20枚: ミュンシュ/オーマンディ ’62/アンセルメ/マルティノン/メータ ’70/フレモー/デ・ワールト ’74/バレンボイム /バーンスタイン/カラヤン/デュトワ/小澤/クラウス・ペーター・フロール/レヴァイン/プレートル ’90/ミュンフン/グザヴィエ=ロト /マルツィオ・コンティ/ヤンソンス ’19/カントロフ CD 評はこちら(サン=サーンスの人物と曲の解説を飛ばします) サン=サーンスの最も有名な曲について演奏を聞き比べてみましょう。交響曲第3番「オルガン付き」です。でも最も有名なのは、むしろ「白鳥」(パロディ音楽「動物の謝肉祭」〜)の方でしょうか。夢見るようにやすらかで、少し哀しみも混じったりするこれ以上ない見事な旋律にうっとりします。どうしたらこんな曲が作れるのでしょう。他にも「序奏とロンド・カプリチオーソ」というのもこの人の作品でよく演奏されます。ジプシーのヴァイオリン協奏曲、みたいなやつです。そして、それぐらいかもしれません。クラシック音楽がかなり好きな人なら、他にもヴァイオリン協奏曲の3番やピアノ協奏曲の2番、チェロ協奏曲なんかを聞かれるかもしれませんし、断片のような作品のいくつかや交響詩、プルーストが好きだったヴァイオリン・ソナタ、個々の楽器をやる人にとっては馴染みの深い晩年の傑作三つ(オーボエ/クラリネット/バスーンの各ソナタ)、それにオペラ・ファンの方には「サムソンとデリラ」もあるかもしれませんが、ちょっと好き、ぐらいの愛好家だとなかなかそこまで深堀りもしないんじゃないでしょうか。たくさん作った人なので一発屋というつもりもないけれど、サン=サーンスという作曲家、受け止められ方としてはベルリオーズやフランクと並んで、ちょっとそんな気配はあります。 クラシックの入門曲 この「オルガン付き」というニックネームは、文字通り曲にパイプ・オルガンが加わっているからです。あまり言われないけど、他にもピアノまでもが付いています。サン=サーンスはピアニストでもあり、その後弾かなくなったものの教会のオルガン奏者だったこともあるわけで、この人の要素が全部詰まっています。「この曲には私が注ぎ込める全てを注ぎ込んだ」と本人も述べているほどの自信作なのです。最盛期の頂点の作品、とも言われます。3管編成でかなり人数が多い上に、そんな変則楽器のおまけまであるのです。大規模なオーケストラは華やかな響きであり、クラシックの入門曲としても相応しいものです。ここでタイトルに「入門曲」と付けたのもそんな理由からです。それに加えて何より大変きれいなメロディーが堪能できます。緩徐楽章に当たる部分は「惑星」の木星に一瞬似ていなくもない感じで、クラシックの静かなオーケストラ曲の中でも一、二を争う美しさだと思います。 オーディオ・チェック用? もう一つ。パイプオルガンは大変低い音まで出ます。スコアで確認したところ、この曲では音程で C1、32.7ヘルツぐらいまでの音が聞けます。オルガンのパートは最後の部分にもありますが、目立つのは第二楽章に当たる(実際は構成上第一楽章の後半部)静かな部分です。音響装置が再生できれば部屋を震わすような音になるでしょう。集合住宅にお住まいの方には難しい上に、本来の楽譜通りならそこまで大音量にもならないわけだし、曲の本質にも関係ないのですが。ただ、こんな風に重低音が聞けるシンフォニーとなると、他に有名なところではこの二十年後のマーラーの第8 (1906) や二十九年後に作曲されたリヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲 (1915) があるぐらいではないでしょうか(オーケストラ作品全般に広げるなら「ツァラトゥストラ (1896)」や「惑星 (1917)」、「ローマの松 (1924)」もあります。重低音ではなく、ただオルガンが活躍するものならさらに前の時代からも存在します)。したがってサン=サーンスのこの曲はその意味ではパイオニアだったと言え、現代ではよくオーディオ・チェック用だなどとも言われて来ました。今やオーディオ店も軒並み閉業し、この分野に興味のある人はすでに絶滅危惧種になっていますが、ビリビリと窓が鳴るのを楽しむ人もいるというわけです。 ただ、実際にそれを味わうのはそれなりに大変ではあります。30センチ口径ぐらいの大きめのユニットが付いた高価なスタジオ・モニターでも50ヘルツまでしかフラットに出していないものが多いわけで、蜜柑箱ぐらいの一般的なブックシェルフ型のスピーカーではそれ以下はよく聞こえないからです。このレポートではどの CD で低い音が出ているか後で述べますが、確認しているスピーカーは何とかそこまで聞こえるものを使っています。35ヘルツぐらいまではほぼほぼフラットで、共鳴器と部屋の反射も加勢してながら30ヘルツでも発振器の入力があまり下がらずに聞こえるレベルは維持しています。別に自慢してるのではなく、何かしらの工夫をしないと普通は C1 などの音程はなかなか難しいというお話です。置き方として推奨はしませんが、スピーカを地べたのコーナーに設置すれば比較的低い方まで出せるかもしれません。質はともかくとして安価な別付けのサブ・ウーファーという装置も存在します。 余談ながら、理想としてはどこまでの低音再生を求めるべきかという話なら、オルガンは楽器としては16ヘルツぐらいまで出ます。こうした超低音を聞くとお化けが見えるって話がここのところ都市伝説の野火みたいに広がってるけど、最近になって日没後に車内に黄色い電球を灯した江若鉄道の二両編成が琵琶湖のほとりを走ってるのをサンダーバードの車窓から見た知人がいます。後で調べて線名分かったんで先入観じゃないんです。廃線電車の幽霊って、誰の想いで化けてるんでしょう。低音再生、チャレンジしてみてください。でも20ヘルツ以下は可聴帯域外で、教会のように頑丈な建物の中で大きな音で響かせれば地震が来たかと思うような圧迫感になるようではあるものの、20ですらスピーカーからの音量を上げてもパタパタという機械振動しか感じません。現代音楽にそういう低いのがあるかどうかは知らないけれども、楽音としてはこのサン=サーンスの32ヘルツぐらいが最低でしょう。あとはグランカッサ(大太鼓)のドスンという音かチャイコフスキーの大砲ぐらい。実際に人が重低音と感じるのは50ヘルツから下、30ヘルツまでの間なので、30が聞こえていれば全くもって上等ということになります。 サン=サーンスについて 作曲家カミーユ・サン=サーンスは1835年、パリのど真ん中、ノートルダム寺院のあるシテ島南側のカル チェ・ラタン地区に生まれたフランスの作曲家です。ブラームスの二つ下なので、区分としてはロマン派の時代。同じフランスで言うならベルリオーズと印象派のちょうど真ん中あたりという世代です。近いところではフランクが十三歳下で、門下生で本人がその一家の世話にもなったフォーレよりは十歳年上になります。印象派に寄った作風の作品が全くないわけではないものの、新古典派と呼ばれるブラームス同様保守的なところがあり、交響曲、協奏曲といった、以前からドイツの伝統であった形式をフランス人ながら踏襲して作曲し、晩年は特に新しい音楽に対して批判的でした。理論によって成立する新ウィーン楽派の無調音列音楽に対して「経験の自然な表現を妨げている」として反発したのは分かるとしても、印象派音楽やストラヴィンスキーに対しても辛辣な言葉を残しました。学者の先生方(茶化した言い方でしょうか)が技法的な意味からこのサン=サーンスの作曲家としてのあり方を議論しようとすると、喧々諤々というのか、論文を読むのも大変なぐらい込み入った表現になってしまうようです。したがって専門的な部分にはここでは能力不足で踏み込むことが出来ません。全てあくまでも感性的な話です。 どんな人だったのでしょうか。人生前半戦で言われるのはまず、大変な神童だったということです。この世界、神童は掃いて捨てるほどいるけれども、三歳で作曲したというのは早過ぎるでしょう。五歳になるとピアノ演奏を披露しました。才能があったのは実は音楽だけではなく、分筆・学問にも優れた能力を発揮したようです。詩人とも言えるし、後年は評論家でもありました。天文学にも明るかったようです。それならば例によって発達障害的な性質があったかというと、別段そうは言われていません。あるいはそうだったかもしれないし、違うかもしれません。 作風は? ただ、この人の音楽を聞いているとちょっと感じることはあります。それを「誇大」と言うと批判的になりますから、どうしたものでしょう。音楽用語で「グランディオース」としておきましょうか。その語だと心理学的な用法もある一方で、「壮麗な」というポジティブな意味にもなります。確かに、サン=サーンスには壮麗な感じがするところがあると思います。それを「自分を大きく見せる効果に関心がある」と補足すると「誇大」の意味になってしまうわけです。 元気で華々しい音楽という意味では、金管が炸裂すればみんなそれなりに聞こえてしまいますから、ブルックナーだってフランクだって、ワーグナーはもちろんシベリウスだって誇大と言えます。ただ、面白いのはこの人、作曲家ではシューマン、メンデルスゾーン、リストなどが好きであり、影響を受けていた、とされることです。この三人に共通する資質って、何なのでしょうか。見方は色々なので、そっとしておきましょう。そして擁護者としては複雑な立場をとったけど、やはりワーグナーにも心情的にはかなり熱烈に惹き付けられていたところがあったようです。作風には影響を受けなかったので、これは後で述べるような意味での純粋に気質の問題かもしれません。ちょっと考えさせられるところではあります。作曲家として当のサン=サーンスに最低限当てはまることとしては、効果を使うことが上手な職人だったとは言えるでしょう。作曲技法において「職人的」だというのは(具体的にどの手法かはともかくとして)実際によく指摘されていることです。 以上のことを勝手にキャッチフレーズのようにまとめさせていただくならば、「映画音楽とオッフェンバックになる作曲家」というのはどうでしょう。片方には映画のワンシーンのようにメロディアスで美しい部分があります。なんせこの作曲家、世界初の、もしくはそれに近い、映画音楽の製作者(「ギーズ公の暗殺」1908)なのです。元々雰囲気を盛り上げる職人の技があります。この交響曲第3番でも最初の楽章(第一楽章に当たる前半のアダージョと後半のポコ・アダージョ)は映画のようでうっとりさせられます。一方で第二楽章のアレグロやプレストは賑やかで、壮麗です。オッフェンバックと言えば、あの運動会の定番「天国と地獄」の人です。でもそう評するのは実はオリジナルの発想ではなくて、「バッハのように始まり、オッフェンバックのように終わる」と、あるピアニストが協奏曲の第2番についてすでに語っているのです(論者ジグムント・ストヨフスキは曲調のみでなく、恐らくは技法の意味で懐古的な手法とロマンティック/モダンな作法への二極分解に陥るこの作曲家独特の傾向について語ったのでしょう)。因みに「映画音楽や運動会のよう」が肯定的か否定的かと言えば、この時点では性質を語っているだけで、どちらでもありません。個人的には「オルガン付き」は大変気に入っています。 でも、演出効果に熟達していて壮麗なことから、「内側のインスピレーションによる作曲ではない」などと言い出す人もあったようです。皮相的(superficial)というような言葉遣いをする人もいますが、それは評価的に過ぎるでしょう。サン=サーンス自身、「芸術は美と個性を創造しようとすることであって、情感(feeling /sensibilité)はただ後からついて来るものだ。そして芸術はそれがなくても上手くやれるし、むしろその方がいい」などと言っています。形を作れば感情は後からついて来る、と言っているようにも読めます。この言い方は、ちょっとシニカルに構えて明晰に論評してみせるフランス文化の伝統なのでしょうか。それがラヴェルだったら照れ隠しでしょう。でもひょっとしたらこの作曲家の場合は、いくばくか素の性質を表しているのかもしれません。 外向者? 心理学的に見るなら、こういうのは果たしてどう表現できるんだろう。作曲において、形式を重んじて「情感(感受性)は後からついて来る」というのは「外向的」な資質に思えます。これは有名な心理学者であるユングの性格区分で、彼は人の気質をまず大きく二つに分けました。外向と内向です。ちょっと分かり難い概念です。外向といっても、パーティ・アニマル(パリピ)の外交・社交的な人、というのと全く同じ意味ではありません。人付き合いがいい方の意味の外「交」的は英語だとソーシャブルでしょうか。一方、こちらの外向/内向はイクストラヴァート/イントラヴァートと言います。外向者というのは世にある知識に精通し、考えに客観性があり、他者の注意を引きつけることに関心のある性質の人であり、行動面で付き合いがいいかどうかはともかく、他人からどう見えるかという評価を気にします。価値基準が外側の世界にあるわけです。ブランド志向などというのは外向者の特徴ということになります。一方で内向者はその反対で、自分の内側の基準に従って行動し、内なる感情と直感を重視し、他人の目は気にしないタイプです。昨今はむしろ現象面である「社交的/内気」の軸に重点を置いて言われがちになっては来ているけれども、元々はそういう、気質の核となる原理のことでした。これをユングは生れながらの傾向で一生変わることがないと考えていたのです。本当にそうかどうかは分かりません。そもそも外向内向と言ったって、一人の人間の中に両方あるわけで、昔は進化論のダーウィンを外向者側に分類する学者がいたけど、最近は反対に内向者だと言う人もいます。でも、サン=サーンスの興味が外に向かっていた、などと言うとなんだか妙に説得力があります。追い詰められると激昂してアクティング・アウト(外への攻撃)の方へ向かい、物を壊すなど、かなり乱暴になったこともあったようです。それは心臓に負担もかかるけど、この人は精神的に壊れると心身症状など、解離性の側へと倒れるタイプだったのでしょうか。外ばかり見る人をヒューズが溶けるようにして休ませ、自らを守るために内側の不調和に否が応でも気づかせる生体の知恵の働きです。いや、これは憶測であって全く分かりません。  私生活
上記以外、個人的生活の上でサン=サーンスの性格を決定づけるような特に変わった報告は少ないようで、学生時代は全てにおいて成績優秀、後にはフォーレなどからは尊敬されました。一つ気づくことと言えば、大変お母さんが好きだったということぐらいでしょうか。動物の本能だし、父権社会では甘やかす役割は母親です。ラテン系、特にイタリア人男性やフランス人男性がマンマやママンが大好きというのは映画にもよく出て来るぐらい普通でしょう。イタリア語にはお母さん子を意味するマモーニという言葉もあるらしい。でもそういう話ではなくて、サン=サーンスが結婚したのは四十歳ぐらいのときでした。それまでの浮いた噂というのもあまりなさそうで、結婚後もお母さんがくっついて来て同居しました。二世帯住宅とかスープが冷めない距離とか、そういう話でもありません。結婚生活は長続きしませんでした。晩婚ですぐ離婚というと学者にありがちなパターンで、フロイトともちょっと似ています。でもこれには気の毒な経緯もあります。その前に二歳の息子が家の窓から落ちて死んでいるのですね。子供を亡くした夫婦の離婚率が高いことはよく知られています。ただ、サン=サーンスの場合は彼の側がそのことで妻を責めたようです。そして別れ方にも特徴があります。二人で行った旅行先でホテルからいなくなり、もう戻らないという手紙を奥さんに届けさせ、以後死ぬまで会わなかったということです。離婚手続きはしなかったらしく、ただ完全黙殺。直接は言えなかっただけかもしれません。お母さんとは以後もずっと仲が良かったようで、その後の彼には女性の噂も出ませんでした。こんなことからまたまたゲイだったという見方もあるようですが、根拠はありません。生涯会わなかったのは事実だけれども、奥さんの方は彼の埋葬の際、片隅で人知れずヴェールを被り、ひっそりと参列していたということです。 その他では、シニカルで痛烈な批判をする人だったということは言われています。また、大変な旅行好きだったようで、子供のことを引きずっていたからとか、何かから逃避したかったからとは言わずとも、晩年でも内側を見つめてじっとしていたという風ではなさそうであり、しょっちゅう旅行していて出ずっぱりだったようです。亡くなったときも海外旅行の最中(アルジェ)でした。心臓発作でした。死の年にそのアフリカで書かれたオーボエ、クラリネット、バスーンの各ソナタなどのように、本当の白鳥の歌はこちらという、澄んだ響きでしんみりとした心情を感じさせる曲も確かにあります。それらはとても皮相的な作品とは呼べない名作です。でもそれ以外の多くの曲には派手な効果を見せるかのようなパートが存在しているのも事実でしょう。そして旅行魔という特徴的な行動パターンが作品と共に気質を表していたかどうかはともかく、外の世界に興味があって動き回るのが好きであり、またそういうことが気晴らしになる人だったということは言えると思います。 楽曲構成など 最も有名で大変聞きやすい名曲である交響曲第3番ハ短調 op.78 はサン=サーンスが1886年、五十一歳という熟年期(八十六歳まで存命)に作られた、曲想、構成ともにこの作曲家を代表する作品です。 二楽章から成りますが、内容としては伝統的な四楽章構成とも言えるもので、それぞれの楽章が二つのパートに分かれています。第一楽章第一部がアダージョ/アレグロ・モデラート、第二部がポコ・アダージョ、第二楽章第一部がアレグロ・モデラート/プレスト、第二部がマエストーソ/アレグロとなっています。出だしは静かで少し盛り上がり、第二楽章に当たるポコ・アダージョが来て、スケルツォの楽章に相当する部分があり、最後が華々しいフィナーレとなります。前半のゆったりした部分は映画の一場面を見るように美しく、フィナーレは大変賑やかです。音楽に美しさを求める人は第一楽章、迫力のようなものを求める人は第二楽章という具合に、くっきりと分けられた造りだとも言えるでしょう。 そのきれいな旋律に溢れた最初の楽章ですが、夢見るような導入の後、グレゴリオ聖歌の「怒りの日」(ディエ ス・イレ)をモチーフにした最初の主題が現れます。怒りの日というとレクイエムなどでも有名ながら、交響曲への導入としてはベルリオーズの幻想交響曲があります。それは最後の楽章で、以前水戸黄門の行進のようだなどとうっかり書いてしまいました。そのベルリオーズでは、♯や♭が最も少ないイ短調にしますと: ドーシードーラーシーソーラーラー/ドードーレードーシーラーソーシードーシー/ララ、という部分です。一方このサン=サーンスの「オルガン付き」では: ドド・シシ・ドド/ララ・シシ・ドド/ミミ・♯レ♯レ・レレ/ドド・シシ・ドド/ララ・ドド・シシ/ララ・♯ソ ♯ソという、弦楽によるさざ波のような音形となります。こうした部分などで半拍遅れて行くやまびこのような構造がじゃまくさくて嫌いだと、オーケストラの知人が言っていました。確かに一流のプロであってもちょっとグズグズっとなりかかってるような演奏がないわけでもありません。弾き難いのでしょう。そしてその次に出て来る主題が、ミーファ・ミーラ・シーミ/ミードォーシ/ラァー♯ソ、というものになりますが、ここを聞くとやはりベルリオーズ同様、どうしても時代劇のオープニング・テーマのつなぎ部分のように聞こえてしまいます。お侍さんがカツラを被って刀を差し、肩で風を切って歩く姿が浮かんで来て仕方がないのです。テナー・サックスかチューバなんかでもったいぶってやられたら、う、上さま、お許しを、となってしまいます。今どき時代劇なんて言っても分かってもらえないでしょうか。やってるのは大河ドラマぐらいでしょう。詳しくないのでそのテーマ曲が昔ながらかどうかも分かりません。でもフランスものだから、ねえお洒落じゃない、とか、そういうのを期待するとちょっと外れるかも、ということです。そして似た形の音型で調性を変える二段構えの不思議な移行をして、次の緩徐楽章の部分に入ります。 後半のポコ・アダージョは牧歌的で夢見るような変ニ長調で、上では惑星の木星にも似てると言いましたが、 ちょっとマーラーの緩徐楽章みたいにここだけ取り出してもいいほど美しい部分です。また、包み込むようなオルガンの低音が心地良い部分でもあります。ただ、「オルガン付き」とわざわざ断っているものの、オルガンが独自のメロディー・ラインを受け持って活躍する種類だとは言えないところもあり、有名なオルガニストにやってほしいかもしれないけれども、案外演奏そのものについては誰であるかが気にならない一面もあります。楽章としては最後の部分こそがオルガンが前面に出るところで、そこですら楽器自体やストップの設定の方に目が行くのです。この楽章ではもっぱら重低音の出方が気になります。 第二楽章になると、最初に幾分ベートーヴェンの第7シンフォニーみたいなスケルツォが来て、後半が第四楽章に当たるフィナーレとなります。フィナーレは晴れやかで、「グランディオーソ」な感じです。オルガンの重厚な咆哮によって始まり、ラストはド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドと順にゆっくりと上昇して行き、ゴール達成、という感じでパーティー・クラッカーが紙吹雪を散らすように華々しく終わります。録音によってはきつくて個人的にはこの最後だけやめてほしいことがあるほどですが、荘厳に感じられて全然大丈夫な演奏もあります。こんな嗜好の者が解説するのもどうかとは思います。でも前述のようにこの曲、オルガンの重低音も聞けてオーディオもチェックでき、何より大変きれいなので、初めてで大好きになるかもしれません。 CDとフォーマットについて 名曲だけにたくさん出ています。全部は挙げることすら難しいので、有名なもの、人気がありそうなもの、そして自分で聞いて良かったものを取り上げます。♡の有無や数については、今回は特に録音の良し悪しに左右されているかもしれません。曲の性質もあるのかどうか、運びの精神性というよりも楽音の美しさの方に魅力を感じがちなようです。 オーディオ的楽しみもある曲ですが、音質について言及している SACD ハイブリッド盤については、CD レイヤーでの比較です。その理由については他のところでも述べましたし、余分な説明でもありますが、もう一度簡 単に触れておきたいと思います。必要なければ飛ばしてください: CD と SACD が一台で切り替えて再生できるプレイヤーにおいて SACD の方が滑らかで情報量が豊かに感じることが多い現象は体験済みなものの、そう作っている場合もある上に、元が機械ごと変わればその評価は逆転することがあります。自然な音の SACD プレーヤーを探してはいないのでフォーマット自体の優劣は分かりませんが、多少でも生に近づいたプレゼンスに感じる場合、それは記録容量の差から来ることではありません。録音の良さはトーンマイスターなどとも言われる録音プロデューサーやバランス・エンジニアなどの仕事によって決まります。それは物理特性ではなくてバランスの問題なのです。したがって CD で十分確認できます。また、再生のクオリティだけ見ても、SACD の規格の優秀さであるダイナミックレンジが大き過ぎても、可聴周波数外まで再生できても実際に聞く際にはほとんど意味がなく、むしろサンプリングの目の細かさの方こそが大切になります。しかしいくらそれが細密であっても再生機器側で歪曲(色付け)が加わる要素が多過ぎ、また、過渡特性がそこまで追いつかずに潰れる場合も多いはずです。不思議なことに、再生音というものは理論上違いが全く再現できないはずのものであっても音色の差を感じることはあります。でもここではそんなオーディオ論議は無視し、主に上記のような理由から CD フォーマットで比較しているのです。加えてオンラインが常識となっている昨今は CD ですら存立が危ぶまれている状況ですから、SACD が将来エルカセットやレーザーディスク、ベータマックスや MD の運命を辿らないという保証はなく、このページでは基本的に扱わないようにしています。消える前に最後に残っているフィジカル・メディアは CD だと思います。もちろんハイ・リゾリューションや SACD が情報量で CD より優れていることは間違いないので、その方が満足行く再生環境をお持ちの方が SACD を買われることに対して否定的な考えではありません。それと、CD の中には盤を購入せず、DA コンバーターを含めて同じ環境でオンラインで確認しているものもここ最近は多数あることをお断りしておきます。誰でも買う前に自分で確かめることができる時代が来ました。 出ている録音 現在出ているもので主だった演奏を録音年度順に掲げてみます(実際はもっとあります): シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団/1959 RCA ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団/1962 Columbia エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団/1962 Decca ジョルジュ・プレートル/パリ音楽院管弦楽団/1964 EMI ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団/1970 Erato ズービン・メータ/ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団/1970 Decca ルイ・フレモー/バーミンガム市交響楽団/1972 EMI エド・デ・ワールト/ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団/1974 Philips ダニエル・バレンボイム/シカゴ交響楽団/1975 DG ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団/1975 EMI レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック/1976 Sony ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団/1980 Telarc ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/1981 DG シャルル・デュトワ/モントリオール交響楽団/1982 Decca エド・デ・ワールト/サンフランシスコ交響楽団/1984 Philips 小澤征爾/フランス国立管弦楽団/1985 EMI クラウス・ペーター・フロール/ベルリン交響楽団/1986 Schallplatten ジェイムズ・レヴァイン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/1986 DG スティーヴン・ガンゼンハウザー/スロヴァキア放送交響楽団/1988 Naxos ジョルジュ・プレートル/ウィーン交響楽団/1990 Erato クリスティアン・バデア/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団/1990 Telarc チョン・ミュンフン/パリ・バスティーユ管弦楽団/1991 DG エマニュエル・クリヴィヌ/リヨン国立管弦楽団/1991 Denon ロリン・マゼール/ピッツバーグ交響楽団/1993 Sony マリス・ヤンソンス/オスロ・フィルハーモニー管弦楽団/1994 EMI ミシェル・プラッソン/トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団/1995 EMI ズービン・メータ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/1995 Teldec クリストフ・エッシェンバッハ/フィラデルフィア管弦楽団/2006 Ondine フランソワ=グザヴィエ・ロト/レ・シエクル/2010 HMF レナード・スラトキン/フランス国立リヨン管弦楽団/2013 Naxos マルク・スーストロ/マルメ交響楽団/2013 Naxos マイケル・スターン/カンザス・シティ交響楽団/2013 Reference マルツィオ・コンティ/オヴィエド・フィラルモニア/2014 Acasia Classics ヤニック・ネゼ=セガン/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/2014 LPO マリス・ヤンソンス/バイエルン放送交響楽団/2019 BR Klassic ジャン=ジャック・カントロフ/リエージュ王立フィルハーモニー管弦楽団/2020 BIS クリステャン・マチェラル/フランス国立管弦楽団/2020 Warner 重低音盤 録音が優秀かどうかということとは関係ないので子供っぽい話かもしれませんが、この中でオルガンの重低音 (30〜40ヘルツ台)がボリューム(音圧レベル)の上でもほどほどに出ているものを列挙すると: シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団/1959 RCA エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団/1962 Decca ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団/1962 Columbia ジョルジュ・プレートル/パリ音楽院管弦楽団/1964 EMI ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団/1970 Erato ルイ・フレモー/バーミンガム市交響楽団/1972 EMI エド・デ・ワールト/ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団/1974 Philips ダニエル・バレンボイム/シカゴ交響楽団/1975 DG レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック/1976 Sony ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団/1980 Telarc エド・デ・ワールト/サンフランシスコ交響楽団/1984 Philips 小澤征爾/フランス国立管弦楽団/1985 EMI クリスティアン・バデア/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団/1990 Telarc チョン・ミュンフン/パリ・バスティーユ管弦楽団/1991 DG マゼール/ピッツバーグ交響楽団/1993 Sony フランソワ=グザヴィエ・ロト/レ・シエクル/2010 HMF レナード・スラトキン/フランス国立リヨン管弦楽団/2013 Naxos マイケル・スターン/カンザス・シティ交響楽団/2013 Reference マルツィオ・コンティ/オヴィエド・フィラルモニア/2014 Acasia Classics マリス・ヤンソンス/バイエルン放送交響楽団/2019 BR Klassic クリステャン・マチェラル/フランス国立管弦楽団/2020 Warner といったところでしょうか。オルガンが活躍する曲ながら、楽器そのものの違いに比べればオルガニストの差は案外感じられ難い曲ではないかということはすでに述べました。音の大きさは録音側の問題でもあるし、奏者で違いがあるとすればフィナーレに当たる楽章の出だしで、ストップ設定によってどれぐらい力強く出るか、ぐらいではないでしょうか。上に掲げたものの重低音については、音程的にはムラがあるものがほとんどです。また、実際には低い方までしっかり出ているけど、音圧が十分とまでは言えないものは省いてあります。ジェイムズ・レヴァイン盤、シャルル・デュトワ盤、クラウス・ペーター・フロール盤などです。どうしても出したければソフトウェア的に3、40ヘルツ近辺を持ち上げる、もしくは音程的に弱いところのみ補正をかけるという方法もありますが、一般的ではないし、邪道でしょう(発売元でのリマスター時には一部で行われている気はしますが)。そしてそもそもがこの部分、楽譜上はピアニシモなのであり、元々「風を感じるほどに地響きを立てて」というのは違うかもしれません。超低域が出る以外で本来の意味で録音の質が高いもの、バランスの良いものについては個々に触れて行きます。 フレンチ・パフォーマンス フランスの音楽だから、フランス人、もしくはフランス文化に関わりのある演奏家/団体によるもので聞きたい、という発想もあるでしょう。実際にフランス的かどうかは不明ですが、その場合だと以下の通りです: シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団/1959 RCA エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団/1962 Decca ジョルジュ・プレートル/パリ音楽院管弦楽団/1964 EMI ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団/1970 Erato ルイ・フレモー/バーミンガム市交響楽団/1972 EMI ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団/1975 EMI シャルル・デュトワ/モントリオール交響楽団/1982 Decca ジョルジュ・プレートル/ウィーン交響楽団/1990 Erato エマニュエル・クリヴィヌ/リヨン国立管弦楽団/1991 Denon チョン・ミュンフン/パリ・バスティーユ管弦楽団/1991 DG ミシェル・プラッソン/トゥールーズ・カピトール国立管弦楽団/1995 EMI フランソワ=グザヴィエ・ロト/レ・シエクル/2010 HMF レナード・スラトキン/フランス国立リヨン管弦楽団/2013 Naxos マルク・スーストロ/マルメ交響楽団/2013 Naxos ジャン=ジャック・カントロフ/リエージュ王立フィルハーモニー管弦楽団/2020 BIS クリステャン・マチェラル/フランス国立管弦楽団/2020 Warner 爆演系? また、「いわゆる爆演系」などと表現する人もいますが、大編成の華麗さや迫力が欲しい、もしくは盛り上がって燃焼している感こそが大切という、振幅が大きめのダイナミックな演奏を好まれる方に高評価かと思われるものは: シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団/1959 RCA ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団/1962 Columbia ズービン・メータ/ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団/1970 Decca ルイ・フレモー/バーミンガム市交響楽団/ 1972 EMI ダニエル・バレンボイム/シカゴ交響楽団/1975 DG レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック/1976 Sony ロリン・マゼール/ピッツバーグ交響楽団/1993 Sony フランソワ=グザヴィエ・ロト/レ・シエクル/2010 HMF ヤニック・ネゼ=セガン/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/2014 LPO といったところが該当するのでしょうか。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Charles Munch Boston Symphony Orchestra Berj Zamkochian (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 シャルル・ミュンシュ / ボストン交響楽団 ベルイ・ザムコヒアン(オルガン) 最初はフランスの指揮者でダイナミックな演奏をすると言われるミュンシュ盤から行きましょう。好みでない方からは大掴みで爆発的、ファンの方からは核心に切り込んで気迫があると評される人かと思います。フランスものではこの四年前にクリュイタンス盤もあったけれども、そちらはモノラルです。ミュンシュはベルリオーズの「幻想交響曲」でも人気の人です。サン=サーンスの「オルガン付き」に関しては、完全にフランスの演奏者であり、かつ迫力もあるという両方の組み合わせを目指す方には残念ながら、これはパリ管ではなく、長く常任指揮者だったボストン・シンフォニーとの演奏です。ミュンシュは19世紀、1891年に独仏の境い目のアルザスに生まれた人で、ドイツ系のフランス人であり、1968年に亡くなっています。指揮者としては「往年の巨匠」と呼ばれるでしょう。 静かな部分でもはやる心を抑えているというのか、やはり燃え上がろうとする勢いをどこかに持っていて、要所で力強さと歯切れの良さを発散させる演奏です。パリ管との「幻想」ほど激しくはないかもしれないし、形の上では整っていて走りもしないものの、エネルギーの点で前へ前へと、フォルテの方へと志向するようなのです。抑揚は大きく付けるところがある一方、弱音に向かって細かにステップを刻む、という方向ではありません。燃焼する感じを大切にされる方にとっては外せない一枚です。 パート別に見てみると、最初はゆったりとしたテンポで音を延ばして入りつつ、オーボエには艶かしいビブラートがかかります。たっぷりとして大変きれいです。第1主題まで来ると、急には速度を上げず、途中から待ち切れなかったように少し速くなろうとしますが、何とか抑えます。強弱に少し急くかのような力強さが感じられ、爆発が後に控えている予感がします。そしてフォルテになると期待通りに元気良く盛り上がり、テンポもより速めとなります。一方でつなぎのフレーズでは表情を抑え、こだわりなく素早く処理して流す場面もあります。 第二楽章に相当する静かなポコ・アダージョは、また出だしこそゆったりめに感じるものの、トータルでは多少軽快な方になるかというテンポ設定であり、さらっと流れて行きます。繊細な弱音へと落とすような手法は用いず、安定してやや大きめの音で淡々と歌って行くものです。 スケルツォでは歯切れよくバシッ、バシッとスタッカート寄りに音を切る場面が聞かれ、思い切りが良い印象で す。 そしてフィナーレの楽章のオルガンの開始も力強いです。ここでは堂々としています。テンポは速くはないもの の、逆にそのまま力を込めていて、十分に壮大です。音の洪水に浸りたい人には気持ちの良い部分だと思います。聞き終えると運動で汗をかいたような満足感が味わえると思います。 録音は1959年のステレオと古いですが、米 RCA の技術は進んでおり、上手にリマスターされているからもあるでしょうが、決して悪くありません。SACD 以外にも、ビル・エヴァンスなどで見事に生のような音を聞かせていた XRCD 仕様も出ています。オーケストラは低音が響くバランスで、弦自体は強くなると艶がある方ではないながら、フォルテで潰れたりはしません。ちょっときつめではあります。金管はバリバリと元気良く弾けます。演奏同様に全体に切れの良い印象を与えるものと言えるでしょう。オルガンの重低音はしっかり出ている方です。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Eugene Ormandy The Philadelphia Orchestra E. Power Biggs (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団 E・パワー・ビッグス(オルガン) これも煌びやかな方に入れられる有名な演奏です。オーマンディは「フィラデルフィア・サウンド」という登録商標のような音で人気がありました。一般には華やかなイメージかと思います。かっちりと区切った拍で生真面目に運んで行くような部分も持っている人の印象ですが、最盛期には元気がありました。それも前へ前へと進んで行こうとするような元気良さではなくて、落ち着いて構えて要所でバシャーンと力強く鳴らすような元気さというのでしょうか。 オーマンディはこの曲が得意であったらしく、何度も録音しています(四回のようです)。そのうち手に入りやすいのはここで取り上げる1962年のコロンビア盤と、デジタルになった80年のテラーク盤(オルガンはマイケル・マレイ)でしょう。それ以外は57年のコロンビア盤で62年と同じオルガン奏者のもの、74年の RCA 盤でバージル・フォックスによるものがあります。62年盤と80年盤では評価が二分されるみたいだけど、比べれば前者は勢いがあり、後者は録音コンディションで勝っていて演奏は少しおとなしいという感じです。リズムの角張り度、ごつごつ感も少なくてよりスムーズです。 どちらがいいということもないけれども、この演奏者が好きな方にとっては元気の良い方、より力強さが感じられる62年盤の方かなと思います。 出だしです。弦の盛り上がる抑揚がはっきりしているという意味で、テラーク盤より濃いかと思います。メリハリもくっきりと付いています。テンポはすごく遅くはないけれども、落ち着いていて実直な感じです。フレーズ一つひとつを独立させて盛り上げ、延び縮みはなく、波打って流れるようでもありません。 緩徐楽章に当たるポコ・アダージョの部分に来ると、フレーズは区切れているけど質はさらっとしているように聞こえます。生真面目なところが感じられ、抑揚表現は割とフラットでしょうか。人によってはちょっとぶつ切れ感を覚えるかもしれません。そうやってメロディーを四角く形にして行く様は、設計図通りきっちり作った鉄骨のガラス張り建物のようであり、敢えて喩えれば、細部まで描かれたアメリカのフォト・リアリズムのようだと言ってもよいかもしれません。 スケルツォに当たる第二楽章の頭の部分ですが、ここも走らずかっちりと行きます。ネジ一本にいたるまで正確にトルク管理されているようです。 続くフィナーレの部分でも走らず、曖昧なところがなくてがっちりしています。力強さは十分で、かといって叩きつけるような荒さでもありません。残響がない分、隙間の風通しも良い感じです。ラストでは少しスピードアップします。隅々まで明快なのが好きな方にはこたえられない演奏だと思います。 1962年のコロンビア録音で、レーベルはソニーです。フィラデルフィア管の本拠地で収録されました。この時期の録音にしては良好なもので、前述の通り残響は少ない方です。オルガンの重低音は出ている方に入ると思います。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Ernest Ansermet Orchestre de la Suisse Romande ♥ Pierre Segond (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団 ♥ ピエール・スゴン(オルガン) この曲の名演として古くから定番化して来た一枚です。フランス語圏スイスに生まれた指揮者アンセルメと、これもフランス語圏ジュネーヴで彼が1918年に設立したオーケストラ、スイス・ロマンド管による演奏です。どちらもスイスですが、フランス文化の香りを期待できるものであり、特にそのオーケストラの木管の音などはフレンチ管独特の華やかな倍音というか、少し鼻にかかった個性的な音色を聞かせます。 エルネスト・アンセルメ(1883-1969)は数学者でもあった人で、正確というのか、明晰で形の崩れのない演奏をします。特にアゴーギク(テンポの揺れ)という意味では真っ直ぐなところがあるかもしれません。前出の オーマンディもテンポを揺らしませんが、でも雰囲気は違います。あちらはもう少しフレーズが角張っていて、所々の拍で間を設けたりする傾向があるでしょうか。かっちりした印象で力強くもあるのですが、同じようなテンポ設定と流れであっても、アンセルメには滑らかさと柔軟性があり、生真面目というよりも、ちょっと華やかなアロマのようなものが加わる気がします。周波数が違って聞こえるのです。この「オルガン付き」でもややゆったりめのテンポで通し、特に変わったことをするでもないですが、この人の美学というのか、独特のきれいさがあります。 楽章ごとに順番に見ますと、出だしはさほどゆっくりではなく聞こえるのですが、そのままの速度を崩さずに続けるので、第一主題からがむしろ幾分遅めのテンポに感じられます。つまり、多くの演奏家が初めだけゆっくりで最初の主題から速めるのに対して、ややゆったりのままで終始リズムが一定なのです。この出だしの例は、全体にもっと遅いですがバーンスタインなど他の一部の指揮者にも見られます(バーンスタインはそこ以外のパートではテンポを動かします)。アンセルメに関しては、正確という意味で例の「数学者」という言葉が浮かびます。インテンポで延び縮みがなく、走ることもないのです。人によっては間延びに聞こえるかもしれないけど、リズムは律儀に進めつつ、角張りはありません。一方で強弱の波としては、端正ながら適度に滑らかであり、動きがやわらかいです。こうした組み合わせにより、同じ正確なリズムが生真面目さというよりも優雅さ、冷静であると同時にどこか品の良さを感じさせるのです。それに加え、木管がフランス管独特のペラっとした色彩的な音でいいです。心なしか弦も華やかに聞こえます。 本来なら第二楽章に当たるポコ・アダージョですが、前半の部分と比べてぐっと遅くすることはなく、速いテンポではないものの比較的さらっとしています。全編スラーとは違い、所々でフレーズの切れ目は入れます。でも歌い方は適度に波のような流動性があり、柔軟で滑らかです。やはりアゴーギク面での動きはほとんど付けません。息を殺すまでではないにしてもスタティックな美しさがあり、弱音部での表情は繊細でやわらかいです。落ち着きが感じられて清潔感のある緩徐楽章です。 三番目のスケルツォ部分(第二楽章の頭)もゆったりとしたリズムで始めます。やはりきっちりしていても角張ってはおらず、諧謔曲といっても終始落ち着いている感じです。派手な効果を使わないので上品です。 続くフィナーレですが、適度に力強いものの、豪快というよりは端正なオルガンの入りです。やはりリズムが明晰で、はやる心という感じは出しません。でも融通が利かないのではなく、心地良い運びです。ラストに向けても興奮の度を高めることはなく、終わりの直前で楽譜の通りに少し速くなる部分はあるにせよ、きれいな形を保って行きます。最後の瞬間もインテンポで、まるでボレロを扱うかのようで却って迫力があります。こういう崩れのなさは、頭では小澤征爾と比較してもいいように思えるのですが、実際に比べるとかなり違いました。どういうのか、小澤盤の方は特にテンポをキープする強い意志のようなものを感じさせるわけではなく、自然に多少速まったりする部分はあります。リズムをくっきりと刻むでもなくスムーズで、テンポはやや速めです。歌わせ方の滑らかさももう少しあるでしょうか。よりニュートラルで力強い方にも繊細な弱音の方にも寄らず、あらゆる意味で中庸の美というか、淡白な印象なのです。どちらがいいかは好みながら、醸し出す雰囲気の点で似て非なるものでした。 1962年のデッカの録音です。オルガンの重低音はしっかりしています。CD にリマスターする際に若干補正をかけたのでしょうか、正確に比較はしてませんが、見事によく出ています。オーケストラの全体のバランスとしてはスレレオ初期のやや古い音ではあるものの、これもリマスタリングのせいもあってかきれいです。デジタルになって以降の、ソリッドできつい音になってしまっているものと比べればむしろ好ましく、今でも十分通用します。フォルテの弦は固まり気味なところも若干あるでしょうか。肉が薄い感じは多少します。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Jean Martinon Orchestre National de l’ORTF ♥ Marie-Claire Alain (org)
サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ジャン・マルティノン/フランス放送管弦楽団 ♥ マリー=クレール・アラン(オルガン) フランスの指揮者、フランスのオーケストラの組み合わせで、その観点で見たときの大御所の一人と目されるマルティノン盤です。1910年のリヨン生まれ。76年に亡くなりました。この人もアルザスのドイツ系の血が混じっているようながら、ミュンシュとは違い、アメリカのオーケストラとは気が合わなかったみたいです。フランスの作品においては常に評価が高かったものの、決して角に力を込めない柔軟な歌謡性と洒落たアゴーギク、弱音の多用、華やかな音の聞かせ方といった、いわゆるフレンチらしいフレンチの典型という感じではないかもしれません。このエラートのサン=サーンスでは比較的そんな部分もあるにせよ、どの演奏も全般的にはあまり形の崩れがなく、「これぞマルティノン節」という特徴は掴み難いことが多かったようにも思います。そして他のニュートラルな表現をする指揮者たちの間にあってはボディがしっかりしたところがあり、ドイツ的とは言わないけど力強さも十分に感じます。 マルティノンの「オルガン付き」の録音は二つあります。ここで取り上げる1970年のエラート盤と、75年の EMI 盤です。オーケストラは同じ、オルガンは前者がマリー=クレール・アラン、後者がベルナール・ガヴォティとなっています。録音の程度に関してどちらも新しいものと比べれば多少見劣りするところがあるのは似たり寄ったりで、大きな音で弦や金管がきつめになるところも似ています。ここで70年盤の方を取り上げたのは、オルガン奏者が有名だからではありません。75年盤はテンポが比較的遅い方に寄って聞こえ、抑揚は旧盤の波打ち方よりややフラット気味に抑えられている一方、叩きつけるような力の入れ方では勝る傾向に聞こえたからです。このあたりは全く好みの問題だと思います。 録音についてさらに違いを言うなら、75年盤はオルガンの重低音は出ていないわけではないけど比べれば旧盤より少なく、オーケストラの低音も旧エラート盤の方が膨らんでいます。フォルテでの弦は新盤の方がややつや消し気味になる箇所もあるので、この時期の一般的な EMI 録音のメタリックな傾向とは多少異なるかのようではありますが、キンとする箇所もやはり聞かれます。ブラスもやわらかさと透明度はない方で(これに関しては旧盤も似たり寄ったりですが)、かなり元気が良い部類です。 さて、エラート盤の演奏ですが、上で概括した通り、抑揚のつけ方が大変フランス的というわけではないけれど も、オーケストラはフランス的な音の演奏、と言える種類ではないでしょうか。 テンポは他と比べてもゆったりしている方に入ります。出だしでは語尾を長く引いて延ばします。波打つようにビブラートの効いたオーボエが大変きれいです。他のパートは割と淡々として形を崩さないけれども、穏やかに歌う抑揚と言えます。 第一主題に入ると定石通りで少し速度を上げます。明るい音色です。結構強弱の波はあり、曲線を描いて大きく盛り上がるところがある一方、速度の面で細かくは揺らしません。ただし前述の通り語尾でゆるめて長く延ばしたりするので、周期的には動いているとも言えます。弱音に落とす効果はしっかりと使い、弱いところにも表情があります。フォルテは丁寧で、駈けてダマになったりせず、解きほぐされています。したがって決して「爆演系」ではなく、力はこもっていながら余裕があります。こうした優雅さはアンセルメ盤とも近いところがあるとも言えるでしょう。もっと抑揚に動きがあって表情は大きいですが。 緩やかなポコ・アダージョに入ると、やはりゆったりした運びで、のんびり感も出ます。間を取りつつよく歌い、弱音の囁きには寄せておらず、たっぷりしています。大らかで屈託がなく、陽性の心地良さというのでしょうか。後半は弱めて行くところが出るものの、淡々としていつつ語尾は柔軟に延ばして歌うという感じです。アンセルメ盤のスイス・ロマンドがフレンチ管らしい音だと言いましたが、このマルティノンもフランスの響きだと言えます。スイス・ロマンド管は特にバソン(ファゴット)が独特に聞こえる一方、こちらはオーボエも細身で艶があり、フルートは軽いです。弦も同様で、ドイツの楽団より明るい感じの響きでしょうか。自動車の乗り味と同じで、昔は今ほど国際化が進んでおらず、国別の特徴がより出ていたと言えるのかもしれません。 スケルツォ部分ではそこそこにテンポを上げますが、丁寧ではあります。やわらかさがあって畳み掛けては来ません。 フィナーレのオルガンは迫力の出だしです。テンポはやはりゆったりめで、おっとりした感覚も同じであり、そのまま雄大さへと変わって行きます。急がず悠然としていて、力強くもあるのです。中ほどで静まるところはかなり滑らかで静かになります。ラストにかけてもほとんど速くはなりません。 1970年のエラートの録音です。当時のこのレーベルは録音バランスの良さでも知られていた通り、今でも十分に聞けるものですが、ブラスなどは多少割れ気味というか、賑やかにはなります。鋭さも感じられます。木管は艶があり、高音弦は強奏部で多少細くてきつめです。オルガンの重低音は地響きというほどではないにせよ、かなり出る方です。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Anita Priest (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ズービン・メータ/ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 アニタ・プリースト(オルガン) 上記のマルティノン盤と同じ年に出たメータ盤です。ご存知ペルシャ系インド人で、ボンベイ交響楽団を創立した人を父に持つながら親イスラエルという指揮者であり、録音においてはデッカから出していた LA フィルハーモニックとのデビュー間もなくの勢いのある演奏で大変人気が出た人です。1936年生まれです。バレンボイムとも気が合うようで、カラヤン、 バーンスタイン、アバドのいない現代の、エスタブリッシュメントの一角に食い込む巨匠の一人と目されています。 メータの「オルガン付き」の録音は新旧二つあり、最初のがここで取り上げる LA フィルとのデッカ盤、新しい方がベルリン・フィルとの1995年のテルデック盤(オルガンはダニエル・コルゼンパ)です。新盤の方が新しいだけに録音は良いかもしれません。弦の音が個人的にはあまり好みの方向ではなかったのと、オルガンの重低音もレベルはあまり大きくないということがあるものの、このレーベルは音響的にも評価されているところです。でも今回そちらを取り上げずに旧盤の方にしたのは音質の話ではなく、演奏の面からです。メータが好きな方は、恐らく活きのいい方を求めるのではないかと思ったのです。新盤の方は、そちらが良い方もいらっしゃるとは思いますが、もう少しまったりしているように聞こえます。 三十四歳頃の演奏です。第一楽章から若々しく元気で、少し速いテンポで間を空けず、前のめり気味に感じられるほどです。 ポコ・アダージョの楽章はゆったりになり、重さと粘りも出します。 スケルツォはそのままテンポを落としてかっちりとやりますが、歯切れが良く、力が入っています。 フィナーレも基本は遅めでじっくりと鳴らし、所々でテンポを速めたりします。ラストに向けても勢いがあり、走り気味になります。 当時優秀な音で聞こえていたデッカの1970年の録音です。悪くないです。それでも時代なりではあり、フォルテでは多少やかましく響くように感じるかもしれません。 メータという指揮者については勉強不足ゆえに自分にはよく分からないところもあるようで、しっかりは書けませんでしたが、飛ぶ鳥を落とす勢いのあった人であり、「春の祭典」などの輝かしいオーケストレーションの曲で人気が沸騰しました。今もこれこそが「オルガン付き」だというファンの方もおられると思います。是非聞いてみてください。 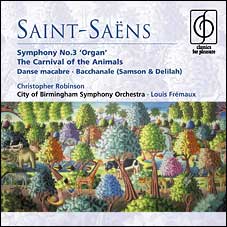 Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Louis Fremaux City of Birmingham Symphony Orchestra ♥ Christopher Robinson (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ルイ・フレモー / バーミンガム市交響楽団 ♥ クリストファー・ロビンソン(オルガン) ルイ・フレモーも昔からのファンならよく知っている名前かもしれません。1921年にベルギーに近いフランスで生まれ、WW2時にはレジスタンス運動にも加わり、2017年に九十五歳で亡くなった指揮者です。ラトルが有名にしたバーミンガム・シティ・オーケストラの前任者でした。レパートリーは専らフランスものを得意としており、ドイツ系の曲は有名なものも含めてほとんど録音していません。それもあってか近頃はあまり再販もされていないようで(EMI が他にもフランス人指揮者を複数抱えていることもあるでしょうか)、どうかすると同じくフランス人のフルネと混同してしまうかもしれません。八つ上という近い世代だし、F で始まる短い名前と都響を振ったりしてる経歴も似ています。流麗かつダイナミックに切れが良くなる瞬間がある(晩年遅くなったフルネの場合は若い頃?)のも両者取り違えそうなところです。フレモーに関しては、このページではすでにカンプラとジルのレクイエム、フランソワのピアノによるショパンの協奏曲1番とジョン・ウィリアムスのアランフェス協奏曲の伴奏盤をご紹介していました。 何となくフォーレのレクイエムもやった気でいたけど、そちらはそれこそフルネと混同したからのようで、実際は取り上げてませんでした。よく聞き込んでないからそういうことになるわけで失礼極まりないですが、サン=サーンスの「オルガン」は高く評価する方がおり、この人の代表盤かもしれません。一人のユニークな個性を類型に嵌めないようにしたいと思います。 そのルイ・フレモーの「オルガン付き」ですが、フランス人らしく滑らかでスムーズな運びが洗練されていると言える一方で、ゆったり歌うばかりでなくテンポを動かし、速くて結構ダイナミックなところも聞かせます。そしてその瞬間でも荒くならないきれいさがあるのは、(また類型に嵌めてしまうけど)やっぱりフランス人らしいところ、なのでしょう。 第一楽章出だしの部分はたっぷりとした運びです。やわらかく粘る抑揚をつけてよく歌うので、フレンチな雰囲気を期待した人を裏切りません。一方で第一主題からはスピードアップし、その後も時折やや速めと言えるテンポにまで加速して切れを見せます。しかし前述の通り、速くてきっぱりしていても流麗でスムーズなところがあり、ドイツ系の演奏者とは違ってフレーズがごつごつしたり、大きく間が空いたりはしません。 ポコ・アダージョではまた大変ゆったりとなり、うねるように大きく歌い上げます。しかも節度があって滑らかです。 スケルツォは速過ぎず遅過ぎずですが、くっきりとして丁寧めに、基本はややゆったりのテンポで運んで行きま す。堅苦しさや生真面目感はありません。所々で素早く流すのも同じで、フィナーレへとつなぐ最後のところは表情豊かにゆっくりと歌います。 フィナーレのオルガンは力強いですが、やかましくはありません。節度と落ち着きがあります。 1972年録音の EMI です。オルガンの重低音はしっかり出ています。最初からよく聞こえ、特定音程で強いところはあるものの、ほぼ満遍ないボリュームと言えるでしょう。録音全体のコンディションもかなり良い方に入ると思います。バランス的に低音も出ていて、しっとりとした潤いも感じられるのです。最高にクリアとまでは言えないかもしれず、強い弦がややさらっとしたり、金管が多少ドライ方向に華やかになるところもなくはないですが、このレーベルにはもっと割れて賑やかなものもあり、これはこの年度としては優秀でしょう。音像が多少引っ込んでいる感じで、楽器との距離を感じるものの、それがむしろ落ち着きとなっているのでしょう。 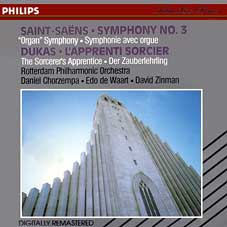 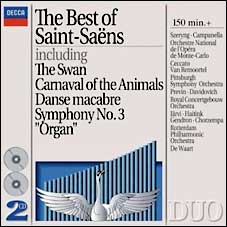 Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Edo De Waart Rotterdam Philharmonic Orchestra ♥♥ Daniel Chorzempa (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 エド・デ・ワールト / ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ ダニエル・コルゼンパ(オルガン) プレートル(新)やマルツィオ・コンティ、カントロフ盤などと並んでこの曲で個人的には最も良かったものの一つです。というのか、古くはアンセルメも好きだけれども、この曲の魅力を初めて教えてもらったと言える懐かしい一枚であり、今なおベストだと思える演奏です。録音も素晴らしく、出た頃の LP 盤には測定された周波数グラフが掲載されているほどオーディオ的にも注目されていました。それはただオルガンの低音がどうこういうだけでなく、アナログ録音ながらバランス的にも大変優れたものでした。 オランダの指揮者、デ・ワールトは1941年生まれで、ミトロプーロス指揮者コンペティションに勝ってバーンスタインとハイティンクの下で働き、67年にロッテルダム・フィルの指揮者となりました。73年からは音楽監督となって本格的なキャリアをスタートさせ、次にはサンフラン響の音楽監督にもなったけれども、その後はミネソタ管、オランダ放送フィルハーモニック、シドニー響、香港フィルハーモニック、ミルウォーキー響、ロイヤル・フランダース・フィルハーモニック、ニュージーランド響、サンディエゴ響などを指導して来たという経歴。素晴らしい郷土料理を楽しめないという話ではないけど、いわゆる世界有数のオーケストラのポジションに就いているメインストリームの指揮者たちとはちょっと立ち位置が違うようです。彼らと比べても劣るどころか良いところが感じられるのに、まあ色々あるのでしょう。2021年、八十歳の誕生日にオランダ放送フィルハーモニックが彼に対して、それまでの「桂冠指揮者(名誉の月桂冠を意味するコンダクター・ローリエット)」に加えて「副指揮者(アシスタント・コンダクターシップ)」という称号まで送ったという記事が出ていました。どんな人生が幸せかは分かりません。六回結婚したという話もあり、普通の感覚では尊敬に値するエネルギーです。その方面ではアバドやデュトワ、 プレヴィンより上かもしれません。どの方面で、上ってどういうことかは知りませんが。このページでもリヒャルト・シュトラウスの二曲とバッハのヴァイオリンとオーボエのための協奏曲、ホリガーによるモーツァルトのオーボエ協奏曲での伴奏盤などについてすでに言及していました。ここで取り上げるサン=サーンスの3番は、この指揮者のベストでもあるのではないかと勝手に考えています。 この盤が一番の一つとまで言える訳は、上記の通り録音の良さもあるのです。というのも、演奏マナーとしては、全体に見ればややゆったりな方ながら格別速くも遅くもないテンポ設定であり、速度・強弱の変化もない方ではなく、かといって付け過ぎる方でもない、という種類だからです。活きいきして実に適切ながら、この部分がこの人らしいという強烈な個性を指摘するのは難しいので、スターのようには評価され難い人かもしれません。同じオランダのハイティンクもそんなところがありましたが、中庸といっても決して無味乾燥の優等生ではありません。曲の構造をよく把握している実力者と言われる種類でしょう。この「オルガン付き」では柔軟に、自発的な心の動きをともなってよく歌っています。動機ごとに解釈がしっかりしており、落ち着いて細部に目が届き、全体として洗練された印象です。 出だしはゆったりしていてよく語尾を延ばして歌います。グレゴリオ聖歌の第一主題から後は定石通りにスピードアップするものの、軽さと滑らかさがあって良いです。決して力づくではなく、荒削りなところがなくて上質な印象。テンポはこの楽章ではその後基本的にこのペースを保ち、重く粘るように遅くしたりはしません。 本来なら第二楽章に当たるポコ・アダージョは、速くはないけれども極端に遅くもない、割とさらっとしたテンポ設定です。これが大変良い感じであり、最初からうねるように熱を込めたレガートで音量変化を大きく付けたり、思い切って囁くような弱音を駆使するという手段で振り幅を稼ぐのではなく、基本は心地良く流して行きます。しかし淡々としているようで情緒豊かにたゆたい、波打って揺れる滑らかな抑揚があります。お終いの鎮静の前に熱く盛り上がって行く感じも十分です。 第二楽章頭のスケルツォも丁寧な出だしで走らず、でも遅過ぎずです。諧謔曲ながら滑らかで落ち着いていて、全体にはそれが却って説得力となるような運びだと言えます。途中スタッカートで飛ばす軽快さも見せ、曲本来のメリハリも効いていて良いです。動きが生きています。 後半のフィナーレの部分では、出だしは力強いオルガンながらやかましくなく、やはり落ち着いた足取りで着実に進めて行きます。それでいながら生真面目な堅さには陥らず、生きたメリハリがあって瞬間瞬間に艶やかな歌を聞かせます。インテンポで進める結果、ラスト手前で速める効果も生きます。そして終わりも同じテンポで堂々と締め括ります。アジらない真性の力強さという感じです。 フィリップスの1976年の録音です。前述の通り見事な優秀録音です。まずオルガンの重低音は出ています。かなり出ている部類でしょう。コルゼンパのオルガンは同時録音です。それはそうとして、フィリップスらしい生っぽい音のバランスがいいのです。弦は強奏部では少し線が細くなり、つや消し気味の強い音に寄る瞬間もあるものの、全体的には決してきつくなく、ふくよかかつ滑らかです。木管も艶があります。オーケストラのバランスとしては、低音もやわらかく豊かに出ています。 ただ、この録音には音の良いことで知られているペンタトーン・レーベルから DSD 変換をした SACD ハイブリッド盤も出ているのですが、そちらは印象が異なりました。低音弦があまり強く響かないバランスになっており、フォルテでの高域は多少リファインされてるかもしれないけれども、全体としては力が減って細めに感じまし た(CD レイヤー再生)。同じ演奏がふくよかにではなく、もっとさらっと聞ける印象なのです。ちょっと悪く言うなら、やわらかさが後退して音色変化が減ったようにも感じられ、デジタル収録の別の演奏を聞いているかのように錯覚します。思わず録音日時を確認してしまうほどでした。オルガンの低音のボリュームも若干減ったでしょうか。このようにリマスターで印象は大分変わるものです。 今回ここで取り上げたのはフィリップスから移行したデッカ・レーベルの CD 盤(所有しているのは旧フィリップス盤)なわけですが、アナログ LP のときはさらにもっと有機的な滑らかさを感じさせるものだった記憶もあります(装置によって異なるので LP が絶対と主張しているわけではありません)。 ワールトのサン=サーンスの3番は、この後にサンフランシスコ交響楽団との新盤も出ています(オルガンはジャン・ギユー)。ゴールデン・ゲート・ブリッジがついたジャケットのやつですが、今回は取り上げませんでした。レーベルは同じくフィリップスで、そちらは1984年の録音です。旧盤の方だけ選んだ一番の理由は録音の問題でしょうか。新しい方もバランス的にはハイ上がりとかではなく、低音も出ていて自然なものかと思いますが、デジタル初期であり、音が大きくなるとこの方式らしいソリッドさというのか、強さが出ます。フォルテの弦が個人的にはちょっときつかったです。したがって優良録音ながら最優秀録音だとは感じませんでした。オルガンの重低音は旧盤同様に出ています。ボリュームがあるというほどでもないながら、十分低いところまで伸び、震える感じがします。 演奏に関しては基本は同じ解釈だと言えるでしょう。でも多少慎重で覚めたところがあるような感じもして、旧の方が表情が豊かで生きており、感覚的には有機的な流れも感じさせる気がしました。このあたりは録音バランスでも大分違って聞こえます。第一楽章の伴奏部分でリズムを刻む弦などがはっきりと聞こえ、着実感がより増した印象です。少し四角くなった感じというのでしょうか。旋律線をなぞる乗りの良さでも旧盤かなと思う一方、新盤には強くクレッシェンドするところもあり、部分的には劇的です。テンポはやや遅くなったでしょうか。 ポコ・アダージョは速く感じないものの、タイム的には反対にやや短くなったようです。旧の方が若干歌に粘りがある気がします。 フィナーレのオルガンはストップの選び方によるのか、一段重い音が加わったようで、力強く物々しい印象です。全体に重い運びで元気が良く、迫力があるのですが、音の加減もあって自分には少し辛いところもありました。むしろそちらの方が好きな方もいらっしゃると思います。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Gaston Litaize (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ダニエル・バレンボイム / シカゴ交響楽団 ガストン・リテーズ(オルガン) バレンボイムはエド・デ・ワールトとは違い、バーンスタイン亡き後、メータやレヴァインなどとも並んで世界の桧舞台で注目を集めて来たエスタブリッシュメントの一人と言ってよいでしょう。もはや説明の必要はないことと思います。1942年アルゼンチン生まれのイスラエル国籍の指揮者です。このサン=サーンスの「オルガン付き」はメジャー・レーベルであるドイツ・グラモフォンから出され、プリズム光のピラミッドのようなジャケット・デザインでこの曲の代表盤のように言われて来ました。メリハリのはっきりしたダイナミックな演奏で、その方面のファンの熱い支持を集めて来た一枚です。 使っているオルガンもなんとシャルトル大聖堂のもので、カラヤンのノートルダムのと並んで有名な人らしい、有名な教会のものを別どりで使っています。聞きどころでしょう。 第一主題が出るまでの出だしの静かな部分ですが、頭の無音のところを除いた実測で1分16秒ほどあります。これはデュトワと並んでこの曲の演奏で最も遅い運びと言えるでしょう。バーンスタインやカラヤン、ミュンシュやプレートルよりもゆっくりです。語尾を長く延ばし、多少思わせぶりかなとも感じられるほどですが、バレンボイムの場合は後で盛り上げる部分とのコントラストを付ける狙いもあるのかと思います。そして最初の主題に入ってからスピードアップして走り出します。ここで速度を上げるのは楽譜上アダージョからアレグロ・モデラートになるので一般的な手法です。反対にゆっくりになったかのように感じる演奏としては、ほとんど速度を変えないバーンスタインなどがいるけれども、それは少数派です。問題はどのぐらい速くやるかということですが、バレンボイムは落差が大きいです。バーンスタインもテンポにメリハリを付けて行くやり方ながら、走るところが違います。そしてまたスローダウンし、ダイナミックにテンポを伸縮させて興奮度を表すことで、聞く側にサービスをしてくれているかのようです。力強いです。 ポコ・アダージョの楽章は速めで、オンながら歌わせ方がさらっとしており、ミュンシュ盤とも少し似た印象で しょうか。弱音には寄せません。 スケルツォも力がこもって活気があり、最後の楽章に当たる部分では所々で駈け足になったりして、またメリハリを付けます。ラストに向けても走り気味です。そして華麗な大技で荘厳なるフィナーレを迎えます。 1975年録音のドイツ・グラモフォンです。低音はバランス的にしっかり出て、歪みはないながらかなり輝かしい高域です。フォルテはやはり多少ソリッドで、DG らしい音だと思います。弦はつや消し気味と言えるでしょうか。この演奏にはオリジナルのジャケットのものと、図柄を斜めに傾けた OIBP リマスター盤とが出ています。リマスターしてない方が若干高域が細く伸びてるように感じるかもしれません。リマスター盤の方は分解能がある一方で、ソリッド でクールな賑やかさも出るようです。オルガンの重低音は出ている方に入ります。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Leonard Bernstein New York Philharmonic Leonard Raver (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニック レナード・レーヴァー(オルガン) ウェストサイド・ストーリーの作者レニーについては説明は不要でしょう。カラヤンと並んで世界の巨匠として君臨したユダヤ系アメリカ人指揮者で、1918年生まれ。90年に惜しまれつつ没しています。スケールの大きな演奏をする人です。上記バレンボイム同様にテンポも思い切って動かすことが多いと思います。このサン=サーンスについては出た頃にその筋に評価が高かったのかどうかなど、不案内にして分かりません。名演と言う人もあるようだし、そうでないという人もいるようです。フレンチっぽくはないと思います。 最初の楽章の印象は、大変ゆっくりしているということです。出だしは多くの演奏者がゆっくりやるわけで、そういう意味では語尾は延ばしても割と標準的な部類の速度とは言えるでしょうか。しかし第一主題が出るアダージョからアレグロ・モデラートへと切り替わるところで速くしないという面白い手段に出ているので、そこからの扱いで総体的に遅く感じるのだと思います。そして上ではバレンボイムと比較しかけたけれども、違いはバーンスタインにはどこかもっと重さが感じられるということです。このアレグロ・モデラート部分からの遅さがそんな印象をもたらしているのかと思う一方、この人には他の演奏の場合であってもそういう重量感が常にある気がします。若いときは違ったかもしれないけど、ものものしいと言っていいのか、どこか深刻さを感じさせるぐらいに重く粘ります。サン=サーンスというフランス人が作った音楽のつもりで聞こうとすると戸惑うかもしれません。この人独自の個性的な音楽になっているでしょう。そしてこの頭四分の一の楽章においてはさらに粘るようなスローダウンを聞かせたりもし、テンポ変動がありつつ最後まで遅いままです。歌わせ方も適度に盛り上げはするものの、バレンボイムのようにはやる心のエキサイトぶりではありません。伴奏音が区切られて聞こえ、丁寧に一つずつ歌うようであり、滑らかというのでもありません。フォルテでは重いままにしっかり強く盛り上げます。 緩徐楽章に当たる四分の二区分のポコ・アダージョもゆったりで、フラットに歌わせます。ここでも重さを感じます。 四分の三目の区分になる第二楽章頭のスケルツォも、やはりゆったりです。重さのせいで弾むような諧謔曲とい う印象ではありません。ところが次の主題に入ると一気に加速し、誰よりも速いぐらいになります。バーンスタインの面目躍如でしょうか。若いときから亡くなる頃まで、こういうメリハリをどこかに付けるというのが彼のスタンダードだったと言えるように思います。ショービズの世界の心憎い配慮かもしれません。そして元の主題に戻ると速度も戻します。 次にフィナーレ部分に入りますが、オルガンの長く尾を引く音が雄大です。ここもゆったりめで、特定フレーズをスローダウンさせたりします。それによってさらに巨大建築のようなスケール感が出ます。ラストはお約束で少しテンポを揺らし、駆け抜けて終わりはしないけれども劇的な感じを醸し出します。 全楽章にわたって重く壮大な印象の演奏です。 1976年コロンビア録音のソニー盤です。オルガンの重低音はしっかり出ています。音程によってむらはあるものの、一音だけ出ているというのではありません。それ以外の音響ではバランスは良いですが、フォルテの弦はややきつめかもしれません。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Herbert von Karajan Berliner Philharmoniker Pierre Cochereau (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ピエール・コシュロー(オルガン) フランスの演奏者とは考え方が違う、ドイツ流の重厚なパフォーマンスです。 カラヤンには「カラヤン・レガート」という術語があって、「颯爽としたテンポ」のとき以外のこの指揮者の特徴のようにも言われます。滑らかで濃厚なクレッシェンドなどが聞けるわけです。しかしこのサン=サーンスに関しては路線として正にそれという感じでもなさそうです。フランスものだからというわけではないでしょう。「幻想」あたりはかなり濃厚でした。かといって速いテンポで行く60年代の演奏とも違います。デジタル最初期の81年というのは例のザビーネ・マイヤー事件の一年前ということになります。どちらかと問われれば「カラヤン・レガート」の区画側ではあり、メロディー・ラインは滑らかながら伴奏のリズムがくっきりと区切られていて、落ち着いています。 カラヤンといえば常に「華麗な」イメージがあるかもしれません。でも、バーンスタインのともまたちょっと違うものの、音の出し方自体にも独特の重みがあり、軽く華やかなフランスのオーケストラとははっきり別物と言えます。それを暗さととるか、しっとりしたクリーミーさととるかはともかく、マッシブでスムーズな印象です。トータルでは流麗なカラヤン節だとも言え、カラヤン・ファンには外せないと思います。 出だしは中庸やや遅めのテンポです。オーボエの入りが早く、滑らかだけど割合淡々としています。最初の主題以降も音はともかく、あまり粘った歌い方はしない方です。メロディ・ラインはスラーで大きくクレッシェンドしたりはする一方で、この指揮者としては割とクールな運びに聞こえるのです。拍がくっきりとして落ち着いており、生真面目というのか、ひょこひょこと角が出るのがドイツ的でしょうか。 ポコ・アダージョはやや遅めのテンポです。滑らかだけど案外力は入れずで、「浄められた夜」ほどの濃厚な抑揚はなく、まったりとしています。粘る大きなクレッシェンドの歌があるわけではなく、特に消え入るような弱音に寄せる風でもないのです。ただ、多少息苦しいぐらいに重い感じはします。音はつなぐけど、華麗なカラヤン・レガートでもないと言ったら良いでしょうか。洗練されているとも言えず、どこか構えが感じられる気はするし、個人的にはもう少し延び縮みがあるとありがたかったです。でもそれは全くの好みの問題でしょう。真面目で大きな演奏です。 スケルツォはテンポ感があります。颯爽というのか、少し速い進行です。そして途中の展開はかなり飛ばします。でも全体には磨かれていて音に重さがあり、弾む諧謔というより多少厳めしさの方に寄るでしょうか。「悲愴」の軽快な部分を聞いているかのような印象です。 フィナーレのオルガンの開始は壮大です。これはノートルダム寺院で別どりしている部分です。バレンボイム盤のシャルトルと並んで立派な大聖堂です。他にもストラスブール、ランス、ルーアン、アミアンなど有名なカテドラルはあるものの、こちらはちょっと前に焼けてしまった首都パリの、フランス一有名なものです。そうなるずっと前に行ったことはあって、登ると怖いぐらいの高い建物でした。比例してオルガンも大きいです。でも礼拝で鳴らしてるぐらいではよく分からなかったもので、これで聞くと圧倒されます。火事では無事だったようで何よりです。そしてこの「オルガン付き」の部分、数々の録音の中でも最も荘厳な音絵巻の一つではないでしょうか。和音が多く感じられ、重低音ではないけれども低音ががつんと響く、華やかで大掛かりな音響です。高い方の倍音の縁取りも明快です。 加えてブラスも元気です。テンポは中庸で決して速くはなく、スケールを感じさせるような、やや遅めと言える設定です。ラスト手前で型通りに少しだけスピードアップするのを除けば、ここもインテンポでがっちりと行きます。最後の瞬間まで力を込め、大音量で雄大に終わります。 1981年のドイツ・グラモフォンで、デジタル録音です。弦の音に適度に艶と潤いがあって、移行期ながら音は決して悪くありません。ベルリン・フィルハーモニー大ホールの収録であり、低音は響く一方、中高音の残響は長くはないです。クールとは言わないけれども、このレーベルらしく、生っぽいやわらかさで行く感じではないでしょう。オルガンの重低音はあまり出ない方です。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Charle Dutoit Orchestre Symphonique de Montréal ♥ Peter Hurford (org)
サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団 ♥ ピーター・ハーフォード(オルガン) この手の曲が悪かろうはずがないデュトワですが、実際はどうでしょう。シャルル・デュトワは1936年ローザンヌ(スイス)生まれで、1977年から2002年までカナダのモントリオール交響楽団(フランス語圏)で音楽監督の地位にあり、そのフランス文化の香り高い演奏によって世界的な評価を得た人です。どちらかというとゆったり方向のテンポ設定で解きほぐすように運び、独自の美的センスによる滑らかで自発的な息遣いをもって歌って行く、洗練された音楽を作る指揮者だったと言えるでしょう。過去形にしてしまうのは失礼かもしれませんが、2017年頃(その時点で八十一歳です)に相次いで表に出て来た女性に関する数々の疑惑で目ぼしいポストを追われました。相手は男性ながら同じ年にジェームズ・レヴァインに起きたことと同じです。その後デュトワの方は小沢征爾の呼びかけでサイトウ・キネン・オーケストラに登場したりはしたものの、巨匠の地位を揺るぎなく確立しているとは言えない現状です。マルタ・アルゲリッチと結婚していた時期があり、彼女は味方についているようです。現在も非難は続いていますが、その真偽も含め、この記事では何も断定せず、演奏以外のことは考慮に入れません。もし申し立ての通りなら大変で、#MeToo の立場は尊重します。果たして騒がれ過ぎなのか、騒がれなさ過ぎなのかは今後歴史が証明する、かもしれません。いずれにせよ、年齢的にも今後の活躍が期待されるというものでもないでしょうし、頂点はこのモントリオール時代でしょう。 さて、このデュトワのサン=サーンスこそ各方面で評価が高いようです。常にメロディ・ラインがくっきり明瞭に浮き立ち、いつもながらの完璧なコントロールによって美しい抑揚で進めますが、曲への割り切りなのか、この「オルガン付き」に関してはいつもより表情がついているようです。テンポの面では他の演奏者と比べても最大遅い部分と、反対に最も速い部類のパートがあり、しっかりとメリハリを付けていて出来過ぎなぐらいに感じました。ただ、それはパートごとに分かれているのであって、同一パート内では特に自在な延び縮みの呼吸があるという感じでもなく、この人にしては案外かっちりと四角な真面目さを感じます。どこにも減点ポイントがないのですが、これは好みの問題なので、♡に関してはいつも満点にすることが多かったにもかかわらず、一つ減らしておきました。評価ではありません。もしパフォーマンス点だったら文句無しに二つでしょう。また、この扱いは彼の疑惑問題とも関係ありません。具体的に見てみます。 出だしはバレンボイム盤と並んでこの曲で最も遅い方の展開です。1分16秒かけて十分に歌います。「怒りの 日」の第一主題からは中庸やや速めまで速度を上げ、メリハリをつけます。抑揚のつけ方はそこでも申し分ないで す。滑らかに漸進的に盛り上がり、二次曲線的に立ち上がったりもする自由自在なクレッシェンドが聞かれ、強弱のステップが多い表情の多彩さ、瞬間的にふわっと速度を緩めるようなアゴーギクの動きなどもあって見事です。録音によるところもありますが、全体に結構華やかな音です。 ポコ・アダージョは冒頭とは違い、前半は割とあっさりしたテンポで品良くまとめられ、そつがないです。表情はあります。ロングトーンの一音の中で古楽のボウイングに負けないぐらいにぐうっと強める手法がこの人らしいです。そして徐々に後半に向けて息の長い抑揚に持ち込む計算になっており、今回は洗練されたあざとさのようなものを多少感じました。 スケルツォ部分は、速めながら大変滑らかに始めます。粗さが全くありません。パーフェクトにコントロールされていて優雅です。中間部はさらに速くなり、一番速いぐらいではないでしょうか。遅いところと大きなコントラストが付きます。この軽快さはいかにもスケルツォという感じです。しかしそこでも滑らかさは失っていません。弱音のストリングスになる前、終わりの方のパートでは、上のメロディ・ラインは優雅にスラーで終始しているのが分かります。結構な速度で、水面下に白鳥の足でしょうか。 フィナーレは適度に力強く、透明なオルガンで入ります。テンポはゆったりめです。静かな部分ではやわらかく優雅に波打つ抑揚をつけながら、オルガンはスタッカート気味に区切ったりもします。全体に落ち着いた展開で、フォルテは力任せではなく、余裕を持たせつつ十分な強さです。また、細部の彫琢に余念がなく、この楽章でも美しさが優先されているかのようです。「幻想」の地獄でもそうでしたが、慌てず騒がず一定の速度を保って行くところはこの人らしいと思います。一つずつの音、フレーズが分解されてよく構成が聞こえるようになっており、ラスト手前では落ち着いてアッチェレランドをかけ、最後までインテンポで最後だけ軽く速めて終わります。 1982年、デジタル初期のデッカ録音です。でもコンディションは大変良いです。このレーベルらしく生のやわらかい自然さという方向ではないですが、音に明るさがあり、高音部の細かいところも聞こえながらあまり硬く固まりません。弦は線の細さがある一方、しなやかさも十分感じられます。同じようにハイがはっきりしていても、DG よりはやわらかいでしょうか。オルガンの重低音はあまり出ている方ではありません。でもポコ・アダージョの楽章の最後の部分などでは、ほどほど低い周波数まで音圧を確認できます。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Seiji Ozawa Orchestre National de France Philippe Lefebvre (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 小澤征爾 / フランス国立管弦楽団 フィリップ・ルフェーブル(オルガン) 世界の小澤です。有名オーケストラのポストを歴任してそう呼ばれた1935年生まれの日本の指揮者ですが、ここでは初登場です。実は「最高の録音」というページでマーラーの7番を取り上げていたのですが、専らレコーディング・プロデューサーの仕事についてのみ語り、演奏には触れず終いでした。というのも、あの独特のざっくばらんな喋り方は好きながら、こちらの力不足でその音楽の特徴はよく理解できていないと思ったからです。優れた才能の持ち主で、ミトロプーロスなどもそうなので音楽家には案外珍しくないのかもしれないけれども、細部まで楽譜を記憶する能力がとんでもないレベルなのだとか。現代の作曲家がぜひ自分のを演奏して欲しいと望んだそうです。というわけで、説明できないなら触れるべきではないと思って来ました。 ただ、いいなと思った演奏はありました。一つ挙げるならラヴェルの「クープランを讃えて」がそうです。ピアノ作品から編曲されたものだけど、ラヴェルは大変好きな作曲家である上に、これは管弦楽曲としても最も好きな作品の一つです。こちらの理解が及ぶ数少ない演奏がちょうど好みの曲であるという事態になり、不思議な気分でした。ラヴェルのページでは他に愛聴している演奏家の録音があるので取り上げはしなかったのです が、その小澤盤、さらっとしてパーフェクトに整った大変美しい演奏です。エミール・ヴュイエルモーズの言葉を解釈し、ラヴェルは正確さこそが大切であり、情緒纏綿や恣意的な表現を受け付けない作曲家だという認識で来ましたので、その意味でもぴったりです。 そしてそれとはまた違った方向で見事だと思ったのは、サイトウ・キネン・オーケストラとのブラームスの4番のシンフォニーです。多少前のめりで間がない感じがするところもあるけれども、覇気があって乗りの良い、熱を感じさせる演奏です。これはライヴではないようながら、初の欧州遠征時でリリース第一弾録音ということもあり、意気込んでいたのでしょうか。オーケストラに自発的な乗りがあるときの演奏は素晴らしいものになるようです。こうしたことから、ライヴでこそ本領を発揮する一面もありそうです。 ではそうしたものに限らず、平均するとこの指揮者はどんな印象かというと、一言でいうと、あっさりとしています。一言でいってはいけない、絶対だめでしょう。どれだけ細部まで完璧な演奏かお前には分からないのか、という事態です。ならばもうちょっと言葉を足すと、全般的にはまず、テンポは少し速めということが多いように思います(例外はあります)。そして余分なものをつけ加えないのです。それはメトロノームのようでは決してないですが、技術的に言えば速度の延び縮みがないという言い方もできます。こういう演奏家の場合には、ここでは常にピュア・ウォーター、純水に喩えて来ました。それで言うなら長野県中部辺りに湧き出した軟水でしょうか。むしろ精製水と言った方がいいかもしれないぐらいに純粋な味です。 そうなると、今までにも同様に「この部分がこの人らしいという強烈な個性を指摘するのは難しい」と表現して来た人たちの一団がいます。上ではデ・ワールトがそうでした。同じオランダのハイティンクもよくそう言われます。でもその人たちとセイジ・オザワは別の種類であるかのように感じます。同じようにテンポがさらっとやや速めのことが多かったイギリスのマリナーとも似て非なるものでしょう。旧東ドイツの楽団を指揮するときのスウィトナーやブロムシュテットとも違うし、晩年のチェリビダッケのようにテンポを遅く固定して強靭な意志を感じさせるという種類でもありません。確かにテンポを揺らさないのは同じなので、そこから肩の力を抜いて全体の速度を速めれば形の上では似てなくもないかもしれませんが。 つまり拍のエッジが立ったドイツ流でも、軽さとやわらかさをもって流暢に流れるフランス流でもないカラーレスな感覚。自身も好きで聞くと仰ってる割に演歌風でも全くないけど、欧州の人たちとは少しだけ音の掴み方が違うようです。伝統の共通言語を持つヨーロッパ以外でというなら、リズムの真っ直ぐな取り方がアメリカのオーマンディに多少近いとは言えるでしょうか。でもあそこまでかくかくしないし、オーマンディは元々ハンガリー出身です。それならばお隣りは韓国のチョン・ミュンフンに似てるかと言えばそれもまたちょっと違い、ミュンフンも素直ながらもう少し表情は大きくとって歌わせ、スローな短調に来ると泣きのこぶしが回る気がします。小澤の方がより分解的と言ってもいいけど、それならば具体的にどう表現するかが色々な意味で難しいのです。 把手になるようなでっぱりというものがありません。キーレス・エントリーで近づけば自ずと開く次世代のあり方でしょうか。良い悪いではなく、やはり純水です。逆説的に言えば、強い個性を打ち出さない点で唯一無二の個性と言えるかもしれません。それも類い稀な才能であり、孤高の人であるとお断りした上で、今回は一歩踏み込んで誤解を恐れずに推論してみましょう。全く違っているかもしれません。 まず、この世界的な指揮者は楽譜の膨大な音符を隅々まで覚えていて、細部に気を配って指示をするということがよく言われます。ひょっとすると、「情感を形の中に捉える」という、次のような立場に立っているということもあり得るでしょうか:
勝手に作文させていただきましたが、別にブーレーズのことを言っているわけではないのです。ノイエ・ザッハリヒカイト(新即物主義)の現代版のようなこの表明、それは大変知能に優れた人が多い唯物主義の科学者の立場のようでもあります。サン=サーンスが言う「サンシビリテ(感情/感受性)は後からついて来る」も近い発想でしょう。仮にそういう姿勢から小澤氏の音楽が成立しているのだとすれば、それは考え方であって文化の問題ではないことになります。
そして考えの元には性格もあるのかもしれません。「純水」に喩えたその音は、平均的な指揮者たちが多少なりとも有している性質とは異なった原理からやって来るものかもしれないわけです。
こんな話があります。予備知識なく人々の生活問題をずばりと言い当ててしまう特殊能力を持つアメリカ人がいて、そこそこに有名な人なのですが、その人と私生活で接してみるとびっくりさせられることがあります。何かと言うと、本人の身の回りの人同士がどんなにあからさまに内紛を起こしていても、彼女はそれを指摘されるまで不思議なぐらい全くそれと気づかないのです。話せば人当たりのいい人物なのだけど、どうも感情の受け止め方に関する周波数のバンドが常人よりちょっとだけ高いか低いかしてるらしい。一点集中の人です。なんか、急にそういう事例を思い出してしまいました。つまり、感情表現への感受性のあり方の違い。小澤征爾の演奏も、素直であっさりしていると言えば日本的なのかもしれないけど、空気を読んで感情を忖度することが少ないという方向に疑えば、反対に日本的ではなくなります。でも、それはこの場合はちょっと違うのかもしれません。ボストン時代には小澤さん、団員の肩叩きがたいそう辛かったと語っておられるようなので、きっと細やかでやさしい気遣いのできる人なのでしょう。
今回サン=サーンスで初めて取り上げてみた理由は、「クープランを讃えて」だけでなく、小澤征爾はフランスものが得意な指揮者だと言われることもあるからです。ラヴェルの曲については全部が好きではなかったけれども、この「オルガン付き」は期待するところがありました。ただ、具体的に描写するのはやはり自分にはなかなか難しいようです。
最初の楽章から端正で丁寧な運びが印象的です。ある意味透明感があると言えるでしょう。導入の部分は完璧ではないでしょうか。第一主題の入りはゆったりに聞こえ、ここで段をつけて速める感じがしないのはバーンスタインの解釈とも共通しています。そして一歩ずつ進めて走らず、強くなっても激することなく正確であり続けます。全体のテンポは中庸です。 ポコ・アダージョの楽章になると適度に遅くなり、まったりとします。表情は素直で真っ直ぐです。 スケルツォは間を多く取らず、整然として切れの良い、小気味良い運びです。大変清潔な感じがします。テンポはすっきりと速めです。ここは気持ちの良い表現ではないでしょうか。終わりの方のストリングスによる歌もきれいでいいです。「クープランを讃えて」の爽やかでありつつ抑揚のある歌の表情とも共通しています。 フィナーレに入ると、乱れはないけれどもオルガンの入りから力強さが感じられます。ラスト手前で定石通りに速くはするものの、落ち着いていてトータルではインテンポです。速度自体は遅くはないです。どこもパーフェクトであり、これは力任せの大仰なものよりずっと好きです。最後の音が残響の中に長く溶け込んで行くところが美しく響きます。 EMI1985年の録音コンディションは良好です。オルガンは別どりで、音圧が最大限ではないながら重低音は 結構出ます。出るか出ないかの区分で言えば、出る側でしょう。オーケストラはフランスのもので、明るさを感じさせるのはそのせいもあるでしょうか。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Claus Peter Flor Berliner Sinfonie-Orchester ♥ Joachim Dalitz (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 クラウス・ペーター・フロール / ベルリン交響楽団 ♥ ヨアヒム・ダーリッツ(オルガン) クラウス・ペーター・フロールは1953年ライプツィヒ生まれのドイツの指揮者で、クルト・マズア、ラファエル・クーベリック、クルト・ザンデルリンクなどに指揮を学び、1984年から91年までベルリン交響楽団の首席指揮者だった人です。リオール・シャンバダールが引率する旧西側の同名の楽団ではなく、現在ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団と名称変更している旧東ドイツの方の楽団です。指揮者としての知名度はさほど高くはないかもしれませんが、この録音時は三十二歳。日本盤として売り出され、雑誌等で賞ももらい、このサン=サーンスの「オルガン付き」は名演とされていたようです。バンベルク交響楽団とのメンデルスゾーンのシンフォニーと並んでこの人の代表盤です。 シャルプラッテンの録音が大変良いバランスです。弦も木管もきれいな優秀録音です。魅力の大きなポイントだと思います。演奏の方は、トータルではテンポは遅め、いかにもドイツ流かどうかは分からないけれどもフレンチっぽくはなく、落ち着いた東ドイツの伝統を感じさせるような正統派のパフォーマンスだとは言えるでしょう。同じ♡一つをつけたデュトワ盤よりも静けさとやわらかさ、自然さにおいて個人的には魅力を感じます。でも単純な楽譜通りではなく、なかなか読みも深くて意識の高い、工夫の感じられるものです。緩徐楽章部分(ポコ・アダージョ)は大変遅く、ラストでは速くなって力も感じさせます。具体的に見ましょう。 第一楽章は中庸のテンポで始まります。でも間は大きめに取ります。そして第一主題からのスピードアップはあまり顕著ではありません。したがってそこからの本番部分はわりとゆったりした運びに感じられます。ただ、テンポは自然に延び縮みし、呼吸が感じられます。四角四面の演奏ではないのです。縮むといっても走りはせず、平均して緩やかであり、弱音部は穏やかです。 本来は第二楽章に当たるポコ・アダージョは、やはり最初から間が大きいのが印象的です。静かな運びで大変ゆったりとしており、大河のように滔々と流れて行きます。タイムとしては11分13秒ほどかけ、バーンスタインより遅いです。これはこの楽章としては最もスローな部類であり、マーラーのアダージョを聞いているようなというのか、チェリビダッケの晩年の演奏みたいにも聞こえます。遅いはたっぷりとも言い換えられるけれども、歌自体はあまり大きくはありません。静けさが魅力なのです。最初は抵抗を覚えるかもしれません。でも慣れるとこれはこれで良いところがあるようにも感じます。 第三楽章に当たるスケルツォ部分ですが、焦らず伸びやかに、ややゆったりのテンポで丁寧に運んで行きます。全体の三分の二ぐらいのところから始まる、通常は駆け足で行くパートの処理が面白いです。タイムで言うと5分38秒前後から後の辺りですが、珍しく走らずにゆっくりにして、分解的に運んで行くことで普段聞き慣れないパートが聞こえたりします。技ありの工夫だと思います。終わりの部分も大変ゆっくりで、その独特の効果に少し驚かされます。 フィナーレはオルガンの入りが澄んでいてきれいな音です。ここも一歩ずつという感じでゆったりな運びであり、その後のオルガンも余裕をもって鳴らされることで全体がほぐされ、塊にならないのでやかましく感じません。ただ、面白いのはそのままおっとりで終わるのかと思ったらさにあらずで、ラストに向けて加速して行き、結果的にかなり速くなります。熱が入り、ゆったりから迫力のある展開へとなだれ込んで行くのです。最後まで乱れることはないけれども、このスケールの大きさは乗りの良い演奏を求めるファンの方にも大変満足できるものだと思います。 1986年録音のドイツ・シャルプラッテンです。旧東側のレーベルで、当時は音源を買って来るのも安かったかもしれないけど、技術は一流であり、上述の通り大変優秀な録音です。でもそれはオルガンの重低音が出るという意味ではなく、全体に見ての話です。オルガンの低音自体は低い方までよく伸びてはいますが、音圧が格別大きいわけではありません。♡♡にしなかったのはポコ・アダージョの楽章が他に例がないほどゆったりしていることと、どこにもまるでフランス的な要素が感じられないところからです。でもそういう曲として聞けば、非常に魅力的です。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” James Levine Berliner Philharmoniker Simon Preston (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ジェイムズ・レヴァイン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 サイモン・プレストン(オルガン) ジェイムズ・レヴァインは1943年生まれで2021年に亡くなったユダヤ系アメリカ人指揮者です。メトロポリタン歌劇場の音楽監督という地位を得て2018年に解雇されるまで活躍し、オペラに強い指揮者とされる一方で、世界中の有名オーケストラに登場し、大手ドイツ・グラモフォンから数々の録音をリリースしました。名門ベルリン・フィルを指揮したこの1986年のサン=サーンスは同レーベルの75年のバレンボイム盤や81年のカラヤン盤と並んで抽象パターンのジャケットを纏い、エスタブリッシュメントとして一時期各メディア推しの有名な盤でした。それら三枚の中では新しい分だけ録音も明晰で、各部の処理が十分に考えられていながらどこかあっさりした印象もあります。完成度の高い演奏だと思います。フランス的洗練という方向ではないし、独自の色はなく、意外な呼吸の妙なども感じさせないかもしれないけど、出るところは出、引っ込むところは引っ込み、押さえるべきところは押さえてよく抑揚も付けつつ、十分に歌ってもいます。「アメリカ的にざっくりとした明るい分かりやすさ」などとも言われるようだけど、安心できる表現であり、欠点のない名演でしょう。コントロールはしっかりする一方で、ひょっとすると上手なオーケストラには委ねる術も知っているリーダーだったのでしょうか。 出だしのテンポは中庸ややゆったりで、語尾はしっかりと延ばします。第一主題からは思い切ってテンポを速め、メリハリを付けます。バレンボイムと同じ扱いですが、よりくっきりとさせています。全体の印象としては適度にダイナミックながら、割とさらっとしていてバーンスタインのような重さは感じません。 ポコ・アダージョの楽章での歌い方も、最初はあっさりしている印象です。テンポも中庸で遅くはありませ ん。濃い抑揚はなく、これといって特徴のない感じでさっと流しているようなのですが、後半になるとだんだん粘りと 歌の大きさが出て来て、熱が入って来ます。考えられています。 スケルツォは中庸なテンポで確実に運びます。歯切れが良く、力も感じさせる展開で、ここはかなりダイナミックな印象です。中間部は痛快に素早く駈けます。そして終わりの方のゆったりしたパートに来ると思い切って静かに歌わせ、それも途中から段を付けてぐっと抑えて行くようにメリハリを付けます。そうしておいて静寂のうちに終わり、次の楽章へと渡します。 フィナーレは十分に力強く、悠然と運びます。バレンボイムほどはダイナミックな抑揚は付けないでしょうか。ラスト手前も走らず、最後の部分も却って一段遅くするぐらいの感覚で堂々と締め括ります。 1986年録音のドイツ・グラモフォンで、大変良い音だと思います。ダイナミック・レンジが大きく取られていて明晰であり、このレーベルらしいバランスです。特にハイ上がりでもなく、被るわけでもでもないし歪感もありませんが、フォルテは多少ソリッドな感じはします。弦の高音は固まらないけれどもさらっとし、特にブラスの強い音は結構きつめというか、色気がある方ではないと言えるでしょう。低音が出ることでの全体のやわらかさは十分あり、トゥッティ以外では弦もきれいです。そしてオルガンの重低音ですが、ほどほど出ています。強いわけではありません。区分けするとすれば出ると出ないの中間でしょうか。  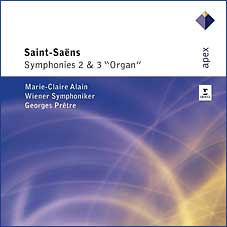 Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Georges Prêtre Wiener Symphoniker ♥♥ Marie-Claire Alain (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ジョルジュ・プレートル / ウィーン交響楽団 ♥♥ マリー=クレール・アラン(オルガン) ジョルジュ・プレートルはフランスの指揮者です。ベルギーとの国境近くで1924年に生まれた人で、世代としてはミュンシュが1891年、マルティノンが1910年、フルネが13年、フレモーが21年、プラッソンが33年なので、フレモーとプラッソンの間ぐらい、有名なフランスの大御所たちより少し後の世代ということになります。個人的にはこの指揮者、熱心には聞いて来なかったところがあるので、今回は得をした気分です。日本では特に音楽関係の出版物を執筆するような人たちから、主に「意外性のある表現」に関して否定的な評価を受けて来たようですが、その方面はあまり読まないので自分が聞かなかったこととは関係がありません。理由はレパートリーの問題もあるけれども、何となくフランスの指揮者としては力一杯の熱演というか、元気な演奏をする人というイメージがどこかでついてしまっていたせいなのです。ちょこっと耳にしただけで先入観を持つのはいけません。このサン= サーンスは意外といっては失礼、ちゃんと聞いたらこの曲のベスト・パフォーマンスの一つと言えるものであり、なんと、ベスト・オブ・ザ・ベスト、かもしれません。 そのプレートルですが、若いときはジャズ・トランペットに熱中していたそうです。ただの趣味じゃなくて、大物ポップス歌手の伴奏なども務めていたようなので本格です。楽器の性質からいってもバップ系の元気の良い即興などは得意だったのかもしれません。クラシカル耳じゃない音楽の捉え方も出来たということでしょう。指揮者としては主にオペラで活躍して来ており、本人に気に入られていたマリア・カラスとの録音は評価が高いです。オペラ以外でも、フランスのみならずアメリカ(ボストン響/フィラデルフィア管/シカゴ響)やウィーン(ウィーン交響楽団/ウィーン・フィル)、ドイツの交響楽団(シュトゥットガルト放響)でも活躍して来ました。カラヤンには気に入られていたようだし、ニューイヤー・コンサートの指揮も二度務めました。したがってレパートリーはオペラとフランスものが中心ながら、ドイツものも十分にこなして来ました。指揮はクリュイタンスやピエール・デルヴォーに習いました。映像記憶型だったかどうかは分からないけど、長く複雑な曲でも暗譜で行ける人でした。私生活では、女性関係に関してはデュトワのように派手なことは何もなく、乗馬や航空機操縦、日本の武道にも情熱を持っていたとのことで、興味の広い人のようです。2017年に亡くなっています。人物は分かりませんが、写真は楽しそうに写ってるものが多いです。 プレートルの「オルガン付き」は二つ録音があります。最初のは1964年の EMI 盤で、オーケストラはパリ音楽院管弦楽団。オルガンはモーリス・デュリュフレでした。デュリュフレは有名な作曲家です。プレートルはこの人から作曲における和声法を学んでいます(自身も作曲しています)。演奏解釈自体は新盤と大きく異ならないもので、大変良いと思います。最後の楽章の終わりに向けて、新盤より少し拍の力が抜けているでしょうか。フランスの楽団の音ということもあって魅力的ながら、ここでは主にその録音の古さゆえに取り上げないことにしました。弦は低い方の楽器がボリュームがあり過ぎるほどなのにもかかわらず、高音弦はややシャランとしていて艶がなく、個人的にはちょっとがさついて聞こえたし、透明度がある方ではないので金管やシンバルもきつく感じました。レーベルと時代から仕方のないことだと思います。こちらの許容度が低いからそういうもの言いになるだけで、本来の演奏の方に目が行って気にならない方もいらっしゃると思います。 それでは、上にジャケットを掲げた新盤の方です。こちらはウィーン交響楽団とのもので、プレートルはそこで 1986年から首席客員指揮者でした。90年の録音です。 一番だと思えるほど魅力的なのに、これも具体的にどうこうと説明するのが難しい部類の演奏です。テンポを全く動かさないという挙に出るわけではないけれども、割とインテンポに近い印象というか、決してはやって走ったりする感じではありません。そして遅いところばかりではないけど、どちらかというと全体にはゆったりで通している印象で、セイジ・オザワのようではないにしても特に変わったことはせず、日本の評論家が「伝統に則らない奇抜」と言うようなところはどこにも感じられません。作為的だったり情緒過多だったりしないけれども、とにかく歌わせ方が自然で情に深く、活きいきとしているところが魅力です。艶と透明感のある優秀な録音も相まって、どこもが心地良いのです。個々に見ます。 第一楽章ですが、ゆったりと歌って入ります。でも過剰さは感じません。第一主題からは楽譜のお決まりで少し加速し、多少軽快な中庸のテンポとなります。これといった趣向はないけれども、一つひとつの歌を滑らかにつなぎつつよく歌い、リズムは弾力をもって心地良く切って行きます。大変表情豊かで、自然な感情の動きが波となって現れ、実に適切に感じます。一部の有名な指揮者で見られるようなやり過ぎ感がないのです。フォルテへの盛り上がりにも、弱め遅くする仕方にも呼吸があり、活きいきしていて瑞々しいです。 ポコ・アダージョの楽章には歌に心があります。思わず「心」と言ってしまいました。何だか「ロマンがありますね」みたいなもの言いです。つまり、十分ゆったりな気分になるけれども、具体的に言えばテンポ自体は最初は特に遅い方ではありません。ただ、適切なところでよく音の語尾を延ばすのでゆったりに感じます。途中からは徐々に速度を落として行く感じになり、客観的にも遅めとなります。それで何と言うのか、また言ってしまうけれども正に心から湧き上がるかのような歌になっていて気持ちが良いのです。4分10秒あたりからの弱音の中間部(転調とピツィカートの前)で弦が掛け合うところでは、通常は前の部分より少し速めるものながらそうせず、ゆったりを維持します。それによって独特の美しさが感じられます。そしてそのテンポはずっと保たれ、最後は大変ゆっくりとなって終わります。クラウス・ペーター・フロールのまるでマーラーの緩徐楽章を聞いているような運びほどは遅くないけれども、デ・ワールトやコンティよりはたっぷり歌わせており、この楽章としては個人的には最も心地良かったものに入ります。 スケルツォのテンポはまた中庸です。タッチは軽過ぎず重過ぎずで、力強いけれども乱れません。でも他の楽章は割と速度一定のような感覚があるものの、この楽章はインテンポで押し通すクラウス・ペーター・フロールのような効果は狙わず、速めるところは速めます。ピアノも登場する次の主題が1分38秒あたりから始まりますが、そこからはかなり軽快なテンポで活きいきと進めます。録音が良いので瑞々しいです。ラストで弦が静かになるところはテンポこそ遅くはしないものの、静かで爽やかです。そして最後でぐっと速度を落として次へと受け渡します。 フィナーレですが、濁りなく力強いオルガンで始め、ここも中庸のテンポです。繰り返し挟まって来る弱音への展開部の扱いが丁寧できれいです。テンポは一定で延び縮みはさせず、細部まで丁寧に描きます。ラスト手前で皆が加速する部分も駈けることなく一定で、最後は重おもしく整然と、力強く締めます。 エラート1990年の録音は大変優秀です。艶が感じられるけど、それが特に強くてフォルテで耳に痛いことはなく、自然で生っぽいです。ホールトーンも感じられ、低音弦もバランス的にはふくよかに出ています。金管も多少後ろに後退していながら、強さは十分あります。ただしオルガンの重低音に関しては、低い方に伸びてはいるものの、ボリュームはない方です。区分けするとしたらあまり出ていない側に入るでしょう。でもフランスのオーケストラでないことも含めて、その点はあまり気になりませんでした。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Myung-Whun Chung Orchestre de l’Opéra Bastille Michael Matthes (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 チョン・ミュンフン / パリ・バスティーユ管弦楽団 マイケル・マッテス(オルガン) 韓国の世界的指揮者、チョン・ミュンフンと旧パリ・オペラ座の管弦楽団によるサン=サーンスです。欧文表記だとミャンウン・チャンで、本人はミョンウン・チョンと英語で自己紹介しており、韓国語だとチョンミャウンとかチョンミャンフンのように聞こえるようです。この国やハンガリーの人はどう日本語にするのが良いのでしょう。ここでは以前もチョン・ミュンフンとしていたので、今回もそのまま慣例に従っておきました。 日本には世界のオザワがいますが、韓国でちょうどそんな地位に就いている人です。ただし世代としてはオザワが1935年生まれなのに対し、チョンは53年なので大分若いです。ソウルで父親が公務員、母親が料理店を営むという音楽に関係のない家庭に生まれ、その後全員での渡米が叶って音楽一家(姉がヴァイオリンで有名なチョン・キョンファとチェリストのチョン・ミョンファ)となるサクセス・ストーリーで、本人は幼い頃からピアノの才能があり、チャイコフスキー・コンペティションで二位に入ったこともあります。指揮者としては LA フィルハーモニックでジュリーニの下で学びました。大成した後はソウル・フィルを世界レベルに引き上げながらも派閥を二分した激しい権力闘争に巻き込まれたり、家族縁故の利権だとかの大統領並みの噂も出たりして(真偽のほどは定かじゃないし、チョンさん全く悪い人に見えません)、まるでどれもが韓国ドラマのようです。国による色ってあるんでしょうか。それなら二人でお酒を飲んでて記憶を失い、朝そろってベッドで裸で目覚めてびっくりという定番劇も現実かもしれません。王朝時代の太子が急に現れるのも夢じゃないかもしれないわけです。親日派で、天皇家とも仲が良く、日本のオーケストラとも共演したり指導したりしています。 ここでの録音は1991年です。それ以前もチョンは各地で有名楽団を指揮していたりはしたものの、本格的に世界への足掛かりを掴むべくパリ・バスティーユ・オペラ(ルイ14世の頃に遡る歴史を持つ、オペラ座で活動するパリ国立オペラ/国立歌劇場と同じ団体で、1989年にバスティーユに新設されたバスティーユ歌劇場落成以降に、特にその付属管弦楽団がバスティーユ管と呼ばれる)の初代音楽監督として立った二年後というタイミングです。元々バレンボイムが就任予定だったものの、音楽マネジメント側の決定に楽団が反発してその招聘を拒否し、宙に浮いてしまったポストに楽団自らが立てたのがこのチョン・ミュンフンだったのです。これによって彼の名は知れ渡ったわけですから、その栄光の始まりの時期ということになるでしょう。本人は時々自分を韓国人であるのと同じぐらいにフランス人やイタリア人のように感じるとも語っています。 世界のチョン・ミュンフンですから、やっぱり小澤征爾と比較するべきでしょうか。ちょっと無理やりな気もするし、日韓の比較となるとより大ごとです。でも似てるところもあるかもしれません。 音楽界一般となると、ポップスの世界では韓国の歌手は歌が圧倒的に上手です。それに対してどこかの国って何気に下手じゃん、などと言ったら大問題だけど、街で可愛さからスカウトされ、そのまま歌手デビューして音量コントロールも音程もハッピーという状態で OK の場合もあるように思います。人々が上手さを求めてないというのか。ただ、韓国のシンガーはティーンの頃から缶詰の全寮生活で人権無視のトレーニングを受けてることも多く、芸能界はどこもそうかもしれないけど契約でがんじがらめの搾取構造があるのだと聞きます。そうなるとどっちがいいのか複雑ではあります。果たしてこうした違いは何に由来するのか。分からないけれども一つ言えるのは、素晴らしいことに若者たちの間では、昨今は日韓もお互いに好感情を持ってるようだということです。 では、クラシック音楽界はどうでしょうか。ジャケ買いがより横行するのは日韓どちらで、技術レベルはどっちが上なんだろう。これは敏感過ぎてとてもここで扱えないし、そもそも知りません。一般にそれぞれの国民性と言われるのは、韓国の人は感情表現がストレートで、年齢の上下にうるさく、情に訴えて家族重視の傾向があり、社会は学歴競争が激しくて言葉は濁音と破裂音を区別しない。ツがチュになっちゃう問題もある、など、色々あるでしょう。一方で、日本人の口から日本の国民性を聞くと「共生」とかのキーワードが飛び出して来ちゃいそうだけど、それは最近流行の「同調圧力」と同じことです。ひょっとすると、権威とメディアの統制圧が人々に具現化したものかも分からないけど、ひとまずは国民性だと思われてるわけです。でもこれら以外は兄弟国家の両国民、かなり似てないでしょうか。 音楽表現においては日韓で共通する二つの側面があるかのように感じます。まず、ひねりがなく真っ直ぐなこと。そして一皮剥くと演歌のメンタリティーが顔を出すこと。演歌というのは、換言すれば自己陶酔的な情緒纏綿のことです。自己憐憫が基調となる国民の生活環境は何かということはひとまず置くとして、韓国の場合はこれを言い表す特別な言葉があります。「恨(ハン)」というものです。上の階級による圧政に忍従しなければならなかった者の心のあり方だと本国では解釈されていますが、文字通りのただの恨みの感情ではなく、憐憫の心地良さを伴っています。なぜ辛いことが心地良いのでしょう。それは肯定的なものと同じように否定的なものも取り込むアイデンティティの作用から来ます。例えば自分の病気を誇らしげに語る人のことを思い出してみてください。痛気持ちいいのです。この「恨」という感情が韓国人と日本人の違うところだ、などと言う人もいますが、違わないと思います。演歌は韓国のトロットにそっくりです。由緒ある日本の社会的同調圧力が忍従に近いからでしょうか。中国にはまた少し別の感情の出し方があるかもしれないけど、こういう心情はどうも東アジアには馴染みの傾向なようで、音楽表現の中にそれが表れていても、恐らく西ヨーロッパの人は聞いてもそういうことだとは気づかないと思います。 さて、日韓とも、根っこの心情に演歌/トロットの泣きがあると言い切ってしまうならば、違いとしては韓国はよりストレート、日本の場合は何らかの力によってより優等生的に抑えられることもある、ということでしょうか。それでも全体に素直なところは共通(特にリズムにおいて)しています。こういう問題を国別に特定するのは恣意的な類型化に過ぎないけれども、それでも何となく特徴が見えるように思えるのは、韓国人の歴史観の土台やアフリカ系アメリカ人のブルー・ノートの響きに暗い物語が隠れてるみたいに、民族が持つ過去の体験の集積が無意識に人々を動かすからです。
以上はオザワさんとチョンさんの話ではなくなってしまった一般論です。ただ、世界の小澤は純水だと形容はしました。彼の場合は、演歌の心などはパターン認識ですり抜けてしまうような別の天才的な資質が関係するのかもしれません。そして我らがチョーナー、チョン・ミュンフンは真っ直ぐなところは同じで、同時に深く歌うところが見事です。具体的に見て行きましょう。 第一楽章ですが、ふくよかに、ゆったりめに入り、オーボエのビブラートがかかって艶かしいです。フレーズ語尾の延ばしが特に長めでしょうか。そして山なりの抑揚を付けて細部まで歌わせます。グレゴリオ聖歌の最初の主題からは楽譜通り少し速めますが、特にひねりはなく、真っ直ぐな抑揚です。作為は感じさせず、表情豊かで流れがあります。 緩徐楽章に当たるポコ・アダージョ部分では粘りはありますが、最初の部分はテンポがぐっと遅いわけではありません。スラーで持続的に変化させる感覚でもなく、大まかに強弱が付いて歌い方としてはわりと平坦とも言えます。でもそれは最初の提示だけで、その後はぐっと遅いテンポに持ち込み、粘りを見せたまま丁寧に歌って行きます。ただし抑揚のひねりや外しはやはりなく、途中で大きく音を弱めたりする表現は聞かれるものの、どこか素直ではあります。日韓の演歌節の話をしましたが、たっぷりとしているところは短調だったら「泣き」と表現できるでしょう。ちょっとこぶしが回る気がするところもあります。そういうことなのか、あるいはオペラが得意だから歌うのでしょうか。プラネタリウムで空を見上げるときの背景音楽のように、夜明けに向かって美しい星たちがゆっくりと回って行きます。本当にきれいです。心置きなくストレートに浸れる感じがコリアン・ホスピタリティだと思います。 第二楽章に入った三番目の区切り、スケルツォの部分では、変わってやや速めの引き締まったテンポになります。でも運びに乱れはなくて丁寧です。正攻法で完成度が高いです。展開部はさらに少し速めますが、やはり乱れません。後ろの方の静かな弦の部分では遅過ぎずに十分静かであり、滑らかな抑揚が乗ります。この楽章の一つの模範的な展開ではないでしょうか。 フィナーレの楽章は、オルガンの無理のない美しい響きで力強く入ります。テンポはやや丁寧さを感じさせる、中庸多少遅めという感じです。一歩ずつ確実に進めて行きます。中間部の静かなところではやわらかい抑揚を付け、よく歌わせています。ラスト手前では徐々に速め、だんだん加速して行ってまた緩めて、と揺らぎを加えます。最後の最後もテンポを揺らし気味にして堂々と終わります。全体を通して恣意的ではなく、しっかりと聞き応えのある見事な演奏だと思います。 1991年の DG 録音です。音響としては滑らかです。被ったような音から強く立ち上がる瞬間が多少デジタルっぽいとは言えるでしょうか。この指揮者が新たに就任したバスティーユのオペラ劇場での収録で、響きはいいけど残響は幾分少なめのようです。オルガンの重低音は出ています。でも驚くことに、これは Allen electronic organ と表記されています。地方のライヴではよく使う手だけど、エレクトーンの本格のようなものでしょう。この録音においてそういうことは全く感じさせません。 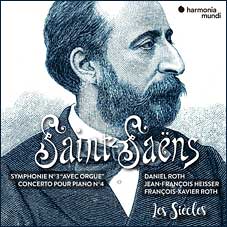 Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” François-Xavier Roth Les Siècles Daniel Roth (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 フランソワ=グザヴィエ・ロト / レ・シエクル ダニエル・ロト(オルガン) フランソワ=グザヴィエ・ロトは2000年以降に活動を始めた古楽の指揮者で、徹底して作品初演当時の楽器にこだわって演奏することでオリジナリティーを追求して来た人であり、なければ作らせてしまうほどです。このサン=サーンスの「オルガン付き」は、この曲で初めての古楽による演奏になるようです。1886年に初演されたこの曲に対して、そうしたアプローチが意味を持つのかどうかは専門的になり過ぎてよく分かりません。ヴァイオリンに関して言うならば、モダン楽器に置き換えられたと言えるのは19世紀のどこかの時点ですが、実際は時間をかけて変わって行ったようです。作家としては、イタリアではプレセンダやロッカといった人たちがモダン・ヴァイオリンを作り始めたとされ、それは19世紀の中頃のこと。20世紀半ばに至ってモダンの様式が確立されたと言われます。ただ、モダン弓の発明はフランスのトルテ(タート)で、この人は1835年には亡くなっています。そしてオールド・ヴァイオリンのモダンへの改造はパガニーニのガルネリの話などが有名ながら、フランスで多く行 われ、1820年頃から盛んになって40年頃にはほぼ完成されたとされます。音楽の担い手が貴族たちから市民へと移り、サロンからホールへと演奏の場所が変わることで大きな音量が必要とされたわけです。そうなるとこの「オルガン付き」は、現代の楽器でやってもよさそうなものです。それでもレ・シエクルとしては意味のないことはしないはずで、過渡期であったとは言えるのでしょう。 1971年パリ生まれです。最初はフルートで音楽を始め、指揮についてはガーディナーの助手を務めていまし た。2000年に指揮者コンクールで優勝した後、2003年には早くもこの古楽オーケストラ、レ・シエクルを結成しています。お父さんはこの録音で弾いている、オルガン奏者のダニエル・ロトです。私設楽団のオーナーではなく、どのような経緯があってこちらの楽団が結成されたのかはざっと調べただけではよく分かりませんでした。力のある人だと思います。 ロトの演奏はフランス人でありながら、一般にフランス的とされるようなものではないと言えるでしょう。古楽器のピリオド奏法なので、ノン・ビブラートによってまず弦などは直線的な感じがします。加えてバロック時代のようにロングトーン一音の中でのメッサ・ディ・ヴォーチェ様の山なりに盛り上げるボウイングはあまり聞かれず、その点でも真っ直ぐです。全体に抑揚が直線的で四角い印象があるのです。男性的な運びで、理論的な側面の強い人なのでしょうか。むしろドイツ人の生真面目な演奏にありがちな、リズムの角張った運びに多少近いのかなとも最初は感じました。エッジが立ち、鋭さがあります。そのように丸いフレーズではなく、短く切れの良い音を響かせるのは他の曲の演奏でも同じでした。それならば伝統的フランス風がどういうのかという話ですが、そうした類型化はもちろん曖昧なものです。大雑把なイメージで言えば、ゆったりに感じられることが多くてもべったりとはしない、やわらかで歌謡的な抑揚が波打つように付き、明るい音色で深刻ぶらず、人によってはリズムの不均等な崩しなどが聞かれる場合もあるという、軽く洒脱な感覚でしょう。スムーズで角ばらないので、大迫力は出難いというのが昔の平均的なフランス流儀だと思います。パイヤールやプラッソン、カントロフやデュトワなんか、そういうところがあります。ソロイストならもっといました。でも古楽の世界や若い人たちの間では尖って速い演奏も出て来ていますので、一概には言えなくなって来たようです。このサン=サーンスは力強くてダイナミックです。重さはあまり感じさせないけれども、新しい録音で迫力がある演奏をお探しの方にはもってこいの一枚だと思います。 楽章ごとに見ます。 出だしではゆったりめで、オーボエには表情があります。語尾は真っ直ぐ延ばし、第一主題からは中庸のテンポで進めます。波のように脈動的に動かすというよりも、細かく小節単位で表情を付けて行きます。ブロック単位というのでしょうか。情緒的な感じというより、分析的という方がぴったりする印象です。フォルテで盛り上がるところでは伴奏の連続したフレーズを短くスタッカート気味に揃えたりし、きびきびしています。弦はピリオド楽器なのでしょうが、バロックの作品のようにはあまり顕著にそれと分かりません。金管はフォルテで結構ドライな音に響きます。 ポコ・アダージョは直線的に歌って行きます。テンポは遅くはなく、動かしません。音量もある程度一定に保たれ、抑え気味の抑揚であって脈打たせたりしませんので、冷静な感じがします。粘って盛り上がるようなクレッ シェンドも加えず、あっさりしています。 スケルツォはメロディー・ラインがスムーズではありますが、少し速めです。間で区切ることなく颯爽と流し、きりっとした運びです。力の入る要所はスタッカートで攻めます。軽くおどけるというよりも、迫力で畳み掛ける感覚が勝っているでしょうか。 フィナーレは重々しいオルガンで迫力満点に始まります。震えがかかった大排気量の V型 NAショートマフラー・サウンドみたいに低くてばりばりっという硬めの倍音が独特です。ストップの選び方でしょうけれども、パリのサン=シュルピス教会のオルガンです。そこにヒーンと鳴くようなノン・ビブラートの乾いたストリングスがアルミの共振ノイズのように重なり、スピード感がいや増して、テンポは中庸だけどやや速めに感じます。ブラスは鋭く、シンバルも力強くて抜けが良く、フレージングは切れ切れで迫力満点です。ラスト手前では雷鳴のような打楽器も加わり、グレネードを持って走って行って爆発させるようであり、全てを出し切った大音響で悠然と終わります。これは好きな人はたまらないはずです。 2010年録音のハルモニア・ムンディ・フランスです。このレーベルとしてはちょっと異色な感じがします。バランスは良く、残響はあっても明晰です。やわらかく包み込むという感じではないけど低音は出ています。優秀な録音でしょう。強い音で弦と金管がややソリッドに固まるところはあります。それも却って迫力が増すでしょうか。全体としてはどちらかと言えば乾いた方の音響に感じるものの、弱音の弦はほどほど滑らかです。問題のオルガンの重低音ですが、出ています。大きくしておくと音程によっては窓が振動するぐらいです。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Marzio Conti Oviedo Filarmonia ♥♥ サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 マルツィオ・コンティ / オヴィエド・フィラルモニア ♥♥ これもこのサン=サーンスの「オルガン付き」でベストの一つではないかと感じた演奏です。珍しい指揮者と地方のオーケストラによるものですが、録音も新しいしオルガンの重低音も聞けます。指揮者のマルツィオ・コンティは1960年のフィレンツェ生まれで、二十歳のときにザルツブルク音楽祭でイ・ソリスティ・ヴェネティのフルーティストとして音楽のキャリアをスタートさせました。2001年からはトリノ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者となり、その後キエーティ(イタリア)の管弦楽団、ピレネーのアンドラ公国の国立室内管弦楽団を経て、2011から2017まで、このオヴィエド・フィラルモニアの首席指揮者でした。 オヴィエド・フィラルモニアはオヴィエド市のオーケストラとして1999年に発足したものです。オヴィエドはスペインの北部アストゥリアス州の州都で、フランスにも面した大西洋のビスケー湾に近い、位置で言えば四角いスペインの上辺の真ん中あたりにある都市です。 実に活きいきとした演奏です。 個々に見ると、導入部では1分05秒ほどのゆったりした出だしで、オーボエ・ソロの息遣いがいいです。最初の主題からはテンポを上げ、やや速めとなります。颯爽としていながら滑らかな運びで、フォルテの拍はきりっと切れの良い感触です。強弱の呼吸が自然ながらよくついて波打ち、表情も豊かです。カントロフなどのフランス勢の歌と比べるとより鮮やかでくっきりとしているように感じるのは、やはりイタリア的と言えるのでしょうか。 ポコ・アダージョですが、テンポは速いという感じでもないけど爽やかにさらっと流す方です。たっぷりした演奏に慣れていると少し物足りないかもしれませんが、決してそっけないものではありません。ふわっとした強弱の抑揚をつけ、情感の盛り上がりに敏感に反応して歌わせて行きます。弱音へと抜く扱いも見事であり、すっきりした明るい穏やかさがあって初々しいです。楽曲をしっかり捉える目とそれに応える表現力があるので大御所の演奏と比べてもむしろ味があると言え、今まであまり知らていなかった指揮者と地方の新しいオーケストラだとは全く思えません。オルガンの音の選択も、たゆたう弦も美しいです。後半は熱も感じます。 スケルツォはかなり速いテンポです。重さは感じさせず、ここも滑らかな旋律部と切れのよいリズムが同居しています。ピアノもくっきりとし、アンサンブルが揃って各部の音が明晰です。編成としてあまり大きくはないのでしょうか。分かりませんが、上手な室内楽団かと思うほど透明感があります。後ろの方に出て来るストリングスの弱音部分でもテンポをキープしつつ、表情豊かに次へとつなぎます。 フィナーレは少しくぐもった音色のオルガンで始まり、テンポは多少遅めとなります。明るいながら荘重な感じが出ています。最初の提示が終わった後のピアノのトレモロの部分はよく分解されて明晰です。全体に力づくで前のめりな感じはしないけれども堂々としており、リズム・セクションの切れもいいです。木管類は見事な歌をうたい、弱音部は思い切って静かに抑えます。最後まで落ち着いたインテンポで進め、ラスト手前で多くの指揮者が走って行かせる部分では無闇に駈けず、くっきりと鳴らして行く方法によって力強さを示します。そしてそのままの堂々たる終わり方です。 2014年の地元のホールでの録音で、レーベルはアカシア・クラシックスです。ワーナーの傘下にあるのでその表示となっています。弦の音が瑞々しく、ライヴな賑やかさやハイが前に出る感じがありません。若干オフで中高音に反響が乗る部分もあるので最優秀録音とは言いませんが、新しいだけに優秀です。オルガンについては詳しいことはよく分からないものの、重低音は出ています。フォルテがうるさくない程度のボリューム設定では比較的穏やかに鳴っており、家を揺るがすほどではないけれども、他と比べても十分な音圧があります。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Mariss Jansens Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ♥♥ Evita Apkalna (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 マリス・ヤンソンス / バイエルン放送交響楽団 ♥♥ イヴェタ・アプカルナ(オルガン) ヤンソンス盤もワン・ノブ・ザ・ベストです。デ・ワールト、プレートル、コンティ、次で取り上げるカントロフに加えてこれも挙げるとなれば一番がいっぱいになってしまいますが、性質が違うので甲乙つけ難いのです。このヤンソンス盤は華やかにして軽く滑らかなフランス流儀ではなく、ドイツ的というのか、より中央ヨーロッパ寄りの正統というのか、重厚で粘りのある歌の聞かれる演奏です。いつもの楽しい波長が前面に出ているものというよりも、深刻ではないけれども熱のこもった名演になっていると思います。 説明の必要もないでしょうが、マリス・ヤンソンスはラトビア(旧ソ連)に1943年に生まれ、2019年に残念ながら七十六歳で亡くなってしまった指揮者です。バーミンガムで輝いたほどではなかったとも言われつつラトルがベルリンを去った後、ミュンヘン・フィルを育てたチェリビダッケもおらず、同じミュンヘンの地にあってもはや実力において(何が実力かを決めるのは大問題ですが)世界の頂点に立っていたと言ってもいいヤンソンス。若いときのライヴでは大きな起伏を見せましたが、晩年は自然体で自発的な乗りを聞かせ、演奏自体を楽しんでいるようでした。 ヤンソンスにはここで取り上げる録音の前に94年 EMI の旧盤も存在しています。そちらはオスロ・フィルハーモニーとです。新しい方と比べるとトータルでの速度設定は大きく異ならないものの、熱量が少し穏やかで表情が薄い方に寄っており、より形が整ってるように思える一方で、アゴーギク(テンポ変化)に関してはメリハ リが逆にあります。緩徐楽章に当たる部分も、比べれば抑揚はおとなしくて平静さが感じられ、スケルツォでは走る部分があってより軽さも出ています。フィナーレのオルガンは音が重なって壮大であり、子音も華やかでこれ以上ないほど物々しい音響となっていますが、重低音は入っていません。アッチェレランドもよりはっきりしてい てメリハリが効いています。大体そんな感じでトータルでは録音も良好ながら、弦がフォルテで多少きついとこ ろもあって今回は見送ることにしました。 新盤の方を楽章ごとに見てみます。出だしはたっぷりとした抑揚でよく鳴らして入ります。テンポは中庸です。第一主題から切り替えて大きく加速するということはなく、自然に速める程度です。しかし自在に強弱をつける歌い方が堂に入っているというか、楽団が乗っている音がしてさすがです。弦は力強く鳴らし切っていてたわませるように熱が入り、伝統と自信を感じさせます。リズム・セクションは角は滑らかながら一音ずつ分かるように分解して進め、その上に乗る旋律の流れは大きく波打ちます。あまりフランス流には感じません。ドイツ的な重厚さ、音の厚みだと言えると思います。後半の盛り上がりは相当な熱量です。弾力があって力強く、でも力まず劇的演出をせず、自発的な印象があります。ブラスの厚みも見事で、これぞオーケストラの正統という響きでしょう。 静かなポコ・アダージョの楽章は、遅過ぎはしないけれどもゆったりめの運びです。ここもフレンチの軽さや何気なさではなく、静かながら生のオーケストラの深ぶかとした音響に浸れます。一音の中で、また音符をまたいで大きく有機的な強弱の息があり、やはり鳴らし切っている感じがします。「真性」という言葉が浮かびます。中間部はエネルギーがつまっていながらゆったり静かであり、伴奏のピツィカートが明確に縁取ります。そのまま後半へと雪崩れ込んで行ってもピツィカートは強調され続け、同じ音型の前半部分とは表情が違います。そして粘りのある大きなクレッシェンドで盛り上げて行き、重々しく閉じられます。 第二楽章のスケルツォは弾力のある瑞々しい弦で始めます。テンポは中庸です。一音もないがしろにせず最大限に鳴らして行く感じで、このやや重さのあるスケルツォもドイツ流儀と言えるでしょう。ベートーヴェンの「舞踏の聖化」を聞いているようです。途中軽く弾ませるパートでは弦が柔軟に動きを示し、でもおどけるというよりも真面目な音響となっています。アゴーギク面では走ったりする効果は使わず、足取りは終始しっかりと確実なものです。後ろの方の弦の弱音パートでもテンポは変えず、さらっと流します。 フィナーレの楽章は重厚なオルガンの響きで始まり、どっしりとしたリズムとテンポです。角張りはしないけど一音ずつが丁寧です。ピアノをオルゴールのようにくっきりとさせ、堂々と勇者の行進のように力強い拍を重ねて進みます。遅いままのインテンポです。ブラスは生っぽく潤いがあり、かといってシンバルは濁りません。後半で指示通りのアッチェレランドは多少見られるものの、全く走らないと言って良い表現でしょう。重く確実な足取りのままラストまで行って締め括りです。最後の音がすごく長く感じます。すぐにブラボーが入るもののフライングではなく、ぎりぎり楽音には重なりません。熱演です。重い重いと言い過ぎましたが、引きずるような重さではありません。 レーベルは自前の BR クラシックで、2019年ガスタイク・ホール収録です。潤いがあって弦も管も自然であり、生のオーケストラを感じさせるバランスで録音は大変良いです。オルガンの重低音は最大とは言わないけどしっかり出ています。出ているか出てないかで分けるなら出ている方です。  Saint-Saëns Symphony No.3 in C minor op.78 “Organ” Jean-Jacques Kantorow Orchestre Philharmonique Royal de Liège ♥♥ Thierry Escaich (org) サン=サーンス / 交響曲第3番ハ短調 op.78「オルガン付き」 ジャン=ジャック・カントロフ / リエージュ王立フィルハーモニー管弦楽団 ♥♥ ティエリー・エスケシュ(オルガン) カントロフ盤です。これもこの曲の演奏として最も魅力的に感じたものの一枚です。同じく新しいものとしてマルツィオ・コンティ盤もどっちが上とは言えないぐらい良かったけれど、これはフランスの香りが十分に感じられる演奏であり、歌わせ方のセンスとしては個人的には一番好きかもしれません。迫力こそをお求めの方にはお薦めしません。 ジャン=ジャック・カントロフと言えば、ヴァイオリン奏者として有名です。熱い演奏を好む人にはさほど人気ではないヴァイオリンかもしれないけれども、歌のセンスの点でラヴェルにせよモーツァルトにせよ、個人的には満点ぐらいに気に入ってました。洗練された抑揚で、あっさりめではあるけれど穏やかによく歌い、正にフレンチという感じ。でも生粋のフランス人だと思ってたら、調べてみると両親はユダヤ系ロシア人なんだそうです。1945年のカンヌ生まれ。ヴァイオリンと指揮の両方を同レベルでこなす人としては東京クァルテットの第一ヴァイオリンだったピーター・ウンジャンも思い浮かびます。派手ではないけど深く読んだ自然体の歌が大変良かった人で、どこか共通するところが感じられるのですが、このカントロフはウンジャンのように腕の故障で転向したわけではないものの、古楽のマンゼなどとは違い、ウンジャンと同じように「まさにあのヴァイオリンがそのままオーケストラになった感じ」という演奏をします。 リエージュ王立フィルハーモニー管弦楽団はフランス語圏ベルギーのオーケストラで、リエージュ以下、管弦楽団とか交響楽団とか、頭にワロンが付いたりとか色々な表記がありました。1960年の創立です。ラヴェルの友人でその著作があるマニュエル・ロザンタールが指揮者だったことがあり、フランソワ=グザヴィエ・ロトがいたこともあります。 第一楽章ですが、オーボエに表情はあるもののゆったり静かに抑え気味に入り、最初の主題からは中庸やや速めのテンポに切り替えます。抑えたところから鮮やかに盛り上げるような抑揚をつけ、派手にはならないものの音も明るめです。かすかな揺れもあって脈打つようにやわらかく、実に適切な表現に感じます。テンポは動かしませんが、その後は速めな感じはあまりしないでしょうか。全体としては自然で、滑らかさとこの人らしいセンスの良さを感じます。 ポコ・アダージョの部分は、テンポはややゆったりめで最初はさらっとしています。抑えた静けさがいい具合で、スラーの弦が丁寧で美しいです。ヤンソンスのように力を込めるわけではなく、コンティほども歌わせないかもしれないけど、微細な動きがあり、このくらいが理想という感じもします。十分に呼吸は深いながら、全体を通して静謐さ、繊細さで一番でしょう。最後の方のパートは非常にゆったりに聞こえます。ラストは息の長いクレッシェンドをして、それでいて品の良さを保っています。 第二楽章に入るとスケルツォです。テンポは中庸と言えるでしょうか。でもあまりスピードは感じません。丁寧に、しかし軽さがあって不器用にならない運びです。特に変わったことはしませんが、明るく繊細な音色が魅力的です。そして次の主題に入るとかなり速くなり、お行儀は悪くないけど軽快に跳ねます。弦のラインは滑らかにつなぎ、力が抜けていて心地の良いスケルツォです。後半は落ち着いており、いろんな細かい音符が聞こえて各部の音がきれいであり、適度に切れもあって感覚的な満足があります。最後のストリングスの静かな部分も特に遅くしたりはせず流しますが、静けさにおいては一番かもしれません。 フィナーレです。オルガンは劇的ではなく、音色のきれいさが際立つストップ選択のようで、運びも落ち着いたテンポで決して重なった大声になったりしません。迫力を求める人には物足りないかもしれないけど、この方が美しくていいです。もちろんトゥッティでの力強さは十分だと思います。落ち着いたインテンポで一つひとつ丁寧に磨き上げて行く設計なのです。個々には十分に切れる音符もありながら、全体には滑らかな雰囲気を失いません。 そうやってずっと落ち着きのある速度に抑えて行って、ラスト手前では一気に加速を見せ、起伏を付けます。そして最後は結構歯切れ良く盛り上がって終わります。常に重なった音の美しさに配慮されている演奏であり、終わった途端に力一杯ブラボーと騒ぎたくなるものではないでしょう。でも個人的にはうるさくてこの楽章が嫌いだったりする演奏がある中、聞いていて最も気持ちのいいものの一つでした。
全体を通して、♡♡をつけた中では最もフランス的なパフォーマンスだと言っていいのではないでしょうか。 スウェーデンのレーベル、BIS の2020年録音です。DSD のセッションです。繊細で透明度の高い優秀録音と言えます。反響は乗っており、ティンパニが轟いてトゥッティでの分解は最高度とは言えないかもしれないけ ど、全体に透き通っていて楽器が見えます。弦の音は大変きれいで滑らかです。バランス的には低音も十分出てい て、全体に潤いが感じられます。ただし、オルガンの重低音はほぼ出ません。そういう効果は狙ってないのだと思います。楽譜の指示に従えばそんなところでしょう。録音プロデューサーはイェンス・ブラウン、サウンド・エンジニアはインゴ・ペトリとなっています。 |