|
短調が悲しいのは生まれつき? / 古楽の愉しみ 2
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン / ルネサンス合唱曲など  このページでは古楽の CD を取り上げつつ、短調はなぜ悲しいのか、あるいは短調の曲を悲しく感じ、不協和音を不快に思うのは人に元々備わった感覚か否かという、いつも話題になる議論についてもちょっと覗いてみよ うと思います。 「短調が悲しいのは生まれつき?」の議論に関心のある方はこちらへ 古楽とは 「古楽」early music という区分は、バッハなどのバロック時代を含んだそれ以前の音楽、という理解でいいのだと思いますが、クラシックの演奏家と大方のファンにとってはバッハぐらいは普通に弾き、聞くレパートリーとなっているので、より本格に古楽に突っ込んでる人となると、バロックよりも前の音楽を愛好しているような状況だと思います。そうすると、有史以来、記録の中にぎりぎりその影を追える最初期の作品から、中世、ルネサンスの音楽ということになります。そして、その古楽を取り上げるのは難しいです。なぜなら専門知識が必要な分野だからです。仮にここで扱っても、古楽の先生の講演会場の外で項目だけ書かれた案内チラシを配ってるアルバイト生のようになってしまうでしょう。この分野がどうしてそんなに学術的様相が強いかと言えば、資料が探し難いことに加えて、背中合わせながら、携わる人口が少ないからでしょう。どんな分野も本来学問として成立するわけですが、誰であれ古楽について解説するだけでどこか 学者みたいになれます。 二つ前のジャズの記事でクリストバル・デ・モラーレスの曲を使っている CD を取り上げました。スペインはルネサンス期の古楽の区分に入る作曲家です。それもあって、あえて似非(えせ)学者風になることを恐れずに古楽も取り上げる ことにしました。グレゴリオ聖歌は前の記事で触れましたので、内容はヒルデガルト・フォン・ビンゲンからルネサンス後期の合唱曲までです。途中が飛びま す。 そもそも古楽ブームと言えるようなものが来たのは1960年代でしょう か。70年代には古楽器を使った演奏が盛んに録音されるようになります。曲の発掘 と演奏流儀の再発見は車の両輪で、バッハの曲はメンデルスゾーンからカザルスに至る人々の活躍でそれ以前に復興されていましたが、あのヴィヴァルディです ら長らく忘れられていたものが再び日の目を見、本格的に研究が始まったのは4、50年代であり、四季の出版こそ1725年だけれども最初の録音は1939 か42年 (異説あり)で、有名になったのはもっと後です。日本で人気が出たのはイ・ムジチからでしょ う。  ヒルデガルト・フォン・ビンゲン 天啓の音楽 グレゴリオ聖歌の成立以降で多声になる前の古楽の中では、12世紀のヒルデガルト・フォン・ビンゲンの曲が大変印象的です。女性が作った同じく単旋律の 合唱曲ですが、ヒルデガルトが予言者のように存在の向こう側を見透す体験を重ねていたことに関係があるのか、どこか深遠で心洗われるような響きに聞こえる のです。この人のその超常的な体験以外でもう一つのキーワードとなるものは、女性の復権ということです。女性で史上最初の作曲家のように言われたり、キリ スト教会の権威に最初の頃に認められた女性であることが、この現代という女性原理が最も必要とされている時代に響くのでしょう。 ヒルデガルト・フォン・ビンゲンは1098年生まれで1179年に81歳ぐらいで亡くなった、今で言えばドイツの、当時は神聖ローマ帝国の修道女です。 女子修道院を作って院長になった人と言った方がいいでしょうか。貴族の出ですが修道女に育てられ、幼少期から幻視体験があり、シトー派を育てたことで有名 なクレルヴォー(北フランス)の聖ベルナルドのとりなしもあって教皇にも認められた正統の人でもあります。女性が中世のカトリックの位階の中でどれほど認 められたのかは分かりません。タロット・カードの女教皇は直感や叡智を象徴しますが、反ローマ教皇の意味もあります。その元となった女教皇ヨハンナは実在 したのでしょうか。何種類もの話があることから女性の地位回復を願う無意識の悲願があったことは確かでしょう。本当だったにせよ、伝承の一つには出産で発 覚して殺されたというのもあります。ましてや予言者のような超常体験をする人が教会権力に認められることが難しいことであったのは想像に難くありません。 旧約の時代では霊媒のようなことをして偽予言者とされれば石打ちで殺されましたし、彼女の時代前後から異端審問による処刑は行われるようになっていまし た。教会権力というよりも民衆が中心となったとも言われますが、占いのようなことをして一度疑われたら火あぶりにされる凄惨な魔女狩りがもう少し後の時代 には大規模に起こります。 なぜこういう話をするかというと、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンが体験したという予言者のような幻視は、一般的には特定の宗教教義には収まらないもの だからです。憑依型だったり覚醒型だったりと時代と場所によって霊媒的な現象はその中心スタイルが変化するものの、自覚的だったケースでは光が感じられた り、全ての条件を超えた幸福感に圧倒されたり、叡智ある存在が語りかけてきたりします。しかし例えば三位一体のように会議で決まって他派は別のことを信じ ているような分割されたセグメントの一方だけの考えをその叡智が支持することはありません。もしあったとしたら、それは最大限に解釈したとしても伝え手が 受け手の立場や限られた理解力に配慮した形で伝達してくれるケースも想定できるからだろうし、ほとんどは体験後に概念的解釈によって予言者本人が既成の教 義の枠に嵌め込んで考えるからです。自覚してそうする場合と、本人も信じてそう思う場合があると思いますが、その境界線を引くのは難いことです。ヒルデガ ルトの場合はどうだったのでしょう。 こうした超常体験というものは、現代の英語圏では便宜的にクレヴォヤンス(光や光景などを見る幻視)、クレアオーディエンス(言葉のように伝えてくるも の)、クレアセンティエンス(推論を通さず感じること)などに分けられるようです。記録によるとヒルデガルトの場合は光を見たり導きを聞いたりしているよ うですから前二つは少なくともあったわけです。しかしこれらは現実の器官である目を通して視覚認識されるのではなく、耳を通して言葉として聞こえて来るも のでもありません。もし自国語や方言で聞こえたと思っても、それは自分の中の言語機能を使ってラジオのようにデコード(再現)されたものです。 体 験後、ヒルデガルトは「キリストの花嫁」や「マリアの処女性」を大切に考えたということですが、それを例えばマリアの肉体が処女であったという卑近な 意味に解すると見落とすことがあるでしょう。1950年にカトリックが「マリア被昇天」を認めたことをユングが喜んだという話がありますが、それは理性 (自我)の男性原理による人類の長い支配が徐々に終わりに近づいていることを象徴していました。ユングは臨死体験者であり、 ある種の超常能力者でもありますから、経験的推論でそんなことを言っていると考えるのは当たらないと思いますが、地 球環境の無制限な開発という問題でも彼の言う変化は待ったなしのところに来ています。単に女性の権利の拡大と平等を訴えるフェミニズムの観点だけでは捉え 切れない潮流なのです。キリストの花嫁という問題も、キリスト意識を体現してそれと一つになるという無原罪の意味で捉えると「無自我」のことになり、マリ アの処女性というのも無原罪の比喩ですから、単にマリアを母親のように思慕するという感覚ではなく、自我の支配(≒男性原理)を超えて行くあり方を問題にしていることになります。 ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの歌のテーマはケルンの守護聖人、聖ウルスラのことがほとんどと言っていいぐらいです。ウルスラとは何でしょうか。これ は実在の人物ではなかったのではないかと今は考えられているイギリスの王女で、1万1千の処女とともに巡礼の旅に出て、その全員と共にフン族に殺されてケ ルンに埋葬されたとされる人です。キリスト教においては長らく聖人として扱われてきました。1万1千という数も、人名や11というローマ数字の読み間違い だとか、聖人の骨を売る商売が繁盛してたくさん売れたことの言い訳だとか言われるようですが、火のないところに煙は立たずなので、何か歴史的な事件があっ たのかもしれません。そしてヒルデガルトは女子修道院という団体を多くの殉教者になぞらえて教化したのかもしれません。フン族は男性原理でしょう。独身の 女子に生きる場がなかった当時の社会の中にあって、多数を導く大きな責任もあったことと思います。事実、次の世紀のフランドルでは女性たちの互助組織、ベギン会が必要とされたのです。 またヒルデガルトは「神のものは神へ、カエサルのものはカエサルへ」を徹底させた人でもあり、光の向こう側 には無境界の愛しかないことを体験で知ってはいたと思いますが、キリスト教会の位階や身分社会のあり方を認め、こちら側の教義と制度の中で自身の教えを説 きました。それでもその音楽からはそうした現実的平衡の精神を超えた何かが聞こえてくるような気もします。その上でその音楽の手法は、天啓によるもので あったにせよ、当時の様式であるモノフォニー(単旋律)聖歌の形から踏み出ることはありません。  Hildegard von Bingen Voice of the Blood Sequentia ♥♥ ヒルデガルト・フォン・ビンゲン / ヴォイス・オブ・ザ・ブラッド / セクエンティア ♥♥ ヒルデガルト・フォン・ビン ゲンで最初に感銘を受けて、その後もやはりこれが一番と思ってよくかける一枚です。歌っているセクエンティアはドイツ・ケルンで バーバラ・ソーントンらによって1977年に結成されたグループで、この作曲家の今の人気を確立させた人たちと言ってもいいでしょう。取り上げられている 曲はケ ルンの守護聖人ウルスラと1万1千の処女がアッティラたちフン族によって皆殺しにされてしまったという伝説に基づいて作られたものです。特に最初の一曲、 「おお血の赤さよ」(O rubor sanguinis)は 大変印象的です。他の演奏者の同曲もいくつか聞きましたが、透き通った音を力強く延ばすのはこれだけで、圧倒されてしまいます。その強い高音は音の浄化と いう感じもします。ここはヘザー・クヌートソンが歌っています。歌詞は血の赤さについて「決して汚されることのない神性の花」と讃えていますが、虐殺され 殉教した者の姿について語っていると同時に、確固とした女性性によって天と人間を繋ぐより高い原理について示唆しているのだと思います。 グレゴリオ聖歌とはまた 違った癒しの音楽としてその後人気が高まり、現在は多くの録音が行われていますが、これはその魅力が決して褪せない最高の一枚だと思います。ドイツ・ハル モニア・ムンディ1994年の録音で、ケルンのWDR(西ドイツ放送)との共同製作盤です。グループはこの作曲家の全作品を網羅した9 枚組の全集を出しており、それ以外に一枚ちょっとの値段で買える8枚組のセットや個々のアルバムも手に入ります。それらの中にはモノフォニーを中世風のハーモニーに仕上げているような曲や、楽器が出てくるものもあります。  Hildegard von Bingen 11000 Virgins Anonymous 4 ♥ ヒルデガルト・フォン・ビンゲン /11000の処女 殉教者 / アノニマス4 ♥ こちらはニューヨークを本拠地とするアメリカの四人グループ、アノニマス4の演奏です。やさしく、やわらかく歌うところに魅力があります。少人数の透明な軽 やかさがとてもいいのです。思わずこちらから耳が聞きに行く感じで聞き 惚れます。このアルバムも上記のものと同じく1万1千人の殉教した処女 たちをテーマにした聖ウルスラの祝日の聖歌を集めていますので、「おお血の赤さよ」も聞くことができます。セクエンティアのところでは他にないなどと言いました が、矛盾するようですがこういう清らかな静けさもいいものです。力が抜けてリラックスしています。ヒーリング効果を狙って静かなグレゴリオ聖歌をかけるなら、このアルバムにするのもいいのではないかと思います。 1997年ハルモニア・ムンディ USA の録音です。  Hildegard von Bingen Hortus Deliciarum (Chants Grégoriens Du Xlle S.) Brigitte Lesne, Discantus ヒルデガルト・フォン・ビンゲン他 / ホルトゥス・デリキアム(12世紀のグレゴリオ聖歌) / ディスカントゥス / ブリジット・レーヌ フランスのボーカリストで様々な楽器をこなし、中世音楽の指揮もするブリジット・レーヌ率いるディスカントゥスの演奏です。 1989年結成の六人〜九人から成る中世音楽に特化した女性ボーカル・グループです。 タイトルにあるように、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンだけでなく、作者不詳のグレゴリオ聖歌が入っています。ヒルデガルトは四曲です。 上と同じく「おお血の赤さよ」(O rubor sanguinis)が入っています。ソロで歌い(キャサリン・サージェント[s])、テンポはそこそこ速くて語尾のフレーズを延ばし過ぎません。 セクエンティアとアノニマス4を両極とすると中間的で、さらっと歌うので別の曲のようです。 二声で和音を聞かせる試みもあります。下のパートが伴奏とし て何度か同じ音を続けて歌い、フレーズ単位で音程を変えて行くもので、声質は違いますがブルガリアの地声の民族合唱のような展開です。それ以外にも一音ごとに平行して5度で行くもの(オルガヌム) もあります。テンポは適度で残響はありますが、少人数でやはり被らない澄んだ音です。 1998年オーパス111年の録音で、現在ナイーヴ・クラシークから出ているのが上掲の写真です。オリジナルは黄色い空をバックに緑の地面 から木が生えている絵でした。 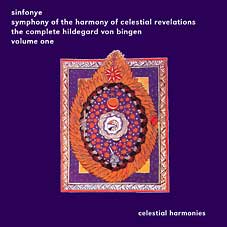 Hildegard von Binven Symphony of the Harmony of Celestial Revelations, The Complete Hildegard von Binven Volume One Sinfonye ♥ ヒルデガルト・フォン・ビンゲン / 天啓の調和によるシンフォニー / シンフォニエ / スティーヴィー・ウィッシャート ♥ 1986年にスティーヴィー・ウィッシャートによって設立されたオーストラリアの中世音楽に特化した古楽グループ、シンフォニエによる演奏です。 最 初に出てくるバグパイプのように響く楽器はハーディ・ガーディでしょうか。木製ホイールが弦を擦って鍵盤で弾く中世の楽器ですが、別名シンフォニアとも言 うようなので、グループの名前みたいです。 合唱は高く軽やかな少女のような声質で美しいです。ここでも「お お血の赤さよ」が歌われますが、やはりハーディ・ガーディの長い前奏が付きます。歌の部分はソロで、倍音の響く通る声で割合ゆったりと歌われます。どの声 も清らかな印象なのがこのアルバムの良いところだと思います。低音部の持続による和声も試みます。合唱の一部では11人(1万1千人)の乙女たちを印象づ けるのでしょうか、非常に高い声のパートを本当に少女のような声が歌います。 1995年の録音でレーベルはセレスティアル・ハーモニーズ。イギリスのトッディングトンの教会で収録されました。こ こではメンバーにオックスフォード女子合唱団のメンバーも加わっています。これは第1巻で、他にも出ています。  中世の音楽 6世紀から15世紀頃の音楽を中世の音楽と呼びます。グレゴリオ聖歌もヒルデガルト・フォン・ビンゲンも時代的には中 世ですが、9世紀頃になると多声の音楽が始まり、12世紀頃には盛んになってきます。中世の作曲家を大雑把に有名なところだけ記します: レオナン [12世紀] 、ペロタン [12〜13世紀](ノー トルダム楽派/アルス・アンティカ) [オルガヌムという、主旋律に対して4度や5度上をなぞるように歌う形式が出て来た] ギョーム・ド・マショー [c.1300 - 1377](仏/アルス・ノヴァ) [これ以降リズムが複雑なものになる] 次には連続的にルネサンス期が始まりますが、これも参考までに途中までを記します: 初期 ジョン・ダンスタブル [c.1390 - 1453](英) ギヨーム・デュファイ [1397 - 1474] 、ジル・バンショワ [c.1400 - 1460](ブルゴーニュ学派) 中期 ヨハネス・オケゲム [c.1410 - 1497]、ジョスカン・デ・プレ [1450/1455 - 1521](フランドル楽派) 後期 オルランド・ディ・ラッソ [1532 - 1594](フランドル楽派) [以降調性感が強まって行く] 中世音楽の音の特徴 グレゴリオ聖歌の後でバロック時代の前というと、中世とルネサンス期の音楽ということになりますが、ここを大雑把に分けるならばルネサンスの後期とそれ以前とでちょっと印象が違います。 グレゴリオ聖歌は単旋律で和音がないところが静かな癒しの音楽という 感じでした。それ以降は和音が聞こえてくるわけですが、現代の我々に馴染みのある音 に聞こえるのはルネサンスも後期になってからという気がするのです。大雑把な説明ですが、我々の音階の基礎であるド・ミ・ソをベースにしたルネサンス後期 以降の音楽に対して、それ以前の音楽は真ん中のミの音が抜けてドとソ(5度)が鳴ってるような印象です。ソだけでなくて、ドとファ(4度)のこともありま すが、いずれにしても真ん中が抜けている感覚は独特です。厳密に言えばこの感覚はイギリスの作曲家、ダンスタブルがドに対してミ(3度)の音を使う流儀を 大陸に伝えた時期から考えて中世までの話であって、ルネサンスも初期からは今のド・ミ・ソのハーモニーということになりそうです。でも聞いた感じでは後期 まではまだこの独特の感覚が多く聞かれるのです。ダンスタブル自身の音楽もミの音は響くけど使い方は限定的で、今とは違って終わりの音は真ん中抜けだった りもして、どことなくモノトーンな感覚に聞こえます。ボリビアの部族社会の人がそうした完全5度の和音をきれいだと感じるという話はあり、我々も同じで しょうが、どこか超然とした音であることに変わりはありません。 理性の優位と5度、 4度 これは5度や4度の二 音には調性感がなく、長調にも短調にも聞こえない、したがって楽しくも悲しくもない からなのです。ではどうして中世の音楽がそういう音になったかといえば、それは頭で考えた理屈によって生まれてきたものだからだと言えると思います。5度 や4度は振動数比がそれぞれ2:3と3:4という整数倍になります。当時の楽譜に残っている音楽は教会の音楽なので、きれいな比率は神の摂理に相応しいと いう発想になっていました。1度(同じ音二つ)や8度(オクターブ)なら振動数比はもっと割り切れるので、より純粋だということになります。この理屈を最 初に発見し、尊重したのは古代ギリシャのピタゴラスだとされています。それが中世になって実際に1度、4度、5度、8度(全て「完全協和音」と呼ばれま す)が神の音程として推奨されるようになりました。4度(ド→ ファ)についてはルネサンス期前後にはっきりしてきた対位法という発想では「解決」を必要とする不協和音ということになってくるし、5度も並行して連続使 用することは後の時代には避けられるようになって行きますが、中世においてはそれが正しかったわけです。つまり聞いて感じる感覚や感情によって決めるので はなく、神学的な理性によって音が決定されていた面が強いと言えるでしょう。 こういう理性優位は何 も昔の時代の特許ではなく、現代の音楽にも見られます。いつも出す例ですが、十二音技法などは調性に縛られない無調の音楽を作ろう とする理性によって生まれたので、一度ドを使ったら他の音が全部使われるまではもう一度ドが出てこないように「音列」というものを設定して、結果的に感覚 や感情に訴える要素が無くなってきます。実験的なジャズでもそうです。そうなると、十二音技法も中世の神学的に純粋な音楽も、特別慣れない限りは、今の 我々には「どれも同じように聞こえる」ことになりがちです。 では古代ギリシャの時 代はどうでしょう。ピタゴラスが言う完全5度のように純粋なハーモニーだけが奏でられていて、音楽に感情的な要素はなかったので しょうか。どうもそうではないようです。プラトンやアリストテレスなどの哲学者は音楽を倫理と結びつけ、そのあるべき姿を論議したりしてはいたものの、一 方でその当人たちが「リラックス」や「悲しさ」などを感じさせる特定の音楽のモード(≒音階)が存在するとも語っていました。我々が悲しいと感じる短音階 (エオリアン)が古代ギリシャでそのまま使われていたわけではないですが、それでも長調系の音階を幸せ感に、短調系の音階を悲しみに関連づけて感じていた 可能性は完全には排除できないと思います。長調系、短調系というのは、音階の最初の音と第3音との間が長3度か短3度かということで、どうしてそうなるか という話は後からしますが、それぞれ一音の間隔全部が全音のド→ミと、半音が混じるラ→ド(もしくはド→ミ♭)の間隔になります。しかし実際にプラトンが 語っていたのが音としてどういうものだったのかは、音階の運用が今と違っていたこと(別枠で触れます)もあってはっきりしません。確かめてみたいもやまや まなのですが。 因みにそのように二つ の音階を分けて使うのは何も西欧だけとは限りません。厳密なイオニアン(長音階)とエオリアン(短音階)ではないですが、長調系と 短調系の音階を別に持つ文化は世界の他の地域にもあります。明治になって西洋音楽が入って来る前の日本でも、雅楽の音階の中にすでに調子の別はあったよう で、民謡にもあります。アラブの音楽はまた独特の短調に近いものに我々には聞こえます。しかしこれらの調子と感情面とのつながりを解き明かして西洋の音階 と比較するのは容易ではないので、現代我々が馴染んでいる長調/短調という概念はこの記事ではとりあえずヨーロッパ発ということにしておきます。 古代ギリシャの音楽に ついては字体を薄くして以下にまとめておきます。詳細に興味のない方は飛ばしてください。 古代ギリシャの音階 プラトンやアリストテ レスの著作の中には、特定のモード(ハルモニアイ≒音階)とそこから喚起される感情の種類についての記述があります。主なところをちょっと要約してみま しょう: 「ミクソリディアンとシ ントノ・リディアンのモードは悲しみを表現し、フリギアンは平和、尊厳、節度を表して礼拝に向き、イオニアンとリディアンはリラッ クスしてやわらかく、酒を飲むとき用であって軍隊では禁じられるべきであり、ドリアンは誠実さの感覚を生み出し、危機と戦争においての使用に合っていて戦 士にふさわしい」(プラトン「ラケス(または勇気)」、「国家」) 「ミクソリディアンは悲 しく厳粛にさせ、フリギアンにはバッカスの激しさがあって熱中・興奮させて感情的にし、イオニアンとリディアンなどのリラックス (弛緩)させるモードは人々をぼけ(stupid)させ、ドリアンは心を落ち着け、厳粛で男らしく(勇ましく)して行き過ぎを防ぐ」(アリストテレス「政 治学」) 二人の意見はフリギア ンのニュアンスが違うけれども後は同じようです。このフリギアンだのミクソリディアンだの言っているのは音階の名前で、現代ではそ れぞれミ(E)から始まったりソ(G)から始まったりする白鍵の1オクターブのことであり、順繰りに7種類あります(ミとファ、シとドの間が半音になるの で始まる音の位置によって印象が変わります)。プラトンは音楽が楽しみをもたらすかどうかで善し悪しを判断されてはいけないと語っており、男らしさや市民 の道徳的義務のような理念で考えているところに違和感を覚えますが、逆に言えば楽しみのために音楽を追求する人(アリストクセノスがそうだという人もいま す)もいたということでしょう。古代ギリシャの時代に悲しみを表現したり感じさせたりする音楽があったというのは面白いことです。 具体的にはミクソリ ディアンが悲しいモードだと言っているわけですが、ミクソリディアンは現代のスケールで言えば「ソラシドレミファソ」で長調系の音階 です。しかし中世の神学者が資料を編纂したときにずれてしまったので、ギリシャ時代のミクソリディアンは現代のロクリアン、「シドレミファソラシ」だった だろうとされています。こちらは一応短調系の音階となります。そしてそれに関しては短調系ということですから悲しいとも言えるかもしれませんが、フリギア ンの方は今のドリアン、リディアンは今のイオニアン、ドリアンは今のフリギアンという具合に翻訳してみると、彼らの言っていることは感覚的には今一つピン とこないところもあります。どうしてでしょうか。 ギリシャ時代にはテト ラコードというもののあり方によって全音音階(ダイアトニック)の他に半音部分が増えた音階(クロマティック)、四分の一音が混 じった音階(エンハーモニック)も存在しており(アリステイデス・クインティリアヌス Aristides Quintilianus の記述)、表し方も上昇ではなくて下降だというように音階そのものに違いがあります。それらをどう運用していたのかは良く分からず、音階だと思われたモー ドの名前は実は7弦のライアー(竪琴)の調弦の種類名だと考え、それをテルパンドロス(古代ギリシャの詩人・音楽家)の調弦法から再現してみようとする人 もいます。 また、第一音を根音と しているのではなく、音階途中の音が基本のキーになっているように聞こえる例もあります。地中海に近いトルコの町で発見された紀元 前後の「セイキロスの墓碑銘」は、墓石に古代ギリシャの音符記号と歌詞が刻まれていて世界最古の曲の手掛かりだと言われてますが、全音音階の古代フリギア ン (またはイオニアン)旋法で書かれているとされます。音にしたものを聞いてみると: ソレー・レー、シドレ ドー/シードレドシラソー、ラファー/ソシレドシドシソー、ラファー/ ソシラドレシソソー、ソ ミレー と聞こえます。♯や♭ がないように移調して書きましたが、ギリシャ時代のフリギアンの音階は今のとは違ってレミファソラシドレです(古代イオニアンなら ドミファソまたはシドレミソラ)。確かに最後はレで終わっていてスケールとしては古代のフリギアンと言えます。しかしフリギアンは始まりと第三音の間が短 3度なので短調系の音階なはずですが、これを聞いているとト長調のように聞こえます。というのは最初の一単位のフレーズが「ソレー・レー、シドレドー」な ので、ソから始まっている音階のように現代の我々の耳には聞こえるからです。そしてその変奏も含む基本単位のフレーズに、付け足したように「ラファー」や 「ソミレー」の下がり尻尾が生えている構造に感じるのです。そこではファに♯が付いてないのでト長調ではないことが分かり、終音はミレー、と下がってくる のでレから始まった音階なのか(?)となります。墓碑銘なので悲しんでいるのかどうかは分かりませんが、歌詞は普遍の真実で、「生きてる間は輝いてほし い、人生は束の間だから」という内容を歌っています。 一方で「古代ギリシャ の音楽」という CD も色々出ていますが、それらを聞いてみると中近東風の音階や日本の琴の調子に近いものだったり、どこか現代音楽風のもの、あるいはもっと調性感の出たもの まであるという具合で、解釈者によって違いが出てきます。このように、ギリシャ時代の音階が感情とどう結びついていたのかを知ろうとしてプラトンの言葉に ついて考えてみても一筋縄で行かず、色々な解釈の余地が出て来てしまうのです。 古代ギリシャの音楽 中世の項目なので前後しますが、少し古代ギリシャ音楽の CD を挙げます。  Musique de la Grèce Antique Atrium Musicae de Madrid Gregorio Paniagua 古代ギリシャの音楽 / アトリウム・ムジケー古楽合奏団 / グレゴリオ・パニアグア 古代ギリシャ音楽の CD については、出て来ている演奏の多くがイマジネーションで補っていると言えるでしょう。前述のようにいくつか資料はあるし、音階についての記述やギリシャ 記号による音符もあるわけですが、細かいことは分からないのです。 これは懐かしい録音です。以前は LP でも発売され、日本でも話題になりました。特にびっくり仰天、目の覚めるような音から始まるのでオーディオ・マニアに受けるという面もありました。本当に こんな音楽だったのか、と思わないでもないですが、こういうものとして は先駆けであり、今や古典的な一枚になりました。1964年にスペイン人の僧グレゴリオ・パニアグアによって設立されたマドリッドの古楽アンサンブル、ア トリウム・ムジケーの演奏です。ハルモニア・ムンディ・フランスの盤で 1978年のアナログ録音です。ギリシャの音楽としては現在は他にも色々出ていますが、まず代表として挙げておきます。  The Ancient Greek Modes Michael Levy 古代ギリシャの旋法 / マイケル・レヴィ こちらはイギリスのライアー(竪琴)の演奏者で研究者、作曲家のマイケル・レヴィが古代ギリ シャの音階のそれぞれを鳴らしてみせているアルバムです。古 代ギリシャの音階は、中世以降現在まで共通となっている音階とは名前が同じでも中身が違います。それぞれを実際に聞いてみることのできるこの CD は当時の音楽を考える際に大変参考になるものです。プラトンやアリストテレスがそれぞれの音階とそれによって引き起こされる感情との関係について言及して いることに触れましたが、それをこれで検証してみることもできます。ただ、我々の耳には悲しい音に聞こえると彼らが言っている(古代)ミクソリディアンよ りもフリギアン・モードの方が短調で悲しいように聞こえたりして、なるほど納得、とも行かないようです。モードの解釈が間違っているか運用法が違うのか、 プラトンの感性がずれていたのか、あるいは我々の感覚とこの時代の人々のそれとが異なっていたのか、結論は出ません。しかし面白いのはここでは和音を使 い、その中には長調や短調の要素を成す長3度、短3度の音も含まれていて調性感が出ていることです。リディアン・モードでレヴィが再現している音楽は全く の長調です。古代ギリシャではグレゴリオ聖歌のように単旋律の音楽だけで和音は使われてなかったと考える方が不自然ですが、資料として残っているのは単旋律の音楽と個々の音階だけで、当時の和音のことは分 かっていないわけです。したがって本当はどんなだったかということは、やはり想像の域を出ません。 マイケル・レヴィはこれ以外にもたくさん CD を出しており、古代ローマ、エジプト、ユダヤなどのライアー音楽再現の試み、キタラー(ライアーの一種)による演奏、そして同じ古代 ギリシャでも複数のアルバムがあって、アポロやヘルメスに捧げるものから、前述のセイキロスの墓碑銘も演奏していて音階の見本ではない楽曲もあります(The Ancient Greek Lyre)。もちろんこれらも古代に忠 実かどうかは誰にも分からないことなので、彼は自身の音楽を作曲による再創造と位置づけているようです。その演奏には古楽器ブームの頃によく聞かれた、フ レーズを幾分途切らせながら進むような好みがあり、途中で頻繁にグリッサンドを下降片方、もしくは往復でポロロロンとかき鳴らす癖もあって、案外私にはど の文明の音楽もマイケル自身の音に聞こえました。それでもギリシャといえば竪琴のイメージがある上、きれいな音で騒々しくないので、この種のものとしては 聞きやすいと思います。 2010年リリースですが、フィジカル CD は現在は扱っておらず、MP3〜FLAC ロスレスまでのダウンロードのみのようです。 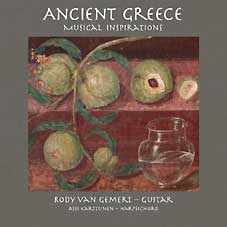 Ancient Greece Musical Inspirations Rody van Gemert (g) Assi Karttunen (Hc) ♥♥ 古代ギリシャ音楽のインスピレーション / ロディ・ファン・ゲメルト(ギター)/ アッシ・カルトゥネン(チェンバロ)♥♥ 古代ギリシャの音楽といっ ても、どのみち誰かのイマジネーションによる再現なので真実は知り得ないのです。ヒルデガド・フォン・ビンゲンのような時間を 超越した霊感があって過去の音が聞ける人が出て来れば話は別ですが。そうでもないならば、学者的な感性の人よりも根っからのミュージシャンにやってもらっ た方が生きいきします。現代的な和声だと嘘のように思えるからにせよ、アラブ風やガムラン風だった りする怪しげなリアリティも考えものです。何かもっと楽しめるものはないでしょうか。 そこで見つけたのがこのア ルバムです。ロディ・ファン・ゲメルトというオランダ系フィンランド人のギタリストがアッシ・カルトゥネンという女性ハープシ コード奏者と組んで自由に演奏しています。解釈としてはギターということもあり、ちょっとスパニッシュなスパイスかもしれませんが、二人は北欧の人たちな わけで、 ジャズの ECM から出ていてもいいかという路線でもあります。これは本当に「音楽」です。ポルトガルの現代ファドの器 楽演奏かブラジルのジスモンティあたりとのコラボレーションかという感じかもしれません。オ リジナル楽器にこだわるならリュートの仲間であるパンドゥーラというものを再現して臨むべきなのでしょうが、それはともかく、ここでは古代ギリシャの音楽 を再現しようとしたものから、ギリシャ音楽にインスパイアされた全くの即興によるものまで様々なグラデーションで描かれます。個人的に好きな作曲家ラヴェ ルに捧げた「ラヴェル風に」という曲もあり、ラヴェル自身の「五つのギリシャ民謡」という歌曲を編曲したものも聞けます。そしてこのアルバムでも世界最古 の音楽「セイキロスの墓碑銘(エピターフ)」が取り上げられていて、モチーフとして最初と最後に置かれています。前述の「ラヴェル風」に、も正確には「セ イキロスの歌・ラヴェル風に」です。チェンバロの音も大変美しく、ギターと掛け合っていると二つとも良く似ており、何の音だろう、とツィターかハープの仲 間を想像しながら古代を思い描いてしまいます。 あまりに創造的で美しい音 楽なので音楽史の趣旨を超えてお勧めしたいですが、CD そのものが欲しい場合は今のところ元のレーベルから直接買うしかなさそうです。今回はそうしました。でもMP3であれば各国で手に入り、日本でも複数の大 手サイトからダウンロードできます。フィンランドの、ピルフィンクというのでしょうか、Pilfink Records レーベルで(JJVCD182)2015年ヘルシンキの教会での録音です。 中世の音楽 ここでいったん中世に戻り、ほんの少し CD をご紹介します。 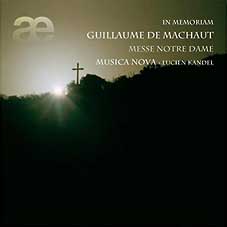 Guillaume de Machaut Messe Notre Dame Enseuble Musica Nova Lucien Kandel ギヨーム・ド・マショー /ノートルダム・ミサ曲 / アンサンブル・ムジカ・ノヴァ / ルシアン・カンデル 中世の宗教曲は単旋律から前進して和声を用いるようになっても、前述のように5度の音程などを 多用し、長調・短調のような調性感がなく、ともすると真ん 中の抜けた空虚な響きに聞こえるのだと申し上げました。それと、もう少し後のルネサンス期に入ると「通模倣様式(つうもほうようしき)」と呼ばれる繰り返 しの多い声部が現れてくるようになり、終わりの見えない息苦しさにもつながる気がします。この時代が好きな方もおられますのでこういう言い方は単に主観に 過 ぎないことを強調しておかねばなりませんが、ここでは「フェイバリット」という観点から楽曲を取り上げさせていただいてますので、無謀にもルネサンス後期 まで飛ばしてしまいます。しかし、どんな響きかということでこれを挙げてみました。 1300年頃に生まれて1377年に亡くなったフランス中世、アルス・ノヴァの作曲家、ギヨー ム・ド・マショーです。演奏しているのは2000年に結成 されたフランス・リヨンの中世音楽を専門とする楽団、アンサンブル・ムジカ・ノヴァです。他の演奏と比べても音が澄んでいてきれいであり、楽譜通り真っ直 ぐ進んで行くのではなく、生きた呼吸があってのびのびとしています。男声だけでなく女声が聞ける点も良いところで、この楽団には楽器のメンバーもいます。 リーダーで指揮者を務めるのはルシアン・カンデル。どこか静けさのある解釈が素晴らしい人です。トータルで大変能力の高いグループだと思いますが、今のと ころ CD リリースは数枚であり、専門ということもあって学問性・趣味性の高いこの中世の音楽、ギヨーム・デュファイ、オケゲム、ジョ スカン・デ・プレなどがほとんどです。ヘンデルも一枚出しているようなので、今後ルネサンス後期にも進んでくれるとうれしいです。 このアルバムはイーオン・レコーズから2010年に出たものです。曲はマショーだけではないで すが、マショーは一番有名なノートルダム・ミサ曲が入って います。大変ゆっくりで、やわらかく抑揚を付けて歌っているので他の演奏とは違って聞こえます。男声で透明感のある演奏としては他にヒリアード・アンサン ブルもきれいです。  Josquin des press Songs and Instrumental music by Joquin des press, his pupils and contemporaries Musica Antiqua of London Philip Thorby ♥ ジョスカン・デ・プレ / マスター・オブ・ミュージシャンズ 〜ジョスカン・デ・プレとその弟子、同時代人たちの歌と器楽 ムジカ・アンティクァ・オブ・ロンドン / フィリップ・トービー ♥ 今度はルネサンス中期に入 りますが、有名なジョスカン・デ・プレです。フランドル楽派で、「通模倣様式」を確立した重要な人でもあります。中世からこの 時代にかけての宗教曲についてはよそ行き顔の5度音程だったりすると言いましたが、世俗歌曲の方に目を向けると、カンティガでも「モンセラートの朱い本」 でもそうですが、舞曲風だったり喋り言葉風だったりになりがちです。オーボエの前身の楽器がベーベー言う中で音程を上ずらせ、裏返った頓狂な声で歌うもの などは面白くはあっても美しいという方向ではありません。アイルランドの今のフォーク・ソング同様、きれいなメロディーがある一方で、多くはがやがやとし た酒場で弾き語る揶揄のような波長だったりするわけです。 そんな中で本当にきれいな 曲となると、ゆったりしたパヴァーヌのようなテンポの、多くは悲しみをうたった歌ということになります。ジョスカン・デ・プレ は一番有名で晩年のポリフォニーの傑作とされる「ミサ・パンジェ・リングァ」もいいですが、「ミル・ルグレ(千々の悲しみ)」というシャンソン(歌曲)は 当時大変ヒットした曲です。神の音程とは違ってさすがに感情を感じ取れる音階になっています。 あなたと別れて その愛らしい顔を後にする ことの千の悲しみ あまりに大きな悲嘆と耐え がたい苦悩によって まるでわが人生がじきにな くなって行くようだ スペイン国王カルロス5世 も好きだったということで、これが入っているジョルディ・サヴァール盤などではそのまま「カルロス5世」というタイトルになっ ていたりします。ルネサンス期のダウランドの名曲「流れよ、わが涙」もそうですが、同時代とその後の多くの作曲家がテーマとしてこのメロディを使って曲を 作り、後述する「楽しいルネサンスの舞曲集」に入っているティールマン・スザートもそうだし、クリストバル・デ・モラーレスのミサ曲などは特に有名です。 このアルバムにはその「ミ ル・ルグレ」がいっぱい入っています。いっぱいというのは正確には五曲で、原曲のシャンソンに加えて、それを元にして他の作曲家がアレンジした器楽曲など も聞けるということです(23〜27トラック)。 タイトル通りジョスカンばかりでなく同時代の人の曲もあるわけですが、「ミル・ルグレ」をちゃんと聞ける数少ない CD の一つであり、低い声の男性が独りで歌うものが多い中、高いパートとハモらせてゆったりと静かに歌われます。中世ものの歌い方の流儀といったらいいのか、 ソプラノをはじめとして音程が若干安定しないように聞こえるところが特にミル・ルグレ以外の曲ではいくらか気にもなるのですが、声自体がきれいで曲の美し さは十分に感じられます。他にあまり探せない魅力的な盤と言えるでしょう。しっとりした曲もジョスカン以外でも何曲かあります。演奏しているのはリコー ダー奏者/指揮者でトリニティ・カ レッジ・オブ・ミュージックの教授であるフィリップ・トービーが結成した16世紀初期の音楽を得意とするムジカ・アンティクァ・オブ・ロンドンで、 2000年シグナム・レコーズです。 中世からルネサンス前半の音楽。その独特の響き が好みであれば、古楽探検も一段と奥が深まることでしょう。正直なところ個人的には前掲マショーの前のノートルダム楽派=アルス・アンティカのレオナンと ペロタン、その後のオケゲム、ジョスカン・デ・プレから、時期的に はルネサンス後期に入るラッソまで、完全協和音だけど感情を排して超然とした5度の音程で進んで行くところのある宗教音楽は、どれをかけても違いを聞き分けることに喜びを感じ難いです。同 じとは言わないけれどもほとんど同じように聞こえてしまいます。  短調が悲しいのは生まれつき? それならば、音楽の感情要素、「長調は楽しい、短調は悲しい」というような現代の我々にとって 単純な感覚は人類に普遍のものなのでしょうか。さらに協和 音と不協和音とでは生理的に人間は協和音を好む傾向を生得的に持っているのでしょうか。この問題は単純に見えて、実は長らく論争が続いてきた難問なので す。この話をしだすと CD 紹介という観点からは大脱線になりますが、少しだけ考えてみます。 西洋音楽の語法に慣れた我々は短調は悲しい、などと当然のように感じます。実際は楽しい、悲し いの二つばかりでなく、旋律や和音のあり方によって様々な 感情の読解ができそうな気がします。例えばモーツァルトの晩年の作品の中で長調のいくつかの緩徐楽章を聞くと、快活明澄ながら静かにして、しかしどこか諦 観を感じさせる、などと多くの方が語ります。そんな風にある程度意見が一致するなら何か根拠があるのかもしれません。 しかしこの「音楽は世界の共通言語」説には必ず反論が起きます。人類の思考の二代潮流の一つで ある経験論哲学や唯物主義の側の発想を好む人たちにとって は、音の感覚も文化と学習によるのであって元々共通な感覚などはなく、生まれたときは白紙(タブラ・ラサ)だと思えるようです。そしてそちら側の陣営は反 対の主張をするグループより常に声が大きい気もします。LGBTQ の人々を受け容れず、その性的嗜好が生得的だとする考えに反発するのと同じ心的構図かもしれません。母系のネイティヴ・アメリカンは例外として、多くの文 化で彼らをありのままに認めず、変えさせようとしてきました。 強い主張の背後には恐れが隠れているケースがありますが、それは運命と感じられるものが怖いか らかもしれません。運命か自由意志かはいつも厄介な問題に なります。短調を悲しいと感じる構造が生まれながらにあると言うのは、神の秩序に似た「理性」の構造が人間の中に生得的に存在している、と主張した合理論 に似ています。経験論の反対の立場です。すでに決まっていて自分が決められないことがあるというのは、たとえ自分自身の仕組みであっても自我にとっては恐 ろしいことです。魂が先に決めてきたことなので自分にはもう変えられない、沈む船の切符もそれと知らずに買う運命だとしたら避けようがない、というわけで す。 そのように、和音や音階と感情との間に普遍的な関係があるとする考えに反対するのは、特に民族 音楽学者や現代音楽の作曲家に多いのではないかという話も 聞きます。声が大きいかどうかはともかく、前者は共通性がないほど多様な世界の音楽を聞いているので、そういう考えは科学的じゃないように感じるのでしょ う。現代音楽の作家の方は不協和音の違いに慣れているし、 感情を第一義としない論理的な曲作りもするので、やはりそんな説はありがたくないのかもしれません。 実験 短調が悲しく、不協和音は不快だと感じるのが本当かどうか、実際に確かめようとした研究もあり ます。最近になってやっと活気づいてきたと言えるほど新し い動きですが、ざっと概観しますと、まず英語圏の人々を対象にして、会話と音楽とにおいて楽しさや悲しさといった感情を伝える語法があるかどうかを調べた 2010年のアメリカの実験があります。結果は短3度の下降音程で被験者が共通して悲しみを覚えることなどが確認されました。答えはイエスです。細かいこ とは後で触れますが、それ以外でも、非ヨーロッパの人を対象に加えようという意図から西洋音楽に触れていないカメルーンのマファ族に行った2009年の実 験もありました。こちらの結果も不協和音は好まれず、長調/短調の曲の感情理解でも概ね西洋人と同じ反応が得られました。これも答えはイエスです。 しかし反対の結果になったものもあります。コンゴのピグミー族に行った2014年の実験では、 不協和音はピグミーの人々も不快に思うものの、西洋人が長 調と短調をそれぞれ楽しい、悲しいと感じるような具合には彼らは音楽を識別せず、どんな西洋音楽を聞かせても楽しいものとして受け取るという結果になりま した。これはピグミー族の人々が肉親の死や狩の前の恐れなど、否定的な感情を覚えるときには音楽によって鼓舞し、悲しみや恐れを吹き飛ばすようにしてきた 伝統と関係があるようです。彼らには悲しい音楽を鑑賞するという習慣がないので、調性による感情の区別もないのです。 さらに、ボリビアのチマネ族を対象にした2016年の研究では、協和音と不協和音を被験者たち は区別せず、どちらも好ましいものと受け取ったということです。都市部のラパスでは西洋人と同じように不協和音を不快と感じたにもかかわらず、です。 ここからは各実験についてもう少し詳しく見ます。重複しますし、細部に関心のない方は飛ばして ください。 悲しさは短3度? 特定の音程(音階/調性)は特定の感情に対応するのか、人は協和音程を好むのか。この問題に関しては色々なところで実験がされてきたようです。その一つとしてボ ストン近郊のタフツ大学のものがあります(「短3度は会話において悲しみを伝えるが、それは音楽用法においても酷似」The Minor Third Communicates Sadness in Speech, Mirroring Its Use in Music. Meagan E. Curtis and Jamshed J. Bharucha, Tufts University 2010)。英語圏の研究ですから人類に普遍ということは言えないけれども、ここで面白いことが分かります。 簡単に説明させていただきますと、この実験では話し手のグループ(演劇部の学部学生)と聞き手のグループを用意し て、話し手にはあらかじめ準備しておい た文をそれぞれ「怒り、幸せ、楽しさ、悲しさ」の四つの感情を込めて語ってもらいます。そしてその発音された音のスペクトラムを分析するとともに、聞き手 にその感情が正しく伝わったかどうかを確認します。結果は正しく伝わったのですが、二音節語の抑揚において、音程が上下するピッチ・パターンの周波数分析 をすると各感情ごとに違いが表れ、特に悲しみを表す場合にはマイナー・サード(短3度)の間隔で音が下がるときが顕著でした。続いて半音下がる場合。これ らは聞き取りにおいても偶然を超える優位差をもって悲しみだと正確に受け取られました。他にも怒りが半音上昇など、否定的感情において結果が明瞭で、肯定 的感情ではそこまでの違いが出ないという結論になりました。 次にこれを MIDI ピアノの合成音として、つまり音楽として聞かせると、悲しみの短3度と半音の下降は会話と同じ結果に、怒りの半音上昇も同じことになりました。怒りについ ては、音楽では「悪魔の音」と言われる不協和音である減5度(三全音)の上昇パターンが怒りを表し、それが完全5度になるとむしろ幸福感に結びついていた のに対して、会話では減5度でも幸福感を表す例があったようです。これは会話において完全5度を出そうとしてそこまで届かなかった音でもそれとみなしたの かもしれませんが、はっきりしたことは言えませんでした。幸福感と楽しさのような肯定的な感情は、会話・音楽共に顕著な特徴が出ませんでしたが、長3度上 昇は幸福感と楽しさが怒りと悲しさよりやや高い結果ではありました。結局最も顕著だったのは短3度下降が悲しみを表すということでしょうか。短3度は音楽 では上昇においても悲しさの度合いがかなり高いようです。 ただし、長3度(ド・ミ)という音程が常に長調で、短3度(ド・ミ♭)が短調であるかのように理解するのは違いま す。長調の最低単位は三音から成るド・ ミ・ソ、短調はド・ミ♭・ソであって、二音だとコードにはならず、調性は出ません。二音の場合、基本の長三和音のド・ミ・ソの上二つを構成するミ・ソも短 3度であり、それだけ同時に鳴らされても特別短調には聞こえないということがあります。音階では根音(ハ長調ではド)から上へ数えて三番目の音が長3度か 短3度かで長調系、短調系が決まります。この実験では二音が時間的前後の配置で上がるか下がるかすることが大事で、短3度が悲しいのもその運び方が基準を 作っていると思われます。 それから、会話における音程の上下を感情の指標にするならば、中国語の四音声のようにあらかじめ語にイントネーショ ンのパターンが組み込まれている言語 ではどうなるのか、など全ての言語でやってみなくてはいけないことになって大変です。それでもこの実験で、音程の上下が会話と音楽とで同じパターンの感情 伝播を担う例となったことは大きな発見でしょう。 非西洋文化でも西洋人と似ている例
以上は西洋文化(英語圏)での例ですから、今度は違う文化ではどうなるのかという比較実験に興味が湧きます。音楽に関してだけですが、それをやって似たよう な結果になった例があります。マックス・プランク研究所、UCL インスティチュートなど、イギリス、ドイツ、カナダの研究機関による2009年発表の合同実験です。ここでは西洋人と、マスメディアに触れたことのないカ メルーンのマファ族を調査しました(Universal Recognition of Three Basic Emotions in Music. Thomas Fritz, Sebastian Jentschke, Nathalie Gosselin, Daniela Sammler, Isabelle Peretz, Robert Turner, Angela D. Friederici, Stefan Koelsch)。マファ族は電気が来ていない地域の、西洋音楽に接したことのない人々ですし、比較のために雇われた西洋人の被験者もマファ人の音楽につ いては知らない人たちです。ここではテーマが二つあって、一つは協和音と不協和音のどちらを好むかということ、もう一つは幸福、悲しみ、恐れの三つの基本 感情に対して音楽の上で西洋人とマファ人が共通した理解を示すかどうかということです。 かいつまんでご説明しますと、まず前者ですが、それぞれのグループが 普段聞いたり演奏したりしている音楽に対して、無加工の音楽と、合成して不協和音 (半音上の音と減5度下の音)を混ぜたものとを聞かせてどちらを好むかを見ます。これは両グループともオリジナルを好んで不協和音を好みませんでした。二 点目はマファの人たちに、西洋の音楽でそれぞれ幸福、悲しみ、恐れを表現していると西洋人が受け止めている音楽を聞かせました。結果はマファの人たちも偶 然を超える割合で西洋人と同じような感情を認識したということです。 長調も短調も同じ?
カ ナダのモントリオール大学とマギル大学、ベルリンの音響コミュニケーション技術大学のチームによる2014年の共同研究(Music induces universal emotion-related psychophysiological responses: comparing Canadian listeners to Congolese Pygmies. Frontiers in Psychology, January 2015 )では、コンゴ北部で電気が来ておらず、ラジオもテレビもない地域に住むピグミー族と、モントリオール市内からさほど離れていない地域のカナダ人を対象に しました。音楽が引き起こす感情が世界共通かどうかを、前記の研究同様、お互いの文化の音楽に接触したことのない被験者を対象に実験したのです。聞かせた 音楽は、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」の短調部分などのオーケストラ音楽、西洋人には愉快に聞こえる「スター・ウォーズ」の宇宙人バンドの音楽、 殺人鬼が刃物を振りかざす「サイコ」、「シンドラーのリスト」などの映画音楽です。すると興奮と鎮静を引き起こす音楽に関しては両グループとも同じ結果に なり、ハーモニーが阻害された不協和音の音楽はピグミー族にとっても否定的な感情を引き起こすことが分かりましたが、受け取る感情に関しては予想を裏切ら れ、ピグミー族の人々はどんな曲を聞いてもハッピーなものと理解するという結果になりました。これは彼らが悲しいときや恐れを抱きそうなときには演奏と踊 りで楽しくなるというように、音楽というものを否定的な感情を追い出す用途に限定して使っているからでした。したがって短調が悲しい、長調が幸せだという 西洋人的共通ルールは見出せなかったのです。 不協和音を区別しない民族
協和音と不協和音とですら好みに違いが出ないという、もっと過激な結果に至った実験もあります。MIT が中心になって行ったボリビアのチマネ族を対象にした2016年の研究です(Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. Josh McDermott, Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts)。 こちらはアマゾンの奥地です。そういう文明と隔絶された地域には文化保護の目的で接触を禁じる取り決めがあったりします が、このときは大丈夫だったのでしょうか。未舗装の道を走ってカヌーで川を遡らなければならない地域だそうです。もちろん電気も水道もテレビもないです が、ラジオに触れる機会は限られていると言っているので、現代文明の存在を知らないほどではないのでしょう。最初64、後に50の村で実験したというので 規模は大きいです。被験者はチマネ村の人だけではなく、比較対象としてアメリカ人や、都市部のラパスとボリビアの辺境の町の人にも行いました。聞かせたの はヘッドフォンを通してで、協和音と不協和音の音源は録音によるものと合成されたもの、加えてチマネの人々の音楽に不協和音を加えたものなど念を入れたよ うですが、結果はチマネの人々は完全5度を好む傾向はあったものの、その他の音については協和音であれ不協和音であれ区別はせず、どちらも心地良いものだ と受け止めたようです。もちろん彼らは協和音と不協和音の違いについては聞いてはっきり理解しています。比較対象のアメリカ人とボリビア人は皆、協和音を 好み、不協和音は好みませんでした。 カントと境界線
実験をしてまでも、このように結論は割れるのです。いったいこの二分 裂は何を意味しているのでしょうか。どちらか一方の考えが正しいとするのが幼稚なん でしょうか。ミクロな物理学の世界では前もって準備した実験装置に合わせて答えが出て来るので、観測者の想定に従って光が波になったり粒子になったりする そうですが、そこまで考えないとだめでしょうか。 認識というものが学習経験によってもたらされるのか、理性と呼ばれる 構造が人間の中に先に存在していることによって可能なのかという二つの考えが「経験 論」、「合理論」という形で人類の哲学史を二分してきたという話にはさっき触れました。二つの哲学を綜合したとされるのはカントです。知ったようなことを 言いたいわけではないのですが、カントの場合、綜合といっても二つの考えを混ぜ合わせたということでは決してなくて、それぞれの立場がどこまで言えるのか という限界を見極めた上で境界線を引いたのでした。ではそれとよく似た音と感情のこの話は、どう分けたらいいのでしょう。 生得説の根拠
まず、音の好みや感覚には生得的な基礎があるはずだと考える人たちに とって都合の良い根拠とされるものを挙げてみると、一つには内耳の構造があります。 不協和音については、周波数の近い二つの音を同時に鳴らされると蝸牛の基底膜(聴覚の細胞があるところで、その位置で周波数を聞き分ける)の近い部分が刺 激されて叩くような不快な干渉の感覚を引き起こし、それが不協和音と感じさせているという研究がありました(Tonal Consonance and Critical Bandwidth. R. Plomp and W. J. M. Levelt 1965)。これはチマネ族の実験結果とは一見矛盾します。 それとは別に、脳の聴覚野の活性パターンを測定して、不協和音の認識 が協和音とは別の聴覚野を刺激するという研究も成されているようです。活性パターンが学習によるのかどうかは分かりません。 また、「波長の共鳴」という物理現象から説明しようとする考えもあり ます。二つの音の周波数がきれいな整数比になっているときは音が共鳴してうなり音が 出ません。不協和音はうなりを上げる音です。例のピタゴラスに発して中世の神の音程とされた発想ですが、これも感覚受容器がどう受け取っているかは未解明 です。 同じ方向の説明は「倍音の構成」という観点から、長調/短調の違いに 対しても成されます。倍音とは一本の弦をはじいた場合に、その基音と同時に整数倍の 周波数の音がいくつも自動的に鳴っているという現象ですが、そこに含まれる音ならば自然なものとして人間も心地良く感じるのだろうと考えます。それで行け ば、ドを鳴らしたときの倍音の中に長調のコードであるド・ミ・ソは全て当てはまり、短調のド・ミ♭・ソとなるとミ♭の音は入らず、ミ♭が鳴ると自然な倍音 に干渉することになるので、少し陰ったようになって何らかの心理的投影を呼ぶのだろうと推測されます。それが悲しみの正体というわけです。因みにドから見 て下に短3度のラの音も第13倍音まで出て来ません。この短調の不自然さが倍音から来ることについてはゲーテも気づいていたようです。 そしてこれも生理学的根拠は見出せませんが、動物の本能に説明を求め る人もいます。動物が戦うときには低い声でうなる方が強く、高い声を出す個体は負け 感情を出しているという点から短調の悲しさを説明するのです。協和音となる3度の音程を二つ重ねるとド・ミ・ソ♯になりますが、このソ♯はドに対しては不 協和音なので解決しようとする力が働きます。その際に下げてド・ミ・ソにする方が強い動物、上げてド・ミ・ラにする方が弱い動物という話で、そもそもなぜ ド・ミ・ソ ♯を持って来たのか、動物の最初の威嚇の声にはそのような非整数倍音(和音)が含まれているのかはよく分からないながら(声に倍音が含まれていることは実 証済みです)、動物に基礎づけるのは面白い発想だと思います。 さらに動物よりは進化して、生後二ヶ月と四ヶ月の幼児にピアノの音で 不協和音(三全音と短九)を聞かせ、協和音(完全5度とオクターブ)とどちらを好むかを見る2002年のマックマスター大学(カナダ)の実験もありました (Preference for Sensory Consonance in 2 and 4 Month-Old Infants)。これはあちこちでよく引用されるものですが、類似のものは日本でも子供を対象に行われているようで すし、いくつもあるようです。結果は、胎教でもない限り教育されているとは言えない乳児であっても、不協和音は好まないということになるようです。不協和 音を続けて聞かせると音への興味を失うそうです。これもチマネ族の実験結果とは整合しませんが、どう位置づけるのかは分かりません。 肉体は何も決めない?
そもそも人間の体の中に、短調を悲しいなどと思 わせる器官などはなく、生物学的基礎としての構造は何も見出せない可能性も考えられます。この線で極端な 話をすると、前世の記憶として詳細に語られた出来事が、本人が知らなかったにもかかわらず歴史的事実と合致する例があります。科学的な手法では証明できな いことですから疑う人はどうやっても疑いますが、その人の記憶の正しさを信じるならば、その記憶は脳にはないことになるでしょう。また、ある種の臨死体験 でも、脳死状態だった人が生き返った後に死んでいた間に観察していた出来事を正確に語ることがありますが、それも脳に起因する記憶ではあり得ません。こう いう可能性を私は信じますが、カントも言っているように理性を超えたものは存在しないのではなくて、理性には語れないのです。こうした話が実験科学的な方 法で解明されることは決してないでしょ う。 学習説の根拠
形而上の話は置いておいて、先ほどの生得説の根 拠に再び戻ると、協和音を好む傾向と長調/短調などが感情に与える影響とにおいて、部分的にせよ人類に普 遍のものはありそうに思えてきます。しかしピグミー族とチマネ族の二つの実験は真っ向からこの考えを否定しているわけです。後者の実験の記事を書いていた 記者が引用していましたが、デカルトは不協和音を好む文化もあると語っていたそうで、ガムラン音楽のチューニングには外れた音もあるし、クロアチアの二重 唱では半音ずれた音程(不協和音)を重ねる例もあるのだそうです。ガムランの方はその複雑な音を聞いた気がしますが、クロアチアの方は私は知りません。そ れを言うなら雅楽も、不協和音に当たる笛の音を特別な意味で使います。いずれにせよチマネ族に限らず、不協和音を嫌がらないように見える人たちも観察され たことがあるということでしょう。あるいは現代音楽の愛好家もそういう感性を発達させているかもしれません。慣れというものはあるのです。実際に中世の5 度音程の音楽もたくさん聞いて行けば作曲家や作品ごとにニュアンスの違いがある程度分かるようになりますし、現代の日本人はあまり聞かなくなっているだろ う三味線の音楽なども、親しんで行けば上手下手が分かり、情緒も感じられるようになると思います。また、調性以外の要素が関わる部分もあるとはいえ、長調 でも悲しく感じる曲はときどきありますし、短調でもさほど悲しみを覚えずにいることもあり得るというのは、皆体験から知っているのではないでしょうか。こ れらは普遍の感覚など存在しないということを裏付けているかのようにも見えます。 ピグミー族とチマネ族の実験は結局具体的にはど ういうことを言っているのでしょうか。それぞれのケースを見てみると、まずピグミー族が長調も短調も区別 せず、音楽を聞いて悲しいという感情を投影しない問題は、元々彼らが音楽を否定的感情を払いのけるためのみに使っていたのであって、そこに感情を聞き取る という訓練を一切していなかったという話があります。ということは、何らかの経験がないと音楽に喜怒哀楽を関わらせることなく過ごすことになり、識別能力 も生まれないということのようです。 チマネ族が不協和音を排除しないことについて も、マスメディアに触れて西洋音楽を聞く機会がある近隣の町の住人はそれを不快がるわけですから、そのよう な一定の文化の音楽に触れる機会がない場合は協和音/不協和音への好みを形成することなく過ごすことができるということになるかもしれません。あるいは幼 児が不協和音を好まないというそれまでの実験結果とは矛盾するので、チマネ族の方が特有の訓練と経験とによって不協和音を不快がらない感性へと発達したと いうことも考えられはしますが、いずれにしても経験・学習の要素というのは重要で、何もないところには好みもないということになります。 この話からもう一つ思い浮かぶ例証もあります。 証明とまでは言えないかもしれませんが、それは催眠状態で昔の部族社会の記憶を思い出す人に聞いてみる と、メディスンマンになる約束であれ自分の結婚の取り決めであれ、個人としてそれが好きとか嫌だとか、そういう風には全く考えてなかったという答えが返っ てくることです。苦しいや悲しいは人間だから当然あるけれども、集団としてのあり方そのものを疑う想像力がありません。悲しい音楽をピグミーの人々が想像 できないのと同じことです。自我の観点からすれば、社会の中で個人の役割が固定されている秩序は後進的であり、それに盲従するのは愚かなことに見えます が、実際のところは部族社会と現代とでどちらかが優れているという問題ではなく、自我の様態が違うステージにあるということでしょう。それを意識の進化の ステージだと捉えると部族社会を低く見るようにも聞こえますが、彼らの方が自然と一体化した直感の面では遥かに優れているので、現代人はもう一度彼らの能 力に目覚めることが求められているとも言えます。そしてこのことはやはり、人は意識をするまでは、個別の能力を発達させないということです。 学習説ではコミュニケーションは成り立たない?
それでは、肉体的な構造によって特定の感情反応 があらかじめ決まっているわけではないからといって、音楽における感情伝達の仕組みが起原においては任意 のものであって、何でも良かったけれども時間とともに今の形式が正式なコミュニケーション・コードへと発達して来たに過ぎないと言えるでしょうか。もしそ うなら、通常とは逆に不協和音を好み、長調を「悲しく」、短調を「楽しく」感じる文化が主流となるなど、別のシナリオもあり得たわけです。これはドイツの レコード会社が録音した音が他のヨーロッパ地域のものより硬く響く傾向があった、などという小さな話ではなく、ちょっと離れた大陸では同じ音を聞いてもそ のコードの受け止め方がまるで違うことも起こり得るということです。 そしてそこまで人間が白紙なら、個々人でもっと ばらつきが出てきてもおかしくありません。いくら同じ文化の中にいるとはいっても、サブ・グループの価値観や家庭環境は様々だからです。 さらに、そのように個々人で環境による感じ方の 偏差が大きかったら、音楽を作り、奏でる人がいて、それを聴衆が聞いて楽しむという関係は今ほど上手くは 行かなかったはずです。相当程度以上の共通言語がなければコミュニケーションは成立しないので、お互いに感動し合うことすら不可能になり、コンサート評も 世の中から消えるでしょう。国際結婚は必ず失敗に終わると言っているようなものです。 ところが実際は言語以上に音楽での意思疎通は容 易だったりするし、感じ方に幾分かの個人差は残るでしょうが、その相対性に埋もれてしまうことなく人々は感動を共有し合っているようなのです。 西洋音楽を経験すれば皆同じになる?
それとも、西洋音楽には魔法がかかっていて、それに触れただけで短調は悲しいという認識を皆が同じように発達させてしまうのでしょうか。何だか人間の集 合的無意識のような話になってきました。好きな話題なのでたびたび出してしまうのですが、人々が集団ごとに一つの無意識を共有していて、各集団も最深部で は皆一つにつながっているという思想です。ユングの心理学ですが、遠く離れた土地の神話が似ていたり、似たような新発明が地球の裏側でも同時に起こるとい うこともこの働きによります。この考えで行くと、各グループ(日本、キリスト教徒、など)では、そこに所属することによって特定の感性を共有します。しか しながら、これはよく見られる現象を上手く説明した一つの形而上の仮説であって、科学の方法で実証できる実体的なものだと考えることはできません。 音楽にただ触れるという経験と、特定の調性が固 有の感情に対応するように訓練することは違います。学校では音楽の時間に「短調のこの曲は悲しい調子です よ」、という説明を数回はすることもあるかもしれませんが、九九のように繰り返し覚えて答えが合うまでやるということはありません。従ってその程度の学習 でここまでコミュニケーション・コードとして一致したものを形成するとは考えられません。それならば、子供番組の「セサミ・ストリート」や「お母さんと一 緒」で悲しい場面のときに流していた音楽が短調だった、というような刷り込みで完全に説明できるでしょうか。ピグミーやチマネ族の人が西洋社会に移住して 長年暮らしたらどうなるのかは、その周辺に住んでマスメディアに接している同じ民族系統の人たちの好みを見れば分かります。やはり皆同じになるという結果 が出ていました。仮に十歳までに覚えた音だけが刷り込まれるので、移住した人は簡単には馴染まないという理屈が認められた場合でも、次の世代で共通してい たら、そのように同じ好みになる何らかの力が働いていることになります。まるで西洋の音楽は簡単に他の地域の音楽を駆逐してしまうかのようです。これはリ ズムについても言えるようで、スラブの舞踊音楽における五拍子など、世界には様々な拍子があったものの、西欧の四拍子には特別な伝染力があり、その新しい 形であるフォービート(ポピュラー音楽の四拍子で、ジャズでは三連符に分割した裏打ちリズム)においてはあっという間に地球を席巻してしまいました。今や 西洋音楽は世界中に溢れ、伝統的には別の音階を持っていた地域ですら同じ感覚を共有していることは、学習説から考えると驚くべきことです。 いろいろ手に入る材料を検討してきました。ここ までで少なくともこれだけは言えるだろうという結論をまとめてみます: 「長調/短調とセットになった感情」は文化の選択 に過ぎず、経験によって識別できるようになる種類のものだけれども、いったん音楽を感情伝達の手段として 捉えてしまうと、その後は個体間で同じように発現して来て互いに了解可能となる隠れた構造があるように見える。理由はよく分からない。しかしそれは伝播す るように、時間に関係なく感染するように広がるので、「経験を経て顕在化して来る無意識の共通構造」だと言えるだろう。 何か聞いたことのあるセリフです。まるで一頃流 行った「構造主義」みたいです。構造主義という潮流は、進化の力をサイコロの偶然以外では説明できなかっ た科学に代わって出て来たようにも思えます。端折ると余計に分かり難いので触れさせていただきますと、まず、なぜ進化というものが起きるのかという問いは 私たちの科学的理解の枠組みを超えてしまうということがあります。偶然突然変異が起き、その中で生存に適した者が生き残ると言うのが科学の説明として精一 杯のものでした。その科学の手法としては確率・統計学的な武器もあるので、単細胞生物が多細胞生物に進化する確率というものも試算できるようです。そして それがあまりに低い確率であるがために、全宇宙の星の数を考慮に入れても人間と同じレベルの知的生命体が他に生まれることは考え難いという人もいます。人 間がその不思議な確率を通り抜けて存在していることは不問にしているのです。DNA も同じことで、あの複雑精巧な構造はとても突然変異の確率では到達できないので、ある人々は宇宙人がやって来て教えたに違いないという。それならその宇宙 人はどうしたんだろう。地球より星の歴史が長かったから可能だったんでしょうか。花に擬態するカマキリや、スズメバチそっくりの蛾とカミキリムシ、珊瑚や ウミヘビに化ける蛸といった自然の驚異も、偶然に細胞が突然変異した結果だとしたら、そうなる確率は途方もない分母になることでしょう。粘菌と呼ばれる生 き物は脳を持たない単細胞生物の集まりに過ぎないのに、知性を持って団体行動をします。このような説明不能の知性に出会ったとき、神とは言いたくないの で、理由は不明だけどそういう秩序を形成する知性の「構造がある」、とひとまず言っておこうというのが構造主義の発想です。文化人類学の「交差いとこ婚」 のようにその知性を人口調節機能として数学的に計算できるケースもありますが、その場合でも何がそうさせたのかを説明することはできません。さっき触れた ユングの仮説と同様で、カントが科学の手法との間にはっきり境界線を引くべきだと言った形而上の問題になります。結局、遍在する叡智(生命力)については 何をやっても証明したことにはならないのです。音楽の中に何らかの深遠 なるものを見出すという営為においても、それが集団ヒステリーでないなら、そうした叡智と同じ種類のものが働いているように思えます。 音楽の話に戻ってきました。現代は脳科学が発達し、意識の様々な活動 に対応する特定部位を割り出せるようになりつつあります。ニューロン発火を図像で見られる計測器もあるそうですし、今後は音と感情の関わりについても何か 新しい見方が出てくるかもしれません。しかしどんな発見も一つの見方を別の形で表したに過ぎません。優良遺伝子を残すための求愛行動と配偶者選択という見 方も仮説ですし、狩猟時代の名残として存在する怒りの感情というのも説明に過ぎず、いくらアドレナリンを分析しても生物学的根拠にはなりません。科学者た ちはエンドルフィンと報酬系という発想に魔法を感じるようですが、すべてが脳にあるとする考えは人工知能が発達すれば生命になるとするのにも等しいでしょ う。音楽芸術は音という現象界の道具を使い、その物理的パターンの中に知能の向こう側にあるものを投影します。したがって音楽の中になぜ心的内容が表されるのかという質問が答えられることは決してないのです。短調が悲しいのは生得的か学習によるのかの論争にも結論は出ないことでしょう。証拠を上げて実証 しようとする限りこの論争は続くのだと思えてきます。  ルネサンス後期の音楽 ルネサンスの音楽については「楽しいルネサンスの舞曲集」という、懐かしいコレギウム・アウレウム合奏団の CD をすでにご紹介しており、それは本当に力が抜けて楽しいものでしたが、ここでは宗教合唱曲を中心にして少し器楽曲にも触れます。 さて、やっとルネサンスも後期になって、それは年号で言えば1520年〜1600年頃までとされるようですが、やっと我々の耳に馴染んだド・ミ・ソの音階のようになってきました。それまでの平行5度的な音から長調/短調の別のある調 性感あふれる和声の時代になったということなのですが、厳密に言うとそれは違うので感覚的に言って、の話です。この時代区分に入るラッソにはまだ中世っぽ い曲があるし、3度の使用という言い方ならもっと前からだろうし、それにここで取り上げる作曲家たちのド・ミ・ソみたいに聞こえるものも、実は学術的には 違う形で説明されるべきものがそう聞こえてるに過ぎないようです。でも昔からすれば随分今風になってきて聞きやすくなり、「ああ我々の音楽だな」という感 じでハーモニーがとてもきれいです。好奇心に頼らず、物好きと言われずしても、愉しみのために聞きたくなる音楽です。 作曲家で言えばトマス・タリス(1505?-1585)、ジョヴァンニ・ピエルルイー ジ・ダ・パレストリーナ(1525?-1594)、クリストバル・デ・モラーレス(1530?-1553)、ウィリアム・バード (1543?-1623)、トマス・ルイス・デ・ビクトリア(1548-1611)、クラウディオ・モンテヴェル ディ(1567-1643)などの活躍した時代です。ビラ配りのアルバイトに過ぎないので学問的解説は無理ですが、気に入った CD をいくつか取り上げてみようと思います。 〜クリストバル・デ・モラーレス セビリア生まれの宗教合唱曲の作曲家で、トマス・ルイス・デ・ビクトリアと並んでルネサンス・スペインを代表する人です。そしてこの時代の他の作曲家たちに 比べても変化に富んだ美しいハーモニーを聞くことができます。今不用意に他と比べてもと申し上げましたが、残念ながら各技法の違いの説明は叶いません。 変化に富んだと言っても1530年頃の生まれであるモラーレスの話 ですから、バッハが同時代の作曲家の中でも飛び抜けて印象的なメロディーを作る能力があったようには、初めて聞く人には思 えないことでしょう。モテットの一部など、いざ、と取り組んでも同じパターンの繰り返しに聞こえてきて、中には輪唱が次々と永遠に続くように思える曲もあ ります。通模倣様式と呼ばれるものですが、慣れてないせいでレコードの針が飛んで同じ溝をなぞってるなどと言いたくなる人もあるでしょう。正しくはフラン ドル楽派以来のポリフォニーに共通した特徴だと表現すべきかもしれませんが、後の時代の作曲家のように個性的な自我の目覚めからはまだ遠いからだとも言え ます。それでもこの時代と様式の中にあっては、モラーレスの曲は今の和声に最も近い感じがするということなのです。 しかしグレゴリオ聖歌もそうですが、じっくり聞くとこれが大変心に沁みる美しさに満ちています。流行のヒーリング・ミュージック だと考えて流しておくだ けでも効果が出そうです。ヤン・ガルバレクというサックス奏者がこの作曲家に合わせて即興を吹いたものがミリオン・セラーになった話については記事に書 き、ここでもすでにその話に触れましたが(「オフィチウム」 [記事の一番下の CD] )、そういう工夫をしないモラーレス自身の元の作品にも素晴らしいものがあります。たくさん作曲している作曲家です が、どれが音楽史的に重要かはともかくとして、中でもその曲が入っている方の Officium Defunctorum と Missa Pro Defunctis という二つのレクイエム、そして 「ミサ・ミル・ルグレ」は有名かつ聞 きやすいものです。  Christóbal de Morales Officium Defunctorum Missa Pro Defunctis La Capella Reial de Catalunya Jordi Savall ♥♥ クリストバル・デ・モラーレス / レクイエム ラ・カペラ・レ イアル・デ・カタルーニャ / ジョルディ・サヴァール ♥♥ モラーレスの曲でレクイエムと呼ばれるものは二つあり、どちらもよく演奏されますが、それらは前述の通りオフィチウム・デフンク トルム=死者のための聖務日課(Officium Defunctorum 4声 1526〜28年頃)とミサ・プロ・デフンクティス=死者のためのミサ曲(Missa Pro Defunctis 5声 1544年)で す。ラテン語の defunct- というのが英語と同じ「死んだ」の意味なのでそうなります。 ヤン・ガルバレクのヒット曲が入っているのは前者ですが、まず二つとも聞けるアルバムを取り上げます。ヴィ オラ・ダ・ ガンバの名手、ジョルディ・サヴァールが1987年にバルセロナで結成したカタロニア音楽を中心に活動するコーラス・グループ、ラ・カペラ・レイアル・ デ・カタルーニャの演奏です。サヴァールという人は自身の楽器演奏は起伏のある意欲的なもので、好きな方とそうでない方とがおられるでしょうが、ここでの 演奏の主体は合唱団の方にあり、彼の波長を予測していると落ち着いた運びに少し意外さを感じるかもしれません。モラーレスのこの曲の定番演奏であり、やは りそれだけのことはあると思います。 しっとりとした男性の低い声に包まれます。ガルバレクの曲についてはやや速めのテンポですが、三つ目にご紹介する「ミサ・ミル・ ルグレ」と同じマクリーシュの演奏でその曲が入っているもう一つの方の盤(フェリペ2世の葬儀を再現した「レクイエム」と題する黒い表紙のアル ヒーフ盤)の速さから比べればゆったりです。 そのマクリーシュのオフィチウム・デフンクトルムについては、出だしは高い声のパート が入ってゆったり歌っていて一番いいなと思えるのですが、途中からは最初に置かれるグレゴリオ聖歌が力強く遅いのに対して本編が速く、ちょっと別の曲に感 じます。 ガルバレクのジャズ盤に入っている演奏(サックスの入らないオリジナル曲も収録されています)の緩やかな歌い方に近いのはガー ディナー/モンテヴェルディ合唱団盤ですが、そちらは「サンチャゴ巡礼(pilgrimage of santiago)」というコンピレーションアルバムで、モラーレスの全曲ではありません。 1991年アストレ・レーベル(Astré Auvidis)の録音です。モラーレスの名曲であ り、特にオフィチウム・デフンクトルムの出だしは長調と短調が交錯する作りで旋律線がはっきりしており、歌い たくなります。ミサ・プロ・デフンクティスの方ではベルリオーズが幻想交響曲でモチーフに使ったグレゴリオ聖歌 も聞けます。CD はMP3配信用の画面も含めてカヴァー・デザ インの違うものも出ています。また、本来のアルバム・タイトルはラテン語による曲名になっていますが、ここでは意訳して「レクイエム」としておきました。 検索ではラテン語の原題の方がいいかもしれません。 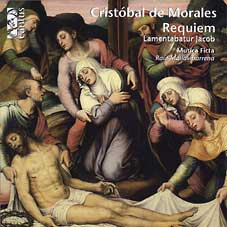 Christóbal de Morales Requiem Musica Ficta Raúl Mallavibarrena Núria Rial ♥♥ クリストバル・ デ・モラーレス / レクイエム ムジカ・フィク タ / ラウル・マリャビバレーナ(指揮) / ヌリア・リアル(ソプラノ) ♥♥ こちらは残念ながらオフィチウム・デフンクトルムの方は入っておらず、5声のミ サ・プロ・デフンクティスのみのレクイエムですが、最高に美しい一枚です。バッハなどでよく OVPP と表記される、1パート1人の歌手による歌唱にオルガンを加えた演奏で、最も目立つソプラノのパートにカタロニア出身の歌手ヌリア・リアルを起用していま す。大変人気のある人で、この方面にご興味があれば画像検索もしてみてください。そのルックスとソプラノ音域ということでケイト・ブッシュみたいな高音の 媚態を期待される向きもあるかもしれませんが、違います。むしろ飾りのない真っ当にきれいな声です。人数が少ないこうした編成だと重なって濁ることがない ので理想的な透明度も得られ ます。しかも女声が上のパートを務めます。 ムジカ・フィクタというグループ名になっていますが、これは中世の音楽理論から来る名前ながら「架空の音楽」という意味になるの が面白いです。指揮者のラウル・マリャビバレーナによって1992年にスペインで結成された古楽合唱グループです。 演奏についてはゆったりとよく歌いますが、これはもう説明不要でしょう。美しい声の響きに癒されます。カントゥス(cuntus スペイン)・レーベルの1998年、バルセロナ・エスペランサ 礼拝堂での録音です。「ヤコブは嘆きぬ」、「我らを憐れみたまえ」などのモテットも入っています。 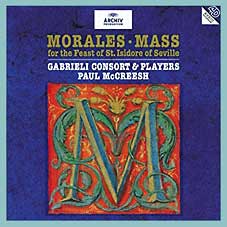 Christóbal de Morales Mass for the Feast of St. Isidore of Seville Gabrieli Consort & Players Paul McCreesh ♥♥ クリストバル・ デ・モラーレス / セビリアの聖イシドロの祭礼のためのミサ(ミサ・ミル・ルグレ) ポール・マク リーシュ / ガブリエリ・コンソート・アンド・プレイヤーズ ♥♥ 今度はモラーレスのもう一つの代表曲、「ミサ・ミル・ルグレ」です。詳しい楽曲解説は他に任せます。ミル・ルグレは「千々の悲しみ」と訳されますが、すでにご紹介したジョスカン・デ・プレの同名 曲をモチーフにしているのでそう呼ばれます。1544年作曲の6声の作品です。 ミサ・ミル・ルグレの演奏ではイギリスの男声ボーカル・グループ、ヒリアード・アンサンブルのものが有名で すが、ここではポール・マクリーシュとガブリエリ・コンソートのアルヒーフ盤を挙げます。ただしこの盤はミル・ルグレだけを順に取り上げているのではな く、他の作品を取り込んで途中にも挟んでいます。セビリアの聖イシドロの祭礼のためのミサと銘打っており、1590年のトレド大聖堂の式典を再現するよう な格好になっているのです。因みにこの聖イシドロというのはマドリッドのサン・イシドロ祭に関するのとは別人です。 最初は会場に入場するための音楽としてフランシ スコ・ゲレーロのファンファーレやフィリップ・ロジエのオルガンなど器楽が入り、グレゴリオ聖歌が来て、 それからミル・ルグレのキリエになります。他の作曲家の作品も盛り込みながら当時のミサの雰囲気を味わわせてくれるのです。この企画独特の起伏によって単 調にならず、ルネサンスの世界を楽しめるものです。 ミル・ルグレの演奏自体もこれが最も気に入りま した。大変ゆったりとして力が抜け、ヒリアード・アンサンブルと違って女声が入っているかに聞こえます。 実際は男声のファルセットであり、昔の式典の再現なので女性が加わることは許されてなかったからなのでしょうが、その高いパートが華やかできれいに聞こえ るのです。個人的にはモラーレスの一番の愛聴盤でもあります。ガブリエリ・コンソート&プレイヤーズはイギリスの古楽の指揮者ポール・マクリーシュによっ て1982に結成されたロンドンの古楽楽団です。前述しましたが、同じ演奏者で二つのレクイエムも出ています。それとこれとが両方一緒になった二枚組もあ ります。また、このミル・ルグレの盤にはブリリアント・クラシクスから出た廉価版も存在します。それだけ定番の演奏だと言えるでしょう。 アルヒーフ1995年の録音です。収録場所はスコットランドとの境界に近いノーサンバーランドのブリンクバーン小修道院とイングランド南東部 バークシャーのドゥエー修道院の二カ所です。 〜ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ 後期ルネサンスの作曲家はそれ以前に比べて聞きやすくなった、という線で話を進めているのですが、それはバロック・古典派以降の近代の機能和声に近く感じ るからだ、ということでした。機能和声だなどと難しげな言葉を使ってみましたが、「ポリフォニー的対位法の上に旋律的独立性が確立された」というような理 屈はさておき、要するに長調・短調の別が出て来て調性感があり、平たく言えばド・ミ・ソのような和音が感じられるということです。何度も同じ話で恐縮です が、そういう意味でハーモニーが最もきれいに感じられ、最もド・ミ・ソ的な人はと言えば前述のモラーレス、そしてもう一人、パレストリーナということにな るかもしれません。ルネサンス合唱の集大成のように言われる作曲家です。 パレストリーナというのはローマ郊外の場所の名前だそうです。この人の本当の名前はその前半にくっついてる「ジョヴァンニ・ピエルルイージ」。1525 年頃生まれのイタリア人です。生い立ちと独自の技法などについて調べて書くと学者然とするのでやめますが、その音の構造はモラーレスとは若干違うでしょう か。間違いを恐れずに感覚的な話をします。 例えばジャズのヤン・ガルバレクがヒットさせた モラーレスのあの名旋律、前掲オフィチウムを例に取れば、あの出だしをドから始まるものと考えて歌うと、「ドード(中略)ドードー・シー」みたいになりま す。それらにくっつく各々の和音をドの下から記すと、「ソ・ド/ ミ・ラ・ド/ファ・ラ・ド/ミ・ソ・ド/レ・ソ・シ」となります。さて、これらはほとんどが長 調の和音ですが、二番目のミ・ラ・ドだけが短調のコードになってます。ミ・ソ・ドというのは転回しないで言えばド・ミ・ソで すから長調ですが、ミ・ラ・ドはラ・ド・ミで短音階の最初の和音です。このように(当時の理論では別の言い方があるにせよ)、短調(と同じ和音)が一瞬挟 まるので、ちょっと影が差したような複雑な感情を呼び覚まされて美しく感じるのです。これはもう今の感性と変わらないです。 その意味ではパレストリーナも同じですが、敢え て言うとこのイタリアの作曲家の場合はより陰りが少なくて、ミサにおいては長調の側に寄った曲は常に輝か しい長調であり、あるいはバッハが好んだ作品など短調寄りのものは短調という具合にくっきりしていて、静かなメジャー・コードに一瞬厳かなマイナーの色が 滲むような微妙な風合いは案外少なめに思えます。大変入り組んでいて技巧的な完成度が高いともされます。 そして普通に聞いている限りこの作曲家の一番の 特徴は、輪唱のように次々と起き上がってくる声部の 作りであるかに思えるかもしれません。繰り返し繰り返し似たフレーズが続いていつまでも展開しないような感覚になり、曲によっては息苦しくなる場合もあり ます。構造をよく観察すると、最初に提示される節のすぐ後で同じフレーズがテノール/バス/ソプラノ/アルトのように別の声部で模倣されています。しかし これはむしろ、パレストリーナが脱却しようとして残していると見ることもできる昔からの技法なのです。フランドル楽派のジョスカン・デ・プレが確立したと される「通模倣様式」、英語ではイミテーションと呼ばれるルネサンスに共通したやり方です。それでもパレストリーナの場合は全体にコントラストのついた明 るい光が差したように聞こえるのは素晴らしい点で、やはりイタリアの太陽なのかと思わせます。そうした彼の様式は、フランドル楽派の完成形とされるロー マ楽派だとか、あるいは独立してパレストリーナ様式などと呼ばれます。  Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Aeterna Christi Munera Incipit Oratio Jeremiae Prophetae Sicut Cervus Desiderat Super flumina Babylonis O bone Jesu Pro Cantione Antiqua Bruno Turner ♥♥ パレストリーナ/ バビロンの川のほとりに パレストリーナ:ミサとモテトゥス / ミサ・エテルナ・クリスティ・ムネラ / 予言者エレミアの言葉 / モテトゥス「谷川慕いて鹿のあえぐごとく」「バビロンの川のほとりに」 / 「おお、慈悲深きイエス」/ プロ・カンティオーネ・アンティカ / ブルーノ・ターナー ♥♥ パレストリーナで最も有名なのは「教皇マルチェ ルスのミサ」です。たくさん作曲している人ですが、色々な意味からそれだけが突出して重要視されているか のようです。ただ、どうもその曲については色々な演奏で何度聞いても一番好きというわけでもないので、最初は別のものから始めます。ここに挙げるのは大分 前の記事ですでに取り上げていたものですが(「ルソン・ド・テネブレ」)、「予言者エレミアの言葉」と三つのモテトゥスなどが入ったアルバムです。本来の目玉はミサ・エテルナ・クリスティ・ムネラ なのでしょうが、そこは飛ばして 「予言者エレミアの言葉」からかけるということで愛聴してきました。その後のモテットも含めて印象的なメロディー・ラインと大変美しいハーモニーの曲たち であり、例の繰り返しのフレーズが少なく、ルネサンス古楽の CD の中でも最も気に入った一枚です。ただ、どうやらまた廃盤のようなのです。LP 時代から好きで待っていたもののなかなか CD にならず、92年に出たのをやっと見つけたのでしたが。 歌っているプロ・カンティオーネ・アンティクァは1968年結成のイ ギリスの男声古楽アンサンブルで、たくさんあるこうしたグループの中でも古くから多くのアルバムを出してきた人たちです。やわらかい声でゆったりと間をと り、深々と滑らかに歌って行くところが大変魅力的なグループです。これ は1974年のアルヒーフの録音で、彼らのものとしても最初の頃のものになります。 廃盤となると今のところ中古を探すしかないこと になりますが、ミサ・エテルナ・クリスティ・ムネラと「谷川慕いて鹿のあえぐごとく」、「バビロンの川のほとりに」の二つのモテトゥスについては、 他の曲と組み合わされた二枚組の "Palestrina Masses & Motets" という Regis レーベルのアルバムが出ています。「予言者エレミアの言葉」の方は、"Palestrina Lamentations of Jeremiah the Prophet", "Palestrina Lamentations of Jeremiah, Book 4", そして "Lamentationum Hieremiae Prophetae for 5 & 6 voices" タイトルの Carlton, Alto, Brilliant レーベルの同一内容盤が存在するのですが、中身はアルヒーフ盤と同じ曲ではありません。 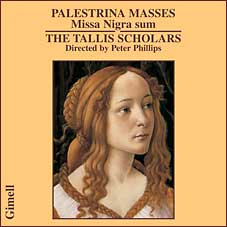 Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Nigra sum The Tallis Scholars Peter Phillips ♥♥ パレストリーナ / ミサ・ニグラ・スム(私は黒い) タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス ♥♥ 次は「ミサ・ニグラ・スム」です。数あるパレス トリーナのミサの中でも聞き飽きることのない緊張感のある音の構成を持つ曲です。このアルバム、最初に同 じタイトルのグレゴリオ聖歌が来て、次にレリティエの曲が来ます。ジャン・レリティエ(Jean L'Héritier)は1480年頃の生まれで1551年までは存命だったフランスの作曲家で、この曲をもとにパレストリーナは自身のミサを作ったので す。そういうのをパロディーと言いますが、彼の曲にはそういう作りのものが多くあります。そしてこのレリティエ、最初不注意にパレストリーナなのかと思っ て聞いていると驚いてしまいます。一瞬明るく行くかに見える和音を交えて始まるものの基本は短調であり、割り切れない複雑な音の展開がたいそう美しい曲な のです。こういうのもありかと思ってタイトルをよく見るとレリティエ。あまり魅力的なのでこの作曲家だけのアルバムが何かないかと思って探しても見つから ないような人です。そしてパレストリーナの部分になり、やはりと納得はするのですが、ここでのパレストリーナも冗長にならず、凛とした空気があります。レ リティエ同様に短調で行く曲で、圧巻はクレドで強く盛り上がるところです。これほど真剣な迫力がこの作曲家にあったのかと思い知らされました。まるでモー ツァルト のレクイエムを聞いているかのごとくです。ミサですから曲の構成上この時代らしい繰り返しは多いのですが、飽きるということはありません。教皇マルチェル スのミサよりも私はこちらの方が聞きたくなります。 ニグラ・スムというのは何でしょうか。ラテン語 で「私は黒い」という意味になりますが、そう聞くと思い出すことがあります。ヨーロッパには各地に黒い聖 母像というのがあるのです。色が黒いからブラック・マリアと呼ばれるのですが、本当はギリシャ神話の女神、デメテルなのだとか、エジプトの女神イシスなの だとか言われ、そう証明されたということで撤去された像もあるようです。どちらの神も穀物、農業、豊穣の神であり、心理学の象徴的解釈としては地母神とい うことになります。大地の生産力を表す概念です。これは歴史に奪い去られた母権制であり、女性原理ですから、例によって現代に復活を望まれているというあ の話になってきます。ただ、黒いマリア像は昔からあるのであって、聖ベルナールなどは旧約聖書で男女の愛を扱っているソロモンの雅歌の一節として理解して いたようです。「私は黒いけど美しい」と歌っている部分ですが、この曲もその聖句に基づいています。羊飼いの恋人を待つ女性が葡萄畑の見張りをしたとき に、自らの顔は見張らなかったので日焼けして黒くなってしまったと恥じらいつつ歌っています。元々のこの聖句は何を語ろうとしているのでしょうか。 演奏は1973年に結成されたイギリスのアカペラ・アンサンブルであるタリス・スコラーズのものです。同 じ頃に結成されたプロ・カンティオーネ・アンティクァやキングス・シンガーズ、ヒリアード・アンサンブルなどと違うところは女声が加わるところで、ルネサ ンスの教会では女性は歌えなかったという史実を重視するか、女性の時代の公平な立場から見るかで評価が違ってきますが、個人的には音の美しさこそが大切な のでこのグループの演奏は最も好きなものとなっています。透明によくコントロールされた清浄な音楽です。1983年録音のギメル・レコーズです。  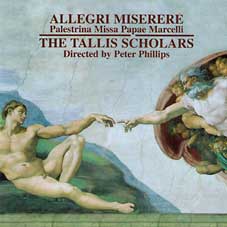 Gregorio Allegri Miserere Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Papae Marcelli The Tallis Scholars Peter Phillips 1978 recording: left, 2005 recording: right アレグリ / ミゼレーレ パレストリーナ/ 教皇マルチェルスのミサ曲 タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス 1978 年盤(左)/2005年盤(右) 個人的にはあまり聞かないようなことを 言ってしまいま したが、パレストリーナの代表曲、教皇マルチェルスのミサ曲もやはり飛ばすわけにも行かないと思います。カトリックでは今も式典で使うようですし、実際出 だしの二曲ほどはうっとりする美しい旋律で、一番の名曲とされるのも納得します。あまり聞かない理由は力強く壮麗な感じのする部分 があることと、私が単に堪え性がなく、声部が重なって繰 り返される通模倣様式の後半が長く感じて飽きてしまうからであって、グレゴリオ聖歌などではメロ ディ・ラインを追わずに環境音楽的にかけているのに不公平な話かもしれません。聖歌のような単旋律特有の心を沈静化する効果がないからでしょうか。この時代の曲は大なり小なりそういうところがあ ります。したがって♡マークは演奏ではなく、曲の観点から付さないでおきます。 最初に取り上げるのは前記のミサ・ニグラ・スムと同じタリス・スコラーズのものです。この人たちの録音はアレグリ のミゼレーレと組み合わされており、これら両方の有名曲の定番録音のように扱われてきました。ミゼレーレのこの曲に関しては、少年モーツァルトのフォトグラフィック・メモリーの凄さを物語る逸話として、楽譜が出回らないよ うにしていたこの曲を耳で聞いただけで全曲記譜してしまったということがよく語られます。ルネサンス古楽で独立して有名な一曲で、すでに他の記事で別の演奏二枚を取り上げましたが(パトリック・ユッソン盤 / ヴォーチェス8盤)、たくさんの録音が出ています。ザ・シックスティーン盤やソール・カークというボーイソプラノが歌うウェストミンスター大聖堂聖歌隊盤、同じウェストミンスターでも寺院聖歌隊の方のサイモン・プ レストン盤などは売れ筋でしょうが、中でも評判と知名度から行けばこの タリス・スコラーズということになるでしょう。確かに素晴らしい演奏で、最 初の部分はすっきりとやや速めで、そこからはゆったりというようにテン ポの起伏があり、弱いところと強く歌うところの差があり、また、遠くで 歌うようなパートもあるなど、コントラストのついた意欲的な表現です。何 より女声の高い声がきれいです。 そして教皇マルチェルスのミサですが、実は新旧 二つの録音があります。1978年録音で長らく定番となってきたものと、それから二十七年後の2005年のものです。旧 盤の方がやわらかい音で残響がたっぷりしており、テンポもゆったりです。新盤の方は1.15倍速くなり、比べれば残響成分の被りがやや少なくて明るい音で 、ソプラノが幾分少年っぽい声に響くことも手伝って爽やかな印象です。どちらがいいかは好みの問題で、静かで溶けるような美しさが良ければ旧盤だし、後半 の曲での繰り返し感がすっきりするという意味では新盤かなと思います。個人的には旧の方がこの団体の特徴が出ていて良いようにも感じました。出しているの は彼らのレーベルである1980年発足のギメルです。つまり旧盤は記念碑的な最初のものということになります。  Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Papae Marcelli Oxford Camerata Jeremy Summerly パレストリーナ/ 教皇マルチェルスのミサ曲 オックスフォード・カメラータ / ジェレミー・サマリー こちらはオックスフォード・カメラータのナクソ ス盤です。これも女声が入っているもので、この団体は1984年に指揮者のジェレミー・サマリーによって設立された室内合唱団です。中心のメンバーは12 人ということです。 これもタリス・スコラーズ旧盤同様に魅力的な演 奏です。テンポはほぼ同じぐらいで多少速めでしょうか。人数の多過ぎない透明感も同様で、新盤同様に音場的に前に出て残響の影響が減った 分少し高域がはっきりして聞こえるかもしれません。力を込めるところでのコントラストがあり、起伏はよりくっきりとしている気がします。弾むように生きい きとした大変レベルの高い歌唱だと思います。1991年の録音です。  Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Papae Marcelli Pro Cantione Antiqua Bruno Turner パレストリーナ/ 教皇マルチェルスのミサ曲 プロ・カンティオーネ・アンティクァ / ブルーノ・ターナー 最初に取り上げた「予言者 エレミアの言葉」とモテトゥスの入った CD と同じ、プロ・カンティオーネ・アンティクァの教皇マルチェルスのミサも素晴らしいです。男声によるもの で、ふくよかでやわらかい声が包 み込むように歌っていて心地良く、合わさって響く音が豊かです。実はこの団体の録音にも二つあって、これは旧盤の方です。どちらも良いですが、ここではこ ちらを挙げました。旧盤の方が高 音部の声が透明でやわらかく聞こえ、80年代の新盤は若干細く繊細に響きます。タイムは旧の方が30分57秒、新盤は36分54秒で、タリス・スコラーズ の場合とは逆転して1.2倍ほど旧盤の方がテンポが速いことになります。ピッチも旧の方が高いようです。しかしやわらかく静かな感じがするのは旧盤の方で す。録音は1978年。レーベルは ASV でしたが現在は新旧盤ともにアルト(Alto Records)から出ています。 〜トマス・ルイス・デ・ビクトリア 美しい響きを味わえるルネサンスの合唱曲、次はクリストバル・デ・モラーレスと同じスペインの作曲家、トマス・ルイス・デ・ビクトリアです。この二人はス ペイン・ルネサンスの二大作曲家です。ビクトリアは1548年頃の生まれというのですからモラーレスより18歳ぐらい若い世代ということになります。十年 ほどローマにいた後スペインに帰国したモラーレスと同様、ビクトリアもローマで活躍し、後に帰国していますが、ローマにいた期間はもう少し長く、より出世 もした後司祭となりました。しかしその音楽は聞けばちょっと印象が異なります。複雑で微妙なハーモニーの美しさを感じさせるモラーレスに対し、より情熱的 で力強い一面があるように思います。 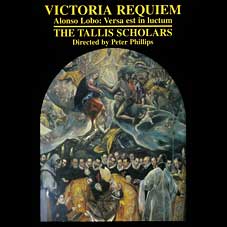 Tomás Louis de Victoria Requiem Tallis Scholars Peter Phillips ♥♥ トマス・ルイス・デ・ビクトリア / レクイエム(死者のための聖務曲集) タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス ♥♥ ビクトリアの 有名曲はレクイエムと表記される「死者のための聖務曲集」と「聖週間のレスポンソリウム集」でしょうか。前者は死者のためのミサ曲で、まずこれから挙げま す。 他の人のミサ と違うところとして、一音を延ばして歌われる息 の長い旋律があります。独特の重さがあって厳かな中に持続するエネルギーを感じさせるものです。全体が切れ目のない大きなスラーの中にあるような一体感が あり、マッシブネスというか、和音にも強さがあります。その和声の造りは短調を基本にして時折メジャーのコードが鳴るものです。通模倣様式だとされます が、 繰り返し感は少なく、ゆったりと運ぶときのモンテヴェルディの嘆きのマドリガーレのようでもあります。そして徐々にクレッシェンドして盛り上がるような大きなうねりもあり、その力強い音にはびっくりさせられるほどです。したがって気楽に聞ける環境音楽ではないですが、真に 迫る美しさがあります。 演奏は前出のタリス・スコラーズです。女声が入 り、透明ながらここでは力強く歌っていて、この曲に相応しいベストな表現の一つではないでしょうか。1987録音のギメルです。 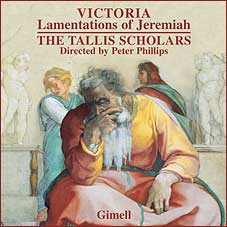 Tomás Louis de Victoria Lamentations of Jeremiah Tallis Scholars Peter Phillips ♥ トマス・ルイス・デ・ビクトリア / エレミア哀歌 タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス ♥ ビクトリアのエレミアの嘆きです。レクイエム より簡潔で、次の「聖 週間のレスポンソリウム集」ほど激情的ではない美しい音楽であり、やはり短調の音です。この作曲家としては最も有名な作品ではないとしても、上記のレクイ エムと並んで最も魅力的な一枚でしょう。後の時代の音楽のように起伏のある展開を期待すると違うかもしれませんが、純化された音が続きます。 これもタリス・スコラーズの演奏を挙げます。 こちらは少し新しく、2010年のギメル録音です。 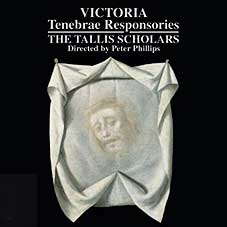 Tomás Louis de Victoria Tenebrae Responsories Tallis Scholars Peter Phillips ♥ トマス・ルイス・デ・ビクトリア / 聖週間のレスポンリウム集 タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス ♥ レクイエムと 並んでビクトリアを代表する「聖週間のレスポンソリウム集」です。曲の成り立ちと用途については解説をご覧になってくださ い。ここではレクイエムのようなやわらかなスラーの長い音ではなく、短く強い音に感情を揺さぶられます。十字架に向かうイエスを劇的な感情をもって見るような激しい調 子です。切々として怒りを秘めたようにすら思える感情のほとばしりがあります。美しくリラックスさせてくれる音楽ではないですが、音はやはり短調の澄んだ響きです。 上と同じタリス・スコラーズです。ギメル・レコーズ1990 年の録音です。 〜 トマス・タリスとウィリアム・バード トマス・タリスとウィリアム・バード イギリスのルネサンス後期の作曲家で有名なのは1505年頃生まれのトマス・タリスと、1543年生まれのウィリアム・バードです。 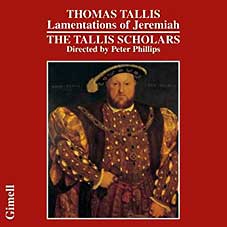 Thomas Tallis Lamentations of Jeremiah The Tallis Scholars トマス・タリス / エレミア哀歌 タリス・スコ ラーズ / ピーター・フィリップス このうちトマ ス・タリスは長期間当時の政権と良好な関係を持った作曲家ですが、その特徴の一つに繰り返される音の感覚が あるような気がします。ルネサンス期の作曲家は皆そうだと言えばそうで、声部が切り替わってフレーズが繰り返される通 模倣様式ということもあるのですが、この人の場合は主題そのものというか、メロディの運びに固有の展開が感じられないような意味で繰り返しが起きているよ うな印象にとらわれる曲もあります。飛躍した例ですが、ちょうどオルガンを得意としたブルックナーの音楽にユニットごとに音が嵌められて進むような飽和し た感覚があるような印象です。美しい和音の響きがありながら私はあまり得意とするところではないので、ここでは一番有名な曲を一つだけ挙げます。「エレミ ア哀歌」です。静かな響きで始まり、嘆くといっても激情ではなくて長音階も出しながら進みますが、メロディはやはり簡潔とは言えなくて尾を引きながらつな がって行くところから、同じ音が続く感覚があります。人によってはこの音のプールの中で泳ぐような感覚に心地良さを覚える方もあるでしょう。演奏はやはり 本家本元、タリス・スコラーズのものが良いと思います。理由は上記の曲と同じです。 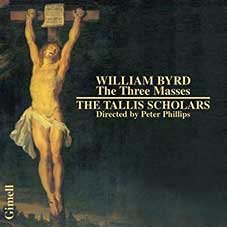 William Byrd The Three Masses Tallis Scholars Peter Phillips ♥ ウィリアム・バード / 三つのミサ曲 タリス・スコラーズ / ピーター・フィリップス ♥ ウィ リアム・バードの方はヴァージナル(チェンバロ)やヴィオールなどの器楽曲にも独特の魅力のあるものが存在しますが、国教会が力を持ってきた時代にカト リックを貫いた人で、宗教合唱曲の中で有名なものは3声、4声、5声のミサ曲です。ふわっと持ち上がる旋律、上記のタリスほど長く尾を引かずにまとまるフ レーズがあり、短音階で展開しつつ最後の和音をメジャーにしたりする動きがダウランドのリュート曲ともちょっと似たところがあります。その泣き笑いのよう な複雑な節回しが懐かしさのある個性的な語法と相まって魅力的なのがバードの音楽です。この曲もハーモニーが美しく、通模倣様式の連続波的な部分ももちろ んありますが、タリスとは違った静けさがある気もします。 ここでもタリス・スコラーズの名唱を挙げます。 女声が入りますが、安心して聞ける透き通った音の演奏です。ギメル・レコーズ1984年の録音です。  William Byrd Masses for 4 And 5 Voices The Sixteen Harry Christophers ♥ ♥ ♥ ウィ リアム・バード / 4声と5声のミサ曲 ザ・シックスティーン / ハリー・クリストファーズ ♥ 1977年に結成されたイギリスの合唱と古楽合奏の団体、ザ・シックスティーンのミサも良いです。5声と4声だけで3声はないで すが、歌い方はタリス・スコラーズと比べるとよ り力が抜けて静けさがあるように感じられ、音としては合唱の高音部がより倍音のはっきりとしたもので、そこが控えめで透明感を感じさせるタリス・スコラー ズよりも繊細感がありつつ人数は多めに聞こえます。1988〜89年録音でヴァージン・クラシクス(ヴェリタス)二枚組です。 他にも教皇マルチェルスのミサ曲でご紹介したオックスフォード・カメラータ / ジェレミー・サマリー(Oxford Camerata Jeremy Summerly)による1991年録音のナクソス盤が同じく4声と5声で出ており、ゆったりで残響が少なめなせいか声がソフトに響き、やや引っ込み気味 に聞こえますが良い演奏だと思います。 ポール・ヒリアー / プロ・アルテ・シンガーズのハルモニア・ムンディ・フランス2000年録音盤(Paul Hillier / Pro Arte Singers)は三曲とも揃うもので、こちらも残響は少なめで女声の加わる静かな演奏が魅力的です。 合唱ではなくソロの歌曲も色々出ています。カークビーが好きな方には2004年録音ではありますがフレットワークの コンソート集があります。 ルネ・ヤーコプスのマタイ受難曲でも歌った韓国 のイム・スンヘが良いのであれば、リコーダー伴奏という面白い趣向で「コンソート・ミュージック・アンド・ソングス」というタイトルの B ファイブ・リコーダー・コンソート盤が2017年にリリースされました。 ヴィオールのファンタズムからはソプラノとテ ナーによる「バード・ソング」という アルバムが2000年に出ています。 カウンター・テナーのジェラール・レーヌによる 「コンソート・ソング&ヴィオールのための音楽」アンサンブル・オーランド・ギボンズ盤は96年ヴァージン・ヴェリタス録音です。 ザ・ニューヨーク・コンソート・オブ・ヴァイオ ルズは「ミュージック・オブ・ウィリアム・バード」をタマラ・クラウト(Tamara Crout)というソプラノ、ルイス・バッガー(Louis Bagger)のチェンバロで米リリコード・ディスクス(Lyrichord Discs)から出しています。1993録音です。 同じレーベルでアメリカのカウンター・テナー、 ラッセル・オバーリン(Russell Oberlin)の歌う William Byrd, Russell Oberlin Music for Voice & Viols という、1958年の録音を1995年に復刻した盤も出ています。モノラルですが音は良く、この声が他に代え難いという意見もあります。ザ・イン・ ノミネ・プレイヤーズ(The In Nomine Players)の演奏で元のレーベルは Expériences Anonymes というところのようです。  William Byrd Byrd: Music for the Virginals Aapo Häkkinen ウィリアム・バード / ヴァージナルの音楽「ハープシコード・ミュージック」 アーポ・ハッキネン ♥♥ 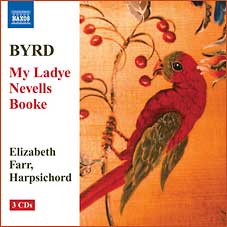 William Byrd Byrd: My Ladye Nevells Booke (1591) (Complete) Elizabeth Farr ウィリアム・バード / ヴァージナルの音楽「私のネヴェル夫人の曲集1591」 エリザベス・ファー ♥ バー ドは器楽曲も大変魅力的です。なかでもヴァージナルの音楽はその一つです。ヴァージナルというのは弦を鍵盤の並びに対して平行に張ったチェンバロのような 楽器ですが、バードの時代ではチェンバロ族一般のことを指していたので、CD の演奏者たちが色々 時代考証の上でそれを選んでいるケースがあるにしても、特にその特定楽器用の音楽ということではありません。バードのチェンバロ曲はこの時代にあって驚く ほど多様で複雑な和音を響かせます。同じようなことをルイ・クープランのクラヴサン曲についても言いましたが、それよりも83年も前の人です。完全5度の 音だった中世から通模倣様式のルネサンスの幕開けを経て、こうした豊かで複雑な調性感のコードを鳴らすようになり ました。 このバードのヴァージナル音楽、その存在を初めて知ったのはグレン・グールドのおかげでした。 彼が選んでギ ボンズの曲と合わせてピアノで弾いているアルバムが出たのです。その選曲と演奏は素晴らしいものでした。今聞いても良い曲ばかりだと思います。それについ てはすでに記事で取り上げました。ダウランドの記事の一番最後です。(バード&ギボンズ / ヴァージナル作品集 / グレン・グールド)。ですのでここでは実際にチェンバロで弾いたものを挙げてみます。多くのチェンバロ奏者が録音してお り、人気のほどが窺われます。聞いてみたものを挙げると以下の通りです: グスタフ・レオンハルト/ク リストファー・ホグウッド/アンドレアス・シュタイアー/スキップ・センペ/ロザリンデ・ハース/コリン・ティルニー/粟田口節子/ピーテル=ヤン・ベル ダー/グレン・ウィルソン/パトリック・アイルトン/エレイン・ソーンバーグ/ジャン=ポール・リアルデ/ウルスラ・デュッチュラー/マーティン・スー ター 使われている技術については私は解説ができません。この中ではホグウッド盤も気に入りましたが、演奏そのものももちろん、この楽 器の場合はいかにナチュ ラルな音に録音できているかということと、良い響きの楽器かという点が自分にとっては重要なことです。聞いていてうっとりできるものを探しているからで す。その素人観点で二つほど良いものが見つかりました。一番きれいだなと思えたのは、バッハやクープランのヴィオラ・ダ・ガンバ曲の伴奏でゆったりした演 奏が素晴らしかったフィンランドのアーポ・ハッキネンです(写真上)。クープランでは単独のクラヴサン曲も弾いていてそれ自体が良かったのですが、この バードもやはり期待を裏切りません。また、この CD は音が大変滑らかでリュートを聞いているかのごとくで全くやかましくなく、豊かな低音に支えられた艶やかな響きに魅了されます。フィンランドのレーベル、 アルバ(Alba)からですが、上記のもの以外にも同じような構成で2017年の SACD ハイブリット盤(ABCD 405)があります。そちらも良いのですが、音としては上記写真の2000年盤(ABCD 178)の方が潤いがあってバランスがとれているように思います。選曲は別のものですが、どちらもダウランドの涙のパヴァーヌのバードによるチェンバロ編 曲版が入っています。その曲、ダウランドのオリジナルのリュートもいいですが、こちらの方が変奏も加わって長く、ただの短調ではない和音で次々飾りながら より複雑に進行して見事なものです。ハッキネンは持ち前のゆったりとした感覚で消えて行く音を味わいながら弾くので、ここだけ聞いても満足してしまいま す。すっかり感情的な世界に浸ってしまいます。 もう少し一般的なレーベルだと、ナクソスから出ているアメリカのチェンバロ奏者エリザベス・ファーによる「私のネヴェル夫 人の曲集1591」と題する2006年の三昧組が落ち着 いた展開で音色も良かったです(写真下)。特にリュート・レジスターなのか、正にリュートに聞こえるような音で弾いている曲がたくさんあり、その音は他の 盤で味わえない大変魅力的なものです。 William Byrd Consort Music au temps de Shakespeare William Byrd et ses Contemporains Spes Nostra Jérôme Hantaï ♥ ウィリアム・バード他「シェイクスピア時代・ウィリアム・バードと同世代のコンソート音楽」 スペス・ノストラ / ジェローム・アンタイ他 ♥ バードだけではないですが、王宮でのヴィオール によるコンソート音楽が聞けるアルバムを一つ。ヴィオールはヴィオラ・ダ・ガンバを含むその仲間の楽器の 総称で、高音用の小さいものからバスまで種類があります。フランスの音楽一家アンタイ・ブラザーズの一人、ジェーローム・アンタイがトレブルとテノールを 担当するヴィオールの楽団、スペス・ノストラによるものが楽しめます。音が連なって行くバードのヴィオール音楽は撫でるように静かに弾いているだけだと眠 くなることもありますが、彼らのは古楽器ムーブメント特有のはっきりとした呼吸のある弓運びでよくうねり、ここではそれがかえって味わい深いものとなって います。教会での収録で響きも豊かです。フランス・アクトゥ・シュッド(Actes Sud) 2015年録音盤です。他にはダウランドも出しているファンタズムによるヴィオール・コンソート全集(William Byrd Complete Consort Music / Phantasm)も出ていて、好みだと思いますが評価は高いようです。そちらは2010年録音です。 前回のグレゴリオ聖歌に引き続き、これまでヒル デガルト・フォン・ビンゲンから順を追って古楽の世界を覗いてきました。そして次に来るべきはルネサンス の作曲家の締め括り、モンテヴェルディとなるわけですが、大分長くなってきましたし、ページをあらためてまた次の項目で触れることにします(古楽の愉しみ 3「モンテヴェルディ」)。    LUX Voces8 ♥♥ Enchanted Isle Voces8 ♥♥ 本来はここでおしまいです。そしてこれは古楽ではないのでテーマから外れていますが、これまで扱ってきたのは合唱の 歴史でもあるわけで、現代の合唱のあ り方の一例として最後に二枚挙げます。といってももちろん現代音楽の和音で作られた作品ではなく、一般に楽しめるものです。特に宗教曲というわけでもありません。また、イギリスのボーカル・グループの演奏をその活躍から必然的に多く選んできたとも言えますが、これもそうです。単旋律、五度音程、ドミソの和音と変化してきた後、不協和音が混ざる前のコードによる合唱の響きであり、録音も素晴ら しいので大きめの音で浴びるように聞くのもいいと思います。実はすでに両方ともエルガーの「ニムロッド」と バーバーの「弦楽のためのアダージョ」のページで取り上げていました。今売り出し中というか、デッカが出していて人気も高まっている2005年結成の若手グループ、ヴォーチェス8が歌って います。 アルバム "LUX" は目玉の二ムロッドが感動的で、他にも古い方はアレグリのミゼレーレ等、有名なメロディがたくさん聞けます。「エンチャンテッド・アイル」はちょっとクラ シック音楽から離れる方向でケルトっぽいイメージに振っているものです。歌い方は静かですがフォーク・ソングと映画のナンバーも取り上げられており、「カ リクフェルガス」のみメンバー外のソロのシンガーがハスキーなポップス的発声で個性的に女性らしく歌います。プロモーションの動画が気に入る方もいらっ しゃるでしょう。他はニュートラルな合唱で、中でもエンヤの「メイ・イット・ビー」はメンバーのソプラノが透明な声で歌い、引きのカメラで上から見せる夕 暮れの輝きの中のラストシーンのように懐 かしくて沁みる音です。二枚とも全体を通して良い曲ばかりが集められており、このメンバーの CD としては最高の出来ではないかと思います。表現の可能性の限界に挑んで歴史に名を刻もうという垂直志向の楽曲は除いて、美しく響く合唱の最終形態と言って も良いのではないかと思います。 古楽の愉しみ 3 / モンテヴェルディ INDEX |