|
�o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079

���グ�� CD �P�W���F�@���q�^�[�^�O���[�t�^�A�[�m���N�[���^�p�C���[���^���I���n���g�^�}���i�[�^�Q�[�x���^�L�c�^�N�C�P���^�A�X�g���E�}�O�i �^�T���@�[���^���t�V�b�c�^�R�[�v�}���^�J�����[�^�E�L�P���j�[�^���`�F���J�[���E�R���\�[�g�^�C���E�K���f���[�m�^��^�J���t�@�b�N�X CD �]�͂�����i�Ȃ̉�������܂��j �@�����ł͊w�҂̌����ɂ���āu���Z���~�T�ȁv���o�b�n�̍Ō�̍�i�ł͂Ȃ����ƌ�����悤�ł����A�����O�܂ł́u���y�̕������v�Ɓu�t�[�K�̋Z�@�v�� ����ł��̒n�ʂĂ��܂����B�ӔN�A�Ƃ����Ӗ��ł͍��ł��������̂��Ǝv���܂��B�����ŁA���y�̕������̂��b������O�ɁA����Ɗ֘A��������ƌ�����t�[�K�̋Z�@�ɂ��Ă������G��Ă݂܂��B�Ƃ����Ă��A�Ȃ̓��e�I�Ȃ��Ƃł͂���܂���B �t�[�K�̋Z�@�Ǝ����Ƃ��� �@�܂��A���̓�͂ǂ����Ċ֘A��������ƌ�����̂ł��傤���B����͂ǂ�����u�J�m����t�[�K�Ƃ����z ����`�����g���Ă��āA���̐�����Nj�����悤�Ȏp���������A��̃e�[�}����W�J���đΈʖ@�I��i�����グ�Ă��邩��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�J�m���͎���`��ŌJ��Ԃ����t�[�K�͈Ⴄ�A�Ƃ����悤�Șb�͒u���Ă����܂��B����ł����A������ȒP���͗����̖��ł�����A����͗���������鐫������������i���A�Ƃ������Ƃł��B����𗠕t���邩�̂悤�ɁA�l����v�f��O�ʂɏo�����ƂŐ������閳�����y�̎n�c�A�V�F�[���x���N��E�F�[�x�����������������A���y������ҋȂ����肵�Ă��܂��B���Ɂu�t�[�K�̋Z�@�v�̕��ȂǁA�������œ˔@�r���I���K�����t���������肷��ƁA�u������Č��㉹�y�ł����H�v�ƕ�����邩������܂���B�x�[�g�[���F���́u��t�[�K�v�����̊y�͂ƈ���ēƓ��̂Ƃ����������܂�����A�~�n������ȉƂ��D�ސ[���Ȃ��̌`�����̂ɂ��������������������Ƃ�����Ƃ͌�����ł��傤�B�����ăo�b�n�̏ꍇ�A���̃t�[�K���\���̌��E��������ǂ��܂ł��W�J����čs���܂��B�����A���ꂢ�ȉ��y���y���݂����Ƃ����P���Ȋ����I���������߂ĐS�\���Ȃ����̋Ȃɐڂ���ƁA�_�̒��ɏ����čs�������H�𑖂�C���ɂȂ邩������܂���B�������Ă��A�����V�ƃR���p�X�i�\���I�ȗ����j�Ȃ��Ɏ��E�̌����Ȃ������Ԃ悤�Ȃ��̂ł��B������Ƃ����킯�ł��Ȃ����ǁu�N���V�b�N���y�̍ō�����ɐ������Ă���v�ƌ����l�����܂��B�j�Z���̔����K�̉_�����n�����葱���A�����ʼn������O�a���āA�~�܂������̒��������čs���܂��B�m���ɂ�������i�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B �ĊO�����₷�� �@����ł́A���̎o����Ƃ��ڂ����u���y�̕������v������Ȃ̂��A�Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͑S������܂���i�܂�ɂ͐����Ɂu�������v�̕����e���ݓ�Ƃ����ӌ�������̂Ŋ����l���ꂼ��ł����j�B ���i�N���V�b�N���y�Ȃǂɂ͂��قNJS���Ȃ��A�L�̐Q�炪�t�����u�����v�Ƃ��� CD ���ɒu���Ă���킪�Ɛl�ɂ���Ƃ��A�u���y�̕������Ȃ��H �������炿�傤�����v���M����_�Ɍ����Ĉꖇ���������Ƃ�����܂����B���`���鑸���Ȃ̂Œf��܂���B�J���`���[�Z���^�[�̂��F�B���Ă�ŗ��āA��~�܂ʂ�܂т��̂悤�Ɏ����b�������̂��D���������l�ŁA�t�[�K�̗��_��m���Ă��킯����Ȃ��Ǝv���܂��B���邢�́A�V���������œ���m�b���������̂�������Ȃ����ǁA�Ȃ͈ȑO����{�l���m���Ă܂�������A�Ȓ����D���������Ƃ͌�����̂ł��傤�B�z������ɁA����݂�Ƃ����Ƃ���ƁA�ӔN�̋��n��������Ƃ����Ɣ��̂悤�Ȕg�����A���������߂Ă�܂Ȃ���炪���̂ӂ邳�ƂɐG�ꂽ�Ƃ������ԂɈႢ����܂���B���������~悂�M�����悤�ŁA��Ō��������܂��傤�B �@�Ƃ�������������o�����Ƃ��A�u���y�̕������v�͒N�ɂł��y���߂��i�ł��B��u�킸���Ɍ��������悤�� �����ɌX���u�Ԃ�����ȊO�A�قƂ�ǑS�ҒZ���ŁA�������̎₵�����������܂��B�ʏ�͕Ґ����傫���Ȃ��A������܂�Ƃ��Ă��܂��B���̍��̃o�b�n�̐S��A�ǂ�Ȃ��̂������̂ł��傤�B�����̉̂Ƃ��Ĕ�r���Ă��A���[�c�@���g�̈�������y���A�x�[�g�[���F���̍�i�P�R�T�̊Ȍ��Ȗ��邳�Ƃ͏�������Ă���悤�ł��B��Ȃ��ꂽ�̂͂P�V�S�V�N�T���V��������̊ԂŁA�S���Ȃ�O�N�قǑO�̍�i�ł��B�o�b�n�͂S�X�N�̂P���ɖ�����������Ƃ��ɂ͒��q������Ă���A�T���ɔ]�����œ|��A�T�O�N�̎O���ɖڂ̎�p�Ɏ��s������N�����Ȃ��Ȃ��āA���̔N�̂V���Q�W���ɘZ�\�܍ŖS���Ȃ��Ă��܂�����A��Ȃł��������Ƃ��Ă͂����ق�ƂɍŌ�̕��ɂȂ�܂��B�W�����ĒZ�����ԂɎd�グ��ꂽ�Ƃ����Ӗ��ł��A�^�̐�M�Ƃ��Ă��悢�ł��傤�B �ӔN�̃o�b�n �@���̍��̍�Ȃ̂�����Ƃ��āA�Ō�̏\�N�A�o�b�n�͂���܂ł��y�[�X�𗎂Ƃ��A���ϗ��N�����B�A�ȏW��Q����S�[���h�x���N�ϑt�ȁA�u�����V�����͗������v�ɂ��J�m�����ϑt�ȁA�����āu�t�[�K�̋Z�@�v�Ƃ��́u���y�̕������v�A���Z���~�T�Ȃɍi���Ďd�������Ă��܂����B�O�������G�l���M�[�͗����A�����ȓI�ɂȂ��Ă����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B���A�a�ɋN�����锒����ƍl�����Ă��܂����A�Z�\���̂P�V�S�T�N�O�ォ�王�͂������ė��Ă���A�����͂ł��Ȃ���ɋ�J�����������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B���̒��ł����́u���y�̕������v�͐���������ʂŁA�قƂ�Ǔ����̉��l������������悤�Ȏd���ł����B���ۂ͖��߂ł͂Ȃ��A���炪�h��ɂ����̂ł����A���̕ӂ̘b�̓j���A���X�ɕ�������܂��B  �o� �@���[�͂P�V�S�V�N�T���V���ł��B���̓��j���̗[���ɁA�o�b�n�͒��j�̃��B���w�����E�t���[�f�}���ƈꏏ�� ���l�̋{�a�ɌĂ�܂����B�����̉��l�Ƃ����̂͗��j��L���ȃt���[�h���q�剤�i�t���[�h���q�Q���^��O��̃v���V�A���B�_�����[�}�c��Ƃ͕ʂ̐l�j�ŁA����͎��j�̃J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G�������̋{��Ń`�F���o���̊y�c���Ƃ��Ďd���Ă������ł����B�剤�͎�����t���[�g�𐁂��A��Ȃ�����Ƃ������y���D�Ƃ������̂ł��B��̊G�́u���y�̕������́v��剤�̉��y��Ɋ֘A���ĕK���o�ė�����̂ł����A�A�h���t�E�����c�F���Ƃ����㐢�̉�Ƃ��z���ŕ`�����A�u�T���X�[�V�{�a�ł̃t���[�g���t�ȁv�Ƃ����^�C�g���̂��̂ŁA�������ŗ����ăt���[�g�𐁂��Ă���̂��t���[�h���q�剤�A���̉E�ō����ă`�F���o ���Ɍ������Ă���̂��J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G���E�o�b�n�A�E�[�ɂ͉��̃t���[�g�̐搶�ʼn��t�@�̒�����c�������n���E���n�q���E�N���@���c�̎p�������܂��B�o�b�n�͓����͂�����ϖ����m��Ă����킯�ŁA���Ƃ��Ă͉��O�X����M�]���Ă���A���̑��q�ł��� CPE �����������Ă��܂����B���O�\�܍A�o�b�n�Z�\��̏o��ł����B�����Ă��̃t���[�h���q�剤�̋{�a�Ƃ��ẮA��ɕt�������̑��z���u�����f���u���N���t�Ȃ̃W���P�b�g�ɂ��g����A���̊G�� ���̃T���X�[�V�{�a���L���Ȃ���A�ʉ�̏ꏊ�͂����ł͂Ȃ��A���͂Ȃ��|�c�_����ł����B �t���[�h���q�剤�ɂ��� �@�����ł܂��A�悭���O�����ɂ���t���[�h���q�剤���ǂ�Ȑ��i�̐l�����Ƃ������Ƃ��C�ɂȂ�܂��B�ނ��� �яK�킷���t������܂��B�u�[�ꐧ�N��ienlightened absolutist�j�v�B���ƂȂ��������Ă�悤�Ɋ�����Ƃ���A�t�����X�v���ɉe����^�����[�֎v�z���`�̂悤�ɍl���Ă��Ƃ���ցA�u�ꐧ�v �Ƃ������t�����܂邩��ł��傤�B���̕ӂ̖��͂����ł̘b��ł͂Ȃ�����ǂ��A���̃t���[�h���q�剤���g���ʗ_�J�Ȃ̌����������l���ŁA�܂��͕����Ŋ�������ʐ�������܂��B���炭�͐����̐��������������e�̉e�����ƌ�����̂ł��傤�B�R�l���Ƃ��Ăꂽ���͔ނ��s�҂���قnj������A�����̓w���f ���� �u����̉��y�v��������C�M���X���W���[�W�P���i�u���͌N�Ղ���ǂ����������v�j�̖��ŁA���Ɍ|�p�������镶���l�ł����B���݂ɂ��̕���������́A��ɔނ�M�����邱�ƂɂȂ�q�g���[�Ƃ��悭���Ă���A�{�l�����܂��O�̎q�������������ɂ��Ă�Ƃ���܂ł�������ł��B �@�Q�C�E�p�[�\���������A�Ƃ������܂��B�����������Ƃ͂킴�킴���グ��������Ȃ̂��l���Ă��܂�����ǂ��A�ߍ��͂قڂ����M�����Ă���悤�ŁA�ǂ�������������܂���B�����͌`�����ň����Ȃ��A���͉�����𗧏�㒚�d�Ɉ����A�������炩���ꂽ������̑��ł����h���������A�Ƃ���܂��B���̏����Ƃ̊Ԃɂ��q���͂���܂���ł����B�Ⴂ�Ƃ��Ɉ�N��̎G�p�W�̏��N�Ɉ��������������Ƃ��L�^����Ă���A���̌�\�s�ȕ����瓦���C�M���X�ւ̓��S�v������A�߉q�R���ł������N�ゾ�������l�̃n���X�E�w���}���E�t�H���E�J�b�e�Ƃ������N�ƌ��s���܂��B�������������ł��������e�ɕ߂܂�A�������߂Ńn���X�͔ނ̖ڂ̑O�Łu�f�B�L���s�e�C�V�����v�Ƃ�������̂���Y�ɏ�����܂��B�r�w�b�f�B���O�ƌ�����蒼�ړI�ł��傤���B�a��A������藎�Ƃ����Ƃ�������v�d�|���̃I�����W�݂����Ɍ�����ꂽ�̂ł��B����O�ɋC�₵�������ł��B �R�l�Ƃ��� �@�����̓�ʐ��̑O�ɂ�����Ƙb�����܂����B�����ăt���[�h���q�剤�{�l�ɕ\�ꂽ�A���e����̕��l�I�Ȑ� �i�̕��ł����A����͑�ϗL�\�Ȑ헪�Ƃ������Ƃ������Ƃł��B�G�w�̈�_���W�����ĕ�����p�A����������A���o�H����ɂ܂Ƃ߂Ėh�����A�����������葤 �̐�͓����W�����������̍��A�����ɖR����������L���ɓW�J��������Ӎ��Ƃ̘A�g�A�f�����Z���U���Ȃǂł��B��������g�̏]�R�o���Ɛ��I�Ȍ����ɂ���Ċm�����܂����B�������Č��X�͖����������I�[�X�g���A�̃n�v�X�u���N�Ƃɑ��Ă���ΐ^��p�̂悤�ɕz���Ȃ��ɐN�U���A�G���炷��Ζ����߂Ȑ킢���d�|�����̂ł��B�܂��A�|�[�����h�����V�A���番�����Ď�ɓ���A�ނ̍�����ɓ��ɕ�����Ď��������m�Ō��𗬂��������j�̒[�����J���܂����B�z�[�G���c�H�������ƍŒ��݈ʂɂ��āA�v���V�A�̌R�����𐄂��i�߂ċ���ȍ��Ƃɂł����Ō�̉��Ƃ����ʒu�t���ł��B ���l�Ƃ��� �@����ŕ����̕����I�ȑ��ʂƂ��ẮA���J�^�̃t���[�g�����牉�t���A�P�Q�P�Ȃ̃\�i�^�A�S�Ȃ̋��t�Ȃ� �ǂ���Ȃ��܂����B���̃M�������g�l���Ƃ�������剤�̃t���[�g�ȁA�����Ă݂�ƁA�O�u���Ə���̑������B���@���f�B���e���}�����A���邢�͂��������� �̗l�����ł�����ƃn�C�h�������Ƃ������A�J���̂Ȃ��i�T���X�[�V�ȁI�j��ۂł��B�����嗬�������}�L���x���̌N��_�ɔ����闧��ɗ������A�N�w�̒��������܂��B��̃t�����X�}�������̂ŁA�����͍Z���҂�t���đS�ăt�����X��Œ����܂����B���z�ɂ������������đ����̌��������āA���p�Ƃ̃p�g�����ɂ��Ȃ�܂����B���������Ɋւ��Ă���r�����A�M���ȊO�ł��ٔ�����㋉�����ɂȂ��悤�ɂ���i�@���v���s���A�̎��R��^���A�܂��A�ږ�����������i�߂ėl�X�ȍ��ЁE�@���̐l�X���}������A���n�Ȃǂ��J�����ăW���K�C���͔|�����サ�܂����B����͑������y�n�ŋQ���Ȃ��悤�ɂ���H������ł���A�J�u�����サ�����ǁA�������̃J�u���q�̕��͖Y���ꂪ���ŁA���u�|�e�g�E�L���O�v�ƌ����邱�ƂƂȂ�܂��B���������ăh�C�c�ł͂ǂ��֍s���Ă��o�ė���l�X�ȃW���K�C�������́A�剤�̌��т��ƌ�����̂ł��B ������Ƃ���A�������Ƃ��� �@�l���]���ɂ����čm��I�Ɍ�����̂́A��Ɍ�҂̕��l�Ƃ��Ă̑��ʂ̂悤�ł����A�R�l�Ƃ��Ă��A�R���� �ł̏㉺�̕����u�Ă̂Ȃ��ԓx�Ől�C���������Ƃ����A�V�������O�̏G�g�݂����Șb�͕�����܂��B�����x�������̂悤�Ȑ�p��N���I�Ȏp���͔ᔻ�̑Ώۂł���A�v���V�A�����瑨�����Ƃ��݈̂̑�Ȍ��тƂ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����ʂł��A�ǂ����̑哝�̂̂悤�ɁA���т��я����̎������������ꂽ���Ƃ͔ے�I�Ɍ����܂��B �@�D��ۂȂ̂́A�����D���ŏb��w�Z��n�݂����肵�����ƁB�j�g�݂��������ǁA�M���ł���ɂ�������炸�A �M���̗V�тł���c���Ȏ���ᔻ�����Ƃ����b������܂��B���Ɍ��Ɣn�������A�n�ɂ͔��Ԃ��g��������Ȃ����������ł��B�A�������D���ĕی삵�悤�Ƃ��܂����B���������_���炩�ǂ����A�ӔN�͍�������u�V�t���b�c�v�ƌĂ�Đe���܂�Ă��܂����B���̂悤�ɗ��j��̎��ݐl���́A���̌��Ɖe�������������̂̂悤�ł��B �Ȃ̎n�܂��@ �@�@ �@���āA�b��߂��ĂP�V�S�V�N�T���V���ł��B���̓��A�n�ԂłP�O�O�L���ȏ�̓��̂���o�ă|�c�_���̉��{�ɒ������o�b�n�ł����A���͑҂��\���Ă���A��s���T���̊Ԃɓ��������Ƃ����������W�̎҂������ė���Ɣ��ōs���đ劽�}���A����G�X�R�[�g���܂����B���{�ł͗[���ɂȂ�Ɩ����̂悤�Ɏ��I�ȃR���T�[�g���Â��Ă��܂�������A���͂ɊW�҂͉��l�����܂����B�����Ă����Ŕނ̓o�b�n�ɕ��������܂��B���N�O�ɔ������ꂽ����̃t�H���e�s�A�m�ł��B���l������ŐV�̎����I�Ȋy������䂩�����Ă�킯�Łi�ʁX�̕����ɂV�䂠�����悤�ŁA���̏��L�͑S���łP�T��Ƃ�����܂��j�A�o�b�n�ɐG�点�Ĕ����������������̂ł��傤�B�I���K���ł��̖��������Ƃ����邩������܂��A�W���o�[�}�����ł��B �@���̂悤�Ɏ��X�Ɗy���n��������тɃo�b�n�͉��t���I���邱�ƂɂȂ�̂ł����A�����ʼn��̓s�A�m��e���A���G�Ȃ���e�[�}�������āA������Ńt�[�K�ɂ��Ă݂�悤�ɗ��݂܂����B���ꂪ���̋Ȃ����ɏo�邱�ƂɂȂ����L���Ȃ��������ł��B�o�b�n�͑����̖��l�ŕ������Ă܂�������A�剤�Ƃ��Ă͋����ÁX�őO�X���炻�̊����l���Ă��̂�������܂���B�^����ꂽ�ۑ���o�b�n�͉��̖ڂ̑O�łR���̃t�[�K�Ƃ��ăt�H���e�s�A�m�Ō����ɂ���Č����܂��B���̂Ƃ��A���Ɍ` �����w�肳��Ă����Ƃ������y�͂Ȃ��悤�ł��B���͂���Ɋ��Ŗ����̈ӂ�\�����A���̏�ɋ����킹���y�c���Ȃǂ͋����Ɗ��т������Č}���܂����B����Ńo�b�n�̕������̉��l�̃e�[�}���ϔ������ƖJ�߁A�������߂ēK�ȃt�[�K�ɂ�����A���i�Łj�ɒ��点�Ă��炤���ƂɌ��߂܂����B �@�����̌��j�A�o�b�n�͉��̊�]�������ċ���ŃI���K����e���܂������A�[���ɂȂ��ĉ����炳��ɂU���� �t�[�K�����������ƌ����܂��B���̂Ƃ������ɁA�ŏ��ɉ����������e�[�}�ł��悤�ɂƂ����w�����������Ƃ͏�����Ă��܂���B�o�b�n�͎����őI�e�[�}�����R�ɃA�����W���ĂU���̃t�[�K�����ɂ��Ȃ��܂����B�����Ă�����D�]�ł����B���̌��ɂ��ẮA���������̃e�[�}�ɂ������A����̂Ńo�b�n�����ނ����Ƃ������߂�����܂����A���̓���Ԃ̉��t�Ɋւ��āA�o�b�n���������s�����Ƃ��A���̐\���o��f�����Ƃ����悤�ȋL�q�͑�ꎟ�I�Ȏ����̒��ɂ͌�������܂���B�������o�b�n�͂��̏�ŁA��芮�S�ȋȂƂ��邽�߁A���̃e�[�}�ɂ��U���̃t�[�K���u��Ȃ��Č�ő��点�Ă��������܂��v�Ɛ\���o���悤�ł��B�����ŏh��ɂ��悤�ƌ��߂Ă����������̂��ƁA���̌�̌��敶�ł��q�ׂĂ��܂��B���ʂ̐�����A�ւ肭�����Ă��̂Ƃ��̉��t���u�����s���������v�Ƃ��q�ׂĂ͂��܂����B�����������A���̏�ŗ^����ꂽ�e�[�}�ɂ��R�p�[�g�̑��������ŁA�\���������Ȃ��ł��傤���B�W���Y�̂���̃C���v�����B�[�[�V�����ȏォ������܂���B�W���Y�����Ċ���e�������i���b�N�j���������O�����č���Ă����A�K���ɂȂ���l�����邮�炢�ł��B�����ē������҂ɉ������Ȃ��������炩�A�T�[�r�X�⎩�Ȗ����Ƃ��Ă������̂��̉��߂͂��Ă����A���̂悤�ɂ��Č������đ������̂��u���y�̕������v�Ƃ����킯�ł��B �@ ���͂���ĂȂ��H �@�t���[�h���q�剤���o�b�n�ɍŏ��Ɏ������e�[�}�ł����A����͒Z���ŏオ���čs������A�����K�ō~��ė� ����̂ŁA���l���̊w�҂����͂����剤�삾�Ƃ͍l�������炸�A�t���[�g�̐搶�������N���@���c�ɍ�点���̂��낤�A�Ƃ��A�o�b�n�̑��q�̃J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G���ɗ��̂��낤�A�Ȃǂƌ����܂��B������v������قǂ̍�Ȕ\�͂͂Ȃ������Ƃ����킯�ł��B�܂��A���錤���҂̓w���f���̃C�Z���̃t�[�K�iHWV609�^���o�ł͂P�V�R�T�N�j�Ɏ��Ă�Ǝ咣���܂����B�w���f���̂��̋Ȃ͕����Α�ϕ��G�ł���A���邭������₷����ȉƂ̃C���[�W�Ƃ͂�����Ȃ��A�w���f�����Ă���ς肷 �����˔\�B���Ă��ȁA�Ƃ��������̍�i�ł��B�m���Ɏ��Ă��āA�剤�̃e�[�}���炢���������O���ēW�J���������A�Ƃ��������܂��B�I���K�����`�F���o���Œe�������̂ł��B���ʓI�Ƀo�b�n�̑��q�����̃w���f���̂��Q�l�ɂ����Ƃ��A�o�b�n�{�l����Ȏ��ɂ�������ɂ����Ƃ��A�z�������܂�������邱�ƂƂȂ�܂��B �h���̌��� �@���͑��q�����������̂̓V�F�[���x���N�ł��B�ނ͂�����ƈӒn���Ȍ��������Ă��āA�t���[�h���q�剤���o�b�n��J�߂邽�߂�㩂Ƃ��āA�킴�킴�Έʖ@�W�J����������K�̉��~�������A�����̎g�p�l�ł���J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G���ɑO�����ėp�ӂ������ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ����̂ł��B�\�Z�@�̗L���ȍ�ȉƂ����ɁA���̈ӌ��͖��炩�ɉe���͂�����܂����B�p���������悤�Ǝv�����A�Ƃ������z���X�p�C�X�����Ă܂��B�@�@�@ �@���������l�K�e�B�u�Ȍ����́A��Ō����t���[�h���q�剤�̓�Ɋ����l���]���̂����A�������Ɋ�Â��� ���̂Ȃ̂ł��傤�B�킴�킴�ނւ̓�̕]�����ɐG�ꂽ�̂́A���̏o��̂���������߂���ۂ̓�̑ԓx�Ɍĉ����邩��Ȃ̂ł��B�剤�ɂ��ẮA�P�X���I�ɂ͂��̌��т�J�߂�_������ł����B�i�|���I�������h���Đ�p���w�сA��Q���������A����˒I�ɏ����ȑ���u�����肵�Ă܂����B���̌�q�g���[���Q���}���̉p�Y�Ƃ��Đ��q��������ǂ��A�q�g���[�̓A���g���E�O���t�ɂ��L���ȃt���[�h���q�̏ё�������L���A�����Ɛg�߂ɏ����Ă������炢�ŁA�Ō�̂P�Q���Ԃ�`�����f��ł����̊G���o�ė��܂��B�����l�ԕs�M�Ɋׂ��Ă����ӔN�̎p�ł���A������Ƌ^����������悤�ȁA�ǂ����߂����ڂ��������̂ł��B �����Ă��̃z���R�[�X�g�̑����̓��A��ƂȂ�A���̑剤�̕]���͋t�]�A�����ɂȂ艺�������̂ł��B��\�ꐢ�I�ɂȂ��Ă܂��A�����`�����ς��n�߂��Ƃ������Ƃł����B �@ �@  Frederick�U, "The Old Fritz", Anton Graff 1781 �@����Ƃ͕ʂɁA�t���[�h���q�ƃo�b�n�̉��y�̍D�݂̈Ⴂ�A�˂��ė��v�z��M�̈Ⴂ�����l�̏o��𑈂����Ƃ̂悤�Ɍ��錩��������܂��B��̓I�ɖ��O�������������Ȃ����A�������ɋ��ʂ����S�̐������낤����ǂ��A�����̘_�҂����������s�a�����Ƃ�܂��B���̍ہA���ꂼ��̌�����莆�Ȃǂ�Ȗ��ɒ��グ�ĉ����𗧂Ă�l�����܂��B �@���邢�͂����Ƒ傫���A��̎���l���̏Փ˂��Ƃ��錩��������܂��B�m���Ƀo�b�n�́A�t���[�h���q�剤 ����鉹�y���ǂ��������̂��͒m���Ă��Ȃ���A���̏�Ŋ����ěZ�т邱�ƂȂ����g�́A�S���g���̈قȂ鋌���̉��y�ʼn��������ƂɂȂ�̂�������܂���B�������A���̓��ӂȃt���[�g�̊���g���I�E�\�i�^�ɂ����Ă͈ꕔ�A���葤�̑����l���i�M�������g�l���Ƌ߂��W�ɂ���j��������Ă݂��Ă���Ƃ����ӌ�������܂��B���ɗl����͑Η����ƌ���ɂ��Ă��A������Ƃ����Ă��݂��ɔ��ڂ������Ă����Ƃ܂Ō������ł��傤���B�����ғ��m���Ԃ���P�[�X�����Ă���܂��B �@������ɂ��Ă��A����ȋ�ɔے�I�Ȍ�������낤�Ƃ����_�҂́A�剤�ɏ����ꂽ�o�b�n�̑����l�i�҂Ƃ� ���Ȃ��悤�ŁA�U���̑����܂�A���̃e�[�}�ł͉ʂ����Ȃ������o�b�n�͂�����������v���A��Ŋy���ɂ��Ē�o�����u���y�̕������v�ł́A�剤�����ӂƂ���t���[�g�̃p�[�g���킴�Ɠ�����Ĕ��������A���邢�͉����Ȃ���i��ŐG��܂��j���d�|�����A�ƍl�����������悤�ł��B�Ђ���Ƃ���ƁA���߂Ɍ��_���肫�A�̘_�c�Ȃ̂ł��傤���B�ӔN�̃o�b�n�̐��i�ɂ��ċ�̓I�ɂ͒m��܂��A�l�Êw�ŐV��ȃA�C�f�B�A��������҂����₽�Ȃ��̂́A����Œ���������Ď����̑��ɗ���Ζ��_������ł��傤�B���j�͉��x�ł��đn���ł��܂��B������V�F�[���x���N�ɕ���āA�܂��܂��F�X�Ȑ������@����ė��邾�낤 �Ǝv���܂��B ���₩�Ȍ��� �@�ł́A����Ƃ͐^�t�́A����܂ł̓`���I�Ș_���͂ǂ����痈���̂ł��傤�B�剤�͗L���ȃJ���g���i���C�v �c�B�q�̃g�[�}�X����̉��y�ēj�ł���o�b�n�h���Ă���A����Ă݂����A�ł�����̔\�͂��m���߂Ă݂����A�ƍD��S���X�Ɍ��Ă����ɈႢ�Ȃ��Ƒ� �����ė��܂����B�o�b�n�̕����l�C�̂���ꍑ�̉��ɂ��₤�₵���h�ӂ��ċ߂Â����͂����A�ƍl�����Ă����킯�ł��B�����������������N���ė����匳�̏�́A���j�̃J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G���E�o�b�n�ƃo�b�n�̒�q�ŗ{�q�ł����������n���E�t���[�h���q�E�A�O���R�[���ɂ��u�̐l���`�v�iBach�fs Nekrolog [obituary], Carl Philipp Emanuel Bach and Johann Friedrich Agricola, 1754�j��A������̉��y�w�҂Ńo�b�n�̍ŏ��̓`�L��ƂƂ��Ȃ������n���E�j�R���E�X�E�t�H���P���̓`�L�iJohann Sebastian Bach: His Life, Art, and Work, Johann Nikolaus Forkel, 1802�j�A�o�b�n���剤�ɑ������y���ɓY����ꂽ���敶�iDedication of the Musical Offering, J.S.Bach July 7, 1747�j�A����ɂT���P�P���t�̓����̃V���s�i�[�V�F�V���̋L���iSpenersche Zeitung, May 11, 1747�j�Ȃǂł��B���݂ɑ�����������_������܂����A��̕`�ʂł͂���炢�������������܂����B�t�H���P���̕��͓������s���Ă��̏�ɂ����t���[�f�}���E�o�b�n���璼�ڕ����Ă���A���������Ă邩������Ȃ��ƌ�������̂́A���̌�̑����̉����̍����ƂȂ��Ă��܂��i�ނ̐��ɂ��ƁA�܂��o�b�n�̕������ɑ����̃e�[�}�����߁A���͂��ꂪ�����ɉʂ������̂����āA���炭�͂����������Ƃ��ǂ��܂ŏo������̂������������̂ŁA�U���ŕ����Ă݂����Ƃ����]�݂�\�������̂��낤�Ƃ������Ƃł��B����͓����� [�V��] �̏o�����Ƃ���Ă���A�o�b�n�͉��̃e�[�}�̑S�Ă̕������U���ɓK����킯�ł͂Ȃ������̂ŁA�����̃e�[�}�ʼn��t�����̂��ƌ����Ă��܂��B���ꂪ��̂U�������̎��s���ւƖc���ōs���܂����j�B �@��l�̏o��̗l�q��`���邱���ŏ��̎����͂ǂ���A�o�b�n�Ɖ��̊W���D�ӓI�ʼn��₩�ȋ�C������� �������̂Ƃ��ĕ`���Ă��܂��B�ł����������C�m�Z���g�Ȍ����A���{�̌���������M����l�A�݂����ɏ�������Ȃ�����������̂ł��傤���B �u�t���f���b�N�E�U�E�O���C�g�v�ƌĂ��剤���ƃt���[�h���q�Q���́A�o�b�n���K�ꂽ���̂Ƃ��A�I�[�X�g ���A�p���푈�̈ꕔ�ł����ꎟ�A�y�ё�V���W�A�i�V�����[�W�G���F�`�F�R�ƃ|�[�����h�̊Ԃɂ���y�n�j�푈�ɏ������A�ΒY��S�Ƃ������z���������L�x�Ȃ��̒n�̗̗L�𐢊E�ɔF�߂��������ł���A�܂��ɖ����̐Ⓒ�B�D�����������N�푈���n�܂�O�̕��a�ȓ��X�𑗂��Ă��܂����B��łȐl�Ԍ����ƕ]�����܂łɂ͂܂��܂����ԓI�P�\������܂��B�̒��͏�ɖ��S�ł͂Ȃ������悤�����ǁA�Z���O�ɂ͗L���ȉ��{�A�O��̃T���X�[�V�̊��������j������������Â��� ����ł����B �@�o�b�n�ƃt���[�h���q�剤�A���̓���Ԃ̐S���𐄎@������悤�Ȓ��ڂ̋L�^�͎c���Ă��炸�A�{�l�������� �邱�Ƃ͉i���ɂ���܂���B��l�̏o��Ɓu���y�̕������v�̔w�i�ɂ������S�����ǂ��ǂ݉������A���ǂ���͘_�҂̐S�̋��Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B  �y�ȍ\���Ɖ��t�]�ɂ��� �@�Ȃ̍\���ɂ��Ăł����A����͉��y�w�҂��D��Ńe�[�}�Ƃ���ʔ������̂ŁA�{���Ȃ炱�̋Ȃ̐����Ƃ��� ������^����ɂ��ׂ��Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����A��������O�ɂ́A���`�F���J�[����J�m���Ƃ͉�����Ƃ��A�U�p�[�g�̉��y���ǂ��������ɂ��Ĉ�l�ł����t�\�ɂȂ�̂��Ƃ������ƂȂǂ��A��ʌ����ɂ͐���������������������������܂���B �`�U�����{�̎�łǂ�����Ēe���H �@����������{�����肪�Ȃ��̂��������i�������^�����p�[�g�j�̋Ȃ���l�Ńs�A�m�Œe����킯�ɂ��ẮA����͓d�b����ȂǂŁA�����̐l�̉�b����{�̃��C���[�ň�x�ɉ^�Ԃ��߂̕��@�ł���u���������d���v�iTDM�j�Ƃ����f�W�^���Z�p�ɂ�����Ǝ��Ă��܂��B��b��A����AB����AC����ȂǁA�d�˂����l�������̉�b��Z�����ď��Ԃɕ��ׂđ���A�l�������I�������܂�A����AB����AC����... �Ɠ��ɖ߂��Ď��̒Z�����ꂽ�����𑗂�܂��B�葤�ł͂����A����̕������AB����̕������܂Ƃ߂ĉ�b�̑���ɔz��̂ł��B���̉�b�҂��ԂɊ��荞��������Z���������ɂȂ�܂����A�����Ă���l�̊��o�͂��̊Ԃ������ŕ⊮ ���܂�����Ȃ����ĕ������܂��B����͗L���ȁu�����t���@�C�I�����̂��߂̃\�i�^�ƃp���e�B�[�^�v�ȂǂƂ������ŁA��l�Ȃ̂ɂ܂�œ�l�Œe���Ă�݂����ɕ��������o���̂���l�Ȃ番���邩������܂���B������e�����̐��������ԓI�ɂ��ɕ���������ŁA���݂ɍ������݂Ȃ��珇�Ԃɒe���A�Ƃ������@�Ŏ������Ă���̂ł��B������Պy��̏ꍇ�A�w�͏\�{����̂ŁA�����ɘa���Ƃ��ĕʂ̐�����炵�Ă��镔���������킯�ł����A�����������G�Ȏ菇�A�f�W�^���Z�p�Ȃ獂���x�̐������U�킪���b�N�������Ă��ꂢ�ɐU�蕪���Ă���邩������Ȃ����ǁA���y�łT���A�U���ƂȂ��ė���Ɠ����p���N����悤�ȋ��낵�����x�ȋZ�ł��B�����ōl�����e�[�}�ł��ɂ���A�����Ƃ������Ƃɂł��Ȃ�A�u�ԓI�Ɋe�p�[�g����Ȃ��āA���������ɂ��č����Ă��܂��B�ǂ�ȓV�˂������낤�Ƃ������̂ł��B�@�@ �`���`�F���J�[���̎d�|�� �u���`�F���J�[���v�Ƃ����̂́A�o�b�n���t���[�h���q�剤�Ɍ��悵�����́u���y�̕������́v�ɕt�����T�u�^ �C�g���ł���Ɠ����ɁA���̃e�[�}�ɉ����č�������̒��̓�̊y�Ȃ̖��O�ł�����܂��B�o�b�n�͂����������O�̋Ȃ����̓�Ȃ�������Ă��܂��A�T�u �^�C�g���̕��́u���̖��ɂ����ƁA������J�m���̋Z�@�ɂ���ĉ����������̑��̊y�ȁv�Ƃ������̂ł���A���e����� Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta �ƋL����܂����B���̓����������� RICERCAR�A���`�F���J�[���ɂȂ�Ƃ����A�Â����d�|���ł��B���̌�́A���X�͑Έʖ@�ŏ����ꂽ�������̖͕�I�Ȋy�Ȃɑ���Â��Ăі��ł���A�U���̃��`�F���J�[���͏����̃��e�b�g�̗l���ō���Ă��邵�A�J�m���Ȃǂ��܂� �āA�o�b�n�̓t�[�K�̑O�g�̂悤�ȁA���邢�͂���Ɠ��ނ̂悤�ȈӖ��Ŏg���Ă���悤�ł��B�C�^���A��́u�T���v�̃j���A���X�����߂��Ă���̂�������܂���B �`�p�Y���̎�ށi���s�E�I�E���s�E�����E��E�ȏ��E�y��j �u�J�m���v�Ƃ����̂͗֏��̂悤�ȍ\���������Ă��āA�i�����`���̃t�[�K�Ƃ͈���āj������ƌ��i�ɓ����` ���Ƃ鐺�����J��Ԃ���A�ςݏd�Ȃ��čs���y�Ȃł��B�����������`�Ƃ����Ă��A���̂܂܌��̎p�ōs�����́i�u���s�J�m���v�j�����łȂ��A�����������납��y�����t�ǂ݂ɂ��� �u�t�s�i�I�`�j�J�m���v��A�㉺���Ђ�����Ԃ��ꂽ�`�ŏd�˂�u���s�J�m���v�A�I���Ȃ��ǂ�ǂ�ǂ�������u�����J�m���v�ȂǁA��ނ�����܂��B�����Ă���ɉ����āu��J�m���v�Ƃ����`�������ł͏o�ė��܂��B�����Ƃ����ƁA�Ⴆ�Ύl�l�p�Ȃ̂ɓ�l�������y�����Ȃ��A�Ƃ��������̂ł��B���Ⴀ�ǂ����邩�B�q���g���L���ŏ�����Ă�ꍇ��������̂́A�y�����Ȃ��p�[�g�́A�J�n�_�≹�̍����A�a���\���ȂǁA�t�҂���������悤�ɍl���ĉ��t����̂ł��B����͋c�_���Ăт܂��B�܂��A�ȓ��m�̏��Ԃ����܂��Ă��炸�i�o�ł���Ă������̊y���ɏ]���ΌŒ肳�ꂽ���̂ƂȂ�܂��j�A�w�肳��Ă��Ȃ��S���y������ɂ��邩�Ƃ����p�Y��������A���́u���y�̕������v�S�̂�������̔������̂̂悤�Ȑ����������Ă���̂ł��B���t�҂ɂ���Ă͓����ȂƂ͎v���Ȃ��d�オ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A��̓I�ɌX�̊y�͂Ƃ������A�Ȃ��ƂɁA���̂�����ƍ��������čs���K�v������ł��傤�B �@�����������̘b�͕�����₷���������Ă����T�C�g������A�u�b�N���b�g���܂߂đ����̉���ł܂���� ��邱�Ƃł��B���̃y�[�W�ł͂�����̔\�͂�������̂Ŋ������܂��B�c�������������A�܂�n�[�h�ʂɂ͐G�ꂸ�ɁA��������ۂ݂̂��L�����Ƃɂ��悤�Ǝv���̂ł��B����͕]�Ƃ��Ă͉��䍜�̂Ȃ��Ƃ̃X�P�b�`�A���S�n�ŕ]������X�|�[�c�J�[�̂悤�Ȃ��̂ł���A���邢�͂܂���s�@�̚g���ɖ߂�Ȃ�A�G���W�����͂���\�A�X�s�[�h�u���[�L�̌����Ƃ��������̂𑪒葕�u�Ȃ��Ɋ��o�Ŏ�������悤�Ȏ��Ԃł��傤�B�O��̃I���K���ȂɈ��������A�܂��܂�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B �`�Ȗ� �@�ȉ��Ɋe�Ȃ̃^�C�g���̂L���܂��B�ȏ��̓x�[�������C�^�[�Ђ̐V�o�b�n�S�W�ɂ����̂ŁA���ɂ��F�X�ȏ����ʼn��t����邱�Ƃ�����܂��F �@�R���̃��`�F���J�[���iRicercare a 3�j �@���̎��ɂ�閳���J�m���iCannons diversi super Thema Regium�j �@�Q���̊I�`�J�m���iCanon a 2 [crab canon]�j �@�Q�̃��@�C�I�����ɂ��Q���̓��x�̃J�m���iCanon a 2 Violin[:/i] in Unisono�j �@�Q���̔��s�J�m���iCanon a 2 per motum contrairum�j �@�Q���̔��s�̊g��ɂ��J�m���iCanon a 2 per augmentationem, contrario motu�j �@�Q���̗����J�m���iCanon a 2 [circularis] per tonos�j �@�T�x�̃J�m�����t�[�K�iFuga canonica in Epidiapante�j �@�U���̃��`�F���J�[���iRicercare a 6�j �@�Q���́u���߂�A����Η^������v�ɂ���J�m���iCanon a 2 �gQuaerendo invenietis�h�j �@�S���̓�J�m���iCanon a 4 �gQuaerendo invenietis�h�j �@�t���[�g�A���@�C�I�����A�ʑt�ቹ�̂��߂̃g���I�E�\�i�^�iA Sonata sopr�fil Soggetto Reale�j �@�@�����S�iLargo�j �@�@�A���O���iAllegro�j �@�@�A���_���e�iAndante�j �@�@�A���O���iAllegro�j �@�����J�m���iCanon perpetuus�j �`�����J�m���ɉB���ꂽ�^���H �@���قǂ́u�����J�m���v�Ƃ����͖̂����J�m���̈��ŁADNA �̗����̂悤�ɁA�J��Ԃ����Ƃɒm��Ȃ������Ɉ�x���������オ���čs�����̂ł��B���̉h���������܂��悤�ɁA�Ƃ����Ӗ����o�b�n�͍��߂Ă��܂����A�_ �O���X�E�z�t�X�^�b�^�[�́u�Q�[�f���A�G�b�V���[�A�o�b�n�v�Ƃ����A�s���[���b�c�@�[�܂�����Ĉꎞ����Ϙb��ɂȂ����{�ł́A���Ȍ��y�̃p���h�b�N�X��������N��������ŁA���w�̘_���A�L�����̉ߒ��A���邢�͔F�����̂��̂��A�����g�D�ɋ��ʂ���B�ꂽ�\������@�\����������鎞���L�̓����������Ă���Ƃ��A������o�b�n�̂��̗����J�m���Ɍ����ĂĎ��グ���悤�ł��B�����Ȃ��ė���ƁA�l�H�m�\�����t�̗̈�������̔����̗͂�Z�����Ƃ͌����ĂȂ����Ƃ��A���̐��w��_���w�̌��t�ŕ\���Ƃǂ��Ȃ�̂��A�V�˃o�b�n�͉��y�̌`����ė\�����Ă����A�̂ł��傤���B���ɂ��ꂪ���ӎ��̍�Ƃ������ɂ��Ă��A����ȏ�R�[�h������Ă���̂�������܂���I ���������̖{�ɂ��ƁA�����㏸���Ă��P�I�N�^�[�u��ɂ͏o���Ɍ��ɖ߂��ė���炵���̂ł����B �@�܂��A��k�͂��Ă����āA�����Ƃ������̂͐��m�����Ȃ��Ɠ���ꍇ������܂��B����������킵��̐����o�����o�Ă��Ă��A�Ƃ肠�������������ƌ����Ă����̂���̗U�f���蓾��A��������܂���B�������o�b�n�̐�含�̏ꍇ�A�U�̃p�[�g�����ĐD�荞��ł���U���̃��`�F���J�[���ȂǁA��i�Ƃ��č��x�ɒm�I�Ȋ����̎Y���ł���ɂ�������炸�A�����Ă��邾���ł��Ɠ��̏������܂��B���������J��Ԃ��̂̓t���[�h���q�̒����̂����ɈႢ�Ȃ��Ƃ��Ă��A���ꂪ�p���āA���Ƃ��Ђ��ނ��Ȋ����ɋ����ė���̂ł��B�剤�ɂ��Ă݂�Ύ����̍D�݂̗l���ł͂Ȃ������̂ł��傤���A��Ȃ���l�ԂƂ��ẮA���̉��l�͂�蕪�������ɈႢ����܂���B �u���y�̕������́v�A�o�b�n�ӔN�̓��B�_�ł���A�����d���͂��邯��nj͂ꂽ���ς̂悤�Ȃ��̂����������A�m�炸���炸�̂����Ɏ䂫���܂���ϖ��͓I�� �Ȃł��B�ɂ߂Čl�I�Ȉӌ������F�X�Ȍ����������������ʔ����ł����A����������ɂ����Ă͂��̍�i�A���l���Ȃ߂�Ӑ}���B���Ă���悤�ɂ͑S�������� ����B   Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Karl Richter (hc/cond.) ♥ Aurèle Nicolet (fl) Otto Büchner (vn) Kurt Guntner (vn) Siegfried Meinecke (vc) Fritz Kiskalt (vc) Hedwig Bilgram (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �J�[���E���q�^�[�i�`�F���o���^�w���j♥ �I�[�����E�j�R���i�t���[�g�j�^ �I�b�g�[�E�r���q�i�[�i���@�C�I�����j �N���g�E�O���g�i�[�i���@�C�I�����j�^ �W�[�N�t���[�g�E�}�C�l�b�P�i�`�F���j �t���b�c�E�L�X�J���g�i�`�F���j�^ �w�h���B�b�q�E�r���O�����i�`�F���o���j �@�^���N�㏇�ɍs���܂����A�܂����炭��Ԃƌ����ė������q�^�[�Ղ���ł��B�Â�����̃t�@���͑�����ŏ��ɔ����Ă����肷���Ȃ��ł��傤 ���B���q�^�[�ɂ��Ă͑����̕����_�l��������Ƃ���ɔ������Ă���킯�ł͌����ĂȂ�����ǂ��A���܂ł��܂�♡��t���ė��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B�ł�����͂悭�����ė��܂����B�ǂ����t���Ǝv���܂��B��ʼnƐl�� CD ���������Ɛ\�����̂͂��̔ՂŁA�������Ⴄ�悤�Ȃ��̂Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���ɂ���Ȗ��ՁA�茳�ɒu���Ƃ��Ȃ��Ă����̂��ȁA�Ƃ�����ƔY�̂��o���Ă��܂��B �@���q�^�[�̃`�F���o���͏��炸�A�d�X�������Ȃ��A��������̃s���I�h�t�@�u�[���ȍ~�́u���߁v���������悤�Ȏ�ނł��Ȃ��A�^����������̂܂܂Ƃ��������ōD�������Ă܂��B�e���|�͓��ɒx�����ł͂���܂���B �@�����Ă��̔Ղł̓t���[�g�Ƀj�R����������Ă���̂��܂���ϖ��͓I�ł��B�I�[�����E�j�R���͂Q�O�P�U�N�ɖS���Ȃ��Ă��܂��܂������A�X�C�X�̖��t ���[�e�B�X�g�ŁA�t���[�g�E�\�i�^�ȂA�����ɔނ̂���Ԃ��Ǝv������������̂��C�ɓ���ł��B������̃����p���ȂǂƂ͈���ď��炸�A���邭���Ȃ��ł����A�����łǂ����z�Ƃ����Ƃ���̂���A�����Ɨ��������ɖ��������t�ɓ���������܂����B���̎��ゾ����r�u���[�g�͂����܂����A���̉��~����� �߂��Ȃ��ėǂ������ł��B���́u���y�̕������v�ł́A�t���[�g������̂̓\�i�^�ł����ċȏW�S�̂ł͂Ȃ����̂́A���Ƀ����S��A���_���e�ł������� �̃e���|�ݒ�ɂȂ��Ă���A�����t�����\�ł��܂��B �@♡♡�ɂ��Ȃ������̂͂�����Ƃ������ƂŁA��Ɍ��̃p�[�g���h�C�c���ɗ͋����A�������Ɖ����悤�Ȓǂ����G�l���M�[��������Ƃ��낪�A�S���l�I�ɂł����A�D�݂̕����Ƃ͏���������Ƃ��������ł��B�����������Ԃ̂��鉉�t�̕����D���ł��B���ŏq�ׂ܂����A�^���̓������W������ł��傤�B�����Ƒ����l�܂�Ƃ͌����܂��A�ǂ����^�������Ƃ��������������āA���邢�͂��ꂱ�����o�b�n�Ɗ��������������������܂���B���������Ƃ���ł̓e���|�������Ēx���͂���܂���B �@�P�X�U�R�N�A���q�[�t�̘^���͍��ł��\���Ɍ����ł��B���������̃h�C�c�E�O�����t�H���i�A���q�[�t�͂��̈ꕔ��ł����j�ɂ��肪���������A�������̔{�����}�����C���ŁA����Ɋ�����������Ē������Ƃ���̂���o�����X�ł����A�����͂Ȃ��A�`�F���o���̉����₩�܂����Ȃ炸�ɗ��������ĕ����܂��B��̃W���P�b�g�̎ʐ^�� CD �ł͂Ȃ��A�I���W�i���� LP �̂��̂ł��B  The Claves Bach Soloists Peter-Lukas Graf (fl) ♥ Hansheinz Schneeberger (vn) Ilse Mathieu (vn) Walter Kagi (va) Rolf Looser (vc) Christine Daxelhofer (hc) Jörg Ewald Dähler (hc) �y�[�^�[�����[�J�X�E�O���[�t�i�t���[�g�j♥ �n���X�n�C���c�E�V���l�[�x���K�[�i���@�C�I�����j �C���[�E�}�e�B�E�i���@�C�I�����j�^ �����^�[�E�P�[�M�i���B�I���j �����t�E���[�U�[�i�`�F���j�^ �N���X�e�B�[�l�E�_�N�Z���z�[�t�@�[�i�`�F���o���j �C�F���N�E�G�[���@���g�E�f�[���[�i�`�F���o���j �@���̓j�R���Ɠ�������Ɋ���������l�̃X�C�X�̃t���[�g�̖���ɂ�鉉�t�ł��B�y�[�^�[�����[�J�X�E�O���[�t�̓j�R�����O���� �P�X�Q�X�N���܂�ŁA�������ł����A�������ɂ����V�����^�����o�ė���悤�Ȑl�ł��Ȃ��ł��傤�B�X�C�X�̃N���[���F�X�Ƃ����A���قǑ傫���͂Ȃ����[�x������o�Ă����ɂ�������炸�A���{�ł̓h�C�c�E�O�����t�H���Ɠ����������Ƃ������Ƃ�����A�ꎞ�������̉��t�������܂����B���ł��ŏ��̘^���̕��̃��[�c�@���g �̃t���[�g�l�d�t�Ȃ� K.285 �̃A�_�[�W�������Ƃ����炩�ŁA�F�X�ȗ��V�̉��t���o�����ł��������ꂩ�ȂƎv���Ă邮�炢�ł��B�j�R���������ƃr�u���[�g�����Ȃ��������A��������Ə�ߑ��ɂȂ�Ȃ������ȉ^�т���������ł��B �@���q�^�[�Ղɑ����������̂Ƃ͈Ⴂ�A�����グ��悤�ȗ͂����������鉉�t�ł͂���܂���B�h�C�c�ł͂Ȃ��X�C�X���V���ƌ����ƒP���߂������ǁA������Ƃ���Ȃ��Ƃ��v���܂����B�͂������ē����ŁA���ȑ��߂̃e���|�ݒ�̋Ȃ͂�����̂́A�c��͂������ȓW�J�ł���A���̎���ł����甏��傫�����炷�悤�ȌÊy�t�@�I�ȑ������͂���܂���B�f���Ő^�������ł��B �@�������ȃ`�F���o���̓���͑������Ȃ��A�Ȃ̂Ȃ��W�J�ŁA���̉��t�����ꂽ�l�͋t�ɋ����ł��傤���B��Ȗڂ̃J�m���ɓ���ƃe���|���オ��A���y�ɂ��A������Ȃ̂Ȃ�������Ƃ����W�J�ƂȂ�܂��B�������t�[�K�̑O�̋ȁi�T�x�̃J�m���j�ɂȂ�ƍ��x�͂����ƃe���|�𗎂Ƃ��܂��B�t�[�K�̓`�F���o���Ƀt���[�g�����ޓW�J�ł��B�U���̃��`�F���J�[���̓`�F���o���݂̂ɂ����̂ł����A��ς�����肵�����x�ł�������i�߂čs���A�������ɂ���Ă͕��R�Ɋ������邩������� ����B�����J�m���̌��̃p�[�g�����l�ŁA�t���b�g�ő�ϒx�������܂��B �@�g���I�E�\�i�^�ł͊��҂��Ă����t���[�g���܂Ƃ߂ĕ����܂��B�O���[�t�炵���A����Ȃ��^���������Ȃ���f���P�[�g�ȗ}�g�̂������̂ŁA������������A�͂������Ă��܂��B�p�C���[���Ղ̃������[���ǂ��ł����A���_���E�t���[�g�ł̐������Ƃ��Ă͂��̋Ȃōł��[���ł�����̂ŁA�Â��Ő�����������܂��B�r���ŃX�s�[�h�A�b�v�������A�x���Ƃ���ł͂��Ȃ�x���W�J�ł��B♡�͂��̃t���[�g�ɕt���܂����B����炵���̂́A�U���̃��`�F���J�[���̃`�F���o����S���̃J�m���̌��y�ɑ�\�����悤�� �t���b�g�ŃX���[�ȓW�J�����܂莩���̍D�݂ł͂Ȃ���������ł��B���������Ă������蕷�������l�����ł��傤�B �@�P�X�U�W�N�̃N���[���F�X�i�I���b�N�X�E���R�[�f�B���O����o�Ă���Ղ�����܂��j�̃R���f�B�V�����͑�ϗǂ��ł��B�U�O�N��Ƃ������ƂŐS�z����悤�ȗv�f�͉����Ȃ��A�c��������Ȃ��瓧���ŁA�����ׂ����Ȃ�߂����A���X�����̂ł��B�����y���ЂƂ̉������ꂢ�ɕ�������^���ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Nikolaus Harnoncourt (vc/gamb) Leopold Stastny (fl-traverso) Alice Harnoncourt (vn) Walter Pfeiffer (vn) Kurt Theiner (va) Herbert Tachezi (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �j�R���E�X�E�A�[�m���N�[���i�`�F���^���B�I���E�_�E�K���o�j ���I�|���g�E�V���^�X�g�j�[�i�t���E�g�E�g�����F���\�j �A���X�E�A�[�m���N�[���i���@�C�I�����j�^ �����^�[�E�v�t�@�C�t�@�[�i���@�C�I�����j �N���g�E�^�C�i�[�i���B�I���j�^ �w���x���g�E�^�w�b�c�B�i�`�F���o���j �@�A�[�m���N�[���͌Êy���[�u�����g�̊���ł��B�w���҂Ƃ��đ�ύD���ŁA�S���Ȃ��Ă��܂��ă����\���X�ƕ���Ŏc�O����������ǁA���[�c�@���g�ƃo���b�N����̂��̂Ɋւ��Ă͂��܂���グ�ė��Ȃ�������������܂���B�s���I�h�t�@�Ƃ��ĕ҂ݏo�����A�t���[�W���O�̓Ɠ��̌����Ȃ������ɂ͂��܂����܂Ȃ���������ł��B�������w�p�I�Ő퓬���[�h�̓W�J�ɂ͔ޓƎ��̐[�����߂��������̂ł��傤�B���́u���y�̕������v�ł͉s�߂���Ƃ������Ƃ͂���܂���B �@�ŏ��͂��܂�Ȃ��Ȃ����Ǝv����`�F���o���Ŏn�܂�܂��B���Ƀs���I�h�t�@�̃A�N�Z���g�������͊��������Ȃ����̂ŁA���X�^�b�J�[�g���Ńt���[�Y�� ����ĊԂ���Ƃ��낪����̂ŁA��������͂��Ă邩�ȂƂ�����ۂł��B���������̓����͔F������ė��܂��B�`�F���o���Ɍ���Ȃ�����ǂ��A�������Ƃ��Ă��āA����t���[�Y���m���߂�悤�ɐi�߂čs���A���d���Đ��^�ʖڂƂ��Ƃ��Ƃ��낪����悤�Ɋ����o���̂ł��B���߂̋��� ���̔���x�点��Ԃ���������Ƃ���܂��B�������S�̂Ƃ��Ă͓��ꊴ������A�ŏ�����{���I�ɂ͂��������g���������̂ł��傤�B����ɑ��ăt���[�g�͔�r�I�f���Ȕ��߂ł��傤���B�e���|�͕��ς�����������߂���A���ʂƂ����Ƃ���ł��B����Œx���Ƃ���ł͑�σX���[�ɂȂ�̂ŁA���\�L�яk�݂���Ƃ������܂��B�� �J�Ŋi���������t�ł���A���q�^�[�Ƃ͈�����Ӗ��ł��ꂱ�����o�b�n�A�Ɗ��������������������ł��傤�B �@���͂��̔Ղ̑O�ɂP�X�T�T�N�̃t�B���b�v�X�^���́A�ŏ��̔Ղ����݂��܂��B������̕������ꊴ�͏��Ȃ����Y���ŁA���̉��ւƃe�k�[�g���̎n�������� �`�F���o���ł���A��������X���[�_�E������Ƃ��낪�����ďd���͂�����̂́A�Êy���߂̃A�N�Z���g�͏��Ȃ��������܂��B�t���[�g�����y�����l�ŁA������芊�炩�ɁA�X���[���������Ă��邩�̂悤�ł��B�e���|�͑����Ă������ł���A�܂�Ƃ���A�s���I�h�t�@�O�̃}�i�[�Ȃ̂ł��B�A�[�m���N�[���͓�\�Z�B������̃A���X�ƈꏏ�ɗ�Ԃ̑�����N�̊�Ŕ`���Ă���ʐ^�����������ŁA���ꂩ��`���̗��ɏ��o���čs���Ƃ���Ȃ̂ł��傤�B��Ԃ�̓��h���t�E�o�E���K���g�i�[�����@�C�I�����Ƃ��ĉ����A�t���[�g�����[�g���B�q�E�t�H���E�v�t�F���c�}���A�`�F���o�����C�]���f�E�A�[���O�����ƂȂ��Ă��āA���̑��̊�Ԃ�͓����ł��B�ŋ߃��}�X�^�[���ꂽ�`�ł��o�ė��Ă��܂��B�����c���͏��Ȃ߂Ȃ����ό��ʂ����ǂ��A�R���f�B�V�����͂Ȃ��Ȃ��ǍD�ł��B�ł����m �����ł͂���܂�����A���邢�͂��̐l�����ɋ����̂���l�����A�ł��傤���B �@�ʐ^���ڂ����V�Ղ̕��́A�P�X�V�O�N�^���̃e���t���P�����Ճe���f�b�N�i�_�X�E�A���e�E���F���N�j�ł��B�h�肳�͂Ȃ�����ǂ����ՂƂ͈���ăf�b�h�ȕ��ł͂Ȃ��A�X�e���I�ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Jean-François Paillard L�fOrchestre de Chambre Jean-François Paillard ♥♥ Maxine Larrieu (fl) Gérard Jarry (vn) Brigitte Angelis (vn) Alain Mehye (va) Raymond Glatard (va) Alain Courmont (vc) Paul Gabard (vc) Laure Morabito (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �W�������t�����\���E�p�C���[�� �^ �p�C���[�������nj��y�c ♥♥ �}�N�T���X�E�������[�i�t���[�g�j�^ �W�F���[���E�W�����i���@�C�I�����j �u���W�b�g�E�A���W�F���X�i���@�C�I�����j�^ �A�����E���C�G�i���B�I���j ���C�����E�O���^�[���i���B�I���j�^ �A�����E�N�[�������i�`�F���j �|�[���E�K�o�[���i�`�F���j�^ ���[���E�����r�g�i�`�F���o���j �@���_���y��̎����I�[�P�X�g���ŁA�V�O�N�ォ��W�O�N��ɂ����Ċ��Đ������ꂽ�������Ă������t�͂ƌ����A���̃t�����X�̃p�C���[���ƃC�M���X�̃}���i�[���o���Ƃ��������ł��傤���B�o�b�n�̃u�����f���u���N���t�Ȃ�w���f���́u����̉��y�v�ȂǁA�|�s�����[�ȋȂŏ�ɍb�������������t�����A�����ł����グ�ė��܂����B������������Ă���Ƃ����Ă��A�}���i�[�������y���ȃe���|���Ƃ��ė}������i�ȗ}�g��t���Ă����̂ɑ��A�A���Z�� ���Ɠ��l�ɐ��w���w�Ƃ����p�C���[���̕��͂ނ�����������������ŁA���m�Ƃ��������Ȑ��I�ȉ̂��������Ƃ�����ۂł��B�W�������t�����\���E�p�C���[���͂P�X�Q�W�N���܂�ŁA�Q�O�P�R�N�Ɍ̐l�ƂȂ��Ă��܂��B �@�����Ă��̃p�C���[���́u���y�̕������v�A���q�^�[�Ƃ͂܂�����������œ��{�ł͈�̒�ԂƂȂ��Ă����Ղł��B�u���{�ł́v�Ƃ����̂́A�o���Ă���̂��f���I���i���f�m���j������ŁA�������̂Ƃł��������A�K�R�I�ɉ��y�G�����ō����]�����ꂽ�肵�Ă����̂ł��B�����������̂ɑa�������ł��A����ڂ��̃��o�C�o���ŃS�[���h�E���_���݂����Ȉ����������L�����������ɂ���܂��B����������A�P�X�V�Q�N�ɖ蕨����Ŏn�܂��� PCM �^���i�p���X�E�R�[�h�E���W�����[�V�����A������f�W�^���^�����ŏ��͂���ȕ��ɌĂ�ł܂����j�Ƃ��ẮA���̓�N�ォ��̉��B�ł̊���P���ł�����܂����B �@���ꂶ�Ⴀ���ƂȂ��Ă͑債�ċ����������Ȃ����t���A�Ƃ����Ƃ��ꂪ�S�����̔��ŁA����Ӗ����݂ł��ł����͓I�Ȉꖇ�ƌ����Ă�����Ȃ����Ǝv���܂��B���������b�N�X���ĕ��������Ƃ������Ƃ��ƁA�ĊO��������������Ȃ�܂��B �@�����I�[�P�X�g���Ƃ������Ƃ́A�l�����ʏ�̉��t��葽�߂ɂȂ�܂��i��̃N���W�b�g�����ۂ͑����ł��j�B�l���������Ƃ������Ƃ́A��l�ЂƂ�̕Ȃ� ���E�������ăX���[�Y���Ƃ������Ƃł��B���炩�ɂȂ��ŁA�Ђ�������������K�[�g�őt�ł�u���y�̕������v�ł��B����ȃ������[�̃t���[�g�������A�ł���g�̂悤�ł��B�D��Ŋp�̎�ꂽ�^�т́A�ǂ����̏��Ǝ{�݂ł������Ă��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B����͈����ۂ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��āA�s���I�h�y��ɂ��l�ؓI�ȓ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Êy�̋|������A�N�Z���g�͂Ȃ��A�r�u���[�g�͎g���܂��B���̎���ɏI����Ă��܂����X�^�C���̍Ō�̋P���Ƃ������A����قǎ��ɐS�n�̗ǂ����t�͖ő��ɂȂ��ł��傤�B������������t�����X�̐l�ԂƂ��āA�����I�����_��I�[�X�g���[�A�C�M���X�ȂǁA�O�̐��E�ŋN���Ă������[�u�����g�̖����ȃA�N�Z���g�ɂ͗^���Ȃ��Ƃ��������ł����āA�O���[�v�̔������̖ړI���炷��Ȃ�A�ނ�Ȃ�̗��V�ŌÊy�@���Đ��ɏo���g���͒S���Ă����ƌ�������������������܂���B�����ɂ��ݔ���u���Ȃ������Ƃ��ẮA�y�Ȃ͂܂��������Ȃ�������Ȃ��̂ł��傤�B �@�e���|�ݒ�ɂ����Ă͔�r�I�y���ȋȂƁA��ς������̂��ȂƂ�����܂��B�܂��t���[�g�ɂ�鉤�̃e�[�}�Ń��`�F���J�[�����n�߂܂����A�������̃e�[�}�ɂ��J�m���̌�ɂ͂܂����̂��߂ɍ��ꂽ�����₷���g���I�E�\�i�^�������ė��āA���ꂩ�����Ɗw���I�p���Ɠ�ɖ������J�m���Q�����グ�A�Ō�͂U���̃��`�F���J�[���Œ��߂�Ƃ����\���ł��B �@PCM �����[���b�p���̂ƌ����܂����B���̊����ŏ��͏����I���E�}�C�N�̗֊s�����̌X�����������Ǝv���܂��B���ꂪ���̉��B���^�ł͌��n�ł̉����߂ƂȂ�A���l�~�V�F���E�K���T�����v���f���[�X���邱�ƂƂȂ�܂����B�������S�ɃG���[�g�̉��ł��B���̌�����̃V���[�Y�A�Z�p�҂𐢊E�Ŋ���l�ɔC����X�����蒅���A����^�̉��B�X�^���_�[�h�̘^������ԉ����čs�����悤�ł��B���̃p�C���[���Ղɂ��ẮA���}�X�^�[������Ă���̂��낤���ǃf�W�^���̕ȂȂ� �������Ȃ��A�����������Č����ɔ��������ł��B�P�X�V�S�N�� DENON �ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Barthold Kuijken (fl-traverso) Sigisward Kuijken (vn) Wieland Kuijken (vc) Robert Kohnen (hc) Gustav Leonhardt (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �o���g���g�E�N�C�P���i�t���[�g�E�g�����F���\�j �W�L�X�����g�E�N�C�P���i���@�C�I�����j�^ ���B�[�����g�E�N�C�P���i�`�F���j ���x�[���E�R�[�l���i�`�F���o���j�^ �O�X�^�t�E���I���n���g�i�`�F���o���j �@�N�C�P���Z�킽���̔Ղ͌�Ŏ��グ�܂����A����͂���Ƀ��I���n���g��������Ă��āA�u���I���n���g�Ձv�̂悤�Ɏv���Ă�����̂ł��B���������Êy �̃}�i�[�̉��t�Ƃ��Ă̓A�[�m���N�[���Ղƕ���Ŕ�r�I���������̘^���ŁA��Ń��q�^�[�ƃp�C���[���̔Ղ����{�Œ�ԉ������Ɛ\���܂������A��������q�^�[�ƃ��I���n���g�̔Ղ��A���{�ł͈�̌��Ђ̂悤�Ɉ����ė����A�ƌ�����ł��傤�B���I���n���g�Ƃ����l���A��ɍ����]��������̃t�@�������݂��镪��̈�l�ł��B�P�X�Q�W�N���܂�łQ�O�P�Q�N�ɖS���Ȃ����I�����_�̌Êy���Ցt�҂ł��B �@�����o�[�̂قƂ�ǂ������Ƃ������ƂŁA�\���̓N�C�P���Ղɋ߂��Ƃ��������܂����A�S�̂ɂ��Êy�̃A�N�Z���g�������ł��B����������Ȃ�G�L�Z�� �g���b�N���Ƃ����ƁA���������킯�ł��Ȃ��A�������Ύ��R�ɕ�������͈͂̂��̂ł��B�y��Ґ��̓��I���n���g�̕������A�N�C�P���ՂƔ�ׂă`�F���o������ �䑝���Ă��܂��B���̃��I���n���g�̃`�F���o���́A�t���[�Y�̋��ň�u�����~�܂�Ƃ������A�����r�炷�悤�ɊԂ���߂̂�����̂ŁA��̃N�C�P���ՂŎ���ɕ��シ�郍�x�[���E�R�[�l���̉^�т��������̃s���I�h�t�@�̕Ȃ��͂����肵�Ă��܂��B���̐l�͎����ɂ���đ����X�^�C�����قȂ�Ƃ��낪����悤�� �C�����܂����A�����ł̂��̌ċz�͑��̊y��ɂ��g�y���Ă��܂�����A���������w���̉��ɍs���Ă���̂��낤�Ƒz�����܂��B�`�F���o���̉��Ƃ��ẮA��̓�J�m��������ł͑����x���Ċp������悤�Ȉ�ۂ�������A�㔼�ʼn����d�Ȃ�A�l�I�ɂ͂�╷����ꂷ�銴�������܂������A����͉��߂ŐF�X����p�[ �g�ł�����A�����I�ɓW�J�������̕����Ȃǂ��܂߂āA���I���n���g�̌����������Ă���Ƃ���Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�g�[�^���ł͂�������Ƃ��ė͂� �������A��ϐ^�ʖڂȃp�t�H�[�}���X�̂悤�Ɋ����܂����B�����������t�}�i�[���L�߂čs���g�������������̂�������܂���B �@�P�X�V�S�N�^���̃Z�I�����ՂŁA���[�x���͌��݃\�j�[�E�N���V�J���ƂȂ��Ă��܂��B�`�F���o�����O�q�̒ʂ��ő����������Ƃ������̏d�Ȃ肪�������܂����A�t���E�g�E�g�����F���\�⌷�́A�����݂����킢�ƂȂ�悤�ȃV�b�N�ȉ������܂��B 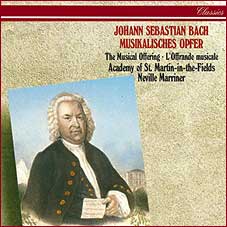 Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Neville Marriner The Academy of St. Martin-in-the-Fields ♥ William Bennett (fl) Iona Brown (vn) Stephen Shingles (va) Denis Vigay (vc) Nicholas Kraemer (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �l���B���E�}���i�[ �^ �A�J�f�~�[�����nj��y�c ♥ �E�B���A���E�x�l�b�g�i�t���[�g�j�^ �A�C�I�i�E�u���E���i���@�C�I�����j �X�e�B�[�����E�V���O���X�i���B�I���j�^ �f�j�X�E���B�Q�C�i�`�F���j �j�R���X�E�N���[�}�[�i�`�F���o���j �@�p�C���[���Ɠ������A���_���y��ɂ�鎺���I�[�P�X�g���̉��t�ł��B�P�X�Q�S�N���܂�łQ�O�P�U�N�ɖS���Ȃ�܂������A�������������̃}���i�[�ɂ�邱�̔ՁA�܂����R�[�_�[�̂悤 �ȉ��̃I���K���Ŏn�܂�܂��B�������Ƃ����Ԃ�Â����������������̂��Ȃ��Ǝv���܂����B�`�F���o�����ƕ��ʂ����Ȃ�Ȃ��̂́A�^�����߂����炩������܂���B���Ǝv���Ύ�����͂��̃`�F���o�����o�ꂵ�A�y��̃o���G�[�V�������y���߂܂��B�\���̕��́A�p�C���[���Ղ̂悤�ɗ���ɖ����ꂽ���̂Ƃ�����ۂ͂����炩���Ȃ��A�Êy�̃A�N�Z���g���Ȃ��Ă�����蒚�J�Ɋ�����ʂ͋��ʂ�����̂́A���Ȃ̂Ȃ��[���Ő^�ʖڂȉ^�тł��B�s���I�h�t�@�ɂ��Ȃ� �u���y�̕������v�́A�����Ŗ͔͓I�ȉ��t���ƌ�����ł��傤�B�h��ȓ������Ȃ����A��������ƋȂ��̂��̂𖡂킦�܂��B �@�P�X�V�X�N�̃t�B���b�v�X�^���ł����A���̃��[�x���ɂ��Ă͎c���͂��܂�Ȃ����ł��B�S�[�W���X�ȋ����ɂ͂Ȃ�Ȃ�����ŁA��ЂƂ̊y�킪�悭���ʂ��ėǂ��Ǝv���܂��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Musik Antiqua Köln Reinhard Goebel (vn/cond.) ♥ Wilbert Hazelzet (fl-traverso) Hajo Bäß (vn) Charles Medlam (gamb) Henk Bouman (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 ���W�J�E�A���e�B�N�@�E�P���� �^ ���C���n���g�E�Q�[�x�� �i���@�C�I�����^�w���j♥ �E�B���x���g�E�n�[�c�F���c�F�b�g�i�t���E�g�E�g�����F���\�j �n�[���E�x�X�i���@�C�I�����j�^ �`���[���Y�E���h�����i���B�I���E�_�E�K���o�j �w���N�E�{�E�}���i�`�F���o���j �@�Q�[�x���ƃ��W�J�E�A���e�B�N�@�E�P�������Êy���[�u�����g�̔�r�I���߂̍��Ɋ����c�̂ŁA���W���[�̃h�C�c�E�O�����t�H�����烊���[�X����A���̎���̃s���I�h�y��ɂ�鉉�t�Q�̈�p�𐬂��Ă��܂����B�Ɠ��̐�s�I�ȃA�N�Z�����g���ڗ����Ă������ɂ����Ă��A���Ɍ��I�ł͂�����Ƃ������߂̓�����ł��o���A�ދ������Ȃ��ʔ������t��������܂����B�����A�����ł͂��܂���グ�ė��Ȃ������Ǝv���܂��B�m�����g�����قǂ���Ȃ��ɂ��Ă��A�����̎���͈͂̏���s���Ƃ��낪����������ł��B �@���������́u���y�̕������v�͈�ۂ��Ⴂ�܂����B�m���Ƀ`�F���o���ɑ��������~�܂�悤�ȃt���[�Y�̐߂������ꂽ��A�e���|���̂��錷�y���t�ƃt���[�g�̃p�[�g�Ɉ��������đ�σX���[�ȃK���o�̉́i�Q���̔��s�̊g��ɂ��J�m���j���������肷����̂́A�v�����قǕȂ������������A�o�b�n�̔ӔN�̍�i�ɗՂގp���Ƃ��Đ^���́A���̍������g�݂����������܂��B�g��������Ȃǂ��o�Ă��������蓾���t�@�̉��߂Ƃ��Ď��R�����A�t���E�g�E�g�����F���\�̉������ꂢ�ł���A���̃{�E�C���O�ƈ�v���Ē��قǂ�グ��Êy�t�@�̌ċz���S�n�ǂ������܂��B�����������̂͂��̂Q���̔��s�J�m���̒x���ƁA�g���I�E �\�i�^�̃����S�ŕ\��L���ɉ���������艄�����肵�Ă���Ƃ��낮�炢�ł���A���̑��̒x���p�[�g�ł̕\��͑z����ł����B�剤�̃e�[�}�ɂ�铯 ���悤�ȋȒ����������̍�i�ɂ����ẮA���̂悤�Ƀ����n����t���������ω��ɕx��ł��ĖO�������Ȃ��Ƃ������܂��B���̊y�c�̐l�C�͂��������Ƃ���ɂ��������ƁA���炽�߂Ĕ[����������ł��B�����炪���ꂽ���Ƃ�����ł��傤�B�Ō�Ɏ����ė����U���̃��`�F���J�[�����A�L�яk�݂���A�S�[�M�N�̕\���Ƒ傫�߂̊Ԃ̋��͕�����܂����A��ϖ��킢������܂��B �@�P�X�V�X�N�̃h�C�c�E�O�����t�H���ł��B�����悤�ȑ_�����������T�N�O�̃��I���n���g�ՂƔ�ׂĂ��A��������悭�����A�o�����X�̗ǂ�������������D�G�Ș^�����Ǝv���܂��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Masahiro Arita (fl-traverso) Ryo Terakado (vn) Natsumi Wakamatsu (vn/va) Tetsuya Nakano (gamb) Chiyoko Arita (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �L�c���L�i�t���E�g�E�g�����F���\�j ���_�˗��i���@�C�I�����j�^ �ᏼ�Ď��i���@�C�I�����^���B�I���j ����N��i���B�I���E�_�E�K���o�j�^ �L�c���q�i�`�F���o���j �@�t���[�g�̗L�c���L�́A�E���W�����̎���̓����N�@���e�b�g���؉떾�^BCJ �̃o�b�n�̃J���^�[�^�ƕ���ŁA���̂ɂ���Ă͂��̋Ȃ̃x�X�g���Ǝv���鉉�t�����Ă���A�����ł����グ�ė��܂����B�D�����I�Ȃ��s�V�̗ǂ��^�тł͂Ȃ��A���݂Ő��������Ƃ�����������̉̂����������܂��B�o�b�n�̃t���[�g�E�\�i�^�ȂǁA�j�R����A���^�C���ǂ���������ǁA���_���E�t���[�g�ł�����㔭�̔ՂȂǁA���͂̓_�ł����������Ă���������܂���B���������Ӗ��ő�ϊ��҂����u���y�̕������v�ł��B���̃\�i�^�̂Ƃ��Ɠ������A�����`�F���o���ʼn�����Ă�����̂ł��B���E�I�ɗL���ɂȂ����Êy�̖���A���_�˗��̃o���b�N�E���@�C�I�����������܂��B �@���̋ȏW�A�t���[�h���q�剤�����ӂ������t���[�g�̃p�[�g�́A����Ǝw�肳��Ă���̂̓g���I�E�\�i�^�ł����āA�S�̂ł͂���܂���B���������ėL�c����l�̃p�t�H�[�}���X�ŕ]������͈̂Ⴄ�ł��傤�B�����A�t���[�g�͂�͂薣�͓I�ȉ������Ă��܂��B��������ł̓��_���E�t���[�g�ł͂Ȃ��A�t���E�g�E�g�����F���\�ł���A�o���b�N�E���@�C�I�������͂��ߌ����s���I�h�y��ł���A�S�̂Ƃ��Ă��Êy�̃}�i�[�ɂ�鉉�t���ƌ����ėǂ��Ǝv���܂��B�����A�A�[�m���N�[����I�����_���Ƃ͈Ⴂ�A���̕Ȃ͂��قNj����͂���܂���B�e���|�����_���y�퉉�t����ɋ߂����炢�������Ɋ�����Ƃ��낪����A��ϒ��J�ň�ЂƂ��m�ɉ��ɂ��čs���悤�ȕ��͋C�������܂����B�t���[�g�E�\�i�^���l���������Ȃ������A��l�̌����x�z�I�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��傤�B�͔͓I�ŗD�G�ȉ��t���Ǝv���܂��B �@�P�X�X�R�N�̃f���I���iDENON�j�ł��B�N�x�̍����A�����V���[�v�Ș^���ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Sigiswald Kuijken (vn) ♥♥ Barthold Kuijken (fl-traverso) Wieland Kuijken (gamb) Robert Kohnen (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �W�L�X�����g�E�N�C�P���i���@�C�I�����j♥♥ �o���g���h�E�N�C�P���i�t���E�g�E�g�����F���\�j ���B�[�����g�E�N�C�P���i���B�I���E�_�E�K���o�j ���x�[���E�R�[�l���i�`�F���o���j �@���I���n���g�Ղ��烌�I���n���g���������A�����y�Ƃ��Ă͍ŏ����̎l�l�\���ʼn��t���ꂽ�u���y�̕������v�ł��B���̓_�Ɋւ��ẮA�o�b�n���g���I�E�\�i�^�Ŏw�肵���y��ōs���Ă�����̂ŁA�K�R�I�ȉ��߂��Ǝ咣���Ă���悤�ł��B�u�b�N���b�g�ɂ̓o���g���h�E�N�C�P���̏ڂ����y�ȉ�����ڂ��Ă���A���̕��ʂɋ����̂�����ɂ͖ʔ����ǂݕ��ł��傤�B���������_�����������悤�ɁA���̉��t�́A�܂����`�I�Ɋw��I���߂ɂ����č����]������Ă�����̂ł��B �@�����Ă��ꂾ���ł͂Ȃ��A����͂����A����Ȍ����b�������Ă����̋Ȃ̃x�X�g�ƌĂ�ł��܂������قǖ��͓I�Ȉꖇ�ł��B��Ԃ̃��q�^�[�Ղ��ǂ��ł����A������͂����Ɨ͂������A���������Ƌ�Ԃ�����������J�����}�i�[�ł��B����Ă炤�Ƃ��낪�Ȃ��A�e���|�͕��ς���Δ�r�I���₩�Ȓ��f�ł����A�O�Ȗڂ̃J�m���Ŏv�����đ�������ȂǁA�����n�����t���Ă��܂��B �@���̐l�����̊�Ԃ�ł�����A���R�Êy��t�@�̃}�i�[�ł��B�����������Ă��ꂪ�������s���R�ł��Ȃ��A��������Ə�������āA����ׂ����̂�����ׂ��Ƃ���Ɏ��܂��Ă���Ƃ�����ۂł��B �@�W�L�X�����g�E�N�C�P���̃��@�C�I�����́A��l�ʼn��t����ꍇ�͐�����A�N�Z���g���o�����Ƃ�����܂������A�A���T���u���ł͏�ɉ��₩�ȕ��͋C�������đ�ϗǂ��ł��B�����̂Ȃ��}�g���▭�ł��B�f���ł��̉��t���Ă���\�������ƁA�̂̃R���M�E���E�A�E���E�����t�c�̂悤�Ȋy�������o�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ�����ǁA��ϐ^�ʖڂȂ���������b�N�X���āA��̕��͋C�����[�h���Ă���悤�ł��B �@�`�F���o���̓��x�[���E�R�[�l���ŁA�P�X�R�Q�N�̃x���M�[���܂�B�u�����b�Z���̉��y�@�ŃI���K���͊w����ǂ��A�`�F���o���͓Ɗw�Ƃ����l�ł��B�Q�O�P�X�N�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B���B�[�����g�E�N�C�P���Ƃ̓L�����A�̍ŏ�����̕t�������ŁA�������̃N�C�P���Z�킽���Ƃ���������悤�ɂȂ��čs������ ���ł��B�����ł͏o�����̌܂ڂ̉����Ȃǂɑ�\�����悤�ȁA�t���[�Y�̕ς��ڂłق�̏��������Ԃ��Ēx�点�锏�̎����������܂��B����ɂ���ă��Y�������R�ɂȂ�Ȃ�����ŁA�S�̂Ƀs���I�h�t�@�̃A�N�Z���g�͋�������܂���B �@�t���[�g�̃o���g���h�E�N�C�P�������I���n���g�Ղ̂Ƃ��Ɠ��l�A�܂���ϖ��͓I�ł��B�s���I�h�y��Ƃ������Ƃŗ͋������̂ł͂Ȃ�����ǂ��A�ӂ���Ƃ��炩���Y���悤�Ń����b�N�X�ł��A�������Č���������̑���������������t���Ȃ��猙�����Ȃ��A��ȉƂ̔ӔN�̂��̈�������\�����Ă��܂��B�������K���o�̃��B�[�����g�������g���ŁA�S�����n���Ĉ�̉��̐D����W�J���čs���̂ł��B��������������A�S�̂ɐÂ��������������閼�����ƌ������ ���傤�B�o�b�n �̂��̍�i�̐����ɂ҂�����ł���A�S��܂ł��`���悤�ł��B �@�P�X�X�S�N�^���̃h�C�c�E�n�����j�A�E�����f�B�ł��B�^�����x�X�g�ł��B���R�ȃo�����X�Ŏ��ɒɂ��{��������̒�����Ȃ��A�y��̉��͑@�ׂɁA�\���� �����Ă��܂��B�`�F���o���������������Ă����Ȃ�܂���B �@���̎l�N��̂Q�O�O�O�N�ɓ��������o�[�ʼn��t�������C���f���� DVD ������Ă���A�ڂŊm���߂邱�Ƃ��ł��܂��B���t�͊�{�͓����悤�ł�����̂́A������͓���ш�ł̔����������炩�����A���搬�����O�֏o�Ă��āA�`�F���o���� �A�N�Z���g���킸���ɑ傫�߂ȏu�Ԃ����邹�����ACD �̕���������₷����ۂ������܂����B����������͋C����������Ƃ��ɂ��������ׂȂ��Ɖ��Ƃ������܂���B�e���|���̂��������Ȃ̂��Ǝv���Ē��ׂĂ݂�ƁA�����������Ƃ͂Ȃ��A�ނ��� CD �̕����^�C���������A�����x���Ȃ������悤�ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Music from Aston Magna ♥♥ Daniel Stepner (vn/cond.) Linda Quan (vn/va) Laura Jappesen (gamb) Christopher Krueger (fl) John Gibbons (fortepiano) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �~���[�W�b�N�E�t�����E�A�X�g���E�}�O�i ♥♥ �_�j�G���E�X�e�b�v�i�[�i���@�C�I�����^�w���j �����_�E�N�A���i���@�C�I�����^���B�I���j�^ ���[���E�W���v�Z���i���B�I���E�_�E�K���o�j �N���X�g�t�@�[�E�N���[�K�[�i�t���[�g�j�^ �W�����E�M�{���Y�i�t�H���e�s�A�m�j �@������Ȃ��u��ԁv�����x���A������Ɓu�T�������v�݂����ɂȂ��Ă��܂��܂��B���łɃp�C���[���Ղł��N�C�P���Ղł����������ė����C�����܂����A�ł����̒c�̂́u���y�̕������v�����Ȃ̈�Ԃ��A�ƌ��������Ȃ�̂ł��B���t���Ă���̂̓A�����J�A�}�T�`���[�Z�b�c�B�ōs����Êy�̉��y�ՁA�A�X�g���E�}�O�i�̖����������c�́A�~���[�W�b�N�E�t�����E�A�X�g���E�}�O�i�Ƃ������ƂŁA���[�_�[�͂P�X�S�U�N���܂�̃A�����J�̃��@�C�I���j�X�g�A�_�j�G���E�X �e�b�v�i�[�B���y�ՂƂ������Â�����c�̒��ʼn��y�ē̗���ɂ���A�u�����_�C�X��w�Ō������ꂽ���f�B�A�����y�l�d�t�c�̃����o�[�ł����B�����Ă����ł̃��@�C�I�����ȊO�̐l�������A�F�A�����J�Ŋ��鉉�t�҂ł��B���ꂼ��ɂ��ďڂ������Ƃ��m��Ȃ����\���m�����Ȃ��̂ł����A�s���I�h�t�@�̌ċz�����R�ŏ���������A�K�x�Ƀ����n���������Ĕ��������t�����Ă��܂��B�Êy��̉����ǂ��A��ϐ������ꂽ�ꖇ���ƌ�����ł��傤�B �@�Ґ��̓����Ƃ��ẮA�`�F���o���̑���Ƀt�H���e�s�A�m�ł���Ă��邱�Ƃ�����܂��B���ꂪ�܂���ϖ��͓I�ł��B���̊y��̋N�p�͑��̔Ղł��ꕔ���� ��܂����A�����ł͑S�ʓI�ɂ������Ă��܂��B���{�Ńt���[�h���q�剤���e�[�}���������̂��A�o�b�n���������t�����Ă݂����̂��t�H���e�s�A�m������ł��傤�B�����A���̋Ȏ��͕̂K����������p�ł͂Ȃ��A�y���ɋ���L�����t����Ă��Ȃ��̂Ō��Ճp�[�g�̓`�F���o�����낤�Ƃ͌����Ă��܂��B�ł�����͂����� �͂Ȃ��ł����B�o�b�n�͍Ő�[�̊y����������Ēe�����킯�ł�����A���̏�ŏ��ɋ����t����ꂽ���ǂ���������܂���B���₢��N�����B�R�[�h������܂�������A�ĊO��肭����Ă̂����ł��傤���B������ɂ��Ă��A���̃t�H���e�s�A�m�̉��͖��͓I�ł��B�`�F���o�����Ƙ^���o�����X���܂���������Ⴊ���Ⴕ�Ă₩�܂����Ȃ�܂����A��������ƂȂ�Ƃ����₩�ŏ�i�ȉ��F�ɂȂ�܂��B�Z�Ȗڂ́u�Q���̔��s�̊g��ɂ��J�m���v�͑�ς������i�ޒ��ŁA ���t�̒Ⴂ���̃s�A�m���A�܂�Ń����[�g���w�̕��łܒe���Ă���悤�ɕ������Ėʔ����ł��B�d���܂����������~���`�F���o�������t�H���e�E�s�A�m�̕��������[�g�ɋ߂����������ʂƂ����̂��A���X����悤�ł��B �@�e�����ɂ͕ςȕȂ͂Ȃ��A���̌Êy��t�҂͂قƂ�ǂ������������ɂȂ��ė��Ă���̂�������Ȃ�����ǂ��A�傫������x�点�Đ߂����悤�Ȃ��Ƃ͂��� ����B�ނ��딽�ɑ���������ɂ���Ƃ�����܂߁A�h��͂���܂��B��������������R�Ȕ͈͂ł��B�s���I�h�t�@�ɂ��Ă͂��������ɏ����Ă��܂����A���ʂƃe���|�̗h���S�̂ɍs���n�点����̖@���ł�����A�����悤�ɉ��ʂƃe���|�ɂ���ĕ\����̕\�����A�G���̒�����y����������悤�ɕ������Ȃ�܂��B���̔g�͍������ꂽ���̂Ȃ̂ŁA���_��͂ǂ�ȗh��̖@���������Ă����̏�ɂ���ɏ�̗h�炬����������͂��ł����A�y��̉��ʂɂ����Y���i�s�̘g�ɂ����E�͂��邽�߁A������͌��邵�A�����t�҂������ɒ��ӂ�����邱�ƂȂ��s���I�h�t�@���ċz�̂悤�ɖ��ӎ����ł��Ȃ�����́A��̕��͂��낻���ɂȂ�܂��B���������Ď���̗���ł���T���߂ɂȂ��ė���͕̂K�R���Ǝv�����A�]�܂������ƂȂ̂ł��B �@�e���|�͒��f������y�����ł��B�^�b�`�ɂ���ċ���͕t������̂ŁA���̃s���I�h�t�@�Ǝ����`�Ńt���[�Y�̒������������߂�悤�Ȍċz������܂��B����������ł��B�S�̂ɂ���ɏ]�����f�B�i�[�~�N��������܂��B���̋ȏW�̃N���C�}�b�N�X�ł�����U���̃��`�F���J�[���ł����A�Ђ��Ђ��Ƃ��ݏグ�ė�����̂�����A�W�����E�M�{���Y�̓��Ղ̉��t�ɍł��������܂����B�ŋ߂��̘^�����蕷�������Ȃ�̂́A���̓_�����Ȃ̂�������܂���B �@��Ȗڂ́u���̎��ɂ�閳���J�m���v�ł̓t���[�g�ƌ��y�����܂����A�e���|�͂����ƒx���ݒ肳��Ă��܂��B���Ǝv���ΎO�Ȗڂł͎v�����đ��߁A���̂悤�ɑS�̂̃e���|�Ɍ��݂Ƀ����n�������Ă��āA�����O���邱�Ƃ�����܂���B�����Ă�͂茷�y�ł��t���[�g�ł��A�s���I�h�t�@�̂��ǂ��ǂ����Ȃ� �����܂���B���Ȃ��悤�Ȍċz���ނ��냂�_����薣�͓I�ł��傤�B���R�ł������ȃp�[�g�ł͗����������������܂��B���ߑ��̂悤�ɒx���u�Q���̔��s�� �g��ɂ��J�m���v�Ȃǂ�����܂����A������킴�Ƃ炵���͂Ȃ��A���ꂢ�ɕ������܂��B�S�̂Ƀo�����X�����Ă��āA��σ��x���̍������t���Ǝv���܂��B �@�P�X�X�T�N�^���Ń��[�x���̓Z���g(�@)�[�i�^�P���^�E���X�j�E���R�[�Y�B�����A�Ĕ̂͂���Ă��Ȃ��̂������₷���͂Ȃ��悤�ŁA���Â��V�i�艿���炢�������肵�܂��B����͊e���Ƃ��͓����悤�ł��B���[�x���̒��̃T�C�g�̓_�E�����[�h�݂̂ł��B�X�g���[�~���O�͂���܂��B �@�J�b�v�����O�Ƃ��Č��ɒ����̂₳�����t���[�g�E�\�i�^�iBWV 1035�j�����Ă����肵�āA�����Ă����Ă����̂��S�n�ǂ��ł��B���̃N���X�g�t�@�[�E�N���[�K�[�Ƃ����t���[�g�A����Ȃ��ł����A���_���̂悤�ɂ� �����ƃ��K�[�g�ōs�����肵�Ȃ��͓̂��R�Ƃ��āA�f�p�Ōy���A�����Ȋ��������Ă������ϗǂ��ł��B�Ō�́u���y�̕������v�Ɠ������ɍ�Ȃ���A�P�X�V�S �N�Ƀt�����X�̉��y�w�҂ɂ���Ĕ������ꂽ�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȂɊ�Â��P�S�́i�l�X�ȁj�J�m���v�iBWV 1087�j�ł��B���y�ƃt���[�g�ʼn��t���Ă��܂��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Le Concert des Nations Jordi Savall (gamb/cond.) Andreas Doerffel (gamb) Marc Hantaï (fl-traverso) Pierre Hantaï (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 ���E�R���Z�[���E�f�E�i�V�I�� �^ �W�����f�B�E�T���@�[���i���B�I���E�_�E�K���o�^�w���j �A���h���A�X�E�f���t�F���i���B�I���E�_�E�K���o�j �}���N�E�A���^�C�i�t���E�g�E�g�����F���\�j�^ �s�G�[���E�A���^�C�i�`�F���o���j �@�J�^���[�j���̃��B�I�[���t�҂Ŏw���҂̃T���@�[�����A���g���ݗ��������e���n�̑t�҂ɂ��X�y�C���̌Êy�I�[�P�X�g���A���E�R���Z�[���E�f�E�i�V�I�� ���w�����Ă��܂��B �@�ŏ��Ƀt���[�g��{�Ńt���[�h���q�剤�̃e�[�}�����t����܂��B�܂�ő剤���g�������Ď����Ă�݂����ł����A���̓t�H���e�s�A�m�Œe���Ă݂����̂ł����B�ł��ʔ����ł��B���������͕��ʂɃ`�F���o���ɂ�鉉�t�ƂȂ�܂��B�e���Ă���̂̓n���K���[�n�t�����X�l�̃s�G�[���E�A���^�C�ŁA�t���[�g�̃}���N�E�A���^�C�Ƃ͌Z��ł��B�e���|�͂��������ł��B�t���[�Y������A�������悤�ɊԂ����Êy��t�@�̌ċz������A�����d�߂ɔS ���ۂł��B �@�O�g���b�N�ڂɂȂ�ƃT���@�[���̃��B�I���E�_�E�K���o��������܂����A�������ƁA�傫���c��܂��Ȃ��瑕�����g���A�Ԃ������Ղ�Ǝ���ď����O�A���̂���̂����܂��B�����̌ċz�Ƃ����̂��A�{�E�C���O�̃A�N�Z���g�͂������A�S�̂ɂ킽���ČÊy�̎R�Ȃ�̂��̂ł��B��̃`�F���o�������������^�тɍ��킹�����̂ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B�g���Ƃ��Ă͂��̑��̌��y���������ł��B �@�x�����Ǝv���A��̃��@�C�I�����ɂ��Q���̃J�m���ȂǁA�����n����t���đ������Ȃ�����A���̕ӂ͏�L�̃A�X�g���E�}�O�i�ՂƂ����ʂ��܂��B �@�g���I�E�\�i�^�ɓ���ƃ}���N�E�A���^�C�̃t���[�g�i�t���E�g�E�g�����F���\�j�����܂����A���̐l�̉��t�͑�ύD���ŁA�o�b�n�̃t���[�g�E�\�i�^�̃y�[�W�ł�♡♡��t���܂����B�����ł��f����������������^�тłӂ�����Ɨǂ��������Ă��܂��B�����A�ŏ��̋ȂȂǂ̓e���|���x���ݒ�ɂȂ��Ă邱�Ƃ������āA������ۂ��Ⴂ�܂��B���̑t�҂����̑傫�Ȍċz���������ė��āA����ɍ��킹�Ă�킯�ł��Ȃ��̂ŐÂ��ɕ����Ă��銴�o������܂��B �ł��g�[�^���ł͓��ꂳ�ꂽ���̊y�c�̔g���ƒ��a���Ă���Ƃ͌�����ł��傤�B�S�̂̒��ł̑��݊��Ƃ��ẮA��͂艹�̏����Ȋy��Ƃ������Ƃ�����A�^�� �Ńo�����X��ς��ĂȂ����ʁA�����f�B�A�X�ȕ����őO�ɏo�ė��銴���ɂ͂Ȃ�܂���B�͂����߂鑬���y�͂ł͂��̌���ł͂Ȃ����̂́A���߂���ƍ��x�͉��̏d�Ȃ芴���o�₷���C�����܂��B�S�̂Ƃ��Č����邱�Ƃ́A�S��̂���̂ƃR���g���X�g���t�����\����͂́A���I�ȁu���y�̕������v���Ƃ������Ƃ� ���B �@�A���A�E���H�b�N�X�P�X�X�X�`�Q�O�O�O�N�̘^���ł��B�����߂����f�b�h�ɂȂ�߂����̗ǍD�ȃo�����X�ł��B��⒆�����ł��傤���B�`�F���o���Ȃǂ͓� �ɓ������̍������ނł͂Ȃ��ł����A�P�Ƃ̍����̓s���Ƃ��Ă��ꂢ�ɋ����܂��B  Konstantin Lifschitz (pf) �R���X�^���`���E���t�V�b�c�i�s�A�m�j �@������̓s�A�m�ʼn��t�����u���y�̕������v�ł��B���_���E�s�A�m���ł��B�������ĕ����ƁA�Z���Ȃ̂Ńt�����X�g�Ȃ̂悤�ł�����A�J��Ԃ����ϑt�Ȍ` ���ɕ������āu�S�[���h�x���N�ϑt�Ȃ����������v�A�Ɠr���Ŏv����������܂��B���邢�͐����̏d�Ȃ肪�A�N�[�v�����̃N�����T���Ȃ̏���̂悤�ɂ��������܂��B���̋Ȃ̐����̒��ł��A���ɐÂ��Ȕ��������ۗ�������y�킾�ƌ�����ł��傤�B����������������l�ŕЕt����̂ɂ͂��Ȃ�̘r���v��͂��ł��B �@�e���Ă���R���X�^���`���E���t�V�b�c�͂P�X�V�U�N���܂�̃��_���n���V�A�l�s�A�j�X�g�ł��B���V�A���E�X�N�[���̓������o�Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA �悭������܂���ł����B�悭���̗��h���\����ƌ�����M�����X�ƃ��q�e���������������Ƃ��v���܂��A���҂ɋ��ʂ��邩������Ȃ����B�ȃt�H���e�Ǝv�����ꂽ���Ղ�̊ɏ��y�͂Ƃ����Ӗ��ł��A�����͕������܂���B���q�e���̃o�b�n�Ƃ��Ⴂ�܂��B���}���h���Ă��Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂��A���̒e �����͌֒��̂Ȃ��f���������������鐫�i�ŁA�Â����ƑN�₩���������ĂȂ��Ȃ����͓I�ł��B���y�͏�ɉ����ʔ����d�| �����Ȃ�������Ȃ����̂ł��Ȃ��A�^�������e���Ă��邱�Ƃł����炪�Ȃ̂�����ɏW�����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A��ʓI�ɕ������̂Ɣ����Ⴄ�������������肵�ĕs�v�c�ȃg�[���Ɋ�����ӏ�������܂����A�y���̂����Ȃ̂����Ȃ̂��A�������͂�����܂���B�ʔ������ƂɁA������ƃ��_���ȋȂ̂悤�Ɋ����܂����B �@�Q�O�O�T�N�I���t�F�I�̘^���ł��B�P���߂����I�t�ɂȂ�߂����̗ǍD�ȉ��F�ɂƂ�Ă��܂��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Ton Koopman (hc) Wilbert Hazelset (fl-traverso) Catharine Manson (vn) David Rabinovich (vn) Jane Rogers (va) Jonathan Manson (vc) Christine Sticher (violone) Tini Mathot (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �g���E�R�[�v�}���i�`�F���o���^�w���j �E�B���x���g�E�n�[�[���[�b�g�i�t���E�g�E�g�����F���\�j �L���T�����E�}���\���i���@�C�I�����j�^ �_���B�h�E�����B�m���B�`�i���@�C�I�����j �W�F�[���E���W���[�Y�i���B�I���j�^ �W���i�T���E�}���\���i�`�F���j �N���X�e�B�[�l�E�V���e�B�q���[�i���B�I���[�l�j�^ �e�B�j�[�E�}�g�[�i�`�F���o���j �@�I�����_�̌Êy�̃o�b�n�̖���A�R�[�v�}���ł����A���́u���y�̕������v�͂Q�O�O�O�N��ɓ����ďo���Ղł��B �@�ŏ����������邩�Ɍ����āA��͂�`�F���o���͑������撣���Ă��܂��B�܂��A�I���K���ł����̐l�ɂ悭��������@�ł����A�s���I�h�t�@�Ƃ��ĊԂ��� ���Ēx�点����߂����̂ł͂Ȃ��A�w������悤�ɏ����O�|���ɂȂ锏���o�܂��B�Ɠ��̊ԍ����ł���A�i���Պy�펩���ł́j�R�[�v�}���ߌ����Ă��ǂ��� ������܂���B���̕ӂɊ����āA����łȂ���A�Ƃ�����������������ł��傤�B�T���@�[���̔S��Ƃ͑���������Ӗ��ő�ϓ������������u���y�̕������v�ł��B �@��Ȗڂ͈�������悤�ȃK���o�Ŏn�܂�A�S�̂����݂̂ɂ��\���ł��B�s���I�h�t�@�Ɠ��̑������œ��ꂳ��Ă���A�����苃���悤�Ȃ������Ƃ����^�тł��B�O�Ȗڂ̓`�F���o���ƌ��ƂŁA�����������ǂ��ł��B���̉��t����͂�A�X�s�[�f�B�ȂƂ���Ǝv�����Ă������̂킹��Ƃ���ƂŃR���g���X�g��t���Ă���A�O���邱�Ƃ�����܂���B �@�t���[�g�ɂ��ẮA������t���[�Y�̋��ŒZ�����@�ł��B���炩�����̓t���[�Y���Ƃɒe�܂���Ƃ���ɓ���������ł��傤���B���̊y�c�̃t���[ �e�B�X�g�ł��B �@�Ō�͂܂��A�Â����������{���ꂽ�R�[�v�}���̃`�F���o���ɂ��U���̃��`�F���J�[���Œ��ߊ����܂��B�悭�e�ށA�t���[�Y�̊p�̗��������C�̂���e�����ł��B���Ȃ���肪�����̂ŁA�t�����X�̃N�����T�����̂̂悤�ɂ��������܂��B���̐l�ł͐������Ȃ��Z�ł��傤�B�ĊO�o�b�n���g�����̂悤�ɉ₩�� �������������Ēe���Ă����̂�������܂���B �@�Q�O�O�W�N�̃`�������W�E�N���V�b�N�X�ł��B�`�F���o���̉��͂��Ȃ肭������Ƒ������đO�ɏo�ė�����̂ł��B�\���̃p�[�g�ł͉��ʂ��オ��A�߂��� ���������ɂȂ�܂��B 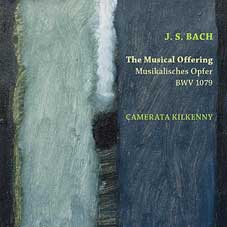 Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Camerata Kilkenny Wilbert Hazelzet (fl) Maya Homburger (vn) Maja Gaynor (vn/va) Sarah McMahon (vc) Malcolm Proud (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �J�����[�^�E�L���P�j�[ �E�B���x���g�E�n�[�c�F���c�F�g�i�t���[�g�j�^ �}���E�z���o�[�K�[�i���@�C�I�����j �}���E�Q�C�i�[�i���@�C�I�����^���B�I���j�^ �T���E�}�N�}�z���i�`�F���j �}���R���E�v���E�h�i�`�F���o���j �@�L���P�j�[�̓A�C�������h�̒��ŁA�A�X�g���E�}�O�i�Ɏ��Ă��邯��ǂ��A�J�����[�^�E�L�P���j�[�͂����̌|�p�t�F�X�e�B���@���ɏW�܂������E�e�n�̃Q�X�g�E�A�[�e�B�X�g������ ����č\������Ă��܂��B�P�X�X�X�N�̌����ł��B���̃����o�[�ȊO�ɂ��e�n�̗L���ȌÊy�I�[�P�X�g���ɍݐЂ���l����������悤�ł��B�\�L�ł͓��ɖ��L�� ��Ă��܂��A�S���s���I�h�y��ł��B �@�^�~�̃��Y���ł͂Ȃ��A�e�t���[�Y�����ł��߂�悤�ɂ���Êy�̌ċz�ƁA�������ŏ��������ɂ߂邩�Ƃ����ȊO�A�قƂ�Ǒf���ȃ`�F���o���Ŏn�܂�܂��B�傫�Ȑߖڂ�삯�o���Ȃǂ��Ȃ��A���������^�т͍D�݂ł��B�����A�U���̃��`�F���J�[�������͈����������ɐi�߂銴�������߂ŁA�����x�������܂����B�������邱�Ƃō\���̌���������悤�Ƃ����Ӑ}�Ȃ̂ł��傤���A�͂������Ă��܂��B�A�C�������h���܂�Ń��I���n���g�Ɋw�}���R���E�v���E�h�Ƃ��� ���Ցt�҂ł��B�����Ă��̃`�F���o�����������y�c�̕\���Ƃ��ẮA�قڏ�L�̃R�[�v�}���Ղ̕��͋C�Ɏ��Ă��銴�������܂��B �@�t���[�g�̓R�[�v�}���Ղł������Ă����A���X�e���_���E�o���b�N�̃E�B���x���g�E�n�[�c�F���c�F�g�ŁA�����\���ł��B�s���I�h�t�@���L�̋�芴�������傫�����̂ł��B �@���y������ɏ��������ꊴ�̂��鑧�����ŁA�S�̂Ɏ��R�Ȕ͈͂̒��œ����̂���A�N�Z���g��������Ƃ������x�ł���A�����₷���ł��B�e�Ȃ̃e���|�ݒ���A�� �����͂肵������ƃ����n����t��������ŕω����o���Ă��܂��B �@�Q�O�P�O�N�^���̃}���E���R�[�f�B���O�X�Ƃ����X�C�X�̃��[�x���ł��B�o�����X�����Ă��āA�`�F���o�����K�x�ɖ����ȕ����A����t���[�g�͎��R�ȉ��ꊴ�ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Ricercar Consort ♥♥ Philippe Pierlot (bass-gamp) Marc Hantaï (fl) François Fernandez (vn) Maude Gratton (hc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 ���`�F���J�[���E�R���\�[�g ♥♥ �t�B���b�v�E�s�G�����i���B�I���E�_�E�K���o�j �}���N�E�A���^�C�i�t���[�g�j �t�����\���E�t�F���i���f�X�i���@�C�I�����j ���[�h�E�O���b�g���i�`�F���o���j �@�O���[�v�̖��O�́u���`�F���J�[���v�A����͏�ŐG�ꂽ�ʂ�ŁA�o�b�n�����l�ɑ��悵���y���ɏ����ꂽ�T�u�^�C�g���̓������ł��B���X�̈Ӗ��̌Â��y�� �̌`�����Ƃ���҂����Ă�̂��낤���ǁA�o�b�n�̕����y�c�ɂƂ��Ă͏d�v�ȈӖ��������Ă���ɈႢ����܂���B�x���M�[�̃��B�I���E�_�E�K���o�t�҃t�B���b�v�E�s�G�����ƃt�����X�̃��@�C�I���j�X�g�A�t�����\���E�t�F���i���f�X��ɂ���ĂP�X�W�O�N�Ɍ������ꂽ�x���M�[�̃A���T���u���ł��B�N�[�v�����́u�R���b���^�A�������^�v�̉��t���f���炵�������̂ŁA���łɎ��グ�Ă��܂����B�����ł̓t���[�g�Ƀ}���N�E�A���^�C�������A�`�F���o���� �P�X�W�R�N���܂�̏������Ցt�ҁA���[�h�E�O���b�g���ɕς���Ă��܂��B��l�Ƃ��t�����X�l�Ƃ������ƂŁA�x���M�[���t�����X�������ł�����A���̃t�����X���̌Êy���\���鉉�t�ƌ����ėǂ��ł��傤�B�����ł̓N�C�P���ՂƓ������ŏ��̎l�l�ł���Ă��܂��B �@���̊y�c�̖��͂́A���ς���e���|�͂������߂Ń����b�N�X�ł��A�Êy�̃t���[�W���O�͂ǂ������Ă͂���̂Ŕ����Ȗ�肾����ǂ��A��͂�t�����X���Ƃ����̂��A�����ӂ��Ɗۂ�����܂��āA�����悤�ȃA�N�Z���g�ْ̋���l�܂芴���Ȃ��Ƃ���ł��B�]�T��������ƌ����������m��I�ł��傤���B�t�Ɍ����A�D�݂łȂ��l�ɂƂ��Ă͊����y�̂悤�ɂ̂�т�A���邢�͂�������ɕ�������̂��낤���A�Ƃ��z�����܂��B�����Ă��������D�낳�A���Ȃ₩���͂��̃o�b�n�ł��ێ�����Ă���̂ŁA�������� �قǂɗǂ����������ė���悤�Ȏ�ށA��������܂���B���������A�t�����X���̂����Ƃ����͗͂������Ă�������Ƃ͂��Ă�ł��傤���B���₢��A����͐���ς�������� ����B�S�̂ɂ������Ƃ����Ă��A�g���I�E�\�i�^�ȂǂŌ����ł����A�D�u�Ƃ��������Ȃ̕\���������Ă��āA���̊�������܂��B �@���`�F���J�[���ő�C���ʂ����`�F���o���ł����A���̂Ƃ���\���A�Êy��̉��t�}�i�[��蒅�����ė����Â�����ł͂���܂���B�����̊Ԃ̋�Ԃ��m�ۂ���悤�ɁA�\���ɂ������Ɖ^��ł��ėǂ��ł��B�ƊE�Œ�ԂƂȂ����A�t���[�Y�̐�ڂő҂��Ĉ����|����悤�ȃA�N�Z���g�������ق�� �����������Ȃ������l�I�ɂ͍D�݂��ȂƂ����C�͂��邯��ǁA�ǂ����낤�A����͂���ŏ\���ɖ��͓I�ł��B�t�����X�l�炵���L���[�g�Ȍ���������Â��_��t���Ă���킯�� �͂���܂���B�U���̕��̂ق����čs���悤�ȉ^�т́A�e���|�̏�ł͏�L�̃J�����[�^�E�L�P���j�[�̃}���R���E�v���E�h�Ƃ����ʂ��܂����A�x���Ƃ�����ϓI�Ȋ��o�ł͂����炩���Ȃ������܂��B�ǂ����Ăł��傤�B��{�̔��œ����ɒ@�����A���ɏ����炷����ł��傤���B �@�}���N�E�A���^�C�̃t���[�g�͍D�݂��ƃT���@�[���Ղ̂Ƃ���ł��q�ׂ܂������A������������̒c�̂Ő����������̐l�ɂ͖������Ȃ��̂��ȁA�Ə����v���܂��B�ނ̔��_����������A���R�Ȋ��������܂��B���̃A���^�C�Ƃ����l���A�Êy�̃A�N�Z���g�Ƃ��Ă͂ӂ��Ƃ������炩���ƕȂ̂Ȃ��f���Ȕ��߂������Ă��܂��B�g���I�E�\�i�^�͂��̉��t�̔����ł��傤�B�����āA�܂���ԂȂǂƌ����̂��ǂ����Ƃ͎v���܂����A�Êy�t���[�g�ł̃g���I�E�\�i�^�̉��t�ł��A���ꂪ�� �Ԃ�������܂���B �@���[�_�[�̃t�B���b�v�E�s�G�����̃��B�I�[���͎��R�̂ŁA������T���@�[�������Ȃ̂Ȃ����ƂȂ����^�тȂ���\���Ɏ����グ��悤�ɂ��Ȃ点��{�E�C ���O�ł���A���X�Ŏ��̉��ɓ���O�ɂ����Ɛ�y���������Ă��āA������Ƒ����������܂��B��͂�D�݂ł��B���̔g���ő��̌��y����ӑR��̂ƂȂ��Ă��� ���͓I�� ���B �@�ȏ��̓g���I�E�\�i�^��O�̕��Ɏ����ė��āA�U���̃��`�F���J�[���͏I��肩���ԖځA�Ō�ɓ�̓�J�m����z����Ƃ������̂ł��B �@�^���͎��R�łƂĂ��ǂ��ł��B�`�F���o��������t�H���e�s�A�m�̂悤�Ȃ��ƂȂ��������ɂ͂Ȃ�Ȃ����̂́A���̊y��Ƃ��Ă̓m�C�W�[�łȂ��A�p����� ���Ȃ������̗������ŁA���������[�g�̂悤�ɋ�������������܂��B���ƃt���[�g������Ȃ������ł��B��������Ƌ߂��ɕ������čׂ��������E���A���炩���A�c���͂قǂقǂ������肠��܂��B�t�����X�̃��[�x���A�~���[���̂Q�O�P�P�N�̘^���ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Il Gardelino ♥ Jan De Winne (fl) Sophie Gent (vn) Tuomo Suni (vn) Vittorio Ghielmi (gamb) Rodney Prada (gamb) Lorenzo Ghielmi (hc/fortepiano) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �C���E�K���f���[�m ♥ �����E�h�E���B���k�i�t���[�g�j�^ �\�t�B�[�E�W�F���g�i���@�C�I�����j �g�D�I���E�X�j�i���@�C�I�����j�^ ���B�b�g���I�E�M�G���~�i���B�I���E�_�E�K���o�j ���h�l�C�E�v���_�i���B�I���E�_�E�K���o�j�^ �������c�H�E�M�G���~�i�`�F���o���^�t�H���e�s�A�m�j �@���B���@���f�B�̊y�ȁu�������Ђ�v���Ӗ�����C���E�K���f���[�m�̓x���M�[�̃I�[�{�G�t�ҁA�}���Z���E�|���Z�[���ƃt���[�e�B�X�g�̃����E�h�E���B �G���k���P�X�W�W�N�ɐݗ������t���~�b�V���i�x���M�[�A�t�����X�A�I�����_�̈ꕔ�ɂ܂�����t�����h���n���j�̌Êy��y�c�ł��B�I�[�{�G�̓���Ȃ����̋Ȃł̃��[�_�[�̓����E�h�E���B���k�ł��傤���B�C�^���A�̌��Ցt�ҁA�������c�H�E�M�G���~��������Ă��܂��B���E�f�B���B�i�E�A�����j�A�Ƃ������g�̊y�c�������Ă��Ďw�������Ă���l�ŁA�ނ��w���f���̃I���K�����t���͑f���炵���A�O�Ɏ��グ�Ă��܂����B �@�����t�̃t���[�g�ʼn��̃e�[�}�������ŏ��Ɏ������n�܂���̓T���@�[���ՂƓ�������ł��B�����ӎ����ĂƂ��������A�o���h���[�_�[���t���[�g������ ��������܂���B�����ĂR���̃��`�F���J�[���̓t�H���e�s�A�m�ł��B������̓o�b�n�����{�ɏ����ꂽ�Ƃ����Č����Ă���̂ł��傤���B�����ł̃t�H���e�s �A�m�͋��낵�������ǂ��A���[�c�@���g�Ȃǂł悭���ɂ��邭�����F�ł͂���܂���B�������̌����`�F���o�����Ƃ����̂��A�N�����B�R�[�h�Ɏ��Ă��܂��B�N�����B�R�[�h�͂��̂ɂ���Ă̓����[�g��������Ɉ����|����悤�ȉ����o���ꍇ������܂����A�����ł̓`�F���o���̍����݂����Ȃ̂ł��B�������t�H���e�s�A�m�ł����炵�����苭�オ�t���Ă���A�����̃s���I�h�t�@�ɂ�鐷��オ�����A�N�Z���g�����C���ǂ��ł��B�e�����͂��߂��o���������悤�ȃ��Y���ł͂���A�X�p�C�X�ŃX�^�b�J�[�g�������܂��B�����ĉ����X���[�ł͌q���Ȃ��Ńp���p���ƓƗ�������X�������������̂́A��������߂�����͂Ȃ��A��r�I�f���ȉ^�тł��B���炩�Ȃ���킸���ɑO�ɂ̂߂�Ƃ���̂������A�X�g���E�}�O�i�̃W�����E�M�{���Y�Ƃ��܂�������ƈႤ�킯�ł��B�e���|�͑������ ����ɕ������钆�f�ł��B �@�����Ėʔ����̂̓t�H���e�E�s�A�m�͍ŏ������ŁA��̓`�F���o���ɂȂ邱�Ƃł��B�y���̓`�F���o����z�肵�Ă��邩�炩�A�ω���t���ė������������邩��ł��傤�B���������ĂU���̃��`�F���J�[���ł̓`�F���o�������킦�܂��B������̓��`�F���J�[���E�R���\�[�g�̃��[�h�E�O���b�g����J�����[�^�E�L�P���j�[�̃}���R���E�v���E�h�̂悤�ɒx�߂̃e���|�ł͂Ȃ��A���Ƃ����đ������Ȃ����f�Ői�߂čs���܂��B���Y���ɗh��͂Ȃ��A�^�ʖڂŒ[���ȉ^�тł��B�w ���f���̂Ƃ����ތ��Ȉ�ۂȂ̂̓o�b�n������ł��傤���B �@������̃��[�_�[���Ǝv����t���[�g�̃����E�h�E���B���k�ł����A�Êy�̃t���E�g�E�g�����F���\�̐������Ƃ��Ă͈ĊO�ꂬ��ɂ����A���Ɖ����Ȃ��čs���Ƃ���ɓ���������܂��B�ɒ[�ɒx�点��߂��o�����A�����O�g�[���̒����������グ��ċz�͂�����̂́A��������܂苭�����ł͂���܂���B���̑f���Ȑ������ɂ͍D�������Ă܂��B���F���ǂ��A�Êy��Ȃ̂Ŕh��ł͂Ȃ��f�p�Ȃ���A�Ⴂ�����Ɠ��̑����ŋ����S�n�ǂ����̂ł��B�g���I�E�\�i�^�ł͗͂��Ď㉹�ɗ��Ƃ��@�ׂȕ\�����Â��ȃp�[�g�ŕ�����A�������ł��B�S�̂ɂ͗��������������ĉ̂��t���[�g���ƌ�����ł��傤�B�����p�[�g�������Ƃ��Đ߂��ꗧ���� ����B�����Ƃ��Ă̓t���[�Y�Ō�̉�����߂ďI��鏈�������Ƒ��߂ł��傤���B�����Ă��̃t���[�g�̋������Ă���ƁA�c�������܂�傫���Ȃ����Ƃ�������܂��B �@���̃p�[�g���A�Êy�t�@�̌ċz�ŃL���[���Ǝ����オ��̂��C�����ǂ��ł����A�e���|�͊T�˒��f�A�������͂��y���Ƃ����Ȃ������A����̓t���[�g������ ����Ƃ���������ł��B���܂葬�x�Ń����n����t����l���͂Ȃ��悤�ŁA�͂�����ƒx�����Ɋ���Ă���ƌ�����̂̓\�i�^�̎O�Ȗڂ��炢�ł��傤���B���߂̋Ȃł̓s���I�h�t�@�I�ɂ������摑�ނ悤�ȃ��Y���̗h�炬���͂����肵�Ă���A������ӂ͏������������̍D�݂̘H���Ƃ͈قȂ�܂����B�����A�u�Q���� �����v�Ƃ������t�����āu���C������v�ƌ���������m��I�ɂȂ���̂ŁA���̍��͔����ł��B �@���[�x���̓I�����_�̃p�b�T�J�[���ŁA�^���͂Q�O�P�Q�`�P�R�N�ł��B�O�q�̒ʂ�c���͂��܂蒷�����ł͂Ȃ��ł����A���̕��e�y��̗֊s��������܂��B���Ƃ����ăn�C���������ꂽ�d���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̒���ɒ���͂�����̂̎��R�ŐS�n�ǂ��o�����X�̘^���ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Bach Collegium Japan Masaaki Suzuki (hc) Kiyomi Suga (fl) Ryo Terakado (vn) Yukie Yamaguchi (vn/va) Emmanuel Balssa (vc) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �o�b�n�E�R���M�E���E�W���p�� �^ ��؉떾�i�`�F���o���j ������݁i�t���[�g�j�^ ���_�˗��i���@�C�I�����j �R���K�b�i���@�C�I�����^���B�I���j�^ �G�}�j���G���E�o���T�i�`�F���j �@�J���^�[�^�S�W�Ō����ȉ��t�����Ă����؉떾�ƃo�b�n�E�R���M�E���E�W���p���iBCJ�j���A�Q�O�P�U�N�ɂȂ��Ă���Ɓu���y�̕������v���o���܂� ���B�o�b�n�̂قڍŌ�̍�i�ł���A���߂�����Ƃ��낪���邩���ɂȂ����̂ł��傤���B���҂��ĕ����܂����B�Ґ��̓N�C�P���Z�킽���̉��߂Ƃ͈Ⴂ�Aviolin �̌�́u�F�v���u i �v�Ɖ��߂����̂��ǂ����iviolini ���ƕ����Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��j�A�ʏ�悭�����悤�Ƀ��@�C�I��������l�����ܐl�̐��ł��B �@�Ȃ�ƂR���̃��`�F���J�[�����ŏ��Ɏ����ė����A�����悤�ɊJ�n�����Q���̋t�s�J�m������n�߂Ă��܂��B���������b�ɂ͐G��Ȃ��ƌ����܂����̂ŁA���߂Ɋւ��邱�ƂȂǂ���ȏ�͏����܂��A���`�F���J�[���Ɠ����悤�Ƀ`�F���o�������̃e�[�}�������Ƃ���ŁA���������~���鉹���������Ƃ���Ă� �� ���B�����Ă��̍Ō�̕����ɂ����������܂���B�����Ȃ��烊�`�F���J�[�����ƐM���Ă����̂ŁA�������~�̕������Έʖ@�W�J�Ɍ����Ȃ��ƌ����Ă�̂��ӎ����ăv���[���ɂ���Ă�̂��Ȃ��A�ȂǂƂ�����ƍl�������̂́A�S�R�W����܂���ł����B����������ȊO�̉ӏ��ŁA����ɂ͑啪�H�v���� �炳��Ă��܂��B������ŏ��͊y������O���̂��A�Ƃт����肵���킯�����ǁA������ɂ�����I�ȃ`�F���o���̉��߂ł͂���ł��傤�B�[���Ӑ}�������� �F�X�Ǝ��݂Ă���ɈႢ�Ȃ��A���̓_���]�v�Ȃ��Ƃ͌����܂���B�܂��A��������݂��Ă��Ă������Ŏ��グ����̂ł��Ȃ��ł��傤�B �u�����J�m���v�Œ��قǂɂȂ��ăt���[�g��������ė���̂ɂ͋����܂����B�܂��A�u�Q�[�f���A�G�b�V���[�A�o�b�n�v�̃A�C�f�B�A�Ƃ͈���āA�����Ƃ���܂ł������菸���ďI���悤�ɕ������鏈���ł��B�u�����J�m���v�͉��t���ǂ��܂ł�����������̂ł����A�t�F�[�h�A�E�g�ŏI��邱�Ƃł���������Ă���悤�ł��B�ǂ�����̉��t�҂Ƃ͋ȏ������Ȃ����Ă��܂��B �@�\���ł͂Ȃ����t�\���̕��Ɉڂ�܂����A�������t�]���ē�ȖڂɁu���x�̃J�m���v�����t�ŗ���Ƃ���ŁA���̊y�c�Ƃ��Ă͑�ό��C�̗ǂ��A�͂��݂̂��������ɋ����܂����B��ߕ��������Ƒ�_�ł��B�Ȃ�Ƃ���ȕ��ɂ����t�ł���̂��A����������ʂ������āA���̋Ȃ͂��̘H���ōs���킯���A�Ǝv���܂������A����͈ĊO�����ł��Ȃ��悤�ŁA���̌�� BCJ �̈�̐������Ǝv���Ă����W�J�ɖ߂�悤�Ɋ����܂����B�܂��ς��ꂢ�ŁA�v���C���[�̕��ς������̈ʒu�Ƃł��������A�t���[�g�����������ア���֊�����A�X�^�e�B�b�N�Ȕ������ł��B�����̃s���I�h�t�@�̕Ȃ͂Ȃ��A���R�ƌ����ƌ��t�������ł����A��r�I�����Ƃ�Ƃ����}�g�ő�ϐ^�ʖڂɁA�܂�ڐ������^��ōs���p�[�t�F�N�g�ȉ��t���Ǝv���܂��B���������_�ł͗L�c���L�̔Ղŕ����ꂽ�o�b�N�̃A���T���u���̂�����Ƃ��������ʂ��Ă���ł��傤���B �@�Q�O�P�U�N�� BIS �̘^���ŁA�ŋ߂̂��̃��[�x���炵�� SACD �n�C�u���b�h�ƂȂ��Ă��܂��B�`�F���o�����e�y��̔{�����悭�E���A�K�x�ɃV���[�v������������D�G�^���ł��B  Bach Musical Offering (Musikalisches Opfer) BWV 1079 Calefax (Reed Quintet) ♥♥ Oliver Boekhoorn (ob/e-hr) Ivor Berix (cl) Raaf Hekkema (sop/alto-sax) Jelte Althis (bass-cl/basset-hr) Alban Wesley (fg) �o�b�n �^ ���y�̕����� BWV 1079 �J���t�@�b�N�X�i�E���[�h�d�t�c�j♥♥ �I�����@�[�E�{�G�N�z�[�����i�I�[�{�G�^�C���O���b�V���E�z�����j �C���@�[�E�x���b�N�X�i�N�����l�b�g�j�^���[�t�E�w�b�P�}�i�\�v���m�^�A���g�E�T�L�\�t�H���j �C�F���e�E�A���g�D�CS�i�o�X�E�N�����l�b�g�^�o�Z�b�g�E�z�����j �A���o���E�E�F�X���[�i�o�X�[���j �@����͊NJy�A���T���u���ɂ��ς���̉��t�ł��B�J���t�@�b�N�X�E���[�h�d�t�c�̓I�����_�̒c�̂ŁA���g�̃E�F�u�T�C�g�ɂ���悤�Ɂu�|�b�v�̃��� �^���e�B�[���������N���V�b�N�̃A���T���u���v�Ƃ����R���Z�v�g�̂悤�ł��B�A���X�e���_���̒����w�Z�̃I�[�P�X�g���c�������ɂ���ĂP�X�W�T�N�Ɍ�������܂����B�Õ��ŗ������܂܉��t���邱�Ƃ����������ŁA���l�T���X����W���Y�܂ʼn��ł����Ȃ��܂��B���{�ł̃t�@���͐��t�y�ɋ����̂���l�����Ȃ̂��A�S�R�Ⴄ�̂��S��������Ȃ����̂́A���������y�c���u���y�̕������v�����グ��͖̂ʔ����ł��B �@�Ґ������܂�ɂ��Ⴂ�߂��邵�A���t�y�c���������킯�ł��Ȃ��̂ł��̕���̉��t���̂��̂̂������`�ʂ���͓̂���ł����A���[�c�@���g�̃f�B���F���e�B�����g���������Ă��邩�̂悤�ȋ����ŁA���O�̎��T�ł����蓾�����Ȋ����ł��B�����Ȃ�ƁA���V���R�̐�v�ҒǓ��Z�����j�[�݂����Ȃ��̂ɂȂ��Ă��� ���ł��傤���B�o�b�n�̃J���^�[�^�Ƀz�[���ɂ�邻���������T�p�i�P�P�W�ԁj���������̂��v���o���܂��B���邢�� FM �̉��y�ԑg�̃I�[�v�j���O�E�e�[�}�Ɏg���Ă�������������܂���B�������̊y�͂ł͍��̊����y�̂悤�ł�����A���邢�͑����Ƃ���ł͈�u�f�B�L�V�[ �����h�E�W���Y�݂���������������܂��B���[�h�y�킾���瓖�R�Ȃ���A�I���K���̋����ɂ������I�Ɏ��Ă���C�����܂��B �@�y��Ґ��ɍ������Ȃ��`���C�X���Ă��邩�炩�ǂ����A�g���I�E�\�i�^�̃����S����n�߂�Ƃ����ς�����ȏ��ŁA���ɂR���̃��`�F���J�[�������āA�Ōオ�U���̃��`�F���J�[���ŏI���܂��B�ĊO�Â���������������A�Ɠ��̖��͂̂��鉉�t�ł��B�I�[�{�G�n�̉���N�����l�b�g�������Ƃ����̂����̋Ȃł͒������A�T�b�N�X����������s�v�c�Ȏ�荇�킹�����ǁA��肭���a���Ă��ĐV�N�Ȋ��o�𖡂킦�܂��B �@�܂��A���̃A���o���ł̓o�b�n���ӔN�Ɏ��g�����Ȃ���i�̈�ł���u�����V�����͗������v�̃R���[���Ɋ�Â��J�m�����ϑt�ȁiBWV 1087�j���������Ƃ��ł��܂��B���ꂾ���ł����l������܂��B�Ȍ��ŘN�炩�Ȉ�ۂ�����A�u���y�̕������v�Ƃ͈���āA���[�c�@���g�̂悤�ɓ˂� �����ċ킯��ӔN�̐Â��ȋ��n���ƌ�����ł��傤�B���ƂȂ��S�ɟ��݂���̂�����܂��B�Ō�͌��J�ŁA�����ڂɉ������킴�ƊO���Ă܂��B�o�b�n��搶�̉��y���A������Ă����A�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �@�Q�O�Q�O�N�̘^���ŁA�I�����_�̃y���^�g�[���E���[�x���ł��B�������]����ł����A�Â����Ƃ܂�₩�������������̂ł��B������������A���x���̍� ���^���ł��傤�B�v������♡♡�ɂ����͉̂��t���������������܂����A�u�����V�����͗������v�������Ă��邩��ƁA��ϖʔ�����悾����ł��B INDEX |