|
バッハ (6つの無伴奏) チェロ組曲 BWV1007-1012
Bach: The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 for unaccompanied cello  取り上げる CD 39組: カザルス/フルニエ/ジャンドロン/マイナルディ/アーノンクール/シャフラン/ナヴァラ /トルトゥリエ(’60 /’82)/ハレル/シフ/ロストロポーヴィチ/シュタルケル/(’63-65 /’92)/ビルスマ(’79 /’92)
/オンツァイ/マイスキー(’84-85 /’99)/パンドルフォ/クイケン/クリーゲル/コッペイ/テル・リンデン(’96 /’06)
/イッサーリス/ケラス/ガスティネル/ガイヤール/トムキンス/ゲリンガス/ウィスペルウェイ/ハイモヴィッツ
/ヨーヨー・マ(’83 /’98 /’18)/ペレーニ/エルベン
CD 評はこちら(曲目解説を飛ばします) 深遠なるもの 無伴奏チェロ組曲。「バッハの真髄」みたいに言われる曲集であり、たくさんあるこの作曲家の名作の中でも間違いなく代表的なものの一つと言えます。チェロ一本でやることもあって派手な効果が期待できず、玄人受けすると思われてるし、その「深遠さ」では学校の教科書で代表曲とされる「マタイ受難曲」に引けを取りません。もう一つ似たものに「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」がありますが、そのチェロ版と言えましょうか。ただしヴァイオリンの方には「シャコンヌ」という独立して評価されるスター的な曲が存在するのに対して、このチェロの方にはそんなのはなく、その点とヴァイオリンよりも低い音域であるという両方で、より渋いと言われるわけです。しかしながらその低音ヴォイスから大きなやすらぎを得られる曲集でもあり、玄人受けと思われつつもイメージCMや映画などでよく使われています。「鮒に始まり鮒に終わる」ではないけれども、チェロを弾く人にとっては練習曲でもあり最後に究める曲でもあります。「どれだけ巧く弾いてもそのときの自分をただ映すのみで、常にそこから先がある」と東洋哲学のように言われるチェリストの聖典なのです。簡潔な作りの中に、複雑な構成の曲に劣らない驚くべき多様性を聞くことができます。 世に出たきっかけと「旧約聖書」 そのように「深遠なる代表曲」であるにもかかわらず、長い間世に忘れ去られていたということがあります。この曲の解説で真っ先に触れられることですが、あの偉大なカタロニアのチェリスト、カザルス(Pablo Casals 1876-1973)によって再発見されたのです。バルセロナの楽譜屋で見つけ出したというのは彼自身のストーリーであって、それまで誰にも知られていなかったわけではないのですが、バッハ研究用の作品、もしくは練習曲のように考えられており、誰も曲自体の独立した価値を認めていなかったということのようです。カザルスは自身の大切なレパートリーとして20世紀の頭からコンサートで精力的に取り上げ、初の全曲録音も残しました。それ以来というか、いつの間にかこの曲集は「チェロの旧約聖書」などと呼ばれるようになりました。19世紀の指揮者、ハンス・フォン・ビューローが平均律クラヴィア曲集のことを旧約聖書、ベートーヴェンのピアノ・ソナタのことを新約聖書と言ったのを誰かがそのまま置き換えたようです。因みにチェロの新約聖書は同じくベートーヴェンのチェロ・ソナタです。 使われる楽器について
ではこのバッハのチェロ組曲、旧約聖書は結構ですけれども、16世紀初頭の登場と言われ、当時はまだ新しかったチェロ専用のものだったのでしょうか。本来は誰のために作られた曲で、何で弾かれていたのでしょうか。 実はこうした楽器をめぐる問題はなかなか一筋縄では行かないのです。あるいはより以前から貴族の世界で主流だったヴィオラ・ダ・ガンバなどで弾かれることもあり得たのかもしれません(パオロ・パンドルフォやミリアム・リニョルのように実際に弾く人もいます)。そんな具合にヴィオラ・ダ・ガンバ(ヴィオール)をチェロの前身のように考えるのは時間軸に沿った見方だけれども、そもそもヴァイオリン族とヴィオール族は別のカテゴリーであって、それは間違いだという見方が一般的です。逆に横軸で見るならば、当時イタリアではチェロ、フランスではガンバが好まれ、ドイツでは両方が弾かれたようです。
チェロ組曲には自筆譜がなく、唯一残されている妻のアンナ・マグダレーナの美しい写譜には、タイトルの部分に ”Suites à Violoncello Solo senza Basso” と書かれています(senza basso は低音なしで、の意味です)。第6番については五弦の楽器での調弦音が記されており、それがヴィオロンチェロ・ピッコロのことだったのか、ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラだったのかということが議論されたりもします。このように、実際は具体的にどんな楽器で弾かれていたのか、それは何本のどんな弦のものだったのかについては様々な説があって、簡単には結論の出そうにない話なのです。
現代のピリオド奏法の演奏者の場合、バロック・チェロという言葉がよく出て来ますが、その場合のバロック・チェロというのはバロック・ヴァイオリンのときと同じことです。19世紀にモダンへと改造された構造を元に戻しているのです。それはガット弦であるということ以外にも、ネック/指板の胴への取り付け角度が浅くて張力が弱く、エンドピンがなく、弓もバロック・ボウであるということがあります。モダンと比べれば音は小さく、音色は倍音が立って、人間の声で言えば子音がより前に出て来る繊細なものとなります。
以上、こうしたチェロ組曲演奏時の適正な楽器の問題に加え、バッハと縁の深いヴィオラ・ポンポーサとは何か、などといった観点についてはこの記事では深く立ち入りませんので、音楽学者たちの論議や WIKI の説明などを参照してください。ここではどうあるべきかよりは今どんな風に弾かれていて、それを聞くとどう感じるかに焦点を合わせます。
作曲時期とバッハの中での位置付け
バッハの人生の中では、恐らくケーテン時代に作られたのだろうと考えられています。三十二歳から三十八歳の間です。この時期はその前のワイマール時代(二十三歳から三十二歳)、次のライプツィヒ時代(三十八歳から亡くなるまで)の両方が、それぞれ月に一回のカンタータを作曲し、毎週日曜の礼拝に自作のカンタータを演奏するために足りない分を作曲するなどという、いわば教会音楽の大きなノルマのようなものを課されていたのに対して、そうした宗教曲の作曲から解放されていた唯一の時代だとされます。宗教色がないというのは、仕えていた領主のレオポルト侯が教会音楽を使わないカルヴァン派の人だったからです。また、レオポルトはヴィオラ・ダ・ガンバの名人で音楽好きでもありました。この時期にバッハは世俗的な曲をたくさん作曲し、中には傑作が多く含まれます。ブランデンブルク協奏曲、管弦楽組曲、平均律クラヴィア曲集、ヴァイオリン・ソナタ、無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ、そしてこのチェロ組曲もそうです。私生活においては最初の奥さん、マリア・バーバラを亡くし、アンナ・マグダレーナと再婚しました。大変ではありましたが、自由に曲を作ることができた実り多き時代でもありました。 精神性が高い? チェロの名手、ヨーヨー・マもこの曲について、バッハが生涯の中で宗教曲から解放されていた短い期間に作曲されたけれども、同時に困難なときに慰め、また励ましてくれる曲であり、人生と共にあったと述べています。そして音楽によって人と人とが共鳴し合う現象を確認するための実験においてもこの曲を用いました。パンデミックによる孤立を慰めたり国境の壁に反対したり、平和を願ったりするために街頭に出て来て弾くときにも、この曲集から選んでいました。バッハのチェロ組曲は心に響く性質があるとされているのです。それならば、長らく忘れ去られていたはずなのに突然皆が目覚めたその性質とはどのようなものでしょうか。評論等でもよく「精神性が高い」などと言われています。 昨今は人工知能によって作曲家の名作を新たに作れる時代が来るだろうなどと言われたりします。例えば「十二音を音列によって平等に扱う」音楽などでは論理が音を決めます。そういう場合はコンピューターの方が上手くやるでしょう。楽器の演奏でも、初期のピリオド奏法のように、遅らせる拍と取り戻す拍の場所やアクセントに明確な決まりがあるような場合は人口知能の方が上手になるのは容易に予想できます。論理で定義できるからです。そして人間と機械の間で出来ることと出来ないことの棲み分けが進み、人は機械に出来ないことのみをするよう仕向けられるとも言われます。それまで曖昧だった境界がはっきりして技術と芸術が分けられ、今まで芸術の範囲だと思われていたものの中にも芸術以下の部分が見えて来て、本当の創造性こそが問われるというわけです。そうであるならば、コンピュータが発達することで、逆に人間は人間らしいあり方を機械から教えられることになります。
ただ、戦闘機のパイロットはいくら熟練しても機械学習を一定時間繰り返した AI に負けると言いますし、コンピュータ相手に練習する将棋の棋士が一番だったりもしますから、バッハらしい曲もその全作品を読み込ませることで、ある程度は自習させられるかもしれません。その上で膨大な情報量を扱うコンピュータが質を量の凌駕で表現しようとしてできない部分があるなら、それこそが物事の深みというものでしょう。生命力によってこの複雑な脳の構造が生まれて来たわけで、その脳の構造を真似て作ったものによって生命が生み出せないことははっきりしています。哲学的な命題になりますが、生命が持つ直感も、論理分析とは異なる次元のものであり、直感は証明不可能です。だから科学者の一部は直感の話となると「それは主観に過ぎない」と言ったりもします。恐らくその部分こそが、チェロ組曲が人を感動させることと関係しているのでしょう。曲の精神性の高さを「論ずる」ことは出来ず、我々は「感じる」のみだからです。何がバッハの深淵といって、最初から結論の出ない話でした。
果たして機械の作曲に我々が騙されるときは来るのでしょうか。少なくとも今のところは全くだめのようです。でもうかうかしていると分かりません。とりあえずチェロ組曲、聞いてみてどこに深みや直感を感じるでしょうか。バッハは先の時代や同時代の作曲家たちを模倣し、学んでいながら、それらのどれにもない独特の曲を生み出す名人でした。安易な精神論はかなわないけれども、人の喜怒哀楽を多面的に映すと同時に、静かな瞑想的境地を示すこともある稀有な作品だと言われます。そしてその作品を知力を超えて弾ける者が、深みのある演奏者に違いありません。
取り上げる CD
聞き比べについては、以前書いていた記事に書き加える形で枚数を増やしました。順序は録音年代順に改めました。同一演奏者で複数種の録音がある場合は、新しい方を基準に並べてあります。♡については若干の見直しもしました。因みにジャクリーヌ・デュ・プレとゴーティエ・カプソンは全曲やってはいないようだし、ジュリアン・ロイド・ウェバー、クリスティアン・ポルテラは探せず、シェク=カネー・メーソンはまだのようでした。 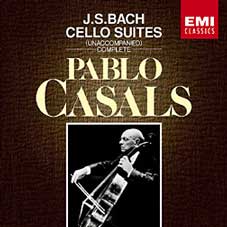 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Pablo Casals (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 パプロ・カザルス(チェロ) この曲集の演奏でまず最初に取り上げられるべきなのは、やはりカザルスでしょう。なんといってもこの曲を世に広めた功労者だからです。1876年生まれのカタロニア(スペイン/同地出身のガンバ奏者にサヴァールがいますが、幾分似たところがあるでしょうか?)の人で、スペイン内乱以降フランコ政権に反発して亡命し、亡命先のプエルトリコで1973年に亡くなりました。著述家たちやフリッツ・クライスラーなどの音楽家らの賛辞もあり、WIKI によると「20世紀前半における並外れたチェリストとして、あるいは史上最も偉大なチェリストの一人して語られる」ことが多く、加えてわが国では特に人道主義的、社会運動的な意味でも偉人として扱われたりします。話を戻してバッハのこの組曲の再発見という意味では、カザルス自身が思春期の頃にバルセロナの楽譜店でそのスコアを「発掘」したかのように言われています。埋蔵金みたいです。それは一つのレトリックにせよ、それまで研究対象か練習曲のようにしか扱われていなかったものを独立した曲としてコンサートに乗せ、芸術作品として世に認めさせたことは間違いありません。そしてここに掲げる CD の音源こそが、この作品初の全曲録音となったものです。 古くからのクラシック・ファンの方なら、このカザルスの録音をもって初めてこの曲集に馴染んだという場合も多いでしょう。その意味でスタート地点を評するのは厄介なことでもあるし、権威という意味でも安易に評し難いわけだけど、その後たくさん現れた現代の演奏者たちと、もし同列に並べて聞いてみるならばそれなりに特徴はあります。まずは気迫とロマン的な感情移入の感じられる模範的な演奏であるとした上で、敢えて恐れずに感想を述べてみましょう: 意志の強さが音に表れたような演奏です。主観的な感情を曲に込めることで新しい時代を切り拓いたという意味でも、演奏史に大きな足跡を残すものです。ごつごつとまでは行かないけど繰り返し現れるアクセントとためによって、脈動的な浮き沈みのリズムが感じられます。それが粘りとなり、スローなところでは独特の濃い歌い回しの感触が出て来ると同時に、フォルテで行くパートでは、フレーズの終わりをやや走り気味にまとめるところ、ためておいて断定するようにぶつけるボウイングの扱いなどが加わって、剛毅で熱血な印象があります。それはいくらか後のピリオド奏法で聞かれる節のあるリズムにも似たところがあるでしょうか。ただし軽くはなく、反対にむしろしっかりと重さがあるので、揺るぎない確信に満ちているとも言えます。そして何気なく続けて聞いていると、楽器の特性からも来るだろう骨太でやや鼻にかかった音色から、頭の横を飛び回る大きな甲虫か、気流に抗う内燃エンジン飛行機のうなりのようにも聞こえて来ます。まあ、それは何気なく聞く方が失礼に当たるわけで、またこうした描写はあくまで主観的なもの言いに過ぎないことも再度お断りしておくべきでしょう。今なお色褪せることのない素晴らしいパフォーマンスであることは間違いありませんので、まだの方は是非聞いてみてください。 カザルスの使用楽器は1733年製のマッテオ・ゴフリラーです。ストラディヴァリやモンタニャーナなどと比べて、太く雄渾な音と言われます。 1936年から39年にかけて収録された EMI 原盤の SP 復刻音源です。最初この記事を書いたときに、波形編集ソフトウェアを使って自分で針ノイズを消して低音を増強してみたことについて、それを公言するとひんしゅくを買うかもしれないなどと予防線を張ったわけですが、最近はアビーロード・スタジオのリマスターも出ており(他にもいっぱいありました)、サブスクライブのサイトで確認してみたけど驚くほど立派な音に蘇っています。さらにそれでも飽き足らずにノイズを手作業で取ったという国内盤も出ているようです(そちらは聞いていません。ポップノイズはスレッショルドを決めて一括で除去する方法と、部分的に波形を選んで一つずつ取り除く方法とがあります。そしてそれにもソフトウェア側にノイズを識別させて一定のアルゴリズムで個々に除くものと、波形を拡大して手動で行う方法とがあります)。ここではどのリマスター盤がいいかということに関して触れられるような試聴にまで至っておりません。いずれにしても、どれかを聞いておく価値のある歴史的な録音です。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Pierre Fournier (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ピエール・フルニエ(チェロ) フルニエは1906年パリ生まれで86年に亡くなったフランス・チェロ界の大御所であり、洗練されていて「貴族的」な演奏家として知られていました。そのバッハはカザルス後に大変評価の高かったもので、何度もリマスターされては出て来ていることがそれを物語っています。常に色褪せない定番の録音ということが言えます。現時点ですら音が大変良いこともありがたいです。 演奏ですが、フランス人らしい滑らかにつないだ音の運びが特徴的です。のびのびとよく歌い、結構強弱のメリハリをつけ、浮き沈みを表現しています。テンポは全般に速くはなく、ためて歌うような音のつなぎが丁寧で、やはり優雅な感じはするのですが、意外と堂々としていて情熱的なところも聞かれます。大変気に入っているケンプとのベートーヴェンのソナタでの流麗さを想像していると、もっとかっちりと区切って行くようなフレージングを感じる箇所もあり、時折かなり強い音を出して強調するようなところが出て来たりして、さすがにバッハの大作ともなると気合いも入るのだなと思いました。ビロードのような音色を追求したフランコ・ベルギー派とも言われますが、ただ滑らかというわけでは決してないのです。敢えて先ほどのベートーヴェンで言うなら、強いタッチのピアノに引っ張られているようにも感じるグルダとのソナタの録音の方に近い印象でしょうか。大変真面目に「旧約聖書」に取り組んだ折り目正しい名演奏だと思います。 1960/61年録音のアルヒーフです。リマスターが正確に何種類あるのか分かりませんが、OMBP や日本独自の高音質盤をうたうもの、最近のブルーレイ・オーディオと一緒になったものなどがあるようです。前述の通り滑らかで瑞々しく、カール=ハインツ・シュナイダーがエンジニアと特記されていたりもして、ステレオ初期ながら音質は大変良いです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Maurice Gendron (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 モーリス・ジャンドロン(チェロ)♥ 続いてまたフランスの名手です。フルニエ、ナヴァラと並び称されるモーリス・ジャンドロンは1920年ニース生まれで、90年に亡くなっている名チェリストです。フレンチ・リヴィエラというとバカンスとお金持という印象ですが、生まれは貧しかったということです。映画館でヴァイオリンを弾いていた母にまずヴァイオリンを習ったものの、チェロの方が好きで転身し、カザルスの教えも受け、自らの才能で立った人ということです。このバッハの組曲の録音はフランスの ACC ディスク大賞をとっています。 滑らかでさらっと流れるところは現代の若手の演奏と比べても全く古さを感じさせない演奏です。現代的と言うとあまり良い意味にはならないかもしれないけど、滑らかで理想的な運びに感じ、全くどこにも過不足がありません。どの曲、どの部分もあるべき様にあるのです。バッハの楽譜をそのまま完全に音にしたような名演奏というべきだと思います。変に偏ったところがなく、生真面目なフレージングにならず、気負ってごつごつと力づくにもなりません。流し過ぎずに流れるようによく歌い、どのパートも瑞々しいです。定番のフルニエよりもこちらの方が個人的には好きです。これが面白くないとおっしゃる方がいるとするなら、そのアクのないように聞こえるところでしょうか。また、敢えて言えば静かでゆったりなパートであまり思い入れを込めないところ、ことさら深く瞑想的という感じにはもって行かないところかもしれません。滑らかに朗々とよく歌っているのだけど、あまり湿った感じがしません。つまりバッハにロマン派的なものは求めず、均整の美を崩すほどに感情移入はしないのです。何か括弧付きの「深み」、「翳り」のようなものを期待して聞くと、多少違うかもしれません。またそこが良いところでもあると思います。 1964年のフィリップス録音です。これもまた、名録音で聞こえた上記フルニエのアルヒーフ盤と比べても劣るどころかむしろ美しく感じる音です。残響が心地良く、潤いがあるのです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Enrico Mainardi (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 エンリコ・マイナルディ(チェロ) カザルスのライバルぐらいに言われる人です。カザルスはいいと思わないけどこれはいい、などと言う人がいたりします。生まれはカザルスより二十一年後なのですが、三年後に亡くなっているだけで、活躍時期が重なります(1897-1976)。スペインではなく、イタリアの人です。ミラノ生まれ。演奏スタイルはカザルスとは似ていません。ここでも取り上げているミクローシュ・ペレーニの先生であり、ペレーニのところでは、その演奏スタイルの特徴についてハンガリー人の国民性に引っ掛けていい加減な仮説を立てておきましたが、案外この師であるマイナルディから来る部分があるという言い方も出来るのかもしれません。師と弟子は大抵似ないと感じてるけど、余計な飾りをつけずに楽譜から立ち現れるバッハに忠実に弾いて行くような姿勢は、ひょっとして教えを引き継いでいるのでしょうか。ペレーニの方がよりフラットで師の方が起伏があるものの、癖をつけずに音同士を続けて行く感覚は似てる気もします。
録音としては上に掲げたステレオ全曲盤の前にも1950年にデッカから3番と4番、次いで54〜55年録音のアルヒーフの全曲盤があり、57年のオルフェオ盤として1番〜3番というのも出ています。自分にはどれも基本的には似た傾向の演奏に感じられるので、細かな違いやどれがいいかということはファンの方に解説していただくべきだろうと思います。デッカ盤は聞いてないし、大雑把に言えばアルヒーフ盤は1番の出だしで大変遅いものではないこと、残響がなく、フレーズ最後の音を長く延ばす部分があったことなどが気づいたところで、オルフェオの方も出だしでやはり比べれば速いところがあり、3番の頭もそうで、遅い楽章はやはり遅いという感じでした。
ここで取り上げるのはオイロディスクが原盤となる、1964年〜65年に録音されたステレオ盤です。全集としては上記の通りアルヒーフに続く二度目で、色々なチェロ組曲の録音の中でも最もトータルの演奏時間が長いもの、というような言われ方がされます(厳密には調べていません)。
何でも国民性で分けるのは無理くりな典型化かもしれないけど、イタリア人の特徴として、カンタービレに歌う以外にもう一つ、ときに無機質なまでに分解的に、遅いテンポで丁寧に進めて行くような演奏が聞かれる場合があるように思います。これは他のところでも言ってしまったことですが、有名な指揮者で言えばジュリーニとか、アバドにも一部そういう演奏があったし、ピアノのミケランジェリの緩徐楽章にも見られます。それがどこから出て来る発想かは分からないにしても、このマイナルディのバッハにも同じように言えるところがあります。
遅くて丁寧で、力がこもっています。重く引きずるような運びに聞こえる拍の扱いがあります。引きずるというのがネガティブな言い方なら、大きく山を描くように滑らかなスラーでつなぐのではなく、テヌートで全体に音の間を空けずに平らに進め、長音の後ろを強く引っ張ったりします。軽々しい飾りで汚したりはしないのです。どの楽章も決して走らず、ゆったりなテンポで摺り足で音をつなげて行く仕方は同じで、アゴーギクの動きは施さず、拍は一音ずつに抑揚はつけずに、敢えて言うなら定規のように真っ直ぐに抑えて鳴らして行く荘重さがあります。
調弦の問題なのかどうか、少し低い方へずれるかのような響きに感じられる部分もありますが、ステレオになって何年も経っている独奏楽器のみ演奏ということもあり、録音コンディションは良好です。残響が豊かです。上記の通りオイロディスク原盤ながら、日本コロムビア(DENON)、タワー・レコードなどで国内盤 CD が復刻されて出ています。カザルス全盛時代にはあまり知られてなかった人ではあるものの、それ以降は日本でも人気が出て来ているようで、LP は高値で取り引きされます。
 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Nikolaus Harnoncourt (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ニコラウス・アーノンクール(チェロ) 古楽器(バロック・チェロ)によるこの組曲の、恐らく最初の録音になるもので、指揮者として有名な古楽の旗手、アーノンクールによる演奏です。彼は1953年に古楽器楽団であるウィーン・コンツェントゥス・ムジクスを結成して活躍したわけだけど、元々はチェリストであり、52年から69年までウィーン交響楽団で弾いていました。今は廃盤になっていて珍しいものながら、だからこそではないにせよ、これこそが隠れた名演だと言う人もいます。
アーノンクールといえば、あのアクセントの強い初期のピリオド奏法を生み出した中心人物の一人だと言えるでしょう。印象に残っている演奏の中には、その後に曲そのものを演奏者が自分を描くパレットへと変えて行く契機となったアグレッシブな「四季」だとか、ティンパニやブラスが咆哮する元気なモーツァルトのシンフォニーなどがあります。でもそういうものをイメージしていると、このバッハはちょっと違っていて、もっと正攻法な感じがします。この人が自身の録音を世に出した最初は1961年でしょうか。この組曲はフォノグラム・シンボル(レコードの著作権マーク:P)が65年となっており、録音は前年かもしれないけど、三十五歳前後で事実上キャリアの最初の頃の演奏です。
まだまだ方法論は確立されていなかったようで、案外ストレートに聞こえる表現となっています。それとも元々チェロを弾くときのマナーはこういう風なのでしょうか。間をとって脈動はするけれども、節くれ立ったアクセントも、語尾をばっさり切ってしまうこともなく、長音のボウイングで中ほどを持ち上げるバロックのイントネーションも遅い楽章以外では強くはありません。テンポは全体には少し速めのところが多いでしょうか。そうした速いパートではリズム面で小節頭のアタックが強い部分が多少あるぐらいで、案外さらっと流しています。むしろいくらかそっけないぐらいに足早で行くところもあります。それは途中から駈け出すという意味ではありません。したがって、ちょっと古楽的ではあるかもしれないけど、カザルスなどの古楽ではない節の強弱のつけ方とあまり変わらないとも言えるでしょう。もちろん彼が指揮する晩年のロマン派作品や、ベートーヴェンの宗教曲などのゆったりしたアプローチではないものの、各サラバンドの静かなところなど、たっぷりと歌っているフレーズもあって聞き応えがあります。素直に情感が感じられ、なかなか良いのです。隠れた名盤なのかどうか、ぜひご自身で確かめていただきたいと思います。
ただちょっと残念なのは録音です。箱鳴りっぽくて潤いがあまり感じられないのです。残響が全くないということはないのだけれども、60年代中頃にしては響きが少し古く感じてしまいます。原盤はアメリカのミュージカル・ヘリテージ・ソサエティのようだけど、ダス・アルテ・ヴェルク盤もハルモニア・ムンディ・フランス盤もあります。CD としてはテルデックからと、ワーナーの廉価版レーベル Apex から出ており、どちらも現行ではないながら、後者はまだ市場で出回ってるようです。使用楽器は1744年製のパリ、アンドレア・カスタネッリのものとのことです。バロック仕様で、弓もバロック・ボウです。
 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Daniil Shafran (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ダニール・シャフラン(チェロ) マイナルディがカザルスのライバルと言われるなら、こちらのシャフランはロストロポーヴィチのライバルです。シャフランなんて、何となくフランス語のような響きかと思うと、ドイツ近辺のユダヤ系(イディッシュ)の名前であり、起源はアラビアのようで、意味としてはスパイスのサフランのことだそうです。ダニール・シャフランはユダヤ系ロシア人であり、1923年のソ連、レニングラードの生まれで1997年に亡くなっています。
現代の若手のような速さですらすら行くのではないにしても、力のこもって遅いマイナルディなどとは違い、もっと何気ない運びでさらっと滑らかに、きれいに弾きこなして行く感覚があります。1番の頭から聞くとまずそんな感じでしょう。弾力としなやかさのある音で、無理がない印象です。ただ、全体にわりと平坦に聞こえるのは、走らずに一音を丁寧に発音して行くからかもしれません。余計な飾りを加えないという意味では、マイナルディにしてもペレーニにしてもそう言えるところがあるので、技巧的に色々見せたり恣意的な感情表現に埋没したりする種類でない点は同じです。その意味で格調の高い演奏です。
そしてスラーで波打つように滑らかに行くという意味ではなく、個々の音の扱いに独特のやわらかさがあり、弾む音が続くフレーズではリズム感良く跳んで行く軽いステップも聞かれます。二本の弦を跨ぐところで両方が開放弦みたいに響き続けるような音が聞かれる箇所もあります。ビブラートをかける細かな揺れが、遅くないパッセージで感じられる部分もあります。技術的にはロストロポーヴィチに負けることがなかったということで、その辺りの話は演奏する人に任せますが、確かに上手なのだと思います。それが独特の優雅なやわらかさ、何気なさに現れているのではないでしょうか。スパイスの名前だからといって、スパイシーな何かが付加されることを望むのは違います。形が整ったと言うとなんですが、もっと新しいところではオンツァイなどに求められるような折り目正しさがあります。
ただ、形の整ったところばかりではなく、2番では力強さも聞かせ、前のめりな気迫も感じられます。録音時期がまとまっていないことと関係あるかどうかは分かりませんが、乗っているときとそうでないときとで、多少ムラがあるのでしょうか。じっくりしたテンポで深々とサラバンドを聞かせる曲もあります。ユニゾンの響きの良さ、弓のテンションを最大に使って響かせる音も聞かれ、見事です。6番も力で押し切りはしませんが、強弱、緩急を思い切ってつけていて溌剌としているところがあります。
ソ連メロディアの録音で、収録されたのは1969年から74年にかけてです。定位は割とオンながら弾力があり、残響は多い方でないのに詰まった感じのしない音です。ちょっと鼻にかかったようなやわらかさのある音のチェロは、1630年製とされるアントニオ・アマティだそうです。
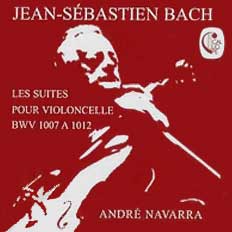 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) André Navarra (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 アンドレ・ナヴァラ(チェロ) フルニエとジャンドロンの間の世代になるナヴァラは1911年生まれのフランスのチェリストですが、イタリア人の血が入った人。88年没です。変わったところではボクサーでもあったというのですが、楽器演奏者とボクサーが両立するのは驚きです。 フルニエやジャンドロンより癖のある運びで個性的な演奏です。その二人よりもカザルスを少し思わせる力強さと太さがある気がします。関係ないかもしれませんが、そのカザルスには師事したことがあります。独特のための効いた呼吸で自在に延び縮みさせ、所々で濃く盛り上げるように歌わせるところもあります。引きずり気味にしたり語尾を多少延ばすところもアクセントになっています。それらが小気味良いリズムとなって進んで行き、癖があるとはいっても無理がなく、恣意的な取って付け感は全くありません。この運びが好きな方には何にも代えられないものではないでしょうか。カザルスの有名な演奏よりずっと音のコンディションが良く、同曲の中でも非常に良いものの一つでもあります。 その録音ですが、1977年で、レーベルはカリオペです。これも最近復刻され、ジョルジュ・キッセルホフの名録音、などとも言われるようです。フィリップスのジャンドロンに劣りません。やわらかいだけでなく、高音になると鼻にかかった猫のような鳴き声すら出る、腰を感じさせて滑らかな艶のある倍音成分が大変心地良いです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Paul Tortelier (vc) 1960 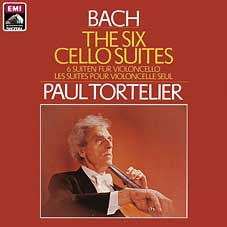 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Paul Tortelier (vc) 1982 バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ポール・トルトゥリエ(チェロ) またしてもフランスの名手です。チェロ奏者にはフランス人が多いのでしょうか。1914年のパリ生まれということで、フルニエ、ナヴァラに次ぐ世代です。彼より年下にはジャンドロンがいます。キブツで生活したことがあり、イスラエル・フィルを振って指揮者デビューしたり、「イスラエル交響曲」を作曲したりしていますが、ユダヤ系ではなく、カトリックの不可知論者とのことで、ケルト系ブルターニュ人の父を持つ人です。カザルスの再来などと言われることもありますが、それは彼自身がカザルスに最も影響を受けたと言っているからでしょう。師事したわけではないようです。評者の中には断定的なフレージングやアーティキュレイション、イントネーションのアプローチはカザルス譲りであり、良い和音の効果を得るためにピッチをわずかに先鋭化したり均したりする方法も学んでいるとする人もいます。 その演奏は「男らしい」などと言う人もいて、どういうことかと思って聞くと、確かに納得するところはあります。録音は二つ出ていて、どちらも EMI ながら、1960年と82年の盤です。 それではまず60年録音の方ですが、男性的ともされて評価の高い人であることがまず意識されるように、思い切りがあって勢いの良い演奏です。テンポは全体に割と速めで、アクセントとためはあるけれどもカザルスやナヴァラほどではなく、ためながらも流れが良い印象です。感覚的にもスピード感があります。そして瞬間的に強めるアクセントが潔く、そういうところも男性的と言われる所以でしょうか。割り切れないことは嫌いなのか、早く決めるように拍が多少前へ出る音もあります。人によってはそれが多少忙しく聞こえる場合もあるかもしれません。その前へ前へと行く推進力は、言い方を変えれば関西で言うところの「いらち」、せっかちとも言えるわけです。一方、ゆったりな楽章では引き締まっていて贅肉はないけど十分に歌い、しっかりとした情緒もあります。ですからせかせかした演奏だ、などとは決して言えません。リズム感があって大変良いです。録音も含めての音ですが、ちょっと硬めで朗々と響き、残響も豊かです。 次に新盤の82年録音盤ですが、世間的には案外旧盤の方が良いという声もあるようで、果たしてどんなものでしょうか。聞いてみると速いのは一緒でも、よりアクセントは控えめな気もします。比べればさらっとしています。音も録音の加減か、やや硬くない方に寄ってます。でも弾き方と波長は似てると思います。この人の演奏が好きなら、新しい方も十分魅力的ではないでしょうか。個人的にはどうだろう、新盤の方がいいかもしれません。より洗練されているからガッツがないように感じられたりするのでしょうか。ぐいぐいとした感じは確かに旧の方がややあるかもしれないし、残響はこちらもあるけれども、旧ほどではないようです。ライヴで生きのいい感じが欲しいか、より整った感触がいいかで分かれるように思います。 どちらにしても、優雅だけど斜に構えて粋なフランス人というイメージは当てはまらないと思います。波打つような歌謡生の演奏でもないでしょう。ブリタニー、ブレトンの人の気質と関係あるかどうかは分かりません。この人らしく熱いことは間違いないと思います。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Lynn Harrell (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 リン・ハレル(チェロ)♥ リン・ハレルは1944年マンハッタン生まれのアメリカ人チェリストで、かのジョージ・セルによって見出されてクリーヴランド管に抜擢された人ということです。チェロはレナード・ローズに師事しました。2020年に亡くなっています。 表情のしっかりおごられた演奏だと思います。伴奏部分にあたる音のアタックが軽く、時折スタッカート気味の切り方をして運びも軽く弾むようなところがあります。強弱については自在な呼吸で細かく付き、といっても深刻さや押しの強さは感じません。動きの気持ち良い運びです。速くても歌うようなリズムがあり、新鮮な印象なのです。トリルもリズミカルです。 一方ゆったりなパートでは結構粘って歌い、アクセントもはっきりとして浮き沈みが聞かれるし、フレーズの語尾も浮上して延ばし止めるような脈動があるのですが、カザルスと比べるならより動きに軽快さと弾力があるかなというところです。そういうところでは音の間は山なりにつないで滑らかです。ベートーヴェンのソナタにおいては、比較的アグレッシブな構えも聞かれるアシュケナージの伴奏が鳴り響くこともあるのかどうか、熱く粘り歌うところは良くても、自分には元気の良いアタックが多少好みからは外れたのでした。でもこのバッハは思い切りよく鳴らしてよく歌い、もう少し何気なくてもいいにせよ、これはこれで大変素晴らしいと思います。これぐらいしっかりとした表現があった方がいい方も多いと思います。 デッカの1982年から84年にかけての録音です。明晰で弾力のある明るい音色で、きれいにとられています。低音も力強いですが、骨太に押すというよりも弾力があり、動きが気持ちいいです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Heinrich Schiff (vc) ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ハインリヒ・シフ(チェロ)♥♥ ハインリヒ・シフはオーストリアの名手です。1951年生まれで、残念ながら2016年に六十五歳で亡くなっています。チェロはナヴァラに師事しました。ツィマーマン・トリオの一員であり、ムローヴァとプレヴィンと組んでベートーヴェンの「大公」も録音していました。このバッハの録音はいくつもの賞に輝いたようで、日本ではどうか分からないけど多くの批評家が絶賛するものです。 出だしは思い切ってかなり速い運びです。ピリオド奏法のような癖が少し感じられます。音像がやや遠くて軽く聞こえますが、勢いが良い感じ。一音のボウイングも山なりに変化をつけて持ち上げて緩め、やはり古楽の奏法を知っている世代かなという感じです。したがって現代的な印象でもあります。音色は艶のある倍音が明るく感じさせる大変心地良い音です。軽さと弾みのある感じは上記のリン・ハレルと比較してもいいかもしれないけど、よりさらっとしてリズミカルであり、表情をいっぱい付けたように聞こえないのは、パートごとにこの人なりのメソッドが統一されているからでしょうか。癖はあるけど非常に魅力的です。もしこれをバロック・チェロの歴史的奏法(モダン・チェロですが)としてカウントするなら、最も魅力的なものの一つだと思います。深みのある大人のピリオド奏法で、乗れる舞踊のようです。 ゆったりなパートでは、やはり呼吸の揺らがせ方が古楽器奏法を思わせるもので、音の間も軽く切ったりします。軽妙で、古楽の最も先鋭的だった頃の演奏者のようによじれて不自然な感じはなく、自然に呼吸の中に取り込まれて消化(昇華)されています。カザルスにも癖のあるこぶしというのか、節くれ立って浮き沈みをつけるリズムがありましたが、それを古楽の洗礼を経て違う形でリファイン(と言うとカザルス・ファンに叱られるけど)し、新たに定義し直したかなという印象もあります。重く剛毅な感じでは全くないです。ナヴァラの指導を受けたということですが、あるいはそういうことも関係あるのでしょうか。一般的には師に似ることはあまりない気もするけど、案外そう思えてしまうところもあります。5番、6番のサラバンドなど、瞑想的な部分でも重く沈潜はしないけど動きがあり、ボウイングの脈があって、チェロの音色も手伝ってしなやかで美しいです。感情移入過多のロマンチシズムとは違った美です。 1984年の EMI の録音です。瑞々しくて豊かな響きがあり、音は大変良いです。最も気持ちの良いものの一つと言っていいでしょう。シフは1711年製のストラディヴァリウス「マーラ」と1739年製のモンタニャーナ「スリーピング・ビューティ」を愛用しており、前者は現在クリスティアン・ポルテラが使っていますが、この録音においてどちらの楽器が使用されたかは明記されておらず、本人も語っていません。ポルテラも複数遣いであまり名言しませんので、聞いて比べようにも難しいところがあります。音で分かる方は教えてください。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Mstislav Rostropovich (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ムスチスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)♥ 説明の必要がないほど有名で人気があり、完璧な技術を持つとも言われる旧ソ連生まれのロシアのチェリスト(1927-2007)です。このバッハもドイツ、イギリスなど各国で数々の賞に輝きました。カザルス、フルニエと並んで名盤とされているものです。弾かないので技術的なことはコメントできませんが、楽々と完璧で、どこにも欠点を見出せない演奏だと思います。変わった細工はせず、真正面から曲の、楽譜のあるべき姿で描いていると言えるでしょう。その意味でバッハの組曲の一つの理想形であり、規範かもしれません。 豊満に響く見事な音で、出だしはさらっと流れるように速く、流暢そのものという感じです。静まるところは敏感に静まり、スラーとかやわらかいの意味ではないですがフレージングに角がなくスムーズで、何のわだかまりもなく音にして行く感じがします。この人が弾くと簡単そうだというのがよく分かります。最初だけでなく、部分的な例外を除いて平均すればテンポは快調な方だと言えるでしょう。でも必要なところでは荒くはないけど適切にしっかりと力も込めます。 一方で5番のプレリュードなど、全般にスローなパートではこの人らしい、やや粘着性のあるたっぷりしたメロディーが朗々と響くのを堪能できます。そうした部分がこの奏者の個性として技術以外で最もよく認識できるところかもしれません。ただバロックのバッハですので、ロマン派のようにやり過ぎているとは言えないでしょう。静かなサラバンドはたっぷり響くけれどもやわらかく、滑らかかつ静かで理想的です。芳醇と言ってもいいでしょう。6番のアルマンド、サラバンドも見事です。ガヴォット I, II は少し重くもたれるような気もしましたが。
本来自分の好みの人というわけでもなかったので以前はフェイバリットの♡マークを付けていませんでしたが、今回見直してみて、やはり付けないわけにはいかない名演ではないかと思い直しました。感じられる人柄も小細工をしない真っ直ぐなところがあるように思います。 1991年の EMI です。他に55年のプラハの音楽祭ライヴもあり、そちらは YouTube に出てます。手に入れてないし、リファレンスの機械でちゃんとは聞き比べてはいませんが、出だしでは流す感じというよりも、気迫を込めてしっかり歌わせるような運びに聞こえます。若さがあってかなり熱い演奏のようですから、そういう方向のものをお求めの方にはそちらということになるのかもしれません。モノラルであって音は豊満さ、ふくよかさはなく、古いから仕方ないけれども基音よりも硬い倍音が前へ出ており、シャープで荒削りな感じがします(時代とコンディションを考えれば優良です)。残響はしっかりあるようです。一方で91年の本盤の方は、ふよかに響くチェロの音が魅力的であり、最大鳴っている感じです。こちらは文句なく優秀録音と言えます。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) János Starker (vc) 1963/65 ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)1963/65 ♥  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) János Starker (vc) 1992 バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)1992 1924年ブダペスト生まれのハンガリーのチェロ奏者、ヤーノシュ・シュタルケルも大家であり、大変有名な人です。ユダヤ系でアメリカに亡命し、2013年に亡くなりました。ロストロポーヴィチとはほぼ同じ世代ということになります。バッハの組曲は熱心に録音しており、全部で四回あります。1952年に出たモノラル時代のピリオド・レコーズ盤、63/65年のマーキュリー盤、74年発売のフィリップス盤、そして92年録音の RCA 盤です。この中でも人気があるのはマーキュリー盤と RCA 盤でしょうか。 まず63/65年録音のマーキュリー盤ですが、始まりは自然なためとたわませ方による理想的な運びで表情があり、テンポは中庸です。無理がなく、作ったようなところもありません。スムーズだけど覇気があるので、スムーズというよりはストレートと言った方がいいでしょうか。後で触れますが、新盤と比べても途切らせるようなフレーズを出さずに真っ直ぐであり、大変よく歌わせていて力強さもあるけれども、もっと流れる演奏です。むしろフレーズの語尾で駈けるように素早くまとめるところも聞かれるぐらいです。 ややスローな二曲目のアルマンドでは細かな延び縮みはありますが、意外とポーカーフェースでしょうか。それ以降も速いパートではくっきりはしているけど素直に流していて、結構速く感じるところもあります。 そして静かな部分ですが、あまり癖を感じさせず、素直に歌わせて行きます。5番のアルマンドやサラバンドのようなよりスローなパートでは静謐さがあって、表情は大きくないけれども寒色系のほの暗さのようなものも少し感じます。それがまたなかなか魅力的です。 全体を通して見ると、ロストロポーヴィチほど楽々感、朗々感はないにしても、劣らず模範的な演奏だと思います。元来技術の高い人であり、この頃(四十一歳)が絶頂という説もあるようです。ここでは上手い下手を評価しているのではなく、聞いた感じを述べているだけなのでそういうことには突っ込みませんが、どちらかといえばかっちりとしていてソフトな雰囲気はなく、表現はほどよくニュートラルでさらっとしたところもあります。いいと思います。 音響的には残響が乗り、少しシャランとした倍音成分が目立つものの良好な録音です。 一方92年の新盤の方は、出だしのテンポと表情は似ていてほとんど同じに感じますが、その後はかなり違いがあります。旧盤も覇気があると言いました。でもこちらはもっと力がこもったように聞こえる演奏です。途切れ気味になるところもあるほどはっきり区切ったフレーズが特徴的で、テンポも自在に動かし、少し重さを感じさせます。換言すればスケールの大きさが良いところだとも言えます。より表現が大きくなり、アクセントもはっきり、間もくっきりさせています。個人的な好みからは外れるものの、良くいえば落ち着きがあってしっかり歌うとも言えるわけです。他の人にない独自の表現を模索したのでしょうか。 63/65年盤ではほの暗い感じが魅力だったスローなパートにはより深刻さが加わり、遅い分表現も大きめに聞こえて、途切れがちなほどに間も空けます。人によってはごつごつとした感じに受け取るかもしれません。バッハの偉大さを意識させる表現です。 こちらの録音は旧盤より音がより前に出て残響も自然になり、子音も目立たず艶やかな美しいチェロが聞けます。オーディオ的にはこちらでしょうか。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Anna Bylsma (vc) 1992 バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 アンナー・ビルスマ(チェロ)1979  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Anna Bylsma (vc) 1992 ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 アンナー・ビルスマ(チェロ)1992 ♥ アンナー・ビルスマは1934年生まれで2019年に亡くなったオランダのチェロ奏者です。男性です。バロック・チェロを使った古楽演奏のパイオニアでもありますが、モダン・チェロも弾くようです。バッハの組曲は少なくとも二回録音しています。 1979年の旧盤はそのバロック・チェロということで、ピリオド奏法的な不均等なリズムと小節単位のテンポ・ルバート様の動きなど、拍に粘りが聞かれ、途中で走り出すような伸縮もあります。また、弾き出しで弱く、途中で盛り上げる古楽特有のアクセントも聞かれますが、今や慣れたこともあるのか、全体に自然な表現に感じてあまり気になりません。テンポとしては全体にやや速めの運びで語るような雰囲気があり、それでいながら活きいきしていて遊びを感じます。5番、6番のサラバンドや6番のアルマンドなど、自らに語り聞かせているかのようにしっかりと無音の間を取り、古楽の引き延ばしたボウイングで山を作ってゆったりと濃く歌って行きます。必ずしも滑らかな歌にはならないので好みは分かれると思いますが、古楽奏法に抵抗がない方には味わい深く感じられると思います。大変魅力的な一枚です。 セオン原盤(発売元は昔はポリドールでしたが、現在はソニー)で録音年が79年。古楽器セッティングだからかどうか、ヴァイオリンがそうなるのと同じく、やや軽くて乾いたというのか、倍音がくっきりとしています。楽器はゴフリラーの1669年のバロック・チェロ、6番のみ1700年製のチェロ・ピッコロだそうです。ゴフリラーといっても野太い音には聞こえません。気持ちの良い残響があって優れた録音です。 92年の新録音の方はモダン楽器のようですが、テンポは総じて遅くなり、表情が深くなっているように感じます。楽器や音色ではなく、弾き方における変化はどう理解すべきでしょうか。出だしから随分ゆったりな呼吸になっていて驚きます。心地良く落ち着いた雰囲気であり、せかせかした古楽の徒という印象は全くありません。具体的にも前ほど古楽器奏法的ではなくなっていると言えるでしょう。それでも所々で音を引き延ばして間を作る呼吸は古楽研究で培ったものであり、音色はともかく依然ピリオド奏法ではあるように聞こえます。旧盤も自然だと言いましたが、しかしこちらの方がイントネーションとしてはより自然というのか、内省的な心情を感じさせる素直な歌となっているのです。部分的には走るところもあるものの、全体にゆったりしている分だけ古楽の語法が苦手な人にも気にならないことと思います。 楽しげな印象は79年盤より多少減ったのかもしれませんが、世間でよく言われるように古い方が名演だということもないように思います。音色はぐっと滑らかになっています。使用楽器は1701年製ストラディヴァリウスの「セルヴェ」です。繊細でやさしさがあって、大変魅力的です。演奏流儀に対する考えの変化からなのか、あるいはこの楽器を使いたかったのでしょうか。奏法に注意を奪われずに味わうなら、個人的には、こちらの新盤の方がしみじみとした雰囲気があって良いと感じました。旧盤が四十五歳時、こちらが五十八歳時ということで、年輪を重ねた分でしょうか。 レーベルはソニー・クラシカルで、大変魅力的な音の優秀録音盤だと思います。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Csaba Onczay (vc) ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 チャバ・オンツァイ(チェロ)♥♥ 1946年生まれのハンガリーのチェリストです。東欧系ということで真面目さ、飾らなさということがまず思い浮かんだりするのですが、先入観はいけないにせよ、まさにその通りの真摯な演奏です。ベートーヴェンのソナタも大変魅力的でした。個人的には♡♡にしたけれども、超有名人でもないし、ナクソスから出ていてこれといって癖がないので、わざわざこの演奏こそがと薦められるかどうかは微妙な気もします。でも珍しいものを評価して差別化を図ろうなどという意図は全くありません。噛めば味が出るの類であり、派手な要素や世評に惑わされずにバッハに向き合うならこれこそという、大変魅力的な一枚だと思います。 出だしは滑らかでやや速いテンポです。弾き方は素直なフレージングで誇張がなく、目立って気になることはないけど細かな表情があります。緩め延ばすところなどはナチュラルな運びでそうしており、決して楽譜通りの平坦な演奏ではなくて、あるべき音楽の呼吸に満ちています。とにかく自然体なのです。そして楽譜を音にするという意味では余計なことをしないストレートな名演としてロストロポーヴィチやシュタルケルの旧盤なども挙げましたが、サンセリフなそれらと比べてもより魅力的に感じた点は、落ち着いてリラックスしているその波長です。確かに1番の ジーグ、2番、3番のクーラントなど、速いところはさらさらと素早く流して行く箇所もあります。でも1〜6番の各サラバンド、6番のアルマンドなどのゆったり静かに歌う部分ではどうでしょうか。これほど素直に心に入って来る歌もないのではないかと思います。同じく自然体でこのページでも最も気に入った演奏として取り上げているヨーヨー・マと比べると、あちらはもっと自由に動かして深く沈潜しますが、こちらはより形が整ったものと言えるでしょう。同じハンガリー人で日本で人気の高いペレーニと比べれば似たスタイルと言えるのかもしれませんが、乗りの部分で受ける印象は異なります。 1992年録音のナクソスです。この音がまた大変気持ち良いです。楽器は分かりませんが、日本で教えているようなので、知っている方もいらっしゃることでしょう。それこそ派手ではないけど、繊細で瑞々しい艶のある響きです。収録の仕方もあると思います。音像はやや引き気味ながら残響が豊かで、バッハの組曲の中でもリラックス方向で大変良い録音だと思います。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Mischa Maisky (vc) 1984/85 バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ミッシャ・マイスキー(チェロ)1984/85  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Mischa Maisky (vc) 1999 バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ミッシャ・マイスキー(チェロ)1999 ミッシャ・マイスキーはチェリストとして日本でも一、二を争う人気の人となっています。姉の亡命によって強制収容所にいたという経歴で、ソルジェニツィンのような苦難をくぐり抜けて来たということです。1948年旧ソビエトのリガ生まれ、ラトビアのチェロ奏者です。その演奏はウルトラ・ロマンティサイズド(超ロマンティックに美化した)と言われることがあるほどたっぷり歌い、ルバートが大きくテンポの揺れも激しいもので、カザルスの熱気とは違うものの、好きな方は熱く語ります。このバッハも大変話題になりました。二つ出ていて、1984/85年の録音と99年になって出た新録音とがあります。 何よりも「熱い」演奏が好きな人は、身振りの大きい84/85年の旧録音を推すようです。出だしはほどよいテンポで進め、しばらく行ったところでかなり大きな間が聞こえて来て、この人らしい部分が出て来たなと思います。そこからはやはり熱い揺らしが加わり、スケールの大きな演奏が展開されます。ゆっくりなサラバンドのパートは5番ではすすり泣くようで、6番はかなり力が入っており、他もたっぷりとした情緒です。どこもしっかりとした抑揚があって満足感が得られると思います。 旧に比べてあまり良いことを言わない人もいる99年の新録音の方ですが、あらためて聞いてみるとこれがかなりいいのです。全体的には旧盤よりも前へ出るせっかちさがなくなり、落ち着いて来て呼吸が深くなっている気がします。しかし出だしなどではむしろテンポはかなり速くなり、意外なほどさらっと流しています。何気なさが加わったというのでしょうか。ただし例の40秒ぐらいのところで旧に呼吸を緩める手法は同じで、表現の幅が広いのはやはりマイスキー独特です。6番の夢みるようなやわらかいアルマンドに加え、サラバンドの方は5番がより静かになり、6番については前より力が抜けています。たっぷりとした情緒があって表情豊かなのは変わりません。 匿名の紳士から贈られたという1720年製モンタニャーナのチェロも素晴らしい音色です。しかしこの寄贈の伝説は一部作り話で、ユダヤ人であるミッシャ・マイスキーに対してユダヤの財団がお金を出し、前のオーナーから買い取って破格の値段で売ったというのが真相のようです。後にマイスキー本人が不足分のいくらかを追加で支払ったともされます。 両録音ともドイツ・グラモフォンです。コンディションはどちらも大変良好です。演奏のせいもあるかもしれませんが、強い音がしっかりラウドに響くからか、旧の方がダイナミックで朗々と鳴り、新の方には細かな音に繊細さが加わるような気もします。いずれを選んでも不満はない優秀録音です。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Paolo Pandolfo (gamb) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 パオロ・パンドルフォ(ヴィオラ・ダ・ガンバ) 1964年生まれのイタリアのヴィオラ・ダ・ガンバ奏者です。したがってここではチェロではなく、ヴィオラ・ダ・ガンバで弾いています。そのガンバはサヴァールに師事しましたが、最初はジャズのベースとギターも弾いていました。ここでこの盤をチェロ組曲として取り上げるのは本来違うのかもしれません。でもそういう演奏例も当時、あったのでしょうか。貴族階級にはチェロよりも好まれ、広く普及していた楽器です。他にも、バッハの当時にこのヴィオラ・ダ・ガンバ(ヴィオール)の方が盛んだった国、フランスのミリアム・リニョルも2020年にシャトー・ドゥ・ベルサイユ・レーベルに録音していますから、すごく珍しいものでもありません。ただ、この楽器で弾くにあたり、二人とも移調を施しています。そうしないと弾けないということではないと思いますが、フレットがあるから調弦によって純正調的にハモるずれるが出るのだろうと思います。手稿譜に指定されてるだけでなく、そこら辺の理屈からもバッハが本来チェロ専用に書いた曲だという説が成り立つのかもしれません。リニョルは全部移調している一方、パンドルフォは二曲しておらず、それぞれの調性も二曲を二人ともが同じにしている以外、別の調でやっています。音色がチェロとは違い、実際の音量は小さい一方で倍音が繊細に浮き立ちますので、この方が好きという方もおられると思います。
演奏ですが、楽器の特性に合わせるようにゆったりな部分、のんびりとしてひなびた感覚があるということはまず言えるでしょう。それはリニョルでも同じです。そうしたヴィオール特有の弾き方以外でのパンドルフォの特徴を挙げるなら、ずいぶんと創意工夫がされたものだということでしょう。ジャズのベースと同様に弓を使わず、ピツィカートでやってみせるところもあります。
1番の出だしでは少し速めの運びで、それも弓の当て方が違ってヴィオール的なのかどうかは分かりませんが、さらさらと力が抜けていて気持ちがいいです。ただ、所々で間を空けて大きなアクセントを施すような、いかにもバロック流といった運びはあります。テンポの延び縮みも自在で、いわゆるピリオド奏法らしい特徴が出ています。前にのめるような攻撃的な波長ではなく、リラックスできるものなので、そうした揺らぎを心地良く感じる種類ではあります。
サラバンドなどのゆっくりな曲では音節の切れ目で立ち止まるように大きく間を空け、確かめるように進めて行きます。特有の真ん中を持ち上げる山なりのボウイングはこの楽器らしく非常にはっきりとしており、独特の世界です。力が抜けた2、5、6番のサラバンドでは静けさも感じられます。4番は一部ピツィカートになっています。リュートの曲みたいな出だしで面白いです。
全体にはアタックがかなり元気なところも聞かれるし、しっかりと古楽器奏法特有の癖もあるので、ゆったりで繊細、リラックスできるものこそがいいというのなら、どちらかと言えばミリアム・リニョル盤の方がお薦めかもしれません。変化を楽しめるのはパンドルフォでしょう。ここではとりあえず先発として代表させておきました。
2000年のグロッサの録音です。チェロよりもボリュームで押して来る感じに聞こえない楽器なので、特有の軽さ、繊細な音色があります。高い倍音がハモるのがきれいに再現されています。残響もほどほどあります。
 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Wieland Kuijken (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヴィーラント・クイケン(チェロ) 古楽のクイケン兄弟たちの中のチェロ奏者、ヴィーラントによる演奏です。しかし古楽の運動が勢いをつけた頃には出さず、21世紀に入ってから録音されたものです。この人は1938年ブリュッセルの生まれで、その活躍は古楽ファンならご存知のことかと思います。そして面白いのは、兄弟たち同様にばりばりの古楽の徒ではあるはずなのですが、楽器はイッサーリス同様にモダンだということです。 その点に関しては、バッハであることを当時の様式で追及することはせず、自分らしく弾くことを目指したと発言しているようですが、アクセントはやはりピリオド奏法独特の要素が前面に出たものとなっています。出だしでは一連の小節の後ろ側の音をスタッカート気味に弾ませるなどして、すぐにそれと分かる運びとなっています。しかしゆっくりな楽章ではイッサーリスよりも粘らせ、音節を前後に絡ませるようにして延び縮みさせつつ、テンポも十分ゆったりとしています。語尾を長く引く表現も出しており、この人は古楽的といっても、全てを短く切る様式ではないようです。瞑想的なパートでは力の抜けた自在な歌が聞けます。というより、どのパートも全体にリラックスはしていると言えるでしょうか。もちろん真っ直ぐ流さずにひねりが効いているところは古楽的であり、アクセントの位置はかなり個性的です。ボウイングもしっかりと身についた古楽そのものです。
アルカナ・クラシック・フランスの2001〜02年の録音です。ただし、現在ダウンロードを除いては入手は困難なようです。音響的にはピリオド楽器然とした細い倍音の出るものではないけれども、潤いがあって響きが大変良いです。60年代から愛用して来たというアンドレア・アマティを模したチェロだそうです。モダン仕様です。第6番のチェロ・ピッコロも古楽の資料によらずに新しく作られたものということです。こういう内容重視の自由な発想、いいと思います。ガンバ・ソナタもカップリングされています。
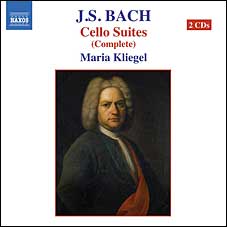 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Maria Kliegel (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 マリア・クリーゲル(チェロ) マリア・クリーゲルは1952年生まれのドイツのチェロ奏者です。シュタルケルに師事し、ロストロポーヴィチ・コンペティションで優勝しています。 多少ピリオド奏法を思わせるところのあるためや引き延ばしのアクセントをつけ、強弱も細かくしっかりめに施しているので、軽く立ち止まりながら進めて行く感触があります。感じ方によっては少しフレーズがごつごつしているように思う方もあることでしょう。しかし全体の流れとしては、速いパートなどは特にですが、さらっと割合速く流して行く運びになっています。そういう意味では前言を翻して矛盾するようながら、スムーズさを感じる場合もあるかもしれません。スピード感はほどほどありながら、節もしっかりついているというのでしょうか。巧者で色々技を繰り出すのに、性質としては斜に構えないで真面目に取り組むところのある人ではないでしょうか。 ナクソスの2003年の録音です。新しいだけに良好なコンディションです。曖昧さのないくっきりとしたチェロで、多少硬質さを感じさせる明晰な響きです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Marc Coppey (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 マルク・コッペイ(チェロ) フランスの期待の星です。ベートーヴェンのソナタも、ドヴォルザークの協奏曲も、数ある録音の中で一番だと言ってもいいぐらい大変見事でした。マルク・コッペイは1969年のストラスブールの生まれ。パリ在住です。バッハ国際コンクールに優勝しているし、ロストロポーヴィチにも認められています。そのバッハはどうでしょうか。 最もリラックスした演奏だと言えるでしょう。現代の人らしく洗練されているけど、モダンに行こうとせずに昔ながらのフレンチの良さも持っています。最初は穏やかに、角の丸いフレージングでやさしく撫でて行くように始めます。テンポは中庸ですが、さらさらっと速い感じになるところはありません。全体に落ち着いていて攻撃的な波長ではないのです。スラーで全て滑らかにつなげるというのではないけれども、古楽寄りの呼吸で大胆に間を設けて切って行くような効果は使いません。スローなパートである4曲目のサラバンドでのように、もし空けても、前後をやわらかく終えてから始めるように弱音で行くので、無音による鮮烈な効果を出す方向には向かいません。しかし拍ごとに強弱の階調は見事に細かくついており、延び縮みの自然な脈動もしっかりとあります。人によっては全体にややもったりとした印象を持たれるかもしれませんが、上記ドイツのクリーゲルのような切れよりもこちらのフランスっぽいマナーを好む方もおられるでしょう。二曲目の緩やかなアルマンドに入っても印象は変わらず、全曲を通してこの感じで弾いて行きます。多くのチェリストが走ってみせるような楽章でも急がず、コントラストをつけてみせたりはしません。静かな各サラバンドはゆったりと、そういうところでは間も取って小声で語りかけるように弾き、5番では大変スローに、6番ではまどろんでいるように運びます。バッハの大曲ではあっても力が抜けているという珍しい人です。最も気負わない演奏だと言えます。 レーベルはイーオンで2003年の録音です。演奏に相応しいやわらかい音で捉えられています。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Jaap ter Linden (vc) 1996 ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヤープ・テル・リンデン(チェロ)1996 ♥♥  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Jaap ter Linden (vc) 2006 ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヤープ・テル・リンデン(チェロ)2006 ♥ 最初にこの記事をまとめたときに、このヤープ・テル・リンデン盤だけをご紹介しようと思い、「癒しのバロックチェロ」というタイトルにしたぐらい気に入った演奏です。後で触れるヨーヨー・マと並んで、この数あるバッハのチェロ組曲の録音の中でも二つのベスト盤だと思っています。「癒し」という言葉自体は昔からあるものの、90年代ぐらいから「ヒーリング」の訳として特に心理療法系、スピリチュアル系から流行したので、ともすると「あやし」系と思われる危惧もあり、今思えばちょっと軽い乗りでした。でも本当にそう呼びたくなるように、包み込むようなやわらかさとたっぷりとした運びに酔い、リラックスした呼吸が深い瞑想へと誘ってくれるような演奏です。 実は新旧二つの録音があり、「癒し」と呼んだのはすぐ次に述べる旧盤の方です。 1996年盤 ハルモニア・ムンディ・フランスから出ている1996年録音の演奏(旧盤/1997年発売)は、ヨーヨー・マとは方向が違い、私的な感情へと掘り下げるものではないような気がします。物語を語るというよりも、あくまでも音楽として流れるのです(ヨーヨー・マが表題音楽的だと言っているわけではないですが)。 ヤープ・テル・リンデンは1947年ロッテルダム生まれのオランダの古楽器演奏家で、ヴィオラ・ダ・ガンバも弾きます(「バッハのヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ」)。ここでのバロック・チェロの音色はマのものよりも基音が低く(マもピッチを変える試みはしています)、倍音は独特の艶を乗せたはっきりとした音です。そして演奏マナーですが、これをピリオド奏法的としていいかどうかは分からないけれども、テンポの前後への伸び縮みは絶妙に伴わせながら、前にのめることはなく、穏やかで心地の良い揺れに誘われます。典型的な縒れて速いものとは違うのです。もはや時代考証の試みではなく、表現としての心地良さを追求した結果だと言えるでしょう。 シャコンヌのページでイリヤ・カーラーを取り上げましたが、あのヴァイオリンのナチュラルな魅力をチェロ組曲でも味わいたいとき、上記のチャバ・オンツァイなどもその路線と言えるにしても、個人的にはまずこの CD を取り出します。違う人の別の楽器の演奏と比較するのもおかしいでしょうか。カーラーの自在に流れ、遊びながら集中するセンスにも匹敵するものを持ちながら、さらにゆったりとリラックスしています。しかし自然であるがゆえに、そのデリケートな感受性を見逃されることもあるかもしれません。人の好みはそれぞれですからどう感じるのも正しいですが、このあたりはイリヤ・カーラーをそっけない演奏と言う人がいるのと同様、「なにも味がしない演奏」と受けとめる人もいるようです。しかしきばった大きな表現はないにせよ、繊細な揺れがたまりません。遅くない楽曲でも深々と歌いますが、後半の組曲の静かなアルマンドやサラバンド、特に5番の深く沈潜した運びは感動的です。
使用楽器は1725〜1730年頃のカルロ・ベルゴンツィ製作のものと、1600年頃のアマティ(第6番)です。音響的には残響が心地良く深々と鳴り、バロック仕様らしいややくっきりとして繊細な倍音をしっかりと捉えています。潤いのある大変美しい響きの録音です。 2006年盤 その後2006年になって、新録音がブリリアント・レーベルから出ました。楽器が1703年製のミラノ、ジョヴァンニ・クランチーノ製作のものに変わっています。ブリリアント・クラシックスは廉価な企画ものを出すところで、この新盤も手頃な価格ですが、録音はややオン・マイクで弓の音がよく聞こえます。残響も少ないようです。その結果として音が前へ出てきてエネルギッシュに聞こえます。この人の最大の魅力であるリラックス感が、若干ですが旧盤よりも少ないようにも思えます。演奏の組み立て方は基本的には変わっていませんが、粘りのある歌い回しが増え、テンポ・ルバート様の動きもわずかに大きくなり、全体により力がこもって情熱的になっ たようです。録音のダイレクト感を差し引いても、演奏自体の気分に違いがあるように感じます。アンナー・ビルスマの92年(新)盤と印象が多少被って来ることもあり、どちらかを選べと言われれば、癒されるという意味でも個人的には穏やかで深々とした旧盤の方を取ります。もちろんこちらの新盤も、数多くの演奏家たちの中で大変魅力的であることは疑いありません。 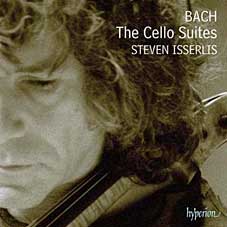 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Steven Isserlis (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 スティーヴン・イッサーリス(チェロ) スティーヴン・イッサーリスは1959年のロンドン生まれで、古楽器奏者というわけではありませんが、ガット弦にこだわるチェリストです。おじいさんがユダヤ系のロシア人である音楽一家に生まれました。多くの賞を取り、シューマンに熱くて著書も売れるなど、本国では大変有名な人のようで、日本でも高く評価するファンがいます。バッハのチェロ組曲については、その精神的な背景としてキリスト教的な考えを持っているということです。宗教的感情の深みが感じられるかもしれません。 ピリオド楽器ではないけれども、延ばし縮めに独特のメリハリがあり、ピリオド奏法を踏まえた演奏です。1番の出だしは速めで弾むような軽快さがあります。その後も全体に、音節の末尾で音を延ばさずにさらさらと流す傾向があり、弾力があって切れの良いフレージングに活気を感じます。静かなサラバンドなどの部分では音の強弱を一音の中でもくっきりとつけ、浮き沈みのある歌をうたいます。ボウイングははっきりと古楽のしなわせ方です。テンポは速くないにしてもたっぷりした方でもなく、語尾は長く引きません。また、フレーズに節がありながらも静けさも感じられるもので、音の間を切りつつ、一人考えを巡らせるように弾いていて情感もあります。
ハイペリオンの録音は2005〜06年で、ヘンリー・ウッド・ホールながら直接音がはっきり捉えられていて残響はあまり多い方ではなく、クリアな響きです。それでありながら、ガット弦でもヴィオラ・ダ・ガンバのように繊細な倍音が浮き立ち、前に出るという感じの音ではありません。張力の関係でしょうか。使用楽器ですが、この人は1726年製ストラディヴァリウス、マルキ・ドゥ・コルブロンを使っているようです。古楽器仕様ではありません。余白には第1番の一部を異なった手稿譜で三つ弾いて聞かせるトラックが入っています。それと、カザルスに敬意を表したのでしょう、「鳥の歌」も聞くことができます。
 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Jean-Guihen Queyras (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ジャン=ギアン・ケラス(チェロ)♥ ジャン=ギアン・ケラスは1976年カナダのモントリオール生まれでフランス国籍のチェリストです。アルジェリアにもいたことがあるようですが、アルカント四重奏団のチェロで、2002年のグレン・グールド賞の受賞者です。 モダンで表現の可能性を追求したような演奏です。他のところでこのケラスの演奏について、相撲でもないのに「技のデパート」などと言ってしまいましたが、技術が高くて何でも出来てしまう人なのかな、という気もします。ベートーヴェンのソナタは見事でした。そしてこちらは実に色々な表情を見せてくれる見本市のようなバッハです。誰も真似できないかもしれません。そしてあらゆる表現を盛り込んでいるものの、それを大振りな感情の押し付けや熱さとしては感じさせず、むしろクールな感覚なのが特徴的です。 1番で見てみましょう。出だしは速めで颯爽としていますが、ための呼吸はしっかりあり、軽々とスムーズに流します。その流暢さが、抑揚と見事なアクセントの動きにまで波及している様子です。全てにそつがなく楽々と弾けてしまうような印象で、この後のパートも含めてどこも完璧に制御出来ているのでコンペティション的な意味で文句なく最高だと思います。でも個人的にはもう少し落ち着きがあって情感の面で訴えて来るものがあった方がいい気もします。ただ、ここまで来ると感心するほかありません。 二曲目のアルマンドは速い楽章ではありませんが、途中から結構速く流す感じがします。技術的に可能なところは完璧なまま飛ばしたくなるのかもしれません。三曲目のクーラントは踊るようなリズムでエネルギッシュに跳ね、四曲目のサラバンドではふわっと弱音に潜らせる手法があります。五曲目のメヌエットはまたダンスを踊るように少しひねり、軽快でリズミカルな動きを見せています。六曲目のジーグはすごく速いです。という具合に、大変表情豊かです。 ではゆったりで静かな楽曲、演奏者によってはロマンティックになったり影が深くなったりすることがある部分のテクスチュアはどうでしょうか。例えば5番のサラバンドなどですが、間を空けて静かに行きますが、均質な音とコントロールがあって、ロマンティックという方向には向かいません。やわらかい霧が微かにたなびいているのにふと気がつくように、スタティックな空気感を感じます。ロングトーンで音の強弱を大きくはつけず、滑らかに均質に、漂わせるように弾くからでしょうか。客観的な視点があり、冷静さのあるモノローグという感じです。ミッシャ・マイスキーなどとは質的に大きく反対の側に振れた現代的な表現ですが、情感がないのではなく、これはこれで独特の抗い難い魅力があります。 2007年録音のハルモニア・ムンディです。ふわっとやわらかく響き、倍音も透明で滑らか、純粋な響きで大変良いです。楽器はジョフレッド・カッパの1696年製ということです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Anne Gastinel (vc) ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 アンヌ・ガスティネル(チェロ)♥♥ ナイーヴの看板娘、ガスティネルです。1971年リヨン生まれ。トルトゥリエ、シュタルケル、ヨーヨー・マに師事したフランスのチェロ奏者です。 全体になんとも爽やかな演奏です。表情はあるけどあっさりと感じさせるもので、その当たりのやわらかさはこの人の性質なのでしょう。リズムの扱いがどうというより、重く押して来るような感覚的印象とは逆の意味で軽さに満ちているのです。何より素晴らしいのは繊細なやさしさが感じられることです。その勢い込むことなく柔軟に、滑らかに動かす強弱と伸縮のマナーはフレンチであることを意識させるとも言えますが、気負わず自らの呼吸で、自在に浮き沈みの抑揚を与えています。ベートーヴェンの「新約聖書」も素晴らしかったです。シューベルトの歌謡的な曲ではそのやさしさをもってしっかりと歌わせていました。このバッハは大曲であり、シューベルトのようにはやりませんが、静かなパートではやはり他では味わえない初々しい歌を披露し、気負いはないようです。同じフランスでモダンなアプローチのケラスと比べても、あそこまで頑張って色々な手法を見せるところまでは行きません。素直さが基本にあるようです。 出だしの曲では速く流して行く現代的でストレートな演奏となっており、それでいて要所で粘らせるしっかりとしたアゴーギクを施しています。その様子はさほど速くはない二曲目のクーラントでも同様で、余裕をもって立ち止まりかけるようなリズムのある、弾力的で柔軟な揺らしとなっています。ピリオド奏法を消化してスムーズだけどしっかりとした表現にしており、自発的な延び縮みに聞こえるのです。サラバンドなどのゆったりしたパートもやはり感触としてはさらっとしており、他では味わえない初々しい歌心を披露しています。気負いがなく、耽溺することのない心地良い落ち着きがあって、この辺はケラスにも似て今っぽい感覚と言えるでしょう。 ただ、一曲目のように速めのテンポ設定の曲は他にも結構あり、全体に素早く流れて行ってしまうように聞こえる人もいるかもしれません。あるいは、ただ棒のようにはやらずにフランス的ともとれるアクセントを施しているところを捻りや崩しと捉える場合もあるでしょうか。いずれにしても、ごつんと来る演奏をお求めの方にはお薦めとは言えないかもしれません。でもごつんと来るところもあるのです。第3番のプレリュードは他のどれとも違ってうなってしまいました。正にバッハにしか書けない曲だけど、目の覚める素早い揺らぎの中を進み、後半を速いテンポのまま一気呵成に行きます。その熱を帯びて展開されて行く迫力に圧倒されたのです。テル・リンデン旧盤のゆったりな癒しとは違う魅力です。ヨーヨー・マ最新の力の抜けた軽さとも違います。個人的にはその二人をベストと言いました。でもそれらに加えてこのガスティネルも、チェロ組曲一番のパフォーマンスとして良いのではないかと感じます。トータルでは、瑞々しさとずっと聞いていたくなる波長に満たされているものです。
2007年のナイーヴの録音です。これも派手ではないけどスムーズで気持ちの良い優秀録音です。楽器は1690年製のミラノのカルロ・ジュゼッペ・テストーレです。やわらかく響くチェロで子音がきつくなりません。したがって艶も出過ぎず輝き過ぎず、また朗々と鳴り過ぎずであり、やや淡白な感触ながら、その飾らないところが演奏に合っています。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Ophélie Gaillard (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 オフェリー・ガイヤール(チェロ)♥ 1974年パリ生まれのチェロ奏者です。バロック・チェロということで、古楽器演奏の範疇に入ります。日本語解説付きの盤が出ていて日本でも人気があるみたいであり、音楽雑誌でどう扱われたのかは知らないけれども販売サイトへの書き込みが多数見られます。これぞ待っていたバッハ、という感じです。同じフランスの女性チェリスト、アンヌ・ガスティネルや、アメリカの古楽奏者、ターニャ・トムキンスあたりと比べられるかもしれません。
リラックスして自分らしい表現を出している、大変表現意欲に満ちた演奏です。ピリオド奏法の呼吸はマスターしており、自由に使いこなしています。この運動初期によくあったような学究的態度ではなく、そこにプラスして言うべきものを持っており、その形式的な締め付けから逃れて余白を獲得していると言えるでしょう。
具体的には、フレーズごとに表情を変えたりして自在な運びです。雰囲気の上では何気なく感じさせながらも、かなり抑揚が豊かなのです。部分的にスタッカートを混ぜたり(主に楽句の後半部分)しますが、満遍なくはやらず、前のめりの攻撃的な姿勢ではありません。スキップするような遊びの感覚であって、この人の歌と乗りになっています。引きずる重さもなく、装飾音を自然に加え、繊細さが感じられます。力の抜きの表現がまた、大変良いと思います。全体に押して来る感じがしなくて、力んで大作をぶつけるようなバッハにならないところが魅力的なのです。
サラバンド等の静かでゆったりした部分では、音を所々で切るなどして、べたっと歌わないのはやはり古楽器の人という感じはします。ただ、かなり表情をつけてたっぷり行っており、そういうパートでもスタッカートを混ぜたり、テンポを揺らしたりして饒舌です。一見逆に思えるそのリラックスぶりと凝った表情の組み合わせは、あるいはバッハの時代の即興とも言えるのかもしれないけど、やっぱり今の人だな、という感じがします。
ガスティネルと比べるなら、ガスティネルの方が表情はもっと素直であり、ガイヤールはやり手という印象です。トムキンスとだと、彼女も非常に表情がありますが、もっとゆったりした雰囲気であり、強弱の点ではしっかりあるけど時間的な揺らしやスタッカートなどのアクセントの面ではやはりもう少し素直に感じます。ガイヤールは作為的な感じまではしないにせよ、はっきりとこの人のバッハになっているところがあり、その独特のバラエティ豊かな表情を自然の範囲として是認するかどうかで好みが分かれるかもしれません。
仏 Aparte の2010年録音です。自然で滑らかな楽器の音が大変良好な録音です。楽器はマッテオの息子、フランチェスコ・ゴフリラーの1737年製だそうで、以前の録音は別の楽器だったようです。ピッコロ・チェロについてはフランドルの作者不明のものとのことです。
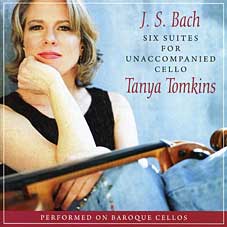 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello)
Tanya Tomkins (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ターニャ・トムキンス(チェロ)♥ ターニャ・トムキンスはアメリカのチェロ奏者で、アンナー・ビルスマに師事し、古楽器による演奏を行っています。現代の女性ということで生年などは発表されていませんが、大学を出てからビルスマに習うために1987年にオランダへ移り住み、十四年間そこにいたということで、モダン楽器も使って印象派の録音なども残しているものの、古楽器によるこの2010年のバッハが彼女の代表作と言えるでしょう。
演奏マナーはゆったりしており、必ずしもピリオド奏法の癖のある演奏とは言えません。女性的と言うと性差別のようですから言い直すなら、他との差を見せようとする種類の攻撃性がなく、よく歌って繊細な抑揚があり、落ち着いていて大らかな包容力を感じさせるものです。このページで一番好きな演奏の一つとして取り上げているヤープ・テル・リンデンのハルモニア・ムンディ盤とも幾分似た癒しの波長があると言えるでしょうか。違いとしては、こちらの方が全体によりゆっくりしている感じであり、途中ですっと弱めるなどの強弱の扱いに工夫があって、抑揚表現の揺れが大きめだということです。アゴーギク(時間的な延び縮み)の面ではあまり癖はない方ながら、フレーズの途中で少し大きな間を空けたりはあります。もう少し節の凹凸が少ない方が好みではあるけど、駈け出したりはしませんし、スタッカートや装飾などの工夫も特にやって来る感じではありません。語尾を短く切るピリオド奏法の癖もありません。伸びのびして気持ちの良いものです。
一つ個人的に気になるところを挙げるならば、サラバンドなどの遅い曲において、ロマンティックに耽溺する感覚とまでは言わないものの、ずいぶんたっぷりやっている部分があることです。もちろんあくまでも好みの問題です。特に5番、6番のサラバンドは大変ゆったり歌わせています。深みがあるとも言えるでしょうか。そして面白いのは、6番のサラバンドですが、後半でまるでオリジナル曲かと思わせるほどの即興を見せています。熱を帯びてどんどん追い込まれて行く展開部が魅力的な、あの「シャコンヌ」のような曲にしたかったようです。
オフェリー・ガイヤールと比べるなら、より落ち着いており、技を見せようという意図を隠しているようには聞こえません。この人の天然の性質だと思います。巧者な印象にならないのです。そこが聞いていて安らげるところでもあり、正直で気持ち良く感じます。ピリオド楽器であるバロック・チェロによる音色がよくて、ピリオド奏法的にせかせかしない最近の録音をお探しならこれかもしれません。
2010年録音の Avie Records です。繊細な倍音を捉えていて胴もよく響き、リラックスできる音です。残響も感じられて優秀な録音です。使用楽器はロンドンのロッキー・ヒル1798年製ということで、モダン改造はされていないバロック仕様です。6番についてはゴフリラーの1699年の五弦のもののレプリカで、1985年のドミニク・ズコヴィッツ製と記されています。
 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) David Geringas (vc) ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ダヴィド・ゲリンガス(チェロ)♥ 1946年旧ソビエトのリトアニア生まれで現在ドイツ国籍のチェリストです。ユダヤ系です。ロストロポーヴィチに師事しました。一般にはスケールの大きな演奏をすると言われることがあるようです。世評通りかどうかはぜひ聞いていただきたいですが、活きいきはきはきとして切れのある演奏に感じました。モダンながら何気ないのではなく、力も見せるというのか。楽器教育の面でも知られた人ということです。ベートーヴェンのソナタは見事でした。 軽く動いてためや沈みをしっかりと出し、アクセントを結構つけます。ピリオド奏法の動かし方に近いと思います。でも恣意的なとって付け感はなく、自由を感じさせます。上記のガスティネルより動かす幅は大きく、思い切りが良い印象です。歯切れの良い明晰なフレージングは技術的な上手さを感じさせます。弾ませるようにややスタッカート気味に聞こえる処理のパートもあります。モダンにさらっと流す感覚やリラックスした雰囲気よりも、鮮烈さが前に出るのです。一曲目の出だしなどは大変スピーディに聞こえます。短調のゆったりした曲でもガスティネル同様に暗く沈み込まず、それでいて深々とした感じは出ています。世代的には大分上だけど、モダンな感覚を身につけているようです。熱の入ったバッハです。 2011年の録音です。レーベルは C2ハンブルク(Es-Dur)です。多少前に出るところのある、楽器を生かす明晰な録音です。チェロは繊細で少し細めの艶が上に乗るような音で、響きは朗々としています。明るめで、くっきりとした輪郭の立ちと弾力のバランスが良く、気持ちの良い音です。1761年製のジョバンニ・バッティスタ・グァダニーニです。 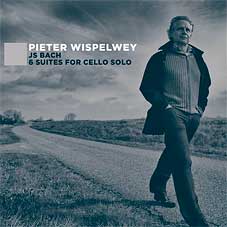 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Peter Wispelway (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ピーター・ウィスペルウェイ(チェロ) ウィスペルウェイのベートーヴェンのソナタも感銘を受けました。ずい分表現意識の高い演奏だと思ったけど、このバッハの大作においてはもっと気合いが入っているかもしれません。技のデパートと言ったケラス以上に頑張って表情に工夫をしているように聞こえ、そう呼ばれることがあるという「修辞学のマスター」の本領発揮だと思いました。 1962年生まれのオランダのチェロ奏者です。アムステルダム在住で習ったのはアンナー・ビルスマでした。オランダ音楽賞をチェロで最初に受賞した経歴があり、注目されています。 実に鮮やかです。上記ゲリンガス同様にはきはきしていて振り幅が大きく、第一曲の始まりなど、かなり速い上に癖をつけているように聞こえます。所々で弱音に飲み込ませるような表情のコントラストもあります。やはり新しい世代だけあって、ピリオド奏法を自分のものにしているのでしょう。人によっては多少せかせかしてるように聞こえる場合もあるかもしれません。それは新しい世代というよりも、ビルスマに習ったので当然と言えば当然でしょうか。ロングトーンで山なりに音圧の変化が聞かれるメッサ・ディ・ヴォーチェ様のボウイングもあるし、ビブラートもかけない音が目立ちます。フランスのケラス以上に表情が大きいと言いましたが、それを恣意的と取るか可能性の追求として賛美するかは人それぞれだろうと思います。そしてケラスやゲリンガスと同様に技術の高さを印象づけるところがあります。メリハリのある演奏をお求めの場合はこれでしょう。5番のアルマンドでも鋭さがあるし、サラバンドでもスタッカートを用いる箇所があったりして、全てに工夫があって鮮やかです。 レーベルはベルギーのイーヴィル・ペンギン・レコーズで、2012年の録音です。チェロは ピーテル・ロンバウツ1710年製です。基音も豊かだし、輪郭もくっきりとしています。良好な録音です。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Matt Haimovitz (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 マット・ハイモヴィッツ(チェロ) 1970年イスラエル生まれで、イスラエル・フィルのソロイストとして活躍し、ハーバード卒という輝かしい経歴のチェリストです。レナード・ローズやヨーヨー・マに師事しました。ウィスペルウェイが出たところで丁度良い登場でしょうか、そのウィスペルウェイよりもさらに表情が濃い感じもするような、様々な趣向を盛り込んでやれることを全部やったようなパフォーマンスです。ユダヤ系の才能ある人には時折、このように洗練の方向とは違うけれどもしっかり感のある有能な人が出て来るようです。ウィスペルウェイで表情過多に感じるならこれは無理かもしれないけど、逆にここまで味が濃い方が好みという方もいらっしゃると思います。 ウィスペルウェイ同様にくっきりとしたイントネーションで時間軸の延び縮みが大きく、走ったり立ち止まったりの運びです。強弱軸でもしっかりとしたアクセントを施しますが、見分けるとするならウィスペルウェイの方がよりピリオド奏法的な印象が強いでしょうか。こちらはそれを土台としつつ、もっと自由に表情をつけて行った感じです。時折装飾も入れ、フレーズの語尾の音で消え入るような効果も加えたりします。テンポ設定に関しては、速いパートでは必ずしも最高速とは言えないけどかなり飛ばし、それでいてアクセントが施されています。反対に5番、6番のサラバンドなど、ゆっくりな楽章では大きく間をとってゆったりと進め、泣きとまでは言いませんが、情緒を込めて最大限にたっぷりとやってくれます。 ペンタトーンの2015年収録です。華やかな音ではないけど、使っている楽器の音色はよく捉えているのであろう良好な録音です。その楽器は1710年のマッテオ・ゴフリラーです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Yo-Yo Ma (vc) 1983 ♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヨーヨー・マ(チェロ)1983 ♥ 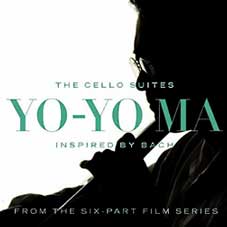 Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Yo-Yo Ma (vc) 1998 ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヨーヨー・マ(チェロ)1998 ♥♥  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Yo-Yo Ma (vc) 2018 ♥♥ バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヨーヨー・マ(チェロ)2018 ♥♥ 同時多発テロの追悼式典でも演奏した中国系アメリカ人のヨーヨー・マは、生まれてから七歳までをパリで過ごし、その後はニューヨークで生きて来た人です。ユダヤ系ではないのに自らの神童ぶりを発揮して有名になり、アメリカではその人格も含めて大変高く評価されています。チェロ組曲は83年と98年、そして2018年の三回録音しています。 1983年盤 最初の83年盤(85年度グラミー賞受賞。因みに彼は19回グラミー賞を受けています)は飾り気のない真っ直ぐな演奏で、テンポも総じてすっきり速めな部分が多いですが、表情の大きな他の名演の中にあって、その飾らない清々しさが魅力でもありました。それでいて4番のサラバンドと次のブーレの二番目にかけてなど、大きくゆったりと歌ったりしています。二十代の録音ですが、感受性の高さと器の大きさを感じさせる堂々としたものです。直球勝負、という感じです。 1998年盤 98年盤の方も気取らず軽やかな部分は旧盤と同じ傾向にありますが、ここでの彼は誰に気兼ねすることもなく、まったく恐れずに自らの感覚に従って歌っています。世に出るにあたってカザルスにはバーンスタインにつないでもらったりしたし、この曲集を世界に再認識させた演奏を理想としているとも発言しているようですが、そのカザルスのように押して来ることはなく、一つひとつの音をじっくり存分に味わっているようです。遅い部分での表情はどの演奏よりもしっとりとした趣きがあります。弾む音の間に自在にテヌートを挟み、湧き出るように強くなり、また深く沈潜して好きなだけ間を取ります。そしてそんなに表情があるのに気負いはなく、あくまでも自然に感じるところはとっくにカザルスを超えてますよ、と褒めたくなります。旧盤より力んでいるなどという評を書く人もいますが、自分には全然そんな風には聞こえませんでした。すべてが内側の声に従っているようで、真っ直ぐだった青年が様々な出来事を経て成熟し、よりその人らしさを出して来たような変化だと言っていいのではないでしょうか。嘘のない共感能力はこの人の性質でしょう。胸が熱くなるときがあります。 そしてこの演奏の最も素晴らしいところは、楽しい気分になるところです。一番好きな演奏と述べたヤープ・テル・リンデンの演奏と比べても、質が違うので正直甲乙つけ難いです。競技ではないですが、このヨーヨー・マを超える、と言える演奏はそうそうないのではないかと思います。 音はやわらかく繊細で、モダン・チェロの美点を余すところなく伝えています。コープマンから古楽を学び、いくつかの曲ではバロック調律でバロック・ボウ(弓)も使っているようです。高音でも朗々と響くところは開放弦のようであり、フレットが刻まれてないのにこれだけの音が出るというのは驚きです。 2018年盤 とうとうヨーヨー・マが2018(録音は17)年になって三度目の録音を出して来ました。二度目の98年盤も見事だったのに、もうそんなに月日が流れたようです。最初にこの記事を書いた後のことですので、今回新たに感想を加えることにします。 初回がデビュー後まだ三年ほどでの演奏だった83(録音は82)年、二回目が98(録音は94〜97)年で、1955年の10月生まれですから、それぞれ二十七、四十二歳の頃、そして今回は六十二歳のときの録音ということになり、二十代、四十代、そしてそれからきっかり二十年を経て再挑戦した成果ということになります。三度目の正直ではなく、全てが素晴らしかったので是非それぞれを聞き比べてみていただきたいですが、タイトルも今回は「エヴォリューションズ (進化)」。年輪を重ねたことが窺えます。
元々マにとってはこのチェロ組曲、上で触れた通り、困難なときに慰め、また励ましてくれ、人生と共にあったとご本人も言う縁の深い曲集で、音楽が聴衆に与える影響という意味でも大変大きいと考えているようです。三歳の頃にヴァイオリンより大きな楽器がやりたいと言って四歳で本格的にチェロを始め、ちゃんとした先生につくまでの間父親に二小説ずつ初めて教わっていたのがこのバッハの組曲であり、そして六歳のときの発表会で聴衆をうならせたのもその第三番でした。最初一部分だけの予定だったのに本人が全曲弾きたいと言い張り、長過ぎるからだめだと告げられると、拍手があったら次の部分に進んでもいいかと聞いて約束を取り付け、結局全部弾いて熱烈な「ブラボー」の叫びを巻き起こしたといいます。 それではこの三度目の組曲の録音、前回の二度目においてもすでに他に並ぶものがないほど魅力的だったけれども、いったいどんな風に仕上がってるでしょうか。 演奏の本質を速度で表せるわけでないのは当然ながら、便宜的に1番から6番までの第1曲目の実測タイムを比較してみます。三つの録音のうち中間のタイムになるものを0、あるいは二つが同じタイムの場合はそれを0として+ーの秒で表してみますと、0, -10, 0/-12, +48, 0/-1, 0, 0/0, -27, +3/-18, 0, 0/-24, 0, +8 となります。このうちこの一曲目が元来スローな曲調のものは第2番と第5番です。 ここから絶対的な傾向を読むことはできないにせよ、概ね二度目の録音のときが最も速度の振幅が大きい傾向にあるようです。速い曲は速く、スローな曲はたっぷりしているということです(といっても上記の通り、十分に自然でした)。つまり二度目は抑揚表現の幅が大きく、それと比べると最初のはさらっと速く流しつつ、あまり大きな表情をつけない傾向。カザルスとは違うやり方を模索していたと言っているようです。一方最新録音ではテンポ設定では両者の中間ぐらいが多いものの、最初のに似てさらっと流す場合でもそれよりは表情があります。そしてテンポ設定を変えることなどによるゼスチャーはむしろ二度目より控えめになり、遅い曲では前回よりもたっぷりさせずに進めるところもあるのですが、強めるのも弱めるのも自由に躊躇なく動くので、表現としては迷いがなく大胆であり、またそうであるがゆえの自然な印象があります。余分なフィルターが取れてダイレクトになった分、湧き上がる情感にありのままという感じでしょうか。 つまり、より軽やかになると同時に、質的な意味で同じように表情豊かであり、情緒的にも同様に深みがある印象です。この曲集を世に広めた権威である往年のカザルスなどと比べても、あの、時折現れる剛毅さと粘りのある濃い歌い回しではなく、時代もあるかとは思いますがより洗練されていて何気なくなっている一方、さりげなく深く感情に入り込んで来るのです。バッハのチェロ組曲のパフォーマンスとして、二度目共々、間違いなくベストの一つだと思います。肩に力が入っているわけではないけど最も真剣度が高くて起伏があり、緩やかなマイナースケールの歌も深々としている二度目、気負いが抜け、場所によっては鼻歌が出そうなほどの乗りの良さを聞かせて楽しんでおり、枯れて自由になった三度目。甲乙つけ難いですが、どちらが好みでしょうか。 この人も使用楽器がよくよく表記されていないことが多いです。持っているのはジャクリーヌ・デュ・プレが使っていた1712年製のストラディヴァリウス「ダヴィドフ」か1733年製のモンタニャーナなのですが、ここでどちらが使われているかは分かりません。分かる方は教えていただきたいと思います。2019年のブルーレイ映像のものはダヴィドフだったようで、バロックの曲はこちらを使いことが多いようなのですが。レーベルは三つの録音ともにソニー・クラシカルです。 二度目は収録時のバランス的にもたっぷりとして深々と響き、三度目はよりさらっとして滑らかという違いはありますが、初回も含めてどれも大変良いコンディションです。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Micros Perenyi (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ミクローシュ・ペレーニ(チェロ) ミクローシュ・ペレーニというチェリストは1948年ブダペスト生まれのハンガリー人で、カザルス国際チェロ・コンクールで賞を取り、カザルスに師事しました。日本では「飾らない本物」として非常に高く評価する人がいます。この2019年、七十一歳時のバッハの録音は1981年に次いで二度目で、2006年にも別音源が DVD 化されているようではあるものの、古い方はどちらも入手困難です。 さて、論評に困りました。どう扱ったらいいでしょうか。ちょっと日本の演奏者を思わせるような真っ直ぐ感、音節の素直さがあります。1番の出だしは必ずしも速いテンポとも言えないけど多少さらっとした運びで、確かに飾りがないと表現できるようなものであり、非常に丁寧でスムーズな演奏です。ためはありません。強いアクセントもありません。無味乾燥でつまらないと評する人と、高く評価する人に分かれるのはそんなあり方が原因でしょう。面白くないとする側であっても、6番だけは味があると販売サイトのレビューに書いている人もいましたが、確かに言わんとすることは分かる気もします。でもこのページは評価のページではないので、とりあえず保留ということにしてもよいでしょうか。 ではどういう意味で日本の演奏者を思わせたかという話ですが、以前から日本とお隣韓国のクラシックの演奏家は平べったくて丁寧な音節になるか、演歌のような泣きの情緒をたっぷり聞かせるかのどちらかになる、特に日本は丁寧で真っ直ぐの側、楽譜に書いてある通りに真面目に聞かせる場合が多い気がすると言って来たわけですが、これは画一教育のせいとか、騎馬民族と農耕民族の違いというよりも、案外言語構造から来ているのかもしれません。 そもそも本当に言語の違いが音楽表現の違いになるかということを真剣に検討すれば、それは大層難しい話です。言葉と音楽が脳の同じ部位によって処理されているのかどうかは長らく議論されて来ており、脳神経生理学者たちの間でも同じ脳のシステムを使うとする人と、司る場所が異なり、別の神経回路があると言う人とに分かれます。最近は fMRI という装置で脳のどこが活性化するか見るのですが、関連する部位としては、まず側頭葉の聴覚野で音を捉え、その内側の扁桃体で快・不快としてブーストされ、側坐核、前帯状皮質(帯状回)などと協働して感情としての体を成しつつ(喜怒哀楽の種類によって微妙に異なります)、海馬で記憶との参照がされ、前頭前野(前頭葉)で文や音楽の規則パターンに反応するとともに情動への抑制が加わって一続きの体験となる、これがアウトラインのようです。その際、聴覚野は言語と音楽の両方で働くものの、話し声と音楽を処理するエリアが分かれているという説があって、しかも歌詞のある歌の場合には領域が重なるのだとか。そういえば音楽といっても歌ものばかりを好む人と、器楽を好む人とは分かれるという話も読んだ気がします。知能と関係づける研究もあって差別的な感じもしますが。そして歌う側でもまるで言葉を喋ってるように歌うボブ・ディランやジョルジュ・ブラッサンス、アバや美空ひばりみたいな歌手がいるかと思えば、歌詞は聞き取り難く、音程や強弱が正確にコントロールされて流れる音のように歌う人もいます。もし言葉と音楽のチャンネルが重なるというのなら、器楽でもドイツの演奏家はよくよく総統の演説のようにエッジが立ち、フランス人は伝統的に滑らかに波打つフレーズで誘惑しようとする事態に納得が行くことになります。 その点で行くと日本語はどうなのでしょう。言葉の分類として言えることは、英語やドイツ語のようなストレス言語、「強勢拍リズム」の言語ではありません。厳密にはフランス語、スペイン語、中国語のような「音節拍リズム」の言語でもなく、その下位区分で半独立している「モーラ拍リズム」と呼ばれる分類に入ります。音節拍リズムは強勢拍とは違って全ての音節が等しい長さになりますが、その中でもモーラ拍は音節というよりもむしろ一定の拍でリズムを刻み続けるものです。結果的にどの音もべたっと等しく発音する丁寧な運びとなります。英語のように a や of が消えて聞こえないというような事態は起こらず、全ての音を洩らさず几帳面に発音して行くのです。日本人は長い間英語を勉強していても、ザ、ドアーズ、オン、ザ、ライト、サイド、ウィル、オープン、と大抵は日本語英語的な発音から抜け出せないけれども、それはこうした拍の構造の違いから来るのかもしれません。頑張ってみても母音が皆 æ に寄って猫が鳴くように聞こえたり、全部 r 発音のようになってしまったりします。ネイティブに近いイントネーションで喋れる人の多くは子どもの頃に海外にいた、あるいは大人になってからも一定期間以上生活したり現地の恋人を持ったりした経験がある人が多いけど、稀には日本から出ずにひたすらネイティブの発音を聞いてシャドーイングする努力によってほぼ習得できる人もいるようです。これは音楽の演奏表現でも同じことが言えるでしょうか。テルマエ・ロマエじゃないけど、日本の演奏家は英語でフラット・フェースと揶揄される平たい顔族となり、どこかのっぺりとした演奏になりがちかもしれません。ストレスがないというか、全部にあるというのか。リズム変化をつけた強弱が苦手なようです。一方でリズム主体の音楽ならジャズなので、ジャズの演奏者ならそんな事態にはならない気もします。でも海外での評価も高い超絶技巧のピアニストの方に(ビルボードで圧倒的順位を誇りました)、複雑な拍子を引き分けるし強弱もあるけど、強いときは全部発音してオフがなく、いつでも全力に聞こえる人もいます。あれはまた違う理由でしょうか。 それでは、ハンガリー語は日本語に似ているでしょうか。苗字と名前の順序は同じです。分類的にはウラル語族、フィン・ウゴル語派のハンガリー語ということになります。この言語は厳密に言えば強勢拍でも音節拍でもモーラ拍でもないようですが、アクセントが必ず一番初めの音節に置かれ、そのアクセントによって長さは変わらず、延ばすかどうかは基本的な発音のルールによって規定されているということです。そうなると音的には英語よりは日本語に近いでしょう(喋っている音を聞いてみてください)。 そういう理由からも日本ではこのペレーニの演奏を高く評価する人が多い、のかもしれません。技術が高くないと無理でしょうが、きっちりと平らに揃えた音に差別がなく、真面目な印象です。ならばハンガリー人の演奏は皆そうかというとそれはまた違っており、そんなことは意識させない人も多くいます(指揮者のオーマンディは平たいにせよ、上記のシュタルケルやオンツァイなどは必ずしも似ているとは言えないし、ピアノのシフのリズムは立体的です)。ただ、派手なアクセントはやはり付けず、東欧系に共通してもいるけど、音楽に真面目に取り組んでいるように聞こえることは多いのではないでしょうか。 言語の特徴がそうしたハンガリーの音楽のあり方にも影響を与えていると言う学者はいるし、マジャール人の心の調べを奏でる楽器はチェロだという人もいます。 なんだか検討違いな話へ長々と逸らしてお茶を濁してしまいましたが、この多くのファンから絶賛を受けるペレーニというチェロ奏者、是非聞いてみてください。フンガロトン・レーベルで2019年録音です。音色も少し渋く、真面目なものです。もちろん良い録音です。  Bach The 6 Cello Suites, BWV1007-1012 (for unaccompanied cello) Valentin Erben (vc) バッハ / (6つの無伴奏)チェロ組曲 BWV1007-1012 ヴァレンティン・エルベン(チェロ) ヴァレンティン・エルベンはアルバン・ベルク四重奏団で三十八年間チェロを務めました。1945年ウィーン生まれのオーストリア人です。有名なところではナヴァラに師事しました。ウィーン国際チェロ・コンペティションと(ARD)ミュンヘン国際音楽コンペティションで優勝しました。 ややテヌート気味の重さというか、多少もったりした感じの重みのあるフレージングで、落ち着いたテンポで始めます。切れの良いアルバン・ベルク四重奏団の人という先入観を持って聞くといくらか意外でしょうか。丸みがあり、気負いは感じません。アゴーギク方向(テンポの延び縮み)の動きは大きくありません。その意味で端正です。前出のミクローシュ・ペレーニほどじゃないけど飾らない、真面目な運びに聞こえます。その後もテンポ設定が異なるにしても、全体に印象は変わりません。淡々と進めて行きます。静かなサラバンドなどで、ことさら静かに抑えたりゆっくりにして引っ張ったりして深みのある雰囲気を出そうという作為もありません。抑揚が大き過ぎないのです。他の部分と同じように落ち着いて、曲のあるがままに任せる感覚というのでしょうか。渋いです。 チェロはわりとやわらかい響きで、目立った倍音が前へ出て来ることがありません。艶はほどほどだし、鋭いエッジを感じさせたりはせず、ボウイングで馬の尻尾が擦れるような基音以外の部分はさほど目立ちません。多少鼻にかかった音色というのでしょうか。オーストリアのパラディーノ・ミュージック・ レーベルで2020年の録音です。 |