|
サン=サーンスの白鳥の歌
オーボエ、クラリネット、バスーン・ソナタ op.166-168 取り上げる CD 9種 (枚): Calliope '75(ブールグ/ギャベ/アラール)/MDG '91(ゴリツキ/ローデンハウザー/イェンセン) /Cala '94(ダニエル/キャンベル/ゴフ)/Hyperíon '04/ナッシュ・アンサンブル)/Naxos '08(ハマン/サイクス/ミラー) /Indesens '10(ガテ/ベロー/トレネル)/Brilliant '14(ディ・ローザ/ノヴェッリ/ボッソーネ) /シュレンベルガー(オーボエ・ソナタ)/コリンズ(クラリネット・ソナタ)
CD 評はこちら(曲の解説を飛ばします) 「白鳥」について前回書きましたが、サン=サーンス(1835-1921)の白鳥の歌はこちら、という曲が実は別にあるので、今回はそれを取り上げることにします。この作曲家で最も有名なのが「白鳥」(「動物の謝肉祭」〜) や交響曲第3番 (「オルガン付き」) だとするならば、それらに負けず、あるいはそれ以上に魅力的なのがこちらの白鳥の歌かもしれません。知られている度合いという意味では、楽器の演奏者やかなりクラシックに突っ込んだ人だけの曲という感じはあるのですが、それではもったいない、心に響く作品です。何気ない曲ではあるけれど、あらゆる室内楽中の名曲としてもよいのではないでしょうか。白鳥の歌というもの自体、心奪われるところがあるためにこのページでは何度も取り上げて来ましたので、一部繰り返しの説明になりますが、 概略を見て行こうと思います。 曲の内訳 全部で三曲あります。ほぼ同時期に作曲されたオーボエ・ソナタ、クラリネット・ソナタ、 バスーン(仏語ではバソン=ファゴット)・ソナタです。それぞれ作品166、167、168となっていますが、いずれもこの作曲家の死の年、1921年に作られたもので、「滅多にソロ・パートが書かれない楽器のためにレパートリーを増やそう」という意図の下に着手された一連の作品の一部となっています。他にもコーラングレのソナタなどの計画もあったけど、その死によって断念され、三曲が残ったのです。最後のバスーン・ソナタは亡くなった地、アルジェで書かれたもので、旅行好きでもあったサン=サーンスは冬の寒さを避けて出かけていたところでした(1830から1962年までアルジェリアは自国フランス領)。そんなわけで、他にもいくつか断片的なものはあるけれども、この三つは事実上サン=サーンスの絶筆と言ってよい曲集ということになります。 白鳥の歌とは 「白鳥の歌」というのは、すでにご存知かとは思いますが、白鳥が死に際して一声鳴くという言い伝えがあったように、芸術家が生涯の最後に創作した作品のことです。そしてただ最後の作品一つにとどまらず、その時期に作られたものには固有の特徴が表れているため、そうした特徴のあり方自体も含め、いくつかの作品が「白鳥の歌」として人々に呼ばれることが多いです。亡くなったときの年齢には関係ありませんので、人生経験の積み重ねによるものではありません。では、音楽においてはそのあり方をどう表現したらよいのでしょう。 ざっくり言うと、多くの作曲家に認められる音の性質として、軽くて屈託がなく、深刻さやこだわりが消えて、ときに快活だったりします。あるいは、少し寂しさのように感じられるものが混じったりする場合もあるけれども、独特の静謐さの中に優美な叙情性が現れたりします。澱を落として鮮やかに、言葉の矛盾かもしれないけど「生きいきとしたやすらぎ」とでも言えるものです。それは一言で「諦観」などとも表現されますが、つまり曲のスピードにかかわらず、何か手放したような、えも言われぬ透明感があるのです。 他の作曲家の白鳥の歌 我々の生の要件にかかわる美として、こうした曲たちは芸術の芸術たる所以でしょう。サン=サーンス以外でも、魅力的な白鳥の歌を聞かせた作曲家は他にも多くいます。 バッハなどは若いときから傑作が目白押しなので、「音楽の捧げ物」やロ短調ミサなどが事実上総決算かもしれませんが、晩年の作品群ばかりに特徴的な高まりが見られるとは必ずしも言えないし、ハイドンも情感の深まりという意味では三十代半ばから四十代ぐらいの「疾風怒涛」期の評価が高かったりするのものの、モーツァルトには K.595の最後のピアノ協奏曲と K.590の弦楽四重奏曲、クラリネットの協奏曲と五重奏曲、ピアノ・ソナタの K.570, 576 などがあります(「モーツァルトの白鳥の歌」)。ベートーヴェンはこれもミサ・ソレムニスのベネディクトゥスやピアノ・ソナタ第32番の第二楽章、弦楽四重奏 op.132 の第三楽章や op.131 などですでにその光を放っているかもしれないけど、その四重奏最後の op.135(16番/「日本人だけが知らない名演奏」)が知られます。シューベルトにはクラリネットが伴奏する歌曲「岩の上の羊飼い」があり、ブラームスもクラリネットの作品群(五重奏と三重奏、二つのソナタ)に間奏曲、そしてR・シュトラウスは「四つの最後の歌」が有名です。こうして見ると、作曲家の晩年の作品に高い確率でクラリネットが登場するのは面白いです。 どういうことが起こっているのか ではこうした白鳥の歌の特徴的な情緒的性質はどこから来るのでしょうか。情緒の起源と言ったって、音楽は思考ではないので、もちろんそれは理屈で証明はできません。無調の現代音楽なら思考によって作られるけれども、その規則に緩みのある作品にのみ情緒的性質が残るわけです。したがって白鳥の歌の透明度といえどもあくまで主観の問題であって、肌で感じる感覚の話に限ってその理由を想像してみるに過ぎません。 死期が近づいた人間に起きる出来事については、芸術家に限らず色々と言われます。自分の死ぬ日を事前に正確に予言したり、すでに亡くなっている親しい人や家族と会っているかのようにベッドサイドで話したりする人のことはよく報告されています。この話も前に書いてしまいました。そういう摩訶不思議なことはいったん横へ置くにしても、今まで意地悪だったり気難しかった人が性格が変わったように穏やかで欲がなくなり、やさしくなったりします。身近でどなたかの経験がある方は分かるかと思いますが、クリスマス・キャロルのスクルージ爺さんとは多少違い、その人を通してまるで向こう側が透けて見えるかのようになると言えばよいでしょうか。これは恐らく、その性質を先取りすることで、本人が向こう側の世界へ旅立つ準備をしているのでしょう。まだ幼さの残る子どもが不治の病で亡くなる場合にも見られることから、その人がその生で学んだ内容とは関わりがありません。半自動的な機制とでもいうのか、まるで急に発つと適応できず、すぐ帰って来てしまうか迷うかするということでもあるかのようです。これは宗教の教説ではないけど全くもって非唯物的な話なので、「向こう側の世界」だなどといっても納得しない人は一笑に付していただいて構わないわけですが、だから芸術作品と同様、死出の準備によってその人自体が透明になって行くように感じるのでしょう。 では、準備の内訳は何でしょうか。まず、形のない世界には形あるものは持って行けないので、欲というものがなくなります。預金残高やスパニッシュ・コロニアル様式の家、領土、コーチビルダーの自動車やジュネーヴの手作り時計に宝石、ハイファイ装置などが彼岸に「転送 transfer!」できないのはもちろんです(あの、スタートレックです。古くてすみません)。しかし置いて行くものはそれだけではありません。物に限らず「私の」 と付くものは全てである可能性があります。名前、役割、自分の属性だと思っていたもの: 力のある、アッパークラス生まれの、その世界で有名な、優れたスコアや指数を獲得した自分。理解力があり、美しい顔立ちの愛らしい性質で、あるいは何かの長や相談役であること、マルチリンガルの、たくさん、もしくは珍しことを知っていること(調べればすぐに分かるサン=サーンスの知る人ぞ知る室内楽がどうだとか?)が誇らしい自分といったこと。あるいは父親や妻としての私など、もっと何気ないものでもそうですが。国別対抗でシュートが決まっても、もはや歓声に加わりません。あらゆる種類の所属意識とアイデンティティが指の間からぼろぼろと零れ落ちて行きます。つまり、自我は持って行けないのでしょう。人と違うことを自他に認めさせるのが自我の生業ですから、自分と 他者を比べて自分の側を大きくする、もしくはユニークに見せようとする欲求は止み、その曇りで見えなかったものがすっかり見透せるようになります。 こうした心の変化は誰にでも訪れるわけではないでしょう。そして死の直前のこともあれば、大分前からの場合もあります。直前になって時が来たことを知り、あらたまって家族に別れの挨拶をする人は比較的珍しくないと言えます。芸術家は論理ではなく直感で仕事をする能力が高いので、本人が無意識である場合もあるにせよ、一般の人よりも時間的に前から特有の境地が現れる頻度は高いかもしれません。少なくとも作品に結晶することはより多いはずです。厳密に言えば、白鳥の歌の現実の作品は愛おしむ人や出来事を振り返り、手放すことへの一抹の寂しさが漂うというか、愛惜の念を超えてはいない部分も少し混じった形で出来上がっているようです。 意外だったサン=サーンス それでは、サン=サーンスが晩年になってそんな白鳥の歌の周波数を響かせるようになったということは、いかにもか意外か、どちらでしょうか。意外だ、などと言うと、いったいこの人の何を知ってたつもりなのか、ということになってしまいますが、なんかちょっと感慨深いところはあります(サン=サーンスの人となりについては「交響曲第3番」の解説を参照してください)。なぜなら、確かにきれいなメロディーもいくつかはあったのです。もっと見直されるべきだと名が挙がるような作品がどうかは分からないけど、「白鳥」以外にも二十歳の頃に作ったピアノ五重奏曲 op.14 のアンダンテや六十八歳時のチェロ・ソナタ第2番の第三楽章、いくつかのロマンスなどは素直に心を開いて聞きやすいものです。でも、それ以外はどうなんだろう。最初にこの作曲家の最も有名な曲に触れてから、その次ぐらいの作品群へと恐るおそる手を伸ばしてみたときにまず思ったのは、随分華々しい音響の部分がある人だな、ということでした。正直少し意欲が萎えたのでした。あくまでも主観だとお断りした上で誤解を恐れずに言うと、空元気とでもいうのか、幾分外面的で空虚な響きに思われ、饒舌で切れ目なく循環していささか騒々しいと感じたところがありました。どの曲がとも言わないけど、いわば中身の感情が抜け落ちたというのか、蓋をしたような感覚。どんな作曲家でも、誰もが認める名作と名作の間の曲にはそんな印象のもあったりするものだけど、このサン=サーンスの鳴り止まなさとちょっと似た波長はシューマンやメンデルスゾーン、リストの一部の曲でも感じたりします。メンデルスゾーンはともかく、これらはサン=サーンスが好んだ作曲家だという話は後から知りました(それは技法上の話かもしれないけど)。調べてみるとこのサン=サーンス本人、時代ごとにかなり毀誉褒貶のあった人で、軽んじられたり見直されたりが繰り返されて来たということです。辛辣な皮肉を言う本人の性格も災いしたのでしょうか。自分と同じように作品に空虚さを感じた評論家などもいたようで、また、楽曲の構成においては博識で、非常に形式にこだわる作曲家という意見もあります。そしてサン=サーンスのこうしたあり方の解釈として、どうも二つぐらいの見方が出来るように思います。 彼の側の理由 まず一つ目は前の記事で提案してみたもので、外向的(extrovert)性格だったという観点(「交響曲第3番」)です。ここではもう繰り返さないけど、これは単なる一つの見方です。本気にしないでください。そしてもう一つは、本人に何か心の傷があって、それを見ないようにして来たのではないか、ということです。もちろん無意識にです。これも過去に他の人の全く同じ意見があって驚きました。曲を作るにあたって、しんみりとした情緒的な曲調、感情を吐露するような運びに突っ込むと、自身の心の痛い部分にも触れないといけなくなる。痛みは避けたいのです。楽曲の形式をことさらに重んじるという話も実は同じ理由です。形式は思考で作るものであり、思考によって感情をブロックできるのです。超絶技巧の作品ばかり作ったり弾いたりする人も、この形式にうるさい人と同じ部分があるのかもしれません。繰り返しになりますが、外向的性格にしても心の傷を見ないふりをする説にしても、これらは相対的な見方であって、真実でも正解でもありません。 各曲の内訳 ところがこの白鳥の歌三曲については、直前までの作品と様子が異なるのです。これら三曲には飛び抜けて独特の情感が漂っており、幾分映画のようであるにしても、どの曲にも共通して透明な光が差しています。快活な速いパートの屈託のなさもそうだけれども、主にはメジャー・コードの静かな部分です。それまでぎゅっと握っていた手を緩めたような肯定の感覚があるのです。名前はソナタですが、三曲とも縛りから解放され、ソナタ形式でもありません。個々にちょっと見てみます。 オーボエ・ソナタニ長調 op.166 まずオーボエ・ソナタですが、最初はアンダンティーノ。ウェストミンスター(ビッグ・ベン)の鐘で始まると言われます。その鐘はあれです、日本の学校の始業/終業のチャイムの基。出だしの音型がそうなっているのです。そしてこの出だしからしてすでに、力の抜けた軽やかさと明るさが独特です。最初から夕映えのような気配もあります。 続く静かな第二楽章はたとえようもなく美しいです。全体はアレグレットとなっているものの、出だしはアド・リビトゥム(ad libitum/自由に)の指示がついています。ベルリオーズの羊飼いたちが吹き交わす笛に似ているでしょうか、午後の強い日差しを岩陰から眺めるかのように、オーボエがゆっくりとソロで歌って行きます。一つ歌う間を、一つの分散和音でピアノがバラバラーンと区切る構造です。最初は C のコードですが、その後は少し諦観を感じさせるセブンスが続きます。一瞬のマイナーの陰りも交え、具体的に言えば CM7, Dm7, CM7sus4, C7といった具合です(どれが根音か、根音とは何かの問題は置いて)。セブンスを使えばみな白鳥の歌になるというならジャズはみな白鳥の歌だけど、この複雑な和音と独り吹く笛の音が組み合わさり、独特の境地を聞かせます。中間部は軽快な9/8拍子でロバの隊列が行くように進み、最後にもう一度最初の「アド・リブ」の部分が戻って来て静かに終わります。 第三楽章はモルト・アレグロで、軽快で速いロンドです。 クラリネット・ソナタ変ホ長調 op.167 次に作ったのがクラリネット・ソナタ。三曲の中では最も知られているでしょうか。最初の楽章はアレグレットとなっていますが、これもオーボエ・ソナタと同様に比較的ゆったりで穏やかに始まります。ふくよかでやわらかいクラリネットの響きが慰めるように歌って行く調べはまさに白鳥の歌。どことなくセピア調にも聞こえる美しい響きです。中間部は短調になり、少し刺すような鋭さを覗かせます。しかしその短調も持続せず、一瞬光が差したりやすらいだり、めまぐるしく調が変わります。平安に至るまでの心の動きでしょうか。最後は静かに肯定するように締め括られます。 第二楽章は軽快で楽しげ。アレグロ・アニマート(生きいきと)指定のスケルツォです。おどけるというよりも、機嫌良く遊びます。 第三楽章こそ大変興味深いです。こだわりなく静かに流れる白鳥の歌にあって、ここは様子が違うのです。透明になる一歩前の浄化の段階でしょうか。ゆっくりなレントながら、最初から重く深刻なホ短調です。悲痛ともとれる、ぶつけるようなピアノが地獄の鐘のように鳴り、通常の旋律よりオクターブ低いクラリネットの唸りで始まります。それが悲劇的な状況を提示した後、ピアノのアルペジオに移行して再度定義し直されると、続いて静かなクラリネットの高い旋律が現れます。それはまるで、今まで目を背けていた悲しみに向き合って、ただあるがままの感情に任せるかのようです。力が抜け、息も絶えだえともとれるし、静かな反芻へ移ったようでもあります。大変美しく、胸が締め付けられる感じがします。ここの部分、サン=サーンスの曲を通じて最も高く評価する声もあるようです。そしてまたさらに静かなピアノのアルペジオが来て、オルゴールのように楽章が締め括られます。 これは自分への挽歌でしょう。作曲家自身が心の痛みに蓋をすることなく直視できるようになったのでしょうか。恐れずにありのままを見ること、自覚出来るようになることは、その問題を乗り越える最初の一歩です。こういうひたむきな美しさは、この作曲家のそれまでの作品にはあまりなかったように思います。以前とは違う、何かを越えた姿があります。 第四楽章はモルト・アレグロで、難しそうな速いパッセージが連続する楽章です。しかし最後はアレグレットの第一楽章に戻って来て、静かに終わります。 バスーン・ソナタト長調 op.168 締め括りはファゴット(日本ではこちらの言い方の方が一般的でしょうか)によるソナタです。オーボエのように高い音での目立ったメロディーラインが出せず、楽器の音自体がユーモラスでもあるので、澄んだ白鳥の歌に相応しくないのではと思うかもしれません。実際に曲の中では楽器の特性を活かし、驚くような低い音も出しています。でも逆にその楽器の人懐っこい音によって、この曲は他の二曲と比べてどこか懐しさ、名残惜しむような感じが強く出ていると思います。音楽学者のジャン・ガロワは「ユーモラスなタッチと同時に静けさに満ちた黙想を含み、活力と軽さ、透明性の手本である」と述べています。これは無知な者の独り言と思っていただきたいですが、ファゴットがソロで活躍する曲の中のベストの出来ではないかと感じています。ひなびたフレーズが印象に残ったのか、第三楽章のくだりが後々まで心の中で響き続けていたのに気づいたこともありました。 ピアノがきらきらと下降する最初の音の選び方からすでに秋の気配がします。途中速くなって喜びがこみ上げるところも、後半でまた穏やかな冒頭の部分に戻って来て満足げに終わるところも、紛れもなく人生最後の作品に相応しい透明感に溢れています。 第二楽章は鶏が鳴きながら歩くようなスケルツォです。面白くもあり、雑事に追われる日常を回想するようでもあります。終わりの方ではちょっと短調に足を踏み入れ、軽く冗談のように締め括られます。 そして見事な第三楽章です。牧歌的な慰めに満ちたモルト・アダージョは陽だまりでまどろむようであり、ありのままを肯定しているような心安さがあります。中間の静かになるところの夢みるような心地良さはどうでしょ うか。滴る雨粒のような静かなピアノのアルペジオに乗って回想に入りかけたのか、ただ雨を味わっているのか、一瞬の忘我の響きです。物事を距離を持って眺めているにしても、諦観というよりも拘泥しないような感覚。このバスーン・ソナタで最もきれいなところだと思います。 それから少しマイナー・スケールの翳りが出たり元気に動いたりした後、また最初の境地へ戻って来て安らぎま す。そして一瞬の感情の高まりが来て、驚きをともなってやや不協和とも言える位置関係にあるフォルテへとジャンプして上り詰めた後、静まります。そこからは短いけれどもアレグロ・モデラートに変わり、軽快な動きを出して楽しく締め括られます。 20世紀の音楽として 三曲の個々の構成を主観的にスケッチしてみました。驚きと喜びをもって知ったことですが、ここには人生の最後に到って傷を乗り越え、正直になったサン=サーンスの姿があるようです。白鳥の歌となったこれらの曲を聞かずして、この作曲家の奥底の心情を理解することは出来ないような気がします。子供の頃から才能を発揮して来た作曲家の、たくさんある曲の中でも最も心打たれる作品群でした。自らの感情に向き合うことで解放され、同時にお別れを告げることになったこのような曲たちは、前述の通り、1921年に作られました。同じく心に傷を負っていたシェーンベルクにより、感情要素を排除することで調性からの自由を獲得した十二音音楽が確立されようとしていた、まさにその年に作曲されたことになります。サン=サーンスは時代遅れの形式主義だと言わていましたが、別の意味で縛りからの自由に到達したと言えるでしょう。 CD 選びについて 比較的珍しい曲であるために出ている CD も少ないかと思いきや、多くはないもののそこそこはあります。種類としては、レーベル企画でこのサン=サーンスの白鳥の歌三つを全て揃えた盤と、それぞれの楽器の演奏家のアルバムという形で、クラリネットならクラリネット、オーボエならオーボエの曲集として他の作曲家の作品と一緒にしてあるものの二通りがあります。サン=サーンスに興味があるか、楽器に興味があるかということですから、今回は白鳥の歌を聞くために枚数をたくさん揃えなくても良い前者からいくつか選び、楽器演奏者の盤はほぼ概観するにとどめることとします。 それでは、出ている CD を見て行こうと思います。白鳥の歌三曲が一枚(一組)に網羅されているものからです。録音年代順です。フェイバリット・マーク♡についてはアルバム全体に対しての他、個々のオーボエ、クラリネット、ファゴットのソナタごとにも付すことにしました。楽器演奏者ではないので、タンギングがどうとか、同じ音を違う指遣いで出してるなど、技術的なことは分かりません。あくまでも聞いた感覚で感想を記します。  Saint-Saëns Les sonates pour instruments A vent Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Maurice Bourgue (ob) Maurice Gabai (cl) ♥ Maurice Allard (fg) Annie d’Arco (pf) サン=サーンス / 木管楽器のためのソナタ集 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 モーリス・ブールグ(オーボエ)/ モーリス・ギャベ(ギャバイ/クラリネット)♥ モーリス・アラール(ファゴット)/ アニー・ダルコ(ピアノ) 古くからの名盤というか、一部で高い評価を得ていたけど長らく廃盤になっており、後に再発されたけどまた廃盤になったというカリオペ原盤の木管楽器集です。販売サイトではまだ手に入らなくはないという状況のようでした。サブスクリプションのサイトにはあります。 これはモーリス・ブールグのオーボエが見事です。名手ハインツ・ホリガーと並んで呼吸の流れるような自然さ、自在な抑揚があるなとずっと思って来た人であり、外せません。ホリガーの方はこの曲をやってないようなので貴重です。1939年生まれのフランス人で、聞いた感じは大変違うけどピエルロに師事し、パリ管の首席でした。 クラリネットはベルギー人のモーリス・ギャベで、生年など詳しいことは分からないけど1955年にコンペティションで優勝し、パリ・オペラの首席を務めた人のようです。 バスーン(ファゴット)は1923年フランス生まれで2004年に亡くなったモーリス・アラール。指揮者のモントゥーとともにボストン・シンフォニーで活躍しました。ピアノのアニー・ダルコは1920年マルセイユ生まれで98年に亡くなった名手です。マルグリット・ロンに師事した人です。 オーボエ・ソナタ ♥♥ からです。ブールグのオーボエ、この曲ではさっぱりと軽快な方へという解釈のようです。テンポは最初の楽章からやや速めであり、滑らかにやり過ぎはしません。敢えて白鳥の歌という静けさを狙わないようでありながら、抑揚はさすがに自然で呼吸が見事です。盛り上げも圧巻であり、弱音もぐっと思い切って付けます。そしてそんな風に表情豊かながら、恣意的になりません。音色は細めの音ですが、艶があます。 出だしが牧歌的な第二楽章ではトリルの巻きが速く、一方でテンポは適度にゆったりです。ここも必要以上に静けさは狙わないようですが、面白いのは、ベルリオーズの幻想交響曲の「野の風景」同様、二本の笛が離れて吹き交わすように、繰り返しの部分で分けて後をぐっと静かにし、音色も変えるところです。技ありの解釈です。中間部は軽やかです。第三楽章は活気があってよく弾みます。 クラリネット・ソナタ ♥ は、ややための表情をつけたピアノに、割合しっかりとした輪郭で艶の感じられるクラリネットが乗って来る出だしです。これもオーボエ・ソナタの演奏同様に、自然だけどそこまで静けさが漂うという雰囲気ではありません。テンポは中庸で抑揚はしっかりあるけど比較的あっさりとしていて、スタッカート気味のところも交えてさらっとした軽快な運びです。 スケルツォの第二楽章はややゆったりめに、しかし力は抜いて行きます。ここも自然です。悲劇的な印象の第三楽章ですが、ピアノは強過ぎず、テンポはあまりゆっくりにしません。深刻さはなく、割合平常心であっさりとしています。弱音部は長いスラーにせず音を途切らせるようにして、力は抜くけれども弱め過ぎて息も絶えだえという感じではありません。やはり少しあっさりに聞こえます。したがって痛々しさはありません。最後の楽章もやわらかく軽やかです。 バスーン・ソナタ ♥ ですが、これも第一楽章は中庸のテンポで適度に力が抜けた演奏です。中間部の盛り上げも、ピアノのパートが細かく速くして熱を入れるのに対して、そこまで強くはしません。バスーンの音色は明るく艶を感じさせる倍音です。第二楽章は速くてリズミカルで、これはかなり速い方です。 のんびりして魅力的なモルト・アダージョの第三楽章はピアノがスタッカートですが、運びはゆったりです。力を抜いたバスーンがリタルタンド気味のためも使い、余裕で吹いて行きます。特に静けさは狙ってないようで、さらさらと自然に流れて行きます。弱音部もあっさりしていて、平静な感覚です。 1975年録音のカリオペ原盤で、写真のジャケットは仏アンデサンス(Indesens)・レーベルの新しいものです。アナログ・ステレオ中期で、音はこのレーベルらしく落ち着いていて潤いのあるものであり、最新録音と比べても遜色ないでしょう。三曲以外にはロマンス op.36、カヴァティーヌ op.144、七重奏曲 op.65 が入っています。ただし七重奏曲だけは録音が古く、再販時にわざわざ加える意味はよく分かりませんでした。  Saint-Saëns Chamber Music for Wind Instruments & Piano Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Ensemble Villa Musica : Ingo Goritzki (ob) Ulf Rodenhäuser (cl) ♥ Dag Jensen (fg) Leonard Hokanson (pf) サン=サーンス / 木管楽器とピアノのための室内楽 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 アンサンブル・ヴィラ・ムジカ: インゴ・ゴリツキ(オーボエ)/ ウルフ・ローデンハウザー(クラリネット)♥ ダーグ・イェンセン(ファゴット)/ レナード・ホカンソン(ピアノ) こちらはドイツの MDG レーベルから出ているものです。演奏は1990年に結成されたアンサンブル・ヴィラ・ムジカです。主にドイツ系の人たちの演奏ということになります。アルバム・トータルとしての印象は、ドイツ人らしいかどうかは分かりませんが、抑揚に余分な動きを加えず、真面目できっちりとしたところのある運びが多いように感じました。まったりと穏やかに展開するので、白鳥の歌に相応しいと言えるかもしれません。 オーボエのインゴ・ゴリツキは1939年のベルリン生まれ。ピアノやフルートもやってましたが、ヴィンシャーマンに師事し、バーゼル響やフランクルルト放響で活躍して多くのオーボイストを育てた重鎮です。
クラリネットのウルフ・ローデンハウザーもドイツの人で、ファゴットのダーグ・イェンツェンはノルウェー人。 ピアノのレナード・ホカンソンは1931年生まれのアメリカ人という構成です。 オーボエ・ソナタ ♥ です。オーボエが最初は切って、二拍目はスラーという入りになっていたりするものの、トータルでは余計な表現を加えない演奏です。テンポは適度に緩やかで、曲に相応しいと思います。具体的には真っ直ぐよく延ばして行く中に強弱を適度に加えます。細かな呼吸変化は目立たず、割と平らな感じではありますが、抑揚はあります。余分な表情がない分自然と言えるでしょうか。音色は細過ぎず、輪郭や艶が特別強くはないニュートラルなものです。 第二楽章もフラットと言うと言葉が悪いですが、波打たせたり山なりに盛り上げたりはしないながら、よく延びる音の中に細かくは変化させない強弱が付きます。それは変わったことをしないニュートラルな抑揚であり、派手さがない分真面目な印象があるでしょうか。噛めば味がするというのか、音の流れにじっくりと身を任せると浸れます。
第三楽章は適度に軽快でくっきりと音を区切ります。音色が細過ぎないとは言いましたが、ここでは案外細身にも感じられ、高く弾むところが魅力的に聞こえます。 クラリネット・ソナタは、最初は角がやわらかく漂う感じですが、平均すると太めの音色でしっかりと吹くところがあります。静けさ狙いではなく、途中からクレッシェンドが際立ち、強い音に力点が移動したかのような抑揚になります。テンポは中庸で、癖はありません。ピアノはやや丸々としたところがあって丁寧な印象です。第二楽章は走らず、真面目にこなします。強い情緒を感じさせる第三楽章はゆっくりですが、ここも割と平坦で、クラリネットはスラーが目立ちます。ピアノは強く叩き過ぎません。中ほどからの弱音部に入ってもスラーで平らに行くのは同じです。また、弱いといってもすごく弱音に寄せるのではなく、フラットに音をつなげて持続音のように運びます。 バスーン・ソナタは中庸のテンポでやや軽快に始めます。静けさ狙いでも滑らかさ狙いでもなく、さらっとしています。楽音がよく鳴っている感じがします。第二楽章も真面目に進め、第三楽章はスタッカートで区切った遅いピアノの上に乗ってややゆったりのテンポで進行します。素直に吹いて行き、弱音部も際立って静かにはせず、穏やかです。 1991年の MDG のセッション録音です。マイナーながら全てゴールド・ディスク仕様にして音に気を使ったレーベルで、ここでも良い音で楽しめます。余計な曲が加わらず、作曲された順番に三つのソナタを聞くことができ、最後にロマンス op.37 とデンマークとロシアの歌による奇想曲 op.79 が入っています。ロマンスは三十五歳のときに作られた穏やかで聞きやすい曲です。 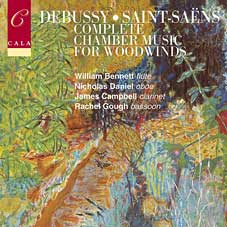 Saint-Saëns French Chamber Music for Woodwinds, Volume One Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Nicholas Daniel (ob) James Campbell (cl) ♥♥ Rachel Gough (fg) John York (pf/clarinet sonata) Julius Drake (pf) サン=サーンス / 木管楽器のためのフランス室内楽曲集 第1巻 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 ニコラス・ダニエル(オーボエ)/ ジェームズ・キャンベル(クラリネット)♥♥ レイチェル・ゴフ(ファゴット)/ジョン・ヨーク(ピアノ/クラリネット・ソナタ) ジュリアス・ドレイク(ピアノ) 今回のこの白鳥の歌のアルバムで、これが自分の聞いた感覚では文句なくベストでした。しかもオーボエ、クラリネット、バスーンのどの曲においてもそれが言えます。問題があるとすると上記ブールグたちのカリオペ盤ほどじゃないけど、多少手に入れ難いかもしれないところでしょうか。ほぼ英国の人たちによる演奏です。 オーボエのニコラス・ダニエルは1962年生まれのイギリス人。音楽祭を企画したり音楽団体や協会をサポートしたりして本国では有名な人のようです。 クラリネットのジェームズ・キャンベルの方は1949年カナダ生まれで、アメリカ国籍も取って活躍している 人。 バスーンのレイチェル・ゴフはイギリス人だけど生年は分かりません。日本や韓国以外では人物紹介でそこまで年齢を問題にしないでしょうし、女性に限らずあまり聞くのは失礼に当たるわけで、公にしないことも多いのですが、世代ということならロンドン・シンフォニーで1999年から首席です。 クラリネット・ソナタでピアノを担当しているジョン・ヨークも生年不明で、イギリス国籍です。残り二曲のピアノであるジュリアス・ドレイクは1959年のロンドン生まれとなっています。まあ、国籍というのも本来は関係ないのですが。 オーボエ・ソナタ ♥♥ ですが、この録音の四年前に同じニコラス・ダニエルのオーボエ、ピアノも同じ人でヴァージン・レコーズからの旧録音がありました。そちらの演奏は第一楽章がより遅くて間などの表情も大きいもので、第二楽章についても当新盤の方が見事な抑揚に感じましたので、ここでは詳しく取り上げません。 そしてこちらの演奏ですが、オーボエ・ソナタとしては一番だった印象です。静けさがあり、控えめながら表情豊かで、曲にぴったりです。最も雰囲気があるとも言えるでしょう。よく歌いますが変な癖はなく、強弱が滑らかです。特に弱音の表情が細やかで、呼吸の入る感じが美しいです。上記カリオペ盤のブールグやデンオン盤のシュレンベルガー、ハイペリオン盤のガレス・ハルスも大変良かったけれど、それらと比べても朗々とし過ぎない静謐さという点で魅力がありあす。第一楽章のテンポは適切な中庸です。楽器の音色は適度に艶があり、輪郭はあるけど立ち過ぎず、オフになり過ぎずです。 第二楽章こそため息ものでした。テンポはここもまた中庸で実に適切であり、力の抜き方、山の作り方など、抑揚がベストです。穏やかで静けさがあり、また、中間部に入る少し前の盛り上がりの鮮烈に力のこもる様がこれ以上ない出来なのです。第三楽章は艶が感じられ、活気と潤いが共存していて自在です。 同じオーボエで良かったモーリス・ブールグは歌い込みという点ではフランス人の粋というのか、より何気なく流す方に寄っていて軽くて活気があります。そして第二楽章では遠近の吹き分け効果を出す方へ重点が置かれており、熱の入ったクレッシェンドは狙っていないようです。ハンスイェルク・シュレンベルガー(DENON/後で取り上げます)も速いところはやはり表現がよりさらっと素直であり、遅いところは逆にまったりじっくりながらももう少し真っ直ぐ真面目な抑揚に感じました。 クラリネット・ソナタ ♥♥ のセピア色の感覚も大変良かったです。適度にゆったりで力が抜け、まったりとした出だしながら、穏やかに表情がついていて白鳥の歌の雰囲気が出ています。音色は最大やわらかいクラリネットではないにしてもやわらかく、低音の強い音のくぐもり方が多少個性的でしょうか。無理なく自然な強弱があり、全体は静かに枯れていながら、湧き上がる感情に従って強く自在な呼吸で速めるところも見事です。その辺は上記オーボエ・ソナタの演奏の波長とも一致しています。第二楽章は軽快だけど速く駈け過ぎず、自然で力みがありません。 問題の悲劇的な第三楽章はピアノが適度に力強く、クラリネットも荘重なものの、強く吹き過ぎません。弱音は思い切って力を抜いて、掠れないぎりぎりぐらいで漂うところがあり、この部分の情感を余す所なく表現しています。しかもわざとらしいどっぷりにならないのです。 バスーン・ソナタ ♥♥ もクラリネット同様ベストに思えました。静かなピアノによって控え目に始まり、バスーンも力が抜けています。自然でわざとらしさがないのが何よりです。穏やかな陽だまり感があります。中間の自然に速くなるところも自在です。第二楽章はスケルツォらしく速めに弾ませるけれど、やはり無理がありません。 第三楽章は穏やかで静かです。第一楽章と並んで、あるいはそれ以上に魅力的な楽章だけど、輪郭が出過ぎるほどまで強く吹きません。実に適切です。静かな中に力の抜けた表情があります。ありのままの肯定感が良く、中間部の静まり方も見事で、惚れぼれ聞き入ってしまいます。ずっと浸っていたい感じです。 このレーベルはイギリスのカーラ(Cala)というところで、現在はもうなくなってしまったのでしょうか、 1994年の録音です。そのときに出た後は2008年にも再販されたけど、一応現在は廃盤のようです。でもまだサイトでは複数出回っており、今後も中古ではしばらく入手可能かもしれません。サブスクリプション・サイトにはあります。 カップリングですが、これは二枚組で、一枚目はドビュッシーの木管室内楽が集めてあります。コーラングレ、フルート、サキソフォンなどが登場し、牧神の午後への前奏曲に近い六音音階寄りの聞きやすくも不思議な音が楽しめる狂詩曲などがいくつか入ってます。下記マイケル・コリンズの新盤にもカップリングされていますが、有名なクラリネットの「第一狂詩曲」もあり、名演だと思います。サン=サーンスの方は二枚目であり、そちらにはオデレット op.162、アルバムのページ op.81、デンマークとロシアの旋律による奇想曲 op.79、ロマンス op.37、タランテラ op.6 が各ソナタの間に配置されています。 マイナーなレーベルですが、録音コンディションは大変優秀なものです。その点でもベストの一つと言えるでしょう。  Saint-Saëns Chamber Music Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 The Nash Ensemble ♥♥ Gareth Hulse (ob) Richard Hosford (cl) Ursula Leveaux (fg) Ian Brown (pf) サン=サーンス / 室内楽作品集 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 ナッシュ・アンサンブル ♥♥ ガレス・ハルス(オーボエ)/ リチャード・ホスフォード(クラリネット) ウルスラ・ルヴォー(ファゴット)/ イアン・ブラウン(ピアノ) こちらはハイペリオン・レーベルが出したもので、「印象」的なジャケットです。この曲集で一番と言った上記カーラ盤と同じくイギリスの人たちによる、その十年後の演奏ということになります。偶然かどうか、今回は本国フランス勢も良かったけれど、英国人たちのパフォーマンスに惹きつけられることが多い感じです。そしてこれも全くもって見事な演奏です。この曲集のベストの一つだと思いました。 ナッシュ・アンサンブルの演奏ということですが、この団体はロンドンで1964年に結成されました。室内楽団なので、ここで演奏している人たちだけではなく、人数はたくさんいます。 オーボエのガレス・ハルスはホリガーに師事したイギリス人ということです。ロンドン・フィル、ノーザン・シンフォニアなど、多くの楽団で首席を務め、現在もロンドン・シンフォニエッタ、このナッシュ・アンサンブルで活躍しています。 クラリネットのリチャード・ホスフォードもイギリスの人で、ヨーロッパ室内管で長らく活動し、ロンドン・フィルの首席を経て現在は BBC 交響楽団のプリンシパルということです。 バスーンのウルスラ・ルヴォーはスコットランド生まれということで、ロンドン・シンフォニアとエンシェント室内管の首席ということです。 ピアノのイアン・ブラウンは2004年に亡くなったヴァイオリニストで指揮者のアイオナ・ブラウンの兄弟で、元々はバスーンをやっててピアノに転向し、現在はナッシュ・アンサンブルのピアノ担当であると同時に指揮活動に励んでいるとのことです。 オーボエ・ソナタ ♥♥ が見事です。これは上記ニコラス・ダニエルの演奏と比べても、違いはあるけど同等に魅力的なオーボエです。静けさのニコラス・ダニエル、軽妙さでこのガレス・ハルスといったところでしょうか。強く押さない感じで、軽やかにして伸びやかな吹き方のオーボエです。音色はやや細めながら滑らかな艶のある大変きれいな音。最初の楽章は中庸のテンポで、落ち着いた理想的な運びで始まり、細かな強弱の抑揚が自然に付いた呼吸がいいです。注目の第二楽章ですが、ここも穏やかで澄んだ空気感が感じられ、自然に膨らませる息遣いが素晴らしいです。第三楽章も軽やかに弾んで愉悦感があり、細めながら艶やかな音色が生かされ、透明感が感じられます。録音もいいです。 クラリネット・ソナタ ♥♥ です。やわらかいけどやや速めで、さらっとした出だしです。もう少しだけ弱音に寄せてゆったり音をつないだ方が好みかなと最初思ったけど、逆にあっさりと流すところが粋だと言えるでしょう。ニュアンスは豊かです。そして中間部以降ではむしろゆったりになります。力は抜けています。第二楽章は走らないけど軽やかで、ここも力が抜けていて大変良いです。景色があって理想的かもしれません。注目の第三楽章は音を延ばしてつなぎ、音色はやわらかさと輪郭のバランスが良く、少し鼻にかかるけれども透明できれいな低音が聞けます。第四楽章は素早い動きに満ち、軽快です。 バスーン・ソナタ ♥ もクラリネット同様力の抜けた軽やかさと何気なさがあります。第二楽章も無理のない速さでさらっとリズミカルに進め、美しい第三楽章はスタッカートのピアノで、ここも力が抜けて軽やかに行きます。テンポはとりたててゆったりな感じというわけではなく、さらっと流す感じです。 2004年のハイペリオンの録音です。瑞々しく細部もとれ、大変優秀な録音です。ピアノはスタインウェイで、ダウンロードも可能であり、24bit 44.1kHz の Hi-Res もあります。 二枚組であり、他は七重奏曲 op.65、フルート、クラリネットとピアノのための「タランテラ」op.6、ピアノ四重奏曲 op.41 と五重奏曲 op.14、デンマークとロシアの歌による奇想曲 op.79 です。  Saint-Saëns Music for Wind Instruments Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Canada’s National Arts Centre Wind Quintet Charles Hamann (ob) Kimball Sykes (cl) Christopher Millard (fg) Stéphane Lemelin (pf) サン=サーンス / 管楽器のための音楽集 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 カナダ・ナショナル・アーツ・センター管楽五重奏団 チャールズ・ハマン(オーボエ)/ キムボール・サイクス(クラリネット) クリストファー・ミラー(ファゴット)/ステファヌ・ルムラン(ピアノ) こちらはナクソスからです。カナダの五重奏団の演奏です。カナダは飛行機のタラップを出た瞬間にアメリカとはまた違い、重さのないクリーンな空気を感じるという人もいますが、そういう国らしいというのか、曲がったところのない素直なきれいさが特徴の演奏だと思います。三曲とも演奏スタイルが似ています。技ありな感じはしないので♡は付けませんでしたが、聞いてある種の清々しさを感じました。 オーボエのチャールズ・ハマンは1971年生まれのカナダ人。国立芸術センター管弦楽団の首席です。客演首席としてはシカゴ響、ロイヤル・フィル、レ・ヴィオロン・デュ・ロワで吹きました。 クラリネットのキムボール・サイクスはバンクーバー生まれで、1985年から国立芸術センター管弦楽団の首席です。バスーンのクリストファー・ミラーも同じく国立芸術センター管弦楽団で首席を務め、ステファヌ・ルムランは1960年生まれのカナダのピアニストで、オタワ大学で教えているということです。ピアノはカナダとアメリカで学び、アルトゥル・シュナーベルの長男でペライアも教えたカール・ウルリッヒ・シュナーベルに師事したようです。カサドシュ国際コンクール(現クリーヴランド国際ピアノ・コンペティション CIPC)受賞とのことですが、調べてみると1983年度に三位入賞となっていました。優勝しなかったピアニストにいい人もいます。マニュエル・ロザンタールのピアノ集とか、個性的なものを録音しています。 オーボエ・ソナタは、おっとりとしたゆるやかなテンポで丁寧に運びます。次のクラリネットと同様に音をつなげてスラーで行く箇所が多く聞かれます。細かな強弱をつける方向ではなく、素直で癖がなく、真っ直ぐな印象です。第二楽章もゆったりめで、やはり素直に吹き、第三楽章も一つひとつ実に丁寧でしっかりしています。 クラリネット・ソナタも、オーボエと似たところが あり、ややゆったりめのテンポで間違いのない丁寧な運びです。第二楽章に入ると適度に軽快なテンポとなりますが、素直に吹かれます。第三楽章は出だしからスラーで音を途切らせず、フラットに行きます。ここも激情というよりもむしろ真面目な運びです。弱音の部分に入る前のピアノの分散和音は大変遅く、次の高く弱く吹かれるクラリネットも、あまり大きな抑揚はつけずにフラットに音をつなげます。息も絶えだえという感覚にはなりません。ただ、これも独特の透明感があっていいと思います。第四楽章は相応に速くなりますが、やはり心地良く丁寧です。 バスーン・ソナタですが、出だしはやや速めのテンポでさらっとしており、強弱は前二つの楽器より付けている感じでしょうか。でもふわっと弱める音が聞かれたりするもので、静けさよりは何気なさが先に来ます。第二楽章は結構リズミカルに軽快に運びます。テンポ自体は速めの方です。第三楽章はピアノがスタッカートで区切るようにやや遅めに始めます。バスーンは音をつなげて行き、丁寧な運びで癖がないところは他の二人と似ています。こだわりのなさが作品に合っていていいでしょう。弱音部も極端に弱くはせず、素直に流れて行きます。 2008年録音のナクソスです。トロントでのセッション録音です。自然な響きの好録音です。カップリングとしては、ソナタ三曲以外にデンマークとロシアの歌による奇想曲 op.79、ロマンス op.67、フルート、クラリネットとピアノのための「タランテラ」op.6 が入っています。 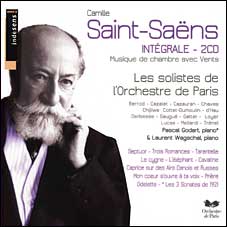 Saint-Saëns Musique de chambre avec vents (Complete Chamber Music with Winds) Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Les Solistes de l’Orchestre de Paris ♥ Alexandre Gattet (ob) Philippe Berrod (cl) Marc Trénel (fg) Pascal Godart (pf) サン=サーンス / 管楽器のための室内楽全集 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 パリ管弦楽団のソリストたち ♥ アレクサンドル・ガテ(オーボエ)/ フィリップ・ベロー(クラリネット) マルク・トレネル(ファゴット)/パスカル・ゴダール(ピアノ) 75年のモーリス・ブールグらによる録音からは大分経っていますが、2010年、再びフランス勢の登場です。パリ管の首席たちによる演奏です。抑揚をあまり欲張らず、おっとりとして平静なオーボエが洗練されており、弱音が訴えるクラリネットもいいです。 オーボエのアレクサンドル・ガテはフランス人ですが生年は不明、1999年にアメリカのフェルナンド・ジレ国際オーボエ・コンペティションで優勝し、2000年よりパリ管で吹いているということです。 クラリネットのフィリップ・ベローは1965年アヌシー生まれ。フランス放送フィルで活躍した後、パリ管の首席になったようです。 バスーンのマルク・トレネルについては詳しいことは分かりませんでした。パスカル・ゴダールは1971年生まれのフランスのピアニストです。 オーボエ・ソナタ ♥ ですが、第一楽章はほどよくゆったりで、力を抜いて最初音をやや切り気味にしたりして粘る歌い方ではありませんが、強弱の呼吸はよく付いています。楽器の音色としてはやわらかさがあり、輝かしさよりは滑らかさに寄っていて、あまり輪郭の強い倍音が乗るものではありません。1940年創業のフランスのオーボエ、マリゴの2001年モデルということです。録音の加減もあってか若干オフにも感じられます。後半は滑らかに歌って行きますが、中間部では一段弱い方へ落とす表現も聞かれます。第二楽章は遅過ぎず速過ぎずで、ややさらっとした質の抑揚がつきます。間は十分に空け、ゆったり延ばすところと駈けるところの差があります。中間部はゆったり力を抜いて行きます。表情のある上手なオーボエだと思います。 クラリネット・ソナタ ♥ は多少軽快に始めますが、流れにわずかな待ちとためがあり、抑揚が自然によくついています。静かながら活気を感じる演奏です。自分の好みよりは幾分さらっと流す感覚が強いような気もしますが、洗練されています。第二楽章はそこそこ速く、軽く流します。第三楽章は音を適度に区切りながら、テンポは中庸です。ことさら深刻さに寄せず、中ほどより後で出て来る弱音のパートはかなり弱く音を出しています。思い切って消え入るかのようにやっていて間も取り気味であり、息も絶えだえという感じがよく出ています。浸れて魅力的な特徴ある演奏だと思います。第四楽章は力が抜けていて軽快です。弱音もやはり思い切っています。 バスーン・ソナタは、さらっとそつなく流して行きます。テンポは遅くありません。第二楽章はリズミカルに、十分軽快なテンポで駈けます。第三楽章は中庸のテンポで、ことさら静かではありませんが穏やかです。弱音部を緩めて十分に美しいです。 レーベルはアンデサンス(indesens)で、2010年のパリ、サン=マルセル教会での収録です。録音は輝き過ぎず、自然です。二枚組で、カップリング曲は動物の謝肉祭より「白鳥」と「象」などのお馴染みのものに加え、七重奏曲 op.65、ロマンス op.36, 37, 67、タランテラ op.6、カヴァティーヌ op.144、デンマークとロシアの旋律による奇想曲、サムソンとデリラより「あなたの声に心は開く」、祈り op.158、叙情小曲 op.162、幻想曲、「白鳥」のフリューゲル・ホルン版となっています。演奏者は上記以外様々です。  Saint-Saëns Chamber Music Oboe Sonata in D major op.166 Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Bassoon Sonata in G major op.168 Soloists of the Accademia di Santa Cecilia Rome Francesco Di Rosa (ob) Stefano Novelli (cl) Francesco Bossone (fg) Akanè Makita (pf) サン=サーンス / 室内楽曲集 オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 バスーン・ソナタ ト長調 op.168 サンタ・チェチーリア・アカデミー管弦楽団のソロイストたち フランチェスコ・ディ・ローザ(オーボエ)/ ステファノ・ノヴェッリ(クラリネット) フランチェスコ・ボッソーネ(ファゴット)/アカネ・マキタ(蒔田朱音/ピアノ) こちらはイタリア勢の演奏で、廉価版のブリリアントが出して来たものです。1908年創設のサンタ・チェチーリア・アカデミー管弦楽団(ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団)でソロをとるミュージシャンによるものです。同楽団の現在の音楽監督はアントニオ・パッパーノです。イタリア人というと、国別で特徴を言うのもどうかとは思いますが、人によっては無機的に寄るかというほどかっちりじっくりの分解的な運びだったり、多くは情熱的なカンタービレだったりするというステレオ・タイプのイメージがあります。ここでは必ずしもそういう感じでもないけど、フラットにゆったり歌わせるのはクラリネットでしょうか。細かく抑揚をつけたりすることを狙わないプレーンな感覚が個性的です。 各ソロイストたちについては詳しいことはあまり分かりませんでした。オーボエのフランチェスコ・ディ・ローザが1967年モンテグラナーロ生まれということと、残り二人もイタリア人であること、ピアノはアッチェント・グラーヴェ付きのアルファベット表記ながら日本の人だということぐらいでしょうか。 オーボエ・ソナタですが、艶は強くないけど、明るめの音色の楽器です。中庸のテンポで比較的さらっと流します。強弱の呼吸はしっかりとあります。第二楽章はトリルがクイックで、テンポ自体は速くないけどさらっとした感触です。もう少し残響があると良いかなと感じました。オーボエ自体はしっかりしたものです。語尾を長く延ばさないで切る傾向はあるでしょうか。白鳥の歌としても、静けさよりは何気なさが前に出ています。 クラリネット・ソナタは、ピアノの出足がゆったり間をとる感じで、続くクラリネットもそのリズムでまったりとしています。一音を丁寧に音にして行く印象で、遅い分平静で延びた感じはするかもしれません。第二楽章は適度にリズミカルで、案外ダイナミックな動きも感じられます。悲劇的な第三楽章は十分にゆったりで、クラリネットは音をつなげます。提示の部分は抑揚をあまり付けていない方でしょう。真ん中より後、弱音部はかなり弱くしており、音に艶がある方ではないので多少途切れつつ進む感じもあります。多分これは意図的でしょう。くすんだ味わいというのでしょうか。 バスーン・ソナタの方は、力の抜けたピアノに乗ってやや軽快な運びでファゴットが入って来ます。大きな表情をつけるわけではないけれども、速い音符で区切って行く表現を出し、穏やかさ、平静さがあります。第二楽章はスタッカートの音の区切れが心地良いです。第三楽章も出だしのピアノが弱いけどしっかりとしたスタッカートです。続いてやわらかくファゴットが、こちははスラーも多用して歌って行きます。ひなびた味わいです。 2014年録音のブリリアントです。コンディションは良好ですが、残響の意味で全体にややオフなところのある音です。楽器の音がよく分かり、鳴り響かない分静かと言えます。バスーン、オーボエ、クラリネットの順でソナタが演奏され、その各ソナタの後ろにそれぞれロマンスの op.67と37、デンマークとロシアの歌による奇想曲 op.79 の三曲が置かれています。 以上がオーボエ、クラリネット、バスーン・ソナタの三曲の白鳥の歌を網羅したアルバムですが、ここから少しだけ、各楽器の演奏者がリーダーとなって一つのソナタを演奏し、残りは別の作曲家の作品を集めているという体裁の CD を概観してみます。 オーボエ・ソナタのみの CD  Saint-Saëns Oboe Sonata in D major op.166 Hansjörg Schellenberger (ob) Rolf Koenen (pf) ♥♥ サン=サーンス / オーボエ・ソナタ ニ長調 op.166 ハンスイェルク・シュレンベルガー(ピアノ)/ロルフ・ケーネン(ピアノ)♥♥ オーボイストがリーダーになり、サン=サーンスはオーボエ・ソナタのみで他の二つは入っていないアルバムですが、呼吸の見事なオーボエなのでこれ一枚はジャケット写真付きで取り上げます。 ハンスイェルク・シュレンベルガーはドイツのオーボエ奏者です。1948年ミュンヘンの生まれで、インター ロッケン(ミシガンにある米国初の芸術系高校)で学び、ホリガーに師事した後、カラヤンに認められて1980年から2000年までベルリン・フィルの首席を務めました。 第一楽章はくっきりとした輪郭で艶のある、軽めの明るい音色で軽快に進めます。テンポ自体も遅くはありませ ん。適度に滑らかさもあります。活気があって滑らかだと言えばよいでしょうか。そして何より自在な呼吸があり、低い音に力を込めて流れるように歌うところが素晴らしいです。ゆったりとした第二楽章に入ると、指数曲線的に力のこもったクレッシェンドが聞かれ、このあたりはホリガーを少し思い起こさせる抑揚です。堂々たる吹きっぷりで、透明感があって大変素晴らしいです。テンポはややゆったりで、この楽章に対して的確でしょう。音色が澄んで輪郭のあるところがきれいで、それも曲に相応しいと思います。白鳥の歌だからといって静けさに寄せている感じはなく、朗々としていますが、これはこれで歌があって見事としか言いようがありません。上で取り上げたニコラス・ダニエルのオーボエがベストと言いましたが、形は違えど甲乙つけ難いです。技術が光る第三楽章も完璧でしょう。 1988年録音で、残響のきれいなベルリン・イエス・キリスト教会での収録です。レーベルは DENON で、楽器の艶と透明度が高い、大変ハイファイな音です。 このアルバムはフランスのオーボエ名曲集という形になっており、サン=サーンス以外はプーランクとデュティ ユーの各ソナタ、ボザのファンタジー・パストラール op.37、ベネットのアフター・シランクスという曲が入っています。このベネットはドビュッシーのフルート曲が元になっているので聞いたことがあるでしょうか。プーランクはよく組み合わされる名曲です。 以下にそれ以外のオーボエ・ソナタのみの CD を簡略に記します。 ニコラス・ダニエル(Nicholas Daniel/オーボエ)/ジュリアス・ドレイク(ピアノ)1990 Virgin Classics 3ソナタが揃ったカーラ盤と同じオーボイストとピアニストによる演奏ですが、録音年度はこちらの方が四年前 で、ウジェーヌ・ボザ、アンリ・デュティユー、シャルル・ケクラン、プーランクの各オーボエ・ソナタとの組み合わせです。新盤と比べると第一楽章では大分遅く丁寧に歌わせており、間もとって表情も大きく感じます。緩徐楽章である第二楽章は逆に速くなっていて歌はあっさりし、中間部で饒舌に加速しています。各楽章のタイムは実測でそれぞれ 3:44(3:15)/5:16(5:21)/2:10(2:14)です(括弧内はカーラ盤)。 アラン・フォーゲル(Allan Vovel/オーボエ)/ブライアン・ベッツォーネ(ピアノ)1997 Delos アメリカのオーボエ奏者で、LA フィルの首席。長く間をとりながら、大変ゆったりとフレーズごとに区切るように丁寧に歌って行く個性的な演奏です。 ヨリス・ヴァン・デン・ファーウェイ(Joris Van den Hauwe/オーボエ)/ダリア・ウジィエル(ピアノ)2008 Aliud classics ベルギーのオーボエ奏者で、ブリュッセル・フィルの首席。歌う楽章では音を区切り気味にし、アラン・フォーゲルほどではないけど間をとって時折立ち止まるようにゆったりと進めます。フレーズの後ろもリタルタンドして緩め、語尾を長く延ばすなどの表情があってよく歌います。 アルブレヒト・マイヤー(Albrecht Mayer/オーボエ)/カリーナ・ヴィシニェフスキ(ピアノ)2009 Tudor 1965年ドイツ生まれで、92年からベルリン・フィル首席。やわらかくやや奥まった音の収録ながら、表情がよくついて朗々としており、延ばす音に力があります。ゆったりしたパートではかなりスローに歌わせて間を空けますが、トリル飾りの部分だけくるっと速めて鳥が囀るように表情をつけたりもします。技のある人という感じです。 ハンバート・ルカレッリ(Humbert Lucarelli/オーボエ)/トーマス・フリンキー(ピアノ)2012 Lyrichord classical 1936年生まれのアメリカのオーボイストで、シカゴ響で吹いていたこともあります。フレーズの中ほどを膨らませて抑揚を付け、音はスラーで滑らかにつないで行きます。スローな楽章は間を大きくとり、やはりスラーでつなげて強めに粘りをつけ、静かというよりも朗々と歌います。 アレックス・クライン(Alex Klein/オーボエ)/フィリップ・バッシュ(ピアノ)2018 Cedille Records 1964年ブラジル生まれで、ジュネーブ国際音楽コンペティションで優勝し、シカゴ響の首席になりました。最初から大変ゆったりです。長く平坦に引っ張り延ばした音でスラーをかけます。丁寧で慎重な印象ですが、音はよく鳴ります。緩徐楽章もゆったりで、フレーズの語尾をよく延ばします。 フランソワ・ルルー(François Leleux/オーボエ)/エマニュエル・シュトロッセ(ピアノ)2018 Warner Classics 1971生まれのフランスのオーボエ奏者で、パリ・オペラ座で活躍し、バイエルン放響の首席です。踊るように強弱がついて軽快に進める演奏です。技術的には違うのかもしれないけど、音色がもっと細身で艶があり、ビブラートを多用すると少しだけ大御所ピエール・ピエルロの軽く翻る吹き方に似ているでしょうか。巧さが引き立つ運びで、その印象は第二楽章でも変わりません。自在な第三楽章はこの人にぴったりかもしれません。 クラリネット・ソナタのみの CD サン=サーンスの三つの管楽ソナタの中では最も知名度が高い人気曲ということもあり、多くのクラリネット奏者がリーダー・アルバムを出しています。以下にその中でも良かったと感じた一枚を取り上げ、残りは簡略にまとめます。 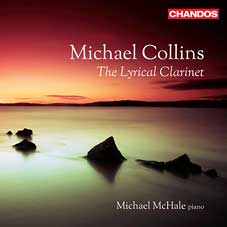 Saint-Saëns Clarinet Sonata in E-flat major op.167 Michael Collins (cl) Michael McHale (pf) ♥♥ サン=サーンス / クラリネット・ソナタ 変ホ長調 op.167 マイケル・コリンズ(クラリネット)/ マイケル・マクヘイル(ピアノ)♥♥ 1962年生まれのイギリスのクラリネッティストです。上でリチャード・ホスフォードを取り上げましたが、過去に同じくナッシュ・アンサンブルの団員だったことがあります。フィルハーモニア管とロンドン・シンフォニエッタの首席で、使用楽器は YAMAHA YCL-SE Artist Model(特注)とのことです。艶や輪郭の面で派手さはないですが、シックでふわっと漂うやわらかさあり、一方音が揃ってフォルテで裏返らない均一な強さも出、破綻のない良い音色だと思います。 滑らかさが光り、静謐感のある演奏です。出だしは少しさらっとしたテンポで力が抜けています。一方で速い第二楽章でもあまり駈けず、落ち着きを維持します。第三楽章では音をつなぎ気味にし、真っ直ぐ滑らかに吹いて、最初の提示フレーズの終わりで一瞬クレッシェンドをかけるのが印象的です。続く弱音部も音をスラーでつなぎ、真っ直ぐに進めて抑揚をつけ過ぎません。まったりとして一つのやわらかい塊が漂うように吹いて、それが美しいです。最後は思い切ってリタルタンドをかけます。ピアノも控えめながら静かな情緒があって良いです。技術面ではくっきりとして巧者でも、全体に静の美というのでしょうか。 2010年収録のシャンドスです。音は透明感があって大変良好です。他から頭一つ飛び出すぐらいの優秀録音だと思います。タイトルが「リリカル・クラリネット」となっており、プーランク、ブルグミュラー、リード、ペルト、フィンジ、ベールマンといった人たちの作品がカップリングされていますが、聞きやすいきれいな曲揃いであり、タイトル通り静かでメロディアスなものが多いです。この企画は人気が出たのかシリーズ化され、その後 Vol.3 まで出ています。 その後2019年収録で今度は BIS から小川典子のピアノによる再録音 ♥ も出ています。そちらの演奏はタイムで言うなら第一楽章と第四楽章が同一、第二楽章で6秒、第三楽章で17秒遅くなっていますが、テンポ感としてはどこもほぼ同じです。演奏の違いと言えば、表現上大きな差はありませんが、第一楽章では旧盤の方がためが少なめでより自然に流れ、第三楽章の始まりでは旧の方が穏やかに、中ほど以降の弱音部では静けさがよりあるという感じでしょうか。全体的には旧の方が鮮度、新の方がまったり感が強い気がします。録音バランス的には新盤の方がクラリネットの高域の倍音がややおとなしく、艶と繊細さは少なくて引っ込み気味ではあるものの、その分やわらかく聞こえます。ピアノの細かな音は大変良く拾っていますのでオフなわけではなく、優秀な録音という意味では優劣はつけられません。客席で聞いた生音に近いとも言えます。タイトルは「パリジャンのクラリネット」で、ドビュッシーの「牧神の午後」的なクラリネットの名曲である「第一狂詩曲」、プーランク二曲、ヴィドール、メサジェ、ラボーの曲とのカップリングです。旧盤のように特別にリリカルなものを集めたという趣向ではなく、こちらの選曲の方が好みという方もあるかと思います。
以下にそれ以外のクラリネット・ソナタのみの CD を概観してみます。
レジナルド・ケル(Reginald Kell/クラリネット)/ブルックス・スミス(ピアノ)1957 DG 1961年生まれで81年に亡くなったイギリスの大御所クラリネット奏者で、ロンドン・フィルやロイヤル・ フィルで活躍しました。遅くてフレーズをしっかり区切り、力強く歌って行く感じです。音色も輪郭がかっちりとしており、低音も明快です。アレグロの第二楽章までゆっくりで驚きます。第三楽章は重々しくくっきりと、弱音パートでも力強く、サキソフォンのようにかすれ気味の音で朗々と歌います。力の抜けた白鳥の歌ではないようです。 ジャネット・ヒルトン(Janet Hilton/クラリネット)/キース・スワロー(ピアノ)1983 Chandos イギリスのクラリネッティストです。テンポはケルより遅く、最も遅い部類の出だしでゆったりやわらかく、叙情的なカンタービレで行きます。同時に丁寧な印象でもあります。第二楽章もゆったりめで、力が抜けています。第三楽章はやわらかいピアノに乗って抑揚をつけてスローに歌って行きます。深刻さより滑らかさが前面に出て、弱音部はやわらかく物寂しく、やはりしっかりと歌をつけます。 ジェルヴァース・ドゥ・ペイエ ♥(Gervase De Peyer/クラリネット)/グウェンネス・プライアー(ピアノ)1987 Chandos 1926年生まれで2017に亡くなったイギリスの有名なクラリネット奏者です。55年から72年までロンドン・シンフォニーの首席でした。あっさりとした延ばさない音を適度にはさみながら自在に歌って行きます。繊細な強弱変化があり、ほんの微かなためとルバート様の揺れも聞かれます。テンポは中庸で、速いところも力が抜けていて軽やかです。深刻な第三楽章もことさら深刻ぶらずに流し、力を入れ過ぎません。静かな高音部は音を切りながら、ことさら弱々しくはやらずにビブラートも使って歌わせ、あっさりとしていながら情感があります。 デイヴィッド・ライト(David Wright/クラリネット)/グレゴリー・デイヴィス(ピアノ)1988 Centaur アメリカのクラリネット奏者。力が抜けて軽さがあります。さらっとしたテンポで極端に滑らかにはせず、語尾も切るところがあって何気なさを感じます。速い楽章は速く、軽くリズミカルに行き、第三楽章もやや切り気味に音符を延ばさず、深刻さはありません。さらっとしていて悲しみはあまり感じさせない運びです。弱音部も抑揚はつけますが、やっぱりさらっとしています。 ポール・メイエ(Paul Meyer/クラリネット)/エリック・ル・サージュ(ピアノ)1991 Denon 現在は世界的に有名なフランスのクラリネット奏者のデビュー盤です。ポール・メイエは1965年生まれでジャズも現代曲も吹いて技巧派と呼ばれているようです。あっさりと語尾を切り、軽さがあります。冒頭のように比較的ゆったり進めるところでも、スケルツォの楽章のように速いところでも、やわらかい抑揚をつけずに直線的に吹きます。速いところは素速く、切れのある鮮やかなパッセージを聞かせており、上手さが際立つ運びです。有名な第三楽章でも出だしの抑揚は抑えて真っ直ぐに、後半の静かな部分では強さを変えずに文字通り息も絶えだえに音間を切っており、その滑らかに山を作らない呼吸は伝統的フレンチというよりも、よりモダンな感覚を出そうとしているかのようです。楽曲の音の可能性を最大限に見せてくれる演奏だと思います。
マルティン・フレスト ♥(Martin Fröst/クラリネット)/ローランド・ペンティネン(ピアノ)1994 BIS 1970年生まれのスウェーデンのクラリネッティストで、現代曲もやるし総合芸術にも関心がある人のようで す。これもあっさりと延ばさない音が聞かれます。すっきりとして切れが良く、鮮やかです。繊細さとダイナミックさを併せ持っており、音色は輪郭がくっきりとしています。弱音の吹き方はたわませず、割と真っ直ぐです。やや寒色系でやすやすと吹く上手さが際立ち、全体に爽やかな印象です。 磯部周平(クラリネット)/岡崎悦子(ピアノ)2003 マイスター・ミュージック 残念ながら日本のレーベルなので著作権に厳しく、サブスクリプションのサイトに制限があって全曲が聞けませ ん。CD は手に入れていません。 リカルド・モラレス(Ricardo Morales/クラリネット)/マイケル・チャートック(ピアノ)2004 Boston Records 1972年生まれのプエルトリコ系アメリカ人クラリネット奏者で、2003年からフィラデルフィア管の首席を務めています。中庸なテンポで抑揚もつけ過ぎずに平穏に始め、第二楽章はあまり速くせずに表情を付け、瞬間的に遅くするためも聞かれます。現代的というのか、さらっとした情感で何気なさが感じられます。第三楽章は必要以上に深刻にせず、語尾を弱める抑揚はありながらも力を抜いてリラックスした印象です。弱音のパートはスラーで、やはり何気なく流して痛々しさはあまり出しません。 ザビーネ・マイヤー ♥(Sabine Meyer/クラリネット)/オレグ・マイセンベルク(ピアノ)2006 EMI 1959年生まれのドイツの女性クラリネット奏者で、カラヤンが楽団員と喧嘩をするきっかけになったことで有名になりました。ベルリン・フィルにはトーンが合わないと言われましたが実力者であり、あれはジェンダー差別の一環だったのでしょう。太く響く低音がまろやかです。吹き方に派手さや明るさはなく、落ち着いた表情で真っ直ぐ飾らずに進めます。スラーでつなぐ傾向は聞かれますが、表情を付け過ぎず、全体にどこもテンポは適切な中庸と言えます。少しくすんだ重さを感じるでしょうか。ピアノの表情が繊細です。 エルマンノ・ヴェリアンティ(Ermanno Veglianti/クラリネット)/エンリコ・マリア・ポリマンティ(ピアノ)2010 Naxos イタリアの演奏者でしょうか。詳細は分かりませんがナクソスからです。たっぷりとした演奏です。遅めの運びであまり細かな強弱をつけずに丁寧に進め、大らかに歌わせます。第二楽章は語尾に力が入るようなリズムで延ばし、あまり速くは感じさせず、やや平滑に撫でるように進めます。第三楽章は鐘のようなピアノが遅く、合わせてクラリネットも一音ずつを切ってスタカッカート気味に行きます。弱音部では粘るようなリズムになり、ナイフでキャンバスに絵の具を擦り付けるように押さえて進めます。最弱音ではなく、割としっかり鳴らします。 イシュトヴァン・コハーン(Istvan Kohan/クラリネット)/高橋ドレミ(ピアノ) 2016 Lakeshore Music 1990年、ハンガリー生まれの演奏者です。中庸のテンポでそっと、弱音の抜きがあります。瞬間的に遅くする表情も、ルバート様のテンポのゆらしも若干加えます。第二楽章は軽快だけど力は抜けています。第三楽章は大変遅いので、抑揚は必ずしも大きくないですが荘重な感じです。弱音のパートでは大変弱めます。全体に表情は大きく付ける方でしょう。 クリストファー・ニコルズ(Christopher Nichols/クラリネット)/ジュリー・ニシムラ(ピアノ)2017 Navona Records これがデビュー・アルバムというアメリカのクラリネット奏者です。ピアノの序奏からして遅い始まりです。強弱は割と平坦に抑え、遅さに合わせるような感じのクラリネットで始めます。その後大きめのクレッシェンドをつけたりしつつも、表情が大きいわけではありません。第二楽章はあまり速くせず、でもくっきりとやや跳ねるように進め、丁寧な印象です。第三楽章は遅いです。一音ずつを区切ってしっかりと鳴らす感じのクラリネットで、対する伴奏の方はあまりがつんと力で叩くものではありません。弱音パートでは音をつなげますが、割と平滑な強弱に抑えてゆったりしています。 トマゾ・ロンクイッチ(Tommaso Lonquich/クラリネット)/アレクサンダー・ロンクイッチ(ピアノ) 2018 Novantiqua イタリア人のコンビのようです。ゆったりめのテンポで弱音で抑えて始め、その後大きくクレッシェンドしたりして、強弱がダイナミックでなかなかメリハリがあります。音色の面では低音は太く力があり、弱音はややオフで輪郭が強いものではありません。ピアノの抑揚も大きめでしょうか。全体にしっかりとした表情の演奏です。 マキシミリアーノ・マルティン(Maximiliano Martin/クラリネット)/スコット・ミッチェル(ピアノ)2021 Delphian スペインのテネリフェ島出身というクラリネットです。スコットランド室内管弦楽団の首席です。遅めで丁寧な運びで、抑揚は割と直線的であり、静かではありますが特にやわらかさを狙っている感じでもないでしょうか。第二楽章は活気があり、しっかりした音でそこそこ速いです。第三楽章も直線的で力強く、輪郭のくっきりした音で聞かせます。後半の弱音パートでは力を抜きますが、そこそこしっかりと吹かれていて消え入るようではなく、ここもテヌートで真っ直ぐな印象です。 バスーン・ソナタのみの CD バスーン奏者がリーダーになって曲を集めた、もしくはサン=サーンスのソナタはバスーンのみというアルバムは大変珍しく、なくはないけど以下のものぐらいしか探せませんでした。しかもそれらも廃盤になっており、中古のメイエル盤以外、サブスクリプション・サイトで聞くのを除いて CD などは必ずしも手に入れやすいものでもなさそうなので、ここでは列挙するだけにとどめます。 ディルク・メイエル(Dirk Meijer/バスーン)/ヤン・ファン・リエル(ピアノ)2000 Apex オランダ人のバスーン奏者です。ファゴット・ソナタ集と題して20世紀前半の曲を集めており、ユリウス・レントヘン、ラウニ・グレンダールの作品と組み合わされています。
ミシェル・ベテ(Michel Bettez/バスーン)/ピエール=リシャール・オーバン(ピアノ)2000 ATMA Classique カナダ人のバスーン奏者です。タイトルは Le Basson Romantique となっており、エルガー、ウジェーヌ・ブルドー、アレッサンドロ・ロンゴ、ウィリアム・ハールストン、バリス・ドヴァリョーナスの作品と組み合わされています。
レベカー・アブラムスキー(Rebekah Abramski/バスーン)/ロン・アブラムスキー(ピアノ)2006 K&K シュトゥットガルトの音楽大学で出会ってトリオを組んだイギリス人たちによるアブラムスキー三重奏団の演奏です。もう一人はオーボエのミリアム・ブッダイですが、サン=サーンスはバスーン・ソナタのみです。オーボエ、ファゴットとピアノによるコンサートと題しており、マウルブロン修道院ライヴということです。ジャン・フランセ、ラヴェル、エドワード・ロングスタッフ、プーランクの作品と組み合わされています。
INDEX |